
益田
@msd
2025年8月21日
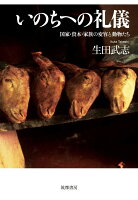
いのちへの礼儀
生田武志
読んでる
・犬/猫の名前が人間の名前と被るようになってきている 例:ハナ・サクラ・リク・メイ
→犬猫の「見た目」などで決める名付けは避けられて、個人の嗜好を示すものになっている
→ある時期まで日本人の名前は家族制度や国家政策、経済政策を反映していた。しかし、現在は「独特の個性」や私的な嗜好を感じさせるものに変化していて、キラキラネームなどの珍しい名前が珍しくない時代に変化→子供とペットの区別することが無くなってきている
牧野恭仁雄「名前にはその時代の欠乏感が反映される」
・あらゆる地域・階層で「単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人」が増えてきてきいる
・「ペットは労働もせず食料も生産せず、手間だけかかっています。こういう存在を、かつては「穀潰し」と言っていました。同じようでも、多くのこどもはやがて働き手として役立つでしょうが、大やネコはほとんどの場合、役立たずなままです。このような「役立たず」な動物を愛するのは、ある種の「倒錯」ではないでしょうか?しかし、エス氏や他の多くの人たちは、こうした動物を「目に入れても痛くない」(=自分の一部の)ように大事に育てています。
こうした動物が「家族」の一員だとすれば、わたしたちの「家族」は「ファミリア(ラテン語で家内奴隷から家畜まで含む世帯単位)」でも「近代家族」でもありません。わたしたち現代家族は、異種間の感情的なつながりを優先した、人類史上例のない共同体なのです。」(p59-60)



