いのちへの礼儀
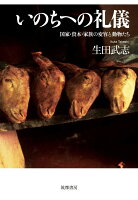
5件の記録
 益田@msd2025年8月28日読み終わったこの手の話題は割と相手サイドを冷笑か罵倒しているイメージだったが、この本はかなり冷静に話を書いていて好感をもった。工業化の実態や捕鯨問題の何が問題なのかなどを丁寧に書いており、それに加えて動物とはどういうモノなのかということに誠実に向き合っている本だと感じた。人間の傲慢さをつきつけつつも、動物と共存・福祉の点を話していてここら辺に疎い身としてはかなり学びが多く、勉強になった。 途中のヴィーガンの論理である人間優先から人格優先になった場合、本当に障害者差別などは起きないのか?と不安と疑問に思った。ここら辺のヴィーガンの論理を学びたい!
益田@msd2025年8月28日読み終わったこの手の話題は割と相手サイドを冷笑か罵倒しているイメージだったが、この本はかなり冷静に話を書いていて好感をもった。工業化の実態や捕鯨問題の何が問題なのかなどを丁寧に書いており、それに加えて動物とはどういうモノなのかということに誠実に向き合っている本だと感じた。人間の傲慢さをつきつけつつも、動物と共存・福祉の点を話していてここら辺に疎い身としてはかなり学びが多く、勉強になった。 途中のヴィーガンの論理である人間優先から人格優先になった場合、本当に障害者差別などは起きないのか?と不安と疑問に思った。ここら辺のヴィーガンの論理を学びたい!



 益田@msd2025年8月24日読んでる「わたしたちがペットの犬や猫を「オスが産まれたらただちに殺処分する」「方向転換できない狭いケージの中で死ぬまで飼う」「二週間程度、絶食・絶水して栄養不足にさせる」「排泄物まみれの寝床で飼い続ける」「去勢手術を獣医師でない者が麻酔なしに行なう」としたら、飼い主であれペット業者であれ、重大な動物虐待として厳しく批判されるにちがいありません。 しかし、牛や豚や鶏へのこうした行為は問題にされません。なぜなら、牛、豚、羊、鶏は「愛護動物」(家族の一員)ではなく「経済動物」(資本の一貫)だからです。事実、こうした家畜たちは、人間の食糧になると同時にペットの「エサ」にもなります。キャットフードの「原材料」表示にある主原料には「鶏、牛、豚、サーモン」がよく書かれています。国産のキャットフードは、主に食品製造段階で出る人間の食用以外の部位が原料にされているからです。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震を通して、ペットについて「家族の一員」から「社会の一員」への転換の必要性が言われました。しかし、家畜動物はその意味での「社会の一員」とはみなされていません。 その背景の一つには、日本には「働く」家畜(役畜)は存在しても「食べる」家畜が存在しなかったという歴史的特異性があります。世界の多くの人にとって、肉食は「大事に育てた動物を、自分の手で屠殺して家庭や地域で食べる」というものとして文字通り血肉化していました。しかし、一二〇〇年の間、日本には「食べるための家畜をかわいがる(尊重する)」という関係は存在しませんでした。近代以降の日本人にとって、肉食は最初から「近代産業」として、家畜は単なる「食材」として捉えられたのです。」(p165-166)
益田@msd2025年8月24日読んでる「わたしたちがペットの犬や猫を「オスが産まれたらただちに殺処分する」「方向転換できない狭いケージの中で死ぬまで飼う」「二週間程度、絶食・絶水して栄養不足にさせる」「排泄物まみれの寝床で飼い続ける」「去勢手術を獣医師でない者が麻酔なしに行なう」としたら、飼い主であれペット業者であれ、重大な動物虐待として厳しく批判されるにちがいありません。 しかし、牛や豚や鶏へのこうした行為は問題にされません。なぜなら、牛、豚、羊、鶏は「愛護動物」(家族の一員)ではなく「経済動物」(資本の一貫)だからです。事実、こうした家畜たちは、人間の食糧になると同時にペットの「エサ」にもなります。キャットフードの「原材料」表示にある主原料には「鶏、牛、豚、サーモン」がよく書かれています。国産のキャットフードは、主に食品製造段階で出る人間の食用以外の部位が原料にされているからです。阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震を通して、ペットについて「家族の一員」から「社会の一員」への転換の必要性が言われました。しかし、家畜動物はその意味での「社会の一員」とはみなされていません。 その背景の一つには、日本には「働く」家畜(役畜)は存在しても「食べる」家畜が存在しなかったという歴史的特異性があります。世界の多くの人にとって、肉食は「大事に育てた動物を、自分の手で屠殺して家庭や地域で食べる」というものとして文字通り血肉化していました。しかし、一二〇〇年の間、日本には「食べるための家畜をかわいがる(尊重する)」という関係は存在しませんでした。近代以降の日本人にとって、肉食は最初から「近代産業」として、家畜は単なる「食材」として捉えられたのです。」(p165-166)

 益田@msd2025年8月23日読んでる「かつて「地域共同体の一員」だった犬や猫は、一九九〇年代以降、「家族の一員」であると同時に、ペット産業によって生死を管理される「商品」=「資本の一員」になりました。しかし、その「大量生産」「大量消費」の中で、ペットたちは過去に例のない虐待を受けるようになりました。 震災のさい、犬や猫は「社会の一員」として扱われず、行き場のない状態が大きな問題となりました。しかし、「生体商品」になった大や猫たちも、やはり必ずしも生命や健康を尊重される「社会の一員」としては扱われなかったのです。」(p71)
益田@msd2025年8月23日読んでる「かつて「地域共同体の一員」だった犬や猫は、一九九〇年代以降、「家族の一員」であると同時に、ペット産業によって生死を管理される「商品」=「資本の一員」になりました。しかし、その「大量生産」「大量消費」の中で、ペットたちは過去に例のない虐待を受けるようになりました。 震災のさい、犬や猫は「社会の一員」として扱われず、行き場のない状態が大きな問題となりました。しかし、「生体商品」になった大や猫たちも、やはり必ずしも生命や健康を尊重される「社会の一員」としては扱われなかったのです。」(p71)

 益田@msd2025年8月21日読んでる・犬/猫の名前が人間の名前と被るようになってきている 例:ハナ・サクラ・リク・メイ →犬猫の「見た目」などで決める名付けは避けられて、個人の嗜好を示すものになっている →ある時期まで日本人の名前は家族制度や国家政策、経済政策を反映していた。しかし、現在は「独特の個性」や私的な嗜好を感じさせるものに変化していて、キラキラネームなどの珍しい名前が珍しくない時代に変化→子供とペットの区別することが無くなってきている 牧野恭仁雄「名前にはその時代の欠乏感が反映される」 ・あらゆる地域・階層で「単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人」が増えてきてきいる ・「ペットは労働もせず食料も生産せず、手間だけかかっています。こういう存在を、かつては「穀潰し」と言っていました。同じようでも、多くのこどもはやがて働き手として役立つでしょうが、大やネコはほとんどの場合、役立たずなままです。このような「役立たず」な動物を愛するのは、ある種の「倒錯」ではないでしょうか?しかし、エス氏や他の多くの人たちは、こうした動物を「目に入れても痛くない」(=自分の一部の)ように大事に育てています。 こうした動物が「家族」の一員だとすれば、わたしたちの「家族」は「ファミリア(ラテン語で家内奴隷から家畜まで含む世帯単位)」でも「近代家族」でもありません。わたしたち現代家族は、異種間の感情的なつながりを優先した、人類史上例のない共同体なのです。」(p59-60)
益田@msd2025年8月21日読んでる・犬/猫の名前が人間の名前と被るようになってきている 例:ハナ・サクラ・リク・メイ →犬猫の「見た目」などで決める名付けは避けられて、個人の嗜好を示すものになっている →ある時期まで日本人の名前は家族制度や国家政策、経済政策を反映していた。しかし、現在は「独特の個性」や私的な嗜好を感じさせるものに変化していて、キラキラネームなどの珍しい名前が珍しくない時代に変化→子供とペットの区別することが無くなってきている 牧野恭仁雄「名前にはその時代の欠乏感が反映される」 ・あらゆる地域・階層で「単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生のパートナーとして扱う人」が増えてきてきいる ・「ペットは労働もせず食料も生産せず、手間だけかかっています。こういう存在を、かつては「穀潰し」と言っていました。同じようでも、多くのこどもはやがて働き手として役立つでしょうが、大やネコはほとんどの場合、役立たずなままです。このような「役立たず」な動物を愛するのは、ある種の「倒錯」ではないでしょうか?しかし、エス氏や他の多くの人たちは、こうした動物を「目に入れても痛くない」(=自分の一部の)ように大事に育てています。 こうした動物が「家族」の一員だとすれば、わたしたちの「家族」は「ファミリア(ラテン語で家内奴隷から家畜まで含む世帯単位)」でも「近代家族」でもありません。わたしたち現代家族は、異種間の感情的なつながりを優先した、人類史上例のない共同体なのです。」(p59-60)



