
阿久津隆
@akttkc
2025年8月8日
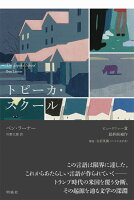
トピーカ・スクール
ベン・ラーナー,
川野太郎
読んでる
読書日記
今日も寝る前は『トピーカ・スクール』。
p.163
彼が高校で抱えた問題は、ディベートをするとナードと、詩をやるとおかまと見なされることだった―そのふたつがあってこそ、ぼんやりと想像した東海岸に立ち、トピーカでの経験を大いなるアイロニーとともに物語ることができたのだが。肝心なのは、ディベートへの取り組みを言葉による戦闘の一種として語ることだった。肝心なのはいじめっ子になること、素早く残忍に、極力挑発と受け取られないような中傷で、いつでも対戦相手をスプレッドできることだった。詩が許されるのは、それが自分の能力を向上させる場合、それが「サイファー」と「フロウ」になる場合、それが、アンバーがレイノルズおよびほかの者たちではなく、自分とセックスする理由のひとつになる場合に限られた。卓越した言語能力によって人を傷つけ、人と寝られるようになるとき、彼は知性と表現力という家庭内の価値観から完全に離れることなく、青年期の社会領域に溶けこむことができた。和解とは言えなかったが、実現可能な拮抗ではあった。彼の髪型の悲惨な折衷案。片頭痛。
アダムの幸運は、自分の攻撃性を言語の領域に持ちこんだとき、それが彼らのようなタイプが採用していた慣習のひとつとして公認されたことだった。
何に惹かれるのだろう、何が響くのだろう、自分も持っていたであろうなんらかのコンプレックスがくすぐられる感じとかもあるのだろう、と思いながら、いいぞアダム、と思う。
p.165
彼は祖母に、どうやって祖父と結婚することになったのかを尋ねていた。出会いはいつ?「ブルックリンでね」と彼女はトピーカで言った。「父が病気になって、家族のためにお金が必要になったから高校を出てタイピストとして働いたんだけど、Jアベニューにある家に帰るのは遅い時間だった。いつもバスに乗ってたわ。そしたらあなたのおじいちゃんがいつもバス停で私を待っていて、歩いて家まで送らせてくれないかって言うの。それが一九三二年のことで」と彼女は一九九七年に言った、「私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった」。
それが一九三二年のことで、私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった、というのがよかった。ブルックリンでね、とトピーカで言った、もよかった。一九三二年のことで、と彼女は一九九七年に言った、というのもよかった。
次は滑稽な場面。スーパーに入ると敵視している同級生と対面して、さあ喧嘩か、と身構えたあと彼が母親と一緒にいることに気づき、「母親がいることで身体的な衝突ができないことに気づき、アダムはほっとし」て、さらに「ママと買い物かよ? アダムは微笑むことで軽蔑を伝えることにした」のあと、
p.169,170
「アダム」―と母の声―「おばあちゃんに、一九四五年とは物価が違うって言ってやってよ」恐ろしいかな、自分の家族が迫ってきた。値段で言い争うユダヤ人。彼らと知り合いでいることを否定したいという、とっさの、馬鹿げた欲望。レスラーは意図の読めない含み笑いを浮かべたが、それがアダムを怯えさせ、激昂させた。二世代にわたる女性といることは、一世代の女性といることよりもまずいだろうか? レスラーはその違いに気づいて馬鹿にしてるのか?
吹き出しちゃった。
