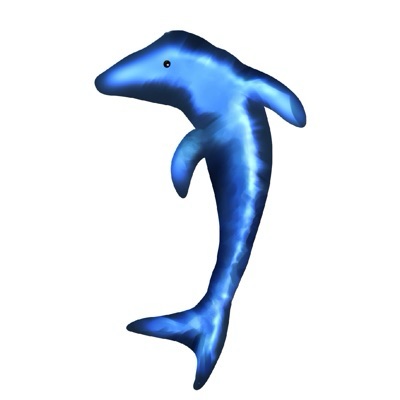🐧
@penguin
2025年9月3日

なぜ書くのか
タナハシ・コーツ,
池田年穂
読み終わった
4章、パレスチナを訪れた記録。
コーツは出世作「賠償訴求訴訟」でアメリカは過去の奴隷制に対して黒人コミュニティに賠償すべきという主張を展開しているが、その論拠としてドイツのイスラエルに対する賠償を挙げた。が、これはイスラエルによるパレスチナ占領を踏まえていないという批判を受けた。この批判がパレスチナを訪れる契機となっている。
ホロコーストからのユダヤ人国家建設、という物語にあらゆるところで触れてきたアメリカ人が、パレスチナのことを知った時にそれを認めるのがいかに難しいかが、コーツ自身の動揺から伝わる。それはイスラエルがパレスチナ人に行っていることとアメリカが黒人たちに行っていることの相似、そしてそれを知らなかったことへの痛みとともに書き進めていく。
コーツでさえそうなのだと思うと、アメリカとイスラエルのつながりってなんて強いんだろうと気が遠くなる。
訪れたのは2023年夏。この時点で、パレスチナの痛みについて限りなく言葉を尽くしているように思える。現在のジェノサイドは本当に、表現できる言葉などないような惨劇なのだと改めて思う。
p161
"私が目の当たりにしたこの取り組み、つまり考古学を援用し、古代の遺跡を破壊し、パレスチナ人を家から追放することは、アメリカ合衆国の具体的な認可を受けていた。ということは、それは私の認可を受けていたことを意味する。これは別の国によってなされる別の悪行だというにとどまらず、私の名のもとに行われた悪行でもあったのだ。"
p174
"この訪問の終わりまでに、私は「ナクバ」を、ジム・クロウや植民地主義、アパルトヘイトといった類似のものを超えた特別なものとして理解するようになっていた。それはたんに警察があなたの息子を撃つことだけではなく(それもありうる)、たんなる人種差別的な監獄制度でもなく(それもここには存在する)、たんに法の前での不平等でもない(それも私の目に入る至る所にあった)。ナクバは、そういったやり口のどれもが役立ったものである——すなわちホームの略奪であり、それは身近なものでもあり恒久的なものでもある略奪である。"