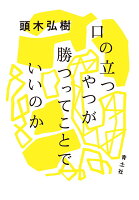🐧
@penguin
本の感想を書く時にちゃんとまとめようとしすぎるところがあって、もう肩肘張りたくない!という強い気持ちがあります。なのでできるだけ適当に運用します。頑張ります。
- 2025年11月11日
- 2025年9月20日
 障害者差別を問いなおす荒井裕樹読み始めた障害者の人たちの置かれている状況をもっと知らなければいけない、と思って手に取った。勉強。 まず2章まで。青い芝の会は障害を「克服」することを否定し「働く=善」という価値観を否定し、とにかく「社会」を敵視し常識を問い直す。その精神性は現代の色々な社会運動にも引き継がれているように見える。ただ、自分が運動に携わる時にここまで強くいられるか。そして健常者である自分がこの価値観で批判された時にきちんと受け止められるか。
障害者差別を問いなおす荒井裕樹読み始めた障害者の人たちの置かれている状況をもっと知らなければいけない、と思って手に取った。勉強。 まず2章まで。青い芝の会は障害を「克服」することを否定し「働く=善」という価値観を否定し、とにかく「社会」を敵視し常識を問い直す。その精神性は現代の色々な社会運動にも引き継がれているように見える。ただ、自分が運動に携わる時にここまで強くいられるか。そして健常者である自分がこの価値観で批判された時にきちんと受け止められるか。 - 2025年9月20日
- 2025年9月19日
 世界99 下村田沙耶香読んでる比喩や情景描写が毎回すごすぎる。美しいのにぞっとして、しかも作品世界に完璧に合っている言葉が次々出てくるのがすごすぎて笑ってしまう。村田沙耶香ってこんなに言葉でしか描けない景色を描く作家だったのか……
世界99 下村田沙耶香読んでる比喩や情景描写が毎回すごすぎる。美しいのにぞっとして、しかも作品世界に完璧に合っている言葉が次々出てくるのがすごすぎて笑ってしまう。村田沙耶香ってこんなに言葉でしか描けない景色を描く作家だったのか…… - 2025年9月15日
 世界99 上村田沙耶香読み始めた感情抜きで社会に過剰適応していく女性が主人公。冷静に人間を観察し分析する主人公は不気味で狂っているように見えるけど、それはただこの不気味で狂った社会を写し取っているだけなんだろう。 「便利」とか「削除」とか、人間に対しては基本的に使わない、あるいは使うとしたら強い悪意とともに使われる言葉が、完全に無感情で使われていてすごい。村田沙耶香の小説の質感だーと思う。
世界99 上村田沙耶香読み始めた感情抜きで社会に過剰適応していく女性が主人公。冷静に人間を観察し分析する主人公は不気味で狂っているように見えるけど、それはただこの不気味で狂った社会を写し取っているだけなんだろう。 「便利」とか「削除」とか、人間に対しては基本的に使わない、あるいは使うとしたら強い悪意とともに使われる言葉が、完全に無感情で使われていてすごい。村田沙耶香の小説の質感だーと思う。 - 2025年9月13日
 平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美読み終わった読了。とりあえず印象に残ったところをメモ。 P150 この袋小路から抜け出すのに他の可能性はない。なぜなら、国際ルールの見直しは、北側世界にとっての課題であるだけでなく、南側世界にとっても、そして地球全体にとっても切実な課題なのだから。社会目標も環境目標もない、資本や財とサービスの自由な流通に立脚する現在の経済システムは、富裕層に利する新植民地主義に大いに通じるところがある。 P163 社会的クオータ制あるいは人種クオータ制の採用を検討する前に、まず取り組むべきはこうした差別と闘うことだ。言い換えれば、人種差別やその他の差別行為を特定し、何よりも、そういう差別行為をしている社会人(雇用主、警察官、支援者、デモの参加者、インターネットユーザーなど)に対して法的措置をとるなど、差別行為をやめさせるためのあらゆる手段を講じる必要がある。 P168 強調すべきは、欧米諸国はこれまでインドで実施されてきた留保制度に匹敵する社会的クオータ制あるいは人種クオータ制を決して採用してこなかったこと、したがって、こうした問題に対処する制度をどんどんつくりだす必要があるということだ。アメリカでは南北戦争後に元奴隷たちに賠償する約束がなされたものの、その約束は決して果たされなかった。1964年、公民権法の成立で人種差別が撤磨されたとき、ジョンソン政権は、政府調達に応募する企業に多様性を誓約することを課すなど、数々の政策を打ち出した。ところが想像とは裏腹に、連邦政府のどの法律にも大学入学、公職、議員職あるいはその他の同様のポストでのクオータ制を定める正式な制度について一切規程されていない。 P182 国際援助の概念そのものをめぐるとんでもない偽善についても強調する必要がある。まず、政府開発援助は想像以上に少なく、総額で世界GDPの0・2%に満たない(緊急人道支援は世界GDPのせいぜい0・03%)。それに引き換え、富裕国の炭素排出によって貧困国が被っている環境上の損害は、それだけで世界GDPの数%に上る。第二の問題は、これは決して些細なことではないのだが、アフリカや南アジアなどいわゆる「援助を受けている」ほとんどの国では、多国籍企業の利益や資本逃避の形で流出する資金が、実際のところ、政府開発援助による流入資金より数倍も多いことだ(表向きの国民経済計算に記載される流出資金に限定する場合も含めて、実際のフローを過小評価していると思われる)。これは、世界の中心と周辺の関係という驚くべき重要な問題点のひとつである。
平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美読み終わった読了。とりあえず印象に残ったところをメモ。 P150 この袋小路から抜け出すのに他の可能性はない。なぜなら、国際ルールの見直しは、北側世界にとっての課題であるだけでなく、南側世界にとっても、そして地球全体にとっても切実な課題なのだから。社会目標も環境目標もない、資本や財とサービスの自由な流通に立脚する現在の経済システムは、富裕層に利する新植民地主義に大いに通じるところがある。 P163 社会的クオータ制あるいは人種クオータ制の採用を検討する前に、まず取り組むべきはこうした差別と闘うことだ。言い換えれば、人種差別やその他の差別行為を特定し、何よりも、そういう差別行為をしている社会人(雇用主、警察官、支援者、デモの参加者、インターネットユーザーなど)に対して法的措置をとるなど、差別行為をやめさせるためのあらゆる手段を講じる必要がある。 P168 強調すべきは、欧米諸国はこれまでインドで実施されてきた留保制度に匹敵する社会的クオータ制あるいは人種クオータ制を決して採用してこなかったこと、したがって、こうした問題に対処する制度をどんどんつくりだす必要があるということだ。アメリカでは南北戦争後に元奴隷たちに賠償する約束がなされたものの、その約束は決して果たされなかった。1964年、公民権法の成立で人種差別が撤磨されたとき、ジョンソン政権は、政府調達に応募する企業に多様性を誓約することを課すなど、数々の政策を打ち出した。ところが想像とは裏腹に、連邦政府のどの法律にも大学入学、公職、議員職あるいはその他の同様のポストでのクオータ制を定める正式な制度について一切規程されていない。 P182 国際援助の概念そのものをめぐるとんでもない偽善についても強調する必要がある。まず、政府開発援助は想像以上に少なく、総額で世界GDPの0・2%に満たない(緊急人道支援は世界GDPのせいぜい0・03%)。それに引き換え、富裕国の炭素排出によって貧困国が被っている環境上の損害は、それだけで世界GDPの数%に上る。第二の問題は、これは決して些細なことではないのだが、アフリカや南アジアなどいわゆる「援助を受けている」ほとんどの国では、多国籍企業の利益や資本逃避の形で流出する資金が、実際のところ、政府開発援助による流入資金より数倍も多いことだ(表向きの国民経済計算に記載される流出資金に限定する場合も含めて、実際のフローを過小評価していると思われる)。これは、世界の中心と周辺の関係という驚くべき重要な問題点のひとつである。 - 2025年9月13日
 平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美まだ読んでる6章の再分配について、アツい!これまでで一番面白く読めている。税の累進性が機能していると経済が上向き、人々の生活も平等に近づく。今は累進性はあるけど実際には富裕層や大企業がすっごい節税できる仕組みになっていたりして、「真の累進性は姿を消してしまった」(P120) P128からの、第二次世界大戦後の戦争債務を帳消しにする世界各国の取り組みも面白い。日本も1946〜1947年の特別資産税の最高税率90%=累進性バカ高い政策を打ち、これによって戦争債務を清算、「大再分配」を果たしている。 完全に理解できているとは言えないけど、とにかく「やればできるんじゃん!!」という気持ちにはなる。
平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美まだ読んでる6章の再分配について、アツい!これまでで一番面白く読めている。税の累進性が機能していると経済が上向き、人々の生活も平等に近づく。今は累進性はあるけど実際には富裕層や大企業がすっごい節税できる仕組みになっていたりして、「真の累進性は姿を消してしまった」(P120) P128からの、第二次世界大戦後の戦争債務を帳消しにする世界各国の取り組みも面白い。日本も1946〜1947年の特別資産税の最高税率90%=累進性バカ高い政策を打ち、これによって戦争債務を清算、「大再分配」を果たしている。 完全に理解できているとは言えないけど、とにかく「やればできるんじゃん!!」という気持ちにはなる。 - 2025年9月13日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった11章からの五松、長岡、木戸のところ圧巻だった。登場人物に情が湧きかけたところでそれを潰す最悪エピソードを入れてくるのすごい。 長岡、木戸は対になって描かれているように見える。世界と同化しながら世界には生きる意味なんてないと怒りに身を焼かれていくおばさんと、世界に取り残されて自分には生きる意味なんてないと身を投げ出すおじさん。木戸の章を読んで、おじさんになるの怖いと思った。 エピローグ的なリコの話には希望があった。長岡木戸が左右の対照だとしたら、上下の対照軸として出現する若者の視点。リコの最後のセリフぐっときたな……中年世代はどうしようもないから若者に希望を託す、みたいな構造に落とし込むとかなり陳腐に聞こえるけど、小説を読むと全然陳腐じゃなく、ちゃんと輝く希望として感じる。 1章から木戸、長岡、五松……五松、長岡、木戸のように語り手が線対称(?)になって進んでいくが、リコの話はその構造に付け足されたように最後に短くあるのも良い。コンクリートでできた構造を突き破る新芽みたいな感じで置かれていると思う。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった11章からの五松、長岡、木戸のところ圧巻だった。登場人物に情が湧きかけたところでそれを潰す最悪エピソードを入れてくるのすごい。 長岡、木戸は対になって描かれているように見える。世界と同化しながら世界には生きる意味なんてないと怒りに身を焼かれていくおばさんと、世界に取り残されて自分には生きる意味なんてないと身を投げ出すおじさん。木戸の章を読んで、おじさんになるの怖いと思った。 エピローグ的なリコの話には希望があった。長岡木戸が左右の対照だとしたら、上下の対照軸として出現する若者の視点。リコの最後のセリフぐっときたな……中年世代はどうしようもないから若者に希望を託す、みたいな構造に落とし込むとかなり陳腐に聞こえるけど、小説を読むと全然陳腐じゃなく、ちゃんと輝く希望として感じる。 1章から木戸、長岡、五松……五松、長岡、木戸のように語り手が線対称(?)になって進んでいくが、リコの話はその構造に付け足されたように最後に短くあるのも良い。コンクリートでできた構造を突き破る新芽みたいな感じで置かれていると思う。 - 2025年9月12日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読んでる10章まで読んだ。これまでの疲弊の蓄積とこれからの破綻の予感が色濃い。 これは8章を読みながら考えたことだけど、「暴走する正義」「強靭なポリコレ」みたいなのってZ世代など若者側のものとして描かれることが少なからずある気がするんだけど(背景にはグレタ・トゥーンベリのような現実の存在もあるし、もっと普遍的な「社会正義に燃える若者」みたいな固定観念があるんだろう)それがここでは大人の長岡友梨奈のほうに託されている。そしてその子の安住伽那のほうは、なんか達観して見える部分がある。それは傷つきたくない、傷つけたくないという思いがあるからだけど。そして長岡友梨奈がこういう感じなのも単なる気質ではなく、性加害を軽く流すのが普通だった時代への怒り、抑圧されていた自分への怒りがあるんだけど。 若者が怒り大人が諦めるのではなく、大人が怒っていて若者が諦めてるという逆転が面白い。そしてそれは実はかなりリアルなんだと思う。だからこそめちゃくちゃ息苦しいんだけど。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読んでる10章まで読んだ。これまでの疲弊の蓄積とこれからの破綻の予感が色濃い。 これは8章を読みながら考えたことだけど、「暴走する正義」「強靭なポリコレ」みたいなのってZ世代など若者側のものとして描かれることが少なからずある気がするんだけど(背景にはグレタ・トゥーンベリのような現実の存在もあるし、もっと普遍的な「社会正義に燃える若者」みたいな固定観念があるんだろう)それがここでは大人の長岡友梨奈のほうに託されている。そしてその子の安住伽那のほうは、なんか達観して見える部分がある。それは傷つきたくない、傷つけたくないという思いがあるからだけど。そして長岡友梨奈がこういう感じなのも単なる気質ではなく、性加害を軽く流すのが普通だった時代への怒り、抑圧されていた自分への怒りがあるんだけど。 若者が怒り大人が諦めるのではなく、大人が怒っていて若者が諦めてるという逆転が面白い。そしてそれは実はかなりリアルなんだと思う。だからこそめちゃくちゃ息苦しいんだけど。 - 2025年9月10日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読んでる真ん中くらいまで読んだ。ぐいぐい読んでしまう。 金原ひとみの小説を読むのは『アンソーシャル・ディスタンス』以来な気がするけど、「ノンセク」とか「性自認が曖昧っぽい」子とかが普通に出てくるんだなあ。中年と若者の書き分け、その感覚の落差に目が眩みそう。でも実際こういう感じだよな、と思わせる。中年は若者に狭い解釈を押し付け、若者は中年を見下している。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読んでる真ん中くらいまで読んだ。ぐいぐい読んでしまう。 金原ひとみの小説を読むのは『アンソーシャル・ディスタンス』以来な気がするけど、「ノンセク」とか「性自認が曖昧っぽい」子とかが普通に出てくるんだなあ。中年と若者の書き分け、その感覚の落差に目が眩みそう。でも実際こういう感じだよな、と思わせる。中年は若者に狭い解釈を押し付け、若者は中年を見下している。 - 2025年9月10日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み始めた鋭い観察に裏打ちされた悪口と率直すぎる本音がテンポよく飛び出すので、救いようがないのに笑ってしまう。が、それはまだかなり序盤を読んでいるからで、告発がはじまるこの先はそんなふうには読めなくなってくるのかも。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み始めた鋭い観察に裏打ちされた悪口と率直すぎる本音がテンポよく飛び出すので、救いようがないのに笑ってしまう。が、それはまだかなり序盤を読んでいるからで、告発がはじまるこの先はそんなふうには読めなくなってくるのかも。 - 2025年9月7日
 平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美読み始めた〈あなたの著書はとても興味深いです。でも、その研究について友人や家族と共有できるように、もう少し短くまとめて書いてもらえるとありがたいですが、どうでしょう?〉 そんな読者の要望に応えて、ピケティの1000ページの本×3=3000ページを250ページに凝縮。本とはもともと膨大な知を凝縮したものだと思うし、読む前からとてもワクワクしている!箔押しの装丁もタイトルも洒落ている〜
平等についての小さな歴史トマ・ピケティ,広野和美読み始めた〈あなたの著書はとても興味深いです。でも、その研究について友人や家族と共有できるように、もう少し短くまとめて書いてもらえるとありがたいですが、どうでしょう?〉 そんな読者の要望に応えて、ピケティの1000ページの本×3=3000ページを250ページに凝縮。本とはもともと膨大な知を凝縮したものだと思うし、読む前からとてもワクワクしている!箔押しの装丁もタイトルも洒落ている〜 - 2025年9月3日
 なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み終わった4章、パレスチナを訪れた記録。 コーツは出世作「賠償訴求訴訟」でアメリカは過去の奴隷制に対して黒人コミュニティに賠償すべきという主張を展開しているが、その論拠としてドイツのイスラエルに対する賠償を挙げた。が、これはイスラエルによるパレスチナ占領を踏まえていないという批判を受けた。この批判がパレスチナを訪れる契機となっている。 ホロコーストからのユダヤ人国家建設、という物語にあらゆるところで触れてきたアメリカ人が、パレスチナのことを知った時にそれを認めるのがいかに難しいかが、コーツ自身の動揺から伝わる。それはイスラエルがパレスチナ人に行っていることとアメリカが黒人たちに行っていることの相似、そしてそれを知らなかったことへの痛みとともに書き進めていく。 コーツでさえそうなのだと思うと、アメリカとイスラエルのつながりってなんて強いんだろうと気が遠くなる。 訪れたのは2023年夏。この時点で、パレスチナの痛みについて限りなく言葉を尽くしているように思える。現在のジェノサイドは本当に、表現できる言葉などないような惨劇なのだと改めて思う。 p161 "私が目の当たりにしたこの取り組み、つまり考古学を援用し、古代の遺跡を破壊し、パレスチナ人を家から追放することは、アメリカ合衆国の具体的な認可を受けていた。ということは、それは私の認可を受けていたことを意味する。これは別の国によってなされる別の悪行だというにとどまらず、私の名のもとに行われた悪行でもあったのだ。" p174 "この訪問の終わりまでに、私は「ナクバ」を、ジム・クロウや植民地主義、アパルトヘイトといった類似のものを超えた特別なものとして理解するようになっていた。それはたんに警察があなたの息子を撃つことだけではなく(それもありうる)、たんなる人種差別的な監獄制度でもなく(それもここには存在する)、たんに法の前での不平等でもない(それも私の目に入る至る所にあった)。ナクバは、そういったやり口のどれもが役立ったものである——すなわちホームの略奪であり、それは身近なものでもあり恒久的なものでもある略奪である。"
なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み終わった4章、パレスチナを訪れた記録。 コーツは出世作「賠償訴求訴訟」でアメリカは過去の奴隷制に対して黒人コミュニティに賠償すべきという主張を展開しているが、その論拠としてドイツのイスラエルに対する賠償を挙げた。が、これはイスラエルによるパレスチナ占領を踏まえていないという批判を受けた。この批判がパレスチナを訪れる契機となっている。 ホロコーストからのユダヤ人国家建設、という物語にあらゆるところで触れてきたアメリカ人が、パレスチナのことを知った時にそれを認めるのがいかに難しいかが、コーツ自身の動揺から伝わる。それはイスラエルがパレスチナ人に行っていることとアメリカが黒人たちに行っていることの相似、そしてそれを知らなかったことへの痛みとともに書き進めていく。 コーツでさえそうなのだと思うと、アメリカとイスラエルのつながりってなんて強いんだろうと気が遠くなる。 訪れたのは2023年夏。この時点で、パレスチナの痛みについて限りなく言葉を尽くしているように思える。現在のジェノサイドは本当に、表現できる言葉などないような惨劇なのだと改めて思う。 p161 "私が目の当たりにしたこの取り組み、つまり考古学を援用し、古代の遺跡を破壊し、パレスチナ人を家から追放することは、アメリカ合衆国の具体的な認可を受けていた。ということは、それは私の認可を受けていたことを意味する。これは別の国によってなされる別の悪行だというにとどまらず、私の名のもとに行われた悪行でもあったのだ。" p174 "この訪問の終わりまでに、私は「ナクバ」を、ジム・クロウや植民地主義、アパルトヘイトといった類似のものを超えた特別なものとして理解するようになっていた。それはたんに警察があなたの息子を撃つことだけではなく(それもありうる)、たんなる人種差別的な監獄制度でもなく(それもここには存在する)、たんに法の前での不平等でもない(それも私の目に入る至る所にあった)。ナクバは、そういったやり口のどれもが役立ったものである——すなわちホームの略奪であり、それは身近なものでもあり恒久的なものでもある略奪である。" - 2025年9月2日
 なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読んでる3章。自身の著作『世界と僕のあいだに』がサウス・カロライナ州のメアリーという教師の授業計画から強制的に排除されようとしていることを知り、その教師に連絡を取る。 アメリカの禁書運動は逆説的に言葉にどれほどの力があるか、どれほど言葉が恐れられているかを証明している。そのことを、メアリーとその支持者たちの運動と著者の体験を「書くこと」で露呈させる。 p76 二〇二〇年の夏の重要性を払いのけようとする衝動は理解できる。「人種的正義についての全国的な対話」や数多くのテレビの特集やドキュメンタリー、さらには抗議活動そのものさえも無意味だと切り捨てたくなる気持ちもわかる。私たちのなかの一部の人びとは、政策の変化に反映されなかったのを見て、その運動自体が無駄だったと思うかもしれない。けれど、政策の変化は終点であって始まりではない。重要な変化が生まれるのは、私たちの想像力とアイデアのなかでだ。 p80 執筆を始めた頃の私には、白人を読者として意識することを極力避け、彼らを頭のなかで単純化し、「翻訳」しようという誘惑に抗うことが必須だと思えていた。それは正しかったと思う。けれど、今回これまでで驚きなのは——喜ばしい驚きではあるが——実際には翻訳は必要ないし、深く掘り下げてゆけば自ずと人間性が明らかになるということだった。ルールにあるように「具体を通って全体へ達せよ」。
なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読んでる3章。自身の著作『世界と僕のあいだに』がサウス・カロライナ州のメアリーという教師の授業計画から強制的に排除されようとしていることを知り、その教師に連絡を取る。 アメリカの禁書運動は逆説的に言葉にどれほどの力があるか、どれほど言葉が恐れられているかを証明している。そのことを、メアリーとその支持者たちの運動と著者の体験を「書くこと」で露呈させる。 p76 二〇二〇年の夏の重要性を払いのけようとする衝動は理解できる。「人種的正義についての全国的な対話」や数多くのテレビの特集やドキュメンタリー、さらには抗議活動そのものさえも無意味だと切り捨てたくなる気持ちもわかる。私たちのなかの一部の人びとは、政策の変化に反映されなかったのを見て、その運動自体が無駄だったと思うかもしれない。けれど、政策の変化は終点であって始まりではない。重要な変化が生まれるのは、私たちの想像力とアイデアのなかでだ。 p80 執筆を始めた頃の私には、白人を読者として意識することを極力避け、彼らを頭のなかで単純化し、「翻訳」しようという誘惑に抗うことが必須だと思えていた。それは正しかったと思う。けれど、今回これまでで驚きなのは——喜ばしい驚きではあるが——実際には翻訳は必要ないし、深く掘り下げてゆけば自ずと人間性が明らかになるということだった。ルールにあるように「具体を通って全体へ達せよ」。 - 2025年8月31日
 なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み始めた読みはじめた。文章の強靭なしなやかさに惹かれる。翻訳でしか読めてないけどきっと原文もリズムがいいんじゃないか。力強く、背筋を正される。 この本の導入的な位置付けでもありそうな1章、自身のルーツを探るセネガルへの旅を描いた2章まで読む。黒人の文化や歴史にそこまで詳しくない自分にとっては複雑なところもある。しかし難解な書き方ではなく、豊かさと悲しみが伝わってくる。 "私たちはもっと深い何ものかによって引き寄せられていたのだ。 その何ものかとは、私たちの大学に、つまりハワード大学は奴隷制という長い影と闘うために設立された、ということに由来するのだろう——その影はまだ消えていないことを私たちは理解していた。 それだからこそ、私たちはたんなるスキルとしてライティングを学ぶわけにはゆかず、学ぶことがより大きな解放の便命に奉仕するものであると借じる必要があった。そのことは、直接言及されることがなくても、何かにつけて暗黙の棚に了解されていた。私たちが取り組んだ作品はどれも、「人間であることの些細なことども」を扱っていたが、これは文学が一般的に扱うものだ。けれどあなたたちが、私たち黒人がこれまで生きてきたように、いつでも人間であることを疑問視されるグループのなかで生きているなら、その「些細なことども」でさえ——いやいや些細なことだからこそ——政治的な意味を持ってしまう。あなたたちにとって、書くことと政治のあいだには隔たりは存在しえないからだ。"p2 "私たちは、黒人として、こちら側でもあちら側でも、西洋の犠牲者である——西洋のリベラルな食 言の外側に押し出されているが、西洋の約束に魅了されるほどには近いところに留められている。私たちは西洋という家の美しさを知っている——その石灰岩の階段、羽目板、大理石の浴室…....。けれと私たちが知っているのはそれだけじゃない。この家が呪われていること、レンガに血が染み込んでおり、屋根裏には幽霊が住んでいることも私たちは知っている。この状態には悲劇と喜劇の両方があることも理解している。私たち自身の人生や文化——音楽、ダンス、書くこと——はすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。"p46
なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み始めた読みはじめた。文章の強靭なしなやかさに惹かれる。翻訳でしか読めてないけどきっと原文もリズムがいいんじゃないか。力強く、背筋を正される。 この本の導入的な位置付けでもありそうな1章、自身のルーツを探るセネガルへの旅を描いた2章まで読む。黒人の文化や歴史にそこまで詳しくない自分にとっては複雑なところもある。しかし難解な書き方ではなく、豊かさと悲しみが伝わってくる。 "私たちはもっと深い何ものかによって引き寄せられていたのだ。 その何ものかとは、私たちの大学に、つまりハワード大学は奴隷制という長い影と闘うために設立された、ということに由来するのだろう——その影はまだ消えていないことを私たちは理解していた。 それだからこそ、私たちはたんなるスキルとしてライティングを学ぶわけにはゆかず、学ぶことがより大きな解放の便命に奉仕するものであると借じる必要があった。そのことは、直接言及されることがなくても、何かにつけて暗黙の棚に了解されていた。私たちが取り組んだ作品はどれも、「人間であることの些細なことども」を扱っていたが、これは文学が一般的に扱うものだ。けれどあなたたちが、私たち黒人がこれまで生きてきたように、いつでも人間であることを疑問視されるグループのなかで生きているなら、その「些細なことども」でさえ——いやいや些細なことだからこそ——政治的な意味を持ってしまう。あなたたちにとって、書くことと政治のあいだには隔たりは存在しえないからだ。"p2 "私たちは、黒人として、こちら側でもあちら側でも、西洋の犠牲者である——西洋のリベラルな食 言の外側に押し出されているが、西洋の約束に魅了されるほどには近いところに留められている。私たちは西洋という家の美しさを知っている——その石灰岩の階段、羽目板、大理石の浴室…....。けれと私たちが知っているのはそれだけじゃない。この家が呪われていること、レンガに血が染み込んでおり、屋根裏には幽霊が住んでいることも私たちは知っている。この状態には悲劇と喜劇の両方があることも理解している。私たち自身の人生や文化——音楽、ダンス、書くこと——はすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。"p46 - 2025年8月31日
- 2025年8月31日
 P126の以下がよかった。 "「支援」という言葉に、「~してあげる」というパターナリズムが感じられるとしたら、新しい言葉を考えたほうがよいのかもしれない。たとえば浦河べてるの家の当事者研究の文脈では「応援」という言葉をつかう。当事者とともにサポートのあり方を話し合うときに「支援ミーティング」ではなく「応援ミーティング」と呼ぶ。「応援」であれば、対等な人同士の関係だ。" この本で主に挙がっている介護施設や子どもの支援などよりも、もうちょっと関係性が流動的でゆるやかな集まりやスペースが自分にとっては身近。友人や知り合い中心のコミュニケーションの中に、困っている人がいたり、さまざまなポジショナリティを考慮する必要があったり、というような。 そこで誰かが困っていた時、「支援」という言葉は適切でないように思う。パターナリズムでもあるし、風通しのよい関係性ではなくなってしまう感じがする。でも、「応援」にはそれがない。お互いにケアし合うイメージがしやすくなる。応援、いいな。言葉としても使っていきたいし、人のことをガンガン応援していきたい。 あと、P148-150の居場所、〈生きるスペース〉の定義も指標になる。 "(1)管理と競争を強いられる閉鎖的な施設や家からの逃げ場、 (2)存在が肯定される場、 (3)仲間がいる場、そのなかで一人でもいられる場、 (4)声を出すことができる場、願いやSOSを伝え、SOSが聞き届けられる場、自由な活動ができる場所、" そして、 "(5)行きたいから行く場所、参加を楽しめる場、帰ることができる場所"
P126の以下がよかった。 "「支援」という言葉に、「~してあげる」というパターナリズムが感じられるとしたら、新しい言葉を考えたほうがよいのかもしれない。たとえば浦河べてるの家の当事者研究の文脈では「応援」という言葉をつかう。当事者とともにサポートのあり方を話し合うときに「支援ミーティング」ではなく「応援ミーティング」と呼ぶ。「応援」であれば、対等な人同士の関係だ。" この本で主に挙がっている介護施設や子どもの支援などよりも、もうちょっと関係性が流動的でゆるやかな集まりやスペースが自分にとっては身近。友人や知り合い中心のコミュニケーションの中に、困っている人がいたり、さまざまなポジショナリティを考慮する必要があったり、というような。 そこで誰かが困っていた時、「支援」という言葉は適切でないように思う。パターナリズムでもあるし、風通しのよい関係性ではなくなってしまう感じがする。でも、「応援」にはそれがない。お互いにケアし合うイメージがしやすくなる。応援、いいな。言葉としても使っていきたいし、人のことをガンガン応援していきたい。 あと、P148-150の居場所、〈生きるスペース〉の定義も指標になる。 "(1)管理と競争を強いられる閉鎖的な施設や家からの逃げ場、 (2)存在が肯定される場、 (3)仲間がいる場、そのなかで一人でもいられる場、 (4)声を出すことができる場、願いやSOSを伝え、SOSが聞き届けられる場、自由な活動ができる場所、" そして、 "(5)行きたいから行く場所、参加を楽しめる場、帰ることができる場所" - 2025年8月29日
- 2025年8月27日
 急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読み終わったこれまでマイノリティに置き換えながら読んできたが、9便冒頭の「最近は◯◯との適切な接し方」のようなものが増えてきた、という話の中で、精神障害者やLGBTが挙がっていた。 "ですが「患者」とか、「元気な人」とかいったように、それぞれの人間が持つ特性にラベルがつけられ、ラベル同士のあるべき連結の仕方が、関係性を具体的に作る人々の外側にいる、ラベルについて深い知識を持っているとされる人たちによって、頻繁に提示されることに私は少々違和感を覚えています。加えて、「あるべき形」から外れた連結が、「元気な人」(マジョリティといってもいいでしょう)から試みられた時、深い知識を持っている人々が、多様性を損ねるとか、配慮がないとか、差別とかいった言葉を掲げ、それを試みた側を糾弾する姿を見ると、その違和感はより増します。 (中略)そのような正義の鉄槌をためらいもなく振りかざす人たちを見ると、「多様な社会とか、人々の繋がりってこんな形で達成されるんだっけ?」と考え込んでしまうのです。"(P182) あまりにもSNSでよく見る景色。そして何度もそれを目にした結果、私たちが内面化してしまっている景色。 でもそれでは人と人の関係はさまざまな可能性を持つ「ライン」を描けず、硬直した連結器になってしまう。連結器の関係にすれば痛みはないが、それ以外もない。 「ラインを描く」って、単純化すれば勇気を出して人を社会を、自分(たち)を信頼するということなんだと思う。 クィアや障害者、在日外国人など被差別的マイノリティは人や社会に傷つけられて、信頼ができない状況にたびたび陥る。がん患者としての宮野さんの立場をこうした被差別的マイノリティと置き換えながら読んできたが、明確な「悪意」に接触する量の多さが、違う点かもしれない。とにかく悪意に取り囲まれているから、「信頼しよう!」とは単純にはなかなか言えない。その信頼を悪用されたりするから(それもまたラインを描けなくさせる要因だろう) でも、だからといって自分で自分をラベルに固定して、適切さの内にとどまっていて良いとは思えない。 どんな言葉なら届くだろう?「宮野の生き様を見ろ!」と言えばいいのかな。
急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読み終わったこれまでマイノリティに置き換えながら読んできたが、9便冒頭の「最近は◯◯との適切な接し方」のようなものが増えてきた、という話の中で、精神障害者やLGBTが挙がっていた。 "ですが「患者」とか、「元気な人」とかいったように、それぞれの人間が持つ特性にラベルがつけられ、ラベル同士のあるべき連結の仕方が、関係性を具体的に作る人々の外側にいる、ラベルについて深い知識を持っているとされる人たちによって、頻繁に提示されることに私は少々違和感を覚えています。加えて、「あるべき形」から外れた連結が、「元気な人」(マジョリティといってもいいでしょう)から試みられた時、深い知識を持っている人々が、多様性を損ねるとか、配慮がないとか、差別とかいった言葉を掲げ、それを試みた側を糾弾する姿を見ると、その違和感はより増します。 (中略)そのような正義の鉄槌をためらいもなく振りかざす人たちを見ると、「多様な社会とか、人々の繋がりってこんな形で達成されるんだっけ?」と考え込んでしまうのです。"(P182) あまりにもSNSでよく見る景色。そして何度もそれを目にした結果、私たちが内面化してしまっている景色。 でもそれでは人と人の関係はさまざまな可能性を持つ「ライン」を描けず、硬直した連結器になってしまう。連結器の関係にすれば痛みはないが、それ以外もない。 「ラインを描く」って、単純化すれば勇気を出して人を社会を、自分(たち)を信頼するということなんだと思う。 クィアや障害者、在日外国人など被差別的マイノリティは人や社会に傷つけられて、信頼ができない状況にたびたび陥る。がん患者としての宮野さんの立場をこうした被差別的マイノリティと置き換えながら読んできたが、明確な「悪意」に接触する量の多さが、違う点かもしれない。とにかく悪意に取り囲まれているから、「信頼しよう!」とは単純にはなかなか言えない。その信頼を悪用されたりするから(それもまたラインを描けなくさせる要因だろう) でも、だからといって自分で自分をラベルに固定して、適切さの内にとどまっていて良いとは思えない。 どんな言葉なら届くだろう?「宮野の生き様を見ろ!」と言えばいいのかな。 - 2025年8月26日
 急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読んでる第6便から第8便まで。 「100パーセント患者」と「0パーセント患者」の2つのフェーズを使い分けていたのが、病が進行してくるとフェーズが衝突することが増えてくる(楽しく友達とお酒を飲む約束をしようとしていたのに、吐き気があったり、ひどい痛みに襲われることがあることを伝えたほうがいいか迷う、など)。そうすると会話が患者本人と患者の関係者、のものとして固定され、ぎこちなくなってくる。(p137) 引き続きマイノリティの話に置き換えながら読んでいるが、これは友達とかのレベルではマイノリティでも起こるなと思う。ただ、パートナーのような親しい人との間では起こりにくい(それも属性によるだろうが)ので、この点は病気というその人の身体で起こる固有性ならではかもしれない。 それに対する7便での磯野さんの返信。「お大事に」などの定型が使えなくなっていって、どんな言葉なら相手を傷つけないのか、傷つけた事実によって自分が傷を負うのを避けられるのかを考え、言葉につまる。その結果、言葉がどんどん硬直していき、「相互虚偽」と呼ばれる状態に陥っていく。(p148) そう、こういう硬直したやりとりを超えていく方法を自分は模索しているんだよな…!時々それこそが正しいコミュニケーションのように語られるけど、やっぱり抗っていきたいと思った。 8便以降は「死」というこの対話にとって本丸となる話に入っていく。続きを読むのが楽しみであり、同時に怖くもある
急に具合が悪くなる宮野真生子,磯野真穂読んでる第6便から第8便まで。 「100パーセント患者」と「0パーセント患者」の2つのフェーズを使い分けていたのが、病が進行してくるとフェーズが衝突することが増えてくる(楽しく友達とお酒を飲む約束をしようとしていたのに、吐き気があったり、ひどい痛みに襲われることがあることを伝えたほうがいいか迷う、など)。そうすると会話が患者本人と患者の関係者、のものとして固定され、ぎこちなくなってくる。(p137) 引き続きマイノリティの話に置き換えながら読んでいるが、これは友達とかのレベルではマイノリティでも起こるなと思う。ただ、パートナーのような親しい人との間では起こりにくい(それも属性によるだろうが)ので、この点は病気というその人の身体で起こる固有性ならではかもしれない。 それに対する7便での磯野さんの返信。「お大事に」などの定型が使えなくなっていって、どんな言葉なら相手を傷つけないのか、傷つけた事実によって自分が傷を負うのを避けられるのかを考え、言葉につまる。その結果、言葉がどんどん硬直していき、「相互虚偽」と呼ばれる状態に陥っていく。(p148) そう、こういう硬直したやりとりを超えていく方法を自分は模索しているんだよな…!時々それこそが正しいコミュニケーションのように語られるけど、やっぱり抗っていきたいと思った。 8便以降は「死」というこの対話にとって本丸となる話に入っていく。続きを読むのが楽しみであり、同時に怖くもある
読み込み中...