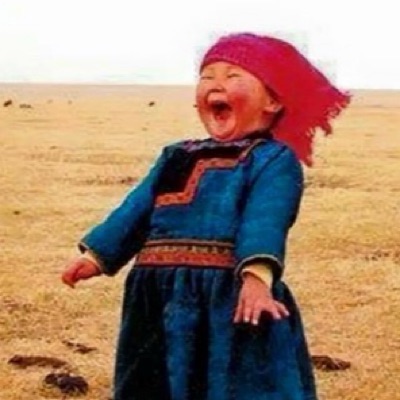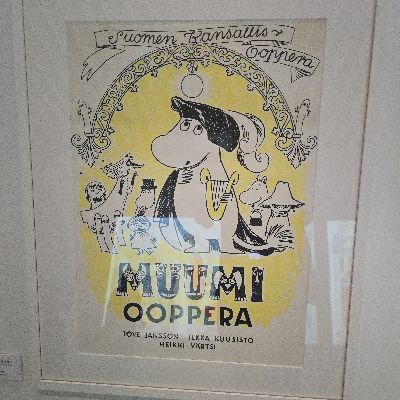なぜ書くのか

39件の記録
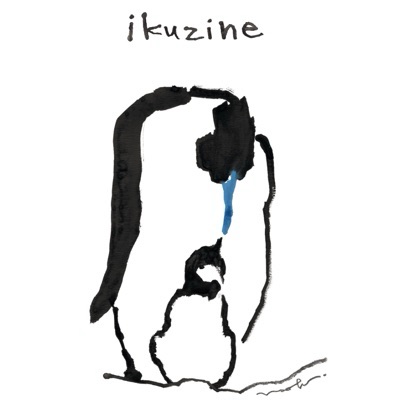 Yamada Keisuke@afro1082026年2月10日読み終わったタナハシ・コーツの新作でこのタイトルとなれば読まざるを得ないと思って読んだ。『世界と僕のあいだに』で好きになって、そのあと小説『ウォーターダンサー』を読んだが、アフリカ系アメリカンの立場からアメリカの過去から現在をリリカルに描き出す書き手だという印象を持っている。本著も紀行文の形式でありながら、彼自身の思考をユニークな表現で提示してくれている一冊だった。 第1章ではタイトルどおり「書くこと」に関する論考が展開されるが、それ以降はセネガル、パレスチナ、アメリカ南部を訪れ、自身の目で見て、耳で聴いて得た知見を基に、彼ならではのパースペクティブで現状を分析している。インターネットのおかげで、なんでもわかったような気にはなっていても実際に訪問して見える景色は別物だと痛感させられる。上記の訪問場所は、時間的、精神的にもコストを伴うものであり、コーツほどの筆力であれば行かずとも素晴らしい文章を書けるだろうが、きちんと取材して自分の中で腹落ちしたものがアウトプットとして出てきている書きっぷりに彼の真髄を見た。 邦題は「書くこと」に寄せているが、著者が最初に提示するのは読む必要性である。試合中の不慮の事故で四肢麻痺となったアメフトのワイドレシーバーの話や、シェイクスピアとラキムへの言及を通して、読むことの意味とナラティブの力が語られる。独自の視点でツカミはバッチリだ。 第二章は初めて訪れるアフリカの地・セネガルの旅行記であり、同時にアフリカ論でもある。ワンドロップルールの不条理さをアフリカの視点で、おもしろおかしく描いているところにウィットを感じる。さらにトニ・モリスン『青い目が欲しい』を引用しながら、外見と人種の問題へと接続していく。アフリカを訪れた経験によって西洋的価値観が相対化され、「西洋の枠組みの外側にもカルチャーがある」という主張は、自分の好きなヒップホップやR&Bの在り方を考えさせるものだった。 私たち自身の人生や文化ー音楽、ダンス、書くことーはすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。 ちょうど選挙のタイミングで読んでいたこともあり、サウス・カロライナ州を訪れて教育委員会の会議に参加する第三章が一番グッときた。著作である『世界と僕のあいだに』が禁書になりそうという話を聞きつけて、現場に自ら足を運ぶ。そこでは賛成派、反対派による派手な衝突が起こるわけではないのだが、禁書に反対する市民がその場で意思表示を行い、誤った判断が是正されていく。そんな当たり前とも言える場面が印象に残った。こういった市民活動の成功体験が政治との距離を縮め、市民の連帯が民主主義を支えているのだと感じた。今の日本に必要なことはこうした生身の横の連帯なのではないか。必要以上に個別化が進み、接触頻度の高いSNSの情報に振り回される現状が、本著を読むと空虚に映った。 そして、もっともページ数を割いているのが、パレスチナ訪問に関する4章である。今に至るまで続く紛争以前のパレスチナの日常や社会の空気といったリアルな実情を手記で読めることが貴重である。外形的な情報はネットや専門書で得ることができるかもしれないが、パーソナルな視点と論考を行き来する構成だからこそ地に足がついている印象を持った。 著者ならではの視点といえば、アメリカにおけるアフリカ系アメリカンと、イスラエルにおけるパレスチナ人の立場の比較であろう。人種差別の被害者であった歴史を持つユダヤ人が、パレスチナ人に対して加害者として振る舞っている現実に驚いた。真綿で首を締めるようなイスラエルからパレスチナ人に対する迫害の状況に読んでいて苦しい。さらにアメリカとイスラエルの複雑な関係性が、アフリカ系アメリカンである著者がパレスチナを訪れる過程のなかで徐々に立ち現れる。読者は著者に伴走するように未知の過酷な現実を知っていくことになりスリリングだった。 著者は過去と現在を接続して自分のリアルな手触りを語り下ろしていく手腕が本当に見事だなと今回も感じた。調査能力もありながら、その結果を噛み砕き、さらには自分の経験もスムーズに混ぜ込んでいく、エッセイ以上論文未満のこの塩梅が、個人的にはとても心地よい。このブログや日本語ラップのnoteも著者のようなスタイルでやっていきたい。 書くこと、書き直してゆくことは、たんに真実を伝えるだけでなく、真実がもたらす恍惚をも伝えようとする営みなのだ。私にとっては、読者に私の主張を納得させるだけでは十分ではない。私が一人で感じているあの特別な歓びをともに感じてほしいのだ。世のなかで、誰かがその歓びの一部でも共有したと聞くことは嬉しいものだ。
Yamada Keisuke@afro1082026年2月10日読み終わったタナハシ・コーツの新作でこのタイトルとなれば読まざるを得ないと思って読んだ。『世界と僕のあいだに』で好きになって、そのあと小説『ウォーターダンサー』を読んだが、アフリカ系アメリカンの立場からアメリカの過去から現在をリリカルに描き出す書き手だという印象を持っている。本著も紀行文の形式でありながら、彼自身の思考をユニークな表現で提示してくれている一冊だった。 第1章ではタイトルどおり「書くこと」に関する論考が展開されるが、それ以降はセネガル、パレスチナ、アメリカ南部を訪れ、自身の目で見て、耳で聴いて得た知見を基に、彼ならではのパースペクティブで現状を分析している。インターネットのおかげで、なんでもわかったような気にはなっていても実際に訪問して見える景色は別物だと痛感させられる。上記の訪問場所は、時間的、精神的にもコストを伴うものであり、コーツほどの筆力であれば行かずとも素晴らしい文章を書けるだろうが、きちんと取材して自分の中で腹落ちしたものがアウトプットとして出てきている書きっぷりに彼の真髄を見た。 邦題は「書くこと」に寄せているが、著者が最初に提示するのは読む必要性である。試合中の不慮の事故で四肢麻痺となったアメフトのワイドレシーバーの話や、シェイクスピアとラキムへの言及を通して、読むことの意味とナラティブの力が語られる。独自の視点でツカミはバッチリだ。 第二章は初めて訪れるアフリカの地・セネガルの旅行記であり、同時にアフリカ論でもある。ワンドロップルールの不条理さをアフリカの視点で、おもしろおかしく描いているところにウィットを感じる。さらにトニ・モリスン『青い目が欲しい』を引用しながら、外見と人種の問題へと接続していく。アフリカを訪れた経験によって西洋的価値観が相対化され、「西洋の枠組みの外側にもカルチャーがある」という主張は、自分の好きなヒップホップやR&Bの在り方を考えさせるものだった。 私たち自身の人生や文化ー音楽、ダンス、書くことーはすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。 ちょうど選挙のタイミングで読んでいたこともあり、サウス・カロライナ州を訪れて教育委員会の会議に参加する第三章が一番グッときた。著作である『世界と僕のあいだに』が禁書になりそうという話を聞きつけて、現場に自ら足を運ぶ。そこでは賛成派、反対派による派手な衝突が起こるわけではないのだが、禁書に反対する市民がその場で意思表示を行い、誤った判断が是正されていく。そんな当たり前とも言える場面が印象に残った。こういった市民活動の成功体験が政治との距離を縮め、市民の連帯が民主主義を支えているのだと感じた。今の日本に必要なことはこうした生身の横の連帯なのではないか。必要以上に個別化が進み、接触頻度の高いSNSの情報に振り回される現状が、本著を読むと空虚に映った。 そして、もっともページ数を割いているのが、パレスチナ訪問に関する4章である。今に至るまで続く紛争以前のパレスチナの日常や社会の空気といったリアルな実情を手記で読めることが貴重である。外形的な情報はネットや専門書で得ることができるかもしれないが、パーソナルな視点と論考を行き来する構成だからこそ地に足がついている印象を持った。 著者ならではの視点といえば、アメリカにおけるアフリカ系アメリカンと、イスラエルにおけるパレスチナ人の立場の比較であろう。人種差別の被害者であった歴史を持つユダヤ人が、パレスチナ人に対して加害者として振る舞っている現実に驚いた。真綿で首を締めるようなイスラエルからパレスチナ人に対する迫害の状況に読んでいて苦しい。さらにアメリカとイスラエルの複雑な関係性が、アフリカ系アメリカンである著者がパレスチナを訪れる過程のなかで徐々に立ち現れる。読者は著者に伴走するように未知の過酷な現実を知っていくことになりスリリングだった。 著者は過去と現在を接続して自分のリアルな手触りを語り下ろしていく手腕が本当に見事だなと今回も感じた。調査能力もありながら、その結果を噛み砕き、さらには自分の経験もスムーズに混ぜ込んでいく、エッセイ以上論文未満のこの塩梅が、個人的にはとても心地よい。このブログや日本語ラップのnoteも著者のようなスタイルでやっていきたい。 書くこと、書き直してゆくことは、たんに真実を伝えるだけでなく、真実がもたらす恍惚をも伝えようとする営みなのだ。私にとっては、読者に私の主張を納得させるだけでは十分ではない。私が一人で感じているあの特別な歓びをともに感じてほしいのだ。世のなかで、誰かがその歓びの一部でも共有したと聞くことは嬉しいものだ。

 𝚗𝚊𝚝@sapphicalien2026年1月22日読み終わったパレスチナ訪問の章がすばらしかった ──「シオニズムの犠牲者たち」。今でも、あれほどのことを見てきた後でも、この言葉をあなたたちに書こうとすると、ペンがそれを避けてしまう。私はニューヨークに戻っていて、朝のコーヒーを飲みながら、バックグラウンドでジョーン・アーマトレイディングを聴いている。「あんたはあたしの味方、それとも敵なの/あたしたちはどこかへ辿り着こうとしているの」と歌う声。そして向こうと同じように、美しい太陽が雲一つない空に輝いている。帰国してから一年が経つが、ときどき、まだパレスチナにいるのだと夢見ることがある。その夢のなかには心地よいものもある——サキヤの崖の上で穏やかな気持ちでいる自分、あたたかいエルサレムセサミブレッドに緑色のひよこ豆のコロッケを包み込む自分、ラマッラーの喧騒とエネルギーを感じる自分、英語を練習したいというトゥバスの小さな女の子に微笑みかける自分……。つまり、私のペンは当たり前だがここでその言葉を避けてしまう。なぜなら、パレスチナ人であるということを、「シオニズムの犠牲者」で片付けてはならないからだ。たしかに、それ以外のこともあるのだ……。(164-165)
𝚗𝚊𝚝@sapphicalien2026年1月22日読み終わったパレスチナ訪問の章がすばらしかった ──「シオニズムの犠牲者たち」。今でも、あれほどのことを見てきた後でも、この言葉をあなたたちに書こうとすると、ペンがそれを避けてしまう。私はニューヨークに戻っていて、朝のコーヒーを飲みながら、バックグラウンドでジョーン・アーマトレイディングを聴いている。「あんたはあたしの味方、それとも敵なの/あたしたちはどこかへ辿り着こうとしているの」と歌う声。そして向こうと同じように、美しい太陽が雲一つない空に輝いている。帰国してから一年が経つが、ときどき、まだパレスチナにいるのだと夢見ることがある。その夢のなかには心地よいものもある——サキヤの崖の上で穏やかな気持ちでいる自分、あたたかいエルサレムセサミブレッドに緑色のひよこ豆のコロッケを包み込む自分、ラマッラーの喧騒とエネルギーを感じる自分、英語を練習したいというトゥバスの小さな女の子に微笑みかける自分……。つまり、私のペンは当たり前だがここでその言葉を避けてしまう。なぜなら、パレスチナ人であるということを、「シオニズムの犠牲者」で片付けてはならないからだ。たしかに、それ以外のこともあるのだ……。(164-165)


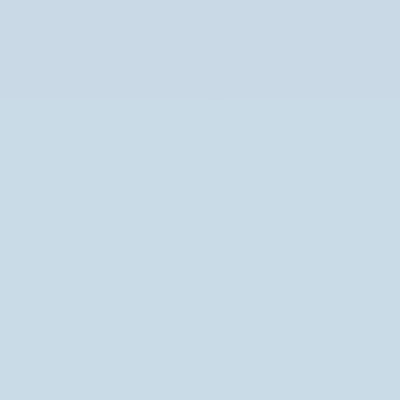
 柿内正午@kakisiesta2025年12月1日“非難する相手の人間たちの持つ法に基づいて告発を行うのは、あなたたちにとって危険なやり方である。どれほど自らの動機を心に留めようとしても、どれほど自分が成功したと感じたとしても、最終的には彼らの世界のなかにいることになり、したがって彼らのシンボルや物語を通して語らざるをえない。そして、あなたたちが彼らにとって異邦人であったり、それどころか敵対者であったりするならば、その必要性はいっそう高まる。というのも、あなたたちの主張はつねにより大きな懐疑の目で見られるからである。(…)” p.103
柿内正午@kakisiesta2025年12月1日“非難する相手の人間たちの持つ法に基づいて告発を行うのは、あなたたちにとって危険なやり方である。どれほど自らの動機を心に留めようとしても、どれほど自分が成功したと感じたとしても、最終的には彼らの世界のなかにいることになり、したがって彼らのシンボルや物語を通して語らざるをえない。そして、あなたたちが彼らにとって異邦人であったり、それどころか敵対者であったりするならば、その必要性はいっそう高まる。というのも、あなたたちの主張はつねにより大きな懐疑の目で見られるからである。(…)” p.103






- 🐧@penguin2025年9月3日読み終わった4章、パレスチナを訪れた記録。 コーツは出世作「賠償訴求訴訟」でアメリカは過去の奴隷制に対して黒人コミュニティに賠償すべきという主張を展開しているが、その論拠としてドイツのイスラエルに対する賠償を挙げた。が、これはイスラエルによるパレスチナ占領を踏まえていないという批判を受けた。この批判がパレスチナを訪れる契機となっている。 ホロコーストからのユダヤ人国家建設、という物語にあらゆるところで触れてきたアメリカ人が、パレスチナのことを知った時にそれを認めるのがいかに難しいかが、コーツ自身の動揺から伝わる。それはイスラエルがパレスチナ人に行っていることとアメリカが黒人たちに行っていることの相似、そしてそれを知らなかったことへの痛みとともに書き進めていく。 コーツでさえそうなのだと思うと、アメリカとイスラエルのつながりってなんて強いんだろうと気が遠くなる。 訪れたのは2023年夏。この時点で、パレスチナの痛みについて限りなく言葉を尽くしているように思える。現在のジェノサイドは本当に、表現できる言葉などないような惨劇なのだと改めて思う。 p161 "私が目の当たりにしたこの取り組み、つまり考古学を援用し、古代の遺跡を破壊し、パレスチナ人を家から追放することは、アメリカ合衆国の具体的な認可を受けていた。ということは、それは私の認可を受けていたことを意味する。これは別の国によってなされる別の悪行だというにとどまらず、私の名のもとに行われた悪行でもあったのだ。" p174 "この訪問の終わりまでに、私は「ナクバ」を、ジム・クロウや植民地主義、アパルトヘイトといった類似のものを超えた特別なものとして理解するようになっていた。それはたんに警察があなたの息子を撃つことだけではなく(それもありうる)、たんなる人種差別的な監獄制度でもなく(それもここには存在する)、たんに法の前での不平等でもない(それも私の目に入る至る所にあった)。ナクバは、そういったやり口のどれもが役立ったものである——すなわちホームの略奪であり、それは身近なものでもあり恒久的なものでもある略奪である。"
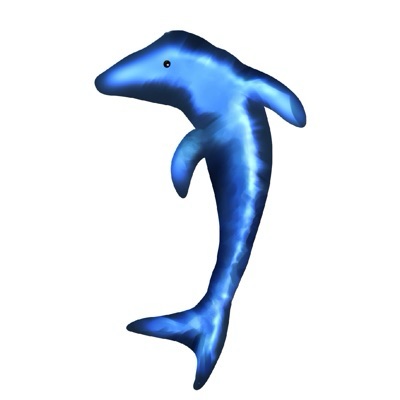
- 🐧@penguin2025年9月2日読んでる3章。自身の著作『世界と僕のあいだに』がサウス・カロライナ州のメアリーという教師の授業計画から強制的に排除されようとしていることを知り、その教師に連絡を取る。 アメリカの禁書運動は逆説的に言葉にどれほどの力があるか、どれほど言葉が恐れられているかを証明している。そのことを、メアリーとその支持者たちの運動と著者の体験を「書くこと」で露呈させる。 p76 二〇二〇年の夏の重要性を払いのけようとする衝動は理解できる。「人種的正義についての全国的な対話」や数多くのテレビの特集やドキュメンタリー、さらには抗議活動そのものさえも無意味だと切り捨てたくなる気持ちもわかる。私たちのなかの一部の人びとは、政策の変化に反映されなかったのを見て、その運動自体が無駄だったと思うかもしれない。けれど、政策の変化は終点であって始まりではない。重要な変化が生まれるのは、私たちの想像力とアイデアのなかでだ。 p80 執筆を始めた頃の私には、白人を読者として意識することを極力避け、彼らを頭のなかで単純化し、「翻訳」しようという誘惑に抗うことが必須だと思えていた。それは正しかったと思う。けれど、今回これまでで驚きなのは——喜ばしい驚きではあるが——実際には翻訳は必要ないし、深く掘り下げてゆけば自ずと人間性が明らかになるということだった。ルールにあるように「具体を通って全体へ達せよ」。


- 🐧@penguin2025年8月31日読み始めた読みはじめた。文章の強靭なしなやかさに惹かれる。翻訳でしか読めてないけどきっと原文もリズムがいいんじゃないか。力強く、背筋を正される。 この本の導入的な位置付けでもありそうな1章、自身のルーツを探るセネガルへの旅を描いた2章まで読む。黒人の文化や歴史にそこまで詳しくない自分にとっては複雑なところもある。しかし難解な書き方ではなく、豊かさと悲しみが伝わってくる。 "私たちはもっと深い何ものかによって引き寄せられていたのだ。 その何ものかとは、私たちの大学に、つまりハワード大学は奴隷制という長い影と闘うために設立された、ということに由来するのだろう——その影はまだ消えていないことを私たちは理解していた。 それだからこそ、私たちはたんなるスキルとしてライティングを学ぶわけにはゆかず、学ぶことがより大きな解放の便命に奉仕するものであると借じる必要があった。そのことは、直接言及されることがなくても、何かにつけて暗黙の棚に了解されていた。私たちが取り組んだ作品はどれも、「人間であることの些細なことども」を扱っていたが、これは文学が一般的に扱うものだ。けれどあなたたちが、私たち黒人がこれまで生きてきたように、いつでも人間であることを疑問視されるグループのなかで生きているなら、その「些細なことども」でさえ——いやいや些細なことだからこそ——政治的な意味を持ってしまう。あなたたちにとって、書くことと政治のあいだには隔たりは存在しえないからだ。"p2 "私たちは、黒人として、こちら側でもあちら側でも、西洋の犠牲者である——西洋のリベラルな食 言の外側に押し出されているが、西洋の約束に魅了されるほどには近いところに留められている。私たちは西洋という家の美しさを知っている——その石灰岩の階段、羽目板、大理石の浴室…....。けれと私たちが知っているのはそれだけじゃない。この家が呪われていること、レンガに血が染み込んでおり、屋根裏には幽霊が住んでいることも私たちは知っている。この状態には悲劇と喜劇の両方があることも理解している。私たち自身の人生や文化——音楽、ダンス、書くこと——はすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。"p46
 mikechatoran@mikechatoran2025年8月9日読み終わった海外文学タナハシ・コーツを初めて読んだが、すばらしい読み応えだった。1章は若者に向けての執筆入門のようなもの、2章は自らのルーツであるセネガルへの旅、3章は第一次トランプ政権後のサウスカロライナへの旅、4章はパレスチナへの旅について。4章がやはりすごかった。10日間の旅だということだったが、パレスチナ(土地と人)へのシステマティックな暴力とアパルトヘイト、イスラエルという国のフィクション的なありよう、シオニズムの植民地主義を暴いている。その上でパレスチナ人自身による発言の重要性を指摘する。アダニーヤ・シブリー『とるに足りない細部』で描かれた不条理がいかによく考えられたものかが垣間みえて一層慄然とした。
mikechatoran@mikechatoran2025年8月9日読み終わった海外文学タナハシ・コーツを初めて読んだが、すばらしい読み応えだった。1章は若者に向けての執筆入門のようなもの、2章は自らのルーツであるセネガルへの旅、3章は第一次トランプ政権後のサウスカロライナへの旅、4章はパレスチナへの旅について。4章がやはりすごかった。10日間の旅だということだったが、パレスチナ(土地と人)へのシステマティックな暴力とアパルトヘイト、イスラエルという国のフィクション的なありよう、シオニズムの植民地主義を暴いている。その上でパレスチナ人自身による発言の重要性を指摘する。アダニーヤ・シブリー『とるに足りない細部』で描かれた不条理がいかによく考えられたものかが垣間みえて一層慄然とした。