
いずみがわ
@IzuMigawa_itsu
2025年9月11日
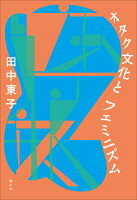
オタク文化とフェミニズム
田中東子
読み終わった
前職にいたころは『浪費図鑑』が楽しく読めていた。けれど環境が変わり「あれ?これってもしかして世の中全てのオタクがあるあるって頷く話じゃなくない?」とモヤモヤし始めた。
コロナ禍で『ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在』の水上文さんの「〈消費者フェミニズム〉批判序説」を読み、だから今私は苦しいしモヤモヤしているんだ!と膝を打つに至った。
そして現在、あの頃から今に至るまでハマってると言える趣味のひとつの節目を迎えるにあたり本書を読んだ。
三次元の推しがいるフォロワーの自我がだんだん無くなってゆく。
そんな体験をしているひとは少なくないだろう。どうでもいいぽわんとしたこと、ときに愚痴も吐いてたあのひとのツイートがだんだん変わってゆくのだ。(私はTwitterと呼ぶ人間です)
そのひとの推しの公式リツイ。「あと何百再生で○○○万再生です。/サブスクでの順位が落ちています。みなさん頑張りましょう」という謎のアナウンス。ドラマや曲名、推しのハッシュタグを併記したキラキラポジティブなツイート。発売日にはお迎えツイート。ライブ参加報告。自身のフォロワーからの視線を考慮して愚痴や政治の話はしない。
そんなひとを何人も見てきた。
本書では、それが本来公式・運営側がお金をかけてプロモーションしなければいけないことを、オタクが好きという気持ちから無償で担わされる搾取だと指摘している。そして推される側のアイドル・アーティストも、移動時間や自宅での時間を使える限り自身のブランド化のためSNSでファンと交流し、正当な報酬を支払われることが少ない感情労働を行っている、と。
可処分時間を全て推しに捧げた結果、リアルに生きる自分自身や周りの社会の問題に目がいかなくなり、それに費やすエネルギーを失ってしまう。日本のように労働時間がバカ長い社会で一億総推し活をすればなるほど、政治のことなんて誰も考えないだろう。
私も応援しているひとがいる。でも今まで「応援のため」とやっていたことをもう止めることにした。
…私が何をせずとも、もうそのひとがある頂点を極めたという幸運もきっかけの一つである。不安な気持ちと別れなければ、なかなかこの決定に至れなかった。
この先行きがわからない社会で、生きているひとを推すことは不安と隣り合わせだ。でも不安な心はお金を落とすし、陰謀論との相性も抜群である。
誰かを好きで応援してるひとがキラキラしているのは確かにそうだ。でも私はあなたの愚痴も聞きたいし、社会や政治の話もしたい。「推し、ちゃんと休めてる?」と心配しているならなおさら。
「推し疲れ」でモヤモヤしているひとは、そのモヤモヤから目を逸らさないでほしい。推しが好き!って気持ちだけじゃなくて、ましてやかけたお金を開示しあうことじゃなくて、そのモヤモヤからでも誰かと繋がって連帯できる可能性もあるのだから。




