

いずみがわ
@IzuMigawa_itsu
フェミニズム、クィア、ノンフィクション、🇩🇪🇷🇺🇰🇷が気になる。児童文学再履修。
- 2026年2月24日
 望月の烏阿部智里読み終わった「私に説得力がないというのは、反論の余地がございません。でも、理不尽を見て見ぬふりをする者は、いつか必ず理不尽に殺されます」 俵之丞と澄生は見つめ合った。 「いつ、博陸侯の望む『良い民』から自分が外れるか分からないのに、どうして自分だけは大丈夫と思えるのですか?」 p.276 この巻で1番うぇええと思ったのは、凪彦が竜笛を吹く描写ですかね…。源氏物語的な遊び心。胸糞!!!(褒め) 源氏物語といえば、政の、イエの道具にされたくないという女の反乱、どうなるんだろう。 澄生がトップになれば解決する話ではもちろん、ない。宮の中や貴族の間だけじゃない、さまざまな階級の女が連帯するところが見たいけど…。 理想主義と現実主義のぶつかり合い。性善説と性悪説。この世の善性を信じたい澄生と、山内への感情は愛憎半ばに見える雪哉。あの春の夜から、一方が生きる限り他方は生きられないところまで来てしまった。この物語は春終わる。そんな気がする。そのとき桜の下に立っていられるのは誰なんだろう。
望月の烏阿部智里読み終わった「私に説得力がないというのは、反論の余地がございません。でも、理不尽を見て見ぬふりをする者は、いつか必ず理不尽に殺されます」 俵之丞と澄生は見つめ合った。 「いつ、博陸侯の望む『良い民』から自分が外れるか分からないのに、どうして自分だけは大丈夫と思えるのですか?」 p.276 この巻で1番うぇええと思ったのは、凪彦が竜笛を吹く描写ですかね…。源氏物語的な遊び心。胸糞!!!(褒め) 源氏物語といえば、政の、イエの道具にされたくないという女の反乱、どうなるんだろう。 澄生がトップになれば解決する話ではもちろん、ない。宮の中や貴族の間だけじゃない、さまざまな階級の女が連帯するところが見たいけど…。 理想主義と現実主義のぶつかり合い。性善説と性悪説。この世の善性を信じたい澄生と、山内への感情は愛憎半ばに見える雪哉。あの春の夜から、一方が生きる限り他方は生きられないところまで来てしまった。この物語は春終わる。そんな気がする。そのとき桜の下に立っていられるのは誰なんだろう。 - 2026年2月15日
 女の子たちと公的機関ダリア・セレンコ,クセニヤ・チャルィエワ,高柳聡子読み終わっただけど私たち女の子は、正直言って、もう子どもなんかもつことはないだろう。私たちには新しい人間を生む気力なんかない、縫い目がほつれていっているあんたたちの底なしの闇を自分の身体で塞いであげる新たな女の子たちの一軍を生むなんて。 p99 ほんまそれ でも私の友人は、何の因果か女の子のママが多い。 彼女たちのためにも抵抗しなければいけないんだ。
女の子たちと公的機関ダリア・セレンコ,クセニヤ・チャルィエワ,高柳聡子読み終わっただけど私たち女の子は、正直言って、もう子どもなんかもつことはないだろう。私たちには新しい人間を生む気力なんかない、縫い目がほつれていっているあんたたちの底なしの闇を自分の身体で塞いであげる新たな女の子たちの一軍を生むなんて。 p99 ほんまそれ でも私の友人は、何の因果か女の子のママが多い。 彼女たちのためにも抵抗しなければいけないんだ。 - 2026年2月6日
 本をすすめる近藤康太郎読み終わったこの本を読んで頭に浮かんだのはEXILE SHOKICHIさんだった。 音楽を愛し、思うようにミュージシャンとしてのキャリアを歩めない時期にもその好きを手放さなかった。 知ることに貪欲で、好きなアーティストからどんどんdigる。クラシックも聴きに行く。 音楽のみならずワインや肉にもハマったらとことん突き詰め、ブルゴーニュに行ったりエスコンフィールド北海道に店を作るまでやる。 愛。誠実さ。好きを諦めない。学び続ける。 「つまり、必死に生きろ、と。人に親切にしろ。善く生きろということ。書評も、同じだと思うんです。」p304 (ここ…まんましょーちゃん) SHOKICHIさんのように生きて学べば、クラシックの骨格を持った揺るがぬオリジナリティある書評が書けるのか。 明日朝起きたとき15分読書するための古典、忘れずに枕元にセットしておこう。彼ならそうするから。
本をすすめる近藤康太郎読み終わったこの本を読んで頭に浮かんだのはEXILE SHOKICHIさんだった。 音楽を愛し、思うようにミュージシャンとしてのキャリアを歩めない時期にもその好きを手放さなかった。 知ることに貪欲で、好きなアーティストからどんどんdigる。クラシックも聴きに行く。 音楽のみならずワインや肉にもハマったらとことん突き詰め、ブルゴーニュに行ったりエスコンフィールド北海道に店を作るまでやる。 愛。誠実さ。好きを諦めない。学び続ける。 「つまり、必死に生きろ、と。人に親切にしろ。善く生きろということ。書評も、同じだと思うんです。」p304 (ここ…まんましょーちゃん) SHOKICHIさんのように生きて学べば、クラシックの骨格を持った揺るがぬオリジナリティある書評が書けるのか。 明日朝起きたとき15分読書するための古典、忘れずに枕元にセットしておこう。彼ならそうするから。 - 2026年2月2日
- 2026年2月1日
 花咲く街の少女たち青波杏読み終わった冒頭で「阿部定とかいう女」が起こした事件が新聞を騒がせているのを、主人公の翠はチラリと見るが関心を持たない。 しかしラスト、おのれの人生を歩き始めた翠は、グロテスクな犯罪の後ろにある定の来し方に想いを馳せ知りたいと願う女性になっているだろう。
花咲く街の少女たち青波杏読み終わった冒頭で「阿部定とかいう女」が起こした事件が新聞を騒がせているのを、主人公の翠はチラリと見るが関心を持たない。 しかしラスト、おのれの人生を歩き始めた翠は、グロテスクな犯罪の後ろにある定の来し方に想いを馳せ知りたいと願う女性になっているだろう。 - 2026年1月15日
 エレガンス石川智健読み終わった「犯罪を見逃すのは、罪を許容することと同義です。空から爆弾を落として罪なき人々を殺している行為を容認することと同じなんです。我々は許されざる行為を糾弾する役目を担わなければならないんです」p154 吉川澄一先生、三澄ミコトでしたわ。 ひとりの尊厳を守ることが、世界を守ることなんだね。 文学、科学、ファッション、そして歴史、色んな要素が入っていて読み応えがあった。キーワードが何度も違う側面を持って出てくるのも面白い。 犯人はなんとなくわかってしまったけれど… p324からの空襲の描写が圧巻。石川光陽が五感を全開にしてライカのレンズ、シャッターと繋がって地獄を記録する2時間半が、改行一切なしの構成で読んでるこちらの瞳孔も開いていく。 対してもうひとりの目線で描くp336からの描写は夢と現実がないまぜになって、この小説を読んできたからこその涙が出てしまう。 追記 家のもの、国家のものじゃない自分を守る抵抗のためのファッション、胸が熱くなった。自分の身体は自分のもの。 全体主義にコミットしたひとたち(警察組織、特高、憲兵etc)には見えない「洋装」「洋髪」の違いを知るドレ女の面々やパーマ屋さん。そして人間が無意識にかけるフィルターを全て剥がすカメラの眼。違いを見極める目が事件解決の鍵になる。世界の解像度が下がるのは、見ようとしてないから。個々の生活、幸せ、苦しみ、夢…それを塗りつぶすのが全体主義、そして戦争なんだよな。 …今の私たちはその写真すら信じられないと思うと悲しい。 永井荷風とのちに成功したオタク(?)になる小西茂也のすれ違いはクスッと笑えた。
エレガンス石川智健読み終わった「犯罪を見逃すのは、罪を許容することと同義です。空から爆弾を落として罪なき人々を殺している行為を容認することと同じなんです。我々は許されざる行為を糾弾する役目を担わなければならないんです」p154 吉川澄一先生、三澄ミコトでしたわ。 ひとりの尊厳を守ることが、世界を守ることなんだね。 文学、科学、ファッション、そして歴史、色んな要素が入っていて読み応えがあった。キーワードが何度も違う側面を持って出てくるのも面白い。 犯人はなんとなくわかってしまったけれど… p324からの空襲の描写が圧巻。石川光陽が五感を全開にしてライカのレンズ、シャッターと繋がって地獄を記録する2時間半が、改行一切なしの構成で読んでるこちらの瞳孔も開いていく。 対してもうひとりの目線で描くp336からの描写は夢と現実がないまぜになって、この小説を読んできたからこその涙が出てしまう。 追記 家のもの、国家のものじゃない自分を守る抵抗のためのファッション、胸が熱くなった。自分の身体は自分のもの。 全体主義にコミットしたひとたち(警察組織、特高、憲兵etc)には見えない「洋装」「洋髪」の違いを知るドレ女の面々やパーマ屋さん。そして人間が無意識にかけるフィルターを全て剥がすカメラの眼。違いを見極める目が事件解決の鍵になる。世界の解像度が下がるのは、見ようとしてないから。個々の生活、幸せ、苦しみ、夢…それを塗りつぶすのが全体主義、そして戦争なんだよな。 …今の私たちはその写真すら信じられないと思うと悲しい。 永井荷風とのちに成功したオタク(?)になる小西茂也のすれ違いはクスッと笑えた。 - 2026年1月13日
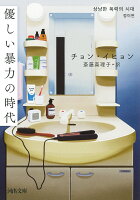 優しい暴力の時代チョン・イヒョン,斎藤真理子買ったかつて読んだ「今は、親切な優しい表情で傷つけ合う人々の時代であるらしい。礼儀正しく握手するために手を握って離すと、手のひらが刃ですっと切られている。傷の形をじっと見ていると、誰もが自分の刃について考えるようになる。」 単行本版に収録されていた作者の言葉をとっておいたのだった。 私はどっち側にいるの?という感覚になる短編集だった。 無視されて口を塞がれて蓋をされる側なのか だれかが暴力を受けてることがわかっていて目を逸らしている側なのか… 「ずうっと、夏」が読みたくて文庫版を買い直した。
優しい暴力の時代チョン・イヒョン,斎藤真理子買ったかつて読んだ「今は、親切な優しい表情で傷つけ合う人々の時代であるらしい。礼儀正しく握手するために手を握って離すと、手のひらが刃ですっと切られている。傷の形をじっと見ていると、誰もが自分の刃について考えるようになる。」 単行本版に収録されていた作者の言葉をとっておいたのだった。 私はどっち側にいるの?という感覚になる短編集だった。 無視されて口を塞がれて蓋をされる側なのか だれかが暴力を受けてることがわかっていて目を逸らしている側なのか… 「ずうっと、夏」が読みたくて文庫版を買い直した。 - 2026年1月11日
 未婚じゃなくて、非婚ですすんみ,ホンサムピギョル読み終わった私たちが夢見る未来。そこが、女性として生まれたという理由で、より多くのことを証明しなくてすむ場所であると願っている。 p.250 推し活からの卒業、脱コルセット…とめちゃくちゃに共感した。財テクは耳が痛い!!! 韓国は結婚しても姓が変わらない、ふーん…日本よりそこはいいじゃんと思ってたら、こどもには原則父の姓を継がせるという🫨 ここにはここの地獄がある。 困難だけどそんな未来に辿り着きたい。高い志なく結婚したくない女性が普通に老いて暮らせる世界がいい。 「生態系撹乱生物」上等!
未婚じゃなくて、非婚ですすんみ,ホンサムピギョル読み終わった私たちが夢見る未来。そこが、女性として生まれたという理由で、より多くのことを証明しなくてすむ場所であると願っている。 p.250 推し活からの卒業、脱コルセット…とめちゃくちゃに共感した。財テクは耳が痛い!!! 韓国は結婚しても姓が変わらない、ふーん…日本よりそこはいいじゃんと思ってたら、こどもには原則父の姓を継がせるという🫨 ここにはここの地獄がある。 困難だけどそんな未来に辿り着きたい。高い志なく結婚したくない女性が普通に老いて暮らせる世界がいい。 「生態系撹乱生物」上等! - 2025年12月28日
 給水塔から見た虹は窪美澄読み終わった熱い手だった。必死でひらがなを覚えるために短い鉛筆を握っていた手だ。p.342 私も仕事で海外にルーツを持つ人たちに接することがある。 家族や仕事を持って暮らす人から日本に来たばかりの技能実習生まで様々だ。自分だったら生まれも育ちもしてない外国でこんなに頑張れるかな…と今年も何度も想像した。 そしてこの本に出てくるのと同様、差別的な呼称や偏見は職場にも銃弾の如く飛び交っている。直撃してない「日本人」でも痛み感じるひと、いるんすよ。きっとわからないだろう。 そんな地獄のような世の救いの一つ本書。書いてくれてありがとう。私たちはひとりじゃないね。 桐乃がまたここに戻ってくるのか、それとも遠くに行ったままなのか。どちらにせよ私はインザハイツのベニーがニーナに言ったように「君はいつか世界を変える人だよ」と伝えたい。 ヒュウが父と訣別したのもよかった。ね、尾形。彼が罪と向き合う流れも誠実だと思う。彼がグエンおじさんにまた会いに来られますように。 桐乃もヒュウも、母や父と自分の境界線に気づき、見えてしまったその線にさみしさを知り、それでも身を剥がすように自分の人生に向き合っていく。 里穂さんは今すぐファブ5に会ってくれ!!!と読んでる途中は思ったけど、残念ながら彼らはなかなか日本に来てくれない。大学も出て複数言語を操る彼女が、非正規で働きながらこうして見返りを求めず人助けをしている。なんてこと。でも…ありがちな話だ。 これが父親だったら読み手の感情も違ったりして…とふと思う。「母親」に私たちが求めるものを省みる絶妙な設定。 ファブ5は言うだろう。「あなたはもっと称えられるべき。世の中からも、自分からも」 彼女はやっと中2の自分を抱きしめられた。この物語の書かれていない続きでもっと仲間が増えていたらいいな。組織立てて助ける体制ができたらいいのになと願っている。 装丁がちょっとキラキラフワフワしすぎでは…?そこはちょっと残念。
給水塔から見た虹は窪美澄読み終わった熱い手だった。必死でひらがなを覚えるために短い鉛筆を握っていた手だ。p.342 私も仕事で海外にルーツを持つ人たちに接することがある。 家族や仕事を持って暮らす人から日本に来たばかりの技能実習生まで様々だ。自分だったら生まれも育ちもしてない外国でこんなに頑張れるかな…と今年も何度も想像した。 そしてこの本に出てくるのと同様、差別的な呼称や偏見は職場にも銃弾の如く飛び交っている。直撃してない「日本人」でも痛み感じるひと、いるんすよ。きっとわからないだろう。 そんな地獄のような世の救いの一つ本書。書いてくれてありがとう。私たちはひとりじゃないね。 桐乃がまたここに戻ってくるのか、それとも遠くに行ったままなのか。どちらにせよ私はインザハイツのベニーがニーナに言ったように「君はいつか世界を変える人だよ」と伝えたい。 ヒュウが父と訣別したのもよかった。ね、尾形。彼が罪と向き合う流れも誠実だと思う。彼がグエンおじさんにまた会いに来られますように。 桐乃もヒュウも、母や父と自分の境界線に気づき、見えてしまったその線にさみしさを知り、それでも身を剥がすように自分の人生に向き合っていく。 里穂さんは今すぐファブ5に会ってくれ!!!と読んでる途中は思ったけど、残念ながら彼らはなかなか日本に来てくれない。大学も出て複数言語を操る彼女が、非正規で働きながらこうして見返りを求めず人助けをしている。なんてこと。でも…ありがちな話だ。 これが父親だったら読み手の感情も違ったりして…とふと思う。「母親」に私たちが求めるものを省みる絶妙な設定。 ファブ5は言うだろう。「あなたはもっと称えられるべき。世の中からも、自分からも」 彼女はやっと中2の自分を抱きしめられた。この物語の書かれていない続きでもっと仲間が増えていたらいいな。組織立てて助ける体制ができたらいいのになと願っている。 装丁がちょっとキラキラフワフワしすぎでは…?そこはちょっと残念。 - 2025年12月28日
 ランペシカ菅野雪虫読み終わったほろ苦ぇ…😢 英雄じゃなくても、過ちから学び続けるプクサのような人でいたい。 災害は人々をギスギスさせ、ひとつの敵が人々を団結させるというリアルを描いてらっしゃるのがさすが…さすがですわ…。 恋が綺麗に終わらず、痛みとして残り続ける。ランペシカがいつかどんな形ででもコタンを出て、もっと多くの人と出会えばいつかは薄れてゆくのかな。
ランペシカ菅野雪虫読み終わったほろ苦ぇ…😢 英雄じゃなくても、過ちから学び続けるプクサのような人でいたい。 災害は人々をギスギスさせ、ひとつの敵が人々を団結させるというリアルを描いてらっしゃるのがさすが…さすがですわ…。 恋が綺麗に終わらず、痛みとして残り続ける。ランペシカがいつかどんな形ででもコタンを出て、もっと多くの人と出会えばいつかは薄れてゆくのかな。 - 2025年12月27日
 黒龍の柩(下)北方謙三読み終わった小栗…こんな感じで死んじゃうんか… 作中の西郷は戦したがりの臆病者と描かれてるけど、危険な芽を早く摘む、捏造事件から開戦に畳み掛ける工作、スパイの使い方などこれぞ国家レベルの軍人で土方達との差を大いに感じてしまった。 下巻でアイヌのことをもっと掘り下げられるかと思ったら、そういう描写は無かった。残念。 久兵衛 なんだったんだ… 上巻でもうすこし狂気の片鱗が見えてたら後半の見え方も違ったかもしれない。 とにかく土方は最後までカッケェ男、浪漫を体現していた。
黒龍の柩(下)北方謙三読み終わった小栗…こんな感じで死んじゃうんか… 作中の西郷は戦したがりの臆病者と描かれてるけど、危険な芽を早く摘む、捏造事件から開戦に畳み掛ける工作、スパイの使い方などこれぞ国家レベルの軍人で土方達との差を大いに感じてしまった。 下巻でアイヌのことをもっと掘り下げられるかと思ったら、そういう描写は無かった。残念。 久兵衛 なんだったんだ… 上巻でもうすこし狂気の片鱗が見えてたら後半の見え方も違ったかもしれない。 とにかく土方は最後までカッケェ男、浪漫を体現していた。 - 2025年12月21日
 エフスタイルの仕事五十嵐恵美,星野若菜読み終わったいいものが、必ずしも早いスピードで多くの人に伝わるとは限らない。ただ、ゆっくりでも本当に必要とされている人の手に届いた時には、使う人に大きな喜びを与え、信頼が寄せられる。 p.62 地方の製造業と手を携えていいものを作り、ゆっくり着実に製品の価値をわかり大切にしてくれるひとのもとへ届けようという生業。 新卒だったデザイナーおふたりと作り手の皆さんのまっすぐさと誠実さ、譲れないものは譲らないこだわり…両者が出会えてよかったなぁと勝手にしみじみする。 作り手が疲弊してしまったら、バズったとしても意味がない。一瞬の大儲けよりも、長く続いて会社や技術の継承を、使い手がボロボロになるまで使ってくれた後にまた縁を作れるものづくりを。 ウッッと胸を押さえてしまう。 新潟のしろい雪、その湿った空気の中に混ざる工場のにおいはどんなだろう。そんな想像をさせられる写真もすてき。
エフスタイルの仕事五十嵐恵美,星野若菜読み終わったいいものが、必ずしも早いスピードで多くの人に伝わるとは限らない。ただ、ゆっくりでも本当に必要とされている人の手に届いた時には、使う人に大きな喜びを与え、信頼が寄せられる。 p.62 地方の製造業と手を携えていいものを作り、ゆっくり着実に製品の価値をわかり大切にしてくれるひとのもとへ届けようという生業。 新卒だったデザイナーおふたりと作り手の皆さんのまっすぐさと誠実さ、譲れないものは譲らないこだわり…両者が出会えてよかったなぁと勝手にしみじみする。 作り手が疲弊してしまったら、バズったとしても意味がない。一瞬の大儲けよりも、長く続いて会社や技術の継承を、使い手がボロボロになるまで使ってくれた後にまた縁を作れるものづくりを。 ウッッと胸を押さえてしまう。 新潟のしろい雪、その湿った空気の中に混ざる工場のにおいはどんなだろう。そんな想像をさせられる写真もすてき。 - 2025年12月21日
 私的な書店ーたったひとりのための本屋ーチョン・ジヘン,原田里美読み終わった「私的な書店」の始まりは、「好きな仕事を私らしく、楽しみながら、持続可能に」するためでした。 p.194 店舗を訪れて感動した本屋さんの通販にて購入。思えばそれも「あなたの本屋に投票してください」になったのだろうか。 お問い合わせに24時間答えようとしていたら疲れてカウンセラーにお世話になった話、常連さんのレビューが気になって自分の好きの優先度を下げたら本のセレクトがぼんやりしてきてしまった話など… 本屋さんじゃなくても、日々の生活でそういうのあるよね。 数字の話も出ていたりしてヒェッ!となった。韓国では本は非課税なんだっけ。それにしてもあのソウルで、お店を一年で家賃の心配をしなくていいようにするジヘさんの才覚とパッション。表紙のリスのイラストはころんとかわいらしいけど、きっと魂がMAMAMOO(私が好き)と同位体。 『韓国文学の中心にあるもの』と同様に、まだ行ったことがない本屋さんやまだ読んでいない韓国や日本の文学に繋がってゆく一冊でした。
私的な書店ーたったひとりのための本屋ーチョン・ジヘン,原田里美読み終わった「私的な書店」の始まりは、「好きな仕事を私らしく、楽しみながら、持続可能に」するためでした。 p.194 店舗を訪れて感動した本屋さんの通販にて購入。思えばそれも「あなたの本屋に投票してください」になったのだろうか。 お問い合わせに24時間答えようとしていたら疲れてカウンセラーにお世話になった話、常連さんのレビューが気になって自分の好きの優先度を下げたら本のセレクトがぼんやりしてきてしまった話など… 本屋さんじゃなくても、日々の生活でそういうのあるよね。 数字の話も出ていたりしてヒェッ!となった。韓国では本は非課税なんだっけ。それにしてもあのソウルで、お店を一年で家賃の心配をしなくていいようにするジヘさんの才覚とパッション。表紙のリスのイラストはころんとかわいらしいけど、きっと魂がMAMAMOO(私が好き)と同位体。 『韓国文学の中心にあるもの』と同様に、まだ行ったことがない本屋さんやまだ読んでいない韓国や日本の文学に繋がってゆく一冊でした。 - 2025年12月20日
 那覇の市場で古本屋宇田智子読み終わった「沖縄本」というジャンルに最初少しびっくりした。 でも5年に一度の世界のウチナーンチュ大会があるということを思い出すとなんだか納得できる。 自分たちを知りたい、伝えたい、プライドがある場所なんだなぁ。 著者さんは自身ではうまく言葉にできない思いで走ってきた…と振り返っている。でも読んでる私からすれば、楽しい!面白い!なんだこれは?!知りたい!好き!という根源的でグッドなバイブスで活動して来られた姿がとても眩しい。 私は暑さも海も苦手なので沖縄はちょっと…と腰が引けていたけれど、こんなに熱い出版・古本の文化があると知ってしまった。どうしよう。冬なら暑くないよな。あ、でももう夏でも本州の方が暑いのか。
那覇の市場で古本屋宇田智子読み終わった「沖縄本」というジャンルに最初少しびっくりした。 でも5年に一度の世界のウチナーンチュ大会があるということを思い出すとなんだか納得できる。 自分たちを知りたい、伝えたい、プライドがある場所なんだなぁ。 著者さんは自身ではうまく言葉にできない思いで走ってきた…と振り返っている。でも読んでる私からすれば、楽しい!面白い!なんだこれは?!知りたい!好き!という根源的でグッドなバイブスで活動して来られた姿がとても眩しい。 私は暑さも海も苦手なので沖縄はちょっと…と腰が引けていたけれど、こんなに熱い出版・古本の文化があると知ってしまった。どうしよう。冬なら暑くないよな。あ、でももう夏でも本州の方が暑いのか。 - 2025年12月11日
- 2025年12月11日
 アレクシエーヴィチとの対話: 「小さき人々」の声を求めてスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ,徐京植,沼野恭子,鎌倉英也読んでる昨年図書館で借りて、しばし読み進めたのち、「良すぎ。手元に置いておかないと後悔する。」と古本で購入。 ま、まだ積んでる…。 森の中の石鹸工場とか本当に笑えない。
アレクシエーヴィチとの対話: 「小さき人々」の声を求めてスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ,徐京植,沼野恭子,鎌倉英也読んでる昨年図書館で借りて、しばし読み進めたのち、「良すぎ。手元に置いておかないと後悔する。」と古本で購入。 ま、まだ積んでる…。 森の中の石鹸工場とか本当に笑えない。 - 2025年12月11日
- 2025年12月11日
 黒龍の柩(上)北方謙三読み終わったTwo men look out through the same bars:one sees the mud, and one the stars. フレデリック・ラングブリッジ「不滅の詩」 この土方は星を見上げる土方だ。 大河ドラマ「新選組!」で山南敬助は脱走前に足に絡みつく新選組の、自分の辛い苦しい現実からふと目線を上げ、日本の未来について思いを巡らせる。そこで坂本龍馬と交わした言葉が薩長同盟のヒントとなり時代は大きくうねり始める。ドラマの創作とはいえ、大好きな登場人物が蝶の羽ばたきを起こした展開に胸が熱くなった。一方、彼が殉じた組織ではその後も苛烈な粛正の嵐が吹き荒れる。法度によって新選組を締め上げ、近藤勇をてっぺんに押し上げる。その目的のために奮闘する土方の視界には夜空の星が映っていただろうか。 本書ではなんと土方が、山南とふたり並んで星を見上げている。というかぶっちゃけ近藤に対してよりも友情感じてる。双子とまで思っている。 (それが無理!!!という人には無理な小説だろう。) とにかく本書の土方歳三はマブダチ山南敬助との友情を胸に、彼が死の間際に指し示した空の星を追いかけてゆく鬼つええ男だ。 というか浮いた話がマジで無い。「組!」で食傷気味ですらあった男女ロマンス要素がゴリゴリ削られ、ずっと「男が男の漢に惚れる…それは愛より重い!」をやっている。明里さんすらいない。俳句も読まない。しかし夢主やん!なオリキャラはいる。どういうバランス??? 幕府側の勝海舟、そして再来年の大河ドラマ主人公小栗忠順が土方と深く関わってゆく。 たとえ今の形の幕府を無くしても徳川家を滅ぼさず、内戦を回避し外国の侵略を防ぎ国を富ませてゆくため、徳川家や旗本が中心となって蝦夷地に新国家を造る。それが勝、小栗、坂本龍馬の目指すところだ。そこに山南に導かれた土方もコミットしてゆく。 しかし彼らのやろうとしていることは、生き残るため富を産むため他者の生きる場所を力で奪う列強の植民地政策と同じだ。「かわいそうな俺たち」とウジウジしながらアイヌが暮らす土地や資源を踏み荒らそうとしている。そのことが下巻で言及されるのかどうかが私にとっては今のところ最大の関心だ。 古今東西物語においてひととひとの道が分たれる瞬間というのは美しいが、上巻ラストの近藤と土方の訣別も例に漏れず、ミュージカルの一幕終わりを見たかのような盛り上がりだった。 近藤は武士として新選組としてどう死ぬかを見つけようと地を見つめ、土方はこの時代をどう生き抜くかを考え遥か北の空に目を凝らしている。 星を見るというのは希望を捨てないだけではなく、生きるために考え続けることなのかな。
黒龍の柩(上)北方謙三読み終わったTwo men look out through the same bars:one sees the mud, and one the stars. フレデリック・ラングブリッジ「不滅の詩」 この土方は星を見上げる土方だ。 大河ドラマ「新選組!」で山南敬助は脱走前に足に絡みつく新選組の、自分の辛い苦しい現実からふと目線を上げ、日本の未来について思いを巡らせる。そこで坂本龍馬と交わした言葉が薩長同盟のヒントとなり時代は大きくうねり始める。ドラマの創作とはいえ、大好きな登場人物が蝶の羽ばたきを起こした展開に胸が熱くなった。一方、彼が殉じた組織ではその後も苛烈な粛正の嵐が吹き荒れる。法度によって新選組を締め上げ、近藤勇をてっぺんに押し上げる。その目的のために奮闘する土方の視界には夜空の星が映っていただろうか。 本書ではなんと土方が、山南とふたり並んで星を見上げている。というかぶっちゃけ近藤に対してよりも友情感じてる。双子とまで思っている。 (それが無理!!!という人には無理な小説だろう。) とにかく本書の土方歳三はマブダチ山南敬助との友情を胸に、彼が死の間際に指し示した空の星を追いかけてゆく鬼つええ男だ。 というか浮いた話がマジで無い。「組!」で食傷気味ですらあった男女ロマンス要素がゴリゴリ削られ、ずっと「男が男の漢に惚れる…それは愛より重い!」をやっている。明里さんすらいない。俳句も読まない。しかし夢主やん!なオリキャラはいる。どういうバランス??? 幕府側の勝海舟、そして再来年の大河ドラマ主人公小栗忠順が土方と深く関わってゆく。 たとえ今の形の幕府を無くしても徳川家を滅ぼさず、内戦を回避し外国の侵略を防ぎ国を富ませてゆくため、徳川家や旗本が中心となって蝦夷地に新国家を造る。それが勝、小栗、坂本龍馬の目指すところだ。そこに山南に導かれた土方もコミットしてゆく。 しかし彼らのやろうとしていることは、生き残るため富を産むため他者の生きる場所を力で奪う列強の植民地政策と同じだ。「かわいそうな俺たち」とウジウジしながらアイヌが暮らす土地や資源を踏み荒らそうとしている。そのことが下巻で言及されるのかどうかが私にとっては今のところ最大の関心だ。 古今東西物語においてひととひとの道が分たれる瞬間というのは美しいが、上巻ラストの近藤と土方の訣別も例に漏れず、ミュージカルの一幕終わりを見たかのような盛り上がりだった。 近藤は武士として新選組としてどう死ぬかを見つけようと地を見つめ、土方はこの時代をどう生き抜くかを考え遥か北の空に目を凝らしている。 星を見るというのは希望を捨てないだけではなく、生きるために考え続けることなのかな。 - 2025年12月6日
 黒龍の柩(上)北方謙三読んでる「い、いいんですか…?!こんな…いいんですか??!」て言いながら第二章の始めを今読んでいる。 追記 「べらぼう」に続いて「逆賊の幕臣」エレメンツも入ってきて横転 「新選組!」4〜33話を抱きしめて拗らせたオタク「"幻想ユメ"じゃねえよな…?!」 2002年刊行の本書が、2004年大河のオタクに、令和の大河の調味料をかけた夢を食わせてくれる。 浪漫がありますね。
黒龍の柩(上)北方謙三読んでる「い、いいんですか…?!こんな…いいんですか??!」て言いながら第二章の始めを今読んでいる。 追記 「べらぼう」に続いて「逆賊の幕臣」エレメンツも入ってきて横転 「新選組!」4〜33話を抱きしめて拗らせたオタク「"幻想ユメ"じゃねえよな…?!」 2002年刊行の本書が、2004年大河のオタクに、令和の大河の調味料をかけた夢を食わせてくれる。 浪漫がありますね。 - 2025年12月3日
読み込み中...


