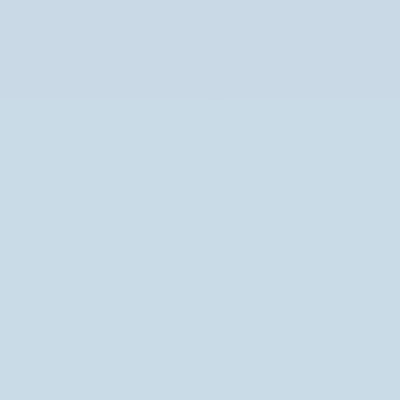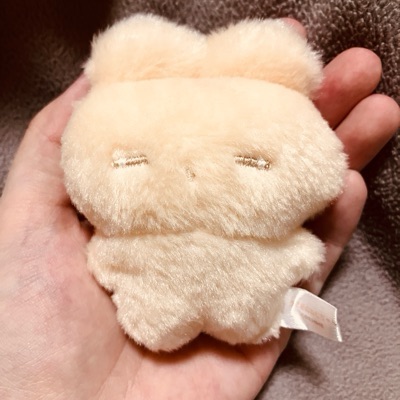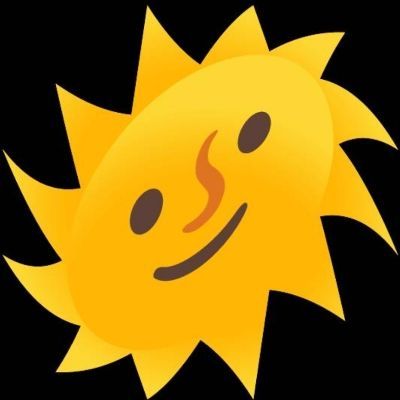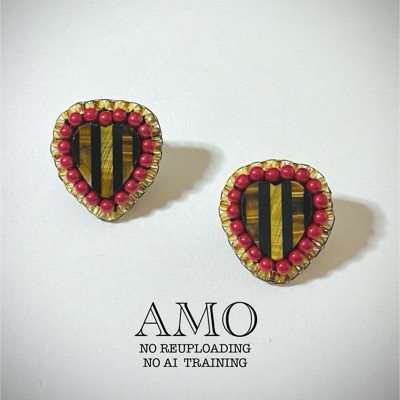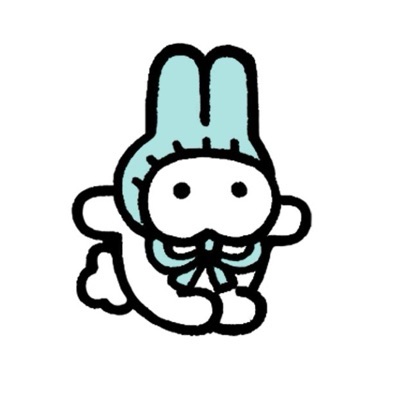オタク文化とフェミニズム
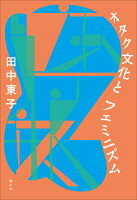
105件の記録
 Sakurada@sakurada_72025年12月30日読み終わった「イン・ザ・メガチャーチ」の副読本として。 帯にある通り「エンターテインメントを巡るモヤモヤを考えるための補助線となる」のは確かに。 ただやっぱりモヤモヤしたままではある笑 「内面化」「再生産」という言葉が出てくるたびにどれだけ複雑な構造の中で私たちはアイドルを応援しているのか突きつけられる気持ち。「じゃあやめましょう」というシンプルな話じゃない。
Sakurada@sakurada_72025年12月30日読み終わった「イン・ザ・メガチャーチ」の副読本として。 帯にある通り「エンターテインメントを巡るモヤモヤを考えるための補助線となる」のは確かに。 ただやっぱりモヤモヤしたままではある笑 「内面化」「再生産」という言葉が出てくるたびにどれだけ複雑な構造の中で私たちはアイドルを応援しているのか突きつけられる気持ち。「じゃあやめましょう」というシンプルな話じゃない。
 445@00labo2025年10月30日気になる『ゼロからの資本主義』を読みながら、 「推し活」って資本側からの労働力の搾取、労働力回復(気力面)の商品化だからほんとクソ。みたいなことを考えている。
445@00labo2025年10月30日気になる『ゼロからの資本主義』を読みながら、 「推し活」って資本側からの労働力の搾取、労働力回復(気力面)の商品化だからほんとクソ。みたいなことを考えている。 いずみがわ@IzuMigawa_itsu2025年9月11日読み終わった前職にいたころは『浪費図鑑』が楽しく読めていた。けれど環境が変わり「あれ?これってもしかして世の中全てのオタクがあるあるって頷く話じゃなくない?」とモヤモヤし始めた。 コロナ禍で『ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在』の水上文さんの「〈消費者フェミニズム〉批判序説」を読み、だから今私は苦しいしモヤモヤしているんだ!と膝を打つに至った。 そして現在、あの頃から今に至るまでハマってると言える趣味のひとつの節目を迎えるにあたり本書を読んだ。 三次元の推しがいるフォロワーの自我がだんだん無くなってゆく。 そんな体験をしているひとは少なくないだろう。どうでもいいぽわんとしたこと、ときに愚痴も吐いてたあのひとのツイートがだんだん変わってゆくのだ。(私はTwitterと呼ぶ人間です) そのひとの推しの公式リツイ。「あと何百再生で○○○万再生です。/サブスクでの順位が落ちています。みなさん頑張りましょう」という謎のアナウンス。ドラマや曲名、推しのハッシュタグを併記したキラキラポジティブなツイート。発売日にはお迎えツイート。ライブ参加報告。自身のフォロワーからの視線を考慮して愚痴や政治の話はしない。 そんなひとを何人も見てきた。 本書では、それが本来公式・運営側がお金をかけてプロモーションしなければいけないことを、オタクが好きという気持ちから無償で担わされる搾取だと指摘している。そして推される側のアイドル・アーティストも、移動時間や自宅での時間を使える限り自身のブランド化のためSNSでファンと交流し、正当な報酬を支払われることが少ない感情労働を行っている、と。 可処分時間を全て推しに捧げた結果、リアルに生きる自分自身や周りの社会の問題に目がいかなくなり、それに費やすエネルギーを失ってしまう。日本のように労働時間がバカ長い社会で一億総推し活をすればなるほど、政治のことなんて誰も考えないだろう。 私も応援しているひとがいる。でも今まで「応援のため」とやっていたことをもう止めることにした。 …私が何をせずとも、もうそのひとがある頂点を極めたという幸運もきっかけの一つである。不安な気持ちと別れなければ、なかなかこの決定に至れなかった。 この先行きがわからない社会で、生きているひとを推すことは不安と隣り合わせだ。でも不安な心はお金を落とすし、陰謀論との相性も抜群である。 誰かを好きで応援してるひとがキラキラしているのは確かにそうだ。でも私はあなたの愚痴も聞きたいし、社会や政治の話もしたい。「推し、ちゃんと休めてる?」と心配しているならなおさら。 「推し疲れ」でモヤモヤしているひとは、そのモヤモヤから目を逸らさないでほしい。推しが好き!って気持ちだけじゃなくて、ましてやかけたお金を開示しあうことじゃなくて、そのモヤモヤからでも誰かと繋がって連帯できる可能性もあるのだから。
いずみがわ@IzuMigawa_itsu2025年9月11日読み終わった前職にいたころは『浪費図鑑』が楽しく読めていた。けれど環境が変わり「あれ?これってもしかして世の中全てのオタクがあるあるって頷く話じゃなくない?」とモヤモヤし始めた。 コロナ禍で『ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在』の水上文さんの「〈消費者フェミニズム〉批判序説」を読み、だから今私は苦しいしモヤモヤしているんだ!と膝を打つに至った。 そして現在、あの頃から今に至るまでハマってると言える趣味のひとつの節目を迎えるにあたり本書を読んだ。 三次元の推しがいるフォロワーの自我がだんだん無くなってゆく。 そんな体験をしているひとは少なくないだろう。どうでもいいぽわんとしたこと、ときに愚痴も吐いてたあのひとのツイートがだんだん変わってゆくのだ。(私はTwitterと呼ぶ人間です) そのひとの推しの公式リツイ。「あと何百再生で○○○万再生です。/サブスクでの順位が落ちています。みなさん頑張りましょう」という謎のアナウンス。ドラマや曲名、推しのハッシュタグを併記したキラキラポジティブなツイート。発売日にはお迎えツイート。ライブ参加報告。自身のフォロワーからの視線を考慮して愚痴や政治の話はしない。 そんなひとを何人も見てきた。 本書では、それが本来公式・運営側がお金をかけてプロモーションしなければいけないことを、オタクが好きという気持ちから無償で担わされる搾取だと指摘している。そして推される側のアイドル・アーティストも、移動時間や自宅での時間を使える限り自身のブランド化のためSNSでファンと交流し、正当な報酬を支払われることが少ない感情労働を行っている、と。 可処分時間を全て推しに捧げた結果、リアルに生きる自分自身や周りの社会の問題に目がいかなくなり、それに費やすエネルギーを失ってしまう。日本のように労働時間がバカ長い社会で一億総推し活をすればなるほど、政治のことなんて誰も考えないだろう。 私も応援しているひとがいる。でも今まで「応援のため」とやっていたことをもう止めることにした。 …私が何をせずとも、もうそのひとがある頂点を極めたという幸運もきっかけの一つである。不安な気持ちと別れなければ、なかなかこの決定に至れなかった。 この先行きがわからない社会で、生きているひとを推すことは不安と隣り合わせだ。でも不安な心はお金を落とすし、陰謀論との相性も抜群である。 誰かを好きで応援してるひとがキラキラしているのは確かにそうだ。でも私はあなたの愚痴も聞きたいし、社会や政治の話もしたい。「推し、ちゃんと休めてる?」と心配しているならなおさら。 「推し疲れ」でモヤモヤしているひとは、そのモヤモヤから目を逸らさないでほしい。推しが好き!って気持ちだけじゃなくて、ましてやかけたお金を開示しあうことじゃなくて、そのモヤモヤからでも誰かと繋がって連帯できる可能性もあるのだから。



 停好@ODAQ2025年6月15日読み終わった面白かった。なんとなく知ってた情動労働≒感情労働ややりがい搾取、初耳のドゥボールのスペクタクルの社会について新しく知れた。 かつファン商売や推しグッズについて列挙されてる箇所を読むと、俯瞰するとこんな変なことしてるんだ、とおかしくて面白い。
停好@ODAQ2025年6月15日読み終わった面白かった。なんとなく知ってた情動労働≒感情労働ややりがい搾取、初耳のドゥボールのスペクタクルの社会について新しく知れた。 かつファン商売や推しグッズについて列挙されてる箇所を読むと、俯瞰するとこんな変なことしてるんだ、とおかしくて面白い。





 まるめ@marume_bk2025年5月21日読み終わった過去の自分の姿や周りにいた過剰な推し活をする人たちの姿がよぎって、あまり冷静に読めなかった、、、 自分に近しい話が多いからか、しっかり根っこの部分まで感じ取らないままに読み飛ばしてしまった感がある。 時間を置いてもう一回読み返したい。
まるめ@marume_bk2025年5月21日読み終わった過去の自分の姿や周りにいた過剰な推し活をする人たちの姿がよぎって、あまり冷静に読めなかった、、、 自分に近しい話が多いからか、しっかり根っこの部分まで感じ取らないままに読み飛ばしてしまった感がある。 時間を置いてもう一回読み返したい。

 ろじ@reads_rjur2025年4月25日読み終わった面白くてスラスラ読んだ! 自分で感じていた推し文化に対する懸念が書かれていて、やっぱそうですよね!?と思いながら読み進めていった。 「推し活」がいまや資本主義と直結していることの怖さは日々感じていたし、コロナの影響もあるとは思っていたけどデータ的にもそうだったとは。 一方で、それまで透明化されていた「女オタク」が推し活のメイン層になっているというのは評価されるべきだと思ってる。まず「推し」という言葉が出来たからカジュアルに「この人/キャラが好き!」と主張出来るようになった気がする。推しという言葉が出来る前は「ミーハー」とか「女オタクキモい」とかで封じられてた気がするので。 それまで見られる側だった女性が見る側に回った、というのは家父長制のカウンターとしては功績なんだろうけど、資本主義に絡め取られていることと世間ではあくまで異性愛規範をベースに推し活が語られていることは罪だよなと思う。この功罪を自覚しながらオタクしていきたい。 そしてテニミュ4thシーズン開始後に書かれた本なのね!?と慄いていたら筆者もテニモンで笑いました。 引用されていた同担拒否について書いた論文、どこかで読めたら読みたいな〜
ろじ@reads_rjur2025年4月25日読み終わった面白くてスラスラ読んだ! 自分で感じていた推し文化に対する懸念が書かれていて、やっぱそうですよね!?と思いながら読み進めていった。 「推し活」がいまや資本主義と直結していることの怖さは日々感じていたし、コロナの影響もあるとは思っていたけどデータ的にもそうだったとは。 一方で、それまで透明化されていた「女オタク」が推し活のメイン層になっているというのは評価されるべきだと思ってる。まず「推し」という言葉が出来たからカジュアルに「この人/キャラが好き!」と主張出来るようになった気がする。推しという言葉が出来る前は「ミーハー」とか「女オタクキモい」とかで封じられてた気がするので。 それまで見られる側だった女性が見る側に回った、というのは家父長制のカウンターとしては功績なんだろうけど、資本主義に絡め取られていることと世間ではあくまで異性愛規範をベースに推し活が語られていることは罪だよなと思う。この功罪を自覚しながらオタクしていきたい。 そしてテニミュ4thシーズン開始後に書かれた本なのね!?と慄いていたら筆者もテニモンで笑いました。 引用されていた同担拒否について書いた論文、どこかで読めたら読みたいな〜




 わきうし@wakiushi8002025年3月31日読み終わったほぼ3次元女オタとフェミニズム。その3次元も大手アイドルと2.5次元で、私は詳しくないけどメン地下とかスポーツ選手とかYouTuberとか芸人とかはほぼ出てこない。 経済に飲み込まれる、推し疲れ、男性性の消費、ルッキズムに縛られることなどに触れている。7章が難しかった…。最終章はエッセイぽくて読みやすかった。
わきうし@wakiushi8002025年3月31日読み終わったほぼ3次元女オタとフェミニズム。その3次元も大手アイドルと2.5次元で、私は詳しくないけどメン地下とかスポーツ選手とかYouTuberとか芸人とかはほぼ出てこない。 経済に飲み込まれる、推し疲れ、男性性の消費、ルッキズムに縛られることなどに触れている。7章が難しかった…。最終章はエッセイぽくて読みやすかった。
 talia@talia0v02025年3月29日読み終わった借りてきたSNSで見かけて気になって読んだ本でした。 色々書いてしまいますが読んで良かったし、こういうオタク文化について説明される本はもっとたくさん発刊されてほしいです。 何を隠そう私もオタクだしフェミニストなので、タイトルからして気になって仕方がない…!という感じでしたが私が自称する『オタク』とはちょっと違う『オタク』の話だな〜と思いながら読みました。 例えばこの本で書かれる『オタク』とは主に3次元や2.5次元アイドルを推す『推し活』をするオタクについて書かれているが、同人活動をするオタクやアニメ・漫画が好きなオタクやゲームオタクなどは(同じぐらいの人口がいると想定して書いてるけど)取り上げられていない。もちろんみんなキッパリと線引いてカテゴライズされるものではなくグラデーションの中で活動をしているオタクがほとんどだと思うものの、タイトルは『オタク文化とフェミニズム』よりは『推し活文化とフェミニズム』の方がしっくりくるな…という内容でした。 全体的にフォントも行間も大きく読みやすいテキストスタイルですが内容は思ったより難しかったです。例えば読者は自分が身近に感じている(もしくはそうではない)オタク文化と並列して語られる、様々な学者や評論家の引用を呑み込みながら本書の内容を読んで理解する必要があります。例えば本書では第一、二波フェミニズムやポストフェミニズムについては一般常識として(フェミニズムについての本を読みたがるならそれはそう、という意見も否定できませんが)説明や注釈なく引用されるし、オタク文化においてルッキズムが人種差別や性差別より不可視化され(作者はこのような書き方はしていないが)、「社会的・文化的に共有されたある種の美醜の基準を、学習しながら生活している」という説明にブルデューの「ディスタンクシオン」を形容詞的に引用している。私がここに引っかかったのは100分de名著の「ディスタンクシオン」を見たことがあって名前を覚えていたからで、この文章を読んでも「(ディスタンクシオンてどういう内容だっけ…?)」と思ってしまったからなので、他にももっと内容として目が滑っている箇所はあるかもしれない。 あとこれだけ引用が多いけれどオタク文化の説明については極めて一人称的で???となった部分もあり、例えばDA PUMPのU.S.A.がヒットした理由は(作者はU.S.A.がヒットする前からのファンらしいので烏滸がましい疑問かもしれないけれど)、YoutubeなどのSNSで踊ってみた動画が大バズりしたからと当時の音楽番組の紹介で見聞きしていて、私もそう思っていたので実際はそうではなくメディアが推し活するオタクを不可視化したのだとかの事実確認がしたくなったなと読みながら思いました。 その辺は はじめに に書かれていた「本書は実証主義的な研究に基づく書籍ではない。〜極めて一人称的な本であることは間違いないだろう。」という記述を私がちゃんと意識できていなかった反省もあります。 色々書いてしまいましたが、オタクでありながら自分が割と距離を置いていた『推し活』文化についてわかりやすく読めたという点と、また『推し活』文化について資本主義的な警鐘を鳴らしつつ男性オタク文化への懸念(/心配?)についても述べられていたこと、何より女性オタク文化に焦点を当てた本!ということで大変読み応えがありました。 著書の他の本や、同じ分野の論文などが気になりだした本でした。 また、「読み始めた」で書いた通り『推し活』について書いた以下の文章が秀逸すぎたので、少し己を改めようとも思いました笑(距離を置いてると書きつつ、全く『推し活』をしていないわけではないので) > "さらに最大の問題は、(中略)、いまや推し活があらゆる問題を解決する万能薬のように取り上げられていることである。メディアに踊るのは、脳を活性化し、健康を維持し、人間らしく生き生きと楽しく生活でき、自己肯定感が上がり、痩せてきれいになり、友達ができて、停帯した日本経済さえ回復させてくれる「推し活の効能」である。とはいえ、もし推し活が本当にあらゆる問題を解決してくれるとするならば、その存在はかなり胡散臭いものと言えるのではないだろうか?"
talia@talia0v02025年3月29日読み終わった借りてきたSNSで見かけて気になって読んだ本でした。 色々書いてしまいますが読んで良かったし、こういうオタク文化について説明される本はもっとたくさん発刊されてほしいです。 何を隠そう私もオタクだしフェミニストなので、タイトルからして気になって仕方がない…!という感じでしたが私が自称する『オタク』とはちょっと違う『オタク』の話だな〜と思いながら読みました。 例えばこの本で書かれる『オタク』とは主に3次元や2.5次元アイドルを推す『推し活』をするオタクについて書かれているが、同人活動をするオタクやアニメ・漫画が好きなオタクやゲームオタクなどは(同じぐらいの人口がいると想定して書いてるけど)取り上げられていない。もちろんみんなキッパリと線引いてカテゴライズされるものではなくグラデーションの中で活動をしているオタクがほとんどだと思うものの、タイトルは『オタク文化とフェミニズム』よりは『推し活文化とフェミニズム』の方がしっくりくるな…という内容でした。 全体的にフォントも行間も大きく読みやすいテキストスタイルですが内容は思ったより難しかったです。例えば読者は自分が身近に感じている(もしくはそうではない)オタク文化と並列して語られる、様々な学者や評論家の引用を呑み込みながら本書の内容を読んで理解する必要があります。例えば本書では第一、二波フェミニズムやポストフェミニズムについては一般常識として(フェミニズムについての本を読みたがるならそれはそう、という意見も否定できませんが)説明や注釈なく引用されるし、オタク文化においてルッキズムが人種差別や性差別より不可視化され(作者はこのような書き方はしていないが)、「社会的・文化的に共有されたある種の美醜の基準を、学習しながら生活している」という説明にブルデューの「ディスタンクシオン」を形容詞的に引用している。私がここに引っかかったのは100分de名著の「ディスタンクシオン」を見たことがあって名前を覚えていたからで、この文章を読んでも「(ディスタンクシオンてどういう内容だっけ…?)」と思ってしまったからなので、他にももっと内容として目が滑っている箇所はあるかもしれない。 あとこれだけ引用が多いけれどオタク文化の説明については極めて一人称的で???となった部分もあり、例えばDA PUMPのU.S.A.がヒットした理由は(作者はU.S.A.がヒットする前からのファンらしいので烏滸がましい疑問かもしれないけれど)、YoutubeなどのSNSで踊ってみた動画が大バズりしたからと当時の音楽番組の紹介で見聞きしていて、私もそう思っていたので実際はそうではなくメディアが推し活するオタクを不可視化したのだとかの事実確認がしたくなったなと読みながら思いました。 その辺は はじめに に書かれていた「本書は実証主義的な研究に基づく書籍ではない。〜極めて一人称的な本であることは間違いないだろう。」という記述を私がちゃんと意識できていなかった反省もあります。 色々書いてしまいましたが、オタクでありながら自分が割と距離を置いていた『推し活』文化についてわかりやすく読めたという点と、また『推し活』文化について資本主義的な警鐘を鳴らしつつ男性オタク文化への懸念(/心配?)についても述べられていたこと、何より女性オタク文化に焦点を当てた本!ということで大変読み応えがありました。 著書の他の本や、同じ分野の論文などが気になりだした本でした。 また、「読み始めた」で書いた通り『推し活』について書いた以下の文章が秀逸すぎたので、少し己を改めようとも思いました笑(距離を置いてると書きつつ、全く『推し活』をしていないわけではないので) > "さらに最大の問題は、(中略)、いまや推し活があらゆる問題を解決する万能薬のように取り上げられていることである。メディアに踊るのは、脳を活性化し、健康を維持し、人間らしく生き生きと楽しく生活でき、自己肯定感が上がり、痩せてきれいになり、友達ができて、停帯した日本経済さえ回復させてくれる「推し活の効能」である。とはいえ、もし推し活が本当にあらゆる問題を解決してくれるとするならば、その存在はかなり胡散臭いものと言えるのではないだろうか?"





 talia@talia0v02025年3月16日読み始めた「推し活の功罪」的な内容を確かに求めて読み始めたのですが、冒頭からこんな文章があって笑ってしまいました。 > "さらに最大の問題は、(中略)、いまや推し活があらゆる問題を解決する万能薬のように取り上げられていることである。メディアに踊るのは、脳を活性化し、健康を維持し、人間らしく生き生きと楽しく生活でき、自己肯定感が上がり、痩せてきれいになり、友達ができて、停帯した日本経済さえ回復させてくれる「推し活の効能」である。とはいえ、もし推し活が本当にあらゆる問題を解決してくれるとするならば、その存在はかなり胡散臭いものと言えるのではないだろうか?"
talia@talia0v02025年3月16日読み始めた「推し活の功罪」的な内容を確かに求めて読み始めたのですが、冒頭からこんな文章があって笑ってしまいました。 > "さらに最大の問題は、(中略)、いまや推し活があらゆる問題を解決する万能薬のように取り上げられていることである。メディアに踊るのは、脳を活性化し、健康を維持し、人間らしく生き生きと楽しく生活でき、自己肯定感が上がり、痩せてきれいになり、友達ができて、停帯した日本経済さえ回復させてくれる「推し活の効能」である。とはいえ、もし推し活が本当にあらゆる問題を解決してくれるとするならば、その存在はかなり胡散臭いものと言えるのではないだろうか?"




 amy@note_15812025年3月7日かつて読んだ感想フェミニズム”わたしたちの消費は「正しい」のだろうか” いわゆる推し活とされるものの現在地と問題点をめぐる批評本 オタクが経済を回している、とはよく聞くけれど主体的な行動に寄るもののはずが、実は強制的でさせられているものではないか 自分たちは何に金を払い、推しに何を求めているのか。また推しはオタクのために何をしているのか、推すことそのものがある種の労働ではないかという推し活を細かく腑分けしていくような本であった 昨今の”推し活”について考えたい人にはうってつけだと思う。ただこういう場で女性アイドルを推す女オタクはやはり全然語られない。いまや同性のキャラクターや芸能人を推すことも多いのだからもっとその点を含めて論じてほしかったなあとは思う 消費活動だけではなく、アイドルの労働環境やルッキズム、メディアとアイドルとファンの関係などここ最近推し活シーンで話題になっていることはだいたい網羅されているよい本だと思った
amy@note_15812025年3月7日かつて読んだ感想フェミニズム”わたしたちの消費は「正しい」のだろうか” いわゆる推し活とされるものの現在地と問題点をめぐる批評本 オタクが経済を回している、とはよく聞くけれど主体的な行動に寄るもののはずが、実は強制的でさせられているものではないか 自分たちは何に金を払い、推しに何を求めているのか。また推しはオタクのために何をしているのか、推すことそのものがある種の労働ではないかという推し活を細かく腑分けしていくような本であった 昨今の”推し活”について考えたい人にはうってつけだと思う。ただこういう場で女性アイドルを推す女オタクはやはり全然語られない。いまや同性のキャラクターや芸能人を推すことも多いのだからもっとその点を含めて論じてほしかったなあとは思う 消費活動だけではなく、アイドルの労働環境やルッキズム、メディアとアイドルとファンの関係などここ最近推し活シーンで話題になっていることはだいたい網羅されているよい本だと思った




 綿@cttn6182025年3月6日読み終わった借りてきたオタクによる推しのPR・宣伝・貢献は趣味の「推し活」を越えて無償労働なのではないか、という考えが結構衝撃だった 本書によって推しの見方、オタクとしての自分の考え方を少し考えさせられた
綿@cttn6182025年3月6日読み終わった借りてきたオタクによる推しのPR・宣伝・貢献は趣味の「推し活」を越えて無償労働なのではないか、という考えが結構衝撃だった 本書によって推しの見方、オタクとしての自分の考え方を少し考えさせられた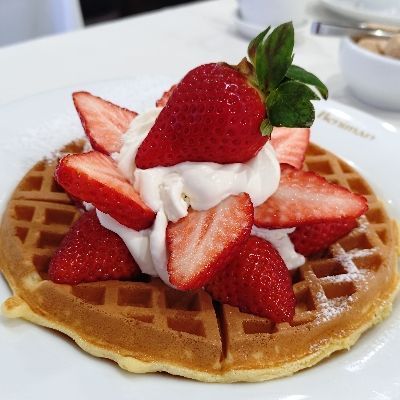 ゆきか@yukikaf1900年1月1日かつて読んだアイドルが好き、2.5舞台が好き、その他「推し」がいる人、そして「推す」の疲れちゃった人も読んでほしい! 推し活を手放しで称賛せず、問題点を丁寧にあぶり出しておられて、わ、わかる〜〜〜私もそれ考えてました……!
ゆきか@yukikaf1900年1月1日かつて読んだアイドルが好き、2.5舞台が好き、その他「推し」がいる人、そして「推す」の疲れちゃった人も読んでほしい! 推し活を手放しで称賛せず、問題点を丁寧にあぶり出しておられて、わ、わかる〜〜〜私もそれ考えてました……!