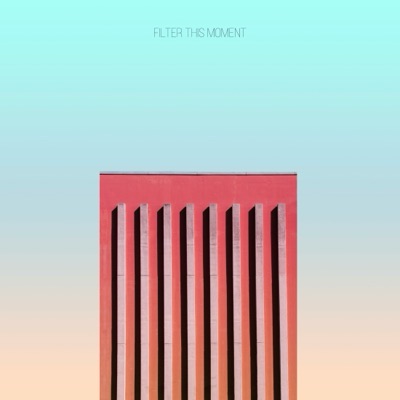大前粟生
@okomeyomuyomu
1900年1月1日

読み終わった
noteでつけてる日記からの転載です。
野田努『ブラック・マシン・ミュージック』(河出文庫)上巻を読んだ。ディスコの登場以降ダンスミュージック、ゲイカルチャー、黒人音楽、ハウス、デトロイト・テクノがどう発展してきたか、めちゃくちゃ詳細なリサーチをもとにかっこいい語り口で教えてくれる本。上下巻あって、上巻では主にシカゴとデトロイトの社会状況、黒人差別の歴史やその反映として(あるいなアシッド・ハウスなど民族的なルーツとは別のものとして)そのときどんな音楽が登場したかが鮮明に描かれている。インタビューや書籍からの引用がとても巧みで、壮大な聞き書きみたいに感じられるんだよな。直接聞いてる証言もあって、引用と談のレイヤーの違いが気にならないくらい語り口がスムーズで痺れる。
菊地成孔+大谷能生『東京大学のアルバート・アイラー』(東大でのジャズ講義本)に野田努がゲスト講師として参加しているのだけれど、その本のなかでしきりに名著だと言われていたので読んでみたかった。もともとは25年ほど前の本で、8年前の増補版と合わせたものが文庫になってくれた。
DJのよさってあまりわからないなあ〜、と思っていたのだけれど、この本に出てくる曲を聴くうちに自分だったらここを反復させるなあとか思うようになってき楽しい。
DJプレイのえらくハンドメイドな技術(曲のつなぎ目にシールを貼ったり布かテープでレコードを繋げたり)を読んでいると、紹介されている大量の固有名詞が頭のなかでもつれてミックスされるような感覚に襲われる。レコードがぐるぐる回り、その隣にはもうひとつのレコードがかけられていて、たくさんの人名がレコードの溝に入り込んで声を出している。この固有名詞の羅列がレイアウトとして醸し出してくる"ハイ"な感じは消費社会を端的に表しているようで、たまにこういう本を読むとモノやカルチャーにまみれる感じがしておもしろい。書かれている音楽も検索すれば聴けるわけで、聴いているあいだは仕事机のまわりの重さがなくなる。名曲として書かれていたCan You Feel It(これにはキング牧師の演説Mixもある)とStrings Of Lifeがすばらしい。Strings Of Lifeについて制作者のデリック・メイは 「ときどき自分の祖父母や母や自分の幼少期のことを思い出す。"Strings"はマーティン・ルーサー・キングのことだ。彼が殺されたとき、希望や夢も破壊された。これはかなえられなかった彼の希望なんだ」と語っている。
こうしたテクノを聴いていると、服を買いたくなるというか、見た目もこのかっこよさにアプローチしたくなるのはどうしてだろう(でもクラフトワークやYMOを聴いても別に見た目を変えようとはならない)
昔は曲を聴きたければこうした本を参考に店に出かけてレコードやCDを漁る必要があったと思うんだけど、その過程できっとコミュニケーションやコミュニティが生まれたりして、それって今となっては得難い価値だろう。だからこそ最近は、その場所に出かけないと繋がることができない、ということへの需要が爆発気味に高まってるように思える。たとえば展示とかは、観賞というより体験の場として近頃は機能しているだろう。わざわざ出かけてある空間に入り込む、という作業をしなければなにがフィクションか実感しがたい世の中なんだと思う。それに友人や恋人と出かけるスポットとして映画や遊園地がもはやかなり高いというのは大きそう。クラブってその意味では今どうなのだろう? 盆踊りが人気っぽい(空気があるよね?)、その延長で流行ったりするだろうか。『ブラック・マシン・ミュージック』を読むといきたい感じはかなり出る。