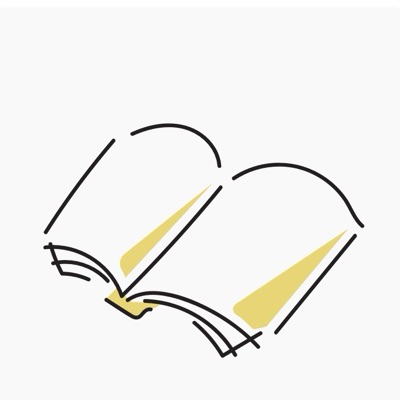
徒然
@La_Souffrance
1900年1月1日

生物と無生物のあいだ
福岡伸一
読み終わった
「いのち動的平衡館」に行ったときに疑問を抱き、もう少し深く知りたくて手に取った。
けれど、読んでみてもそのモヤモヤは完全には晴れなかった。
本書の大きな主張は、「生命の本質は動的平衡である」というものだ。
生命は、エントロピーの増大に逆らうように、自分を壊しながら作り直すことで、同じ“かたち”を保ち続けている。つまり、止まっているように見える体も、実は絶え間なく入れ替わっている——そういう仕組みを「動的平衡」と呼んでいる。
この説明はとても印象的で、「なるほどな」と思う部分もあった。
でも一方で、「なぜそのプロセスそのものが“生命”だと言えるんだろう?」という疑問は残った。
私の感覚では、動的平衡を成立させている分解や代謝のような生命活動は、遺伝子の情報をもとに起こっている。だから、生命の本質が動的平衡であるというのであれば、その動的平衡を維持している遺伝子こそが中心になるのではないか、と思ってしまう。
しかし筆者は、そうした「遺伝子がすべて」という考えに対して、「生命はそれだけでは説明できない」と言いたいのだと思った。
設計図(遺伝子)があっても、実際に“流れ”がなければ生命とは呼べない。
つまり、彼は“生命を実体ではなくプロセスとして見る”視点を示しているのだろう。
ただ私は、そこにやや飛躍を感じた。
遺伝子だけでは生命体を説明できないことや、プロセスが大事だというのは感覚としてわかるけれど、「生命=プロセス」と言い切られると、肝心な説明が抜け落ちたような印象を受けた。
科学的な裏付けを期待して読んだ分、思想的な語り口が強くて戸惑ったというのが正直なところだ。
それでも、「生命とは何か」という問いを改めて考えるきっかけをもらえた本だった。
「生命=遺伝子」と捉えるのか、「生命=流れ」と捉えるのか。
その視点の違いを意識するだけでも、世界の見え方が少し変わる気がする。
カバーと表紙のデザイン好き。




