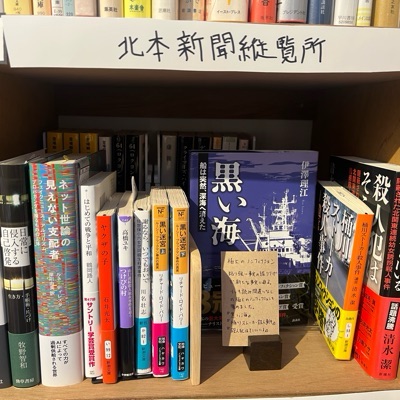あき
@4rcoid
2025年10月13日

現代思想入門
千葉雅也
読み終わった
まとめ
現代思想は差異の哲学。
デリダ、ドゥルーズ、フーコーという三人を脱構築という観点から論じている。
脱構築とは二項対立(善と悪、自然と文化など)の良いとされる側の前提にある価値観を疑い揺さぶりをかけること。
新たな読み直しや新しい思考の可能性を開くことが出来る。
デリダは脱構築を持ち出した哲学者であり"概念の脱構築"と紹介される。
パロール(音声言語)とエクリチュール(文字言語)の二項対立を基本としてあらゆるものに応用できる。
パロールとは話し手が話した直接的なものであり本質的なものである。
エクリチュールとは聞き手が文字として書き起こしたものであり、解釈や誤解の余地があり非本質的なものとされている。
この非本質的なものの重要性を説いている。
本質を崩すことでより世界を開放的に捉えている(本質主義批判)
ドゥルーズは"存在の脱構築"
『差異と反復』(1968)にて世界は差異でできているとしており、同一性より先に差異があるとしている。
例えるなら同じ範囲の歴史の授業でもその時の生徒の反応やクラスの雰囲気、先生の体調等によって全く同じものにはならない。
そういった差異が繰り返される中で同一的のものが一時的に生まれてくる。
存在も同一的に見えるが異なるものに変化している途中である(生成変化)
人間の身体も常に細胞が死んだり作られたりして変化している途中である。
同一的だと思われているものも永遠不変ではなく、諸関係の中で一時的にその形をとっている(準固定状態)
すべてはプロセスである。
『アンチ・オイディプス』(1972)において精神分析批判をおこなっており、精神分析は自分自身をある基準点に向けて固めていくことで治った気にさせるまやかしの技法だとする。
精神分析とはいまの自分の不安や人間関係のトラブルは幼少期の家族関係の中でのトラウマにあると仮定して自由連想で記憶を手繰る手法。
自分自身を家族との関係だけの狭い範囲の同一性で捉えるのは間違っているとする。
メッセージとして多様な関係のなかで色々なチャレンジをして自分の準安定状態を作り出せと伝えている。
『千のプラトー』(1980)にて世界全体をより解放的なものとして捉えている。
リゾーム(根茎)という多方向に広がる中心のない関係性を提示している。
すべてが関係していると考えるとすべてに責任を持たないといけないのか?となってしまうが、根本的な"無関係性"と存在の"無責任"を肯定している。
これはお互いの自律性を維持するために必要。
例えば介護者が介護に全生活を捧げると生きていくことが出来なくなり、被介護者も監視されていると感じたり支配されている状態になる。
遊離(デタッチメント)の態度を持つことでお互いに対する気遣いを持ち、また相手を管理することにならないようにすることで他者との共存ができる。
フーコーは"社会の脱構築"
支配者(権力)と被支配者(弱者)の二項対立は被支配者がただ受け身なのではなく、むしろ積極的に支配されることを望む構造があるとしている。
これを聞くと一瞬そんなはずはない!という感想を持つがこれはひとりの真の悪玉がいるのではなく「無数の力関係」があることによるもの。
そもそも近代社会はクリーン化されることにより発展していったが、このクリーン化は主流派にとってのものである。
主流派にとっての倫理観や価値観に合わないものは監獄(病院など)にノイズ(犯罪者)として隔離集約されていった。
またそれが進み「治療」を行い社会に戻す動きも出てきた。
これは人に優しい世界になった友思えるがむしろ統治の巧妙化だという。
つまり主流派の価値観に洗脳して少しでも役立つ人間に変化させるということだ。
フーコーの価値観としては正常と異常とをはっきりと区別せずに曖昧で互いに寛容であるような価値観である。
権力の時代別の流れとしては
王権の時代は悪事はバレると晒し首や市中引き回しなど大変なことになるがバレなければOKで様々な逸脱の可能性が広がっていた。
近代では「規律訓練」という誰に見られずとも自分で進んで悪事をしないように心掛ける自己抑制がすすんでいった。
これはパノプティコンという監獄を例に示されており、看守は中央の塔から囚人を監視することができるが、囚人の側からは看守がいるのかは確認出来ない。また隣人とも隔離されている。そのため見られているかもしれないという自己監視する状態におかれる。
いまでいう学校や家族生活のなかでしつけもこれに当てはまる。
王様という支配者から支配者の不可視へと変化していった。
また「生政治」という大規模に人々に働きかける統治もすすんでいった。これは病気の発生率や出生率、人口密度を考えた都市設計など即物的なコントロールである。
新型コロナウイルスの流行を例にとると飲みにいったり出歩くのを控えるのは規律訓練であり、ワクチンを国民一律に接種させるのが生政治である。
現代は規律訓練と生政治の両輪である。
忖度も規律訓練の一種であり、よかれと思ってやっていることが支配の強化や主流派の価値観の護持に繋がっている。
古代では悪事は明確化されておらず、個別具体的でその都度注意するものであった。
自己との終わりなき闘いではなくその都度注意し適宜自分の人生をコントロールするという"自己への配慮"があった。
人間が持つ過剰さ故の多様性(逸脱)を整理し過ぎず、泳がせておくような社会の余裕や他者性を尊重するような倫理を持つことも必要。