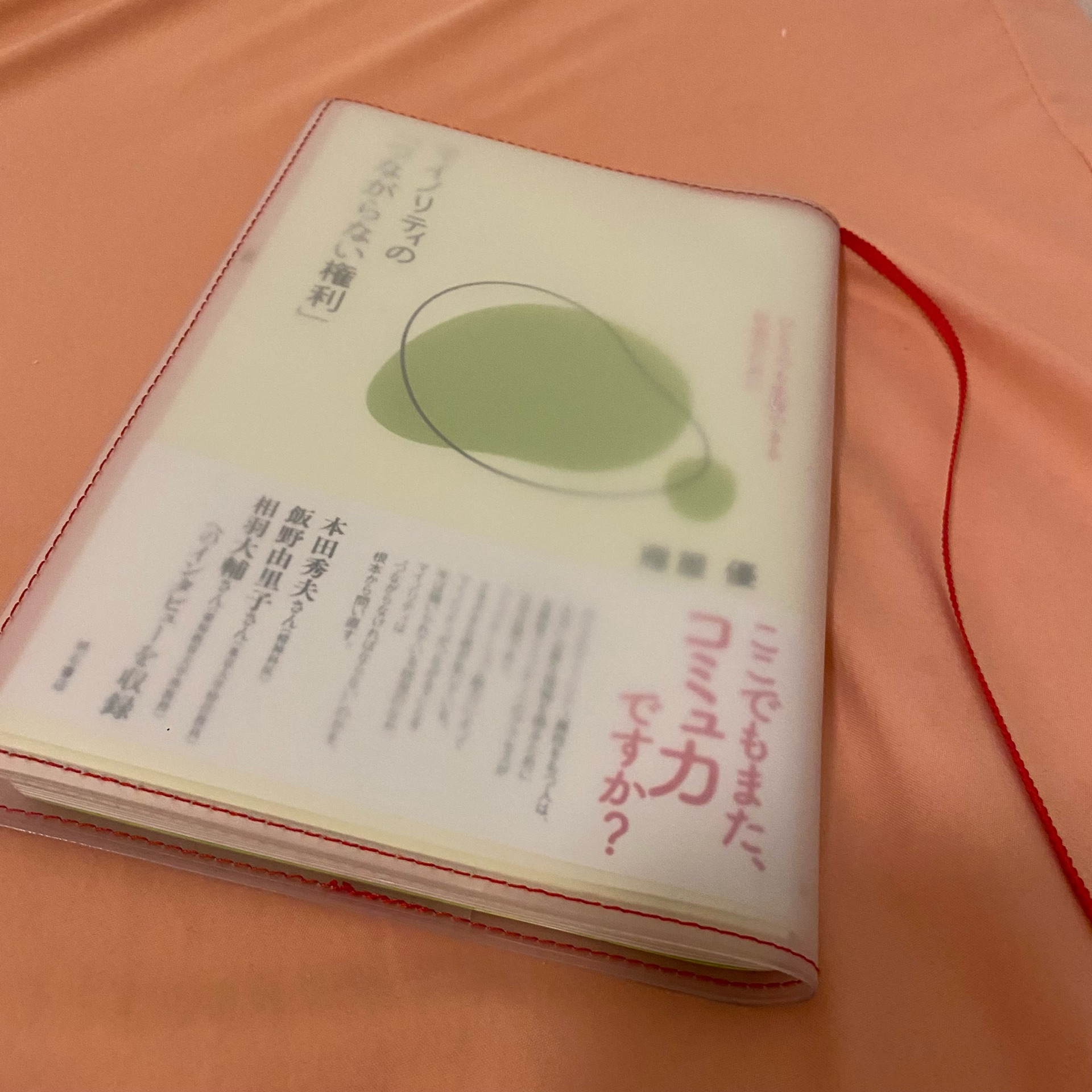桃缶
@mel0co
2025年10月15日

読み終わった
@ 自宅
夏の選挙前に某党に入党して、社会と繋がるって素晴らしいな〜と感じたことで、「つながらない権利」てなんなんだろうと気になっていた。
選挙の結果と夏の厳しさで体調と精神を崩してしまい、結局党の活動もあまりできなくなったことでさらに「つながらない権利」気になり、最近涼しくなってやっと調子が良くなってきて読み終えることができた。
一章はマイノリティが当事者コミュニティへ所属することでコミュニケーションが強いられている危機感が述べられていた。筆者の個人的なコミュ力への忌避感を感じ、感情移入の入口としてはよかったが、では具体的にどうすればいいのだろうということがあまり見えてこず、消化不良感があった。(それについては3章に書かれている)
私がこの本を読んでよかったと思うのは対話形式で書かれた2章だった。
特に飯野由里子さんとの対話がよかった。
「対人のコンフリクトを起こさないではなく、起きたときにどう対処をするかを学校で教えなければならない。違っていて当たり前だからコンフリクトも生じる。」という旨の発言は、前の選挙でのひどい排外主義に対抗できる考え方だとも思った。
また、本田秀夫さんとの対話でも触れられていたが、筆者の内面化した能力主義、つまり「障害があるからこそ何かに優れていなければならない」という考え方には自分にも身に覚えがある。その能力主義が一章のコミュニケーション力への忌避感とも繋がるのだろうと思った。
また、飯野由理里子さんの「社会は一人の人や、一つの団体が変えていくものではなく、お互いやってることも知らない、話したこともないような人々が、それぞれ重なる問題意識を持ちながら、自分のできる範囲でやりたいことを積み重ねていくなかで変わっていくものだと考えます。」(P131 11行目)という言葉も、最近の自分の悩みを晴らすものだった。
「ガザとは何か」(岡真理)でも、パレスチナ人の俳優、ジュリアーノさんがウトロ地区の訴訟で人々が闘っている姿を見て、自分たちと同じ闘いだとし、勇気づけ励まされた話を挙げ、「私たちが私たちの闘いをしっかりと闘うことも、パレスチナと連帯することにつながります。」と書いてあり、感動したことを思い出した。
夏の選挙は本当に無力さを感じた。
自分自身は頑張って闘ったつもりではあったが、排外主義に負けてしまったという気持ちでいて、しかもガザの状況はずっと地獄が続いているし、友人はSNSにマックやスタバの写真を上げている。その状況が本当につらくて、暑さもあって精神的に参ってしまった。党の会議に参加できないことも、自分は何もしていないと思えて辛かった。
でも、この本では「マイノリティであるからとコミュニケーションをしなければならないのは人権侵害だ。」と著者がはっきり書いている。私もまた、コミュニケーションをして社会とつながらなければ生きていけないという能力主義を内面化していたのかもしれない。
「本当は現代の技術や知識で何とかできるのに」という言葉は、坂本龍一が生前、音楽を作るAI(生成AI)に対して「そんなことにAIを使うより、気候変動をどうするかとか、貧困や格差をどうするか、そういうことにAIを使ってほしい。」と言っていたことを思い出す。
どうして人々は素晴らしい技術を自然や弱者に還元せず、個人の儲けを考えてしまうんだろう。結局、資本主義って疲れるよね。となってしまう。結局個人が自分のできる範囲のことをできる限りでやって、それぞれゆるくつながりつつ、つながらないでいつつ、頑張っていくしかないのだ。