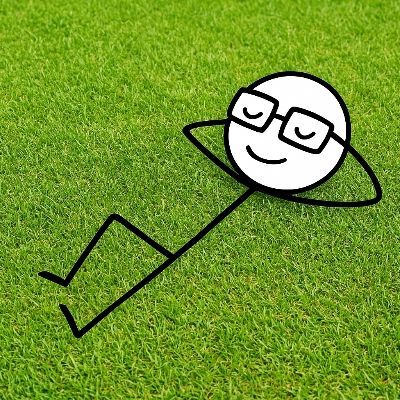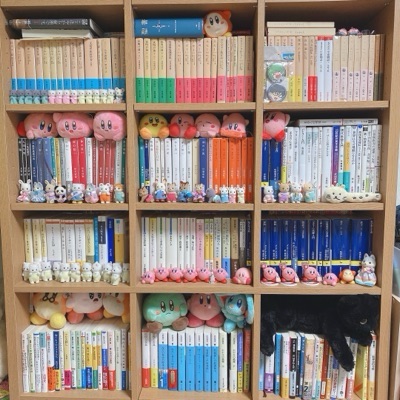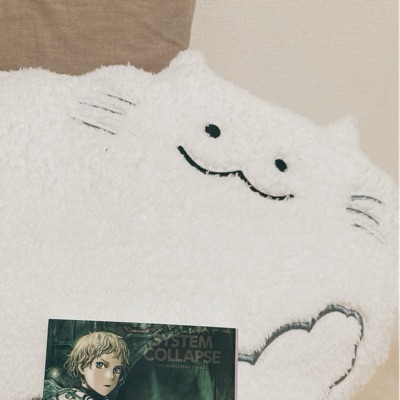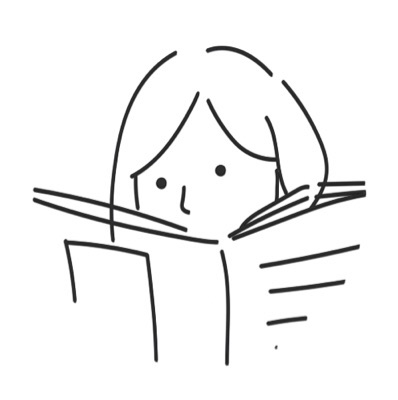マイノリティの「つながらない権利」

138件の記録
 くりこ@kurikomone2026年1月20日読みたい近年右傾化する政治に危機感を感じてたし去年の選挙から人に誘われたので某政党に入党してたのだけど、ごったごったがあり離党。せっかくなのに残念な結果になり悲しい。悲しいのでつながらないことについて考えたい
くりこ@kurikomone2026年1月20日読みたい近年右傾化する政治に危機感を感じてたし去年の選挙から人に誘われたので某政党に入党してたのだけど、ごったごったがあり離党。せっかくなのに残念な結果になり悲しい。悲しいのでつながらないことについて考えたい






 桃缶@mel0co2025年10月15日読み終わった@ 自宅夏の選挙前に某党に入党して、社会と繋がるって素晴らしいな〜と感じたことで、「つながらない権利」てなんなんだろうと気になっていた。 選挙の結果と夏の厳しさで体調と精神を崩してしまい、結局党の活動もあまりできなくなったことでさらに「つながらない権利」気になり、最近涼しくなってやっと調子が良くなってきて読み終えることができた。 一章はマイノリティが当事者コミュニティへ所属することでコミュニケーションが強いられている危機感が述べられていた。筆者の個人的なコミュ力への忌避感を感じ、感情移入の入口としてはよかったが、では具体的にどうすればいいのだろうということがあまり見えてこず、消化不良感があった。(それについては3章に書かれている) 私がこの本を読んでよかったと思うのは対話形式で書かれた2章だった。 特に飯野由里子さんとの対話がよかった。 「対人のコンフリクトを起こさないではなく、起きたときにどう対処をするかを学校で教えなければならない。違っていて当たり前だからコンフリクトも生じる。」という旨の発言は、前の選挙でのひどい排外主義に対抗できる考え方だとも思った。 また、本田秀夫さんとの対話でも触れられていたが、筆者の内面化した能力主義、つまり「障害があるからこそ何かに優れていなければならない」という考え方には自分にも身に覚えがある。その能力主義が一章のコミュニケーション力への忌避感とも繋がるのだろうと思った。 また、飯野由理里子さんの「社会は一人の人や、一つの団体が変えていくものではなく、お互いやってることも知らない、話したこともないような人々が、それぞれ重なる問題意識を持ちながら、自分のできる範囲でやりたいことを積み重ねていくなかで変わっていくものだと考えます。」(P131 11行目)という言葉も、最近の自分の悩みを晴らすものだった。 「ガザとは何か」(岡真理)でも、パレスチナ人の俳優、ジュリアーノさんがウトロ地区の訴訟で人々が闘っている姿を見て、自分たちと同じ闘いだとし、勇気づけ励まされた話を挙げ、「私たちが私たちの闘いをしっかりと闘うことも、パレスチナと連帯することにつながります。」と書いてあり、感動したことを思い出した。 夏の選挙は本当に無力さを感じた。 自分自身は頑張って闘ったつもりではあったが、排外主義に負けてしまったという気持ちでいて、しかもガザの状況はずっと地獄が続いているし、友人はSNSにマックやスタバの写真を上げている。その状況が本当につらくて、暑さもあって精神的に参ってしまった。党の会議に参加できないことも、自分は何もしていないと思えて辛かった。 でも、この本では「マイノリティであるからとコミュニケーションをしなければならないのは人権侵害だ。」と著者がはっきり書いている。私もまた、コミュニケーションをして社会とつながらなければ生きていけないという能力主義を内面化していたのかもしれない。 「本当は現代の技術や知識で何とかできるのに」という言葉は、坂本龍一が生前、音楽を作るAI(生成AI)に対して「そんなことにAIを使うより、気候変動をどうするかとか、貧困や格差をどうするか、そういうことにAIを使ってほしい。」と言っていたことを思い出す。 どうして人々は素晴らしい技術を自然や弱者に還元せず、個人の儲けを考えてしまうんだろう。結局、資本主義って疲れるよね。となってしまう。結局個人が自分のできる範囲のことをできる限りでやって、それぞれゆるくつながりつつ、つながらないでいつつ、頑張っていくしかないのだ。
桃缶@mel0co2025年10月15日読み終わった@ 自宅夏の選挙前に某党に入党して、社会と繋がるって素晴らしいな〜と感じたことで、「つながらない権利」てなんなんだろうと気になっていた。 選挙の結果と夏の厳しさで体調と精神を崩してしまい、結局党の活動もあまりできなくなったことでさらに「つながらない権利」気になり、最近涼しくなってやっと調子が良くなってきて読み終えることができた。 一章はマイノリティが当事者コミュニティへ所属することでコミュニケーションが強いられている危機感が述べられていた。筆者の個人的なコミュ力への忌避感を感じ、感情移入の入口としてはよかったが、では具体的にどうすればいいのだろうということがあまり見えてこず、消化不良感があった。(それについては3章に書かれている) 私がこの本を読んでよかったと思うのは対話形式で書かれた2章だった。 特に飯野由里子さんとの対話がよかった。 「対人のコンフリクトを起こさないではなく、起きたときにどう対処をするかを学校で教えなければならない。違っていて当たり前だからコンフリクトも生じる。」という旨の発言は、前の選挙でのひどい排外主義に対抗できる考え方だとも思った。 また、本田秀夫さんとの対話でも触れられていたが、筆者の内面化した能力主義、つまり「障害があるからこそ何かに優れていなければならない」という考え方には自分にも身に覚えがある。その能力主義が一章のコミュニケーション力への忌避感とも繋がるのだろうと思った。 また、飯野由理里子さんの「社会は一人の人や、一つの団体が変えていくものではなく、お互いやってることも知らない、話したこともないような人々が、それぞれ重なる問題意識を持ちながら、自分のできる範囲でやりたいことを積み重ねていくなかで変わっていくものだと考えます。」(P131 11行目)という言葉も、最近の自分の悩みを晴らすものだった。 「ガザとは何か」(岡真理)でも、パレスチナ人の俳優、ジュリアーノさんがウトロ地区の訴訟で人々が闘っている姿を見て、自分たちと同じ闘いだとし、勇気づけ励まされた話を挙げ、「私たちが私たちの闘いをしっかりと闘うことも、パレスチナと連帯することにつながります。」と書いてあり、感動したことを思い出した。 夏の選挙は本当に無力さを感じた。 自分自身は頑張って闘ったつもりではあったが、排外主義に負けてしまったという気持ちでいて、しかもガザの状況はずっと地獄が続いているし、友人はSNSにマックやスタバの写真を上げている。その状況が本当につらくて、暑さもあって精神的に参ってしまった。党の会議に参加できないことも、自分は何もしていないと思えて辛かった。 でも、この本では「マイノリティであるからとコミュニケーションをしなければならないのは人権侵害だ。」と著者がはっきり書いている。私もまた、コミュニケーションをして社会とつながらなければ生きていけないという能力主義を内面化していたのかもしれない。 「本当は現代の技術や知識で何とかできるのに」という言葉は、坂本龍一が生前、音楽を作るAI(生成AI)に対して「そんなことにAIを使うより、気候変動をどうするかとか、貧困や格差をどうするか、そういうことにAIを使ってほしい。」と言っていたことを思い出す。 どうして人々は素晴らしい技術を自然や弱者に還元せず、個人の儲けを考えてしまうんだろう。結局、資本主義って疲れるよね。となってしまう。結局個人が自分のできる範囲のことをできる限りでやって、それぞれゆるくつながりつつ、つながらないでいつつ、頑張っていくしかないのだ。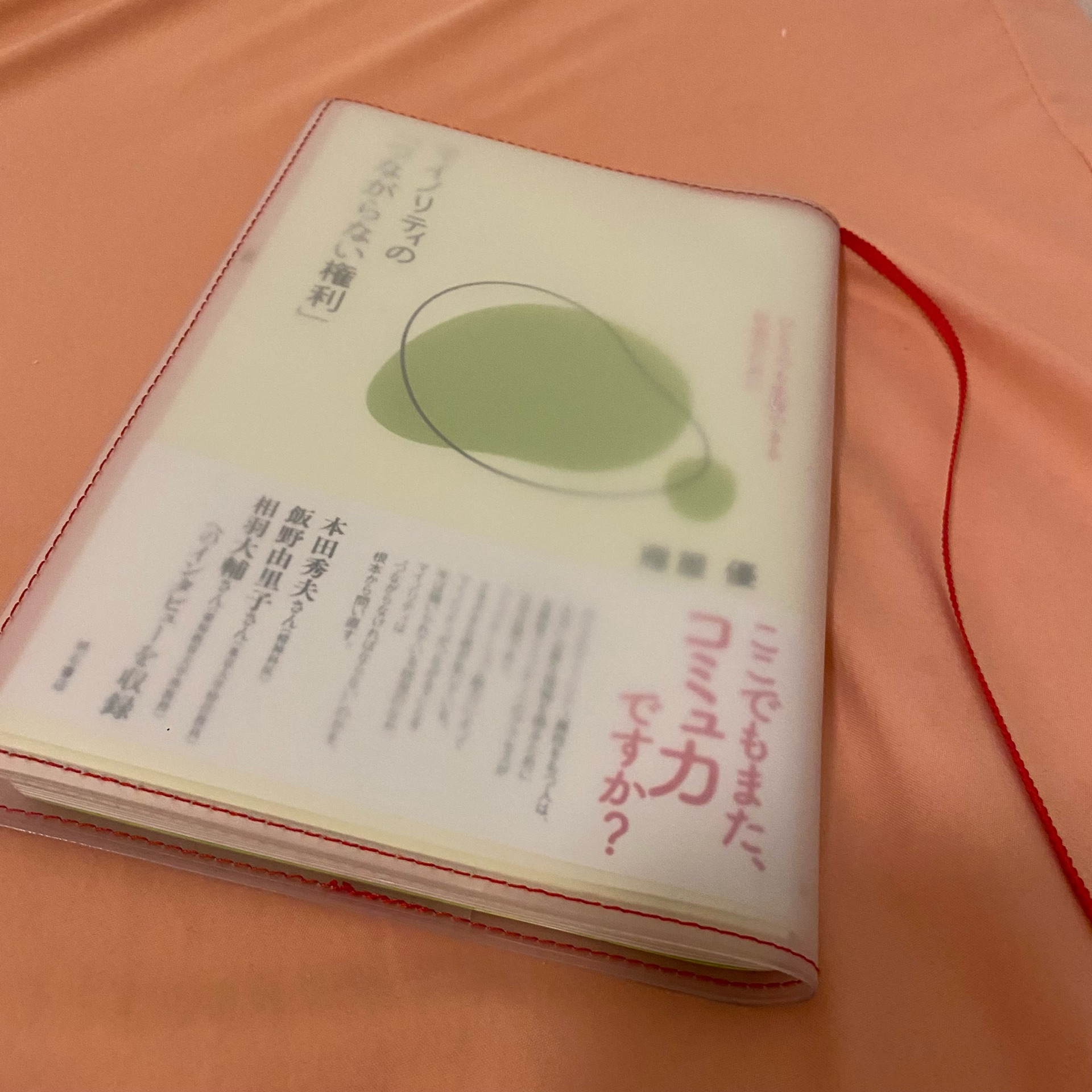




 sasai@sasai_742025年9月10日読んでるマイノリティについて考えるとき、能力主義の根深さに直面して気圧されてしまう。 まずは自分への差別意識をなくさねば。それは他人に向けているつもりはなくても既に向いているに等しい。 まだつながるかどうかを選択する段階に至れていない。
sasai@sasai_742025年9月10日読んでるマイノリティについて考えるとき、能力主義の根深さに直面して気圧されてしまう。 まずは自分への差別意識をなくさねば。それは他人に向けているつもりはなくても既に向いているに等しい。 まだつながるかどうかを選択する段階に至れていない。
 pamo@pamo2025年8月15日読み終わった感想図書館本このアプリで知って気になっていたら、図書館のおすすめ棚に並んでいたので。 自分自身もつながるのが嫌いで、なるべくつながらずに生きていたい。 しかし例えマイノリティでなくとも、やっぱりつながらない人はつながる人に比べてビハインドになる(学校のノートの貸し借り、ママ友の情報ネットワーク、会社の社内政治や飲みニケーション・タバコミュニケーションetc) マイノリティは、マジョリティよりもずっとそのビハインドが切実だ。 知り合いに、全国的にニュースになった大事故に巻き込まれた被害者がいる。トラウマの対処として「被害者の会」に参加していたが、しかし自身の被害は軽度だったため、重篤な被害を受けた人たちの切実ぶりを前にして引け目を感じ、その会からは遠のいてしまったそうだ。 マイノリティの支えとしてコミュニティがあるが、コミュニティというものはとかく、人との相違を感じさせることから逃れられない。 正直、読んでいて「世の中なんてそんなモンでしょ」という気持ちもある。歳をとればとるほど、今の世の中がこうなっている理由も分かってくる。 そういう意味では100%この本に賛同する気持ちにはなれないのだが、しかし自分の中に根深く染み付いた先入観に気づかせてもらえるという点では読んで良かった。 この方がこの先どのように生き、どのように考え、何を書いていくのか、気になる人だ。
pamo@pamo2025年8月15日読み終わった感想図書館本このアプリで知って気になっていたら、図書館のおすすめ棚に並んでいたので。 自分自身もつながるのが嫌いで、なるべくつながらずに生きていたい。 しかし例えマイノリティでなくとも、やっぱりつながらない人はつながる人に比べてビハインドになる(学校のノートの貸し借り、ママ友の情報ネットワーク、会社の社内政治や飲みニケーション・タバコミュニケーションetc) マイノリティは、マジョリティよりもずっとそのビハインドが切実だ。 知り合いに、全国的にニュースになった大事故に巻き込まれた被害者がいる。トラウマの対処として「被害者の会」に参加していたが、しかし自身の被害は軽度だったため、重篤な被害を受けた人たちの切実ぶりを前にして引け目を感じ、その会からは遠のいてしまったそうだ。 マイノリティの支えとしてコミュニティがあるが、コミュニティというものはとかく、人との相違を感じさせることから逃れられない。 正直、読んでいて「世の中なんてそんなモンでしょ」という気持ちもある。歳をとればとるほど、今の世の中がこうなっている理由も分かってくる。 そういう意味では100%この本に賛同する気持ちにはなれないのだが、しかし自分の中に根深く染み付いた先入観に気づかせてもらえるという点では読んで良かった。 この方がこの先どのように生き、どのように考え、何を書いていくのか、気になる人だ。



 annan@tsundokunoyama2025年6月28日買った積読中日本が一億年後ぐらいに公助の充実した社会になっても「つながり」がキモだ。わかっちゃいるけどぶっちゃけしんどい。そんな自分を正当化したくて買いました。
annan@tsundokunoyama2025年6月28日買った積読中日本が一億年後ぐらいに公助の充実した社会になっても「つながり」がキモだ。わかっちゃいるけどぶっちゃけしんどい。そんな自分を正当化したくて買いました。
 リチ@richi2025年6月15日読んでる作中に出てきた、これらの本が気になる。 「ふれる社会学」(ケイン樹里安、上原健太郎編集 北樹出版) 「はじめてのジェンダー論」(加藤秀一著 有斐閣) 「トランスジェンダー問題 議論は正義のために」(ショーン・フェイ著明石書店)
リチ@richi2025年6月15日読んでる作中に出てきた、これらの本が気になる。 「ふれる社会学」(ケイン樹里安、上原健太郎編集 北樹出版) 「はじめてのジェンダー論」(加藤秀一著 有斐閣) 「トランスジェンダー問題 議論は正義のために」(ショーン・フェイ著明石書店)

 雨晴文庫@amehare_bunko20232025年5月31日読み終わったまた読みたいつながることの重要性を訴える主張が多い昨今において、「つながらない権利」を掘り下げて考えた貴重な一冊。 “マイノリティは「つながらない」を選べない。あるいは、選ぶと生活の質が下がるから、仕方なく、「つながる」ことにしている。そういうマイノリティがいることを忘れて、「つながる」ことを手放しに称賛するのは危うい。”p72 わたしは障がい者の当事者運動に関わる家庭で育ち、今は我が子の不登校からその当事者活動をしているけれど、人と関わることが本来苦手だから、ほんとうに疲れ果てることがある。 これをやることでしか社会に居場所を作れない気がしてやめることができないけれど、やらなくても最低限の権利が守られ穏やかに暮らせるのなら…と思うことも多い。 この本のように「つながること」を強いられるのはなぜなのか?という問いはもっと注目され、議論されて然るべきだと思う。
雨晴文庫@amehare_bunko20232025年5月31日読み終わったまた読みたいつながることの重要性を訴える主張が多い昨今において、「つながらない権利」を掘り下げて考えた貴重な一冊。 “マイノリティは「つながらない」を選べない。あるいは、選ぶと生活の質が下がるから、仕方なく、「つながる」ことにしている。そういうマイノリティがいることを忘れて、「つながる」ことを手放しに称賛するのは危うい。”p72 わたしは障がい者の当事者運動に関わる家庭で育ち、今は我が子の不登校からその当事者活動をしているけれど、人と関わることが本来苦手だから、ほんとうに疲れ果てることがある。 これをやることでしか社会に居場所を作れない気がしてやめることができないけれど、やらなくても最低限の権利が守られ穏やかに暮らせるのなら…と思うことも多い。 この本のように「つながること」を強いられるのはなぜなのか?という問いはもっと注目され、議論されて然るべきだと思う。




 はな@hana-hitsuji052025年5月24日読み終わったどこに行っても、よそ者の自覚があった。 この一文に尽きる。 この気持ちを知っているから手に取ってしまったんだと思う。 今、並行して読んでいる本や勉強していることにも次々リンクすることが書かれており、作者の考えやそれを表現する言葉が変わっていったり、意思や方向がクリアになっていく過程が良かった。 私が『選ばない、選びたくない』という権利は、先人が苦労して獲得してきたもののひとつかもしれない。 だから今の私が自分の意思で選択出来るということを心に留めておかねばならないなと思った。 そして目の前の人の不便や困り事を、その人のものとして捉えている自分が恥ずかしいというか、おかしみを感じた。 その人は自分の未来かもしれないと微塵も考えていない部分に鏡を突きつけられて、その中の自分と目が合った。 こんなに自分と相手を区別して優劣をつけて殺して、人間の生存戦略は一体何なんだよと苛々していたが、人権の保障の徹底を目指すことが自分の生存にも有益だという言葉を読んで、あー…人のためにすることが巡り巡って自分のためになるのはこのことかと。 これが私たちの、人間の目指している特化された力だと信じたい。 あー…。いつも新しい本を読むたびに、自分の中にあるもののうち何かと何かがリンクする。 そして自分の考えが広がり行動が変わる瞬間を自分が1番目に感じることが出来る。これだよ、読書。
はな@hana-hitsuji052025年5月24日読み終わったどこに行っても、よそ者の自覚があった。 この一文に尽きる。 この気持ちを知っているから手に取ってしまったんだと思う。 今、並行して読んでいる本や勉強していることにも次々リンクすることが書かれており、作者の考えやそれを表現する言葉が変わっていったり、意思や方向がクリアになっていく過程が良かった。 私が『選ばない、選びたくない』という権利は、先人が苦労して獲得してきたもののひとつかもしれない。 だから今の私が自分の意思で選択出来るということを心に留めておかねばならないなと思った。 そして目の前の人の不便や困り事を、その人のものとして捉えている自分が恥ずかしいというか、おかしみを感じた。 その人は自分の未来かもしれないと微塵も考えていない部分に鏡を突きつけられて、その中の自分と目が合った。 こんなに自分と相手を区別して優劣をつけて殺して、人間の生存戦略は一体何なんだよと苛々していたが、人権の保障の徹底を目指すことが自分の生存にも有益だという言葉を読んで、あー…人のためにすることが巡り巡って自分のためになるのはこのことかと。 これが私たちの、人間の目指している特化された力だと信じたい。 あー…。いつも新しい本を読むたびに、自分の中にあるもののうち何かと何かがリンクする。 そして自分の考えが広がり行動が変わる瞬間を自分が1番目に感じることが出来る。これだよ、読書。







 はな@hana-hitsuji052025年5月23日まだ読んでる図書館で借りた得意じゃなくて興味や好きに着目する。 得意ってなんだろう? 自分にとっては、ずっとやり続けても負担がなくむしろ楽しんでやれること。 苦じゃないのだから、そちらでも良いのでは?むしろそっちを取っていけば伸びるものがあるのでは?と思っていたけど、もしそれを失うと能力主義が顔を出してくるのか。 そしてそれは家父長制度に繋がっている、のところでえええ!と驚くくらいには、この制度が自分の価値観や人生に染み付いているのかもしれない。 読んでてずっと興味深い、この本。 p160「できない」人を低く見ていいとする発想は容易に優生思想へと繋がっていく。 ガザやパレスチナの本を読んでいても思うけど… 例えばライオンは肉食だから肉を噛み切れるように歯が尖ってる。シマウマは草をすりつぶして食べるから歯が平たいとか、動物は生き残るために必要な部分を特化させて生きているのが本当に興味深いなと感じる。 人間は社会性を武器にしてここまで増えたとして、この性質が私たちの特化した部分なの??なんなの?? 感情や思考があっても、この呪いの強さよ。
はな@hana-hitsuji052025年5月23日まだ読んでる図書館で借りた得意じゃなくて興味や好きに着目する。 得意ってなんだろう? 自分にとっては、ずっとやり続けても負担がなくむしろ楽しんでやれること。 苦じゃないのだから、そちらでも良いのでは?むしろそっちを取っていけば伸びるものがあるのでは?と思っていたけど、もしそれを失うと能力主義が顔を出してくるのか。 そしてそれは家父長制度に繋がっている、のところでえええ!と驚くくらいには、この制度が自分の価値観や人生に染み付いているのかもしれない。 読んでてずっと興味深い、この本。 p160「できない」人を低く見ていいとする発想は容易に優生思想へと繋がっていく。 ガザやパレスチナの本を読んでいても思うけど… 例えばライオンは肉食だから肉を噛み切れるように歯が尖ってる。シマウマは草をすりつぶして食べるから歯が平たいとか、動物は生き残るために必要な部分を特化させて生きているのが本当に興味深いなと感じる。 人間は社会性を武器にしてここまで増えたとして、この性質が私たちの特化した部分なの??なんなの?? 感情や思考があっても、この呪いの強さよ。





 はな@hana-hitsuji052025年5月20日まだ読んでる図書館で借りた自分が考えたことを文章や言葉にして残そうと思うのは、海に手紙の入ったボトルを流すのと似ている。 そして本を読むのは流れてきたボトルを拾って中の手紙を読むのと似ている。 たった一文でも自分と同じ感覚や現象を知っている人、新たな視点を与えてくれる人に出会う瞬間というか。 こんなふうに考える自分は頭がどうかしたのかな?と心配になるような誰とも共有出来そうにない気持ちや価値観が、ある日突然流れ着いてくる。 この本にもそれがいっぱい詰まっていて、こんなに惜しみなくリンクする物を与えてくれるのに(作者は与えたつもりはないだろうけど)2000円は破格だなと改めて思う。 マイノリティのことを想定していない前提で溢れかえる情報の中にいるから、マジョリティはマイノリティの存在さえ身近ではないしマイノリティはもっと辿り着けない。 そもそも私は、私のことをよく知らないまま頭を抱えてきたのだなと痛感する。 もっと知らないことを知りたい。
はな@hana-hitsuji052025年5月20日まだ読んでる図書館で借りた自分が考えたことを文章や言葉にして残そうと思うのは、海に手紙の入ったボトルを流すのと似ている。 そして本を読むのは流れてきたボトルを拾って中の手紙を読むのと似ている。 たった一文でも自分と同じ感覚や現象を知っている人、新たな視点を与えてくれる人に出会う瞬間というか。 こんなふうに考える自分は頭がどうかしたのかな?と心配になるような誰とも共有出来そうにない気持ちや価値観が、ある日突然流れ着いてくる。 この本にもそれがいっぱい詰まっていて、こんなに惜しみなくリンクする物を与えてくれるのに(作者は与えたつもりはないだろうけど)2000円は破格だなと改めて思う。 マイノリティのことを想定していない前提で溢れかえる情報の中にいるから、マジョリティはマイノリティの存在さえ身近ではないしマイノリティはもっと辿り着けない。 そもそも私は、私のことをよく知らないまま頭を抱えてきたのだなと痛感する。 もっと知らないことを知りたい。







 はな@hana-hitsuji052025年5月19日まだ読んでる図書館で借りた私には友達と呼べる人が人生に2人いて、その子達には『こんなことを思ってる、こんなことがあったんだって正直に話したらどう思うかな。離れていってしまうのかな』と全く恐れたり心配することのない人たちなんだけど その子達とこの本について語り合いたくて仕方ない。 この作者は、当事者コミュニティのメリットに理解を示した途端『でも、それでいいのだろうか?』と自問するところがすごく好きだ。 確かにそう、確かに良いことがある、だから求めるし集まるよね、でも…?と、常に考えてる。 それが自分のこれまでの経験とカチャカチャとリンクしていく音が聞こえてきそう。 モヤモヤしてたもの、沢山言語化してくれて本当にありがたい。それなんだよ〜うううう。 自分が周囲に言語化すると、茶化されたり軽視されたりするようなこと、今のところ全てのそれらと静かに見つめあっている気持ち。静寂。
はな@hana-hitsuji052025年5月19日まだ読んでる図書館で借りた私には友達と呼べる人が人生に2人いて、その子達には『こんなことを思ってる、こんなことがあったんだって正直に話したらどう思うかな。離れていってしまうのかな』と全く恐れたり心配することのない人たちなんだけど その子達とこの本について語り合いたくて仕方ない。 この作者は、当事者コミュニティのメリットに理解を示した途端『でも、それでいいのだろうか?』と自問するところがすごく好きだ。 確かにそう、確かに良いことがある、だから求めるし集まるよね、でも…?と、常に考えてる。 それが自分のこれまでの経験とカチャカチャとリンクしていく音が聞こえてきそう。 モヤモヤしてたもの、沢山言語化してくれて本当にありがたい。それなんだよ〜うううう。 自分が周囲に言語化すると、茶化されたり軽視されたりするようなこと、今のところ全てのそれらと静かに見つめあっている気持ち。静寂。








 はな@hana-hitsuji052025年5月18日読み始めた図書館で借りたようやく貸出の順番が回ってきた! めちゃ不謹慎な気がして当時なかなか言い出せなかったが、地震などの災害や自分の持つマイノリティの側面で不便や困難が生じた時、絆や繋がり的なものを重視されたり求められたりすることに正直言ってうんざりすることがあった。 コミュニティの中に入っていって関係性を円滑に育てられない心境、状態の時に、1番欲しい情報はそこにしかないしんどさが確かにある。 丸ごと繋がりたいわけじゃない。 親切なフリした詮索やお節介は自分の求めているものを手に入れるための交換条件みたいに感じて辟易としてしまい、自己嫌悪にもなったりして。 こういう切り口の本、待ってたよ!
はな@hana-hitsuji052025年5月18日読み始めた図書館で借りたようやく貸出の順番が回ってきた! めちゃ不謹慎な気がして当時なかなか言い出せなかったが、地震などの災害や自分の持つマイノリティの側面で不便や困難が生じた時、絆や繋がり的なものを重視されたり求められたりすることに正直言ってうんざりすることがあった。 コミュニティの中に入っていって関係性を円滑に育てられない心境、状態の時に、1番欲しい情報はそこにしかないしんどさが確かにある。 丸ごと繋がりたいわけじゃない。 親切なフリした詮索やお節介は自分の求めているものを手に入れるための交換条件みたいに感じて辟易としてしまい、自己嫌悪にもなったりして。 こういう切り口の本、待ってたよ!









 oɥı̣ɥS@irid2025年5月7日読み終わった借りてきた第3報:「ママ友」も、本来なら子が属する施設が出すべき情報が不足しているばかりに、自分にフィットするとは限らない非公的集団に不承不承属する面もありそう(2025/05/20) 第2報:売り文句だとコミュ力重視への嫌厭を描いているように見えるが、マイノリティにとっての生活必需情報の入手が望まないコミュニケーションスタイルと引き換えになることへの問題提起だった。むしろ、当事者会や先人たちの政治への働きかけに対しては著者の敬意さえ感じた。また、著者が生き延びるためのよすがとしての能力への執着が、社会学に触れ、各ゲストと対談を重ねる中で「執着」から客観的なお付き合いへと変化していく様子も伺えた(2025/05/08) 第1報:マイノリティのと題されてますが、「ママ友」も強いられるつながりに入るのかな
oɥı̣ɥS@irid2025年5月7日読み終わった借りてきた第3報:「ママ友」も、本来なら子が属する施設が出すべき情報が不足しているばかりに、自分にフィットするとは限らない非公的集団に不承不承属する面もありそう(2025/05/20) 第2報:売り文句だとコミュ力重視への嫌厭を描いているように見えるが、マイノリティにとっての生活必需情報の入手が望まないコミュニケーションスタイルと引き換えになることへの問題提起だった。むしろ、当事者会や先人たちの政治への働きかけに対しては著者の敬意さえ感じた。また、著者が生き延びるためのよすがとしての能力への執着が、社会学に触れ、各ゲストと対談を重ねる中で「執着」から客観的なお付き合いへと変化していく様子も伺えた(2025/05/08) 第1報:マイノリティのと題されてますが、「ママ友」も強いられるつながりに入るのかな


 lily@lily_bookandcoffee2025年4月17日読み終わった「家父長制を基盤とした日本の社会においては、人に優劣をつけて、優位に立つ人が劣位に立つ人を支配する構造があります。家父長制や能力主義に染まってしまうと、劣位に立ったときに自尊心を持てなくなったり、自分より優位に立つ人に物を言えなくなったりしてしまいます。」
lily@lily_bookandcoffee2025年4月17日読み終わった「家父長制を基盤とした日本の社会においては、人に優劣をつけて、優位に立つ人が劣位に立つ人を支配する構造があります。家父長制や能力主義に染まってしまうと、劣位に立ったときに自尊心を持てなくなったり、自分より優位に立つ人に物を言えなくなったりしてしまいます。」

 lily@lily_bookandcoffee2025年4月16日読んでる「つまり、当事者コミュニティにつながること以外の情報収集の手段が確立されないと、当事者であると「認めたくない」人々は身動きが取れなくなってしまうのだ。そして、身動きが取れなくなった人々の怒りや悲しみの矛先は、他の当事者に向かうこともある。」
lily@lily_bookandcoffee2025年4月16日読んでる「つまり、当事者コミュニティにつながること以外の情報収集の手段が確立されないと、当事者であると「認めたくない」人々は身動きが取れなくなってしまうのだ。そして、身動きが取れなくなった人々の怒りや悲しみの矛先は、他の当事者に向かうこともある。」






 rimo@rimo2025年3月29日買った読んでる「はじめに」を読んでなるほどなーと思いつつ、何かすごく引っかかる感覚があるので、それが何なのかを考えている。人権的観点から最低限必要と思われる情報を得るのに、能力を要求されるのは良くないというのは、そう思う。何か語り口に違和感があるから、大事な視点が抜け落ちているのかも。
rimo@rimo2025年3月29日買った読んでる「はじめに」を読んでなるほどなーと思いつつ、何かすごく引っかかる感覚があるので、それが何なのかを考えている。人権的観点から最低限必要と思われる情報を得るのに、能力を要求されるのは良くないというのは、そう思う。何か語り口に違和感があるから、大事な視点が抜け落ちているのかも。

 fuyunowaqs@paajiiym2025年3月18日読むのがこわい未読。 タイトルを見て衝撃を受けた。子どものころから漠然と「他人に迷惑をかけると面倒くさいからはやめに死にたい」と考えてきたが、その願いは真正のものではなかったのかもしれない。たとえ一瞬でも「他人とつながらなくても生きていけるなら生きてみたい」と感じたことに驚き、悲しくなった。
fuyunowaqs@paajiiym2025年3月18日読むのがこわい未読。 タイトルを見て衝撃を受けた。子どものころから漠然と「他人に迷惑をかけると面倒くさいからはやめに死にたい」と考えてきたが、その願いは真正のものではなかったのかもしれない。たとえ一瞬でも「他人とつながらなくても生きていけるなら生きてみたい」と感じたことに驚き、悲しくなった。






 廣畑達也@pirohata122025年3月6日買った@ ブックファースト 新宿店話題のこちらも購入。マイノリティは声を社会に届かせるには連帯せざるを得ない立場に置かれやすいが、それしか選択肢が社会にないというのは、確かに引っかかる。読んで解像度を高めたい。お世話になっている飯野さんのインタビューも掲載。
廣畑達也@pirohata122025年3月6日買った@ ブックファースト 新宿店話題のこちらも購入。マイノリティは声を社会に届かせるには連帯せざるを得ない立場に置かれやすいが、それしか選択肢が社会にないというのは、確かに引っかかる。読んで解像度を高めたい。お世話になっている飯野さんのインタビューも掲載。 talia@talia0v02025年2月27日読み終わった友人たちと有志で開催してる読書会で読みました。 明石書店さんのSNSアカウントの紹介により買った本です。 昨今のSNSのあれこれを憂いなんとなく関連を求めて私がリクエストした本ですが、実際はもっと切実な「つながらない権利」を求めた内容でした。 本の構成は筆者雁屋さんの体験談を含めた連載から始まり、著書紹介にもある本田さん、飯野さん、相羽さんへのインタビューを経て、筆者のまとめのざっくり3部。 少しネタバレだけど、「つながらない権利」を求めていた筆者ですが、連載を通したインタビューを経てからは「つながる」期間や頻度、コミットの仕方などグラデーションの重要性に焦点がいくので、タイトルから想像するよりもターゲットになる読者層は広いのでは(気になった人は一読の価値あるのでは)と思いました。 例えばあとがきに 「私は対面コミュニケーションから逃げたいし、人と距離をとっておきたいと考えている。でも、中には対面コミュニケーションが苦手だけど、そこでしか満たされないものがあり、それを求めている人もいるだろう。そういう人には本書は有意義な提案をできていない」 とあり、読みながら私のニーズはどちらかというと後者かもしれない…と思う箇所が度々ありましたが、「つながりたくない」と切実に思ってるマイノリティのつながらなければ生きていけない社会を想像するきっかけになれたし、インタビューも含めた「つながる」グラデーションの話には自分事として頷ける内容もありました。 読書会ではサブタイトルの「ひとりでも生存できる」から「マイノリティが生存に必要な情報とはどんなものがあるか」を考えたり、本の内容をふまえて「本当に『つながらない権利』< コミュニケーションの多様化で良いのか」をブレストしてみたり、自分たちにも当てはまる能力主義について話したりしました🙌 https://www.akashi.co.jp/smp/book/b657339.html
talia@talia0v02025年2月27日読み終わった友人たちと有志で開催してる読書会で読みました。 明石書店さんのSNSアカウントの紹介により買った本です。 昨今のSNSのあれこれを憂いなんとなく関連を求めて私がリクエストした本ですが、実際はもっと切実な「つながらない権利」を求めた内容でした。 本の構成は筆者雁屋さんの体験談を含めた連載から始まり、著書紹介にもある本田さん、飯野さん、相羽さんへのインタビューを経て、筆者のまとめのざっくり3部。 少しネタバレだけど、「つながらない権利」を求めていた筆者ですが、連載を通したインタビューを経てからは「つながる」期間や頻度、コミットの仕方などグラデーションの重要性に焦点がいくので、タイトルから想像するよりもターゲットになる読者層は広いのでは(気になった人は一読の価値あるのでは)と思いました。 例えばあとがきに 「私は対面コミュニケーションから逃げたいし、人と距離をとっておきたいと考えている。でも、中には対面コミュニケーションが苦手だけど、そこでしか満たされないものがあり、それを求めている人もいるだろう。そういう人には本書は有意義な提案をできていない」 とあり、読みながら私のニーズはどちらかというと後者かもしれない…と思う箇所が度々ありましたが、「つながりたくない」と切実に思ってるマイノリティのつながらなければ生きていけない社会を想像するきっかけになれたし、インタビューも含めた「つながる」グラデーションの話には自分事として頷ける内容もありました。 読書会ではサブタイトルの「ひとりでも生存できる」から「マイノリティが生存に必要な情報とはどんなものがあるか」を考えたり、本の内容をふまえて「本当に『つながらない権利』< コミュニケーションの多様化で良いのか」をブレストしてみたり、自分たちにも当てはまる能力主義について話したりしました🙌 https://www.akashi.co.jp/smp/book/b657339.html