
本屋lighthouse
@books-lighthouse
2025年11月2日
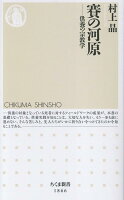
賽の河原
村上晶
読み始めた
『失われたいくつかの〜』を家に忘れてきたためこちらを読む。
こうした抽象的な口寄せの内容が依頼者にとってリアルになるためには、聞いている側が具体的な人間や事件を組み入れる必要があるとする。そうした依頼者の参加がなければ口寄せは無意味になるという。(p.41)
そうした曖昧な感覚を捉えるためには、むしろ真偽という尺度は邪魔になる。真偽を突き詰めようとすると、本当でも嘘でもないという次元が見えなくなってしまうためである。(p.45)
イタコの語りを読み解くには、イタコと依頼者のあいだに「型」が共有されている必要があるとのこと。ゆえにそれが共有され得ない「有名人を降霊させる」といったものは虚無である。
生成AIによるフェイク動画のことを考えてみると、おそらくここにも「騙す/騙される」の型がある。フェイクだとわかって楽しむ、あるいは本気で騙されたとしても最後にはフェイクだとわかるような仕掛けがある。そういった型があるからこそ、我々は安全に楽しむことができる。しかしここ最近のフェイク動画はその型を失っていて、作り手は本気で騙すために作り、受け手は騙されていることに気づけないままでいることが増えている。もはやこれは娯楽ではない。「騙されている」ことに気がつかない者がミサイルのボタンを押す未来はすぐそこにある。「騙されていることに気がつかない者がミサイルのボタンを押している」フェイク動画を見た別の最高責任者が、それを本当だと信じてミサイルのボタンを押すかもしれない。こんな陳腐なストーリーで世界は滅ぶ。





