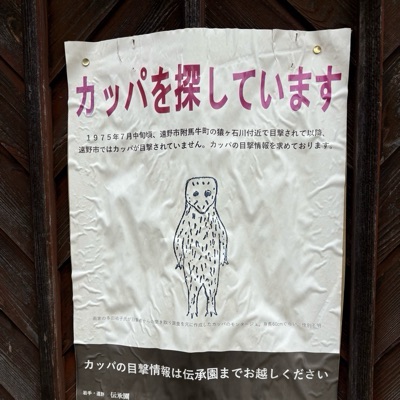犬山俊之
@inuyamanihongo
2025年11月14日

透明な夜の香り
千早茜
読み終わった
台北の一間書店 the1bookstore で台湾中文版《透明夜晚的香氣》を見つけて教室用に購入していたので、日本語の原著も手に入れて読んでみました。(新井見枝香氏との共著エッセイ『胃が合うふたり』もよかったので。)
最初、表紙を見たときは、「香水とか、お香についてのウンチク話?」と思ったのですが、「人間のにおい」、「生きる=におう」ことについての話でした。
人は、肉体としてはそれぞれ離れているけれど、生活する上では匂いを介してお互いに接しているのだと気づかされます。匂いから相手を知り、気遣い、思い遣ることもできる。考えてみれば、自分も人を見たり、人の言葉を聞いたりしながら、人と接していますが、どの感覚をとっても、この小説の登場人物ほど誠実に他人を感じてはいなかった。人の事を考えてはいなかった、と。
「香り/においを書く」という試みはおもしろかったです。
* *
それから、小説の内容とは関係ないのですが、また振り仮名の話を。
この小説の重要な登場人物の名前は「小川朔」というのですが、みなさん読めるでしょうか。
「おがわ さく」さん。
「朔」は常用漢字に入っていないので、日本人でも小中学生だと読めないかもしれません。
また、「小川」ですが、実はこれ、日本語学習者にとっては非常に難しいのです。「小さい(ちいさい)」は最初に習う。「小学校(しょうがっこう)」も読める。でも、「小鳥」は「ちいとり?」。「小川」は?
「小鳥」が「ことり」、「小川」が「おがわ」と読めるのは、事前に耳からのインプットが十分にある人だけです。つまり、日本語環境でで長期生活していたり、日本で基礎教育を受けた人のみ。実は、日本語の文章というのは、すでに日本語が十分にわかる人しか読めないのです。「本を読んで勉強しよう」ということが、実はできない、或いは非常に難しいのです。本を読もうにも、漢字が音読できないので、読み進めることができないのです。いちいち辞書で調べますか。そこまでできずに、放り投げる人が多いでしょう。
この20年台湾の日本語学習者と接してきて、また台湾人と日本人の間に生まれた子どもたちの日本語を見てきて、このことを痛感しています。
解決策は簡単です。振り仮名をつけること。できるなら総ルビにすること。本書中の「小川朔」も初出時には振り仮名がついています。しかし、一回だけ。以降は振り仮名なしです。一回では覚えられません。総ルビが理想。何度も目にすることで、意図せずに覚えることができます。特に本書のような、若い読者が手にとるような本は総ルビにすることはできないでしょうか。読むだけで、教育効果が見込まれます。
たとえば、100前に生きた婦人解放運動家・伊藤野枝などの伝記を読むと、当時は総ルビであった古新聞を何度も読み込むことで知識を得ることができたというエピソードが書かれています。
#全ての出版物にふりがなを
海外ルーツを持ち、日本での生活を始めたばかりの人や海外にいる読者に日本語の書籍を読ませたい、買ってもらいたいと思うなら、総ルビが一番。もちろん日本の子どもたち、なんなら日本の大人だって、振り仮名があるとすごく読みやすいのです(漢字が多い歴史小説を読んでいて、途中で挫折した人は多いと思います)。
#全ての出版物にふりがなを
集英社をはじめ、出版関係者の方、一考を▼