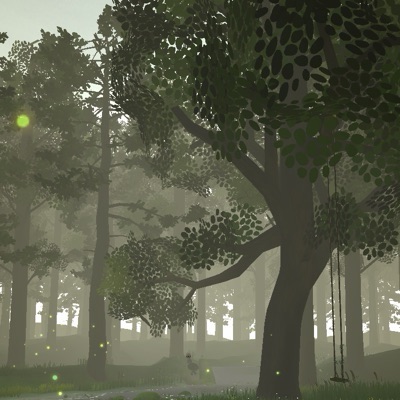柿内正午
@kakisiesta
2025年11月17日

近代小説の表現機構
安藤宏
読み始めた
“ここで文学を構成する要素として、「言葉」「人間」「状況」という三つの因子を挙げておきたい。
いうまでもなく、「言葉」「人間」「状況」に関して、近代の人文学はそれぞれ独自の学問領域を切り開いてきた。たとえば「言葉」のメカニズムに関しては言語学的なアプローチがあり、「人間」に関しては、哲学や倫理学を通して実存的な問題を追究していくことが可能だろう。「状況」に関しては、歴史学、社会学をはじめとする、さまざまな社会科学の方法的蓄積がある。こうした中であえて文学研究の意義を問うのであるとするなら、実はこれらのいずれでもあっていずれでもないということ、すなわちその要請は、「言葉」「人間」「状況」相互の「あいだ」を一個の関係概念として読み解いていく方法論にこそかかっているのではあるまいか。
すべての出発点にまず「言葉」があり、言葉で構築された虚構世界への関心を抜きに文学は成り立たない。その上で、虚構世界の生成と享受に深くかかわる「人間」と「状況」の、その可変的な相互関係を問う発想にこそ、文学研究本来の面目があるように思われるのである。そしておそらくその際の要点は、相互関係のベクトルが他に双方向を話す矢印でなければならないという原則にあるといってよい。(…)
いつの時代にあってももっとも困難なのは、流行に惑わされず、相互変革的な関係から普遍的なるものをめざしていく中庸の精神なのであろう。少なくともこの半世紀の文学研究をとりまく状況は、矢印が一方向に偏ることをあえて省みず、みずからの方法的な特権を信じ続けてきた歴史であったように思われる。研究の個別の成果が、かえって作用と反作用の働く“場”を見えにくくしてきたのだとしたら、それははなはだ不幸な事態であったにちがいない。「言葉」を通して「人間」と「状況」との可変的な相互関係を問い返していくということ——こうした基本に立ち返ることが、実はいつの時代にあってももっとも困難な道なのである。”
p.17-20