綾鷹
@ayataka
2025年11月20日
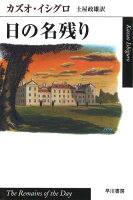
日の名残り
カズオ・イシグロ,
土屋政雄
第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけての時代に、英国有力貴族の屋敷で執事を務める男を主人公に据えたーーというか彼の視点から語られるーー年代記。
本心を偽り、感情を表現することを恐れ、自分の信じた価値観にしがみつき、記憶を作り変える主人公の姿は、自分とも重なって切なくなる。
誰しも過去の選択や行動を後悔することはあるけど、自分のダメな部分も抱えて進んでいくしかないのだな。
主人公の仕事への姿勢がすっと入ってきやすかったが、村上春樹の解説を読んで納得。
この物語とは関係ないが、カズオ・イシグロがミュージシャンを目指していたことに驚き。
・その偉大さを真似しようとした人々が、うわべを本質と取り違えてしまったのです。私どもの世代は「飾り」を追い求めすぎました。本来なら、執事としての基本の習得にすべての時間とエネルギーを振り向けるべきなのに、やれ誰の矯正だ、弁舌だ、百科事典だ、雑学事典の勉強だと、どれほど時間を無駄遣いしてきたことでしょうか。
・品格の有無を決定するものは、みずからの職業的あり方を貫き、それに堪える能力だと言えるのではありますまいか。並の執事は、ほんの少し挑発されただけで職業的あり方を投げ捨て、個人的なあり方に逃げ込みます。そのような人にとって、執事であることはパントマイムを演じているのと変わりません。ちょっと動揺する。ちょっとつまずく。すると、たちまちうわべがはがれ落ち、中の演技者がむき出しになるのです。偉大な執事が偉大であるゆえんは、みずからの職業的あり方に常住し、最後の最後までそこに踏みとどまれることでしょう。外部の出来事にはーーそれがどれほど意外でも、恐ろしくても、腹立たしくてもーー動じません。偉大な執事は、紳士がスーツを着るように執事職を身にまといます。公衆の面前でそれを脱ぎ捨てるような真似は、たとえごろつき相手でも、どんな苦境に陥ったときでも、絶対にいたしません。それを脱ぐのは、みずから脱ごうと思ったとき以外にはなく、それは自分が完全に一人だけのときにかぎられます。まさに「品格」の問題なのです。
・あまりにも理想主義的にすぎ、理論的にすぎて、大方の理解は得られないのではありますまいか。
たしかに、ある程度の真実は含まれておりましょう。イギリスのような国に住む私どもには、世界の大問題についても自分なりに考え、自分なりの意見をもつことが、多少は期待されているのかもしれません。しかし、現実の生活に追われている一般庶民が、あらゆる物事について「強い意見」をもつことなど、はたして可能でしょうか。ここの村人たちはみなもっている、というミスター・スミスの主張は、おそらく空想にすぎぬでしょう。一般庶民にそのようなことを期待するのは、とても無理というものです。さらには、望ましいことでもないようにー私にはし思われます。
一般人が知り、理解できることには、たしかに限界があるのです。そのことを無視して、誰もが国家の大問題について「強い意見」をもち、発言すべきだと主張するのは、とても賢明とは思われません。
・しかし、あの朝、ビリヤード室でが私に語ってくださったことの中には、重要な真実が合まれていたことも否定できますまい。ミスター・スペンサーが私にお尋ねになったたぐいの質問に権威をもって答えることなど、どのような執事にも期待するほうが無理と申すものでしょう。それができなければ「品格」を保てない、などというミスター・スミスの主張は、ナンセンスの最たるものと言ってよかろうかと存じます。執事の任務は、ご主人様によいサービスを提供することであって、国家の大問題に首を突っ込むことではありません。この基本を忘れてはなりますまい。国家の大問題は、常に私どもの理解を超えたところにあります。大問題を理解できない私どもが、それでもこの世に自分の足跡を残そうとしたらどうすればよいか・・・・?自分の領分に属する事柄に全力を集中することです。文明の将来をその双肩に担っておられる偉大な紳士淑女に、全力でご奉仕することこそ、その答えかと存じます。
・この結果は少しも意外なことではありません。結局はそうなるのです。と申しますのは、雇主に対して批判的な態度をとりながら、同時によいサービスを提供するということは、現実にはとても可能とは思われないからです。もちろん、レベルの高いお屋敷になりますと、つまらないことに気をとられていたら、執事のもとに出される無数の要求をさばききれないというのも事実でございまして、それも理由の一つと考えられましょうが、それだけではありません。より基本的には、「思誠心」の問題に行き着きます。雇主の行動について「強い意見」をもとうと絶えず鵜の目鷹の目をつづけている執事は、この職業に従事するすべての人々に不可々の特質である「忠誠心」を、必然的に久くことになるのです。
・ダーリントン卿にお仕えした長い年月の間、事実を見極められるのも、最善と思われる進路を判断されるのも、常に卿であり、卿お一人でした。私は執事として脇にひかえ、常にみずからの職業的領分にとどまっておりました。最善を尽くして任務を遂行したことは、誰はばかることなく申し上げることができます。そして、私が提供申し上げたサービスが一流だったと認めてくださる方々も、決して少なくはありません。卿の一生とそのお仕事が、今日、壮大な愚行としかみなされなくなったとしても、それを私の落ち度と呼ぶことは誰にもできますまい。私がみずからの仕事に後悔や恥辱を感じたりしたら、それはまったく非論理的なことのように思われます。
・私にはダーリントン卿がすべてでございました。もてる力をふりしぼって卿にお仕えして、そして、いまは・・・・私には、ふりしぼろうにも、もう何も残っておりません
・ダーリントン卿は悪い方ではありませんでした。さよう、悪い方ではありませんでした。それに、お亡くなりになる間際には、ご自分が過ちをおかしたと、少なくともそう言うことがおできになりました。卿は勇気のある方でした。人生で一つの道を選ばれました。それは過てる道でございましたが、しかし、卿はそれをご自分の意思でお選びになったのです。少なくとも、選ぶことをなさいました。しかし、私は・・・・私はそれだけのこともしておりません。私は選ばずに、信じたのです。
私は卿の賢明な判断を言じました。卿にお仕えした何十年という間、私は自分が価値あることをしていると信じていただけなのです。自分の意思で過ちをおかしたとさえ言えません。そんな私のどこに品格などがございましょうか?
・人生が思いどおりにいかなかったからと言って、後ろばかり向き、自分を責めてみても、それは詮無いことです。私どものような卑小な人間にとりまして、最終的には運命をご主人様のーーこの世界の中心におられる偉大な紳士淑女のーー手に委ねる以外、あまり選択の余地があるとは思われません。それが冷厳なる現実というものではありますまいか。あのときああすれば人生の方向が変わっていたかもしれないーーそう思うことはありましょう。しかし、それをいつまで思い悩んでいても意味のないことです。私どものような人間は、何か真に価値あるもののために微力を尽くそうと願い、それを試みるだけで十分であるような気がいたします。そのような試みに人生の多くを犠牲にする覚悟があり、その覚悟を実践したとすれば、結果はどうであれ、そのこと自体がみずからに誇りと満足を覚えてよい十分な理由となりましょう。
◾️村上春樹 解説
・ずいぶんたくさん音楽の話をしたことを記憶している。イングロも僕に劣らず音楽が大好きだった。彼は小説家になる前はミュージシャンになることを志していたということだし、僕自身も小説家になる前は、音楽に関わる仕事をして生計を立てていた。
・この本のページを繰りながら、読者は当時の英国貴族の暮らしぶりの中に、また彼に仕える忠実な執事の生き方や心理の中に、そしてそこに繰り広げられるドラマの中にとても自然に、抵抗なく引き込まれていく。しかし物語全体を読み終えたときに、僕がひとつ強く実感したのは、「これはまるで日本人の物語であるみたいに書かれているな」ということだった。ひょっとしてこの物語をそのまま日本に置き換えても、それほど不自然ではないんじゃないかと思うくらいに。
たしかにここに描かれている社会環境はすべて英国のそれであり、取り扱われているのはまさに英国的なものごとであり事象だ。しかしそこに登場する人々の感覚や感情は、あるいはその感覚や感情の描きかは、僕に驚くほどありありと、日本的な感覚や感情を想起させることになる。誤解されると困るのだが、僕はこの物語が「国際的」「普遍的」な域に達しているとか、文化の違いを超えて共感が成立しているとか、そういう一般的なことを主張しているわけではない。僕が言いたいのはもっと狭義に、それが優れて日本的なものとして成立しているということだ。たとえばーーこれはあくまで一例に過ぎないがーーそこに描かれた英国人執事のどこまでもストイックな、自らを殺してまで主人に仕える、あるいは規範に殉じるその生き方は、そして彼の内で堅固にクリアに維持される限定された世界観は、日本古来の武士の生き方と共通項を有しているようにさえ感じられ
る。
・なぜか?その理由はとてもはっきりしている。それはイシグロが高い能力を有した作家であり、しかも常に新しいテーマを追求し続けている、スリリングで意欲的な創作者であるからだ。僕が考えるところ、世の中には大きく分けて二種類の小説作家がいると思う。ひとつは作品をひとつひとつ系統的に積み重ね、いわば垂直的に進歩していく(あるいは進歩しようと試みている)作家であり、もうひとつはそのたびに異なったテーマや枠組みを取り上げて、自分を水平的に試しながら進歩していく(あるいは進歩しようと試みている)作家だ。僕自身はどちらかといえば前者に属すると思う(進歩を遂げていればいいと思う)。そしてイシグロはどちらかといえば後者に属しているようだ(間違いなく進歩を遂げている)。
『日の名残り』(一九八九)を書き上げたあとのイシグロは『充たされざる者』(一九九五)『わ
たしたちが孤児だったころ』(二〇〇〇)『わたしを離さないで』(二〇〇五)『忘れられた巨人』(二〇一五)と、そのたびに異なるフォーマットを持つ長備小説に次々に挑戦してきた。あるものはカフカ的な道具立てを用い、あるものは歴史ミステリーの衣を纏い、あるものはサイエンス・フィクションの構図を借用し、あるものは古代説話を下敷きにしている。まことに多種多様だ。
僕の知る限り、一人の作家がこれほど多様なスタイルを用いて小説を書くというのは、他にほとんど例を見ないことだ。そして僕の目からすれば驚くべきことに(というべきだろう)、どの作品も水準を軽々とクリアしている。
・そのような実験的な姿勢をポストモダン的手法のひとつととるか、あるいはあくまで個人的な方向性ととるかは、評価の分かれるところだろうが、僕としてはとりあえず「結果的にポストモダン的手法ともとれる、しかしあくまで個人的な営為」みたいなものではないかと考えている。そして彼の追求する自らのアイデンティティーの中には、彼の「内なる日本人性」みたいなものも間違いなく含まれているだろうし、そのことと彼の物語の「水平志向性」をどこかで結びつけて考えてみるのも、彼の文学を追究するための興味深いアプローチのひとつとなるかもしれない。
