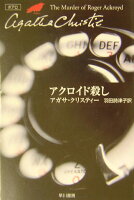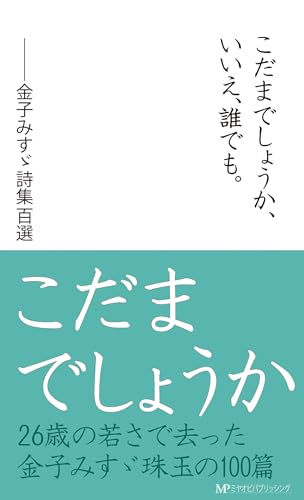綾鷹
@ayataka
読んだ本の内容を忘れちゃうので、自分の記録用...
- 2026年2月20日
 すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子おくるみ、産着、雪、骨、灰、白く笑う、米と飯……。生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの街と、朝鮮半島の記憶が交差する。朝鮮半島とワルシャワの街をつなぐ65の物語が捧げる、はかなくも偉大な命への祈り。 ハン・ガンさんの小説は初めて。 生と死とが色々な白いもので表現されていて、 読んでいる間、気持ちが冷たく静かな気持ちになった。 複数の種類の紙とフォントを使ってるのも素敵だった。 ◾️おくるみ 雪のように真っ白なおくるみに、さっき生まれたばかりの赤ん坊がしっかりとくるまれている。子宮はどこよりも狭くて温かい場所だから、急に広い空間に出てびっくりしてしまわぬようにと、看護師がきゅっと包んでくれたのだ。 たった今、肺での呼吸を始めたばかりの人。自分が誰で、ここがどこで、今始まったばかりのものが何なのかを知らない人。生まれたばかりの小鳥や子犬より無力な、どんな動物の赤ん坊よりもまだ稚い、いちばん稚い生きもの。 血をたくさん流したために青ざめた女が、泣いている赤ん坊の顔を見る。当惑しながら、おくるみごと赤ん坊を抱き取る。泣きやませるにはどうしたらいいのか、まだ知らない人。 さっきまで、肩じられないほどの痛みを経験していた人。赤ん坊がしばし泣きやむ。何かの匂いのためだろう。二人はまだつながっている。まだ見えていない赤ん坊の黒い目が、女の顔の方へー声のする方へと向く。何が始まったのかはわからないまま、まだ、二人はつながっている。血の匂いがする沈黙の中で、体と体の間に真っ白なおくるみをはさんで。 ◾️雪 ぼたん雪が黒いコートの袖に止まると、特別に大きな雪の結晶は肉眼でも見ることができる。正六角形の神秘的な形が少しずつ溶けて消えるまでにかかる時間はわずか一、二秒。 それを黙々と見つめる時間について、彼女は考える。 雪が降りはじめると、人々はやっていたことを止めてしばらく雪に見入る。そこがバスの中なら、しばらく顔を上げて窓の外を見つめる。音もなく、いかなる喜びも哀しみもなく、霏々として雪が舞い沈むとき、やがて数千数万の雪片が通りを黙々と埋めてゆくとき、もう見守ることをやめ、そこから顔をそらす人々がいる。 ◾️白く笑う 白く笑う、という表現は(おそらく)彼女の母国語だけにあるものだ。途方に暮れたように、寂しげに、こわれやすい清らかさをたたえて笑む顔。または、そのような笑み。 あなたは白く笑っていたね。 例えばこう書くなら、それは静かに耐えながら、笑っていようと努めていた誰かだ。 その人は白く笑ってた。 こう書くなら、(おそらく)それは自分の中の何かと訣別しようとして努めている誰かだ。 ◾️輝き 人間はなぜ、銀や金、ダイヤモンドのような、きらきらする鉱物を貴いと感じるのだろう?一説には、水のきらめきが古代の人々にとって生命を意味したからだという。輝く水はきれいな水だ。飲める水ー生命を与えてくれる水だけが透明なのだ。沙漠を、ブッシュを、汚い沼沢地帯を大勢でさまよったはてに、白く輝く水面を遠くに見出したときに彼らが感じたのは、刺すような喜びであったはずだ。生命であり、美であったはずだ。 ◾️沈黙 長かった一日が終わると、沈黙のための時間が必要だった。暖炉の火の前に座ったときにひとりでにそうなるように、沈黙のわずかなぬくもりにむかって、こわばっていた手をさしのべ、広げる時間が。 ◾️下の歯 お姉ちゃん(オンニ)、という発音は、赤ん坊の下の歯(アレンニ)というときに似ている。私の子の薄い歯ぐきから生え出た、初芽のような二つの小さな歯。 もう私の子は成長し、赤ん坊ではない。十二歳になったその子の首もとまでふとんを引き上げ、かけてやり、規則正しい息の音にしばらく耳を傾けてから、空いた机に戻る。 ◾️ 私の母国語で白い色を表す言葉に、「ハヤン(まっしろな)」と「ビン(しろい)」がある。綿あめのようにひたすら清潔な白「ハヤン」とは違い、「ヒン」は、生と死の寂しさをこもごもたたえた色である。私が書きたかったのは「ヒン」についての本だった。その本は、私の母が産んだ最初の赤ん坊の記憶から書き起こされるのでなくてはならないと、あのようにして歩いていある日、思った。二十二歳の母は一人で突然赤ん坊を生み、その女の子が息を引き取るまでの二時間、「死なないで、お願い」とささやきつづけていたという。
すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子おくるみ、産着、雪、骨、灰、白く笑う、米と飯……。生後すぐに亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの街と、朝鮮半島の記憶が交差する。朝鮮半島とワルシャワの街をつなぐ65の物語が捧げる、はかなくも偉大な命への祈り。 ハン・ガンさんの小説は初めて。 生と死とが色々な白いもので表現されていて、 読んでいる間、気持ちが冷たく静かな気持ちになった。 複数の種類の紙とフォントを使ってるのも素敵だった。 ◾️おくるみ 雪のように真っ白なおくるみに、さっき生まれたばかりの赤ん坊がしっかりとくるまれている。子宮はどこよりも狭くて温かい場所だから、急に広い空間に出てびっくりしてしまわぬようにと、看護師がきゅっと包んでくれたのだ。 たった今、肺での呼吸を始めたばかりの人。自分が誰で、ここがどこで、今始まったばかりのものが何なのかを知らない人。生まれたばかりの小鳥や子犬より無力な、どんな動物の赤ん坊よりもまだ稚い、いちばん稚い生きもの。 血をたくさん流したために青ざめた女が、泣いている赤ん坊の顔を見る。当惑しながら、おくるみごと赤ん坊を抱き取る。泣きやませるにはどうしたらいいのか、まだ知らない人。 さっきまで、肩じられないほどの痛みを経験していた人。赤ん坊がしばし泣きやむ。何かの匂いのためだろう。二人はまだつながっている。まだ見えていない赤ん坊の黒い目が、女の顔の方へー声のする方へと向く。何が始まったのかはわからないまま、まだ、二人はつながっている。血の匂いがする沈黙の中で、体と体の間に真っ白なおくるみをはさんで。 ◾️雪 ぼたん雪が黒いコートの袖に止まると、特別に大きな雪の結晶は肉眼でも見ることができる。正六角形の神秘的な形が少しずつ溶けて消えるまでにかかる時間はわずか一、二秒。 それを黙々と見つめる時間について、彼女は考える。 雪が降りはじめると、人々はやっていたことを止めてしばらく雪に見入る。そこがバスの中なら、しばらく顔を上げて窓の外を見つめる。音もなく、いかなる喜びも哀しみもなく、霏々として雪が舞い沈むとき、やがて数千数万の雪片が通りを黙々と埋めてゆくとき、もう見守ることをやめ、そこから顔をそらす人々がいる。 ◾️白く笑う 白く笑う、という表現は(おそらく)彼女の母国語だけにあるものだ。途方に暮れたように、寂しげに、こわれやすい清らかさをたたえて笑む顔。または、そのような笑み。 あなたは白く笑っていたね。 例えばこう書くなら、それは静かに耐えながら、笑っていようと努めていた誰かだ。 その人は白く笑ってた。 こう書くなら、(おそらく)それは自分の中の何かと訣別しようとして努めている誰かだ。 ◾️輝き 人間はなぜ、銀や金、ダイヤモンドのような、きらきらする鉱物を貴いと感じるのだろう?一説には、水のきらめきが古代の人々にとって生命を意味したからだという。輝く水はきれいな水だ。飲める水ー生命を与えてくれる水だけが透明なのだ。沙漠を、ブッシュを、汚い沼沢地帯を大勢でさまよったはてに、白く輝く水面を遠くに見出したときに彼らが感じたのは、刺すような喜びであったはずだ。生命であり、美であったはずだ。 ◾️沈黙 長かった一日が終わると、沈黙のための時間が必要だった。暖炉の火の前に座ったときにひとりでにそうなるように、沈黙のわずかなぬくもりにむかって、こわばっていた手をさしのべ、広げる時間が。 ◾️下の歯 お姉ちゃん(オンニ)、という発音は、赤ん坊の下の歯(アレンニ)というときに似ている。私の子の薄い歯ぐきから生え出た、初芽のような二つの小さな歯。 もう私の子は成長し、赤ん坊ではない。十二歳になったその子の首もとまでふとんを引き上げ、かけてやり、規則正しい息の音にしばらく耳を傾けてから、空いた机に戻る。 ◾️ 私の母国語で白い色を表す言葉に、「ハヤン(まっしろな)」と「ビン(しろい)」がある。綿あめのようにひたすら清潔な白「ハヤン」とは違い、「ヒン」は、生と死の寂しさをこもごもたたえた色である。私が書きたかったのは「ヒン」についての本だった。その本は、私の母が産んだ最初の赤ん坊の記憶から書き起こされるのでなくてはならないと、あのようにして歩いていある日、思った。二十二歳の母は一人で突然赤ん坊を生み、その女の子が息を引き取るまでの二時間、「死なないで、お願い」とささやきつづけていたという。 - 2026年2月20日
- 2026年2月19日
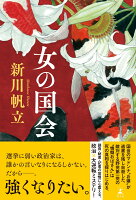 女の国会新川帆立選挙に弱い政治家は、 誰かの言いなりになるしかない。 だからーー。強くなりたい。 国会のマドンナ“お嬢”が遺書を残し自殺した。 敵対する野党第一党の“憤慨おばさん”は死の真相を探りはじめる。 議員・秘書・記者の覚悟に心震える、政治 大逆転ミステリ! ミステリーとしても、登場人物が権力に打ち勝つ物語としても、とても面白かった。 ミソジニーにも皮肉で返す、理不尽に見舞われても力強く乗り越える高月の姿はかっこよくて憧れる。 女性だったら大体の人はこの物語に出てくるような苦しみを味わっているのだろうか。 沢村が世の中全体を憎んでしまうシーン、間橋が自然に押さえ込んでいた苦しみ・無念さに気付くシーンは特に共感した。 今を生きている私たちの言動で世の中はもっとよくできると、理不尽なことがあっても諦めたくないという気持ちにさせてくれる物語だった。 そして、自分の想像が及ばないところで別の苦しみを抱えている人も必ずいるということを忘れないようにしたい。 ・「また、変な記事を書かれますよ。今日のうちにオンライン記事の一本や二本、出ちゃいま す」 沢村が声をひそめて言うと、高月はなぜか得意げな笑みを浮かべた。 「見出しはきっと、『憤慨おばさんVSウソ泣きお嬢女同士の対決の行方は?』とか、そういうのだよ。どうせ」 参議院議員のうち女性は二十五%程度、議院になると十%未満だ。女同士の対決というだけでニュースになる。 うんざりしながら沢村は言った。「女、女って、キワモノ扱いして、何かあればすぐに揚げ足をとってやろうと待ち構えている。減点法で、こきおろしてばっかり」 「仕方ないよ」 と、高月は屈託なく、白い歯を見せて笑った。 「それが民主主義だからさ」 高月は事務所に戻って荷物をつかむと、椅子に腰かける間もなく出ていった。 ・「あのおやじ、何度晩酌に付き合ってやったことか」足を放り出しながら高月が言った。「普段とれだけお愛想したって意味ないね。何かあると、情け容赦なく責任を押しつけてくるんだ から」 沢村はぼそりと言った。「ジェンダー的な見栄えって、一体何なのでしょう」「知らないよ。国民感情ってやつでしょ。世論調査するわけでもないのに。オッサン連中のメンツを、国民におっかぶせて代弁させているんだよ」 朝沼と高月、女同士の喧嘩として片づけられるのは、党として幸運なのだろうか。男が女をいじめるのはシャレにならないが、女が女をいじめるのはまだマシなのか。 胸のうちにもやもやとした感情が広がったが、それ以上口にすることはできなかった。高月は事態をより深刻にとらえているだろう。言っても仕方ないことを言って、ことさらに気分を害したくない。 ・それから二週間のうちに、事態はどんどん悪化した。 週刊誌は「十五年にわたる女の闘い嫉妬、陰口、裏切り」などと題して、高月と朝沼の間の確執を盛んに報じた。たいていは口論をしたとか悪口を言ったとか、その程度のものだ。 記事に嘘は含まれていなかったが、編集に悪意があった。 高月は相手を選ばず口論したし、他人について辛辣な意見を口にした。誰とでも喧嘩していたのである。朝沼との仲が特に悪かったわけではない。 「別にいいじゃん」 事務所で欠伸しながら、高月はあっけらかんと言った。 「もともと攻撃的な女、気の強い女ってイメージで悪く書かれていたんだし。でも考えてごらんよ。国会議員、特に議院議員なんて、男も女も、みんな気が強いよ。そうでなくちゃ、小選挙区選に勝てるわけないじゃん」 沢村は、せりあがる不満に蓋をすることができなかった。 「でも男の場合は扱いが違います。攻撃的でも気が強くても、リーダーシップがあるとか、いさというときに戦える男だとか、好意的に語られるわけでしょう」 「まあそうだけどさ。最近はこれでも、だいぶ良くなってきたんだよ。私が初当選したときの記事なんてひどかったよ。少し喧嘩しただけで、『黄色い声を張りあげて、紅い気炎を吐く」なんて書かれたもん。ヒステリックな女が男を焼き尽くすって印象を植えつけたいんだよ」 「印象操作ですか」 高月はにやりと笑った。「言論の自由だよ」 ・「こんな状況だからさ。県連を説得して、女性が公認を勝ちとるためには、党本部からの強いプッシュが必要なの。だけど党には通常、女性候補者を増やすインセンティブがない。女性はあくまでピンチヒッターなの。困ったときだけ、目新しい印象を与えたいときだけ、女性を入れればいい。残酷だけど、彼らの率直な感覚はそんなものよ」野党であれば、与党にはない新鮮さを印象づけるために女性候補者擁立をもくろむことがある。与党であれば、野党に惨敗したあとの選挙のときに、イメージ刷新目的で大量の女性候補者を擁立することがある。いずれにしても、ピンチヒッターにすぎない。 「私たち女性は、味変調味料ってことですか」沢村が言うと、高月はきょとんとした顔をした。 「味変調味料?」 「のり塩とか、ラー油とか、七味唐辛子とか。定番の味にちょっと加えて、目新しい印象をもたらすだけの存在。丼ぶりの具は何も変わらないのに」 ・「沢村ちゃんのお父さんは何をしている人?」 福森が訊いた。 「中学校の教師をしています。もうすぐ定年ですが」 「そうか。お堅いおうちなんだね。だから沢村ちゃんはしっかりしているのかな」 北海道の両親を思い浮かべた。 母親も中学校の教師をしていた。姉さん女房で、何をやらせてもしっかりこなす人だ。その世代では珍しく、産休育休を挟んですぐに復帰し、定年まで勤めあげた。だが福森は、沢村の母の職業を訊くことはなかった。 ・高月に生贄にされたのだ。 ちょうど若い女の子が秘書に入ったから、エロジジイにあてようと思ったに違いない。 県連からの推薦のため、党の公認のため、票のため。すべては高月が政治家であり続けるためだ。そのために沢村は差し出された。普段の仕事ぶりやロースクールで学んだことは関係ない。大事なのは、若い女性であるということだけ。 腹が立った。 だがその怒りは不思議と高月へ向かなかった。高月の着物姿が視界の端に入るたび、むしろ悲しくなった。 普段からパンツスーツと丸眼鏡で、女性性を感じさせない。国民からは「女を捨てたおばさん」とか「おじさんかと思った(笑)」といった言葉を浴びせられることもある。 そんな高月ですら、選挙がからむと女性性を前面に出して媚を売る。そこまでしないと勝てないからだ。 ーー秘書の仕事は、先生を選挙に勝たせることだ。 出柄が言っていたことの重みが深く胸に落ちてきた。 身体を差し出してまで、先生に勝たせるのが秘書の仕事だというのか。 やはりどうしようもなく腹が立った。高月に対してでもなく、福森に対してでもなく、世の中全体が憎いような気がした。 ・高月はどういう気持ちであの着物を選んだのだろう。どちらかといえば夏の模様だから、季節に合わせて選んだわけではないはずだ。 無愛想にしていれば女らしくないと言われ、女性らしくすれば女を使っていると言われる。 障害だらけの環境で、それでも負けじと泳いでいこうとする高月の決意があらわれている気が した。 議院の片隅でこっそりと泳ぐ鯉たち。 そこに自分を重ね、袖を通しているのではないか。 今はこうして愛想笑いを浮かべ、媚を売っている。だが自分は政治家なのだ、政治家であり続けるのだという決意表明である。決意をかたちにしておかないと、心が折れてしまう瞬間があるのかもしれない。 自分を奮い立たせながら、高月は戦ってきた。 一人でやってきたんだから、今回も一人でやってほしかった。同じ女だからって、沢村までまき込まないでほしい。そう思わないでもなかった。 だが高月は追い込まれていた。そういうときに頼れる人がいなかったらどうなっていただろう。 ・新聞社、通信社に占める女性の割合は二割強にすぎない。「記者」とは呼ばれない。いつも「女性記者」だ。女であるだけで目立つ。特オチなんてしてしまった日には男性記者の何倍も冷たい視線が向けられてしまう。 特ダネをとってやろうという意気込みはわいてこない。目立たぬように、波風を立てず、つつがなく仕事をこなすのに精いっぱいだった。 ・たしなめるように言いながらも、脳裏には、口元を歪めて笑う顕造の顔が浮かんでいた。戦後日本の政治のと真ん中を歩いてきた、典型的な男性政治家だ。権力を振りかざし、我を通して、仲間内で利権を分け合う。自分たちが何を踏みつけているのか、意識をすることもない。 打ち倒さなくてはならない、と唐突に思った。 踏みつけられるのはもう嫌だった。 ・「あなた、なんでそんなに自分の実力を否定するの?」高月はじっと目を見つめてきた。その眼力の強さにたじろと。 「なんでか分かるよ。あててやろうか。戦うのが怖いからでしょ。圧倒的に不利な男社会で前に出たところで、濃されるに決まっている。本当は実力があるのに性差別のせいでそれが発算できない。そんな理不尽を目の前にしたら苦しい。だから、実力を下方修正する。自分はもともと栄光に触しない人間なんだと思い込むことで、自分の心を守っている。そうでしょう」 ・テーブルの上に視線を落とした。何と答えていいか分からなかった。 嫌われるのが怖くて、選挙カーを避けているわけではない。自分がされて嫌だったことを、他人にしたくないだけだ。 だけど、嫌だったことは他にもたくさんある。男性と比べても、女性アナウンサーばかり外見に言及されて、「テレビの顔」「職場の華」という扱いを受けていたこと。どんなにまっとうなことを言っても、「主婦が言っている」というだけで軽んじられ、誰にも聞いてもらえないこと。議員になってなお、下働きは当然のように女性にまわってきて、目立つ部分は男性議員がかっさらっていくこと。女だって働いていいけど、家庭のこともきちんとしてよね、という風潮。 自分を取り囲むピースが、自分のかたちを決めてしまっている。世間の扱いが先にきて、わずかに残ったすき間に、身体を無理やり合わせておさまっている。間橋は柔らかかった。周りに合わせることが苦痛ではなかった。少なくとも自分ではそう思っていた。だけど本当は、苦しかったのかもしれない。 ・首相になんてなれるわけないでしょ、と言いそうになったが、やめた。きっと夫は、みゆきなら大丈夫だよ、と返してくる。 自分は首相になれないって、どうして思ったんだろう。女だから?政治家の家系じゃないから?人生はあと何十年もあるのに。どうして最初からあきらめていたんだろう。 日本で女性首相が生まれたことはない。 百年以上前から、百回以上組閣されているのに。女性首相はゼロだ。ネットで内閣総理大臣と検索すると、おじさんたちの写真がずらりと並ぶ。男、男、男、男・•・・・・スクロールしても、しても、男の写真しか出てこない。 これがどれだけ異様なことか、気持ちの悪いことか、どうして今まで気づかなかったのだろう。 女は怒っていい。こんなのおかしいと言っていい。 百年後の女の子たちには、「そんなひどい時代があったのか」と驚いてほしい。その頃にはきっと、今よりマシな現実があるはずだから。 ・勢いづいたように、兵頭首相は続けた。 「どうか加賀美君を、皆さんの力で、国会に送ってやってください。加賀美君を、男にしてやってください」 四人の女たちは、茫然と立ち尽くしていた。 しかし誰からともなく顔を見合わせた。 「男にしてやってください、だってさ」高月はニヤッと笑った。「女の国会議員は何なんだって話だよ」 間橋は苦笑いしながら言った。 「ほんとですよね。今の加賀美さんは男じゃないのかって感じですし」 選挙カーの脇では、「妻です」「娘です」と太字のタスキをかけた女性たちがしきりに頭をさげていた。 兵頭首相は、がなるように演説を続けている。 「・・・・・・・私は、加賀美君に尋ねました。男子一生の仕事に身をささげる覚悟はあるか、と。加賀美君は答えた。この身が朽ち果てようとも、日本の堆肥となるのであれば本懐です、と。ここまで言いきる男はあっぱれだ。是が非でも勝たせてやらなければ、私の男の沽券にも関わる。 しかしね、外ではこれほど堂々としている加賀美君も、一旦家に入ると奥様に頭があがらず、靴下一つ買うにも決裁が必要なんだそうです。考えてみてください。三百円も自分で使えない。これほど金に綺麗な男がおりますでしょうか」 群衆から笑いがもれた。 「こんな演説でも、刺さる人には刺さるんだもんな」高月がしみじみと言った。「男になったとか、男子一生の仕事だとか、男の沽券とか、本懐とか。何でもいいけど。男の人って結構、スピリチュアルが好きだよね」 ハンディカメラを持っていた和田山がくすりと笑った。 ・「大丈夫なの?」 「はい」表情は引きしまり、顔に生気が戻っている。「生卵にはびっくりしたけど、こんな記事まで拡散されちゃうと、逆にやってやるぞという気になってきました。私が梅命にしたことは、ただの親切、手助けです。それをこんなふうに書かれて。政治家として議席を争う場面で、女というだけで足を引っ張られる。女が政治の場に出ていくのが我慢ならない人たちが、どういうわけか、いるようですね。そういう人たちを利用して、加賀美さんが私を叩きのめそうとしている。このまま負けたら相手の思うつぼって感じで、悔しくってたまらないですよ」支援者によりそわれながら、間橋は事務所を出ていった。 ・「あなたには分からないでしょうね。どうしてこんなに面倒なことをするのか。でもね、答えはこのノートにそのまま書いてある。僕は首相になりたかった。だけど、この国で、トランスジェンダーは首相になれない。これは誰が何と言おうと、動かぬ現実です。人口の半分を占める女性の首相すら、一人も生まれていないんですよ。いわんや、性的マイノリティが首相なんて、まず無理です。そういうトップが誕生する未来がありえるとしても、何十年先になるんでしょうか。性同一性障害を公表したら、選挙に通るのも難しくなる。仮に、数限りない誹謗中傷を乗りこえて、票をかき集め、なんとか当選したとしても、シスヘテロ男性が支配する永田町で勝ちあがることはできません。普通の男だったら気にすることもない障害が次々と降りかかる。つまりそういうことです。差別というのは」 ・何と言っていいか、分からなかった。 顕太郎が感じている痛みは、想像できた。高月のような女性も、同じように感じることが多いからだ。「普通の男」なら経験しないような障害が、毎日毎日、何十年も降りかかる。それにめげてしまうと「女の人は長続きしない」「出世する気がない」「意欲がない」「適性がない」と、個人の資質のせいにされる。女であるだけで、有権者に嫌われることもある。 だが軽々に「あなたの気持ちが分かる」と言うこともできなかった。 直面する障害の重さも、数も、顕太郎の場合は、比べ物にならないだろうから。 「僕が愚かだったんですよ」 唐突に、顕太郎が言った。 「朝沼さんが、彼女が分かってくれたから。期待してしまったんだ。他の人も分かってくれるかもしれないと。自分がマイノリティであることを公表したくなった。気持ちの整理をつけるためにその手記を書いた」
女の国会新川帆立選挙に弱い政治家は、 誰かの言いなりになるしかない。 だからーー。強くなりたい。 国会のマドンナ“お嬢”が遺書を残し自殺した。 敵対する野党第一党の“憤慨おばさん”は死の真相を探りはじめる。 議員・秘書・記者の覚悟に心震える、政治 大逆転ミステリ! ミステリーとしても、登場人物が権力に打ち勝つ物語としても、とても面白かった。 ミソジニーにも皮肉で返す、理不尽に見舞われても力強く乗り越える高月の姿はかっこよくて憧れる。 女性だったら大体の人はこの物語に出てくるような苦しみを味わっているのだろうか。 沢村が世の中全体を憎んでしまうシーン、間橋が自然に押さえ込んでいた苦しみ・無念さに気付くシーンは特に共感した。 今を生きている私たちの言動で世の中はもっとよくできると、理不尽なことがあっても諦めたくないという気持ちにさせてくれる物語だった。 そして、自分の想像が及ばないところで別の苦しみを抱えている人も必ずいるということを忘れないようにしたい。 ・「また、変な記事を書かれますよ。今日のうちにオンライン記事の一本や二本、出ちゃいま す」 沢村が声をひそめて言うと、高月はなぜか得意げな笑みを浮かべた。 「見出しはきっと、『憤慨おばさんVSウソ泣きお嬢女同士の対決の行方は?』とか、そういうのだよ。どうせ」 参議院議員のうち女性は二十五%程度、議院になると十%未満だ。女同士の対決というだけでニュースになる。 うんざりしながら沢村は言った。「女、女って、キワモノ扱いして、何かあればすぐに揚げ足をとってやろうと待ち構えている。減点法で、こきおろしてばっかり」 「仕方ないよ」 と、高月は屈託なく、白い歯を見せて笑った。 「それが民主主義だからさ」 高月は事務所に戻って荷物をつかむと、椅子に腰かける間もなく出ていった。 ・「あのおやじ、何度晩酌に付き合ってやったことか」足を放り出しながら高月が言った。「普段とれだけお愛想したって意味ないね。何かあると、情け容赦なく責任を押しつけてくるんだ から」 沢村はぼそりと言った。「ジェンダー的な見栄えって、一体何なのでしょう」「知らないよ。国民感情ってやつでしょ。世論調査するわけでもないのに。オッサン連中のメンツを、国民におっかぶせて代弁させているんだよ」 朝沼と高月、女同士の喧嘩として片づけられるのは、党として幸運なのだろうか。男が女をいじめるのはシャレにならないが、女が女をいじめるのはまだマシなのか。 胸のうちにもやもやとした感情が広がったが、それ以上口にすることはできなかった。高月は事態をより深刻にとらえているだろう。言っても仕方ないことを言って、ことさらに気分を害したくない。 ・それから二週間のうちに、事態はどんどん悪化した。 週刊誌は「十五年にわたる女の闘い嫉妬、陰口、裏切り」などと題して、高月と朝沼の間の確執を盛んに報じた。たいていは口論をしたとか悪口を言ったとか、その程度のものだ。 記事に嘘は含まれていなかったが、編集に悪意があった。 高月は相手を選ばず口論したし、他人について辛辣な意見を口にした。誰とでも喧嘩していたのである。朝沼との仲が特に悪かったわけではない。 「別にいいじゃん」 事務所で欠伸しながら、高月はあっけらかんと言った。 「もともと攻撃的な女、気の強い女ってイメージで悪く書かれていたんだし。でも考えてごらんよ。国会議員、特に議院議員なんて、男も女も、みんな気が強いよ。そうでなくちゃ、小選挙区選に勝てるわけないじゃん」 沢村は、せりあがる不満に蓋をすることができなかった。 「でも男の場合は扱いが違います。攻撃的でも気が強くても、リーダーシップがあるとか、いさというときに戦える男だとか、好意的に語られるわけでしょう」 「まあそうだけどさ。最近はこれでも、だいぶ良くなってきたんだよ。私が初当選したときの記事なんてひどかったよ。少し喧嘩しただけで、『黄色い声を張りあげて、紅い気炎を吐く」なんて書かれたもん。ヒステリックな女が男を焼き尽くすって印象を植えつけたいんだよ」 「印象操作ですか」 高月はにやりと笑った。「言論の自由だよ」 ・「こんな状況だからさ。県連を説得して、女性が公認を勝ちとるためには、党本部からの強いプッシュが必要なの。だけど党には通常、女性候補者を増やすインセンティブがない。女性はあくまでピンチヒッターなの。困ったときだけ、目新しい印象を与えたいときだけ、女性を入れればいい。残酷だけど、彼らの率直な感覚はそんなものよ」野党であれば、与党にはない新鮮さを印象づけるために女性候補者擁立をもくろむことがある。与党であれば、野党に惨敗したあとの選挙のときに、イメージ刷新目的で大量の女性候補者を擁立することがある。いずれにしても、ピンチヒッターにすぎない。 「私たち女性は、味変調味料ってことですか」沢村が言うと、高月はきょとんとした顔をした。 「味変調味料?」 「のり塩とか、ラー油とか、七味唐辛子とか。定番の味にちょっと加えて、目新しい印象をもたらすだけの存在。丼ぶりの具は何も変わらないのに」 ・「沢村ちゃんのお父さんは何をしている人?」 福森が訊いた。 「中学校の教師をしています。もうすぐ定年ですが」 「そうか。お堅いおうちなんだね。だから沢村ちゃんはしっかりしているのかな」 北海道の両親を思い浮かべた。 母親も中学校の教師をしていた。姉さん女房で、何をやらせてもしっかりこなす人だ。その世代では珍しく、産休育休を挟んですぐに復帰し、定年まで勤めあげた。だが福森は、沢村の母の職業を訊くことはなかった。 ・高月に生贄にされたのだ。 ちょうど若い女の子が秘書に入ったから、エロジジイにあてようと思ったに違いない。 県連からの推薦のため、党の公認のため、票のため。すべては高月が政治家であり続けるためだ。そのために沢村は差し出された。普段の仕事ぶりやロースクールで学んだことは関係ない。大事なのは、若い女性であるということだけ。 腹が立った。 だがその怒りは不思議と高月へ向かなかった。高月の着物姿が視界の端に入るたび、むしろ悲しくなった。 普段からパンツスーツと丸眼鏡で、女性性を感じさせない。国民からは「女を捨てたおばさん」とか「おじさんかと思った(笑)」といった言葉を浴びせられることもある。 そんな高月ですら、選挙がからむと女性性を前面に出して媚を売る。そこまでしないと勝てないからだ。 ーー秘書の仕事は、先生を選挙に勝たせることだ。 出柄が言っていたことの重みが深く胸に落ちてきた。 身体を差し出してまで、先生に勝たせるのが秘書の仕事だというのか。 やはりどうしようもなく腹が立った。高月に対してでもなく、福森に対してでもなく、世の中全体が憎いような気がした。 ・高月はどういう気持ちであの着物を選んだのだろう。どちらかといえば夏の模様だから、季節に合わせて選んだわけではないはずだ。 無愛想にしていれば女らしくないと言われ、女性らしくすれば女を使っていると言われる。 障害だらけの環境で、それでも負けじと泳いでいこうとする高月の決意があらわれている気が した。 議院の片隅でこっそりと泳ぐ鯉たち。 そこに自分を重ね、袖を通しているのではないか。 今はこうして愛想笑いを浮かべ、媚を売っている。だが自分は政治家なのだ、政治家であり続けるのだという決意表明である。決意をかたちにしておかないと、心が折れてしまう瞬間があるのかもしれない。 自分を奮い立たせながら、高月は戦ってきた。 一人でやってきたんだから、今回も一人でやってほしかった。同じ女だからって、沢村までまき込まないでほしい。そう思わないでもなかった。 だが高月は追い込まれていた。そういうときに頼れる人がいなかったらどうなっていただろう。 ・新聞社、通信社に占める女性の割合は二割強にすぎない。「記者」とは呼ばれない。いつも「女性記者」だ。女であるだけで目立つ。特オチなんてしてしまった日には男性記者の何倍も冷たい視線が向けられてしまう。 特ダネをとってやろうという意気込みはわいてこない。目立たぬように、波風を立てず、つつがなく仕事をこなすのに精いっぱいだった。 ・たしなめるように言いながらも、脳裏には、口元を歪めて笑う顕造の顔が浮かんでいた。戦後日本の政治のと真ん中を歩いてきた、典型的な男性政治家だ。権力を振りかざし、我を通して、仲間内で利権を分け合う。自分たちが何を踏みつけているのか、意識をすることもない。 打ち倒さなくてはならない、と唐突に思った。 踏みつけられるのはもう嫌だった。 ・「あなた、なんでそんなに自分の実力を否定するの?」高月はじっと目を見つめてきた。その眼力の強さにたじろと。 「なんでか分かるよ。あててやろうか。戦うのが怖いからでしょ。圧倒的に不利な男社会で前に出たところで、濃されるに決まっている。本当は実力があるのに性差別のせいでそれが発算できない。そんな理不尽を目の前にしたら苦しい。だから、実力を下方修正する。自分はもともと栄光に触しない人間なんだと思い込むことで、自分の心を守っている。そうでしょう」 ・テーブルの上に視線を落とした。何と答えていいか分からなかった。 嫌われるのが怖くて、選挙カーを避けているわけではない。自分がされて嫌だったことを、他人にしたくないだけだ。 だけど、嫌だったことは他にもたくさんある。男性と比べても、女性アナウンサーばかり外見に言及されて、「テレビの顔」「職場の華」という扱いを受けていたこと。どんなにまっとうなことを言っても、「主婦が言っている」というだけで軽んじられ、誰にも聞いてもらえないこと。議員になってなお、下働きは当然のように女性にまわってきて、目立つ部分は男性議員がかっさらっていくこと。女だって働いていいけど、家庭のこともきちんとしてよね、という風潮。 自分を取り囲むピースが、自分のかたちを決めてしまっている。世間の扱いが先にきて、わずかに残ったすき間に、身体を無理やり合わせておさまっている。間橋は柔らかかった。周りに合わせることが苦痛ではなかった。少なくとも自分ではそう思っていた。だけど本当は、苦しかったのかもしれない。 ・首相になんてなれるわけないでしょ、と言いそうになったが、やめた。きっと夫は、みゆきなら大丈夫だよ、と返してくる。 自分は首相になれないって、どうして思ったんだろう。女だから?政治家の家系じゃないから?人生はあと何十年もあるのに。どうして最初からあきらめていたんだろう。 日本で女性首相が生まれたことはない。 百年以上前から、百回以上組閣されているのに。女性首相はゼロだ。ネットで内閣総理大臣と検索すると、おじさんたちの写真がずらりと並ぶ。男、男、男、男・•・・・・スクロールしても、しても、男の写真しか出てこない。 これがどれだけ異様なことか、気持ちの悪いことか、どうして今まで気づかなかったのだろう。 女は怒っていい。こんなのおかしいと言っていい。 百年後の女の子たちには、「そんなひどい時代があったのか」と驚いてほしい。その頃にはきっと、今よりマシな現実があるはずだから。 ・勢いづいたように、兵頭首相は続けた。 「どうか加賀美君を、皆さんの力で、国会に送ってやってください。加賀美君を、男にしてやってください」 四人の女たちは、茫然と立ち尽くしていた。 しかし誰からともなく顔を見合わせた。 「男にしてやってください、だってさ」高月はニヤッと笑った。「女の国会議員は何なんだって話だよ」 間橋は苦笑いしながら言った。 「ほんとですよね。今の加賀美さんは男じゃないのかって感じですし」 選挙カーの脇では、「妻です」「娘です」と太字のタスキをかけた女性たちがしきりに頭をさげていた。 兵頭首相は、がなるように演説を続けている。 「・・・・・・・私は、加賀美君に尋ねました。男子一生の仕事に身をささげる覚悟はあるか、と。加賀美君は答えた。この身が朽ち果てようとも、日本の堆肥となるのであれば本懐です、と。ここまで言いきる男はあっぱれだ。是が非でも勝たせてやらなければ、私の男の沽券にも関わる。 しかしね、外ではこれほど堂々としている加賀美君も、一旦家に入ると奥様に頭があがらず、靴下一つ買うにも決裁が必要なんだそうです。考えてみてください。三百円も自分で使えない。これほど金に綺麗な男がおりますでしょうか」 群衆から笑いがもれた。 「こんな演説でも、刺さる人には刺さるんだもんな」高月がしみじみと言った。「男になったとか、男子一生の仕事だとか、男の沽券とか、本懐とか。何でもいいけど。男の人って結構、スピリチュアルが好きだよね」 ハンディカメラを持っていた和田山がくすりと笑った。 ・「大丈夫なの?」 「はい」表情は引きしまり、顔に生気が戻っている。「生卵にはびっくりしたけど、こんな記事まで拡散されちゃうと、逆にやってやるぞという気になってきました。私が梅命にしたことは、ただの親切、手助けです。それをこんなふうに書かれて。政治家として議席を争う場面で、女というだけで足を引っ張られる。女が政治の場に出ていくのが我慢ならない人たちが、どういうわけか、いるようですね。そういう人たちを利用して、加賀美さんが私を叩きのめそうとしている。このまま負けたら相手の思うつぼって感じで、悔しくってたまらないですよ」支援者によりそわれながら、間橋は事務所を出ていった。 ・「あなたには分からないでしょうね。どうしてこんなに面倒なことをするのか。でもね、答えはこのノートにそのまま書いてある。僕は首相になりたかった。だけど、この国で、トランスジェンダーは首相になれない。これは誰が何と言おうと、動かぬ現実です。人口の半分を占める女性の首相すら、一人も生まれていないんですよ。いわんや、性的マイノリティが首相なんて、まず無理です。そういうトップが誕生する未来がありえるとしても、何十年先になるんでしょうか。性同一性障害を公表したら、選挙に通るのも難しくなる。仮に、数限りない誹謗中傷を乗りこえて、票をかき集め、なんとか当選したとしても、シスヘテロ男性が支配する永田町で勝ちあがることはできません。普通の男だったら気にすることもない障害が次々と降りかかる。つまりそういうことです。差別というのは」 ・何と言っていいか、分からなかった。 顕太郎が感じている痛みは、想像できた。高月のような女性も、同じように感じることが多いからだ。「普通の男」なら経験しないような障害が、毎日毎日、何十年も降りかかる。それにめげてしまうと「女の人は長続きしない」「出世する気がない」「意欲がない」「適性がない」と、個人の資質のせいにされる。女であるだけで、有権者に嫌われることもある。 だが軽々に「あなたの気持ちが分かる」と言うこともできなかった。 直面する障害の重さも、数も、顕太郎の場合は、比べ物にならないだろうから。 「僕が愚かだったんですよ」 唐突に、顕太郎が言った。 「朝沼さんが、彼女が分かってくれたから。期待してしまったんだ。他の人も分かってくれるかもしれないと。自分がマイノリティであることを公表したくなった。気持ちの整理をつけるためにその手記を書いた」 - 2026年2月18日
 感情労働の未来恩蔵絢子◾️未来の感情労働 ・共感をした上で切り離す、そして表層だけではないものを見る、そんな、本当に人を理解する感情労働とはどういうもので、どうしたら可能なのだろうか? 今までにいくつかヒントは出てきていた。他者と自分を切り離す良い感情労働としては、例えば異文化の人に慣れない見た目の料理を出す研究で見たように、(1)人に優しくできなくなったら、自分の抱えている荷物を下ろす。またインストルメンタル・コンバージェンスの例で見たように、(2)自分と感じ方や考え方が違う人と関わる際には、食事など根本的な要求については一緒にすることができ、それが満たされればとりあえず十分であると考える。また依存関係の例で見たように、(3)自分から「待つ」という痛みを取る。「好き」は「欲しい」に圧倒されて消えていくので、強い風で小さな火が消えないように両手で守るように、自分と相手の間に空間を作る。 そしてトランザクティブ・メモリーの例で見たように、(4)相手の良いところ(自分に直接利益となるところ)だけではなくて、悪いところ(自分の不利益になるところ)も含めて、全人格で関わる。そして日本人の癖として見たように、(5)相手や集団を大事にしすぎて、自分の「助けて」という気持ちを消さないようにする、などが考えられるだろう。 基本的には、「こうでなくてはならない」ということで他人と関わるのではなく、もっとりラックスして、自分と他人に余裕を与える。自分と違う相手に本当に興味を持つということになるのだろう。 ・どんな課題にも対応できる流用的知性(1Q)だけでは人間の知性は説明し尽くせず、っひとつの課題に特定的に驚くべき力を発揮する人たちがいるとして、1983年アメリカの心理学者ハワード・ガードナーは「多重知能理論」を発表した。これによれば少なくとも人間には8種類の異なる知能があるという。(1)言語的知能、(2)論理・数学的知能、(3)空間的知能、(4)身体・運動感覚的知能、(5)音楽的知能、(6)博物的知能、加えて(7)対人的知能と(8)内省的知能である。 ・感情の欠点は、感情は正解のないところでも、私たちに意思決定をさせてくれる能力であり、言い方を変えれば、差がないところに差をつける力、理由なく一方を好ませるものであって、すなわち偏見を生む力にもなっている。また、初めてのことに出合って感情のシステムが大きく動く(例えば強い恐怖を感じる)ことで、記憶のシステムに刺澈が行き、絶対に忘れられない記憶を形成することも述べた。このシステムのおかげで次に似たような恐怖には出合わないように行動を変えることができるのだが、これは、少しでも似た状況になると体が硬直してしまう、危険の全くないところでも危険を感じ、何もかもが怖くなるというPTSDの要因でもある。もちろんこれは感情の矢点である。 さらに感情は他者との関係性で問題になるところがある。情動的共感で私たちは他者としっかり結びつくことができるのだが、そのせいで切り離しが難しくなり、自分の延長として他者を提えモノとして扱ってしまったり、虐待をしてしまったり、また自分をモノとして扱うという問題が生じる。 同調圧力もこの仕組みと関係する。この人が本当に大切なことを言っているのかどうか、私たちは自分で考えずに、なんとなくの雰囲気だけで肩じてしまうことがある。そして同じ感情を感じていない人のことを付き合いにくいと感じたり、「空気が読めない人」と言って仲間はずれにしたりすることがある。脳が典型的な発達とは違った発達をしていたり、違う文化的背景で育ったりした人が、均一を前提とした社会に入ると、感情が伝わるのに時間がかかることがある。感情は伝染することで、伝わる速さを手がかりに、仲間とそうでない人を分ける圧力になってしまうのだ。 感情は我々の根本なのだが、大きな力であるがゆえに、長所が点にあっという間に変わる。 感情にはどうしても手入れが必要になる。ここで鍵となるのが「気づき」なのである。 ・人を本当に理解するのには、物事の因果関係を簡単に考えてはいけない。「そうではないかもしれないな」と判断を保留しなくてはならない。感情は常に動かしていなければならない。 その動いている感情を掘むにとどめ、型に入れないことが感情的知性なのである。 ・自分の気持ちに気づきうまく表現することによってポジティブな感情を増大させて、ネガティブな感情を減少させることができる。 「感情表現(emotional expressivity)」は感情と気づきがセットになった一つの感情的知性である。 「表現」というのは面白い技術だ。表層演技のように「抑制」ばかりをするのではなく、自分が本当に今感じていることはどういうことなのかに気がついて、表現することが大事なのである。 ・何か条件が変わったら、こだわらずに違うプランを考えられる力を「認知的柔軟性(cognitive Rexiblity)」と呼ぶ。感情表現だけでなく、この力によっても、人生の中に喜びを増やし、悲しみを減らすことができるわけである。 ・ここで、人間の能力を私なりに整理してみよう。 大脳新皮質には大きく分けて3つのネットワークがある。一つ目は、言語能力やIQ、すなわち「頭がいい」と通常言われるような能力、テキパキと物事をなんでもこなせ、大きな短期記憶(今この場で何か課題を実行するために、必要な情報を集め、一時的に蓄えておく力、容量)を持ち、人と長く雑談している時も自分が何を言いたかったのか決して見失わないような能力を担当するシステムで、「セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(centralexecutive network)」と呼ば はいがいそくぜんとうぜんや れている。セントラル・エグゼクティブ・ネットワークは、背外側前頭野や後頭頂皮質という大脳新皮質の外側にある領域が主に形成している。 その他に、「デフォルト・モード・ネットワーク」と、「サリエンス・ネットワーク (saliencenetwork)」が存在する。デフォルト・モード・ネットワークは、セントラル・エグゼクティブ・ネットワークとは正反対の働きをしていて、人間が何にも集中しておらず、本当にリラックスしている時に活動が高まる脳領域である。内能頭前野や後説帯状という、大脳新皮質の内側に位置する領域からなっている。 デフォルト・モード・ネットワークは、集中とは正反対で、白昼夢のように、心があちこち術衛っている状態を作り出し、ぼーっとああでもない、こうでもない、とセントラル・エグゼクティブ・ネットワークを駆使していた時に体験したことを整理している脳部位である。シャワーを浴びたり、散歩をしたり、私たちが休憩していて特別に何にも集中していないからこそ、記憶の整理はできるのであり、こうして知らないうちに体験を整理してくれることで、私たちは再び効率的に動けるようになるのである。 そしてサリエンス・ネットワークは、セントラル・エグゼクティブ・ネットワークとデフォルト・モード・ネットワークの切り替えをしている脳領域である。何か注目すべきことが起こった時に、ぼんやりしていないでセントラル・エグゼクティブ・ネットワークを働かせろと命令してくるシステムだ。島皮質や前部帯状回という、痛みなどの強い感情の伝染を司っていた回路で、皆戒号を送る回路でもある。不安を感じやすく、この部位がいつも過剰に働き続けている人は、安らげないためデフォルト・モード・ネットワークをうまく働かせることができず、結局セントラル・エグゼクティブ・ネットワークの働きも落ちて、柔軟に物事を考えることが苦手になることが知られている。 サリエンス・ネットワークの中の島皮質は特に面白い領域である。痛みを感じている時に働く脳部位だと言ったが、芸術作品など理由もわからず何かを私たちが美しいと感じている時に働く脳部位でもあり、身体や内臓の感覚をまとめあげ、感じる時、島皮質が活動すると言われている。身体で起こっていることの自覚をする部位が島皮質なのだ。「失感情症(alexithymia)」といって、自分の感情を認識できず、言語化することが苦手な人たちがいる。この人たちは、この島皮質と展体の体積が、小さくなっていることが知られている。 仏教の瞑想のトレーニングが、私たちの内なる感覚や、外の世界の出来事に気づきを高める「マインドフルネス(mindfulness)」として広まっている。過剰に物事に反応せず、良い悪いとすぐに決めつけず、判断を保留にして気づくにとどめ、その観察力に基づいて行動をする「マインドフル」な人たちは、失感情症の人たちとは逆で、島皮質と扁桃体の体積が大きいことがわかっている。 私たちは、IQばかりを気にしてきた時間が長かったが、やりたいと思うことを適切に実行できることの背景には、私たちの知らないところで行われているデフォルト・モード・ネットワークの処理と、深い身体からの知らせに気づくサリエンス・ネットワークの処理がある。 外から龍力として目につきやすい、光り輝く部分ばかりを私たちは大事にするが、目に見えにくいところで行われている処理が光の部分を支えているのであり、時に私たちはその無意識の処理に目を向けなくてはならないのだ。目に見えにくい自分の欲求、他人の欲求、そして人間だけでなく、人間が支えられている環境の中の複雑すぎるつながりに少しずつ気づいていくことが、自分自身を取り戻す、人を理解する感情労働であると言える。 ・意識されている物事の中で、「こうなったのはこのせいだ」と私たちは理由を見つけようとするが、私たちには、どうにもコントロールの及ばない、無意識というものがあり、せいぜい そのうちの少しに気づくことができるだけなのかもしれない、という視点を持つことは大切だ。 全てがコントロールできるわけではないのだ。 言語化されたものだけをみるのではなく、コントロールできないものの動きを感じてみる。 見かけの因果関係に騙されずに、感情的知性を使って、見えない心の広がりを感じてみる。 グッドハートの法則のように、「偏差値」「売上」「どれだけ「いいね」がつくか」というわかりやすい尺度に自分をあてはめず、本当にやりたいことをやってみる。自分の小さな感想を表現してみる。見た目だけを重要視しないで、感じていることを掴む努力をする。自分と同じと考えないで他人に興味を持つ。他人の小さな「好き」を守れるように、風よけの手を差し出す。このような感情の働かせ方を通して、社会的な正解・不正解に従って、みんながみんな同じ人間にならねばならないかのような苦しさからは解放されるのかもしれない。人間の心は、均質なもの、動きのないものなどではなく、いかに広大か。人間の心の広大さを知ることこそが、私たちの息苦しさや耐えがたさを減らす方法だと思う。 全てがコントロールできるという勘違いから離れ、コントロールが利かない世界の中で、時々ある「気づき」を大切にする。それだけで良いのかもしれない。 人間が人間と付き合う価値は、人間の動く心がわかるようになることに尽きるのだろう。 ◾️おわりに ・ここまで感情労働について考えてきたが、感情労働は、他人のために自分の本当の感情を犠牲にするところがあるという意味では「利他性」の考察が必要である。最後にそれを考えたい。 自分を犠牲にしてまで、他人のために動く、という利他性の起源はどこにあるのか。 通常、血縁関係にあるものを助けるためには、自分の身を危険に晒すことは意味があるとされる。なぜなら、自分の子どもやきょうだいが生き残れば、自分の遺伝子が残るのだから。これは「利他性の血縁選択説(kin selection)」である。また、血縁関係になくとも、自分を今危険に晒して相手を助けることで、将来相手から自分を助けてもらえる可能性がある場合は、利他行動に出る意味があるとされる。これは「互恵的利他主義(reciprocal altruism)」である。 しかし、人間の社会で現れている利他性を説明するのに、血縁選択説と互恵的利他主義だけでは不十分として、アメリカの心理学者レダ・コスミデスらは、「かけがえのなさ(irreplaceability)」を導入している。 ・コスミデスらによると、平常時には自分に大きな利益をもたらす人同士で元気に交流していればいいだろうが、私たちが狩猟採集民だったとすると、狩りの時に怪我をしたり、敵から攻撃されたり、病気をしたりということは頻繁にあって、困った時には、平常時に優しかった人が自分を助けてくれるとは限らないという。相手にとっての自分の価値が低くなってしまったからである。それゆえに困った時にも、他者の援助を引きつける能力が我々には必要で、そのために、自分の他には代わりがいないということを人にわかってもらおうとして、他人に評価される自分だけの特徴を見つけようとしたり、技術・習慣・属性などを獲得しようと力を尽くしたり、実力はなくとも他者に自分がかけがえのない存在であることを肩じさせようと嘘をついたり、倍じてくれる人がいなければ自分を必要としてくれる社会的グループを求めて居場所を移していったり、同じグループ内で自分と同じような能力を持つ個体にはやきもちを焼いたり、といった人間社会でよく観察される行動が現れてきたのだという。 かけがえのなさということを考えると、人間には無限の種類の価値があることになる。なぜなら、相性の問題があるからだ。このグループには、りんごが溢れていて、私の持っているりんごは価値がないけれども、りんごのない土地に行けば、私の持っているりんごは欲してもらえることになる。自分にないものを持っている人が素敵に見える。人によって素敵に見えるものは変わってくる。みんな同じものを持っていなければならないのではなく、他人を助ける動機はさまざまになる。そして他人に対する感情もさまざまになる。 そして昔は自分が危機に陥ることはかなりの頻度であったので、正真正銘の困った時に助けてくれる友がどの人かは感じやすかったが、今のような比較的安定した社会では、いい時だけの友だちが真の友だちのふりをしていることがたくさんある。それで今の私たちがなんとなく、自分が他人のために何かやってあげた時に、すぐにモノとしてお礼を渡されると寂しい気持ちになったりするのは、真の友だちはそのような直接的な利益のやりとりとは遠いものであることを私たちが知っているからだと言う。 「便利」とは違う価値、曰くいい難い価値が、それぞれの人にはあるということである。 ・私たちの意識が、物質である脳からどのように生み出されているのか、という問題は、脳・神経科学の中の最大の謎であり、「ハード・プロブレム」と呼ばれている。物質である脳の働きをいくら調べてみても、意識がどのように生み出されているかはわからないから、「ハード」プロブレムと呼ばれるのである。 私が感じていることは、言葉には表しきれない。それなのに、今私たちは言葉で言えば全てがわかると思っている。言葉に頼りすぎていて、言葉だけを膨大に読み込んで大規模言語モデルを作り上げ、それが人間を超える知性を見せるようになるかということにまで挑んでいる。 私たちの言葉に私たちの心は、どこまで含まれているだろうか。 わかりやすさだけを求める世界は、息苦しい。「Aと言えばAと伝わる」そんな世界は本当は存在しない。全てが言葉に表れているというならば、物言えぬ人たちには心がないのだろうか。私は、大規模言語モデルは無意識で言葉を流暢に話すけれども、認知症になった母は言葉を流暢には話せなくなったが大規模言語モデルよりもずっと豊かな心を持っていると感じていた。人間の無意識と、大規模言語モデルの無意識は、一つの言葉を発するまでの処理という意味で、異なっているのかもしれない。 意識を科学的に解くのが難しいということは上記のようにハード・プロブレムとして長らく知られてきたのだが、無意識だって科学的に解くのは同じくらい難しいのだろう。私たちの心はどのように動くものなのか?そして私たちの心はどこまで広いものなのか?人工知能を鏡に、改めて私たちはこれから確かめていったらどうだろう。人間らしさを存分に発揮するためにはそれしかないような気がするのである。 本当に感情を働かせるというのは、AならばAと伝わり、必要なことが手に入り、互いが相手にとっての空気になる、ということとは違って、衝突しながら、動きながら、面倒なことを背負う中で一つひとつ気づくことが増えていき、無意識の感情の空間を探索し、「利用」とは違った意味で、誰の心ともつながれるようになることをいうのではないか?人間の広大な心を知ろうとすることが、今の私たちにとって必要な感情労働なのではないかと私は思う。そのためにまず、真っ暗闇に目を向けて、必ずしもうまく言葉にはならない、感情の動きを感じてみよう。自分や他人の小さな感情を意識的に大切にする社会が作れたら、とてもうれしい。
感情労働の未来恩蔵絢子◾️未来の感情労働 ・共感をした上で切り離す、そして表層だけではないものを見る、そんな、本当に人を理解する感情労働とはどういうもので、どうしたら可能なのだろうか? 今までにいくつかヒントは出てきていた。他者と自分を切り離す良い感情労働としては、例えば異文化の人に慣れない見た目の料理を出す研究で見たように、(1)人に優しくできなくなったら、自分の抱えている荷物を下ろす。またインストルメンタル・コンバージェンスの例で見たように、(2)自分と感じ方や考え方が違う人と関わる際には、食事など根本的な要求については一緒にすることができ、それが満たされればとりあえず十分であると考える。また依存関係の例で見たように、(3)自分から「待つ」という痛みを取る。「好き」は「欲しい」に圧倒されて消えていくので、強い風で小さな火が消えないように両手で守るように、自分と相手の間に空間を作る。 そしてトランザクティブ・メモリーの例で見たように、(4)相手の良いところ(自分に直接利益となるところ)だけではなくて、悪いところ(自分の不利益になるところ)も含めて、全人格で関わる。そして日本人の癖として見たように、(5)相手や集団を大事にしすぎて、自分の「助けて」という気持ちを消さないようにする、などが考えられるだろう。 基本的には、「こうでなくてはならない」ということで他人と関わるのではなく、もっとりラックスして、自分と他人に余裕を与える。自分と違う相手に本当に興味を持つということになるのだろう。 ・どんな課題にも対応できる流用的知性(1Q)だけでは人間の知性は説明し尽くせず、っひとつの課題に特定的に驚くべき力を発揮する人たちがいるとして、1983年アメリカの心理学者ハワード・ガードナーは「多重知能理論」を発表した。これによれば少なくとも人間には8種類の異なる知能があるという。(1)言語的知能、(2)論理・数学的知能、(3)空間的知能、(4)身体・運動感覚的知能、(5)音楽的知能、(6)博物的知能、加えて(7)対人的知能と(8)内省的知能である。 ・感情の欠点は、感情は正解のないところでも、私たちに意思決定をさせてくれる能力であり、言い方を変えれば、差がないところに差をつける力、理由なく一方を好ませるものであって、すなわち偏見を生む力にもなっている。また、初めてのことに出合って感情のシステムが大きく動く(例えば強い恐怖を感じる)ことで、記憶のシステムに刺澈が行き、絶対に忘れられない記憶を形成することも述べた。このシステムのおかげで次に似たような恐怖には出合わないように行動を変えることができるのだが、これは、少しでも似た状況になると体が硬直してしまう、危険の全くないところでも危険を感じ、何もかもが怖くなるというPTSDの要因でもある。もちろんこれは感情の矢点である。 さらに感情は他者との関係性で問題になるところがある。情動的共感で私たちは他者としっかり結びつくことができるのだが、そのせいで切り離しが難しくなり、自分の延長として他者を提えモノとして扱ってしまったり、虐待をしてしまったり、また自分をモノとして扱うという問題が生じる。 同調圧力もこの仕組みと関係する。この人が本当に大切なことを言っているのかどうか、私たちは自分で考えずに、なんとなくの雰囲気だけで肩じてしまうことがある。そして同じ感情を感じていない人のことを付き合いにくいと感じたり、「空気が読めない人」と言って仲間はずれにしたりすることがある。脳が典型的な発達とは違った発達をしていたり、違う文化的背景で育ったりした人が、均一を前提とした社会に入ると、感情が伝わるのに時間がかかることがある。感情は伝染することで、伝わる速さを手がかりに、仲間とそうでない人を分ける圧力になってしまうのだ。 感情は我々の根本なのだが、大きな力であるがゆえに、長所が点にあっという間に変わる。 感情にはどうしても手入れが必要になる。ここで鍵となるのが「気づき」なのである。 ・人を本当に理解するのには、物事の因果関係を簡単に考えてはいけない。「そうではないかもしれないな」と判断を保留しなくてはならない。感情は常に動かしていなければならない。 その動いている感情を掘むにとどめ、型に入れないことが感情的知性なのである。 ・自分の気持ちに気づきうまく表現することによってポジティブな感情を増大させて、ネガティブな感情を減少させることができる。 「感情表現(emotional expressivity)」は感情と気づきがセットになった一つの感情的知性である。 「表現」というのは面白い技術だ。表層演技のように「抑制」ばかりをするのではなく、自分が本当に今感じていることはどういうことなのかに気がついて、表現することが大事なのである。 ・何か条件が変わったら、こだわらずに違うプランを考えられる力を「認知的柔軟性(cognitive Rexiblity)」と呼ぶ。感情表現だけでなく、この力によっても、人生の中に喜びを増やし、悲しみを減らすことができるわけである。 ・ここで、人間の能力を私なりに整理してみよう。 大脳新皮質には大きく分けて3つのネットワークがある。一つ目は、言語能力やIQ、すなわち「頭がいい」と通常言われるような能力、テキパキと物事をなんでもこなせ、大きな短期記憶(今この場で何か課題を実行するために、必要な情報を集め、一時的に蓄えておく力、容量)を持ち、人と長く雑談している時も自分が何を言いたかったのか決して見失わないような能力を担当するシステムで、「セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(centralexecutive network)」と呼ば はいがいそくぜんとうぜんや れている。セントラル・エグゼクティブ・ネットワークは、背外側前頭野や後頭頂皮質という大脳新皮質の外側にある領域が主に形成している。 その他に、「デフォルト・モード・ネットワーク」と、「サリエンス・ネットワーク (saliencenetwork)」が存在する。デフォルト・モード・ネットワークは、セントラル・エグゼクティブ・ネットワークとは正反対の働きをしていて、人間が何にも集中しておらず、本当にリラックスしている時に活動が高まる脳領域である。内能頭前野や後説帯状という、大脳新皮質の内側に位置する領域からなっている。 デフォルト・モード・ネットワークは、集中とは正反対で、白昼夢のように、心があちこち術衛っている状態を作り出し、ぼーっとああでもない、こうでもない、とセントラル・エグゼクティブ・ネットワークを駆使していた時に体験したことを整理している脳部位である。シャワーを浴びたり、散歩をしたり、私たちが休憩していて特別に何にも集中していないからこそ、記憶の整理はできるのであり、こうして知らないうちに体験を整理してくれることで、私たちは再び効率的に動けるようになるのである。 そしてサリエンス・ネットワークは、セントラル・エグゼクティブ・ネットワークとデフォルト・モード・ネットワークの切り替えをしている脳領域である。何か注目すべきことが起こった時に、ぼんやりしていないでセントラル・エグゼクティブ・ネットワークを働かせろと命令してくるシステムだ。島皮質や前部帯状回という、痛みなどの強い感情の伝染を司っていた回路で、皆戒号を送る回路でもある。不安を感じやすく、この部位がいつも過剰に働き続けている人は、安らげないためデフォルト・モード・ネットワークをうまく働かせることができず、結局セントラル・エグゼクティブ・ネットワークの働きも落ちて、柔軟に物事を考えることが苦手になることが知られている。 サリエンス・ネットワークの中の島皮質は特に面白い領域である。痛みを感じている時に働く脳部位だと言ったが、芸術作品など理由もわからず何かを私たちが美しいと感じている時に働く脳部位でもあり、身体や内臓の感覚をまとめあげ、感じる時、島皮質が活動すると言われている。身体で起こっていることの自覚をする部位が島皮質なのだ。「失感情症(alexithymia)」といって、自分の感情を認識できず、言語化することが苦手な人たちがいる。この人たちは、この島皮質と展体の体積が、小さくなっていることが知られている。 仏教の瞑想のトレーニングが、私たちの内なる感覚や、外の世界の出来事に気づきを高める「マインドフルネス(mindfulness)」として広まっている。過剰に物事に反応せず、良い悪いとすぐに決めつけず、判断を保留にして気づくにとどめ、その観察力に基づいて行動をする「マインドフル」な人たちは、失感情症の人たちとは逆で、島皮質と扁桃体の体積が大きいことがわかっている。 私たちは、IQばかりを気にしてきた時間が長かったが、やりたいと思うことを適切に実行できることの背景には、私たちの知らないところで行われているデフォルト・モード・ネットワークの処理と、深い身体からの知らせに気づくサリエンス・ネットワークの処理がある。 外から龍力として目につきやすい、光り輝く部分ばかりを私たちは大事にするが、目に見えにくいところで行われている処理が光の部分を支えているのであり、時に私たちはその無意識の処理に目を向けなくてはならないのだ。目に見えにくい自分の欲求、他人の欲求、そして人間だけでなく、人間が支えられている環境の中の複雑すぎるつながりに少しずつ気づいていくことが、自分自身を取り戻す、人を理解する感情労働であると言える。 ・意識されている物事の中で、「こうなったのはこのせいだ」と私たちは理由を見つけようとするが、私たちには、どうにもコントロールの及ばない、無意識というものがあり、せいぜい そのうちの少しに気づくことができるだけなのかもしれない、という視点を持つことは大切だ。 全てがコントロールできるわけではないのだ。 言語化されたものだけをみるのではなく、コントロールできないものの動きを感じてみる。 見かけの因果関係に騙されずに、感情的知性を使って、見えない心の広がりを感じてみる。 グッドハートの法則のように、「偏差値」「売上」「どれだけ「いいね」がつくか」というわかりやすい尺度に自分をあてはめず、本当にやりたいことをやってみる。自分の小さな感想を表現してみる。見た目だけを重要視しないで、感じていることを掴む努力をする。自分と同じと考えないで他人に興味を持つ。他人の小さな「好き」を守れるように、風よけの手を差し出す。このような感情の働かせ方を通して、社会的な正解・不正解に従って、みんながみんな同じ人間にならねばならないかのような苦しさからは解放されるのかもしれない。人間の心は、均質なもの、動きのないものなどではなく、いかに広大か。人間の心の広大さを知ることこそが、私たちの息苦しさや耐えがたさを減らす方法だと思う。 全てがコントロールできるという勘違いから離れ、コントロールが利かない世界の中で、時々ある「気づき」を大切にする。それだけで良いのかもしれない。 人間が人間と付き合う価値は、人間の動く心がわかるようになることに尽きるのだろう。 ◾️おわりに ・ここまで感情労働について考えてきたが、感情労働は、他人のために自分の本当の感情を犠牲にするところがあるという意味では「利他性」の考察が必要である。最後にそれを考えたい。 自分を犠牲にしてまで、他人のために動く、という利他性の起源はどこにあるのか。 通常、血縁関係にあるものを助けるためには、自分の身を危険に晒すことは意味があるとされる。なぜなら、自分の子どもやきょうだいが生き残れば、自分の遺伝子が残るのだから。これは「利他性の血縁選択説(kin selection)」である。また、血縁関係になくとも、自分を今危険に晒して相手を助けることで、将来相手から自分を助けてもらえる可能性がある場合は、利他行動に出る意味があるとされる。これは「互恵的利他主義(reciprocal altruism)」である。 しかし、人間の社会で現れている利他性を説明するのに、血縁選択説と互恵的利他主義だけでは不十分として、アメリカの心理学者レダ・コスミデスらは、「かけがえのなさ(irreplaceability)」を導入している。 ・コスミデスらによると、平常時には自分に大きな利益をもたらす人同士で元気に交流していればいいだろうが、私たちが狩猟採集民だったとすると、狩りの時に怪我をしたり、敵から攻撃されたり、病気をしたりということは頻繁にあって、困った時には、平常時に優しかった人が自分を助けてくれるとは限らないという。相手にとっての自分の価値が低くなってしまったからである。それゆえに困った時にも、他者の援助を引きつける能力が我々には必要で、そのために、自分の他には代わりがいないということを人にわかってもらおうとして、他人に評価される自分だけの特徴を見つけようとしたり、技術・習慣・属性などを獲得しようと力を尽くしたり、実力はなくとも他者に自分がかけがえのない存在であることを肩じさせようと嘘をついたり、倍じてくれる人がいなければ自分を必要としてくれる社会的グループを求めて居場所を移していったり、同じグループ内で自分と同じような能力を持つ個体にはやきもちを焼いたり、といった人間社会でよく観察される行動が現れてきたのだという。 かけがえのなさということを考えると、人間には無限の種類の価値があることになる。なぜなら、相性の問題があるからだ。このグループには、りんごが溢れていて、私の持っているりんごは価値がないけれども、りんごのない土地に行けば、私の持っているりんごは欲してもらえることになる。自分にないものを持っている人が素敵に見える。人によって素敵に見えるものは変わってくる。みんな同じものを持っていなければならないのではなく、他人を助ける動機はさまざまになる。そして他人に対する感情もさまざまになる。 そして昔は自分が危機に陥ることはかなりの頻度であったので、正真正銘の困った時に助けてくれる友がどの人かは感じやすかったが、今のような比較的安定した社会では、いい時だけの友だちが真の友だちのふりをしていることがたくさんある。それで今の私たちがなんとなく、自分が他人のために何かやってあげた時に、すぐにモノとしてお礼を渡されると寂しい気持ちになったりするのは、真の友だちはそのような直接的な利益のやりとりとは遠いものであることを私たちが知っているからだと言う。 「便利」とは違う価値、曰くいい難い価値が、それぞれの人にはあるということである。 ・私たちの意識が、物質である脳からどのように生み出されているのか、という問題は、脳・神経科学の中の最大の謎であり、「ハード・プロブレム」と呼ばれている。物質である脳の働きをいくら調べてみても、意識がどのように生み出されているかはわからないから、「ハード」プロブレムと呼ばれるのである。 私が感じていることは、言葉には表しきれない。それなのに、今私たちは言葉で言えば全てがわかると思っている。言葉に頼りすぎていて、言葉だけを膨大に読み込んで大規模言語モデルを作り上げ、それが人間を超える知性を見せるようになるかということにまで挑んでいる。 私たちの言葉に私たちの心は、どこまで含まれているだろうか。 わかりやすさだけを求める世界は、息苦しい。「Aと言えばAと伝わる」そんな世界は本当は存在しない。全てが言葉に表れているというならば、物言えぬ人たちには心がないのだろうか。私は、大規模言語モデルは無意識で言葉を流暢に話すけれども、認知症になった母は言葉を流暢には話せなくなったが大規模言語モデルよりもずっと豊かな心を持っていると感じていた。人間の無意識と、大規模言語モデルの無意識は、一つの言葉を発するまでの処理という意味で、異なっているのかもしれない。 意識を科学的に解くのが難しいということは上記のようにハード・プロブレムとして長らく知られてきたのだが、無意識だって科学的に解くのは同じくらい難しいのだろう。私たちの心はどのように動くものなのか?そして私たちの心はどこまで広いものなのか?人工知能を鏡に、改めて私たちはこれから確かめていったらどうだろう。人間らしさを存分に発揮するためにはそれしかないような気がするのである。 本当に感情を働かせるというのは、AならばAと伝わり、必要なことが手に入り、互いが相手にとっての空気になる、ということとは違って、衝突しながら、動きながら、面倒なことを背負う中で一つひとつ気づくことが増えていき、無意識の感情の空間を探索し、「利用」とは違った意味で、誰の心ともつながれるようになることをいうのではないか?人間の広大な心を知ろうとすることが、今の私たちにとって必要な感情労働なのではないかと私は思う。そのためにまず、真っ暗闇に目を向けて、必ずしもうまく言葉にはならない、感情の動きを感じてみよう。自分や他人の小さな感情を意識的に大切にする社会が作れたら、とてもうれしい。 - 2026年2月18日
 感情労働の未来恩蔵絢子◾️脳の進化と感情労働 ・私たちは自分のいる場所にあるものは全て意識できていて、その中で自分が全ての行動を意図的に選んでいるように感じている。しかし実際は、自分の予測に合ったものでなければほとんど意識されず、「感情の評価理論」などで意識的に感情を動かすことはできると言われているものの、第1章で書いたように、ほとんどのことは感情が気づかぬうちにやっていて、無意識の支配が絶大なのである。私たちが意識できる領域はとても限られている。本当に意識にのぼるのはごくわずかであり、これを「知覚のオーバーフロー(perceptual overlow)」という。 ・勉強すればするほど、課題に熟達すればするほど、脳はたくさん働くのかと思いきや、逆なのである。熟達者は非常に省エネで、新人ほど本当に苦労してその課題の中の全てのことに意識的に、脳領域全てを使って対処しようとする。意識は、意外なこと、自分が経験したことがないことが起こって、注意が必要になった時にだけ灯る電灯のようなもので、自分がどう行動したらいいかを明晰に考えさせるために存在するものなのだと思われる。 つまり意識は、自分が必要としているけれどもうまく自分がコントロールできない事態専用なのにもかかわらず、私たちは時にこの意識こそが全てだと勘違いする。 ・パソコンやスマートフォンの登場で24時間、一度も顔を合わせたことがない人とすらもつながっていられるようになったことで、無制限に「もっともっと」と欲しがることが可能な環境ができてしまった。人々の注意を得ることが経済的価値になるという「アテンション・エコノミー」を予言したアメリカの認知心理学者ハーバート・サイモンは、注意とは自分の動機に合わせて思考の範囲を狭めるもの(botteneck of human thought)と定義している。注目するというのは、他の可能性を排除して、それにばかり向かっていく力を持たせるものでもある。 ・何か自分の興味のあることをがんばって、それで人から承認されることはうれしいことだが、承認自体が目的になることはあやういことだ。「一度尺度が目的になると、それはもはや良い尺度とは言えなくなる」という法則は「グッドハートの法則(Goodharts law)」と呼ばれる。イギリスの経済学者チャールズ・グッドハートが、1975年にイギリスの金融政策に関する論文で提唱した法則である。今に当てはめると、例えばいろいろなことを知るのが楽しくて、勉強に打ち込んでいると偏差値という尺度も上がっていくかもしれないが、偏差値を上げるための勉強になってしまうと、それはいいことではなくなってしまうというのがそうである。勉強が嫌いになってしまうかもしれず、本来の目的が失われた、狭いものになってしまうからである。会社でも例えば、良い商品が作りたいと思ってその商品が売れたりすると、売上という尺度だけが重要視され、売れる商品だけが作られて良い商品から離れていってしまう、という場合がそうである。 ・一人ひとりの他者を認識し、他者の欲望、倉念、感情、意図を読み、その人の性質や行動を理解する。それぞれの人の行動パターンについての予測が利くようになる。多くの他者のモデルが頭の中にできるようになる。そうして人の理解が深まるのに伴い、いろいろな人と比べることで自分自身がどういう人間かということも理解していく。他者への配慮を身につけ、なり たい自分という理想も持つようになる。そのような社会性に関わる脳部位(側頭頭頂接合部や上側頭溝、前頭連合野など)は、感覚野が生後すぐに変化のピークを迎えるのに対して、思春期から青年期(大体10歳から25歳)に劇的な変化をする。 ・大規模言話モデルは人間が生み出す最も高沢なものの一つ(すなわち言語)から生まれた子どもである。世界に強大な大脳新皮質が生まれてしまって、私たちはこれからの未来、どのような方向へ進んで行きたいのか、AIに指示したり、あるいは善悪という価値を与えたりする大脳辺縁系としてより強大になることを、私たちは今求められているのだと思う。この二つがうまく付き合う方法を発見することは、世界に新たな社会脳を誕生させることでもあるのかもしれない。 ・人間の脳はなんのためにこれほど大きくなったのかという疑問に対して、イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは、「社会脳仮説(social brain hypotheis)」を提案した。この「脳の大きさ」と「グループのサイズ」との相関関係から推定すると、人間の脳の大きさでは、人間のグループサイズは150、すなわち人間が普段から互いに気にかけあえる関係性の数は150人だそうである。この数は「ダンバー数」と呼ばれている。 すなわち、人間の脳がこれだけ大きく進化したのは、他者のことを考えるためであり、人間の知性とは人付き合いのために進化したものであるというのが社会脳仮説の主張である。 ・実は、私たちは全く同じ気持ちにならなくても、他人の精神的な状態を推測できる。自分の今の心の状態と、他人の今の心の状態は違うものだと理解していて、自分と違う相手の心の状態を推測できる。「あの人は今このような状態なのではないかな」「こう思っているのではないかな」と推定する。他人の複雑な気持ちは直接知ることはできず、顔色や態度や行動、話の内容や環境、今までのその人との関わりの記憶などから、なんとなく感じたり、推測したりするしかないものである。だからこそ、科学者は「私たちは他者の心を持っている」と言わずに「私たちは他者の「心の理論』を持っている」と表現する。心の理論とは、他者の心についての推測のことである。 ・人間に一番関心を持ち、「自分」と「他人」を区別して、その中で苦しみなどいろいろな感情を感じ、時に動けなくなるというのが人間の心の理論の発達には必要なのであって、そのような関心は、人工知能の中にはなさそうなのである。人間の「心」は、「mind」よりも広いものなのだと私は思う。 ・言葉にならないもの(感覚情報)から生まれた言葉が人間の言葉で、言葉から生まれた言葉が人工知能の言葉なのである。しかし、人間の言葉は、私たちの知覚したこと、感じたことが全て含まれそれを凝縮したものだから、人間の言葉だけを膨大に学習したら、ChatCPT もその中から人間の心をある程度学習できる。しかしそこで「心」と言うのは、一度言葉に表され、固定されたものから推しはかられるものであって、全てが意識の上で展開されているような世界でのお話なのである。 ・人間には身体があり、複数の種類の感覚器から膨大な情報を受け取り、生命維持や価値判断のシステムを備え、情動的共感を持ち、言葉にできないことを人間と人間の間で高速にやりとりしている。そのような言語以前の仕組みがあるからこそ、会話の中で一つの言葉の意味をある程度、的確に捉え、人工知能のような文脈の逸脱をしないですんでいるのかもしれない。私は、ここに現代を象徴する問題が現れているように思う。 今私たちは、インターネット、SNSの登場などで、リアルに顔と顔を合わせることなく、言葉だけで他者と付き合う機会が膨大になっている。自分たちの複雑な心を、身体と切り離し、目に見え耳に聞こえる形になった言葉だけから探るという苦労をしている。人間は大規模言語モデルに近づいているのかもしれない。私たちの人の心の読み方には今、変化が起こりつつあるのではないか? ◾️SNSは感情労働の最前線? ・新型コロナウイルスの夢延で、私たちはマスクをして、3年以上顔の半分を隠して過ごしていた。それまでは、リアルで会話する二人の間の言葉の意味は、ある種、顔色や表情によって、初めて確定するところがあった。顔を見ればパッと瞬時に感情が伝わるという、情動的共感のメカニズムが私たちには備わっているけれども、そうして人の気持ちを読むのに無意識のところで頼りにしていた顔色や表情が、マスクにより頼りにできなくなった。命を守るためだからマスクをするほうがいいと、人の気持ちは後回しにならざるを得なかったのである。人と思うようにつながれなかったり、人の気持ちが思うように読めなかったりすることで、人とのつながりで生きる楽しみを得ていた人たちは、気持ちが落ち込んで、健康状態が悪くなり、死を考えることすらあった。気持ちが大切にされないと、生命に関わることがあるのである(例えば、20代女性で「新型コロナウイルスが流行する前と比較して、孤独を感じることが多くなった」という回答割合は65%となり、若い女性の自殺者数がコロナ禍で増加した(厚生労働省「令和4年版自殺対策白書」第2章第2節「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺の動向」。しかしそのような目に見えない関係性は考慮に入れられず、気持ちよりも命が大切だ、と長い間、私たちの感情が後回しにされてきた結果、私たちは人とのコミュニケーションに戸惑うようになっている。 例えば、友達はいいけれど、知らない人を見るとただ怖いと感じる。龍車で少しでも咳をする人からは離れたいと感じる。不用意に話しかけることなどできなくなった。また、情動的共感を介さずにテキストだけで、必要なやりとりだけをすることが増えるにつれ、「それってあなたの感想ですよね」と、個人的で小さな感想を言うことを責めるような言葉が小学生の間でも流行り、「コストパフォーマンス」「タイムパフォーマンス」という言葉に代表されるように、「効率」が重視され、小さな失敗、面倒なこと、ダサいこと、一人の感想にすぎないことは排除されるようになった。ホックシールドの言う深層演技、また、目に見えない人の気持ちを見るという感情労働と、効率は相性が悪いものである。「いいね」がたくさんつくことや目立つ成果だけが重要視されている。私たちはまるで私たちが存在する意味を立証しなければ存在してはいけないかのように扱われることが多くなった。このような風潮に、本当はみんな息苦しさを感じているはずである。小さな感想を軽視することは、自分の首を絞めることだと私は思う。 ・「あなたを見ています」「ちゃんと聞いています」ということを示すため、視線を合わせる、声を大きくするというように、非言語コミュニケーションの部分を明示的にするように、私たちはコントロールをしている。Noomだけではない。TiTokでもYouTube でも、テロップを入れるなど、わかりやすいプレゼンでなければ相手の注意を引きつけることはできない。グローバルな社会で、誰とでもつながれる中で、小さな自分に気づいてもらうために、もっとはっきりしなければならないと私たちは思い込むようになった。全てを明示的にするように求められるようになった今、私たちは、自らもわかりやすさを追い求めるようになってきている。 「AならばB」というように明快な言い回しで自分を語る、言いにくいことは存在しないことにして、意識の世界だけで生きる、今まで体験したことがない時代になったのだ。 言語と身体をかつてなく切り離した現代人は、見えにくい人の心を理解するという方向で苦労する代わりに、見えにくい心を誰からも見えやすいように加工するという苦労を選んでいるのかもしれない。 ・実際インターネットに依存している若者の脳の中では特に、「欲しい」の回路がまわり、街動を抑えて今やるべきことに集中する回路の働きが落ちているという。すなわち、インターネットはあまりにも強すぎる刺激であり、そもそも衝動のコントロールが苦手な若者の脳はそちらに向かいやすく、そればかりを求めて、小さな報酬を無視するようになるので、この時期に発達させるべき回路を発達させられなくなる。自分のやりたいことを見つけ、それを育てるためには、一つの強すぎる刺数だけを求めていては難しく、その瞬間にはどんなことに役に立つのかわからないような現実的な宿題なども実際にやってみる必要がある。しかし、そんな小さく、わしいことよりも、強い刺潡のあるインターネットを求めてしまい、衝動をコントロールする訓練がいっそうできなくなってしまうのである。 ・アメリカだけでなくヨーロッパでも10歳から18歳の子どもは一日7・5時間オンラインで過こしている。つまり、オンラインとオフラインの世界は重なり合っており、子どもたちは仲間とのつながりを深めるためだったり、自己表現や自己の確立のためだったり、他者との比較をして社会の規範を知るためだったり、と学校などのオフラインの生活の助けになるようにオンラインを使っているという。それはオンラインには学びがたくさんあるということだが、いじめなどが激化してしまうのは、この時期の子どもたちが高次認知機能と感情システムの連携が大人よりもずっとうまくいかない脳を持つ中で、自分と年齢の近い仲間たちを重んじ、同じく冒険的である仲間たちから善/悪、格好の良いこと/悪いことなどを学ぼうとし、仲間たちからの称賛が彼ら・彼女らの強い報酬になることが一つの重要な要因であると考えられている。 仲間たちから認められたいという気持ちが強く、SNS上ではどこまでもそれが過激化し得て、産に上ったり、竈車の上に飛び乗ったりという無理な挑戦をしてその動画を上げたり、自分のプライベートな部分をどんどん開示してしまったりすることがあるのである。 ・SNSは誰にでも開かれていて、どんなことでも表現できる個人のメディアであり、人間が感情を創造的に爆発させられる場所に思われるが、それぞれの人の小さなやりたいことが出ら、人間の豊かな感情が溢れ出している場所というよりは、承認欲求から刺激の強いコンテンツが生まれる場所になりがちなようである。まるでグッドハートの法則(一度足度が目的になると、その尺度はもう良い尺度とは言えなくなる)のように、「いいね」を集めるという一つの目的に向かってみんなが競争しており、創造的な世界が構築されるようになったというより、自分を苦しめることにつながっている。社会脳の確立の時期にある子どもたちは、逆に自分にとって大事なことにじっくり取り組めなくなり、不安を高めている場合も多いのである。 それゆえに、法律で禁止する国が出てくるなど、利用の時間を区切り、制限することで、現実の時間を増やし、人間の生活の全体性を同復させることが必要とされてきている。 ・先に若者たちが外見にフォーカスするようになっていると専門家たちが問題視していると述べた。 1997年、アメリカの心理学者バーバラ・フレドリクソンとトミ・アン・ロバーツは他者からの評価を内在化して、自己の容姿にとらわれるようになることを「自己のモノ化(selfobjectification)」と呼んだ。例えば、ある女性をその人の人格を見るのではなく、モノとして見るような発言、「顔が小さいね」「スタイルがいいね」「胸が大きいね」などパーツだけを重要視する発言に接したり、写真としても、スタイル抜群のセクシーな女性しか雑誌の中にいなかったりすることは多く、そのように他人が女性の外見しか気にせず、まるでモノのように見てくることで、女性たちが「自分で自分をモノのように扱うようになっていくこと」を指摘したのだ。そしてこの自己のモノ化は、自尊心の低下、人生の満足度の低下を引き起こし、自分の体に対する羞恥心や不安感から、摂食障害、鬱病、性機能障害にもつながることがわかってきた。 「スタイルが良くなければいけない」などと思い込んで、自分の体をその他人から与えられた理想に合わせようとコントロールしていく時に、うまくいかずに自言を喪失したり、行きすぎて摂食障害を患ってしまったりするのである。興味深いことに、自分をモノ化する傾向の高い女性は、自分の実際の身体の感覚に疎くなることが示されている。 ファッション(見た目)のほうが寒さ(自分の身体が感じていること)よりも大事で、自分の身体からの情報を積極的に無視したり、自然と身体からの情報に疎くなったりすることが示唆された。つまり自分で感じることよりも他人からどう見えるかを大事にすると、自分が「ヒト」ではなく「モノ」であるかのように、「感じる」ことが少なくなってしまうのだ。 ・昔は雑誌やテレビなどを参照していたのだが、今はSNSがそれらの代わりとなった。そこではモデル、セレブリティという見知らぬ他者の姿をただ見かけるだけではなく、友人、知人のアップした姿を目撃するようになった。比較する他者の数が膨大になったのである。また、一方的に見るだけではなく、自分の写真もあげることになり、さらにはそれについて他者からさまざまなコメントがつくようになった。比較の激化である。 近しい友人や、少し距離のある仲間たちと自分を毎日比べていることのほうが、モデルやセレブリティたちと比べることよりも自分の体に対する不満を高めることが明らかになっている。 モデルやセレブリティの着ているドレスは高すぎて、自分には手が届かなかったり、スタイルも自分とはかけ離れていたりして非現実的だが、身近な人の素敵な姿は、我々にとって達成可能であるために、比較対象として、遠い人より身近な人から我々は大きな影響を受けるという。 私たちは自己のモノ化が圧倒的に進む条件に生きている。 ・この研究で特に面白いのは、顔を出さないこと、顔を意図的にぼかすことは、その人の人格を剥ぎ取ることだと理解されていることだ。特に英語圏の研究では、顔を出さずに身体だけに注目することが代表的なモノ化の例になっている。日本人が自ら顔にスタンプを貼るなど顔を消して写真をアップしたり、友達以外の他人には自分とわからないほどに顔を加工したりしていることは、自分を守る手段でありながら、英語圏の人々よりも、自分を人でなくモノとして見ているからなのかもしれない。確かに日本は、Twitter(調査時。現在のX)の使い方を見ても、匿名で使っている人が多く・日常で人格を消す傾向が他の国に比べて高いと言える。 感情が企業の商品となって、やりとりされることが従来の感情労働の問題だったが、SNS の登場により私たちは自分で自分をモノにして、やりとりしてしまっているのである。 ・今、みなさんは、困ったことがあった時にどれくらい人に助けを求めようとするだろうか? 日本人など東アジアの人々は、西洋の人々に比べて、助けを求めることに対して抵抗を感じる人が多いという。確かに、私自身、「こんなことを質問していいのかな」「人に迷惑をかけるのではないかな」「これが欲しいけれど、それを口にしたら拒絶されるのではないかな」「バカだと思われるのではないかな」と感じて、自分にとって必要なことを言わないでいることがたくさんある。 社会的支援とは、困った時に直接的に助けてもらったり、感情的に寄り添ってもらったりして、「自分は他人から愛され、価値あるものとされ、互恵的な関係性の一部になっていると感じられること」をいう。それは私たちにとってもちろん必要なものである。例えば、痛みを感じている時に、頼している人が手をつないで寄り添ってくれていると、脳の中で痛みを感じている時に働く部位の反応が弱まる。そして社会的支換があると感じられていると、病気などからの回復も早くなることが知られている。テイ・ショウホウら一橋大学と名古屋大学の共同研究によると、生きていくためには必要なものなのに、私たち東アジアの人々が助けをあまり求められないのは、実は、他者が困っている時にも、あまり哀れみを感じないからであるという。東アジアは「集団」の文化で、自分と他者を西洋の人々よりもつながった存在であると見ており、自分自身の目標よりも、集団の目標のほうを重んじる傾向がある。そのような文化ではどうしても集団に対する責任感が強くなり、自分が自分の目的を達成するために「助けて」と口にするのは、集団にとって「迷惑になる」可能性があるから抵抗を感じ、他者が困っている時も、それは集団に対してその人がなんらかの悪いことをしたからだろうと類推するから、同情が薄くなるのだという。逆に、アメリ 力などの「個」の文化では、自分と他者は違う存在というのが前提であり、自分の目的で行動するので、それが失敗した時には、「悪いことをしたから」ではなくて、「そもそもうまくいくかどうかはわからないから」で、他人が失敗した時にも自分もそうなのだからと助ける傾向になるという。 他人と自分を切り離さない人のほうが、困った時に他人に冷たくなりやすいというのは衝撃ではないか?そして私たちは、集団に対する責任感から、集団に合わせる思考法をしていて、「人の迷惑になる」「私の要求は人に拒絶される」のが当然という見積もりをしているという。 私たちは、人に迷惑をかけないようにと常に他者を気遣い、自分よりも集団を優先することで、「感情労働をして疲れる」と言っているが、それで人に優しくなっているというよりも、互いに「助けない」という、孤立の道を歩んでいるのかもしれないのである。だとすればその「労働」の意味はあるのだろうか?私たちは感情を動かし、やりたいことを実現できるように努力し、他人のやりたいことも叶えるよう手伝い、今より良く生きられる、今より良い社会を作り上げるというのではなく、ただなんとなく今の社会に合わせて、自分たちを抑え、自分たちの価値がわからなくなるという方向で感情を使っているのである。 実際に私たちの自己肯定感は下がっている。日本の特に若者、小中高生の自殺者数は2024年で529人、過去最多となったという。わかりやすさを求めて全てを明示的にするように力を使い、他人と自分を頻繁に比較し、「迷惑にならないように」と規律的に動いて、安心して暮らせる場所を作っているつもりで、実際には安心して存在することができなくなっている。 私たちは自分の弱さをもう少し見せ合って、かけがえのなさを取り戻さなければならないのではないか? 人の心を理解することがうまくできるようになる前に、情報過多のSNS時代を生きる私たちは、見えにくいものを見えやすく加工するという力の使い方をしている。それは推し活で見るように創造力の一つの発揮ではあるのだが、自分で「感じる」という心の動きはおろそかにされているようである。現代特有の見直されるべき感情労働とは、膨大な他者の中で一人の人のかけがえのなさを忘れる方向に努力していることなのかもしれない。
感情労働の未来恩蔵絢子◾️脳の進化と感情労働 ・私たちは自分のいる場所にあるものは全て意識できていて、その中で自分が全ての行動を意図的に選んでいるように感じている。しかし実際は、自分の予測に合ったものでなければほとんど意識されず、「感情の評価理論」などで意識的に感情を動かすことはできると言われているものの、第1章で書いたように、ほとんどのことは感情が気づかぬうちにやっていて、無意識の支配が絶大なのである。私たちが意識できる領域はとても限られている。本当に意識にのぼるのはごくわずかであり、これを「知覚のオーバーフロー(perceptual overlow)」という。 ・勉強すればするほど、課題に熟達すればするほど、脳はたくさん働くのかと思いきや、逆なのである。熟達者は非常に省エネで、新人ほど本当に苦労してその課題の中の全てのことに意識的に、脳領域全てを使って対処しようとする。意識は、意外なこと、自分が経験したことがないことが起こって、注意が必要になった時にだけ灯る電灯のようなもので、自分がどう行動したらいいかを明晰に考えさせるために存在するものなのだと思われる。 つまり意識は、自分が必要としているけれどもうまく自分がコントロールできない事態専用なのにもかかわらず、私たちは時にこの意識こそが全てだと勘違いする。 ・パソコンやスマートフォンの登場で24時間、一度も顔を合わせたことがない人とすらもつながっていられるようになったことで、無制限に「もっともっと」と欲しがることが可能な環境ができてしまった。人々の注意を得ることが経済的価値になるという「アテンション・エコノミー」を予言したアメリカの認知心理学者ハーバート・サイモンは、注意とは自分の動機に合わせて思考の範囲を狭めるもの(botteneck of human thought)と定義している。注目するというのは、他の可能性を排除して、それにばかり向かっていく力を持たせるものでもある。 ・何か自分の興味のあることをがんばって、それで人から承認されることはうれしいことだが、承認自体が目的になることはあやういことだ。「一度尺度が目的になると、それはもはや良い尺度とは言えなくなる」という法則は「グッドハートの法則(Goodharts law)」と呼ばれる。イギリスの経済学者チャールズ・グッドハートが、1975年にイギリスの金融政策に関する論文で提唱した法則である。今に当てはめると、例えばいろいろなことを知るのが楽しくて、勉強に打ち込んでいると偏差値という尺度も上がっていくかもしれないが、偏差値を上げるための勉強になってしまうと、それはいいことではなくなってしまうというのがそうである。勉強が嫌いになってしまうかもしれず、本来の目的が失われた、狭いものになってしまうからである。会社でも例えば、良い商品が作りたいと思ってその商品が売れたりすると、売上という尺度だけが重要視され、売れる商品だけが作られて良い商品から離れていってしまう、という場合がそうである。 ・一人ひとりの他者を認識し、他者の欲望、倉念、感情、意図を読み、その人の性質や行動を理解する。それぞれの人の行動パターンについての予測が利くようになる。多くの他者のモデルが頭の中にできるようになる。そうして人の理解が深まるのに伴い、いろいろな人と比べることで自分自身がどういう人間かということも理解していく。他者への配慮を身につけ、なり たい自分という理想も持つようになる。そのような社会性に関わる脳部位(側頭頭頂接合部や上側頭溝、前頭連合野など)は、感覚野が生後すぐに変化のピークを迎えるのに対して、思春期から青年期(大体10歳から25歳)に劇的な変化をする。 ・大規模言話モデルは人間が生み出す最も高沢なものの一つ(すなわち言語)から生まれた子どもである。世界に強大な大脳新皮質が生まれてしまって、私たちはこれからの未来、どのような方向へ進んで行きたいのか、AIに指示したり、あるいは善悪という価値を与えたりする大脳辺縁系としてより強大になることを、私たちは今求められているのだと思う。この二つがうまく付き合う方法を発見することは、世界に新たな社会脳を誕生させることでもあるのかもしれない。 ・人間の脳はなんのためにこれほど大きくなったのかという疑問に対して、イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは、「社会脳仮説(social brain hypotheis)」を提案した。この「脳の大きさ」と「グループのサイズ」との相関関係から推定すると、人間の脳の大きさでは、人間のグループサイズは150、すなわち人間が普段から互いに気にかけあえる関係性の数は150人だそうである。この数は「ダンバー数」と呼ばれている。 すなわち、人間の脳がこれだけ大きく進化したのは、他者のことを考えるためであり、人間の知性とは人付き合いのために進化したものであるというのが社会脳仮説の主張である。 ・実は、私たちは全く同じ気持ちにならなくても、他人の精神的な状態を推測できる。自分の今の心の状態と、他人の今の心の状態は違うものだと理解していて、自分と違う相手の心の状態を推測できる。「あの人は今このような状態なのではないかな」「こう思っているのではないかな」と推定する。他人の複雑な気持ちは直接知ることはできず、顔色や態度や行動、話の内容や環境、今までのその人との関わりの記憶などから、なんとなく感じたり、推測したりするしかないものである。だからこそ、科学者は「私たちは他者の心を持っている」と言わずに「私たちは他者の「心の理論』を持っている」と表現する。心の理論とは、他者の心についての推測のことである。 ・人間に一番関心を持ち、「自分」と「他人」を区別して、その中で苦しみなどいろいろな感情を感じ、時に動けなくなるというのが人間の心の理論の発達には必要なのであって、そのような関心は、人工知能の中にはなさそうなのである。人間の「心」は、「mind」よりも広いものなのだと私は思う。 ・言葉にならないもの(感覚情報)から生まれた言葉が人間の言葉で、言葉から生まれた言葉が人工知能の言葉なのである。しかし、人間の言葉は、私たちの知覚したこと、感じたことが全て含まれそれを凝縮したものだから、人間の言葉だけを膨大に学習したら、ChatCPT もその中から人間の心をある程度学習できる。しかしそこで「心」と言うのは、一度言葉に表され、固定されたものから推しはかられるものであって、全てが意識の上で展開されているような世界でのお話なのである。 ・人間には身体があり、複数の種類の感覚器から膨大な情報を受け取り、生命維持や価値判断のシステムを備え、情動的共感を持ち、言葉にできないことを人間と人間の間で高速にやりとりしている。そのような言語以前の仕組みがあるからこそ、会話の中で一つの言葉の意味をある程度、的確に捉え、人工知能のような文脈の逸脱をしないですんでいるのかもしれない。私は、ここに現代を象徴する問題が現れているように思う。 今私たちは、インターネット、SNSの登場などで、リアルに顔と顔を合わせることなく、言葉だけで他者と付き合う機会が膨大になっている。自分たちの複雑な心を、身体と切り離し、目に見え耳に聞こえる形になった言葉だけから探るという苦労をしている。人間は大規模言語モデルに近づいているのかもしれない。私たちの人の心の読み方には今、変化が起こりつつあるのではないか? ◾️SNSは感情労働の最前線? ・新型コロナウイルスの夢延で、私たちはマスクをして、3年以上顔の半分を隠して過ごしていた。それまでは、リアルで会話する二人の間の言葉の意味は、ある種、顔色や表情によって、初めて確定するところがあった。顔を見ればパッと瞬時に感情が伝わるという、情動的共感のメカニズムが私たちには備わっているけれども、そうして人の気持ちを読むのに無意識のところで頼りにしていた顔色や表情が、マスクにより頼りにできなくなった。命を守るためだからマスクをするほうがいいと、人の気持ちは後回しにならざるを得なかったのである。人と思うようにつながれなかったり、人の気持ちが思うように読めなかったりすることで、人とのつながりで生きる楽しみを得ていた人たちは、気持ちが落ち込んで、健康状態が悪くなり、死を考えることすらあった。気持ちが大切にされないと、生命に関わることがあるのである(例えば、20代女性で「新型コロナウイルスが流行する前と比較して、孤独を感じることが多くなった」という回答割合は65%となり、若い女性の自殺者数がコロナ禍で増加した(厚生労働省「令和4年版自殺対策白書」第2章第2節「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺の動向」。しかしそのような目に見えない関係性は考慮に入れられず、気持ちよりも命が大切だ、と長い間、私たちの感情が後回しにされてきた結果、私たちは人とのコミュニケーションに戸惑うようになっている。 例えば、友達はいいけれど、知らない人を見るとただ怖いと感じる。龍車で少しでも咳をする人からは離れたいと感じる。不用意に話しかけることなどできなくなった。また、情動的共感を介さずにテキストだけで、必要なやりとりだけをすることが増えるにつれ、「それってあなたの感想ですよね」と、個人的で小さな感想を言うことを責めるような言葉が小学生の間でも流行り、「コストパフォーマンス」「タイムパフォーマンス」という言葉に代表されるように、「効率」が重視され、小さな失敗、面倒なこと、ダサいこと、一人の感想にすぎないことは排除されるようになった。ホックシールドの言う深層演技、また、目に見えない人の気持ちを見るという感情労働と、効率は相性が悪いものである。「いいね」がたくさんつくことや目立つ成果だけが重要視されている。私たちはまるで私たちが存在する意味を立証しなければ存在してはいけないかのように扱われることが多くなった。このような風潮に、本当はみんな息苦しさを感じているはずである。小さな感想を軽視することは、自分の首を絞めることだと私は思う。 ・「あなたを見ています」「ちゃんと聞いています」ということを示すため、視線を合わせる、声を大きくするというように、非言語コミュニケーションの部分を明示的にするように、私たちはコントロールをしている。Noomだけではない。TiTokでもYouTube でも、テロップを入れるなど、わかりやすいプレゼンでなければ相手の注意を引きつけることはできない。グローバルな社会で、誰とでもつながれる中で、小さな自分に気づいてもらうために、もっとはっきりしなければならないと私たちは思い込むようになった。全てを明示的にするように求められるようになった今、私たちは、自らもわかりやすさを追い求めるようになってきている。 「AならばB」というように明快な言い回しで自分を語る、言いにくいことは存在しないことにして、意識の世界だけで生きる、今まで体験したことがない時代になったのだ。 言語と身体をかつてなく切り離した現代人は、見えにくい人の心を理解するという方向で苦労する代わりに、見えにくい心を誰からも見えやすいように加工するという苦労を選んでいるのかもしれない。 ・実際インターネットに依存している若者の脳の中では特に、「欲しい」の回路がまわり、街動を抑えて今やるべきことに集中する回路の働きが落ちているという。すなわち、インターネットはあまりにも強すぎる刺激であり、そもそも衝動のコントロールが苦手な若者の脳はそちらに向かいやすく、そればかりを求めて、小さな報酬を無視するようになるので、この時期に発達させるべき回路を発達させられなくなる。自分のやりたいことを見つけ、それを育てるためには、一つの強すぎる刺数だけを求めていては難しく、その瞬間にはどんなことに役に立つのかわからないような現実的な宿題なども実際にやってみる必要がある。しかし、そんな小さく、わしいことよりも、強い刺潡のあるインターネットを求めてしまい、衝動をコントロールする訓練がいっそうできなくなってしまうのである。 ・アメリカだけでなくヨーロッパでも10歳から18歳の子どもは一日7・5時間オンラインで過こしている。つまり、オンラインとオフラインの世界は重なり合っており、子どもたちは仲間とのつながりを深めるためだったり、自己表現や自己の確立のためだったり、他者との比較をして社会の規範を知るためだったり、と学校などのオフラインの生活の助けになるようにオンラインを使っているという。それはオンラインには学びがたくさんあるということだが、いじめなどが激化してしまうのは、この時期の子どもたちが高次認知機能と感情システムの連携が大人よりもずっとうまくいかない脳を持つ中で、自分と年齢の近い仲間たちを重んじ、同じく冒険的である仲間たちから善/悪、格好の良いこと/悪いことなどを学ぼうとし、仲間たちからの称賛が彼ら・彼女らの強い報酬になることが一つの重要な要因であると考えられている。 仲間たちから認められたいという気持ちが強く、SNS上ではどこまでもそれが過激化し得て、産に上ったり、竈車の上に飛び乗ったりという無理な挑戦をしてその動画を上げたり、自分のプライベートな部分をどんどん開示してしまったりすることがあるのである。 ・SNSは誰にでも開かれていて、どんなことでも表現できる個人のメディアであり、人間が感情を創造的に爆発させられる場所に思われるが、それぞれの人の小さなやりたいことが出ら、人間の豊かな感情が溢れ出している場所というよりは、承認欲求から刺激の強いコンテンツが生まれる場所になりがちなようである。まるでグッドハートの法則(一度足度が目的になると、その尺度はもう良い尺度とは言えなくなる)のように、「いいね」を集めるという一つの目的に向かってみんなが競争しており、創造的な世界が構築されるようになったというより、自分を苦しめることにつながっている。社会脳の確立の時期にある子どもたちは、逆に自分にとって大事なことにじっくり取り組めなくなり、不安を高めている場合も多いのである。 それゆえに、法律で禁止する国が出てくるなど、利用の時間を区切り、制限することで、現実の時間を増やし、人間の生活の全体性を同復させることが必要とされてきている。 ・先に若者たちが外見にフォーカスするようになっていると専門家たちが問題視していると述べた。 1997年、アメリカの心理学者バーバラ・フレドリクソンとトミ・アン・ロバーツは他者からの評価を内在化して、自己の容姿にとらわれるようになることを「自己のモノ化(selfobjectification)」と呼んだ。例えば、ある女性をその人の人格を見るのではなく、モノとして見るような発言、「顔が小さいね」「スタイルがいいね」「胸が大きいね」などパーツだけを重要視する発言に接したり、写真としても、スタイル抜群のセクシーな女性しか雑誌の中にいなかったりすることは多く、そのように他人が女性の外見しか気にせず、まるでモノのように見てくることで、女性たちが「自分で自分をモノのように扱うようになっていくこと」を指摘したのだ。そしてこの自己のモノ化は、自尊心の低下、人生の満足度の低下を引き起こし、自分の体に対する羞恥心や不安感から、摂食障害、鬱病、性機能障害にもつながることがわかってきた。 「スタイルが良くなければいけない」などと思い込んで、自分の体をその他人から与えられた理想に合わせようとコントロールしていく時に、うまくいかずに自言を喪失したり、行きすぎて摂食障害を患ってしまったりするのである。興味深いことに、自分をモノ化する傾向の高い女性は、自分の実際の身体の感覚に疎くなることが示されている。 ファッション(見た目)のほうが寒さ(自分の身体が感じていること)よりも大事で、自分の身体からの情報を積極的に無視したり、自然と身体からの情報に疎くなったりすることが示唆された。つまり自分で感じることよりも他人からどう見えるかを大事にすると、自分が「ヒト」ではなく「モノ」であるかのように、「感じる」ことが少なくなってしまうのだ。 ・昔は雑誌やテレビなどを参照していたのだが、今はSNSがそれらの代わりとなった。そこではモデル、セレブリティという見知らぬ他者の姿をただ見かけるだけではなく、友人、知人のアップした姿を目撃するようになった。比較する他者の数が膨大になったのである。また、一方的に見るだけではなく、自分の写真もあげることになり、さらにはそれについて他者からさまざまなコメントがつくようになった。比較の激化である。 近しい友人や、少し距離のある仲間たちと自分を毎日比べていることのほうが、モデルやセレブリティたちと比べることよりも自分の体に対する不満を高めることが明らかになっている。 モデルやセレブリティの着ているドレスは高すぎて、自分には手が届かなかったり、スタイルも自分とはかけ離れていたりして非現実的だが、身近な人の素敵な姿は、我々にとって達成可能であるために、比較対象として、遠い人より身近な人から我々は大きな影響を受けるという。 私たちは自己のモノ化が圧倒的に進む条件に生きている。 ・この研究で特に面白いのは、顔を出さないこと、顔を意図的にぼかすことは、その人の人格を剥ぎ取ることだと理解されていることだ。特に英語圏の研究では、顔を出さずに身体だけに注目することが代表的なモノ化の例になっている。日本人が自ら顔にスタンプを貼るなど顔を消して写真をアップしたり、友達以外の他人には自分とわからないほどに顔を加工したりしていることは、自分を守る手段でありながら、英語圏の人々よりも、自分を人でなくモノとして見ているからなのかもしれない。確かに日本は、Twitter(調査時。現在のX)の使い方を見ても、匿名で使っている人が多く・日常で人格を消す傾向が他の国に比べて高いと言える。 感情が企業の商品となって、やりとりされることが従来の感情労働の問題だったが、SNS の登場により私たちは自分で自分をモノにして、やりとりしてしまっているのである。 ・今、みなさんは、困ったことがあった時にどれくらい人に助けを求めようとするだろうか? 日本人など東アジアの人々は、西洋の人々に比べて、助けを求めることに対して抵抗を感じる人が多いという。確かに、私自身、「こんなことを質問していいのかな」「人に迷惑をかけるのではないかな」「これが欲しいけれど、それを口にしたら拒絶されるのではないかな」「バカだと思われるのではないかな」と感じて、自分にとって必要なことを言わないでいることがたくさんある。 社会的支援とは、困った時に直接的に助けてもらったり、感情的に寄り添ってもらったりして、「自分は他人から愛され、価値あるものとされ、互恵的な関係性の一部になっていると感じられること」をいう。それは私たちにとってもちろん必要なものである。例えば、痛みを感じている時に、頼している人が手をつないで寄り添ってくれていると、脳の中で痛みを感じている時に働く部位の反応が弱まる。そして社会的支換があると感じられていると、病気などからの回復も早くなることが知られている。テイ・ショウホウら一橋大学と名古屋大学の共同研究によると、生きていくためには必要なものなのに、私たち東アジアの人々が助けをあまり求められないのは、実は、他者が困っている時にも、あまり哀れみを感じないからであるという。東アジアは「集団」の文化で、自分と他者を西洋の人々よりもつながった存在であると見ており、自分自身の目標よりも、集団の目標のほうを重んじる傾向がある。そのような文化ではどうしても集団に対する責任感が強くなり、自分が自分の目的を達成するために「助けて」と口にするのは、集団にとって「迷惑になる」可能性があるから抵抗を感じ、他者が困っている時も、それは集団に対してその人がなんらかの悪いことをしたからだろうと類推するから、同情が薄くなるのだという。逆に、アメリ 力などの「個」の文化では、自分と他者は違う存在というのが前提であり、自分の目的で行動するので、それが失敗した時には、「悪いことをしたから」ではなくて、「そもそもうまくいくかどうかはわからないから」で、他人が失敗した時にも自分もそうなのだからと助ける傾向になるという。 他人と自分を切り離さない人のほうが、困った時に他人に冷たくなりやすいというのは衝撃ではないか?そして私たちは、集団に対する責任感から、集団に合わせる思考法をしていて、「人の迷惑になる」「私の要求は人に拒絶される」のが当然という見積もりをしているという。 私たちは、人に迷惑をかけないようにと常に他者を気遣い、自分よりも集団を優先することで、「感情労働をして疲れる」と言っているが、それで人に優しくなっているというよりも、互いに「助けない」という、孤立の道を歩んでいるのかもしれないのである。だとすればその「労働」の意味はあるのだろうか?私たちは感情を動かし、やりたいことを実現できるように努力し、他人のやりたいことも叶えるよう手伝い、今より良く生きられる、今より良い社会を作り上げるというのではなく、ただなんとなく今の社会に合わせて、自分たちを抑え、自分たちの価値がわからなくなるという方向で感情を使っているのである。 実際に私たちの自己肯定感は下がっている。日本の特に若者、小中高生の自殺者数は2024年で529人、過去最多となったという。わかりやすさを求めて全てを明示的にするように力を使い、他人と自分を頻繁に比較し、「迷惑にならないように」と規律的に動いて、安心して暮らせる場所を作っているつもりで、実際には安心して存在することができなくなっている。 私たちは自分の弱さをもう少し見せ合って、かけがえのなさを取り戻さなければならないのではないか? 人の心を理解することがうまくできるようになる前に、情報過多のSNS時代を生きる私たちは、見えにくいものを見えやすく加工するという力の使い方をしている。それは推し活で見るように創造力の一つの発揮ではあるのだが、自分で「感じる」という心の動きはおろそかにされているようである。現代特有の見直されるべき感情労働とは、膨大な他者の中で一人の人のかけがえのなさを忘れる方向に努力していることなのかもしれない。 - 2026年2月18日
 感情労働の未来恩蔵絢子AI時代、人間が持つ最大の能力は、感情になる! 感情を抑圧し“他者にあわせる”ストレスフルな現代から、“他者を理解する”感情的知性の未来へ。人間の可能性に話題の脳科学者が迫る。 AIが人間の代わりにできることが増えたことで、重視されるもの(IQ→EQ)が変わってきている。 コロナで不必要なものを排除する動きが加速したが、排除したことによる新たなストレスも見つかってきている。 不確かさを認識することの大切さを感じると共に、不確かであるからこそ今まで重視されず見落とされてきたものが重視されていく点には希望を感じた。 ◾️感情とは何か ・感情とは「正解がわかる前に、体を動かす力」「正解がなくとも、意思決定する力」(日常生活から、道徳的な意思決定に至るまで)だ。感情は、新しい物事の到来を自分に知らせるものであると同時に、自分の価値判断であり、世界に対する今の自分の解釈を表すものでもある。 ・感情の特徴 1 感情は初めての時に一番動く 2 感情が動いたことは強く記憶される 3感情は速い(そして感情は変わっていくものである) 4感情は個人差・文化差がある ・世界の不確実性(ほとんどのことに正解がない)に適応するために感情は進化してきた。ある状況に対してみんなが同じ反応を示したら、その反応が結局良くないものであった場合、人類自体が滅びてしまうかもしれず、それぞれが別々の反応をすることが、人類の生き延びる戦略となっており、だからこそ個人差や文化差が大事。 ・これまで、今何をすべきで、何をすべきでないかという「道徳的」判断は、感情ではなく、人間の理性が司ると考えられてきた。しかし、理性的能力、すなわち言語能力や記憶力という知的能力が残っていても、他者に対して適切に振る舞うことはできなかったのである。ゲージ氏は、道徳の源は感情であり、感情がなければ、人間は道徳的には振る舞えないという可能性を示唆した。また道徳的判断だけではなくて、「次は何をしようか」という日常の小さな意思決定も、苦手になっていた。感情、すなわち、身体の反応が、私たちの意思決定には必要なのではないか、この仮説をアメリカの神経科学者アントニオ・ダマシオらは、「ソーマティック・マーカー仮説」と名づけている。日常的な意思決定から、道徳などの高尚に見える意思決定に至るまで、感情が重要な役割を果たしていると考えられるのである。 ◾️感情労働とは ・「感情労働」は企業イメージのために個人の感情の動かし方が企業の規則で決められること、個人の感情が商品化され搾取されることから始まった。(客室乗務員、金の取立て) ・ホックシールドは、「どういうふうに感じるか」「何を表出するか」ということを管理されてしまうと、自分の感情のどこからどこまでが企業のもので、どこからどこまでが自分のものなのかがわからなくなってしまうという問題があると言うのだ。そうやって個人の感情が企業に搾取されていることを指摘する言葉が、「感情労働」という言葉なのだ。 ・感情労働を求められる職業に共通する三つの特徴 (1) 対面あるいは声による顧客との接触が不可である。 (2)他人の中に何らかの感情変化ー感謝の念や恐怖心等ーを起こさせなければならない。 (3)雇用者は、研修や管理体制を通じて労働者の感情活動をある程度支配する。 ・自分の知らぬところで動いている感情の影響は大きいが、それを抑え、修正し、感情労働をすることは可能である。そして燃え尽き症候群とは、感情を動かすのは力のいることであり、感情自体も限られた資源である、ということなのだ。 ・感情労働の手段は「表層演技(surface acting)」(脳科学では「感情の抑制(emotional suppression)」と呼ばれる)と「深層演技(deep acting)」(脳科学では「認知的再評価(cognitive reappraisal)」と呼ばれる)の二つある。この手段で感情をコントロールすることは可能だが、身体が休みなく無限に動かせるわけではないのと同じように、感情を動かすにも限界がある。感情を自分のものか、企業のものかわからなくなるほどに使いすぎてしまえば、これ以上の感情的消耗を避ける必要が生まれ、感情がこれ以上動かせなくなり、他人の気持ちがどうでも良くなり人間扱いできなくなったり、自分に対してもそうなって、休日になっても「自分」という感覚が戻らなかったり、自分の価値がわからなくなってしまったりするのである。 ・脳には、無意識のうちに企業や他者に合わせるような仕組みもあることがわかっている。知らず知らずやっている感情の書き換えがあり、その一つは「認知的不協和(cognitive dissonance)」という現象。もう一つ、脳には無意識のうちに上司やリーダーに合わせるような仕組みもある。(前頭葉を人に明け渡してしまうことは、危険。それは依存関係になるということであり、人を利用し、人に自分が利用されるということも起こり得る。そして自分自身が決定して、その行動の結果の責任を取ることができないために、成功の喜びを感じたり、失敗の痛みを感じて学んだりすることもできなくなってしまう。) ・仕事場でなく、家庭の中や、友人同士という私的な領域で行われる、相手の気持ちを考えて行動することを「感情作業」と呼ばれているが、脳から見ると、その方法自体や脳に起こり得る結果は同じ。 ◾️脳はどのようにして人の心を理解するのか ・「人間らしさ」の一つの定義は、人間に独特な意識や、自意識、他者意識を持ち、自分とは違う他者のことを思いやって行動できることである。しかし他者を思いやるというのは、自分を消して他者に合わせるという意味ではなく、自分の気持ちも他者の気持ちも大事にし、自分の感じていることを伝え合い、交渉し、時にはぶつかったり、嫌な気持ちになったり、させたりしながら、その責任を取り、調和して暮らせるようになることだ。 ・第一印象で思ったことを言うのにはあまり苦労はいらないのだ。言わないでいること、言い方を考えることには努力を要し、認知的な負荷がかかる。すなわち人の気持ちを考えて、自分の感情を表出する、というのは、感情と高次認知機能の共同作業であり、それが、感情労働の基本的な仕組みなのである。また感情労働に関し、ここで言えるのは、認知的負荷がかかっている時、感情抑制はしにくいということだ。仕事が忙しすぎたり、悩みがあったりすると、人に優しくすることはできない。自分に負荷がかかりすぎている時は、人よりもむしろ自分のほうが大切にされるべきだと感じて、自分の要求ばかりを人に伝えてしまうこともある。自分で持てる以上の荷物をなるべく持たないことが大事で、人に優しくできなくなったらそれは、荷物を減らせというサインなのである。 ・テレフォンオペレーターなどのように他者から苦情を受けて、感情労働をすることが必須な仕事にAIを導入し、相手の音声から感情をリアルタイムでパターン認識して、その人の感情労働を補助するシステムは登場しはじめている。しかしそのようなシステムはまだ、繰り返し使っていると、いつも似たような励ましになることが多く、オペレーターが効果を感じにくくなっていく点があり、今のところは人間の代わりになっているとは言えない状況である。AIの導入で、むしろ人間にやっかいな感情労働が増えるという研究もある。感情労働は、今一番得意なのが人間で、知的能力とは別種の知性といっていいのである。人間の可能性が一番あるのもここなのかもしれない。 ・大規模言語モデルは、通常一人の人間が蓄えられる知識を遥かに超えた知識を持ち、人間とは違う方法で進化する。今のところ、大規模言語モデルは自分から何かを考えたり、やりたいことを持ったりすることはなく、一つの人格や意識を持っているようには見えず、むしろ人類全ての平均のような意見を、頼まれた時にだけ出力してくる存在である。私たちがこの知性を鏡として、自分たちの能力を見直していく中で明らかになってきたことの一つは、人工知能ができるようになったことは、人間の能力とは認めなくなる傾向が私たちにはあるということで、これは「AIエフェクト」と呼ばれる。かつては言葉をしゃべることが他の動物とは違う人間の偉大な能力と考えられていたが、言葉はAIでもしゃべれるようになり、人間だけの特徴とは言われなくなった。それでは人間だけの特徴はどこなのだということになって、「感情的になるな」「知性が大事だ」などと言われてきたように長い間自分たちがあまり見ようとしてこなかった感情の領域が、今重要になってきたのである。 ・マサチューセッツ工科大学のトマス・マローンらは、視覚的なパズルを解く、ブレインストーミングをする、道徳的な判断を行う、限られた資源の分配について交渉するなどの多様な課題を用意し、チームごとにやらせて、どんなチームが一番安定して、成績が良くなるかを調べた。チームとしてさまざまな課題に対して高い成果を出すために、一番関係があったのは、そのチーム内に、人の気持ちにどれだけ敏感かという「社会的感受性」が高い人がいるかどうかだった。 ・アメリカの心理学者、ダニエル・ウェグナーが1985年に集団としての記憶を「トランザクティブ・メモリー(交換記憶)」と名づけた。トランザクティブ・メモリーのおかげで、カップルや家族は、一人で暮らすよりも遥かに複雑で効率的な処理ができるようになる。ここで面白いのは、トランザクティブ・メモリーが機能するのは、一人ひとり個性が違っていて、相手が何が得意で何が苦手なのか、相手は何をやりたがるのか、相手がどんな人なのかをよく知っている親密な集団に限るということだ。1Qの高さなどではなく、その人の全人格を知るように人と人が関わっていることが必要で、寄せ集めのこの場限りの集団ではうまくいかないという。 人の気持ちに敏感であること、またゆっくりと関係を築き、長所や矢点をよく理解し、それでもつながっているということが、集団的知性の発揮には重要なのである。 ・人と自分とを同じ存在だと考えないのが重要ということである。共感(同じ気持ちになること)と人間理解は異なっていて、本当に他人を理解するためには、むしろ他者と自分を切り離さなくてはならない。共感することは人とわかりあえたという感じのすることであり、「共感=人間理解」と思う人が多いのだが、それだけではうまくやれないことがあるのだ。 ・自分と切り離して相手を理解し、集団のために役立てるという感情労働が人間にとってとても難しいのは確かだ。人間の人間理解の根本は、やはり共感にあるからだ。相手に共感をした上で、切り離す、という2段階構造が人間理解なのである。人間には何も言葉にしないでも感情が伝わってくることがある。このような能力は今のところAIには存在しない。だからAIは我が道を貫けるところがあるのだが、人間は言葉を使わずに高速で感情をやりとりし、他人と同調してしまうところがある。これは人間の長所でもあり、短所でもある。 ・みなさんの経験でも、他人の痛み、喜び、悲しみ、緊張などの強い感情は即座に伝わるものだと感じているのではないだろうか?これは専門的には「情動的共感(emotional empathy)」と呼ばれる。島皮質や前部帯状回が情動的共感の脳基盤とされている。これらのおかげで人間はAIとは違って、すばやくリアルタイムに言葉を介さずに、他者とつながれるのである。 この人は自分と違ってこういうことを考えているのだろうと、言語的に推論するのではなく、ほぼ自動的に相手が痛みを感じていたら自分の痛みであるかのように反応したり、相手をもっともっとと求めたりして、心を重ねる。どんどん一体化していくのである。 親子が最初に積み上げていくのが情動的共感であることからわかるように、私たちは他者と情動的にしっかり結びつくことが必要なのだ。恋愛関係でも同じように、恋人の写真を見ている時は、親友の写真を見ている時に比べて、相手を批判的に見る部位の活動が下がり、報酬系の活動が高まる。すなわちもっともっとと相手を求めて相手と狂おしいほど一体化するというのが人間関係の始まりなのだが、こうして他者と一体化してしまう仕組みがあることの欠点として、いつまでも親離れ、子離れがしにくく、過剰な期待を相手に押しつけ、小さな子どもや高齢の親を、思い通りにならないことで、大人が虐待する要因にもなってしまう。恋人関係でも、依存関係となり、相手に自分と同じように考えてもらうこと、自分の要求に応じてもらうことだけが大事になり、疲弊する関係になってしまったりする。「相手が自分の期待に沿ってくれる=自分が愛されていると感じる」ということになるともう、自分とは違う一人の人を尊重ることとは正に対で、相手の気持ちは見えなくなっている。自分と相手を一体化するというのは究極的には自分の心も相手の心もなくすことなのだ。 ・自分がやりたいことと、他人がやりたいこととがあって、それが食い違うからこそ、人のことを理解するという感情労働が存在する。他人を自分に合わせさせる、自分を他人に合わせる脳の使い方だけでは、その場だけで「一体になれた!」という大きな喜びは得られるけれども、それは相手と自分を理解することとは程遠い。同じ気持ちになることで快を感じて「欲しい」の回路を回すことは、相手を自分の思い通りにコントロールすることにつながっているのであり、自分の感情のコントロールでもなければ、人を理解することでもないのである。 依存関係に陥らず、本当に人間を理解するためには、自分の必要と、相手の必要は食い違って当然なのだから、共感した上で切り離すという大きな痛みを取らなくてはならない。
感情労働の未来恩蔵絢子AI時代、人間が持つ最大の能力は、感情になる! 感情を抑圧し“他者にあわせる”ストレスフルな現代から、“他者を理解する”感情的知性の未来へ。人間の可能性に話題の脳科学者が迫る。 AIが人間の代わりにできることが増えたことで、重視されるもの(IQ→EQ)が変わってきている。 コロナで不必要なものを排除する動きが加速したが、排除したことによる新たなストレスも見つかってきている。 不確かさを認識することの大切さを感じると共に、不確かであるからこそ今まで重視されず見落とされてきたものが重視されていく点には希望を感じた。 ◾️感情とは何か ・感情とは「正解がわかる前に、体を動かす力」「正解がなくとも、意思決定する力」(日常生活から、道徳的な意思決定に至るまで)だ。感情は、新しい物事の到来を自分に知らせるものであると同時に、自分の価値判断であり、世界に対する今の自分の解釈を表すものでもある。 ・感情の特徴 1 感情は初めての時に一番動く 2 感情が動いたことは強く記憶される 3感情は速い(そして感情は変わっていくものである) 4感情は個人差・文化差がある ・世界の不確実性(ほとんどのことに正解がない)に適応するために感情は進化してきた。ある状況に対してみんなが同じ反応を示したら、その反応が結局良くないものであった場合、人類自体が滅びてしまうかもしれず、それぞれが別々の反応をすることが、人類の生き延びる戦略となっており、だからこそ個人差や文化差が大事。 ・これまで、今何をすべきで、何をすべきでないかという「道徳的」判断は、感情ではなく、人間の理性が司ると考えられてきた。しかし、理性的能力、すなわち言語能力や記憶力という知的能力が残っていても、他者に対して適切に振る舞うことはできなかったのである。ゲージ氏は、道徳の源は感情であり、感情がなければ、人間は道徳的には振る舞えないという可能性を示唆した。また道徳的判断だけではなくて、「次は何をしようか」という日常の小さな意思決定も、苦手になっていた。感情、すなわち、身体の反応が、私たちの意思決定には必要なのではないか、この仮説をアメリカの神経科学者アントニオ・ダマシオらは、「ソーマティック・マーカー仮説」と名づけている。日常的な意思決定から、道徳などの高尚に見える意思決定に至るまで、感情が重要な役割を果たしていると考えられるのである。 ◾️感情労働とは ・「感情労働」は企業イメージのために個人の感情の動かし方が企業の規則で決められること、個人の感情が商品化され搾取されることから始まった。(客室乗務員、金の取立て) ・ホックシールドは、「どういうふうに感じるか」「何を表出するか」ということを管理されてしまうと、自分の感情のどこからどこまでが企業のもので、どこからどこまでが自分のものなのかがわからなくなってしまうという問題があると言うのだ。そうやって個人の感情が企業に搾取されていることを指摘する言葉が、「感情労働」という言葉なのだ。 ・感情労働を求められる職業に共通する三つの特徴 (1) 対面あるいは声による顧客との接触が不可である。 (2)他人の中に何らかの感情変化ー感謝の念や恐怖心等ーを起こさせなければならない。 (3)雇用者は、研修や管理体制を通じて労働者の感情活動をある程度支配する。 ・自分の知らぬところで動いている感情の影響は大きいが、それを抑え、修正し、感情労働をすることは可能である。そして燃え尽き症候群とは、感情を動かすのは力のいることであり、感情自体も限られた資源である、ということなのだ。 ・感情労働の手段は「表層演技(surface acting)」(脳科学では「感情の抑制(emotional suppression)」と呼ばれる)と「深層演技(deep acting)」(脳科学では「認知的再評価(cognitive reappraisal)」と呼ばれる)の二つある。この手段で感情をコントロールすることは可能だが、身体が休みなく無限に動かせるわけではないのと同じように、感情を動かすにも限界がある。感情を自分のものか、企業のものかわからなくなるほどに使いすぎてしまえば、これ以上の感情的消耗を避ける必要が生まれ、感情がこれ以上動かせなくなり、他人の気持ちがどうでも良くなり人間扱いできなくなったり、自分に対してもそうなって、休日になっても「自分」という感覚が戻らなかったり、自分の価値がわからなくなってしまったりするのである。 ・脳には、無意識のうちに企業や他者に合わせるような仕組みもあることがわかっている。知らず知らずやっている感情の書き換えがあり、その一つは「認知的不協和(cognitive dissonance)」という現象。もう一つ、脳には無意識のうちに上司やリーダーに合わせるような仕組みもある。(前頭葉を人に明け渡してしまうことは、危険。それは依存関係になるということであり、人を利用し、人に自分が利用されるということも起こり得る。そして自分自身が決定して、その行動の結果の責任を取ることができないために、成功の喜びを感じたり、失敗の痛みを感じて学んだりすることもできなくなってしまう。) ・仕事場でなく、家庭の中や、友人同士という私的な領域で行われる、相手の気持ちを考えて行動することを「感情作業」と呼ばれているが、脳から見ると、その方法自体や脳に起こり得る結果は同じ。 ◾️脳はどのようにして人の心を理解するのか ・「人間らしさ」の一つの定義は、人間に独特な意識や、自意識、他者意識を持ち、自分とは違う他者のことを思いやって行動できることである。しかし他者を思いやるというのは、自分を消して他者に合わせるという意味ではなく、自分の気持ちも他者の気持ちも大事にし、自分の感じていることを伝え合い、交渉し、時にはぶつかったり、嫌な気持ちになったり、させたりしながら、その責任を取り、調和して暮らせるようになることだ。 ・第一印象で思ったことを言うのにはあまり苦労はいらないのだ。言わないでいること、言い方を考えることには努力を要し、認知的な負荷がかかる。すなわち人の気持ちを考えて、自分の感情を表出する、というのは、感情と高次認知機能の共同作業であり、それが、感情労働の基本的な仕組みなのである。また感情労働に関し、ここで言えるのは、認知的負荷がかかっている時、感情抑制はしにくいということだ。仕事が忙しすぎたり、悩みがあったりすると、人に優しくすることはできない。自分に負荷がかかりすぎている時は、人よりもむしろ自分のほうが大切にされるべきだと感じて、自分の要求ばかりを人に伝えてしまうこともある。自分で持てる以上の荷物をなるべく持たないことが大事で、人に優しくできなくなったらそれは、荷物を減らせというサインなのである。 ・テレフォンオペレーターなどのように他者から苦情を受けて、感情労働をすることが必須な仕事にAIを導入し、相手の音声から感情をリアルタイムでパターン認識して、その人の感情労働を補助するシステムは登場しはじめている。しかしそのようなシステムはまだ、繰り返し使っていると、いつも似たような励ましになることが多く、オペレーターが効果を感じにくくなっていく点があり、今のところは人間の代わりになっているとは言えない状況である。AIの導入で、むしろ人間にやっかいな感情労働が増えるという研究もある。感情労働は、今一番得意なのが人間で、知的能力とは別種の知性といっていいのである。人間の可能性が一番あるのもここなのかもしれない。 ・大規模言語モデルは、通常一人の人間が蓄えられる知識を遥かに超えた知識を持ち、人間とは違う方法で進化する。今のところ、大規模言語モデルは自分から何かを考えたり、やりたいことを持ったりすることはなく、一つの人格や意識を持っているようには見えず、むしろ人類全ての平均のような意見を、頼まれた時にだけ出力してくる存在である。私たちがこの知性を鏡として、自分たちの能力を見直していく中で明らかになってきたことの一つは、人工知能ができるようになったことは、人間の能力とは認めなくなる傾向が私たちにはあるということで、これは「AIエフェクト」と呼ばれる。かつては言葉をしゃべることが他の動物とは違う人間の偉大な能力と考えられていたが、言葉はAIでもしゃべれるようになり、人間だけの特徴とは言われなくなった。それでは人間だけの特徴はどこなのだということになって、「感情的になるな」「知性が大事だ」などと言われてきたように長い間自分たちがあまり見ようとしてこなかった感情の領域が、今重要になってきたのである。 ・マサチューセッツ工科大学のトマス・マローンらは、視覚的なパズルを解く、ブレインストーミングをする、道徳的な判断を行う、限られた資源の分配について交渉するなどの多様な課題を用意し、チームごとにやらせて、どんなチームが一番安定して、成績が良くなるかを調べた。チームとしてさまざまな課題に対して高い成果を出すために、一番関係があったのは、そのチーム内に、人の気持ちにどれだけ敏感かという「社会的感受性」が高い人がいるかどうかだった。 ・アメリカの心理学者、ダニエル・ウェグナーが1985年に集団としての記憶を「トランザクティブ・メモリー(交換記憶)」と名づけた。トランザクティブ・メモリーのおかげで、カップルや家族は、一人で暮らすよりも遥かに複雑で効率的な処理ができるようになる。ここで面白いのは、トランザクティブ・メモリーが機能するのは、一人ひとり個性が違っていて、相手が何が得意で何が苦手なのか、相手は何をやりたがるのか、相手がどんな人なのかをよく知っている親密な集団に限るということだ。1Qの高さなどではなく、その人の全人格を知るように人と人が関わっていることが必要で、寄せ集めのこの場限りの集団ではうまくいかないという。 人の気持ちに敏感であること、またゆっくりと関係を築き、長所や矢点をよく理解し、それでもつながっているということが、集団的知性の発揮には重要なのである。 ・人と自分とを同じ存在だと考えないのが重要ということである。共感(同じ気持ちになること)と人間理解は異なっていて、本当に他人を理解するためには、むしろ他者と自分を切り離さなくてはならない。共感することは人とわかりあえたという感じのすることであり、「共感=人間理解」と思う人が多いのだが、それだけではうまくやれないことがあるのだ。 ・自分と切り離して相手を理解し、集団のために役立てるという感情労働が人間にとってとても難しいのは確かだ。人間の人間理解の根本は、やはり共感にあるからだ。相手に共感をした上で、切り離す、という2段階構造が人間理解なのである。人間には何も言葉にしないでも感情が伝わってくることがある。このような能力は今のところAIには存在しない。だからAIは我が道を貫けるところがあるのだが、人間は言葉を使わずに高速で感情をやりとりし、他人と同調してしまうところがある。これは人間の長所でもあり、短所でもある。 ・みなさんの経験でも、他人の痛み、喜び、悲しみ、緊張などの強い感情は即座に伝わるものだと感じているのではないだろうか?これは専門的には「情動的共感(emotional empathy)」と呼ばれる。島皮質や前部帯状回が情動的共感の脳基盤とされている。これらのおかげで人間はAIとは違って、すばやくリアルタイムに言葉を介さずに、他者とつながれるのである。 この人は自分と違ってこういうことを考えているのだろうと、言語的に推論するのではなく、ほぼ自動的に相手が痛みを感じていたら自分の痛みであるかのように反応したり、相手をもっともっとと求めたりして、心を重ねる。どんどん一体化していくのである。 親子が最初に積み上げていくのが情動的共感であることからわかるように、私たちは他者と情動的にしっかり結びつくことが必要なのだ。恋愛関係でも同じように、恋人の写真を見ている時は、親友の写真を見ている時に比べて、相手を批判的に見る部位の活動が下がり、報酬系の活動が高まる。すなわちもっともっとと相手を求めて相手と狂おしいほど一体化するというのが人間関係の始まりなのだが、こうして他者と一体化してしまう仕組みがあることの欠点として、いつまでも親離れ、子離れがしにくく、過剰な期待を相手に押しつけ、小さな子どもや高齢の親を、思い通りにならないことで、大人が虐待する要因にもなってしまう。恋人関係でも、依存関係となり、相手に自分と同じように考えてもらうこと、自分の要求に応じてもらうことだけが大事になり、疲弊する関係になってしまったりする。「相手が自分の期待に沿ってくれる=自分が愛されていると感じる」ということになるともう、自分とは違う一人の人を尊重ることとは正に対で、相手の気持ちは見えなくなっている。自分と相手を一体化するというのは究極的には自分の心も相手の心もなくすことなのだ。 ・自分がやりたいことと、他人がやりたいこととがあって、それが食い違うからこそ、人のことを理解するという感情労働が存在する。他人を自分に合わせさせる、自分を他人に合わせる脳の使い方だけでは、その場だけで「一体になれた!」という大きな喜びは得られるけれども、それは相手と自分を理解することとは程遠い。同じ気持ちになることで快を感じて「欲しい」の回路を回すことは、相手を自分の思い通りにコントロールすることにつながっているのであり、自分の感情のコントロールでもなければ、人を理解することでもないのである。 依存関係に陥らず、本当に人間を理解するためには、自分の必要と、相手の必要は食い違って当然なのだから、共感した上で切り離すという大きな痛みを取らなくてはならない。 - 2026年2月18日
 毎日読みますファン・ボルム,牧野美加また読書に関する本。 どこかに私と同じように本を読み、本に救われている人がいると思うだけで、幸せな気持ちになる。 また読みたい本が大量に増えてしまった。。 ・本を読むことは、わたしとは切っても切り離せないものだ。人生で問題が起きたら、最終的には本に答えを求めるしかないのだから。世の中が、人生が、自分自身が、あなたのことが気になるとき、理解できないとき、知りたいときは、やはり本を開くしかないのだから。 本が毎回明確な道を示してくれたわけではないけれど、手がかりは与えてくれた。どの道を行けば、求めている答えを見つけられるだろう、という手がかり。わたしはその手がかりを握りしめ、見知らぬ道へと足を踏み出した。そうやって本を読んでいるうちにわかったことがある。何も持たずに道を歩んでいくときよりも、誰かが丁寧に握らせてくれた手がかりを頼りに歩んでいくときのほうが、わたしは、より勇気ある、より揺らがない人間になれるという点だ。 少しの勇気と、少しの強さを、わたしは本から得た。 ・退屈で、物語が恋しくて、虚しくて、友だちに共感したくて、世の中に希望を持ちたくて、そして究極的には、ただただ何かが読みたくて、わたしは毎日本を読んできた。これからも読みつづけるだろう。 ・いつだったか、人間は自分の手で作った物をより高く評価する、という文章を読んだことがある。目の前の友人の作ったものとそう変わらない紙飛行機を作ったとしても、アイデアを絞って一生懸命作ったぶん「わたしの紙飛行機」のほうが価値あるように感じられる、という内容だった。わたしも、無限大から「1を引く」ことに費やした労力を思い、「わたしの本」を高く評価していた。書店で苦労して選んだ本が並ぶ「わたしの本棚」は、もはやリビングにある本棚とは比べ物にならなかった。 ・「君は君の人生を変化させなければならない」それが、パトリック・ジュースキントが結論づけた、わたしたちが本を読む理由だ。わたしはその文章を頭の中で何度もつぶやきながら、もし一冊の本を読む前の自分と読んだあとの自分が少しでも変化していたなら、たとえその本を読んだことすら覚えていなくても問題ないのだと自分を慰めた。 ・そういう場面に、わたしは本のロマンを見いだす。本はロマンチックだ。本を読む人もそうだ。本の中に深く潜り込んでいる人だけが放つ空気。その雰囲気。その視線。この世でもっともひそやかで静かな変化は本を読んでいる人の内面で起こっていて、その人の姿そのものが、わたしにとってはもっともロマンチックなイメージとなる。だからわたしもそのイメージの中に一度入ってみたいのだ。 ・かつて人文学ブームのさなか、人々は、本をたくさん読めば成功できるだろうと期待した。 絶望だらけの社会に本が希望をもたらしてくれるなら、実に喜ばしいことだ。けれどわたしは、本の効用が社会的成功にあるとは思えなかった。わたしの読書法では、シェークスピアの戯曲と資本主義の成功公式を結びつけることができなかったからだ。荘子の本を読んだ人が、あるいは「無用之用」を理解した人が、果たして成功だけを望むだろうか?成功を求めて人文学の本を読みはじめたとしても、最終的には、成功ではなく人生に目覚めるのではないだろうか。 「おまえは本に何を求めているのか?」という問いに対するわたしの答えは、こう続く。本を読んで強くなりたい。より揺らがない、よりどっしりした人間になりたい。傲慢でもなく、無邪気でもない人間になりたい。自分の感情に率直でありながらも、感情に振り回されないようになりたい。大げさに言えば知恵を得たい、日常生活では賢明になりたい。世の中を理解し、人間のことがわかるようになりたい。 こうやって答えを羅列してみると少々気恥ずかしい。いっそ成功を望むほうが簡単そうだ。 今の自分の姿と、自分の望む姿とのギャップがとてつもなく大きいという事実を思えば、なおのこと。一方では、こうした望みの数々が、自分が本を読むもっとも強い原動力になっていることも知っている。「欠如」が人を導くように、数多くの「不十分さ」がわたしを本の中へと 導く。 ・本を読む人が、読まない人より揺らがないように見えるのは、読む人の心の中にある「人生の本」のおかげかもしれない。人生で途方に暮れたとき、わたしは本を思い浮かべる。誰かの言葉に振り回される代わりに、自分の中の「人生の本」コレクションを頭に浮かべ、心の中で読むのだ。以前わたしを支えてくれた本が、今回も支えてくれる。人生の本が増えていくほどに、生きていく力が生まれる。 ・本を一冊読み終えて、次は何を読めばいいかわからないときは、「なぜこの本を良いと思ったんだろう?」と一度考えてみるのだ。そして、その「なぜ」をたどっていき、目には見えない本のつながりを頭の中に描いてみる。著者の思想が気に入ったのなら、その思想に影響を及ぼした作家は誰なのかを調べてみる。テーマが良いと思ったのなら、同じテーマのほかの本を検索してみる。引用句が特に印象的だったなら、引用された本を読んでみる。クモの巣のように緻密に張り巡らされた「読書の網」から、簡単には抜け出せなくなるはずだ。 ・とにかく結末は、ハッピーエンディングでなければサッドエンディングだ。望むものを手に入れても、入れられなくても、それがハッピーエンディングであれ、サッドエンディングであれ、エンディングが来れば物語は完成する。物語は、登場人物が望むものを手に入れようが入れまいが、そんなことはお構いなしだ。人生も物語だとすれば、同じことが言えるだろう。この人生は、わたしの成功や失敗には関心がない。その代わり、わたしがどれほどすごいことを望んだのか、それによってどれだけ自分の人生を鮮烈に感じ、また何を学んだのか、その結果、どんな語が生まれたのかーそういう問いだけが重要なのだろう。 ・絶望感、挫折感、不安、宙ぶらりんの存在、悲観的な見通し。エピローグの続きの文章に並ぶ言葉だ。カムフラージュしてはいるけれどわたしたちの内面に存在しているものでもある。 だからわたしは、読書とは、自分の人生の光と闇を、他人の人生の光と闇を受け入れることだと思う。作家の紡ぎ出す、人生の孤独な瞬間や満ち足りた瞬間。小説家の描き出す、複雑で立体的で、泣き、笑う人物たち。哲学者の目に映る、幸せだったり不幸せだったりする人物たち。 そして、そういう人物と大して変わらないわたしたち個々人が築いていく人生。わたしたちに知識が必要だとしたら、まさにそういう人生についての知識であるはずだ。 ・わたしたちは自分のことを隠して生きているが、本の中の人物たちは隠しては生きられない。 だからわたしは、彼らがさらけ出しているものを通して、わたしたちが隠しているものを見る。 わたしが、あなたが、ロ・ギワンのように人知れずむせび泣いている場面を見る。わたしはロ・ギワンが頭から離れず数日苦しんだ。もしかしたらそれは、この世のすべての「ロ・ギワン」たちを思う悲しみだったのかもしれない。 ・苦しい本を読んで楽しいはずがない。それでも逃げ出してはならない理由は、世の多くの真実というのはそのように不快で、苦しいものだからだ。楽に手に入れられる確合は、自己啓発書の言うところの「成功」には必要かもしれないが、真実とはかけ離れている。それゆえわたしたちには、苦しみに耐える力が必要なのだ。 ・イリイチは、人間のあらゆる行為が商品に従属し、わたしたちの人生が没収されていくさまを直視する。春の野に咲き乱れる花のように多様な美しさを持つ個々人の人生が商品によって標準化され、もはや誰が誰だか区別がつかないありさまだと危惧する。そういう社会で個人が自分の人生に満足するのは容易ではない。 自分を守る、自分を保護する読書が必要な理由がここにある。商品を積み上げるのではなく、世の中を理解する知識を積み上げるために。メディアの提案してくる幸せではなく、自分の望む幸せを追求するために。孤独なとき、マートではなく友人の家へと向かうために。安定感に飢えているとき、豪華な家を夢見るのではなく、今ここでシンプルな生活を営むために。自分の不安の根源をみずからたどっていくために。自分の選択をする際に自分の気持ちを蔑ろにしないために。自分の中の欲望を理解し、それを解消する方法を自分で見つけるために。そのために、わたしたちは本を読まねばならないのだ。 メディアの生み出すストーリーは、どうしようもなく誘惑的だ。強烈なイメージはしつこくわたしたちにまとわりつき、思考や行動を掌握する。自分ではないほかの誰かの利益を代弁するメディアに対抗できるよう、わたしたちみんなが自分の中に「物語の自販機」を一つずつ持つといいと思う。自分を力づけてくれる物語がどっさり入っている奇跡の自販機を。必要なときに心のスイッチを押して物語を一つずつ再生するのだ。 ・アンドリュー・パイパーの文章を読んで、わたしもハッとした。そうだ、本がなくなったら「読者」もいなくなるのだ。それは、わたしのアイデンティティーの一部がなくなるという意味だ。一日に何時間も、鉛筆でアンダーラインを引きながらページをめくり、夢中で読んでいるうちに夜一二時を回っていることに気づいて消灯するわたし。初対面の人を前にすると、この人は本を読む人だろうか、読まない人だろうかと心の中で推察し、もし読む人ならどんな本を読むのだろうと想像しながらも結局本人には聞けず、家に帰ってきてから考えるわたし。知り合って何年にもなる友人よりも同じ本を読んだ人のほうが話がよく通じると感じ、しきりに友人たちに本を薦めるわたし。ぱっとしない自分の生活も本のおかげでそれなりに良くなったと肩じ、本を一冊手にしていると世界とつながっているようで安心するわたし。そして、退屈なときや孤独なとき、腹が立っているときや憂鬱なとき、世の中や人間に嫌気がさしたときにわたしの心を立て直してくれた本たち。そういう本なしに、わたしは生きていけるだろうか?ああ、わたしも本のない世界なんて想像できない。わたしは死ぬまで読者として生きていたい。
毎日読みますファン・ボルム,牧野美加また読書に関する本。 どこかに私と同じように本を読み、本に救われている人がいると思うだけで、幸せな気持ちになる。 また読みたい本が大量に増えてしまった。。 ・本を読むことは、わたしとは切っても切り離せないものだ。人生で問題が起きたら、最終的には本に答えを求めるしかないのだから。世の中が、人生が、自分自身が、あなたのことが気になるとき、理解できないとき、知りたいときは、やはり本を開くしかないのだから。 本が毎回明確な道を示してくれたわけではないけれど、手がかりは与えてくれた。どの道を行けば、求めている答えを見つけられるだろう、という手がかり。わたしはその手がかりを握りしめ、見知らぬ道へと足を踏み出した。そうやって本を読んでいるうちにわかったことがある。何も持たずに道を歩んでいくときよりも、誰かが丁寧に握らせてくれた手がかりを頼りに歩んでいくときのほうが、わたしは、より勇気ある、より揺らがない人間になれるという点だ。 少しの勇気と、少しの強さを、わたしは本から得た。 ・退屈で、物語が恋しくて、虚しくて、友だちに共感したくて、世の中に希望を持ちたくて、そして究極的には、ただただ何かが読みたくて、わたしは毎日本を読んできた。これからも読みつづけるだろう。 ・いつだったか、人間は自分の手で作った物をより高く評価する、という文章を読んだことがある。目の前の友人の作ったものとそう変わらない紙飛行機を作ったとしても、アイデアを絞って一生懸命作ったぶん「わたしの紙飛行機」のほうが価値あるように感じられる、という内容だった。わたしも、無限大から「1を引く」ことに費やした労力を思い、「わたしの本」を高く評価していた。書店で苦労して選んだ本が並ぶ「わたしの本棚」は、もはやリビングにある本棚とは比べ物にならなかった。 ・「君は君の人生を変化させなければならない」それが、パトリック・ジュースキントが結論づけた、わたしたちが本を読む理由だ。わたしはその文章を頭の中で何度もつぶやきながら、もし一冊の本を読む前の自分と読んだあとの自分が少しでも変化していたなら、たとえその本を読んだことすら覚えていなくても問題ないのだと自分を慰めた。 ・そういう場面に、わたしは本のロマンを見いだす。本はロマンチックだ。本を読む人もそうだ。本の中に深く潜り込んでいる人だけが放つ空気。その雰囲気。その視線。この世でもっともひそやかで静かな変化は本を読んでいる人の内面で起こっていて、その人の姿そのものが、わたしにとってはもっともロマンチックなイメージとなる。だからわたしもそのイメージの中に一度入ってみたいのだ。 ・かつて人文学ブームのさなか、人々は、本をたくさん読めば成功できるだろうと期待した。 絶望だらけの社会に本が希望をもたらしてくれるなら、実に喜ばしいことだ。けれどわたしは、本の効用が社会的成功にあるとは思えなかった。わたしの読書法では、シェークスピアの戯曲と資本主義の成功公式を結びつけることができなかったからだ。荘子の本を読んだ人が、あるいは「無用之用」を理解した人が、果たして成功だけを望むだろうか?成功を求めて人文学の本を読みはじめたとしても、最終的には、成功ではなく人生に目覚めるのではないだろうか。 「おまえは本に何を求めているのか?」という問いに対するわたしの答えは、こう続く。本を読んで強くなりたい。より揺らがない、よりどっしりした人間になりたい。傲慢でもなく、無邪気でもない人間になりたい。自分の感情に率直でありながらも、感情に振り回されないようになりたい。大げさに言えば知恵を得たい、日常生活では賢明になりたい。世の中を理解し、人間のことがわかるようになりたい。 こうやって答えを羅列してみると少々気恥ずかしい。いっそ成功を望むほうが簡単そうだ。 今の自分の姿と、自分の望む姿とのギャップがとてつもなく大きいという事実を思えば、なおのこと。一方では、こうした望みの数々が、自分が本を読むもっとも強い原動力になっていることも知っている。「欠如」が人を導くように、数多くの「不十分さ」がわたしを本の中へと 導く。 ・本を読む人が、読まない人より揺らがないように見えるのは、読む人の心の中にある「人生の本」のおかげかもしれない。人生で途方に暮れたとき、わたしは本を思い浮かべる。誰かの言葉に振り回される代わりに、自分の中の「人生の本」コレクションを頭に浮かべ、心の中で読むのだ。以前わたしを支えてくれた本が、今回も支えてくれる。人生の本が増えていくほどに、生きていく力が生まれる。 ・本を一冊読み終えて、次は何を読めばいいかわからないときは、「なぜこの本を良いと思ったんだろう?」と一度考えてみるのだ。そして、その「なぜ」をたどっていき、目には見えない本のつながりを頭の中に描いてみる。著者の思想が気に入ったのなら、その思想に影響を及ぼした作家は誰なのかを調べてみる。テーマが良いと思ったのなら、同じテーマのほかの本を検索してみる。引用句が特に印象的だったなら、引用された本を読んでみる。クモの巣のように緻密に張り巡らされた「読書の網」から、簡単には抜け出せなくなるはずだ。 ・とにかく結末は、ハッピーエンディングでなければサッドエンディングだ。望むものを手に入れても、入れられなくても、それがハッピーエンディングであれ、サッドエンディングであれ、エンディングが来れば物語は完成する。物語は、登場人物が望むものを手に入れようが入れまいが、そんなことはお構いなしだ。人生も物語だとすれば、同じことが言えるだろう。この人生は、わたしの成功や失敗には関心がない。その代わり、わたしがどれほどすごいことを望んだのか、それによってどれだけ自分の人生を鮮烈に感じ、また何を学んだのか、その結果、どんな語が生まれたのかーそういう問いだけが重要なのだろう。 ・絶望感、挫折感、不安、宙ぶらりんの存在、悲観的な見通し。エピローグの続きの文章に並ぶ言葉だ。カムフラージュしてはいるけれどわたしたちの内面に存在しているものでもある。 だからわたしは、読書とは、自分の人生の光と闇を、他人の人生の光と闇を受け入れることだと思う。作家の紡ぎ出す、人生の孤独な瞬間や満ち足りた瞬間。小説家の描き出す、複雑で立体的で、泣き、笑う人物たち。哲学者の目に映る、幸せだったり不幸せだったりする人物たち。 そして、そういう人物と大して変わらないわたしたち個々人が築いていく人生。わたしたちに知識が必要だとしたら、まさにそういう人生についての知識であるはずだ。 ・わたしたちは自分のことを隠して生きているが、本の中の人物たちは隠しては生きられない。 だからわたしは、彼らがさらけ出しているものを通して、わたしたちが隠しているものを見る。 わたしが、あなたが、ロ・ギワンのように人知れずむせび泣いている場面を見る。わたしはロ・ギワンが頭から離れず数日苦しんだ。もしかしたらそれは、この世のすべての「ロ・ギワン」たちを思う悲しみだったのかもしれない。 ・苦しい本を読んで楽しいはずがない。それでも逃げ出してはならない理由は、世の多くの真実というのはそのように不快で、苦しいものだからだ。楽に手に入れられる確合は、自己啓発書の言うところの「成功」には必要かもしれないが、真実とはかけ離れている。それゆえわたしたちには、苦しみに耐える力が必要なのだ。 ・イリイチは、人間のあらゆる行為が商品に従属し、わたしたちの人生が没収されていくさまを直視する。春の野に咲き乱れる花のように多様な美しさを持つ個々人の人生が商品によって標準化され、もはや誰が誰だか区別がつかないありさまだと危惧する。そういう社会で個人が自分の人生に満足するのは容易ではない。 自分を守る、自分を保護する読書が必要な理由がここにある。商品を積み上げるのではなく、世の中を理解する知識を積み上げるために。メディアの提案してくる幸せではなく、自分の望む幸せを追求するために。孤独なとき、マートではなく友人の家へと向かうために。安定感に飢えているとき、豪華な家を夢見るのではなく、今ここでシンプルな生活を営むために。自分の不安の根源をみずからたどっていくために。自分の選択をする際に自分の気持ちを蔑ろにしないために。自分の中の欲望を理解し、それを解消する方法を自分で見つけるために。そのために、わたしたちは本を読まねばならないのだ。 メディアの生み出すストーリーは、どうしようもなく誘惑的だ。強烈なイメージはしつこくわたしたちにまとわりつき、思考や行動を掌握する。自分ではないほかの誰かの利益を代弁するメディアに対抗できるよう、わたしたちみんなが自分の中に「物語の自販機」を一つずつ持つといいと思う。自分を力づけてくれる物語がどっさり入っている奇跡の自販機を。必要なときに心のスイッチを押して物語を一つずつ再生するのだ。 ・アンドリュー・パイパーの文章を読んで、わたしもハッとした。そうだ、本がなくなったら「読者」もいなくなるのだ。それは、わたしのアイデンティティーの一部がなくなるという意味だ。一日に何時間も、鉛筆でアンダーラインを引きながらページをめくり、夢中で読んでいるうちに夜一二時を回っていることに気づいて消灯するわたし。初対面の人を前にすると、この人は本を読む人だろうか、読まない人だろうかと心の中で推察し、もし読む人ならどんな本を読むのだろうと想像しながらも結局本人には聞けず、家に帰ってきてから考えるわたし。知り合って何年にもなる友人よりも同じ本を読んだ人のほうが話がよく通じると感じ、しきりに友人たちに本を薦めるわたし。ぱっとしない自分の生活も本のおかげでそれなりに良くなったと肩じ、本を一冊手にしていると世界とつながっているようで安心するわたし。そして、退屈なときや孤独なとき、腹が立っているときや憂鬱なとき、世の中や人間に嫌気がさしたときにわたしの心を立て直してくれた本たち。そういう本なしに、わたしは生きていけるだろうか?ああ、わたしも本のない世界なんて想像できない。わたしは死ぬまで読者として生きていたい。 - 2026年2月16日
 在野研究ビギナーズ荒木優太「在野研究者」とは、大学に属さない、民間の研究者のことだ。 卒業後も退職後も、いつだって学問はできる! 現役で活躍するさまざまな在野研究者たちによる研究方法・生活を紹介する、実践的実例集。 「在野研究者」という存在を初めて知り、読んでみた。 在野研究のメリットは好きなことを好きなペース・方法で研究できること、デメリットは資金・時間の不足、資料の閲覧制限、モチベーション維持の困難さ等。 個人的には朱喜哲さんのお話が良かった。 今まで研究をしたことがないため、自分が在野研究者となるイメージは持っていないが、研究者型のビジネスパーソンの考え方を知り、日々の業務の先のより大きなテーマを持つことを考えたい。 ・ちなみに、筆者がよく読む分野は、情報法学、憲法学、法哲学、公共政策学などだ。「情報技術は人と社会にどのような影響を与えるか?それにどう制度対応すべきか?」という関心が先に立ち、ディシプリンは後から付いて来いよ的なパワープレイをしているので、雑食化した。その反面、興味がひとつの分野全域には及ばない。例えば、筆者が専門にしている(はずの)憲法学について、統治機構には強い関心があるが、人権・基本権論にはあまり食指が動かない。こうした興味の限局性(または既存分野との噛み合わせの悪さ) が、専任研究職に向かないと自己診断した理由のひとつである。他方で、情報技術を社会実装する現場にいる方が、守秘義務などで外からは得がたい先端の知見を蓄積でき、筆者の問題関心に資するとの直観もあった。 ・一人で論文を読むのも面白いが、誰かと議論するのも楽しい。自分とは違った視点をもらえるし、対話により思考が整理される瞬間が嬉しい。 しかも他者との討議は、研究を生み出す側に回る第一歩になる。自分で問いを立て、妥当な方法を選択し、答えを出すことが研究だ。問いと答えの枠組みを適切に設定するスキルは、訓練で身につく。前提や出典を示すのもそのひとつだ。例えば、歴史学者の興那覇潤は「情報が錯綜する現在、みずからの主張の典拠を明らかにしつつ発言するのは、【中略) 根拠のない不当な批判に貶められないよう、あるいは自身が結果的に誤った言動をしてしまわないよう、発言内容のうち直接責任を負える範囲を明示して「自分を守る」ことでもある。そのように足場を固めることで、人は未知のこと、答えがまだ(あるいは、永遠に) 出ない問いに対してすらも、論じる作法を手に入れる」と指摘する。 ・大学の聴講生になることもおすすめである。自分の専門分野で興味深い研究を行っている研究者が、自宅や勤務先近くの大学で講義をしている場合は、勉強の補助として聴講できるどうか調べてみるといい。また、聴講生になると図書館の利用アカウントがもらえる場合があり、図書の貸出や電子ジャーナルへのアクセスが可能になることもある。腕講費用が年間一0万円から二〇万円程度かかるが、自宅や勤務先の近くの大学の聴講生募集に関する情報を調べてみることをおすすめする。 ・GoogleBooksで本文レベルの言葉が直接引ける ・国会図書館が人文リンク集を提供している https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/humanitieslinks ・ウィキペディアの項目を見て、そこに文献の引用があれば確認する ・どの分野にも言えることだが、在野の場合、各々が自由な視点、やり方で研究を進めることができる。何らかの研究成果を発表する義務もないから、例えば昨日はアニメキャラクターとしての妖怪を調べ、今日は古典文学に記された妖怪を調べ、明日は絵巻に描かれた妖怪を調べる、といった統一性のないこともできる。 ・筆者はこれまで偏狭な視野のもと、見えない将来への不安に怯え、細く長い平均台を歩いているような心地で生きていた。修士課程のうちに学会発表や論文投稿をこなし、日本学術振興会の特別研究員になり・・・・・といった「こうしなければならない」というレールをいかに踏み外さずに進めるかという具合にである。しかし、一度盛大に平均台から落下し、泥だらけになって、良くも悪くも開き直って好きなことをしようと思えるようになった。 ・経験を積んでしまえば、共同討議を経るまでもなく自分だけで予測がつくことは増える。当然、新たな気づきや仮説改訂の機会は減る。できるだけ新奇性の高い案件を求め、自らもそうしたビジネス開発に関わりはじめたものの、いちど得たスキルセットや相場観をリセットできるわけではないので、知的刺激はどうしても減ってくる。途端に気になってくるのは、そもそもビジネスの個別案件における究極の課題が、特定のモノがどうすれば、誰に売れるのか、その行動にどう介入可能なのかという、ごく限定的なものだということだ。そして、課題に共同で挑む快楽はあっても、課題そのものにはほとんど関心をもてないのである。要するに、情熱を維持することが難しくなった。 ここに至ってあらためて目が向いたのは、チームのボスや先輩たちは、はるか以前から同様の境地にあるはずで、にもかかわらず新人を圧倒する熱量と独自性をもって個別案件に臨んでいたという事実である。なぜそんなことが可能だったのか。よくよく観察し、訊ねてみると答えはすぐにわかった。そうした人たちは、目の前の課題とは別に、自身で設定したより大きなテーマを保持しており、しかもそれは複数あったのだ。 個別案件が数週から数カ月間隔で取り組む短期的なリサーチ・プログラムだとすれば、そこでのデータや示唆が部分として貢献しうるような年単位の中期的なプログラムが複数あり、さらに射程が広く、具体的なステップがまだ見えていないような長期的なプログラムが構想されていた。そうした大きな研究構想を念頭に、そこから個別案件を捉えることで、それらを独自の観点から「面白がれる」角度や糸口を数多くもち合わせていたのだった。 大きなテーマとは、もはや目先のビジネスとは直接結びつかないもので、「インターネットは人類をどう変えたか」とか「情報とは何か」といったレイヤーのものだ。それらは個別の学問分野、ビジネス領域で即座に扱えるような問いではない。しかし、そこから派生する問いを積み上げていけば、いずれは輪郭をなすような論題である。こうした大テーマから実務に落とし込める複数の中テーマを設定し、異なる個別案件に自分なりの統一的なビジョンをもつことこそ、特定のビジネス領域の専門家に留まらない「研究者」型のビジネスパーソンという在り方を実現させていたのだった。言い換えれば、優秀なビジネスパーソンであることが「在野研究者」であることと一致していたのである。
在野研究ビギナーズ荒木優太「在野研究者」とは、大学に属さない、民間の研究者のことだ。 卒業後も退職後も、いつだって学問はできる! 現役で活躍するさまざまな在野研究者たちによる研究方法・生活を紹介する、実践的実例集。 「在野研究者」という存在を初めて知り、読んでみた。 在野研究のメリットは好きなことを好きなペース・方法で研究できること、デメリットは資金・時間の不足、資料の閲覧制限、モチベーション維持の困難さ等。 個人的には朱喜哲さんのお話が良かった。 今まで研究をしたことがないため、自分が在野研究者となるイメージは持っていないが、研究者型のビジネスパーソンの考え方を知り、日々の業務の先のより大きなテーマを持つことを考えたい。 ・ちなみに、筆者がよく読む分野は、情報法学、憲法学、法哲学、公共政策学などだ。「情報技術は人と社会にどのような影響を与えるか?それにどう制度対応すべきか?」という関心が先に立ち、ディシプリンは後から付いて来いよ的なパワープレイをしているので、雑食化した。その反面、興味がひとつの分野全域には及ばない。例えば、筆者が専門にしている(はずの)憲法学について、統治機構には強い関心があるが、人権・基本権論にはあまり食指が動かない。こうした興味の限局性(または既存分野との噛み合わせの悪さ) が、専任研究職に向かないと自己診断した理由のひとつである。他方で、情報技術を社会実装する現場にいる方が、守秘義務などで外からは得がたい先端の知見を蓄積でき、筆者の問題関心に資するとの直観もあった。 ・一人で論文を読むのも面白いが、誰かと議論するのも楽しい。自分とは違った視点をもらえるし、対話により思考が整理される瞬間が嬉しい。 しかも他者との討議は、研究を生み出す側に回る第一歩になる。自分で問いを立て、妥当な方法を選択し、答えを出すことが研究だ。問いと答えの枠組みを適切に設定するスキルは、訓練で身につく。前提や出典を示すのもそのひとつだ。例えば、歴史学者の興那覇潤は「情報が錯綜する現在、みずからの主張の典拠を明らかにしつつ発言するのは、【中略) 根拠のない不当な批判に貶められないよう、あるいは自身が結果的に誤った言動をしてしまわないよう、発言内容のうち直接責任を負える範囲を明示して「自分を守る」ことでもある。そのように足場を固めることで、人は未知のこと、答えがまだ(あるいは、永遠に) 出ない問いに対してすらも、論じる作法を手に入れる」と指摘する。 ・大学の聴講生になることもおすすめである。自分の専門分野で興味深い研究を行っている研究者が、自宅や勤務先近くの大学で講義をしている場合は、勉強の補助として聴講できるどうか調べてみるといい。また、聴講生になると図書館の利用アカウントがもらえる場合があり、図書の貸出や電子ジャーナルへのアクセスが可能になることもある。腕講費用が年間一0万円から二〇万円程度かかるが、自宅や勤務先の近くの大学の聴講生募集に関する情報を調べてみることをおすすめする。 ・GoogleBooksで本文レベルの言葉が直接引ける ・国会図書館が人文リンク集を提供している https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/humanitieslinks ・ウィキペディアの項目を見て、そこに文献の引用があれば確認する ・どの分野にも言えることだが、在野の場合、各々が自由な視点、やり方で研究を進めることができる。何らかの研究成果を発表する義務もないから、例えば昨日はアニメキャラクターとしての妖怪を調べ、今日は古典文学に記された妖怪を調べ、明日は絵巻に描かれた妖怪を調べる、といった統一性のないこともできる。 ・筆者はこれまで偏狭な視野のもと、見えない将来への不安に怯え、細く長い平均台を歩いているような心地で生きていた。修士課程のうちに学会発表や論文投稿をこなし、日本学術振興会の特別研究員になり・・・・・といった「こうしなければならない」というレールをいかに踏み外さずに進めるかという具合にである。しかし、一度盛大に平均台から落下し、泥だらけになって、良くも悪くも開き直って好きなことをしようと思えるようになった。 ・経験を積んでしまえば、共同討議を経るまでもなく自分だけで予測がつくことは増える。当然、新たな気づきや仮説改訂の機会は減る。できるだけ新奇性の高い案件を求め、自らもそうしたビジネス開発に関わりはじめたものの、いちど得たスキルセットや相場観をリセットできるわけではないので、知的刺激はどうしても減ってくる。途端に気になってくるのは、そもそもビジネスの個別案件における究極の課題が、特定のモノがどうすれば、誰に売れるのか、その行動にどう介入可能なのかという、ごく限定的なものだということだ。そして、課題に共同で挑む快楽はあっても、課題そのものにはほとんど関心をもてないのである。要するに、情熱を維持することが難しくなった。 ここに至ってあらためて目が向いたのは、チームのボスや先輩たちは、はるか以前から同様の境地にあるはずで、にもかかわらず新人を圧倒する熱量と独自性をもって個別案件に臨んでいたという事実である。なぜそんなことが可能だったのか。よくよく観察し、訊ねてみると答えはすぐにわかった。そうした人たちは、目の前の課題とは別に、自身で設定したより大きなテーマを保持しており、しかもそれは複数あったのだ。 個別案件が数週から数カ月間隔で取り組む短期的なリサーチ・プログラムだとすれば、そこでのデータや示唆が部分として貢献しうるような年単位の中期的なプログラムが複数あり、さらに射程が広く、具体的なステップがまだ見えていないような長期的なプログラムが構想されていた。そうした大きな研究構想を念頭に、そこから個別案件を捉えることで、それらを独自の観点から「面白がれる」角度や糸口を数多くもち合わせていたのだった。 大きなテーマとは、もはや目先のビジネスとは直接結びつかないもので、「インターネットは人類をどう変えたか」とか「情報とは何か」といったレイヤーのものだ。それらは個別の学問分野、ビジネス領域で即座に扱えるような問いではない。しかし、そこから派生する問いを積み上げていけば、いずれは輪郭をなすような論題である。こうした大テーマから実務に落とし込める複数の中テーマを設定し、異なる個別案件に自分なりの統一的なビジョンをもつことこそ、特定のビジネス領域の専門家に留まらない「研究者」型のビジネスパーソンという在り方を実現させていたのだった。言い換えれば、優秀なビジネスパーソンであることが「在野研究者」であることと一致していたのである。 - 2026年2月14日
 シンプルな情熱アニー・エルノー,堀茂樹離婚後独身でパリに暮らす女性教師が、妻子ある若い東欧の外交官と不倫の関係に。 彼だけのことを思い、逢えばどこでも熱く抱擁する。 その情熱はロマンチシズムからはほど遠い、激しく単純で肉体的なものだった。 「ある女」に続いて。 アニー・エルノーは自伝的な作品が多いのかな。(2作しか読んでないけど) 相手を片時も忘れられないほどの恋をし、そのために、クラシック音楽を捨ててこともあろうにシルヴィ・ヴァルタンに聴き入り、女性誌を手に取ればまっさきに星占いの頁を開き、つまらぬことで根拠のない嫉妬に悶える・・・・・ 共感に加えて、現実を直視する強さを感じる内容だった。 最後の「今の私には、贅沢とはまた、ひとりの男、またはひとりの女への欲しい恋を生きることができる、ということでもあるように思える。」という言葉が素敵だった。 ・化粧がすみ、髪も結え、家の中も片づいて用意がととのってしまうと、私は、たとえ時間が残っていても、読もうとする本は手につかず、生徒たちの答案のチェックをする気にもなれなかった。ある意味では、Aを待つことから気持ちを逸らせたくなかったのだともいえる。待つということを大切にしたかったのだ。しばしば一枚の紙に、日付・時刻とともに「もうすぐ彼が来る」と記したうえで、彼がもしかしたら来ないのではないかとか、いつもほど私を欲しがっていないのではないかとか、不安な気持ちを文にして書きつけた。夜になってから、その紙をもう一度取り出し、「彼が来た」と記し、その日の逢い引きの細々したことを思い出すままに書き連ねた。それから私は、乱雑に文字を書きなぐったその紙を前にし、それぞれ事前と事後に書いたのだけれど、一気に続けて読むことのできる二つのパラグラフを眺めて、茫然自失した。この二つの書きつけの間に、いくつかの言葉が発せられ、いくつかの動作がおこなわれた。 その言葉や動作に比べたら、それらを定着しようとして文章を綴ることも含めて、他のいっさいの行為は取るに足らなかった。彼の車ルノー25の二つの音、ブレーキをかけて停車する音とふたたび発進していく音に区切られた時間の持続の間、私は確信していた。これまでの人生で、自分は子供も持ったし、いろいろな試験にも合格したし、遠方へも旅行したけれど、このことー昼下がりにこの人とベッドにいること以上に重要なことは何ひとつ体験しなかった、と。 ・私は、人がその気になればどんなことを仕出かし得るか、何でもやりかねないのだということを発見した。崇高な、あるいは致命的な欲望、みっともない振る舞い、あるいはまた、自分自身がそれに頼ったり訴えたりすることになるまでは他人事として見て、およそばかげていると思っていたある種の嬉心や行動…………..。彼は、彼自身の知らぬ間に、私を以前より深く世界に結びつけてくれたのだ。 ・子供の頃の私にとって、贅沢といえば、毛皮のコート、ロング・ドレス、それに海辺の別荘だった。その後、贅沢といえるのは、知識人の生活を営むことだと信じた。今の私には、贅沢とはまた、ひとりの男、またはひとりの女への欲しい恋を生きることができる、ということでもあるように思える。
シンプルな情熱アニー・エルノー,堀茂樹離婚後独身でパリに暮らす女性教師が、妻子ある若い東欧の外交官と不倫の関係に。 彼だけのことを思い、逢えばどこでも熱く抱擁する。 その情熱はロマンチシズムからはほど遠い、激しく単純で肉体的なものだった。 「ある女」に続いて。 アニー・エルノーは自伝的な作品が多いのかな。(2作しか読んでないけど) 相手を片時も忘れられないほどの恋をし、そのために、クラシック音楽を捨ててこともあろうにシルヴィ・ヴァルタンに聴き入り、女性誌を手に取ればまっさきに星占いの頁を開き、つまらぬことで根拠のない嫉妬に悶える・・・・・ 共感に加えて、現実を直視する強さを感じる内容だった。 最後の「今の私には、贅沢とはまた、ひとりの男、またはひとりの女への欲しい恋を生きることができる、ということでもあるように思える。」という言葉が素敵だった。 ・化粧がすみ、髪も結え、家の中も片づいて用意がととのってしまうと、私は、たとえ時間が残っていても、読もうとする本は手につかず、生徒たちの答案のチェックをする気にもなれなかった。ある意味では、Aを待つことから気持ちを逸らせたくなかったのだともいえる。待つということを大切にしたかったのだ。しばしば一枚の紙に、日付・時刻とともに「もうすぐ彼が来る」と記したうえで、彼がもしかしたら来ないのではないかとか、いつもほど私を欲しがっていないのではないかとか、不安な気持ちを文にして書きつけた。夜になってから、その紙をもう一度取り出し、「彼が来た」と記し、その日の逢い引きの細々したことを思い出すままに書き連ねた。それから私は、乱雑に文字を書きなぐったその紙を前にし、それぞれ事前と事後に書いたのだけれど、一気に続けて読むことのできる二つのパラグラフを眺めて、茫然自失した。この二つの書きつけの間に、いくつかの言葉が発せられ、いくつかの動作がおこなわれた。 その言葉や動作に比べたら、それらを定着しようとして文章を綴ることも含めて、他のいっさいの行為は取るに足らなかった。彼の車ルノー25の二つの音、ブレーキをかけて停車する音とふたたび発進していく音に区切られた時間の持続の間、私は確信していた。これまでの人生で、自分は子供も持ったし、いろいろな試験にも合格したし、遠方へも旅行したけれど、このことー昼下がりにこの人とベッドにいること以上に重要なことは何ひとつ体験しなかった、と。 ・私は、人がその気になればどんなことを仕出かし得るか、何でもやりかねないのだということを発見した。崇高な、あるいは致命的な欲望、みっともない振る舞い、あるいはまた、自分自身がそれに頼ったり訴えたりすることになるまでは他人事として見て、およそばかげていると思っていたある種の嬉心や行動…………..。彼は、彼自身の知らぬ間に、私を以前より深く世界に結びつけてくれたのだ。 ・子供の頃の私にとって、贅沢といえば、毛皮のコート、ロング・ドレス、それに海辺の別荘だった。その後、贅沢といえるのは、知識人の生活を営むことだと信じた。今の私には、贅沢とはまた、ひとりの男、またはひとりの女への欲しい恋を生きることができる、ということでもあるように思える。 - 2026年2月14日
 ある女アニー・エルノー,堀茂樹金原ひとみさんのエッセイの中に アニー・エルノーが出てきたので読んでみた。 著者の母親の死と、その母親の女性としての生き方を描いた小説。 貧しい階層に生まれながらも小売商売人になり果敢に生きていく母親、無学ながら何事も学ぶことに熱心だった母親、娘に自分よりいい生活をさせるために犠牲も厭わない母親、強く美しい母親、自分の考えを押し付ける感情的で暴力的な母親... 様々な母親の姿を回顧する中で、愛と憎しみと母親に対する相反する著者の感情がはっきりと感じられる。 自分と家族のことをこんなに剥き出しで語るのは勇気がいるのではないだろうか。(自分なら向き合うことが怖くて逃げてしまうと思う。。) 母娘の愛と苦しみがこんなに感じられる小説は初めてだった。 ・一九三一年、彼らは、イザトーから二十五キロ離れた、人口七千人の労働者の町リルボンヌに、酒類提供及び食料品小売の店を賦払いで買った。カフェ兼食料品店は、ラ・ヴァレ(谷間)地区にあった。十九世紀以来の繊維工場が、掘り籠から墓場まで、人々の時間と生活を支配している地区だった。今でも、戦前のラ・ヴァレと言えば、それだけで何を言いたいのか察しがつく。人口に占めるアルコール中毒患者と未婚の母のパーセンテージの極度の高さ、壁を水滴がしたたり落ちるほどの湿気、そして、消化不良の下痢で二時間ばかりで死んでしまう乳幼児たち。当時、母は二十五歳だった。まさしくその土地で、彼女は彼女になり、私が長い間初めから彼女のものだったように思い込んでいたあの顔と、あの趣味と、あの物腰を身につけたのにちがいない。 ・ある日曜日、父と母は私を連れ、ある森の近くの土手で、家から用意していった軽食を食べた。家族水入らずで、肉声と、生身の体と、途絶えることのない笑いに満たされた親密さの中にいた思い出。帰り道、私たちは空襲に出くわした。私が父の自転車に乗せてもらっているその前方を、母は先に立って坂を下っていく。サドルの上にどっかりとお尻を乗せ、背筋を伸ばしてー。私たちは二人とも、母に恋していたように思える。 ・私は、母の粗景さ、溢れんばかりの愛情、また非難の言葉を、彼女の性格の個人的特徴としてのみ考えるのではなく、それらを彼女の人生の軌跡と社会的境遇の中にも位置づけようと試みている。この書き方ー真実に近づいていく方法のように私が感じているこの書き方は、私が個人的な思い出の孤独と闇から出ようとするのを、より一般的な何らかの意味の発見を促すことで助けてくれる。ところが私は、自分の中の何かが抵抗するのを感じる。できれば、もっぱら情緒的な母のイメージ、温もりとか戻のようなものを、それに意味など与えずに取っておきたい気がする。 ・彼女はますます、まわりにいる人間を区別も識別もしなくなっていった。さまざまな言葉が彼女の耳に届いたが、それらにはもう固有の意味がないも同然だった。それでも彼女は、行き当たりばったりに答えていた。相変わらず、意思伝達をしたがっていた。彼女の言語機能は少しも損なわれていなかった。彼女の口から発せられる文には軽合性があったし、語も正確に発音されていた。 ただ、言葉が物から離れ、本人の想像の世界にのみ従属していたのだ。彼女は、もはや自分のものではなくなってしまった人生を、空想で作り上げていた。パリへ行く、一匹の金魚を買った、夫の墓へ案内された、等々。が、時折、彼女は知っていた。「私の状態は、もう元に戻らないんじゃないかと心配だわ」あるいは、彼女は憶えていた。「わたしはね、できることは何でもして娘を幸せにしようとしたんだよ、でも娘は、そのぶん幸せになったわけじゃなかったわ」 ・この本は伝記ではないし、もちろん小説でもない。おそらく文学と社会学と歴史の間に位置する何かだと思う。被支配階層に生まれ、そこから脱出しようとした母自身が、歴史となる必要があったのだ。彼女の望みにしたがって、言葉と思想を持つ支配階層に移った私が、その階層の中で、自分をそれほど孤独でも不自然でもないと感じるためにー。 私が彼女の声を聞くことは、もはやない。大人の女である私を、子供だった頃の私に結びつけていたのは、彼女と、そして、彼女の話し言葉、彼女の手、仕種、笑い方、歩きぶりなどだった。私は、自分の生まれ故郷にあたる階層との間の最後の絆を失った。
ある女アニー・エルノー,堀茂樹金原ひとみさんのエッセイの中に アニー・エルノーが出てきたので読んでみた。 著者の母親の死と、その母親の女性としての生き方を描いた小説。 貧しい階層に生まれながらも小売商売人になり果敢に生きていく母親、無学ながら何事も学ぶことに熱心だった母親、娘に自分よりいい生活をさせるために犠牲も厭わない母親、強く美しい母親、自分の考えを押し付ける感情的で暴力的な母親... 様々な母親の姿を回顧する中で、愛と憎しみと母親に対する相反する著者の感情がはっきりと感じられる。 自分と家族のことをこんなに剥き出しで語るのは勇気がいるのではないだろうか。(自分なら向き合うことが怖くて逃げてしまうと思う。。) 母娘の愛と苦しみがこんなに感じられる小説は初めてだった。 ・一九三一年、彼らは、イザトーから二十五キロ離れた、人口七千人の労働者の町リルボンヌに、酒類提供及び食料品小売の店を賦払いで買った。カフェ兼食料品店は、ラ・ヴァレ(谷間)地区にあった。十九世紀以来の繊維工場が、掘り籠から墓場まで、人々の時間と生活を支配している地区だった。今でも、戦前のラ・ヴァレと言えば、それだけで何を言いたいのか察しがつく。人口に占めるアルコール中毒患者と未婚の母のパーセンテージの極度の高さ、壁を水滴がしたたり落ちるほどの湿気、そして、消化不良の下痢で二時間ばかりで死んでしまう乳幼児たち。当時、母は二十五歳だった。まさしくその土地で、彼女は彼女になり、私が長い間初めから彼女のものだったように思い込んでいたあの顔と、あの趣味と、あの物腰を身につけたのにちがいない。 ・ある日曜日、父と母は私を連れ、ある森の近くの土手で、家から用意していった軽食を食べた。家族水入らずで、肉声と、生身の体と、途絶えることのない笑いに満たされた親密さの中にいた思い出。帰り道、私たちは空襲に出くわした。私が父の自転車に乗せてもらっているその前方を、母は先に立って坂を下っていく。サドルの上にどっかりとお尻を乗せ、背筋を伸ばしてー。私たちは二人とも、母に恋していたように思える。 ・私は、母の粗景さ、溢れんばかりの愛情、また非難の言葉を、彼女の性格の個人的特徴としてのみ考えるのではなく、それらを彼女の人生の軌跡と社会的境遇の中にも位置づけようと試みている。この書き方ー真実に近づいていく方法のように私が感じているこの書き方は、私が個人的な思い出の孤独と闇から出ようとするのを、より一般的な何らかの意味の発見を促すことで助けてくれる。ところが私は、自分の中の何かが抵抗するのを感じる。できれば、もっぱら情緒的な母のイメージ、温もりとか戻のようなものを、それに意味など与えずに取っておきたい気がする。 ・彼女はますます、まわりにいる人間を区別も識別もしなくなっていった。さまざまな言葉が彼女の耳に届いたが、それらにはもう固有の意味がないも同然だった。それでも彼女は、行き当たりばったりに答えていた。相変わらず、意思伝達をしたがっていた。彼女の言語機能は少しも損なわれていなかった。彼女の口から発せられる文には軽合性があったし、語も正確に発音されていた。 ただ、言葉が物から離れ、本人の想像の世界にのみ従属していたのだ。彼女は、もはや自分のものではなくなってしまった人生を、空想で作り上げていた。パリへ行く、一匹の金魚を買った、夫の墓へ案内された、等々。が、時折、彼女は知っていた。「私の状態は、もう元に戻らないんじゃないかと心配だわ」あるいは、彼女は憶えていた。「わたしはね、できることは何でもして娘を幸せにしようとしたんだよ、でも娘は、そのぶん幸せになったわけじゃなかったわ」 ・この本は伝記ではないし、もちろん小説でもない。おそらく文学と社会学と歴史の間に位置する何かだと思う。被支配階層に生まれ、そこから脱出しようとした母自身が、歴史となる必要があったのだ。彼女の望みにしたがって、言葉と思想を持つ支配階層に移った私が、その階層の中で、自分をそれほど孤独でも不自然でもないと感じるためにー。 私が彼女の声を聞くことは、もはやない。大人の女である私を、子供だった頃の私に結びつけていたのは、彼女と、そして、彼女の話し言葉、彼女の手、仕種、笑い方、歩きぶりなどだった。私は、自分の生まれ故郷にあたる階層との間の最後の絆を失った。 - 2026年2月13日
 チャーリーとの旅ジョン・スタインベック,青山南「かくして、わたしは気がついたのだ、自分の国を知らない、と」。時は1960年、大統領選挙の直前。ロシナンテと名づけたトラックに乗り、老プードル一匹を相棒にアメリカ全土をめぐる旅行譚。 アメリカ全土への旅のために車を快適に改造する描写も描かれているが、とても憧れる。。 旅には人をわくわくさせる力があるなぁ。 大統領選や南部の黒人差別についての話題も出るが、飼い犬のチャーリーがいることで終始気を張らずに読むことができた。 訪れた土地についてだけでなく、人との出会いと対話もこの本を魅力的にしている。 著者の相手を理解しようとする姿勢は素敵だった。 時間を空けてまた読みたい。 アメリカ杉がジュラ期からある植物だとは初めて知った。 昔のアメリカ旅行の際に見れたらよかったなぁ。 ・計画され支度されていたものがひとたび実行に移されると、旅は新たな一面を見せるようになる。 旅も狩りも探検も、他とは違う独自のものとなるのだ。旅そのものが人格や感情を持ち、個性的で独特なものとなる。旅自体が一個人であり、似たものは二つとない。あらかじめ計画していようが安全を気にかけていようが役に立たないし、規制したり禁止したりしたって無駄である。 長年もがいた末に我々はこう悟る。人が旅に出るのではなく、旅が人を連れ出すのだ。 旅そのものが個性を発揮しはじめたら最後、かっちりと定めた目的も練り上げた計画も取っておいた予約も木っ端みじんにされる。そして本物の風来坊は、それを確かめた時だけ安らかに旅に身を任すことができる。そうなって初めて欲求不満が解消されるのだ。 その点、旅は結婚に似ている。コントロールしようというのが間違いのもとなのだ。 ・チャーリーは背の高い犬である。助手席に座ると頭の位置はだいたい私と同じ高さになる。彼は鼻面を私の耳に近づけ、「フッチュ」と言った。 私の知る限り、彼は子音のFを発音できる唯一の犬だ。これは門歯が曲がっているためで、おかげでドッグショーに出られないのは悲劇だが、上の門歯がわずかに下唇に触れてFが発音できる。 「フッチュ」は大抵、茂みや木に挨拶したいという意味だ。 ドアを開けて外に出してやると、彼は儀式にとりかかった。彼にとっては意識せずともうまくやれることである。字も読めず車も運転できず算数も分からず、多くの面でひどく無知な彼だが、いくつかの分野では私より賢いようだ。今実行しているような彼の専門分野、ゆったり堂々とにおいを嗅ぎまわって片足を上げるという儀式においては、彼の右に出る者はいない。 もちろん彼の世界は限られたものだが、では私の世界はどれほど広いというのだろう? ・「どちらまで?」 「どこまでも」 そして私が見たのは、旅の間に何度となく見ることになった憧れのまなざしだった。 「いやあ、私も行けたらなあ」「ここが気に入らないんですか?」「そりゃ満足はしてますよ。でも行きたいもんですね」「どこに行くかも分からないのに?」「構やしません。どこでもいいから行きたいね」 ・現場に飛び、鍵を握る人物に鋭く質問し、世論を掴み、道路地図のように整ったレポートをまとめるような記者を、私は前々から尊敬している。そういう技術を羨ましいとも思うが、同時にそうしたレポートが現実をそのまま映しているとは言じない。一つのレポートだけを肩じるには、現実の捉え方は多すぎると思うからだ。 私がこの本に書くことは一面の真実だろう。しかし私以外の誰かが同じ道を辿れば、また別のやり方で世界を捉え直すに違いない。文芸批評において、批評家が目についた犠牲者を自分の身の丈に合わせて作り変えるのと同じことだ。 ・えらく低次定の話だが、神話が作られていく仕組みを紹介しよう。生まれ故郷の町を訪れた時、私を子供の頃から知っている老人と話した。彼の私に関する記憶は鮮明だった。私は痩せこけた子供で、ある凍てつく朝に展えながら彼の家の前を通ったらしい。オーバーコートのサイズが合わないので、馬用の毛布を留めるピンを使って小さな胸の前で留めていたのだそうだ。 かわいそうな貧しい子供だった私が、まあ大したスケールではないにしろ、大人になって出世している。ーー些細な話だが、これこそが神話を作る材料なのである。 私はその時の記憶などないのだが、そんなことはありえないと分かっていた。私の母はボタンつけにはとびきり熱心だったのだ。ボタンがついていない服なんて、だらしないのを通り越して罪悪だった。もしも私がコートをピンで留めていようものなら、母に殴り飛ばされたことだろう。 本当のわけがないのだが、老人はこの話をとても気に入っていて、訂正したところで納得しそうもなかった。だから私もあえて言わなかった。もしも故郷の町が私に馬用毛布のピンをつけさせたいのなら、私が別のものに替えることなどできっこない。その子のオーバーコートは、真実などでは留められないのだ。 ・時がたつにつれ、自分の反応が鈍くなっているのに気がついた。いつも口笛を吹いていたのに吹かなくなった。飼っていた大とも話さなくなった。微妙な感情というのが消えていたのだろう。とうとう快楽と苦痛だけを基準にするようになっていたのだ。 そこで分かった。感情や反応の機微というのはコミュニケーションの結果なのだ。コミュニケーションがなければ機徴もなくなる。何も言うべきことがない人間は言葉を失う。逆もまた真なりで、何か言ってくれる相手がいない人間にも言葉は必要なくなり、言葉を失うのではなかろうか? ・こういう話は、懐古主義に凝り固まった年寄りの繰り言とか、改革反対を叫ぶ馬鹿や金持ちの主張のように響く。しかしそうではない。今のシアトルは、私の知っているシアトルが変化したものではない。新たにできた別物だった。ここがシアトルだと知らずに連れてこられたら、私はどこにいるのか分からないだろう。 いたるところが狂ったように発展している。ガン細胞のような発展だ。ブルドーザーが緑の森をなぎ倒してゴミに変え、積み上げて燃やそうとしている。コンクリート建築から撤去された足場用の白い丸大が灰色の壁の脇に積み上げられている。 発展というものは、どうしてこうも破壊と似ているのだろう。 ・アメリカ杉の木々からは静寂と畏怖が伝わってくる。肩じられない大きさや、見る間に移り変わる他合いだけではなく、我々の知っているどんな木とも違う存在なのだ。彼らは違う時代からの使者なのである。百万年前に絶滅したシダ類が、三億年前の石炭紀において石炭へと変化したという謎も、太古から生きる彼らの中には秘められているのだ。 光も影も彼らの中にある。どんなに自惚れた人間も、どんなに有頂天で不遜な人間も、アメリカ 杉を目の当たりにすると敬の念に打たれてしまう。まさに言葉通りに畏れ敬うのだ。紛れもない王者の風格を前にすると、人は頭を下げるべきだと感じるものなのである。 ・しかし私の頭で覚えたりもっと深い感覚に刻んだりしてきたものは、絡み合った無数の出みたいなものだ。ずっと以前に海洋生物の採取と分類に取り組みながら悟ったのだが、何を見つけるかはその時の気分に深く影響されるものなのだ。自分の外部の現実であっても、突き詰めれば自分の内部と繋がりを持っているものである。 巨大な国土の最強の国家、未来を生み出す種子たるアメリカも、私という小宇宙から見た大宇宙だと分かった。もしイギリス人やフランス人やイタリア人が私と同じルートを旅して、私と同じものを目にし、私と同じことを耳にしたとしたら、心に残る光景は私とは違ったものになるだろう。 ・「さて、この犬が喋れて、二本足で立つことができたらと考えてみてください。きっと何であっても上手にやってみせることでしょう。彼を晩餐会に招待することだってできるかもしれません。しかし、あなたは彼を人間と見なすことができますかな?」「つまり、自分の妹を彼の嫁にできるかってことですね?」 彼は笑った。 「わしはただ、物事に対する感情を変えるのがいかに難しいかを申し上げておるのです。それからこうはお考えになれませんか?黒人たちにしても、我々白人に対する感情を変えるのは難しいのです。それは我々が黒人への感情を変えるのと同じことですな。なにも新しい話ではないのです。長いこと続いてきたことですよ」 ・私が何度も寝返りを打つものだから、とうとうチャーリーが怒って何度も「フッチュ」と文句を言った。チャーリーは人間たちの問題など関係ない。原子を分裂させる知恵があるのに平和に暮らす知恵はないような種になど、犬は属していないのだ。チャーリーは人種のことなど知らないし、自分の妹の結婚なんて気にもかけない。そんな心配ごととは無縁なのである。 かつてチャーリーはダックスフントに恋をしたことがある。種族的に釣り合わず、体格的にも馬鹿げており、機能的にも無理がある恋だった。しかしそんな諸問題などチャーリーは気にしなかった。彼は相手を深く愛し、犬らしく全力を尽くしたのである。 なんだって千人もの人間が集まって一人の小さな人間を罵っていたのか、犬に向かって論理的かつ倫理的に説明するのは難しかろう。私は犬たちの瞳の中に、呆れて馬鹿にした表情が一瞬浮かんで消えるのを何度も見てきた。犬たちは基本的に人間を馬鹿だと思っていると、私は確信している。 ・私はただ、幾人かの人々が私に語ったこと、そして私が見たことを記しただけである。それが典型的なことなのか、そこから何らかの結論が導けるものなのか、私には分からない。私に分かるのは、南部は苦しみの中にあり、人々が混乱に陥っているということだ。そして解決に至る道のりは険しく込み入っていることだろう。 ムッシュー・シ・ジの言う通りだ。問題は結末ではなく、そこに至る手段なのだ。その手段が、恐ろしく不確かなのである。
チャーリーとの旅ジョン・スタインベック,青山南「かくして、わたしは気がついたのだ、自分の国を知らない、と」。時は1960年、大統領選挙の直前。ロシナンテと名づけたトラックに乗り、老プードル一匹を相棒にアメリカ全土をめぐる旅行譚。 アメリカ全土への旅のために車を快適に改造する描写も描かれているが、とても憧れる。。 旅には人をわくわくさせる力があるなぁ。 大統領選や南部の黒人差別についての話題も出るが、飼い犬のチャーリーがいることで終始気を張らずに読むことができた。 訪れた土地についてだけでなく、人との出会いと対話もこの本を魅力的にしている。 著者の相手を理解しようとする姿勢は素敵だった。 時間を空けてまた読みたい。 アメリカ杉がジュラ期からある植物だとは初めて知った。 昔のアメリカ旅行の際に見れたらよかったなぁ。 ・計画され支度されていたものがひとたび実行に移されると、旅は新たな一面を見せるようになる。 旅も狩りも探検も、他とは違う独自のものとなるのだ。旅そのものが人格や感情を持ち、個性的で独特なものとなる。旅自体が一個人であり、似たものは二つとない。あらかじめ計画していようが安全を気にかけていようが役に立たないし、規制したり禁止したりしたって無駄である。 長年もがいた末に我々はこう悟る。人が旅に出るのではなく、旅が人を連れ出すのだ。 旅そのものが個性を発揮しはじめたら最後、かっちりと定めた目的も練り上げた計画も取っておいた予約も木っ端みじんにされる。そして本物の風来坊は、それを確かめた時だけ安らかに旅に身を任すことができる。そうなって初めて欲求不満が解消されるのだ。 その点、旅は結婚に似ている。コントロールしようというのが間違いのもとなのだ。 ・チャーリーは背の高い犬である。助手席に座ると頭の位置はだいたい私と同じ高さになる。彼は鼻面を私の耳に近づけ、「フッチュ」と言った。 私の知る限り、彼は子音のFを発音できる唯一の犬だ。これは門歯が曲がっているためで、おかげでドッグショーに出られないのは悲劇だが、上の門歯がわずかに下唇に触れてFが発音できる。 「フッチュ」は大抵、茂みや木に挨拶したいという意味だ。 ドアを開けて外に出してやると、彼は儀式にとりかかった。彼にとっては意識せずともうまくやれることである。字も読めず車も運転できず算数も分からず、多くの面でひどく無知な彼だが、いくつかの分野では私より賢いようだ。今実行しているような彼の専門分野、ゆったり堂々とにおいを嗅ぎまわって片足を上げるという儀式においては、彼の右に出る者はいない。 もちろん彼の世界は限られたものだが、では私の世界はどれほど広いというのだろう? ・「どちらまで?」 「どこまでも」 そして私が見たのは、旅の間に何度となく見ることになった憧れのまなざしだった。 「いやあ、私も行けたらなあ」「ここが気に入らないんですか?」「そりゃ満足はしてますよ。でも行きたいもんですね」「どこに行くかも分からないのに?」「構やしません。どこでもいいから行きたいね」 ・現場に飛び、鍵を握る人物に鋭く質問し、世論を掴み、道路地図のように整ったレポートをまとめるような記者を、私は前々から尊敬している。そういう技術を羨ましいとも思うが、同時にそうしたレポートが現実をそのまま映しているとは言じない。一つのレポートだけを肩じるには、現実の捉え方は多すぎると思うからだ。 私がこの本に書くことは一面の真実だろう。しかし私以外の誰かが同じ道を辿れば、また別のやり方で世界を捉え直すに違いない。文芸批評において、批評家が目についた犠牲者を自分の身の丈に合わせて作り変えるのと同じことだ。 ・えらく低次定の話だが、神話が作られていく仕組みを紹介しよう。生まれ故郷の町を訪れた時、私を子供の頃から知っている老人と話した。彼の私に関する記憶は鮮明だった。私は痩せこけた子供で、ある凍てつく朝に展えながら彼の家の前を通ったらしい。オーバーコートのサイズが合わないので、馬用の毛布を留めるピンを使って小さな胸の前で留めていたのだそうだ。 かわいそうな貧しい子供だった私が、まあ大したスケールではないにしろ、大人になって出世している。ーー些細な話だが、これこそが神話を作る材料なのである。 私はその時の記憶などないのだが、そんなことはありえないと分かっていた。私の母はボタンつけにはとびきり熱心だったのだ。ボタンがついていない服なんて、だらしないのを通り越して罪悪だった。もしも私がコートをピンで留めていようものなら、母に殴り飛ばされたことだろう。 本当のわけがないのだが、老人はこの話をとても気に入っていて、訂正したところで納得しそうもなかった。だから私もあえて言わなかった。もしも故郷の町が私に馬用毛布のピンをつけさせたいのなら、私が別のものに替えることなどできっこない。その子のオーバーコートは、真実などでは留められないのだ。 ・時がたつにつれ、自分の反応が鈍くなっているのに気がついた。いつも口笛を吹いていたのに吹かなくなった。飼っていた大とも話さなくなった。微妙な感情というのが消えていたのだろう。とうとう快楽と苦痛だけを基準にするようになっていたのだ。 そこで分かった。感情や反応の機微というのはコミュニケーションの結果なのだ。コミュニケーションがなければ機徴もなくなる。何も言うべきことがない人間は言葉を失う。逆もまた真なりで、何か言ってくれる相手がいない人間にも言葉は必要なくなり、言葉を失うのではなかろうか? ・こういう話は、懐古主義に凝り固まった年寄りの繰り言とか、改革反対を叫ぶ馬鹿や金持ちの主張のように響く。しかしそうではない。今のシアトルは、私の知っているシアトルが変化したものではない。新たにできた別物だった。ここがシアトルだと知らずに連れてこられたら、私はどこにいるのか分からないだろう。 いたるところが狂ったように発展している。ガン細胞のような発展だ。ブルドーザーが緑の森をなぎ倒してゴミに変え、積み上げて燃やそうとしている。コンクリート建築から撤去された足場用の白い丸大が灰色の壁の脇に積み上げられている。 発展というものは、どうしてこうも破壊と似ているのだろう。 ・アメリカ杉の木々からは静寂と畏怖が伝わってくる。肩じられない大きさや、見る間に移り変わる他合いだけではなく、我々の知っているどんな木とも違う存在なのだ。彼らは違う時代からの使者なのである。百万年前に絶滅したシダ類が、三億年前の石炭紀において石炭へと変化したという謎も、太古から生きる彼らの中には秘められているのだ。 光も影も彼らの中にある。どんなに自惚れた人間も、どんなに有頂天で不遜な人間も、アメリカ 杉を目の当たりにすると敬の念に打たれてしまう。まさに言葉通りに畏れ敬うのだ。紛れもない王者の風格を前にすると、人は頭を下げるべきだと感じるものなのである。 ・しかし私の頭で覚えたりもっと深い感覚に刻んだりしてきたものは、絡み合った無数の出みたいなものだ。ずっと以前に海洋生物の採取と分類に取り組みながら悟ったのだが、何を見つけるかはその時の気分に深く影響されるものなのだ。自分の外部の現実であっても、突き詰めれば自分の内部と繋がりを持っているものである。 巨大な国土の最強の国家、未来を生み出す種子たるアメリカも、私という小宇宙から見た大宇宙だと分かった。もしイギリス人やフランス人やイタリア人が私と同じルートを旅して、私と同じものを目にし、私と同じことを耳にしたとしたら、心に残る光景は私とは違ったものになるだろう。 ・「さて、この犬が喋れて、二本足で立つことができたらと考えてみてください。きっと何であっても上手にやってみせることでしょう。彼を晩餐会に招待することだってできるかもしれません。しかし、あなたは彼を人間と見なすことができますかな?」「つまり、自分の妹を彼の嫁にできるかってことですね?」 彼は笑った。 「わしはただ、物事に対する感情を変えるのがいかに難しいかを申し上げておるのです。それからこうはお考えになれませんか?黒人たちにしても、我々白人に対する感情を変えるのは難しいのです。それは我々が黒人への感情を変えるのと同じことですな。なにも新しい話ではないのです。長いこと続いてきたことですよ」 ・私が何度も寝返りを打つものだから、とうとうチャーリーが怒って何度も「フッチュ」と文句を言った。チャーリーは人間たちの問題など関係ない。原子を分裂させる知恵があるのに平和に暮らす知恵はないような種になど、犬は属していないのだ。チャーリーは人種のことなど知らないし、自分の妹の結婚なんて気にもかけない。そんな心配ごととは無縁なのである。 かつてチャーリーはダックスフントに恋をしたことがある。種族的に釣り合わず、体格的にも馬鹿げており、機能的にも無理がある恋だった。しかしそんな諸問題などチャーリーは気にしなかった。彼は相手を深く愛し、犬らしく全力を尽くしたのである。 なんだって千人もの人間が集まって一人の小さな人間を罵っていたのか、犬に向かって論理的かつ倫理的に説明するのは難しかろう。私は犬たちの瞳の中に、呆れて馬鹿にした表情が一瞬浮かんで消えるのを何度も見てきた。犬たちは基本的に人間を馬鹿だと思っていると、私は確信している。 ・私はただ、幾人かの人々が私に語ったこと、そして私が見たことを記しただけである。それが典型的なことなのか、そこから何らかの結論が導けるものなのか、私には分からない。私に分かるのは、南部は苦しみの中にあり、人々が混乱に陥っているということだ。そして解決に至る道のりは険しく込み入っていることだろう。 ムッシュー・シ・ジの言う通りだ。問題は結末ではなく、そこに至る手段なのだ。その手段が、恐ろしく不確かなのである。 - 2026年2月11日
 強運の持ち主瀬尾まいこショッピングセンターの片隅で占い師を始めたルイーズ吉田は、元OL。かつて営業職で鍛えた話術と、もちまえの直感で、悩む人たちの背中を押してあげるのが身上だが、手に負えないお客も千客万来。「お父さんとお母さん、どっちにすればいいと思う?」という小学生。何度占いがはずれてもやって来る女子高生。「俺さ、物事のおしまいが見えるんよ」という大学生まであらわれて、ルイーズはついに自分の運勢が気になりだす…。 短編4つともとても心が温かくなった。 瀬尾まいこさんの小説はからっとした明るさと人と関わる温かさに溢れてるなぁ。 どの小説も、大変なことがあってもなんとかなるさと楽観的な気持ちになれるし、自分の周りにも人の温かさは沢山あると信じたい気持ちになる。 特に好きだったのは、再婚に最適な時期が占いで出てるのに、竹子さんが子供を理由に時期をずらすと伝えるシーン。 正論やデータよりも、自分の直感や感情が自分の大切にしたいものを表しているのだと思う。 ルイーズが帰宅すると、いつも通彦が変わったご飯を作って待っているところもほっこり。 相手への愛情って日常のそういうところに感じられるよなぁ。 人との関わりに疲れたら、また読みたい小説だった。 ・その晩はそのまま二人でリビングで朝まで過ごした。二人とも翌日仕事があるのに、うとうとしては目を覚まして、しゃべったり、愛し合ったりして過ごした。 通彦の身体の柔らかさも温かさも、どれもずっとなじんできたもので、終わりのにおいはどこにもない。通彦にくっつきながら、私の中の不安はおもしろいくらい簡単にするすると消えていった。結局、どんな才能のある人の言葉でも、予言や占いは当てにならない。自分で確かめてこそ、納得ができるのだ。 とりあえず、私と通彦の終わりはまだまだ訪れそうもない。通彦と抱き合っていると、そう確 僧できた。そして、それと同時に、私は自分のおしまいが何なのかがわかった。私の元に訪れるおしまいは、もっと他のことだったのだ。 ・うん。いくら正しいことでも、先のことを教えられるのは幸せじゃないよ。占いにしたって、事実を伝えるのがすべてじゃない。その人がさ、よりよくなれるように、踏みとどまってる足を進められるように、ちょっと背中を押すだけ。占いの役割って、そういうことなんだね。武田君におしまいを宣告されて、身をもってそれがわかった気がする ・「忙しかったけど、楽しかったな」と、大きな伸びをした。 「たくさんの人を見ると、その分やっぱり面白いよね」 「ええ。見ず知らずのいろんな人の話を聞くだけでも面白いのに、その上、その人の身の上のこととか、将来のこととか一緒に考えられるんだもん。お得な商売です」 「いかにも竹子さんらしい発想だね」 と、私は笑った。でも、案外当たっているかもしれない。それが占いの醍闘味なのかもしれな い。 ・「でも、早くしないと彼の運気はどんどん下がるよ。五月までに結婚しておかないとうまくいくかどうか・・・・・・」 「そうでしたね」 「そうでしたねって、せっかく今がチャンスなのに」「いいんです。私の人生は、健太郎しだいだから」「健太郎しだい?」 「ええ。いくら相性がよくても、健太郎がいやなものはだめだし、いくら時期がよくても、健太郎が認めてくれないと動けないから」 占いにまじめな竹子さんが、さらりと言ってのけた。 「そうなんだ」 「そうなんです。子どもがいると、大変ですよ。占いにも従えないんだもん」竹子さんはちっとも大変そうではなく、楽しそうに顔をしかめて見せた。 竹子さんの明日を決めるのは、占いでも自分自身でもない。竹子さんの明日は子どもによって、動いていく。私の運勢を動かすのは、今はまだ自分自身だ。だけど、ほんの少し、私のこれからを決めるのに、通彦が入り込んでる。通彦も同じ。私が入り込んでるはずだ。
強運の持ち主瀬尾まいこショッピングセンターの片隅で占い師を始めたルイーズ吉田は、元OL。かつて営業職で鍛えた話術と、もちまえの直感で、悩む人たちの背中を押してあげるのが身上だが、手に負えないお客も千客万来。「お父さんとお母さん、どっちにすればいいと思う?」という小学生。何度占いがはずれてもやって来る女子高生。「俺さ、物事のおしまいが見えるんよ」という大学生まであらわれて、ルイーズはついに自分の運勢が気になりだす…。 短編4つともとても心が温かくなった。 瀬尾まいこさんの小説はからっとした明るさと人と関わる温かさに溢れてるなぁ。 どの小説も、大変なことがあってもなんとかなるさと楽観的な気持ちになれるし、自分の周りにも人の温かさは沢山あると信じたい気持ちになる。 特に好きだったのは、再婚に最適な時期が占いで出てるのに、竹子さんが子供を理由に時期をずらすと伝えるシーン。 正論やデータよりも、自分の直感や感情が自分の大切にしたいものを表しているのだと思う。 ルイーズが帰宅すると、いつも通彦が変わったご飯を作って待っているところもほっこり。 相手への愛情って日常のそういうところに感じられるよなぁ。 人との関わりに疲れたら、また読みたい小説だった。 ・その晩はそのまま二人でリビングで朝まで過ごした。二人とも翌日仕事があるのに、うとうとしては目を覚まして、しゃべったり、愛し合ったりして過ごした。 通彦の身体の柔らかさも温かさも、どれもずっとなじんできたもので、終わりのにおいはどこにもない。通彦にくっつきながら、私の中の不安はおもしろいくらい簡単にするすると消えていった。結局、どんな才能のある人の言葉でも、予言や占いは当てにならない。自分で確かめてこそ、納得ができるのだ。 とりあえず、私と通彦の終わりはまだまだ訪れそうもない。通彦と抱き合っていると、そう確 僧できた。そして、それと同時に、私は自分のおしまいが何なのかがわかった。私の元に訪れるおしまいは、もっと他のことだったのだ。 ・うん。いくら正しいことでも、先のことを教えられるのは幸せじゃないよ。占いにしたって、事実を伝えるのがすべてじゃない。その人がさ、よりよくなれるように、踏みとどまってる足を進められるように、ちょっと背中を押すだけ。占いの役割って、そういうことなんだね。武田君におしまいを宣告されて、身をもってそれがわかった気がする ・「忙しかったけど、楽しかったな」と、大きな伸びをした。 「たくさんの人を見ると、その分やっぱり面白いよね」 「ええ。見ず知らずのいろんな人の話を聞くだけでも面白いのに、その上、その人の身の上のこととか、将来のこととか一緒に考えられるんだもん。お得な商売です」 「いかにも竹子さんらしい発想だね」 と、私は笑った。でも、案外当たっているかもしれない。それが占いの醍闘味なのかもしれな い。 ・「でも、早くしないと彼の運気はどんどん下がるよ。五月までに結婚しておかないとうまくいくかどうか・・・・・・」 「そうでしたね」 「そうでしたねって、せっかく今がチャンスなのに」「いいんです。私の人生は、健太郎しだいだから」「健太郎しだい?」 「ええ。いくら相性がよくても、健太郎がいやなものはだめだし、いくら時期がよくても、健太郎が認めてくれないと動けないから」 占いにまじめな竹子さんが、さらりと言ってのけた。 「そうなんだ」 「そうなんです。子どもがいると、大変ですよ。占いにも従えないんだもん」竹子さんはちっとも大変そうではなく、楽しそうに顔をしかめて見せた。 竹子さんの明日を決めるのは、占いでも自分自身でもない。竹子さんの明日は子どもによって、動いていく。私の運勢を動かすのは、今はまだ自分自身だ。だけど、ほんの少し、私のこれからを決めるのに、通彦が入り込んでる。通彦も同じ。私が入り込んでるはずだ。 - 2026年2月10日
- 2026年2月9日
 何者朝井リョウ就職活動を目前に控えた拓人は、同居人・光太郎の引退ライブに足を運んだ。光太郎と別れた瑞月も来ると知っていたから――。瑞月の留学仲間・理香が拓人たちと同じアパートに住んでいるとわかり、理香と同棲中の隆良を交えた5人は就活対策として集まるようになる。だが、SNSや面接で発する言葉の奥に見え隠れする、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えていく……。 就活のときの惨めさを思い出した。。 友達の結果に一喜一憂して自己嫌悪に陥るのなんて身に覚えがありすぎて😱笑 自分の就活時代を思い出して胸がきゅーっとなると共に、登場人物の心理描写がリアルで共感できる小説だった。 自尊心を保つために人は本心を隠すけど、サワ先輩が言うように敢えて言わない本音、弱さを想像できたら、自分も相手も尊重できる気がする。 ・ツイッターの自己紹介画面に映っている自分の名前。にのみやたくと@劇団プラネット。 劇団の脚本を書いたり役者として舞台に上がるときは、漢字をひらいて、名前をひらがなで表記する。 漢字をひらがなにする、たったそれだけのことで何者かになれた日々は、もう遥か昔のことのようだ。 ・いつからか俺たちは、短い言葉で自分を表現しなければならなくなった。フェイスブックやブログのトップページでは、わかりやすく、かつ簡潔に。ツイッターでは一四〇字以内で。就活の面接ではまずキーワードから。ほんの少しの言葉と小さな小さな写真のみで自分が何者であるかを語るとき、どんな言葉を取捨選択するべきなのだろうか。 ・就職課には、内定者ボランティア、と呼ばれる人たちが常駐している。就活生のどんな相談にも乗ってくれる内定者ボランティアはみんな、首から小さなカードをぶら下げている。そこにはその人の名前より大きな文字で、内定先の企業名が書かれている。 ・個人の話を、大きな話にすり替える。そうされると、誰も何も言えなくなってしまう。 就職の話をしていたと思ったら、いつのまにかこの国の仕組みの話になっていた。そんな大きなテーマに、真っ向から意見を言える人はいない。こんなやり方で自分の優位性を確かめているとしたら、隆良の足元は相当ぐらぐらなんだろうな、と俺は思った。 ・やっぱり、想像力が無い人間は苦手だ。 どうして、就職活動をしている人は何かに流されていると思うのだろう。みんな同じようなスーツを着るからだろうか。何万人という学生が集まる合同説明会の映像がニュース番組などで流れるからだろうか。どうして、就職活動をしないと決めた自分だけが何かしらの決断を下した人間なのだと思えるのだろう。周囲がみんな黒髪でスーツを着ているときに髪を染めて私服を着ていられるからだろうか。つまらないマナー講座を笑っていられるからだろうか。 たくさんの人間が同じスーツを着て、同じようなことを訊かれ、同じようなことを喋る。 確かにそれは個々の意志のない大きな流れに見えるかもしれない。だけどそれは、「就職活動をする」という決断をした人たちひとりひとりの集まりなのだ。自分はアーティストや起業家にはきっともうなれない。だけど就職活動をして企業に入れば、また違った形の「何者か」になれるのかもしれない。そんな小さな希望をもとに大きな決断を下したひとりひとりが、同じスーツを着て同じような面接に臨んでいるだけだ。 「就活をしない」と同じ重さの「就活をする」決断を想像できないのはなぜなのだろう。 決して、個人として何者かになることを諦めたわけではない。スーツの中身までみんな同じなわけではないのだ。 ・俺たちは、人知れず決意していくようになる。なんでもないようなことを気軽に発信できるようになったからこそ、ほんとうにたいせつなことは、その中にどんどん埋もれて、隠れていく。 光太郎が、成績証明書が必要になるくらいの段階にまで辿り着いていたことだって、ツイッターもフェイスブックもメールも何も無ければ、隠されていたような気持ちはしなかったかもしれない。ただ話すタイミングが無かったんだ、と、思えたかもしれない。だけど、日常的に光太郎のことを補完してくれるものがたくさん存在してしまうから、意図的に隠されていたような気持ちになってしまう。 俺は紙の白を見つめる。 ほんとうのことが、埋もれていく。手軽に、気軽に伝えられることが増えた分、ほんとうに伝えたいことを、伝えられなくなっていく。 ・就職活動において怖いのは、そこだと思う。確固たるものさしがない。ミスが見えないから、その理由がわからない。自分がいま、集団の中でどれくらいの位置にいるかがわからない。面接が進んでいく中で人数が減っていき、自分の順位が炙り出されそうになったところで、また振り出しに戻ってしまう。マラソンと違って最初からゴールが定められているわけではないから、ペース配分を考えるなんていう頭脳戦にも持ち込めない。クールを装うには安心材料がなさすぎるのだ。 だから、その中でむりやりクールを装おうとすると、間違った方向に進んでしまうことになる。説明会で自分だけ私服だったことをアピールしてみたり、就活という制度そのものを批判することで、個性とか、夢とか、そういう大きな話への転換を試みてみたり。 ・「お前、こんなことも言ってたよな」 返事をすることができないでいると、サワ先輩の声が少し、小さくなった。 「メールやツイッターやフェイスブックが流行って、みんな、短い言葉で自己紹介をしたり、人と会話をするようになったって。だからこそ、その中でどんな言葉が選ばれているかが大切な気がするって」 サワ先輩は、ツイッターもフェイスブックも利用していない。 「俺、それは違うと思うんだ」 サワ先輩は用があるならメールじゃなくて電話して、と、いつも俺に言ってくる。 「だって、短く簡潔に自分を表現しなくちゃいけなくなったんだったら、そこに選ばれなかった言葉のほうが、圧倒的に多いわけだろ」サワ先輩は、この現実の中にしかいない。 「だから、選ばれなかった言葉のほうがきっと、よっぽどその人のことを表してるんだと思う」 俺はサワ先輩の背中を見つめる。 「たった一四〇字が重なっただけで、ギンジとあいつを一緒に束ねて片付けようとするな よ」 いつのまにか、目の前には、目的の図書館がある。 「ほんの少しの言葉の向こうにいる人間そのものを、想像してあげろよ、もっと」 ・誰も渡らない深夜の横断歩道を前にして、タクシーは動かない。 「なんかみんなさ、すげえ考えてんの。これからの出版業界のこととか、どういう企画やりたいとか、すげえ熱く語れんの、すでに」 十数時間前、光太郎は、会社の同期に初めて会った。昼に人事部を含めて食事会をして、そのあとは同期だけで夕方までファミレスにいたという。 「それ聞いてさ、俺、思ったんだよね」 僧号が青になる。 「俺って、ただ就活が得意なだけだったんだって」車が動き出して、背もたれに乗っている光太郎の頭が小刻みに揺れた。 「足が速いとかサッカーがうまいとか、料理ができるとか字がうまいとかそういうのと同じレベルで、就活が得意なだけだったんだよ」また、メーターが上がる。 「なのに、就活がうまくいくと、まるでその人間まるごと超すげえみたいに言われる。就活以外のことだって何でもこなせる、みたいにさ。あれ、なんなんだろうな」チッチッチッチ、と音がしたと思うと、タクシーが右に曲がった。 「それと同じでさ、ピーマンが食べられないように、逆上がりができないように、ただ就活が苦手な人だっているわけじゃん。それなのに、就活がうまくいかないだけで、その人が丸ごとダメみたいになる」 ・「笑われてることだってわかってるくせに、そんなことしてるのは何でだと思う?」 理香さんは、歯を食いしばりながら、言葉の続きを絞り出しているように見える。 「それ以外に、私に残された道なんてないからだよ」 唇からではなく、全身から、声が聞こえてきたような気がした。 「ダサくてカッコ悪い自分を理想の自分に近づけることしか、もう私にできることはないんだよ」 鳴っているみたいだ、と俺は思った。 「ダサくてカッコ悪い今の自分の姿で、これでもかってくらいに悪あがきするしかないんだよ、もう」 震えるようにそう言う理香さんは、まるで全身を鳴らしているように見える。 耳の中で、いろんな人の声が蘇る。 「自分は自分にしかなれないんだよ。だって、留学したってインターンしたってボランティアしたって、私は全然変わらなかったもん。憧れの、理想の誰にもなれなかった。貧しい国の子どもと触れあったり、知らない土地に学校を建てたりした手でそのまま、人のアドレスからツイッターのアカウント探したり、人の内定先をネットで検索したりしてる。 それがブラック会社って噂されてるようなところだったら、ちょっと、慰められたりしてる。今でも、ダサくて、カッコ悪くて、醜い自分のまま。何したってね、何も変わらなかった」
何者朝井リョウ就職活動を目前に控えた拓人は、同居人・光太郎の引退ライブに足を運んだ。光太郎と別れた瑞月も来ると知っていたから――。瑞月の留学仲間・理香が拓人たちと同じアパートに住んでいるとわかり、理香と同棲中の隆良を交えた5人は就活対策として集まるようになる。だが、SNSや面接で発する言葉の奥に見え隠れする、本音や自意識が、彼らの関係を次第に変えていく……。 就活のときの惨めさを思い出した。。 友達の結果に一喜一憂して自己嫌悪に陥るのなんて身に覚えがありすぎて😱笑 自分の就活時代を思い出して胸がきゅーっとなると共に、登場人物の心理描写がリアルで共感できる小説だった。 自尊心を保つために人は本心を隠すけど、サワ先輩が言うように敢えて言わない本音、弱さを想像できたら、自分も相手も尊重できる気がする。 ・ツイッターの自己紹介画面に映っている自分の名前。にのみやたくと@劇団プラネット。 劇団の脚本を書いたり役者として舞台に上がるときは、漢字をひらいて、名前をひらがなで表記する。 漢字をひらがなにする、たったそれだけのことで何者かになれた日々は、もう遥か昔のことのようだ。 ・いつからか俺たちは、短い言葉で自分を表現しなければならなくなった。フェイスブックやブログのトップページでは、わかりやすく、かつ簡潔に。ツイッターでは一四〇字以内で。就活の面接ではまずキーワードから。ほんの少しの言葉と小さな小さな写真のみで自分が何者であるかを語るとき、どんな言葉を取捨選択するべきなのだろうか。 ・就職課には、内定者ボランティア、と呼ばれる人たちが常駐している。就活生のどんな相談にも乗ってくれる内定者ボランティアはみんな、首から小さなカードをぶら下げている。そこにはその人の名前より大きな文字で、内定先の企業名が書かれている。 ・個人の話を、大きな話にすり替える。そうされると、誰も何も言えなくなってしまう。 就職の話をしていたと思ったら、いつのまにかこの国の仕組みの話になっていた。そんな大きなテーマに、真っ向から意見を言える人はいない。こんなやり方で自分の優位性を確かめているとしたら、隆良の足元は相当ぐらぐらなんだろうな、と俺は思った。 ・やっぱり、想像力が無い人間は苦手だ。 どうして、就職活動をしている人は何かに流されていると思うのだろう。みんな同じようなスーツを着るからだろうか。何万人という学生が集まる合同説明会の映像がニュース番組などで流れるからだろうか。どうして、就職活動をしないと決めた自分だけが何かしらの決断を下した人間なのだと思えるのだろう。周囲がみんな黒髪でスーツを着ているときに髪を染めて私服を着ていられるからだろうか。つまらないマナー講座を笑っていられるからだろうか。 たくさんの人間が同じスーツを着て、同じようなことを訊かれ、同じようなことを喋る。 確かにそれは個々の意志のない大きな流れに見えるかもしれない。だけどそれは、「就職活動をする」という決断をした人たちひとりひとりの集まりなのだ。自分はアーティストや起業家にはきっともうなれない。だけど就職活動をして企業に入れば、また違った形の「何者か」になれるのかもしれない。そんな小さな希望をもとに大きな決断を下したひとりひとりが、同じスーツを着て同じような面接に臨んでいるだけだ。 「就活をしない」と同じ重さの「就活をする」決断を想像できないのはなぜなのだろう。 決して、個人として何者かになることを諦めたわけではない。スーツの中身までみんな同じなわけではないのだ。 ・俺たちは、人知れず決意していくようになる。なんでもないようなことを気軽に発信できるようになったからこそ、ほんとうにたいせつなことは、その中にどんどん埋もれて、隠れていく。 光太郎が、成績証明書が必要になるくらいの段階にまで辿り着いていたことだって、ツイッターもフェイスブックもメールも何も無ければ、隠されていたような気持ちはしなかったかもしれない。ただ話すタイミングが無かったんだ、と、思えたかもしれない。だけど、日常的に光太郎のことを補完してくれるものがたくさん存在してしまうから、意図的に隠されていたような気持ちになってしまう。 俺は紙の白を見つめる。 ほんとうのことが、埋もれていく。手軽に、気軽に伝えられることが増えた分、ほんとうに伝えたいことを、伝えられなくなっていく。 ・就職活動において怖いのは、そこだと思う。確固たるものさしがない。ミスが見えないから、その理由がわからない。自分がいま、集団の中でどれくらいの位置にいるかがわからない。面接が進んでいく中で人数が減っていき、自分の順位が炙り出されそうになったところで、また振り出しに戻ってしまう。マラソンと違って最初からゴールが定められているわけではないから、ペース配分を考えるなんていう頭脳戦にも持ち込めない。クールを装うには安心材料がなさすぎるのだ。 だから、その中でむりやりクールを装おうとすると、間違った方向に進んでしまうことになる。説明会で自分だけ私服だったことをアピールしてみたり、就活という制度そのものを批判することで、個性とか、夢とか、そういう大きな話への転換を試みてみたり。 ・「お前、こんなことも言ってたよな」 返事をすることができないでいると、サワ先輩の声が少し、小さくなった。 「メールやツイッターやフェイスブックが流行って、みんな、短い言葉で自己紹介をしたり、人と会話をするようになったって。だからこそ、その中でどんな言葉が選ばれているかが大切な気がするって」 サワ先輩は、ツイッターもフェイスブックも利用していない。 「俺、それは違うと思うんだ」 サワ先輩は用があるならメールじゃなくて電話して、と、いつも俺に言ってくる。 「だって、短く簡潔に自分を表現しなくちゃいけなくなったんだったら、そこに選ばれなかった言葉のほうが、圧倒的に多いわけだろ」サワ先輩は、この現実の中にしかいない。 「だから、選ばれなかった言葉のほうがきっと、よっぽどその人のことを表してるんだと思う」 俺はサワ先輩の背中を見つめる。 「たった一四〇字が重なっただけで、ギンジとあいつを一緒に束ねて片付けようとするな よ」 いつのまにか、目の前には、目的の図書館がある。 「ほんの少しの言葉の向こうにいる人間そのものを、想像してあげろよ、もっと」 ・誰も渡らない深夜の横断歩道を前にして、タクシーは動かない。 「なんかみんなさ、すげえ考えてんの。これからの出版業界のこととか、どういう企画やりたいとか、すげえ熱く語れんの、すでに」 十数時間前、光太郎は、会社の同期に初めて会った。昼に人事部を含めて食事会をして、そのあとは同期だけで夕方までファミレスにいたという。 「それ聞いてさ、俺、思ったんだよね」 僧号が青になる。 「俺って、ただ就活が得意なだけだったんだって」車が動き出して、背もたれに乗っている光太郎の頭が小刻みに揺れた。 「足が速いとかサッカーがうまいとか、料理ができるとか字がうまいとかそういうのと同じレベルで、就活が得意なだけだったんだよ」また、メーターが上がる。 「なのに、就活がうまくいくと、まるでその人間まるごと超すげえみたいに言われる。就活以外のことだって何でもこなせる、みたいにさ。あれ、なんなんだろうな」チッチッチッチ、と音がしたと思うと、タクシーが右に曲がった。 「それと同じでさ、ピーマンが食べられないように、逆上がりができないように、ただ就活が苦手な人だっているわけじゃん。それなのに、就活がうまくいかないだけで、その人が丸ごとダメみたいになる」 ・「笑われてることだってわかってるくせに、そんなことしてるのは何でだと思う?」 理香さんは、歯を食いしばりながら、言葉の続きを絞り出しているように見える。 「それ以外に、私に残された道なんてないからだよ」 唇からではなく、全身から、声が聞こえてきたような気がした。 「ダサくてカッコ悪い自分を理想の自分に近づけることしか、もう私にできることはないんだよ」 鳴っているみたいだ、と俺は思った。 「ダサくてカッコ悪い今の自分の姿で、これでもかってくらいに悪あがきするしかないんだよ、もう」 震えるようにそう言う理香さんは、まるで全身を鳴らしているように見える。 耳の中で、いろんな人の声が蘇る。 「自分は自分にしかなれないんだよ。だって、留学したってインターンしたってボランティアしたって、私は全然変わらなかったもん。憧れの、理想の誰にもなれなかった。貧しい国の子どもと触れあったり、知らない土地に学校を建てたりした手でそのまま、人のアドレスからツイッターのアカウント探したり、人の内定先をネットで検索したりしてる。 それがブラック会社って噂されてるようなところだったら、ちょっと、慰められたりしてる。今でも、ダサくて、カッコ悪くて、醜い自分のまま。何したってね、何も変わらなかった」 - 2026年2月7日
 満月が欠けている穂村弘歌人である著者が持病である緑内障とその周辺について語った本。 子供時代から弱かった目の話から、眼科の主治医・精神科医との対談、目に関する詩、死生観についての話が書かれている。 弱みを抱えて生きるということ。 でも、世間一般で考えられている弱みは本当に弱さなのだろうかと考えさせられる。 「涙と同じ成分の目薬は何かに違反してる気がする」という詩と、「統合失調症患者は人類にとっての『生きのびるための保険』だと言えるのではないか」という話が特に好きだった。 ・人は苦しむ以上に恐れる フランスの哲学者のアランの『幸福論』という本の中に「われわれは苦しむ以上に恐れるのである」という言葉があります。子供の頃、その言葉を見つけて、線を引いた記憶があります。 ちなみに、私がとても恐れているのが睡眠不足です。夜中に自宅に帰ってきて、翌朝早くに起きなくてはいけないことになると、今すぐ寝てもほとんど眠れないのではないかと思ってなかなか寝つけないんです。 すると、余計な心配が頭に浮かんできてすごく焦り始めます。ただ、実際に寝不足で大失敗したことなんて人生で記憶にないくらいのことなんですよ。だけど、寝不足を恐れたことは100回や200回じゃ済まないぐらいあります。その労力に全然釣り合っていないんですよね。自分にとっては苦しんだり失敗したりすることよりも、不安で恐れることのほうが心の中に占める割合がすごく大きいみたいです。 実際には、ほとんど寝ていなくても次の日に眠くなった記憶はありません。むしろ、仕事が終わって、たっぷり寝た次の日のほうが眠いことがあるから不思議ですよね。 どうやら、まだ物事が起きていない時にこそ、人間は不安を感じるらしい。 実際に本番になったら、「昨日俺は寝ていないんだ」みたいには思わないですよね。 でも、どうしても克服できない。次の仕事の前日になると、また同じ不安に駆られてしまうんです。 ・ビクビクの個人差 私の中で睡眠不足を恐れることと緑内障を恐れることは似た側面があります。緑内障は自分が病気であることに気づいていない人が多いそうです。現在治療している人はほんの一部で、潜在的には500万人近い人が緑内障の有病者だと言います。 でも、たとえ病気に気づいていなくても、失明などの致命的なことが起きる割合は、おそらくそんなには多くないのではないでしょうか。なぜなら、緑内障は高齢者に多い病気なので、実際に自覚症状が出る前に亡くなる人が多いからです。おそらくそうした人は、自分の目が悪いとはまったく思わずに人生を終えたのではないかと思います。 でも、私は早めに緑内障が見つかったので、すごくビクビクしていろいろと情報を調べました。眼科にも何度も行って目薬も総額でいくらになるのか分からないほど購入しています。時間もお金もメンタルも削られて、最後まで何とか生活に不自由のない視野が保てれば、「良かった」と思うことができるわけですが、緑内障であることに気づかないまま亡くなった人と私の差っていったい何なのだろうと考えると、不思議な感情に襲われます。 でも、気づいてしまった以上、ギリギリセーフとギリギリアウトは大きな違いです。 リアルタイムの患者としては、早く見つかって良かった、というのは確かなことです。 ただ、緑内障の患者さんの中には、病気が見つかっても放置する人も多いと聞きます。だから、誰もが未来のことを恐れるわけじゃないんですよね。 徹夜が平気な人もいれば、仕事に行って居眠りをして失敗をしても、さほど気にしないという人もいます。それどころか、また同じことを繰り返す強いメンタルの人すらいます。物事を恐れる度合いには大きな個人差があるみたいですね。 ・涙と同じ成分の目薬は何かに違反してる気がする シラソ ・消し惜しむ手術前夜の冬灯視力戻るは五分五分なれば 越前春生 ・誰も他人のことは分からない 妻と食堂に入ると、「きっとこれを注文するだろう」と、予想してみるのですが、結構な割合で外れてしまいます。今まで一度も頼んだことのないようなものを急に注文したりして、驚くことがよくあります。長年いっしょにいてご飯を食べている夫婦でも、そういうものなんですね。 また、違った意味で予想できなかったのが、編集者の二階堂奥歯さんのことです。 二階堂さんと本の打ち合わせをしていた時、私がのろのろしていて、なかなか仕事を進めないことに業を煮やした彼女が、「早く書いてくれないと、私死んじゃうかもしれないから間に合いませんよ」って言ったんです。 私はその言葉を完全に冗談だと思っていました。なぜなら、彼女は若くて賢くてセンスがあって、編集者としても非常に優秀な人でした。また、多くの友人に囲まれて恋人もいて家族仲も良かったそうなんです。客観的に見ると、死ぬ理由なんてまったくないように思えたんです。 ところが、ある日、訃報というタイトルのメールが来ていて、文面を見たら、二階堂さんが亡くなったという知らせでした。衝撃でした。「あの言葉は本当だったんだ」と思いました。実際、二階堂さんとつくろうとしていた本は、まだ打ち合わせ段階で完成しませんでした。私は全然、分かっていなかった。 芸能人などの自殺のニュースに驚くことがありますよね。美しくて活躍していて幸せそうで、苦しみの気配なんて見えなかった人が突然亡くなってしまう。 でも、その人からしたら、生きていたくないほど苦しかったんでしょう。それなのに、他人が外から見ても、そのことは分からないという事実に衝撃を覚えます。これってすごく怖いことですよね。 もしそうなら、死のこと以外でも、親しいと思っている人に嫌われている可能性だって、そのほかのなんだって、十分あり得るわけですから。 ・精神科の場合、病気を治すという発想でやっていたらあまり意味がありません。患者さんの考える幸福の着地点をいっしょに見つけるほうが重要だと思います。軽い病人であるほうが幸せなんていう人はいくらでもいるわけです。健康すなわちハッピーとはまったく言えません。 どう生きていきたいのかという患者さんの主観にかかっているんですね。 病気を「やっつける」「退治する」といった単純な考え方では、精神科では通用しないということです。その延長で申すなら、ぜんそくや緑内障などの慢性疾患も完治するという発想を捨てれば、どの辺りで折り合いをつけるのかという話になると思います。その点では精神科と近いところがあるのではないでしょうか。 ・私が診療で重要だと思っているのが、「プロセス」と「罪悪感」です。人生にはなかなか結論や結果が出ないとか、どう頑張っていいのか分からないとか、中途半端であったり曖昧な状態にとにかく耐えなければならないシーンが多い。我武者羅に努力すればどうにかなる、なんてわけにはいかない。だからせめて過去の成功体験にすがって自分を勇気づけたり、本やドラマを通して自身を鼓舞したり、楽天的で前向きな気持ちになろうとあれこれ工夫しつつ機が熟すのを待つしかない。 でも精神を病むと、機が熟すのを待つだけの余裕が失われてしまうんです。「待てば海路の日和あり」と驚場に構えてみるとか、せめて可能な範囲で準備を繋えるとか、ちょっと方向性を変えてみるとかの「ゆとり」がなくなってしまう。 あたかも無駄とか回り道のように見えるプロセスの必要性を患者さんは倍じられなくなる。私が言う「プロセス」とは、そのような無意味に映るけれども実は必要不可分な過程のことですね。 罪悪感について言えば、患者さんの中には親の期待に応えられなかったり、自分自身の理想に近づけなかったりといったある種の後悔を引きずっている人がいます。でも、罪悪感を持っていない人なんていません。むしろエネルギーにすらなり得る。そのことをはっきりと指摘したほうが患者さんの中で気持ちが整理されて楽になる場合もあるんですよね。 ・人間以外の動物はおそらく死ぬのはまったく怖くないのだと思います。種として存在してさえいればいいというようなある種の安心感のようなものを感じます。人間以外の動物にとって死は皮膚細胞の一つがはがれるような感覚なのでしょう。 確かにそう見えますね。動物にとって死は恐れることではないとすると、時間の概念がないとも言えると思います。でも、動物も歳をとります。動物が時間を知らなくても老化を免れないというのは、不思議な感じがしますね。 春日 動物も「最近不便になったな」というような感覚はあるのではないでしょうか。 「もっと高くジャンプできたのに」とか思っているかもしれませんね。でも、人間は「今60歳なのでまだこれぐらいはジャンプできるけど、80歳になったらさぞかし厳しいだろう」とか思ってしまいます。どうしたら、人間は主観的な幸福感を最大限にして死んでいけるのでしょう。 誰もが工夫していますが、いまだ達成できていないテーマだと思います。ただ、最近のベストセラー本を読んでいると、「自分が滅びてもいずれ誰かが達成できればよいと思えるようなライフワークを見つけなさい」とは言っていますね。 いわゆる大義ってことでしょうか。でも、動物は繁殖できればライフワークは達成なのでしょう。ある時代までは人間もそのような感じだったのかも。やがて家族や家という制度ができてくる。 精神科の立場で見ると、家族や家が精神病理に与える影響は大きいものがあります。ちなみに、思想家の内田さんは両親と子一人の核家族は家族ではなく、単なるパワーゲームの場だと言っています。つまり、子供が小さいうちは親の権力が絶大で、子供が成長すれば親に復讐することもあるというわけです。そこで、内田さんは「おじさんか、おばさんがいれば、親の絶対性が揺らいでパワーバランスが整うのだ」と指摘しています。もし、そのような環境がないのだとしたら、就職や結婚などで早いうちに家の外に出ることが生物的に自然なことなのだと思います。精神的に不健康な家族から逃げ損ねた人を診察していると、親といることで、精神病理がますます煮詰まっていく傾向にあるように感じます。 確かに、動物は早いうちにみんな独り立ちしますよね。そうなると、人間にとって家を出るというのはどういった意味があるのでしょうか。 「自分なりの価値観に基づいて生きていく」ということでしょう。自分に正直に、ね。でもそんなことを言いながら私も30歳まで家にいましたけどね。 ・生と死について疑問に思っていることがあります。私たちはふだん、生をノーマル状態、死を一種の非常事態のように捉えていますが、実際は逆なのではないかということです。死の大海の上にかろうじて浮かんでいる木切れのような生のイメージです。むしろ生のほうが例外的な事態なんじゃないか。 そんな我々にとって、死は無根拠に突然襲ってくるものなので、本来は絶えずそれに対して心を向けていなくてはいけないはずです。でも、その事実による衝撃があまりにも大き過ぎるので、とても耐えることができない。ですから、私たちの意識は死をぎりぎりまで直視しないように隠蔽する方向に向かうのだろうと思います。 確かに、医療現場で患者さんが亡くなって家族が泣いているシーンを見ても、泣かなきゃいけないと思って泣いている人が案外多いように感じます。死を特別なものとして扱わなければならないというある種の思い込みがあるのでしょ らね。 詩人の言語感覚に死への感度を見ることがあります。以前、あるイベントに登壇して、最初に一人ずつ「こんにちは」と自己紹介をしている時、詩人の白石かずこさんは第一声で「私が死のうと思った夜、電話が鳴った」と言われました。 思わず息を呑んでしまいましたが、考えてみると、最初は「こんにちは」から入るというのは「しばらくは死なない」と宣言しているようなものかも。言わば、死の隠蔽が手順化したものと言えるのではないでしょうか。 白石さんが「こんにちは」と同じくらいの感覚で「自殺を考えていることをほのめかす」というのは死を日常的なものとして見ているということですよね。 精神科医をしていると、度々自殺をする患者さんに遭遇することがあります。 自殺は個別的に見ると痛ましい出来事ですが、仮に私が神様で人間をつくるとしたら、自省を促す契機を与えるといった意味合いで、一定の割合で自殺をするプログラムを組み込むと思います。自殺によって「人間の心はなんて不可解なんだろう」と、時にはショックを与えることも必要なのではないかと思っています。そうやって人間の感情を揺さぶることによって、不可解な出来事を探求したり繊細な感情を表現したりする哲学や思想や芸術が生まれたのでしょう。 マクロな視点で見れば意味があるということですね。 詩人の感受性と世間でときおり生じる不可解な自殺とは、どこかで通底しているのかもしれません。 ところで、統合失調症患者は孤独と痛みに対してとても強いと言われています。 彼らはどこか浮世離れしていたり、そつなさを求められる通常のコミュニケーションではハンディがありますが、ジャングルの中で水源を発見するような場面ではある種の鋭敏さを発揮します。 現代の基準では非日常的な場面でこそ力を発揮するということですね。 ちなみに、「統合失調症患者はどの国、どの人種にもほぼ1%弱いる」と言われています。神様が非常時に救世主となる存在をプログラムしていると考えるならば、統合失調症患者は人類にとっての「生きのびるための保険」だと言えるのではないでしょうか。 途方もない天変地異が起きても誰かが生き残るためには、現代社会では力を発揮できないような人が一定数いなければいけない。言わば多様性ですよね。そういったマクロな視点で見ると、病気にも潜在的な意味があるのではないでしょうか。 ・本当に大切なもの 私は子どもがカブトムシやプラモデルを大切に思う気持ちと大人が健康やお金を大切に思う気持ちには、大きな隔たりがあると思っています。子どもは健康を損ねたり、お金を自分で使ったり管理したりする経験が乏しいので、これらを強く意識することはありません。つまり、子どもがカブトムシやプラモデルを大事に思う気持ちの中には純粋な関心や興味しかないんです。一方、大人が健康やお金が大事という時には、言葉の詐術による価値のすり替えのようなものが働いているのではないかと思っています。 私も歳を重ねるにつれて、健康を維持するために病院に行く機会が増えています。 内科だけでも二つとか行くようになると、お金も時間もかかります。歳をとると通勤するように病院に行く感覚がだんだんと分かるようになってきました。でも、本当は病院に行きたい人なんていないと思います。それよりも旅行に行ったり趣味に時間を使ったりしたいはずですが、病院のほうが強制力が強いんですよね。会社にも病院と似たところがあって、こちらはお金のためですね。もしかしたら、病院や会社に行きたい人もいるかもしれないですが、健康やお金のためだと思うと強制力は強くならざるを得ません。 でも、私は本当の意味ではお金や健康など大切ではないと思っています。それらはただ、なくてはとても困るものというだけなんです。お金はただの紙切れと金属だから、大切なわけがないのですが、なくては困るんです。健康だって自分自身を人質に取られているようなものです。 一方、カブトムシやプラモデルはなくても絶対的に困ることはない。ただ、純粋に好きだから大切というだけです。なくては困るものを大切と言うのであれば、健康やお金はもちろん何よりも大切ですが、私にはその二つは本当は別のことのように思われます。 ・「生きる」と「生きのびる」 表現をする際に意識していることは他にもあって、例えば「生きのびる」と「生きる」という概念です。生きのびるというのは、前述のように健康やお金について、「なくては困る」がイコール「大切」と意識がずらされている状態を言います。つまり、生きのびなければ、生きることができないということです。ちなみに、生きのびるということの目的は全員が共有しています。当然目指すべきベクトルもいっしょになっていきます。 病院や会社を最高の場所と思っていなくても、生きのびるためにどうしても行かなくてはならないことがあります。我々は生きのびるという土台の上で、初めて生きることができるからです。 一方、生きるのほうは、先ほど述べたように詰将棋や乗り物の空気抵抗の考察など、人によってやりたいことの方向性が異なります。例えば、住宅地の道で私がずっとしゃがんでいるとしましょう。すると、不審者だと思われてお巡りさんがやってきます。 この時お巡りさんに「コンタクトレンズを探しています」と言えば、全員が共有している生きのびるの概念に該当して、社会的にOKになります。コンタクトレンズを探すのは「なくては困る」からですよね。 しかし、「このアリの列がどこまで続いているのかなと思って」と言うとNGになります。この「なぜアリの列が見たいのか?」と聞かれても答えることができない状態こそが生きるに相当します。その人にとって、なぜそれが大切なのかは説明が難しいけれども、人間の最終的な目標は生きるのほうのはずです。多くの人が死ぬ時に後悔するのは生きのびることに資源を割き過ぎたということなんですね。「もっと純粋に生きることに熱中すれば良かった」と思う。でも、死ぬまでの時間を何十年も引き延ばされてしまうと、生きのびることの強制力のほうがどうしても強くなってしまうんです。 無頼派の詩人やロックスター、冒険家、犯罪者といった非社会的な適性がある一部の人以外は、なかなか生きのびることへの強制力に抗えません。また、多くの場合、生きのびることに抗ったロックスターや冒険家や犯罪者は早く死にがちです。そうしたこともあって、我々はこうした人々のことを心のどこかで羨ましく思いつつ、決して真似しようとは思いません。 ・みんな方舟の上に乗っている 社会は生きのびるという全員の共通目的の上で、個人に対して最大公約数的な生存への優位性を求めます。ただ、それも時代や国が変われば、まったく変わってしまうんです。例えば、「みだらな行為」という言葉がありますよね。つまり、これは性的な行為のことを指すわけですが、この言葉が使われるのは報道の場面など特定の状況だけです。本来は種の保存にとってなくてはならない行為が局面によって善にも悪に もなる。 昔の日本ではいわゆる婚前交渉は禁忌で「一線を越える」などと表現していましたが、時代を経るにつれて「できちゃった婚」「授かり婚」といったようにネーミングが変わっていきました。いつの間にか良いものであるかのように意味さえも変わってしまっているんです。現象自体は同じことを指しているのに、ネーミングが変わっているのは社会のニーズが変化したからだと言えるでしょう。 そうした観点で今の社会を見ていると、自分が若かった頃に関心を持ち、みんなが資源を投入して、コミットした問題は、もはや現在の重要事項ではなくなっているという感覚があります。でも、それが果たして解決したのかと言うと、必ずしもそうではないと思います。私はこうした時代の変化の本質をマイノリティ性の問題として捉えています。 若い世代の人たちは、当事者性やマイノリティ性の問題に非常に敏感です。さまざまな領域の若い人たちと話すと、彼ら、彼女らの多くは弱さをキーにした表現の展開に関心を持っています。 私も以前からマイノリティ性や弱さを表現のテーマの一つにしてきましたが、それは自分の資質的なものが大きかったんです。「暗いダメ人間が魔法の杖を手に入れて世界をひっくり返す」というようなイメージを持っていました。単に今までマイナスだったから、プラスになる魔法の杖はないかなと探すような感じですね。これは弱さが強さに反転するという夢を求めているだけなんですよ。 でも、若い世代の人たちはもっと倫理的なことを考えているみたいです。その根本では、他者とどう向き合っていくのかということが問われていると思っています。人間の数だけ無限の立場と考え方があり得るわけなんです。でも、かつての私が表現の中で想定していたのは他者がいない世界なんです。 私の若い頃には世界が滅びるとか日本がダメになるとか、そういう感覚はありませんでした。当時は、世界はとても広く、ポテンシャルがまだまだあると思っていました。そうした条件下においては、他人と傷つけあっても互いに別の場所で生きていけばいいだけで、無数の選択肢があると考えることができました。 でも、時代の流れの中で近年感じるのは、全員が方舟に乗って危うい運命を共有しているような感覚です。そんな状況だと、方舟の上で喧嘩するとか焚き火をしちゃうとかいったことは、非常にリスクが高くなってしまいます。加害性について全員が敏感になる必要がある。かつてのようにそこにポテンシャルがあれば互いに傷つけあってもいいだろう、といった考え方は今は成立困難に思えます。
満月が欠けている穂村弘歌人である著者が持病である緑内障とその周辺について語った本。 子供時代から弱かった目の話から、眼科の主治医・精神科医との対談、目に関する詩、死生観についての話が書かれている。 弱みを抱えて生きるということ。 でも、世間一般で考えられている弱みは本当に弱さなのだろうかと考えさせられる。 「涙と同じ成分の目薬は何かに違反してる気がする」という詩と、「統合失調症患者は人類にとっての『生きのびるための保険』だと言えるのではないか」という話が特に好きだった。 ・人は苦しむ以上に恐れる フランスの哲学者のアランの『幸福論』という本の中に「われわれは苦しむ以上に恐れるのである」という言葉があります。子供の頃、その言葉を見つけて、線を引いた記憶があります。 ちなみに、私がとても恐れているのが睡眠不足です。夜中に自宅に帰ってきて、翌朝早くに起きなくてはいけないことになると、今すぐ寝てもほとんど眠れないのではないかと思ってなかなか寝つけないんです。 すると、余計な心配が頭に浮かんできてすごく焦り始めます。ただ、実際に寝不足で大失敗したことなんて人生で記憶にないくらいのことなんですよ。だけど、寝不足を恐れたことは100回や200回じゃ済まないぐらいあります。その労力に全然釣り合っていないんですよね。自分にとっては苦しんだり失敗したりすることよりも、不安で恐れることのほうが心の中に占める割合がすごく大きいみたいです。 実際には、ほとんど寝ていなくても次の日に眠くなった記憶はありません。むしろ、仕事が終わって、たっぷり寝た次の日のほうが眠いことがあるから不思議ですよね。 どうやら、まだ物事が起きていない時にこそ、人間は不安を感じるらしい。 実際に本番になったら、「昨日俺は寝ていないんだ」みたいには思わないですよね。 でも、どうしても克服できない。次の仕事の前日になると、また同じ不安に駆られてしまうんです。 ・ビクビクの個人差 私の中で睡眠不足を恐れることと緑内障を恐れることは似た側面があります。緑内障は自分が病気であることに気づいていない人が多いそうです。現在治療している人はほんの一部で、潜在的には500万人近い人が緑内障の有病者だと言います。 でも、たとえ病気に気づいていなくても、失明などの致命的なことが起きる割合は、おそらくそんなには多くないのではないでしょうか。なぜなら、緑内障は高齢者に多い病気なので、実際に自覚症状が出る前に亡くなる人が多いからです。おそらくそうした人は、自分の目が悪いとはまったく思わずに人生を終えたのではないかと思います。 でも、私は早めに緑内障が見つかったので、すごくビクビクしていろいろと情報を調べました。眼科にも何度も行って目薬も総額でいくらになるのか分からないほど購入しています。時間もお金もメンタルも削られて、最後まで何とか生活に不自由のない視野が保てれば、「良かった」と思うことができるわけですが、緑内障であることに気づかないまま亡くなった人と私の差っていったい何なのだろうと考えると、不思議な感情に襲われます。 でも、気づいてしまった以上、ギリギリセーフとギリギリアウトは大きな違いです。 リアルタイムの患者としては、早く見つかって良かった、というのは確かなことです。 ただ、緑内障の患者さんの中には、病気が見つかっても放置する人も多いと聞きます。だから、誰もが未来のことを恐れるわけじゃないんですよね。 徹夜が平気な人もいれば、仕事に行って居眠りをして失敗をしても、さほど気にしないという人もいます。それどころか、また同じことを繰り返す強いメンタルの人すらいます。物事を恐れる度合いには大きな個人差があるみたいですね。 ・涙と同じ成分の目薬は何かに違反してる気がする シラソ ・消し惜しむ手術前夜の冬灯視力戻るは五分五分なれば 越前春生 ・誰も他人のことは分からない 妻と食堂に入ると、「きっとこれを注文するだろう」と、予想してみるのですが、結構な割合で外れてしまいます。今まで一度も頼んだことのないようなものを急に注文したりして、驚くことがよくあります。長年いっしょにいてご飯を食べている夫婦でも、そういうものなんですね。 また、違った意味で予想できなかったのが、編集者の二階堂奥歯さんのことです。 二階堂さんと本の打ち合わせをしていた時、私がのろのろしていて、なかなか仕事を進めないことに業を煮やした彼女が、「早く書いてくれないと、私死んじゃうかもしれないから間に合いませんよ」って言ったんです。 私はその言葉を完全に冗談だと思っていました。なぜなら、彼女は若くて賢くてセンスがあって、編集者としても非常に優秀な人でした。また、多くの友人に囲まれて恋人もいて家族仲も良かったそうなんです。客観的に見ると、死ぬ理由なんてまったくないように思えたんです。 ところが、ある日、訃報というタイトルのメールが来ていて、文面を見たら、二階堂さんが亡くなったという知らせでした。衝撃でした。「あの言葉は本当だったんだ」と思いました。実際、二階堂さんとつくろうとしていた本は、まだ打ち合わせ段階で完成しませんでした。私は全然、分かっていなかった。 芸能人などの自殺のニュースに驚くことがありますよね。美しくて活躍していて幸せそうで、苦しみの気配なんて見えなかった人が突然亡くなってしまう。 でも、その人からしたら、生きていたくないほど苦しかったんでしょう。それなのに、他人が外から見ても、そのことは分からないという事実に衝撃を覚えます。これってすごく怖いことですよね。 もしそうなら、死のこと以外でも、親しいと思っている人に嫌われている可能性だって、そのほかのなんだって、十分あり得るわけですから。 ・精神科の場合、病気を治すという発想でやっていたらあまり意味がありません。患者さんの考える幸福の着地点をいっしょに見つけるほうが重要だと思います。軽い病人であるほうが幸せなんていう人はいくらでもいるわけです。健康すなわちハッピーとはまったく言えません。 どう生きていきたいのかという患者さんの主観にかかっているんですね。 病気を「やっつける」「退治する」といった単純な考え方では、精神科では通用しないということです。その延長で申すなら、ぜんそくや緑内障などの慢性疾患も完治するという発想を捨てれば、どの辺りで折り合いをつけるのかという話になると思います。その点では精神科と近いところがあるのではないでしょうか。 ・私が診療で重要だと思っているのが、「プロセス」と「罪悪感」です。人生にはなかなか結論や結果が出ないとか、どう頑張っていいのか分からないとか、中途半端であったり曖昧な状態にとにかく耐えなければならないシーンが多い。我武者羅に努力すればどうにかなる、なんてわけにはいかない。だからせめて過去の成功体験にすがって自分を勇気づけたり、本やドラマを通して自身を鼓舞したり、楽天的で前向きな気持ちになろうとあれこれ工夫しつつ機が熟すのを待つしかない。 でも精神を病むと、機が熟すのを待つだけの余裕が失われてしまうんです。「待てば海路の日和あり」と驚場に構えてみるとか、せめて可能な範囲で準備を繋えるとか、ちょっと方向性を変えてみるとかの「ゆとり」がなくなってしまう。 あたかも無駄とか回り道のように見えるプロセスの必要性を患者さんは倍じられなくなる。私が言う「プロセス」とは、そのような無意味に映るけれども実は必要不可分な過程のことですね。 罪悪感について言えば、患者さんの中には親の期待に応えられなかったり、自分自身の理想に近づけなかったりといったある種の後悔を引きずっている人がいます。でも、罪悪感を持っていない人なんていません。むしろエネルギーにすらなり得る。そのことをはっきりと指摘したほうが患者さんの中で気持ちが整理されて楽になる場合もあるんですよね。 ・人間以外の動物はおそらく死ぬのはまったく怖くないのだと思います。種として存在してさえいればいいというようなある種の安心感のようなものを感じます。人間以外の動物にとって死は皮膚細胞の一つがはがれるような感覚なのでしょう。 確かにそう見えますね。動物にとって死は恐れることではないとすると、時間の概念がないとも言えると思います。でも、動物も歳をとります。動物が時間を知らなくても老化を免れないというのは、不思議な感じがしますね。 春日 動物も「最近不便になったな」というような感覚はあるのではないでしょうか。 「もっと高くジャンプできたのに」とか思っているかもしれませんね。でも、人間は「今60歳なのでまだこれぐらいはジャンプできるけど、80歳になったらさぞかし厳しいだろう」とか思ってしまいます。どうしたら、人間は主観的な幸福感を最大限にして死んでいけるのでしょう。 誰もが工夫していますが、いまだ達成できていないテーマだと思います。ただ、最近のベストセラー本を読んでいると、「自分が滅びてもいずれ誰かが達成できればよいと思えるようなライフワークを見つけなさい」とは言っていますね。 いわゆる大義ってことでしょうか。でも、動物は繁殖できればライフワークは達成なのでしょう。ある時代までは人間もそのような感じだったのかも。やがて家族や家という制度ができてくる。 精神科の立場で見ると、家族や家が精神病理に与える影響は大きいものがあります。ちなみに、思想家の内田さんは両親と子一人の核家族は家族ではなく、単なるパワーゲームの場だと言っています。つまり、子供が小さいうちは親の権力が絶大で、子供が成長すれば親に復讐することもあるというわけです。そこで、内田さんは「おじさんか、おばさんがいれば、親の絶対性が揺らいでパワーバランスが整うのだ」と指摘しています。もし、そのような環境がないのだとしたら、就職や結婚などで早いうちに家の外に出ることが生物的に自然なことなのだと思います。精神的に不健康な家族から逃げ損ねた人を診察していると、親といることで、精神病理がますます煮詰まっていく傾向にあるように感じます。 確かに、動物は早いうちにみんな独り立ちしますよね。そうなると、人間にとって家を出るというのはどういった意味があるのでしょうか。 「自分なりの価値観に基づいて生きていく」ということでしょう。自分に正直に、ね。でもそんなことを言いながら私も30歳まで家にいましたけどね。 ・生と死について疑問に思っていることがあります。私たちはふだん、生をノーマル状態、死を一種の非常事態のように捉えていますが、実際は逆なのではないかということです。死の大海の上にかろうじて浮かんでいる木切れのような生のイメージです。むしろ生のほうが例外的な事態なんじゃないか。 そんな我々にとって、死は無根拠に突然襲ってくるものなので、本来は絶えずそれに対して心を向けていなくてはいけないはずです。でも、その事実による衝撃があまりにも大き過ぎるので、とても耐えることができない。ですから、私たちの意識は死をぎりぎりまで直視しないように隠蔽する方向に向かうのだろうと思います。 確かに、医療現場で患者さんが亡くなって家族が泣いているシーンを見ても、泣かなきゃいけないと思って泣いている人が案外多いように感じます。死を特別なものとして扱わなければならないというある種の思い込みがあるのでしょ らね。 詩人の言語感覚に死への感度を見ることがあります。以前、あるイベントに登壇して、最初に一人ずつ「こんにちは」と自己紹介をしている時、詩人の白石かずこさんは第一声で「私が死のうと思った夜、電話が鳴った」と言われました。 思わず息を呑んでしまいましたが、考えてみると、最初は「こんにちは」から入るというのは「しばらくは死なない」と宣言しているようなものかも。言わば、死の隠蔽が手順化したものと言えるのではないでしょうか。 白石さんが「こんにちは」と同じくらいの感覚で「自殺を考えていることをほのめかす」というのは死を日常的なものとして見ているということですよね。 精神科医をしていると、度々自殺をする患者さんに遭遇することがあります。 自殺は個別的に見ると痛ましい出来事ですが、仮に私が神様で人間をつくるとしたら、自省を促す契機を与えるといった意味合いで、一定の割合で自殺をするプログラムを組み込むと思います。自殺によって「人間の心はなんて不可解なんだろう」と、時にはショックを与えることも必要なのではないかと思っています。そうやって人間の感情を揺さぶることによって、不可解な出来事を探求したり繊細な感情を表現したりする哲学や思想や芸術が生まれたのでしょう。 マクロな視点で見れば意味があるということですね。 詩人の感受性と世間でときおり生じる不可解な自殺とは、どこかで通底しているのかもしれません。 ところで、統合失調症患者は孤独と痛みに対してとても強いと言われています。 彼らはどこか浮世離れしていたり、そつなさを求められる通常のコミュニケーションではハンディがありますが、ジャングルの中で水源を発見するような場面ではある種の鋭敏さを発揮します。 現代の基準では非日常的な場面でこそ力を発揮するということですね。 ちなみに、「統合失調症患者はどの国、どの人種にもほぼ1%弱いる」と言われています。神様が非常時に救世主となる存在をプログラムしていると考えるならば、統合失調症患者は人類にとっての「生きのびるための保険」だと言えるのではないでしょうか。 途方もない天変地異が起きても誰かが生き残るためには、現代社会では力を発揮できないような人が一定数いなければいけない。言わば多様性ですよね。そういったマクロな視点で見ると、病気にも潜在的な意味があるのではないでしょうか。 ・本当に大切なもの 私は子どもがカブトムシやプラモデルを大切に思う気持ちと大人が健康やお金を大切に思う気持ちには、大きな隔たりがあると思っています。子どもは健康を損ねたり、お金を自分で使ったり管理したりする経験が乏しいので、これらを強く意識することはありません。つまり、子どもがカブトムシやプラモデルを大事に思う気持ちの中には純粋な関心や興味しかないんです。一方、大人が健康やお金が大事という時には、言葉の詐術による価値のすり替えのようなものが働いているのではないかと思っています。 私も歳を重ねるにつれて、健康を維持するために病院に行く機会が増えています。 内科だけでも二つとか行くようになると、お金も時間もかかります。歳をとると通勤するように病院に行く感覚がだんだんと分かるようになってきました。でも、本当は病院に行きたい人なんていないと思います。それよりも旅行に行ったり趣味に時間を使ったりしたいはずですが、病院のほうが強制力が強いんですよね。会社にも病院と似たところがあって、こちらはお金のためですね。もしかしたら、病院や会社に行きたい人もいるかもしれないですが、健康やお金のためだと思うと強制力は強くならざるを得ません。 でも、私は本当の意味ではお金や健康など大切ではないと思っています。それらはただ、なくてはとても困るものというだけなんです。お金はただの紙切れと金属だから、大切なわけがないのですが、なくては困るんです。健康だって自分自身を人質に取られているようなものです。 一方、カブトムシやプラモデルはなくても絶対的に困ることはない。ただ、純粋に好きだから大切というだけです。なくては困るものを大切と言うのであれば、健康やお金はもちろん何よりも大切ですが、私にはその二つは本当は別のことのように思われます。 ・「生きる」と「生きのびる」 表現をする際に意識していることは他にもあって、例えば「生きのびる」と「生きる」という概念です。生きのびるというのは、前述のように健康やお金について、「なくては困る」がイコール「大切」と意識がずらされている状態を言います。つまり、生きのびなければ、生きることができないということです。ちなみに、生きのびるということの目的は全員が共有しています。当然目指すべきベクトルもいっしょになっていきます。 病院や会社を最高の場所と思っていなくても、生きのびるためにどうしても行かなくてはならないことがあります。我々は生きのびるという土台の上で、初めて生きることができるからです。 一方、生きるのほうは、先ほど述べたように詰将棋や乗り物の空気抵抗の考察など、人によってやりたいことの方向性が異なります。例えば、住宅地の道で私がずっとしゃがんでいるとしましょう。すると、不審者だと思われてお巡りさんがやってきます。 この時お巡りさんに「コンタクトレンズを探しています」と言えば、全員が共有している生きのびるの概念に該当して、社会的にOKになります。コンタクトレンズを探すのは「なくては困る」からですよね。 しかし、「このアリの列がどこまで続いているのかなと思って」と言うとNGになります。この「なぜアリの列が見たいのか?」と聞かれても答えることができない状態こそが生きるに相当します。その人にとって、なぜそれが大切なのかは説明が難しいけれども、人間の最終的な目標は生きるのほうのはずです。多くの人が死ぬ時に後悔するのは生きのびることに資源を割き過ぎたということなんですね。「もっと純粋に生きることに熱中すれば良かった」と思う。でも、死ぬまでの時間を何十年も引き延ばされてしまうと、生きのびることの強制力のほうがどうしても強くなってしまうんです。 無頼派の詩人やロックスター、冒険家、犯罪者といった非社会的な適性がある一部の人以外は、なかなか生きのびることへの強制力に抗えません。また、多くの場合、生きのびることに抗ったロックスターや冒険家や犯罪者は早く死にがちです。そうしたこともあって、我々はこうした人々のことを心のどこかで羨ましく思いつつ、決して真似しようとは思いません。 ・みんな方舟の上に乗っている 社会は生きのびるという全員の共通目的の上で、個人に対して最大公約数的な生存への優位性を求めます。ただ、それも時代や国が変われば、まったく変わってしまうんです。例えば、「みだらな行為」という言葉がありますよね。つまり、これは性的な行為のことを指すわけですが、この言葉が使われるのは報道の場面など特定の状況だけです。本来は種の保存にとってなくてはならない行為が局面によって善にも悪に もなる。 昔の日本ではいわゆる婚前交渉は禁忌で「一線を越える」などと表現していましたが、時代を経るにつれて「できちゃった婚」「授かり婚」といったようにネーミングが変わっていきました。いつの間にか良いものであるかのように意味さえも変わってしまっているんです。現象自体は同じことを指しているのに、ネーミングが変わっているのは社会のニーズが変化したからだと言えるでしょう。 そうした観点で今の社会を見ていると、自分が若かった頃に関心を持ち、みんなが資源を投入して、コミットした問題は、もはや現在の重要事項ではなくなっているという感覚があります。でも、それが果たして解決したのかと言うと、必ずしもそうではないと思います。私はこうした時代の変化の本質をマイノリティ性の問題として捉えています。 若い世代の人たちは、当事者性やマイノリティ性の問題に非常に敏感です。さまざまな領域の若い人たちと話すと、彼ら、彼女らの多くは弱さをキーにした表現の展開に関心を持っています。 私も以前からマイノリティ性や弱さを表現のテーマの一つにしてきましたが、それは自分の資質的なものが大きかったんです。「暗いダメ人間が魔法の杖を手に入れて世界をひっくり返す」というようなイメージを持っていました。単に今までマイナスだったから、プラスになる魔法の杖はないかなと探すような感じですね。これは弱さが強さに反転するという夢を求めているだけなんですよ。 でも、若い世代の人たちはもっと倫理的なことを考えているみたいです。その根本では、他者とどう向き合っていくのかということが問われていると思っています。人間の数だけ無限の立場と考え方があり得るわけなんです。でも、かつての私が表現の中で想定していたのは他者がいない世界なんです。 私の若い頃には世界が滅びるとか日本がダメになるとか、そういう感覚はありませんでした。当時は、世界はとても広く、ポテンシャルがまだまだあると思っていました。そうした条件下においては、他人と傷つけあっても互いに別の場所で生きていけばいいだけで、無数の選択肢があると考えることができました。 でも、時代の流れの中で近年感じるのは、全員が方舟に乗って危うい運命を共有しているような感覚です。そんな状況だと、方舟の上で喧嘩するとか焚き火をしちゃうとかいったことは、非常にリスクが高くなってしまいます。加害性について全員が敏感になる必要がある。かつてのようにそこにポテンシャルがあれば互いに傷つけあってもいいだろう、といった考え方は今は成立困難に思えます。 - 2026年2月7日
 ケーキの切れない非行少年たち宮口幸治児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開する本。 自分が当たり前だと思っていることが当たり前でない人がいる、他の人が感じない行きづらさを抱えて生きている人がいるということを知り、自分の"当たり前"だけでモノを見る危険性を再認識できた。 著者が挙げる社会面の支援は知能の高低に関わらず必要だと感じた。 最近は非認知能力の大切さについて広く人口に膾炙しているが、前提として認知能力あってのことだとわかった。 ・自分に自肩がないと自我が脆くて傷つきやすいので、"また俺の失敗を指摘しやがって"と攻撃的になったり、”どうせ俺なんていつも目だし・・・・・・と過剰に卑下したりして、他者の言葉を好意的に受け取れないのです。 ・怒りのもう一つの背景として自分の思い通りにならない”といったものもあります。 これは「相手への要求が強い」「固定観念が多い」といったことが根底にあります。相手に「こうして欲しい”と願う要求の強さや、"僕は正しい””こうあるべきだ”といった歪んだ自己愛や固定観念が根底に強くあるのです。 ・1次障害:障害自体によるもの 2次障害:周囲から障害を理解されず、学校などで適切な支援が受けられなかったことによるもの 3次障害:非行化して矯正施設に入ってもさらに理解されず、厳しい指導を受け一層悪化する 4次障害:社会に出てからもさらに理解されず、偏見もあり、仕事が続かず再非行に繋 がる ・ここで気付いて欲しいことがあります。時代によって知的障害の定義が変わったとしても、事実が変わるわけではないことを。IQ70~84の子どもたち、つまり現在でいう境界知能の子どもたちは、依然として存在しているのです。 彼らは知的障害者と同じくしんどさを感じていて、支援を必要としているかもしれません。では、これらの子どもたちはどのくらいいるのでしょうか。知能分布から算定すると、およそ14%いることになります。つまり、現在の標準的な1クラス35名のうち、約5人いることになります。クラスで下から5人程度は、かつての定義なら知的障害に相当していた可能性もあったのです。もちろん話はそんな単純ではありませんが、現在の学校では、このようにクラスで下から5人の子どもたちは、周囲から気付かれずに様々なSOSのサインを出している可能性があるのです。 ・前章でもお伝えしましたが、現在知的障害者の定義はおおよそIQが70未満で社会性に障害があることとなっています。この定義であれば、およそ2%が知的障害に該当することになります。しかし、1950年代の「IQ85未満」を適用すると、16%ということになります。16%から2%を引くと、IQ70~84のかつての軽度知的障害者は14%もいた、という計算になります。もちろん最新のDSMー5による知的障害の診断基準ではIQの値がなくなり、今では全く当てはまりませんが、この世の中で普通に生活していく上で、1Qが100ないとなかなかしんどいと言われています。IQ85未満となると相当なしんどさを感じているかもしれません。 ・"褒める"話を聞いてあげる”は、その場を繕うのにはいいのですが、長い目でみた場合、根本的解決策ではないので逆に子どもの問題を先送りにしているだけになってしまいます。 例えば、勉強ができないことで自をなくしイライラしている子どもに対して、「走るのは速いよ」と褒めたり、「勉強できなくてイライラしていたんだね」と話を聞いてあげたりしても、勉強ができない事実は変わらないのです。根本的な解決策は、勉強への直接的な支援によって、勉強ができるようにすること以外では有り得ません。 ・第二に、そもそも「自尊感情が低い」ことは問題なのか、ということです。 我々大人はどうでしょう。自尊感情は高いのでしょうか?仕事がうまくいかず、自肩を失って自尊感情が低いことはあるでしょう。逆に、仕事が軌道にのり、社会的に成功すれば、自尊感情が高くなることもあるでしょう。それでも、社会の荒波に揉まれながら思った通りの仕事ができない、職場の対人関係がうまくいかない、理想の家庭が築けないなど、自肩がなかなか持てず、自尊感情が低くなってしまっている大人の方が多いのではないでしょうか。 だからと言って、ほとんどの人が社会で犯罪を行っている、不適応を起こしているわけでもありません。つまり、自尊感情が低くても社会人として何とか生活できているのです。逆に、自尊感情が高すぎると自己愛が強く、自己中のように見えてしまうかもしれません。大人でもなかなか高く保てない自尊感情を、子どもにだけ「低いから問題だ」と言っている支援者は、矛盾しているのです。 問題なのは自尊感情が低いことではなく、自尊感情が実情と乖離していることにあります。何もできないのにえらく自言をもっている。逆に何でもできるのに全然自信がもてない。要は、等身大の自分を分かっていないことから問題が生じるのです。 "自尊感情が低い"といった言葉に続くのは、「自尊感情を上げるような支援が必要である」といった締めの言葉です。こんな文章を見る度、「そもそも文章を書いている心理技官の自尊感情は高いのか」と聞きたくなります。無理に上げる必要もなく、低いままでもいい、ありのままの現実の自分を受け入れていく強さが必要なのです。もういい加減「自尊感情が••・・・」といった表現からは卒業して欲しいところです。 ・社会面の支援とは、対人スキルの方法、感情コントロール、対人マナー、問題解決力といった、社会で生きていく上でどれも分かせない能力を身につけさせることです。これらのどれ一つでも出来ていなければ、社会ではうまく生活していけないでしょう。 そういった最も大切な社会面の支援が、学校教育で系統立ててほとんど何もなされていないということが、私にはどうしても理解できません。学校教育で何もなされていないので、少年院に入ってきた少年には、一から社会面について支援していかないといけないのです。 ・しかし、一つ問題があります。このソーシャルスキルトレーニングは認知行動療法に基づいていますので、「対象者の認知機能に大きな問題がない」ことが前提になっています。認知行動療法は、考え方を変えることによって不適切な行動を適切な行動に変えていく方法ですが、"考え方"を変える以上、ある程度の「考える力」があることが当然の前提になっています。そこには聞く力、言語を理解する力、見る力、想像する力、判断する力が必要なのです。これらの力がまさに認知機能と呼ばれるものです。 逆に言えば、対象者の認知機能に何かしらの問題があれば、トレーニングを受けていても何をやっているのか理解できない、判断できない、といった状況が生じてしまい、その効果は分からなくなってくるのです。にもかかわらず、矯正教育や学校教育の現場の中には、対象者の能力を考慮せずに、ソーシャルスキルを上げるにはとにかくソーシヤルスキルトレーニングを、といった形式的な対応がなされていることもあるのです。 ・ここに述べた実際の声は、大きく次の二つにまとめられるかと思います。一つは自己への気づきであり、もう一つは自己評価の向上です。 人が自分の不適切なところを何とか直したいと考えるときは、「適切な自己評価」が 150 スタートとなります。行動変容には、まず悪いことをしてしまう現実の自分に気づくこと、そして自己洞察や葛藤をもつことが必要です。適切な自己評価ができるからこそ "悪いことをする自分”に気づき、”また悪いことをやってしまった。自分って何で駄目な奴なんだろう""いつまでもこんなことしていられない。もっといい人になりたい”などといった自己洞察・自己内省が行えるのです。そして、理想と現実の間で揺れ動きながらも、自分の中に「正しい規範」を作り、それを参照しながら"今度から頑張ろう”と努力し、理想の自分に近づいていくのです。そのためにはやはり、自己を適切に評価できる力、つまり”自分はどんな人間なのか"を理解できることが大前提なのです。 ・自己に注意を向けることで自己洞察や自己内省が生じる背景に、自覚状態理論というものがあります。自己に注意が向くと、自分にとってとても気になっている事柄に強く関心が向くようになります。その際、自己規範に照らし合わせ、その事柄が自己規範にそぐわないと、不快感が生じます。この不快な感情を減らしたいという思いが、行動変容するための動機づけになる、というものです。例えば、ある少年が万引きをしようと考えた時、自己に注意を向ける機会があると、万引きという行為自体についても関心を向けるようになります。そして、万引きは悪いことだ”といった規範をその少年がもっていれば、そんな自分を不快に感じ、万引きを止めるきっかけになる、というわけです。 自己に注意を向けさせる方法として、他人から見られている、自分の姿を鏡で見る、自分の声を聴く、などがあります。かつて飛び込み自殺が多かった札幌の地下鉄のホームに鏡を設置したところ、自殺者が減った、といった報道がありました。事実関係を直接調べたわけではありませんが、これは頷ける話です。鏡で自分の姿を見ると自己に注意が向けられ、「自殺はよくないことだ」という自己規範が生じ、自殺者は減るだろうと考えられるからです。 この理論が正しいなら、学校で先生が子どもに対し"あなたを見ていますよ”といったサインを送るだけでも効果があります。また、少人数のグループワークではメンバー同士、お互いがお互いを密に観察し合っていますので、それだけでも抜群の効果があると考えられます。学校でのグループワークの大切さの所以です。加えて、平生から我々大人が見本となり、「正しい規範」を子どもに見せることが重要なのは言うまでもありません。 自分が変わるための動機づけには、自分に注意を向け、見つめ直すことが必要です。 先に挙げた少年たちが変わろうと思ったきっかけに共通しているのも、これまで社会で失敗し続けて自肩をなくしてきた彼らが、集団生活の様々な人との関係性の中で、 “自己への気づきがあること” そして様々な体験や教育を受ける中で、 ”自己評価が向上すること" のこうなのです。特に自己への気づきについては、押しつけでなく少年自身が自ら「気づきのスイッチ」を入れねばなりませんので、我々としては少しでも多くの、かつ様々な気づきの可能性のある場を提供し、スイッチを入れる機会に触れさせることが大切です。 これらは学校教育でも全く同じと感じます。矯正教育に長年携わってきた方が、こう言っていました。「子どもの心に扉があるとすれば、その取手は内側にしかついていない」。まさにその通りだと思います。子どもの心の扉を開くには、子ども自身がハッとする気づきの体験が最も大切であり、我々大人の役割は、説教や叱責などによって無理やり扉を開けさせることではなく、子ども自身に出来るだけ多くの気づきの場を提供することなのです。 ・それで気づきました。少年たちに"教えるんだ"という視点では駄目なのだ、と。これまで幾度となく”こんなのも分からないの?"と言われ馬鹿にされ続けてきた少年たちは、自分たちも、 ”人に教えてみたい” ”人から頼りにされたい” "人から認められたい" という気持ちを強くもっていることを知りました。そしてそれが自己評価の向上に繋がっていくのです。学校でも「どうせやっても無駄」と思っていて、やる気のない子どもがいるでしょう。しかし、そのような子どもでも、皆に問題を出す役や答えを教える役などをやってみたい、という気持ちがあるかもしれません。そのまま導入するのは難しいとは思われますが、人の役に立つことで自己評価の向上に繋がり、次第に勉強へのやる気も出てくる可能性があるのです。
ケーキの切れない非行少年たち宮口幸治児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づく。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたが、問題の根深さは普通の学校でも同じなのだ。人口の十数%いるとされる「境界知能」の人々に焦点を当て、困っている彼らを学校・社会生活で困らないように導く超実践的なメソッドを公開する本。 自分が当たり前だと思っていることが当たり前でない人がいる、他の人が感じない行きづらさを抱えて生きている人がいるということを知り、自分の"当たり前"だけでモノを見る危険性を再認識できた。 著者が挙げる社会面の支援は知能の高低に関わらず必要だと感じた。 最近は非認知能力の大切さについて広く人口に膾炙しているが、前提として認知能力あってのことだとわかった。 ・自分に自肩がないと自我が脆くて傷つきやすいので、"また俺の失敗を指摘しやがって"と攻撃的になったり、”どうせ俺なんていつも目だし・・・・・・と過剰に卑下したりして、他者の言葉を好意的に受け取れないのです。 ・怒りのもう一つの背景として自分の思い通りにならない”といったものもあります。 これは「相手への要求が強い」「固定観念が多い」といったことが根底にあります。相手に「こうして欲しい”と願う要求の強さや、"僕は正しい””こうあるべきだ”といった歪んだ自己愛や固定観念が根底に強くあるのです。 ・1次障害:障害自体によるもの 2次障害:周囲から障害を理解されず、学校などで適切な支援が受けられなかったことによるもの 3次障害:非行化して矯正施設に入ってもさらに理解されず、厳しい指導を受け一層悪化する 4次障害:社会に出てからもさらに理解されず、偏見もあり、仕事が続かず再非行に繋 がる ・ここで気付いて欲しいことがあります。時代によって知的障害の定義が変わったとしても、事実が変わるわけではないことを。IQ70~84の子どもたち、つまり現在でいう境界知能の子どもたちは、依然として存在しているのです。 彼らは知的障害者と同じくしんどさを感じていて、支援を必要としているかもしれません。では、これらの子どもたちはどのくらいいるのでしょうか。知能分布から算定すると、およそ14%いることになります。つまり、現在の標準的な1クラス35名のうち、約5人いることになります。クラスで下から5人程度は、かつての定義なら知的障害に相当していた可能性もあったのです。もちろん話はそんな単純ではありませんが、現在の学校では、このようにクラスで下から5人の子どもたちは、周囲から気付かれずに様々なSOSのサインを出している可能性があるのです。 ・前章でもお伝えしましたが、現在知的障害者の定義はおおよそIQが70未満で社会性に障害があることとなっています。この定義であれば、およそ2%が知的障害に該当することになります。しかし、1950年代の「IQ85未満」を適用すると、16%ということになります。16%から2%を引くと、IQ70~84のかつての軽度知的障害者は14%もいた、という計算になります。もちろん最新のDSMー5による知的障害の診断基準ではIQの値がなくなり、今では全く当てはまりませんが、この世の中で普通に生活していく上で、1Qが100ないとなかなかしんどいと言われています。IQ85未満となると相当なしんどさを感じているかもしれません。 ・"褒める"話を聞いてあげる”は、その場を繕うのにはいいのですが、長い目でみた場合、根本的解決策ではないので逆に子どもの問題を先送りにしているだけになってしまいます。 例えば、勉強ができないことで自をなくしイライラしている子どもに対して、「走るのは速いよ」と褒めたり、「勉強できなくてイライラしていたんだね」と話を聞いてあげたりしても、勉強ができない事実は変わらないのです。根本的な解決策は、勉強への直接的な支援によって、勉強ができるようにすること以外では有り得ません。 ・第二に、そもそも「自尊感情が低い」ことは問題なのか、ということです。 我々大人はどうでしょう。自尊感情は高いのでしょうか?仕事がうまくいかず、自肩を失って自尊感情が低いことはあるでしょう。逆に、仕事が軌道にのり、社会的に成功すれば、自尊感情が高くなることもあるでしょう。それでも、社会の荒波に揉まれながら思った通りの仕事ができない、職場の対人関係がうまくいかない、理想の家庭が築けないなど、自肩がなかなか持てず、自尊感情が低くなってしまっている大人の方が多いのではないでしょうか。 だからと言って、ほとんどの人が社会で犯罪を行っている、不適応を起こしているわけでもありません。つまり、自尊感情が低くても社会人として何とか生活できているのです。逆に、自尊感情が高すぎると自己愛が強く、自己中のように見えてしまうかもしれません。大人でもなかなか高く保てない自尊感情を、子どもにだけ「低いから問題だ」と言っている支援者は、矛盾しているのです。 問題なのは自尊感情が低いことではなく、自尊感情が実情と乖離していることにあります。何もできないのにえらく自言をもっている。逆に何でもできるのに全然自信がもてない。要は、等身大の自分を分かっていないことから問題が生じるのです。 "自尊感情が低い"といった言葉に続くのは、「自尊感情を上げるような支援が必要である」といった締めの言葉です。こんな文章を見る度、「そもそも文章を書いている心理技官の自尊感情は高いのか」と聞きたくなります。無理に上げる必要もなく、低いままでもいい、ありのままの現実の自分を受け入れていく強さが必要なのです。もういい加減「自尊感情が••・・・」といった表現からは卒業して欲しいところです。 ・社会面の支援とは、対人スキルの方法、感情コントロール、対人マナー、問題解決力といった、社会で生きていく上でどれも分かせない能力を身につけさせることです。これらのどれ一つでも出来ていなければ、社会ではうまく生活していけないでしょう。 そういった最も大切な社会面の支援が、学校教育で系統立ててほとんど何もなされていないということが、私にはどうしても理解できません。学校教育で何もなされていないので、少年院に入ってきた少年には、一から社会面について支援していかないといけないのです。 ・しかし、一つ問題があります。このソーシャルスキルトレーニングは認知行動療法に基づいていますので、「対象者の認知機能に大きな問題がない」ことが前提になっています。認知行動療法は、考え方を変えることによって不適切な行動を適切な行動に変えていく方法ですが、"考え方"を変える以上、ある程度の「考える力」があることが当然の前提になっています。そこには聞く力、言語を理解する力、見る力、想像する力、判断する力が必要なのです。これらの力がまさに認知機能と呼ばれるものです。 逆に言えば、対象者の認知機能に何かしらの問題があれば、トレーニングを受けていても何をやっているのか理解できない、判断できない、といった状況が生じてしまい、その効果は分からなくなってくるのです。にもかかわらず、矯正教育や学校教育の現場の中には、対象者の能力を考慮せずに、ソーシャルスキルを上げるにはとにかくソーシヤルスキルトレーニングを、といった形式的な対応がなされていることもあるのです。 ・ここに述べた実際の声は、大きく次の二つにまとめられるかと思います。一つは自己への気づきであり、もう一つは自己評価の向上です。 人が自分の不適切なところを何とか直したいと考えるときは、「適切な自己評価」が 150 スタートとなります。行動変容には、まず悪いことをしてしまう現実の自分に気づくこと、そして自己洞察や葛藤をもつことが必要です。適切な自己評価ができるからこそ "悪いことをする自分”に気づき、”また悪いことをやってしまった。自分って何で駄目な奴なんだろう""いつまでもこんなことしていられない。もっといい人になりたい”などといった自己洞察・自己内省が行えるのです。そして、理想と現実の間で揺れ動きながらも、自分の中に「正しい規範」を作り、それを参照しながら"今度から頑張ろう”と努力し、理想の自分に近づいていくのです。そのためにはやはり、自己を適切に評価できる力、つまり”自分はどんな人間なのか"を理解できることが大前提なのです。 ・自己に注意を向けることで自己洞察や自己内省が生じる背景に、自覚状態理論というものがあります。自己に注意が向くと、自分にとってとても気になっている事柄に強く関心が向くようになります。その際、自己規範に照らし合わせ、その事柄が自己規範にそぐわないと、不快感が生じます。この不快な感情を減らしたいという思いが、行動変容するための動機づけになる、というものです。例えば、ある少年が万引きをしようと考えた時、自己に注意を向ける機会があると、万引きという行為自体についても関心を向けるようになります。そして、万引きは悪いことだ”といった規範をその少年がもっていれば、そんな自分を不快に感じ、万引きを止めるきっかけになる、というわけです。 自己に注意を向けさせる方法として、他人から見られている、自分の姿を鏡で見る、自分の声を聴く、などがあります。かつて飛び込み自殺が多かった札幌の地下鉄のホームに鏡を設置したところ、自殺者が減った、といった報道がありました。事実関係を直接調べたわけではありませんが、これは頷ける話です。鏡で自分の姿を見ると自己に注意が向けられ、「自殺はよくないことだ」という自己規範が生じ、自殺者は減るだろうと考えられるからです。 この理論が正しいなら、学校で先生が子どもに対し"あなたを見ていますよ”といったサインを送るだけでも効果があります。また、少人数のグループワークではメンバー同士、お互いがお互いを密に観察し合っていますので、それだけでも抜群の効果があると考えられます。学校でのグループワークの大切さの所以です。加えて、平生から我々大人が見本となり、「正しい規範」を子どもに見せることが重要なのは言うまでもありません。 自分が変わるための動機づけには、自分に注意を向け、見つめ直すことが必要です。 先に挙げた少年たちが変わろうと思ったきっかけに共通しているのも、これまで社会で失敗し続けて自肩をなくしてきた彼らが、集団生活の様々な人との関係性の中で、 “自己への気づきがあること” そして様々な体験や教育を受ける中で、 ”自己評価が向上すること" のこうなのです。特に自己への気づきについては、押しつけでなく少年自身が自ら「気づきのスイッチ」を入れねばなりませんので、我々としては少しでも多くの、かつ様々な気づきの可能性のある場を提供し、スイッチを入れる機会に触れさせることが大切です。 これらは学校教育でも全く同じと感じます。矯正教育に長年携わってきた方が、こう言っていました。「子どもの心に扉があるとすれば、その取手は内側にしかついていない」。まさにその通りだと思います。子どもの心の扉を開くには、子ども自身がハッとする気づきの体験が最も大切であり、我々大人の役割は、説教や叱責などによって無理やり扉を開けさせることではなく、子ども自身に出来るだけ多くの気づきの場を提供することなのです。 ・それで気づきました。少年たちに"教えるんだ"という視点では駄目なのだ、と。これまで幾度となく”こんなのも分からないの?"と言われ馬鹿にされ続けてきた少年たちは、自分たちも、 ”人に教えてみたい” ”人から頼りにされたい” "人から認められたい" という気持ちを強くもっていることを知りました。そしてそれが自己評価の向上に繋がっていくのです。学校でも「どうせやっても無駄」と思っていて、やる気のない子どもがいるでしょう。しかし、そのような子どもでも、皆に問題を出す役や答えを教える役などをやってみたい、という気持ちがあるかもしれません。そのまま導入するのは難しいとは思われますが、人の役に立つことで自己評価の向上に繋がり、次第に勉強へのやる気も出てくる可能性があるのです。 - 2026年2月7日
 夜明けのすべて瀬尾まいこPMS(月経前症候群)で感情を抑えられない美紗。パニック障害になり生きがいも気力も失った山添。 友達でも恋人でもないけれど、互いの事情と孤独を知り同志のような気持ちが芽生えた二人は、自分にできることは少なくとも、相手のことは助けられるかもしれないと思うようになり、少しずつ希望を見出していくーー。 瀬尾まいこさんの物語はどうしてこんなに温かいんだろう。。 私は本当にこういう物語が好きだなぁ。 生きていると苦しいことも多いけど、希望にも満ちていることを教えてくれる。 自分を気にかけてくれる、温かく見守ってくれる人がいることが、どれくらい支えになるだろう。 自分が苦しみを知っていることで、より人を支えることができるのだと思う。 私もそんな強さと弱さを持った人になりたい。 ・そう思うと同時に、「病気にもランクがあったんだね」という藤沢さんの言葉が頭に浮かんだ。俺は知らず知らず、自分の病気をかさに着るようになったのだろうか。まさか。 本当のことなんだからしかたない。PMSよりパニック障害のほうがつらいに決まっている。いや、はたして、本当にそうだろうか。俺はPMSどころか生理のことも知らない。 実際は想像以上にしんどいのかもしれない。ああ、もう考えるのはやめだ。そんなことどうだっていい。俺はざわざわした思いが広がりそうになるのを振り払うように、炭酸を一気に飲んだ。 ・五年前、婦人科でもらった薬について調べたことがある。その時、ソラナックスを服用する症状としてPMS以外に、鬱やパニック障害という病名にたどり着いた。パニック障害がどういう病気か、いくつがネットのページを見て知ってはいたはずだ。 それなのに、山添君が発作を起こす姿を見るまで、彼がパニック障害だったことにまったく気づかなかった。 飴やガムを食べるのは気分を落ち着かせるためだったかもしれないし、思いどおりに行動できず遅刻してしまっていたのかもしれない。顔色だって冴えないのに、どうして私は簡単に、彼のことをやる気のない人間だと決めてかかっていたのだろう。 「生理は病気じゃない」 そう思っている人はけっこういる。女同士であっても、生理を理由に休むことをずるいと言われることもあった。PMSが病気というカテゴリーに入るかどうかはわからないし、同情や心配を欲してもいない。だけど、気持ちの問題では決してない。体がどうしたって思いどおりに動かないのだ。どう努めても、感情がコントロールできない。治せるならなんだってする。以前の私は、それをどうすれば周りがわかってくれるのだろうかと悩んでいた。それなのに、自分以外の病気については、妊娠や生理を鼻で笑っている男と同じくらい無知だったなんて。 ・「そうですね。えっと、水虫もたいへんそうです」私が言うと、社長は「藤沢さんらしいね」と笑ってから、「もう年季が入った水虫だから、うまく付き合ってるけどね。だけどさ、誰にも言わずにいるんだけど、かみさんには気づかれているみたいで、靴に炭入れられたりスリッパこまめに干されたりしてる」 「そうなんですね」 「かみさんは自分に移されたくなくてやってるんだろうけど、そうやって気にしてくれる人が一人でもいるだけで、気は楽さ。山添君もそうじゃないかな」社長は「よいしょ」と席を立った。もうすぐ住川さんが出勤してくる。私も自分の席へ戻った。 誰かの負担を和らげるのは、強引に髪を切ったり、勝手に告白したりすることなんかじゃない。靴に炭をしのばせる。そういうことが、苦しさを軽減させてくれるのかもしれな い。 ・藤沢さんにはパニック障害だと知られているから平気だったのだろうか。いや、それなら付き合っていた千尋だってそうだった。千尋は俺が最初にパニック障害を打ち明けた相手だ。何度も大きな病院に行くようにと勧めてくれたし、すぐに治るはずだと励ましてもくれた。千尋とは一年以上一緒にいたから、ありのままの自分も見せていたし、泣き言や弱音も吐いていた。でも、千尋の前では、いつもどおりの俺でいたかった。失敗するのも、間違って恥をかくのもいい。だけど、理由もなく発作を起こして倒れることはしたくなかった。治る見込みのない症状を抱えて千尋のそばにいるのはつらかった。心配や同情や励ましや慰め。ありがたいけど、毎日それらを向けられるのは重圧だった。千尋もそんな俺にどう接していいか迷っているようで、無駄に気を遣わせていた。一緒にいると楽しかった。顔を見るだけでほっとできた。それなのに、パニック障害になってから、千尋と会うたび心のどこかが緊張した。 ・「PMSはいいところあるんですか?」 「そうだなあ。PMSになって、ヨガとかピラティスとかいろいろやったから、体は柔らかくなったかな」 藤沢さんが「昔は体硬かったのに、今、足一八〇度開くよ」と自慢げに言うのに、俺も「そういえば、パニックになって外に出なくなったから無駄遣いはしなくなったな。給料は減ったのに貯金は増えました」と答えた。 どこかずれているような気もするけど、困難が襲ってきて得るものって、実は現実的なものかもしれない。それにしても柔軟性と貯金って。俺たちはなんとなく顔を見合わせて、思わず笑った。 ・PMSだから、誰とも付き合えないと思っているわけではない。だけど、説明して理解してもらって、それでも驚かれて謝って、少しずつ距離を縮めて......。そういうのを考えると億劫になってしまう。そこまでして、人と一緒にいるのはしんどい。 「そんなの、大丈夫だよ。それに、環境変わったら、けろっと治ったりするかもしれないしさ。先のこと心配したってしかたないじゃん」「うん、かもね」 いろいろ手を尽くしてきて現在があるのに、環境の変化で治るわけがない。それでも、こうやって心配してくれる友達がいるのはありがたいことだ。 ・伊勢神宮のお守り。まだ俺のことを覚えていてくれたんだ。辻本課長は今の俺を見て、どう思うだろうか。社会に出たばかりの俺にすべてを教えてくれた人だ。こんな俺に、がつかりするだろうか。いや、あの人は自分がかかわってきた人間に、失望することはない。 恋人に友達、一緒に仕事に向かっていた仲間や上司。みんな遠くに行ってしまったと思っていた。パニック障害を抱えてしまっているのだ。新たに誰かと打ち解けることなどないと思っていた。でも、本当にそうだろうか。 お守りを手にしながら、藤沢さんが買ってきてくれたコーラの残りを飲み干す。俺はすべてから切り離された場所にいるわけではない。完全な孤独など、この世の中には存在しないはずだ。 ・パニック障害になってから忘れていたことを、この半年足らずでいくつか思い出した。 クイーンをよく聴いていたこと、和菓子が好きだったこと、自転車に乗るのが得意だったこと。同時にできないことも思い知った。映画館に入ることも、電車に乗ることも、まだ俺にはできそうにない。 でも、手段はある。 美容院に行けなければ髪くらい家で切ればいいし、映画館に入れないのならポップコーンを食べながらサントラを聴けばいい。電車が無理でも自転車がある。代わりではなく、そのほうがずっと楽しいことも多い。 ・「こんなにたくさんいらないよ。明後日には退院するのに。山添君、家で飲んで」そう言って、藤沢さんが袋に入れてくれた飲み物は、冷蔵庫に入っていたものだろう。俺が持って行った数より増えている。カーテンで仕切られた病室の狭いスペース。藤沢さんといるその空間は、緊張感も圧迫感もなかった。 寒い十一月の土曜日。髪の毛を切りに来た藤沢さんが、ハンドクリーナーやらごみ袋やらを出してきたことを思い出した。突拍子もないことをしてしまえるところじゃなく、俺は藤沢さんのそういうところが好きなんだ。そう思った。 ・働かないと生きていけないし、仕事がなければ毎日することもない。だから会社に勤めている。けれども、仕事のもたらすものはそれだけではない。自分のできることをほんの少しでも、何かの役に立ててみたい。自分の中にある考えを、何らかの形で表に出してみたい。そういう思いを、仕事は満たしてくれる。働くことで、漠然と目の前にある大量の時間に、少しは意味を持たせられる気がする。 ・人に悪く思われないためなのか、人に喜んでもらいたいためなのか、自分の行動の根源にあるものは自分でもわからない。けれど、嫌われたくない。そればかりだったら、みじめだ。気を遣っているわけじゃなく好きでやっている。そういうことにしておけば、気持ちは楽だ。 「そんなふうに考えられたら、少しは自分のこと嫌じゃなくなりそうだね」 「無理して好きになることもないですけどね」 おやつまで待てないと、桜餅を食べながら山添君が言った。 「そう?自分のこと好きでいるのは基本でしょう。自分を大事にできない人間は人を大事にできないって、よく聞くよね」 「そんな理論がまかり通ったら、人を粗末にする人が続出しますよ。藤沢さんの聞き間違いじゃないですか」 「まさか」 自分を好きになることが大切だって、小学生のころから何度も聞いたことがある。そのままの自分を好きになろうって、自分を好きになれる人が他人を愛せるんだって、歌でだって小説でだってよく言っている。 「ぼくは自分が嫌いです。臆病だし、将来の見通しもゼロ。好きになれる要素がないで す」 山添君はパソコンに向かっていた体をこちらに向けて、話し出した。 「そんな悲観することないだろうけど」 「悲観はしてませんよ。ただ、タコと自分が好きじゃないだけで。でも、藤沢さんを好きになることはできます」 ・昔の俺は、誰とでも近づいて、たくさんの言葉を交わしていた。人と知り合うことも、みんなで集まることも好きだった。そのころは社交的だとよく評された。それに比べ、今の俺は、口数は当時の半分にも満たない。交友関係を広げることもなく、人と接することを避けている。 だけど、あのころの俺は、悲しい話が展開されるとわかっていて、会話を進めることができただろうか。自分の発作のことをこんなにも自然に口にできただろうか。数えきれないほど冗談を口にし、笑いあってきた。けれど、今のような話を誰かとしたことはなかった。 ・「薬、減らして大丈夫でしょうか?」 「一気にではなく徐々にやればいいし、できなきゃ、また元に戻せばいいだけだからね」 医者はさらりと言った。 断薬はつらいし、一度失敗すると苦労する。そういう話は、ネットの情報で何度も読んだ。俺にそれができるのだろうか。 「たいへんだってよく聞きますけど・・・・・・・」 「誰から?」 「まあ、ネットで」 「でしょうね。簡単に手に入れられる情報なんて、声が大きい人のものがほとんどですよ。山添さんのことを知っている人が発している意見ではないでしょう?」
夜明けのすべて瀬尾まいこPMS(月経前症候群)で感情を抑えられない美紗。パニック障害になり生きがいも気力も失った山添。 友達でも恋人でもないけれど、互いの事情と孤独を知り同志のような気持ちが芽生えた二人は、自分にできることは少なくとも、相手のことは助けられるかもしれないと思うようになり、少しずつ希望を見出していくーー。 瀬尾まいこさんの物語はどうしてこんなに温かいんだろう。。 私は本当にこういう物語が好きだなぁ。 生きていると苦しいことも多いけど、希望にも満ちていることを教えてくれる。 自分を気にかけてくれる、温かく見守ってくれる人がいることが、どれくらい支えになるだろう。 自分が苦しみを知っていることで、より人を支えることができるのだと思う。 私もそんな強さと弱さを持った人になりたい。 ・そう思うと同時に、「病気にもランクがあったんだね」という藤沢さんの言葉が頭に浮かんだ。俺は知らず知らず、自分の病気をかさに着るようになったのだろうか。まさか。 本当のことなんだからしかたない。PMSよりパニック障害のほうがつらいに決まっている。いや、はたして、本当にそうだろうか。俺はPMSどころか生理のことも知らない。 実際は想像以上にしんどいのかもしれない。ああ、もう考えるのはやめだ。そんなことどうだっていい。俺はざわざわした思いが広がりそうになるのを振り払うように、炭酸を一気に飲んだ。 ・五年前、婦人科でもらった薬について調べたことがある。その時、ソラナックスを服用する症状としてPMS以外に、鬱やパニック障害という病名にたどり着いた。パニック障害がどういう病気か、いくつがネットのページを見て知ってはいたはずだ。 それなのに、山添君が発作を起こす姿を見るまで、彼がパニック障害だったことにまったく気づかなかった。 飴やガムを食べるのは気分を落ち着かせるためだったかもしれないし、思いどおりに行動できず遅刻してしまっていたのかもしれない。顔色だって冴えないのに、どうして私は簡単に、彼のことをやる気のない人間だと決めてかかっていたのだろう。 「生理は病気じゃない」 そう思っている人はけっこういる。女同士であっても、生理を理由に休むことをずるいと言われることもあった。PMSが病気というカテゴリーに入るかどうかはわからないし、同情や心配を欲してもいない。だけど、気持ちの問題では決してない。体がどうしたって思いどおりに動かないのだ。どう努めても、感情がコントロールできない。治せるならなんだってする。以前の私は、それをどうすれば周りがわかってくれるのだろうかと悩んでいた。それなのに、自分以外の病気については、妊娠や生理を鼻で笑っている男と同じくらい無知だったなんて。 ・「そうですね。えっと、水虫もたいへんそうです」私が言うと、社長は「藤沢さんらしいね」と笑ってから、「もう年季が入った水虫だから、うまく付き合ってるけどね。だけどさ、誰にも言わずにいるんだけど、かみさんには気づかれているみたいで、靴に炭入れられたりスリッパこまめに干されたりしてる」 「そうなんですね」 「かみさんは自分に移されたくなくてやってるんだろうけど、そうやって気にしてくれる人が一人でもいるだけで、気は楽さ。山添君もそうじゃないかな」社長は「よいしょ」と席を立った。もうすぐ住川さんが出勤してくる。私も自分の席へ戻った。 誰かの負担を和らげるのは、強引に髪を切ったり、勝手に告白したりすることなんかじゃない。靴に炭をしのばせる。そういうことが、苦しさを軽減させてくれるのかもしれな い。 ・藤沢さんにはパニック障害だと知られているから平気だったのだろうか。いや、それなら付き合っていた千尋だってそうだった。千尋は俺が最初にパニック障害を打ち明けた相手だ。何度も大きな病院に行くようにと勧めてくれたし、すぐに治るはずだと励ましてもくれた。千尋とは一年以上一緒にいたから、ありのままの自分も見せていたし、泣き言や弱音も吐いていた。でも、千尋の前では、いつもどおりの俺でいたかった。失敗するのも、間違って恥をかくのもいい。だけど、理由もなく発作を起こして倒れることはしたくなかった。治る見込みのない症状を抱えて千尋のそばにいるのはつらかった。心配や同情や励ましや慰め。ありがたいけど、毎日それらを向けられるのは重圧だった。千尋もそんな俺にどう接していいか迷っているようで、無駄に気を遣わせていた。一緒にいると楽しかった。顔を見るだけでほっとできた。それなのに、パニック障害になってから、千尋と会うたび心のどこかが緊張した。 ・「PMSはいいところあるんですか?」 「そうだなあ。PMSになって、ヨガとかピラティスとかいろいろやったから、体は柔らかくなったかな」 藤沢さんが「昔は体硬かったのに、今、足一八〇度開くよ」と自慢げに言うのに、俺も「そういえば、パニックになって外に出なくなったから無駄遣いはしなくなったな。給料は減ったのに貯金は増えました」と答えた。 どこかずれているような気もするけど、困難が襲ってきて得るものって、実は現実的なものかもしれない。それにしても柔軟性と貯金って。俺たちはなんとなく顔を見合わせて、思わず笑った。 ・PMSだから、誰とも付き合えないと思っているわけではない。だけど、説明して理解してもらって、それでも驚かれて謝って、少しずつ距離を縮めて......。そういうのを考えると億劫になってしまう。そこまでして、人と一緒にいるのはしんどい。 「そんなの、大丈夫だよ。それに、環境変わったら、けろっと治ったりするかもしれないしさ。先のこと心配したってしかたないじゃん」「うん、かもね」 いろいろ手を尽くしてきて現在があるのに、環境の変化で治るわけがない。それでも、こうやって心配してくれる友達がいるのはありがたいことだ。 ・伊勢神宮のお守り。まだ俺のことを覚えていてくれたんだ。辻本課長は今の俺を見て、どう思うだろうか。社会に出たばかりの俺にすべてを教えてくれた人だ。こんな俺に、がつかりするだろうか。いや、あの人は自分がかかわってきた人間に、失望することはない。 恋人に友達、一緒に仕事に向かっていた仲間や上司。みんな遠くに行ってしまったと思っていた。パニック障害を抱えてしまっているのだ。新たに誰かと打ち解けることなどないと思っていた。でも、本当にそうだろうか。 お守りを手にしながら、藤沢さんが買ってきてくれたコーラの残りを飲み干す。俺はすべてから切り離された場所にいるわけではない。完全な孤独など、この世の中には存在しないはずだ。 ・パニック障害になってから忘れていたことを、この半年足らずでいくつか思い出した。 クイーンをよく聴いていたこと、和菓子が好きだったこと、自転車に乗るのが得意だったこと。同時にできないことも思い知った。映画館に入ることも、電車に乗ることも、まだ俺にはできそうにない。 でも、手段はある。 美容院に行けなければ髪くらい家で切ればいいし、映画館に入れないのならポップコーンを食べながらサントラを聴けばいい。電車が無理でも自転車がある。代わりではなく、そのほうがずっと楽しいことも多い。 ・「こんなにたくさんいらないよ。明後日には退院するのに。山添君、家で飲んで」そう言って、藤沢さんが袋に入れてくれた飲み物は、冷蔵庫に入っていたものだろう。俺が持って行った数より増えている。カーテンで仕切られた病室の狭いスペース。藤沢さんといるその空間は、緊張感も圧迫感もなかった。 寒い十一月の土曜日。髪の毛を切りに来た藤沢さんが、ハンドクリーナーやらごみ袋やらを出してきたことを思い出した。突拍子もないことをしてしまえるところじゃなく、俺は藤沢さんのそういうところが好きなんだ。そう思った。 ・働かないと生きていけないし、仕事がなければ毎日することもない。だから会社に勤めている。けれども、仕事のもたらすものはそれだけではない。自分のできることをほんの少しでも、何かの役に立ててみたい。自分の中にある考えを、何らかの形で表に出してみたい。そういう思いを、仕事は満たしてくれる。働くことで、漠然と目の前にある大量の時間に、少しは意味を持たせられる気がする。 ・人に悪く思われないためなのか、人に喜んでもらいたいためなのか、自分の行動の根源にあるものは自分でもわからない。けれど、嫌われたくない。そればかりだったら、みじめだ。気を遣っているわけじゃなく好きでやっている。そういうことにしておけば、気持ちは楽だ。 「そんなふうに考えられたら、少しは自分のこと嫌じゃなくなりそうだね」 「無理して好きになることもないですけどね」 おやつまで待てないと、桜餅を食べながら山添君が言った。 「そう?自分のこと好きでいるのは基本でしょう。自分を大事にできない人間は人を大事にできないって、よく聞くよね」 「そんな理論がまかり通ったら、人を粗末にする人が続出しますよ。藤沢さんの聞き間違いじゃないですか」 「まさか」 自分を好きになることが大切だって、小学生のころから何度も聞いたことがある。そのままの自分を好きになろうって、自分を好きになれる人が他人を愛せるんだって、歌でだって小説でだってよく言っている。 「ぼくは自分が嫌いです。臆病だし、将来の見通しもゼロ。好きになれる要素がないで す」 山添君はパソコンに向かっていた体をこちらに向けて、話し出した。 「そんな悲観することないだろうけど」 「悲観はしてませんよ。ただ、タコと自分が好きじゃないだけで。でも、藤沢さんを好きになることはできます」 ・昔の俺は、誰とでも近づいて、たくさんの言葉を交わしていた。人と知り合うことも、みんなで集まることも好きだった。そのころは社交的だとよく評された。それに比べ、今の俺は、口数は当時の半分にも満たない。交友関係を広げることもなく、人と接することを避けている。 だけど、あのころの俺は、悲しい話が展開されるとわかっていて、会話を進めることができただろうか。自分の発作のことをこんなにも自然に口にできただろうか。数えきれないほど冗談を口にし、笑いあってきた。けれど、今のような話を誰かとしたことはなかった。 ・「薬、減らして大丈夫でしょうか?」 「一気にではなく徐々にやればいいし、できなきゃ、また元に戻せばいいだけだからね」 医者はさらりと言った。 断薬はつらいし、一度失敗すると苦労する。そういう話は、ネットの情報で何度も読んだ。俺にそれができるのだろうか。 「たいへんだってよく聞きますけど・・・・・・・」 「誰から?」 「まあ、ネットで」 「でしょうね。簡単に手に入れられる情報なんて、声が大きい人のものがほとんどですよ。山添さんのことを知っている人が発している意見ではないでしょう?」 - 2026年2月7日
 spring恩田陸バレエダンサーにして振付家の萬春(よろず・はる)。 彼は八歳でバレエに出会い、十五歳で海を渡った。 同時代に巡り合う、踊る者 作る者 見る者 奏でる者―― バレエダンサーの深津純、春の叔父の稔、幼少期同じバレエ教室に通っていた幼馴染であり作曲家の七瀬、萬春本人の視点から彼の肖像が浮かび上がっていく。 登場人物が美しくバレエを踊る姿がイメージできる小説だった。 「蜜蜂と遠雷」も同様にその道の天才達を描いた小説だったが、「蜜蜂と遠雷」と比較するとそこまで物語にのめり込めなかった。 七瀬のパートで知らない知識が大量に出てきて置いてけぼりのような気持ちになったからかな、、、 もしくは本人視点になるまで主人公の欠点が1つも出てこず、主人公に全く感情移入できなかったからか、、、 ・歌舞伎にしろ、バレエにしろ、つくづく型のあるものは強いな、と思う。 身体に染みこみ、叩き込んだ型があってこそ、自由に踊れるようになるのだ。 俳句に短歌、漢詩にソネット。どれも厳格な縛りや約束ごとがある。それらの制約の中でこそ、イメージは無限に翔べる。 ・それは、ダンサーにとっても、振付家にとっても非常に重要なものだ。語彙が増えれば増えるほど、より繊細に、より複雑な物語を語れる。血肉となったその豊富な語彙から、いかに自分らしい言葉を選び、自分らしく語るか。それがダンサーとしての大きさ、振付家としての大きさに繋がる。 ・要は、何が言いたいかというと、終わった仕事はあまり振り返らない、ということだ。 『アサシン』の成立過程について、後でいろんな人からさんざん聞かれたし、本に書いた人もいるのだが、これまで話してきたように一直線に出来上がったわけじゃないし、あちこち種を蒔いて徐々に下地が築かれてきた上に花開いたものなので、そうひと口に説明はできない。 春ちゃんもまた、あまりおのれの作品を残すということに執着しない人なので、「「アサシン』、大変だったなー」くらいの認識しかなくて、取材した人たちは一様に面喰らっていたようだ。あたしも同じ言葉で済ませたい。「アサシン』、大変だった。 ・時分の花、という言葉がある。まだ未熟で未完成なアーティストであっても、その若さでしか、その時にしか表現できない、刹那の輝き。散ることのない、「まことの花」とは異なる、一過性の、散ってしまう花。なんとなく、ジャンがしばしば俺に「HANA」を明らせたのはそういうものを自覚させたかったのかなと思う。 俺には、もちろん「踊りたい」という衝動は常にあったが、割と早くから自分の頭の中にある踊りを観たい、という衝動も強かった。こちらに留学してすぐに振付を始めたのも、早く踊りを観たい、と焦っていたのだろう。 ジャンは、「今は踊れ」としばしば俺をたしなめた。ダンサーとして極めろ、と再三言った。ダンサーには成長過程でその時々の「時分の花」があるのだから、それをしかるべき時にちゃんと体験していないと決して成熟できないし、将来振付をする時に、他のダンサーの「時分の花」にも気付けないぞ、と。 「時分の花」は世阿弥の「風姿花伝』に出てくる言葉だが、ジャンの口から普通に出てきたのを聞いた時はびっくりした。 ・西行法師の有名なあの歌。 願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ 「春」と「死」の文字の並びがパッと目に飛び込んできて、ずしんと胸を衝かれた。 春は死の季節。そんなことをうっすらと考えるようになったのは、この歌のせいかもしれない。ジャンだったか、誰だったか。たぶん、複数の先達に言われた言葉が、頭の中で混ざりあっている。 歳を重ねて老年の境地に足を踏み入れるようになると、年々、春が恐ろしくなる。今年も冬を越せたという喜びよりも、生き延びて春を迎えるいたたまれなさのほうが勝るようになる。春の臆面もない明るさに、芽吹く生命の獰猛さに、気後れを覚えるようになる。 さあ、年寄りども、道を空けろ、新しい生命に居場所を空けろ。そう糾弾されているよう な心地すらするーー
spring恩田陸バレエダンサーにして振付家の萬春(よろず・はる)。 彼は八歳でバレエに出会い、十五歳で海を渡った。 同時代に巡り合う、踊る者 作る者 見る者 奏でる者―― バレエダンサーの深津純、春の叔父の稔、幼少期同じバレエ教室に通っていた幼馴染であり作曲家の七瀬、萬春本人の視点から彼の肖像が浮かび上がっていく。 登場人物が美しくバレエを踊る姿がイメージできる小説だった。 「蜜蜂と遠雷」も同様にその道の天才達を描いた小説だったが、「蜜蜂と遠雷」と比較するとそこまで物語にのめり込めなかった。 七瀬のパートで知らない知識が大量に出てきて置いてけぼりのような気持ちになったからかな、、、 もしくは本人視点になるまで主人公の欠点が1つも出てこず、主人公に全く感情移入できなかったからか、、、 ・歌舞伎にしろ、バレエにしろ、つくづく型のあるものは強いな、と思う。 身体に染みこみ、叩き込んだ型があってこそ、自由に踊れるようになるのだ。 俳句に短歌、漢詩にソネット。どれも厳格な縛りや約束ごとがある。それらの制約の中でこそ、イメージは無限に翔べる。 ・それは、ダンサーにとっても、振付家にとっても非常に重要なものだ。語彙が増えれば増えるほど、より繊細に、より複雑な物語を語れる。血肉となったその豊富な語彙から、いかに自分らしい言葉を選び、自分らしく語るか。それがダンサーとしての大きさ、振付家としての大きさに繋がる。 ・要は、何が言いたいかというと、終わった仕事はあまり振り返らない、ということだ。 『アサシン』の成立過程について、後でいろんな人からさんざん聞かれたし、本に書いた人もいるのだが、これまで話してきたように一直線に出来上がったわけじゃないし、あちこち種を蒔いて徐々に下地が築かれてきた上に花開いたものなので、そうひと口に説明はできない。 春ちゃんもまた、あまりおのれの作品を残すということに執着しない人なので、「「アサシン』、大変だったなー」くらいの認識しかなくて、取材した人たちは一様に面喰らっていたようだ。あたしも同じ言葉で済ませたい。「アサシン』、大変だった。 ・時分の花、という言葉がある。まだ未熟で未完成なアーティストであっても、その若さでしか、その時にしか表現できない、刹那の輝き。散ることのない、「まことの花」とは異なる、一過性の、散ってしまう花。なんとなく、ジャンがしばしば俺に「HANA」を明らせたのはそういうものを自覚させたかったのかなと思う。 俺には、もちろん「踊りたい」という衝動は常にあったが、割と早くから自分の頭の中にある踊りを観たい、という衝動も強かった。こちらに留学してすぐに振付を始めたのも、早く踊りを観たい、と焦っていたのだろう。 ジャンは、「今は踊れ」としばしば俺をたしなめた。ダンサーとして極めろ、と再三言った。ダンサーには成長過程でその時々の「時分の花」があるのだから、それをしかるべき時にちゃんと体験していないと決して成熟できないし、将来振付をする時に、他のダンサーの「時分の花」にも気付けないぞ、と。 「時分の花」は世阿弥の「風姿花伝』に出てくる言葉だが、ジャンの口から普通に出てきたのを聞いた時はびっくりした。 ・西行法師の有名なあの歌。 願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ 「春」と「死」の文字の並びがパッと目に飛び込んできて、ずしんと胸を衝かれた。 春は死の季節。そんなことをうっすらと考えるようになったのは、この歌のせいかもしれない。ジャンだったか、誰だったか。たぶん、複数の先達に言われた言葉が、頭の中で混ざりあっている。 歳を重ねて老年の境地に足を踏み入れるようになると、年々、春が恐ろしくなる。今年も冬を越せたという喜びよりも、生き延びて春を迎えるいたたまれなさのほうが勝るようになる。春の臆面もない明るさに、芽吹く生命の獰猛さに、気後れを覚えるようになる。 さあ、年寄りども、道を空けろ、新しい生命に居場所を空けろ。そう糾弾されているよう な心地すらするーー - 2026年2月6日
- 2026年2月4日
 そして誰もいなくなったアガサ・クリスティーアガサ・クリスティー没後50年とのことで。 結末を知っていても面白い。 よくこんな設定を思いつくよなぁ。 登場人物が過去の自分を正当化するところや 疑心暗鬼に陥るところがやけにリアル。
そして誰もいなくなったアガサ・クリスティーアガサ・クリスティー没後50年とのことで。 結末を知っていても面白い。 よくこんな設定を思いつくよなぁ。 登場人物が過去の自分を正当化するところや 疑心暗鬼に陥るところがやけにリアル。
読み込み中...