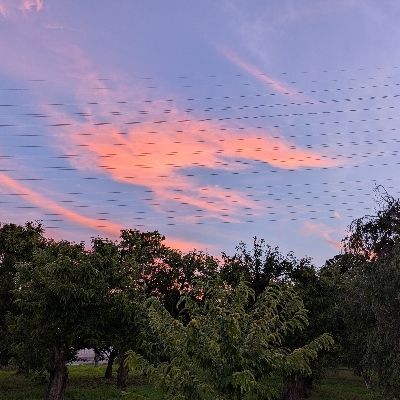いるかれもん
@reads-dolphin
2025年12月10日

読み終わった
ネガティブな感想
(かなりネガティブなことを書いています)
昨年非常に話題になった本であり、何となく「売れてるから読もう」と思っていつか買ってしばらく放置していた。その間、SNS上で統計に基づき本書の試聴を否定的に批判する投稿も目にしており、あまりいい印象を持っていなかった。そのような中本書を読み進めた。あらかじめそうした目線で読んだ感想であることを承知願いたい。
SNS上での批判で統計調査によるとそもそも「働いていると本が読めなくなる」という事実はないというものを見た。「働いていると本が読めなくなる」ことが本書の前提となっているが確かに、その根拠として挙げられているものは著者の実感と、映画作品(『花束みたいな恋をした』。本作はこの本の中でたびたび引用される。)、著者のSNSに寄せられる声くらいで客観性のある裏付けがないまま本論に入っている印象がある。
そして本書は、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いから、明治、大正、昭和戦前・戦中、1950~60年代、70年代、80年代、90年代、2000年代、2010年代それぞれの労働史と出版史(読者の歴史)について述べながら進んでいく。それぞれの時代の労働者の姿や、図書館員としては出版事情に関する内容は面白いと思った。出典も丁寧に書かれているので、個人的には気になる本も結構あったし、読書の歴史について改めて本を読んでみたいとも思った。また、それぞれの時代の様子を表す文学作品も紹介されている。ちょうど自分がぼちぼち読み進めていた谷崎潤一郎『痴人の愛』も紹介されていて「なるほど」と思うこともあった。そうした文芸作品の紹介はさすが文芸評論家だと思う。しかし、一方で、(別に私は歴史に詳しいわけではないけれど、)各次代の労働者の姿と、出版事情ってそんな簡単に結びつけていいの?という気もした。文献的な裏付けがあるのかないのかわからないような箇所もあり、おそらく著者の想像も入っているのではないかと思う。また、映画や文芸作品の紹介を持って、各次代の労働者像や読者像の裏付けとしている(「この作品にはこういう労働者がいるから、この次代の労働者はこういう姿だった」というような説明の仕方)部分があり、読者を煙に撒くような乱暴な展開の仕方に思えた。
そして、終盤にかけて読んでいて疑問を持つ点が続々増えていった。特に「知識」と「情報」の差異という部分については大きく疑問を持った。本書では「情報」とは知りたいことであり、「知識」とはそこにノイズ(他者の歴史や社会の文脈)が乗っているものとしている。それぞれがインターネットなどで得られるもの、読書によって得られるものとしている。その上で、現代では労働により、そうしたノイズを自身に受け入れることが難しくなったため「働いていると本が読めなくなる」と主張している。しかし、先日読んでいた根本彰『情報リテラシーのための図書館』などでは、知識や情報は階層構造をなしていて、情報に推論や確信などが付加されることにより知識になるとしており、「情報+ノイズ=知識」などと単純化できるものではないと感じた。また、何が情報で何をノイズと感じるのかは非常に主観的なものだと思う。この本の定義に乗れば「自分の歴史や文脈(必要性)」に沿うものが「情報」でそれ以外は「ノイズ」ということになるが、それは自分が今抱えている問題を解決するためにどれくらいの詳細さが必要なのか、自分がどれくらい詳細な「情報」で納得するのかによっても変わる。図書館情報学などで「情報とは何か」「知識とは何か」といった議論が交わされている中で、「知識=情報+ノイズ」とする考え方はあまりにも短絡的で、都合よく解釈しているようにしか思えなかった。
著者はこの「情報」と「知識」の区別を前提にして、「自分から遠く離れた文脈に触れることーそれが読書である」(働いていると本が読めなくなる理由は)「仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。」と結論づける。しかし、私の実感としては、自分自身の文脈を拡張することで本を読んでいるように感じている。何となく気になった事柄の本を読む、とかまさにそうした行為に思う。もちろん、本の中には著者の主張するような「他者の文脈」もあるかもしれないが、それを読書とするのも、やっぱり都合よく解釈しているように思える。そして、最後、著者は現在の社会を新自由主義などを背景として、労働者が仕事にフルコミットすることを強いられている「全身労働社会」とし、仕事など一つのことにコミットするわけではない「半身労働社会」を目指そう、「全身」ではなくて「半身」を目指そうと主張する。その際に、何かにフルコミットする「全身」の方が「半身」より楽だ、と主張するがもはや何の根拠もなく、ただただテンションで押し切っていてさすがに読んでいて苦しかった。その半身社会が「働いていても本を読める社会」であり、理想像として語っているが、全員が半身になった時、仕事に半身を捧げたとして読書などの文化にもう半身を捧げられるわけではない気もする。実際私は、働き始めてからの方が本を読めるようになった。
読み終わった後に、飯田一史の今月の新刊『この時代に本を売るにはどうすればいいのか』第1章を試し読みした。これは、本書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」(以下、「なぜはた」という)の検証であり、基本的に「なぜはた」の主張が誤りであるとしており、出版や読書動向について広く流布している誤った言説を前提としていることがわかった。そもそも「働いていると本が読めなくなる」という認識自体が統計的にが裏付けられないという指摘をしているほか、「なぜはた」に中で参照されている統計データの扱いの誤りも指摘している。正直データの読み解きの誤りであれば仕方ない面もあるかもしれないが、調査結果に付されている解釈上の注意を無視しているという点は流石に酷いと思った。著者の問題でもあるけれど、個人的には校閲の問題もあると思う。
総じてネガティブなことばかり書いてしまったが、印象としては、部分部分面白いし、読んでよかったと思うけれど、ご都合主義で書かれた客観性に欠けた本という印象だった。エッセイとして書いてくれたら良かったのではないかと思う。でも、新書で出したってことは、バズり目的だったのかなとも正直思ってしまった(著者がはっきりと「新書大賞取りたい」とか言っていたし。。。)それこそ、ノイズを排除して自分の文脈に合う「情報」のみで組み立てられた本なのかもしれない。実は普段、新書は基本的に研究者やアカデミックな背景を持つ専門家の書いたものや、中公新書、岩波新書などの固めのレーベルしか読まないようにしているのだけれども、その方針で間違っていなかったように思う。多分、普通に読んでいたら、ここまで考察しなかったし、普通に納得していた気がする。