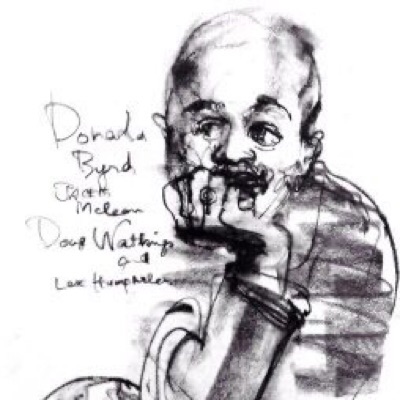駄々
@inugasuki
2025年12月23日

長い読書
島田潤一郎
読み終わった
心を静かに穏やかに保ちながら読める1冊。それでも最後の「長い読書」を読んだあとは胸がぎゅっとなって、さまざまなことを考える時間となった。
【好きな言葉】
・そうした時間のずっと底のほうには、昨日読んだ本の思い出がある。それは実際に経験した記憶と比べればとてもはかなく、うまく言葉にできない。うまく言葉にできないから、だれにも話さない。でも、本のタイトルと作家名ぐらいは同僚に告げることがある。
・本はページを開いたところで、読者の意志と関係なくスタートするわけではない。それはどんなにおもいしろい物語でも同じ。本を読み進めるには、ほんの少しの意志が要る。
・それまでは何も考えずにやり過ごせたことが、少しずつ、やり過ごせなくなってくる。毎日、なにかを不安に思う。自分の身体とこころが、次第にずれはじめているように感じる。
・どんなに寡黙な学生でも、どんなにふざけた態度しか見せない学生でも、カラオケではみな一生懸命に歌をうたった。「夢をあきらめない」とか「あの恋を忘れない」とか、ふだんは絶対にいえないようなことも、マイクをとおしてであれば、他の学生たちに素直に伝えることができた。ぼくはカラオケでは、いつもモニターに映る歌詞を真剣に読んでいた。そこには何かしらの真実があるような気がしたし、歌の歌詞を深く読み込むことで、同級生たちのこころを深く理解できるような気がしていたからだ。
・本屋に来ると、さまざまな欲望が次々と湧いてくる。ぼくはもっと、立派な人間になりたい。でもいまのぼくはまだ、150ページの小説に完全にお手上げなのだ。
・21歳のぼくのなかにあったのもまた「軽蔑と憧れ」で、おそろしいことに、そこには中間というものが存在しなかった。
・若いぼくに力を与えてくれたのは文体だ。文章ではなく、文体。知恵や経験、物語よりも先にある、作家の脈拍のようなもの。音楽でいうところの「ビート」のようなもの。
・世の中には「規範」というものがあり、お手本とすべきような「態度」があり、「流行」のようなものがある。
・言葉は、ぼくとだれかをつなげる。でもそれは見方を変えれば、ぼくとだれかを同じにすることでもある。
・本を読み始めたばかりのころは、難解な語彙や、カタカナで表記されるようなあたらしい用語に強く惹かれた。
・客観的に見れば、状況はたしかに苦しかった。でも、ぼくのこころのなかにはさまざまな作家の文体が蓄積されつつあった。それはぼくの未来に直接的なヒントも、こたえも、何一つとして与えてくれることはなかったが、すくなくとも、世界には今の社会とは別の「規範」のようなものがあることを教えてくれた。
・自分の人生というものはそれがたった一度である限り、練習することも、理解することもかなわないということだ。ひょっとしたら、臨終の際になってようやく、「わたしの人生はこうだった」と認識し、理解できるものなのかもしれないが、そのときには誰かに伝える術がない。(⋯)それまでのぼくは人生になにかしらの意義があり、目的があって、その目的に殉じるように生きなければならないのだと思っていたからだ。
・話すことによって初めて、たしかめられる何かがある。あるいは、発見できる何かがある。
・大好きな恋人がいなくても、長年抱いていた夢が叶わくても、親しい人が病とたたかっていなくても、人生は続くし、毎日は続く。仕事をし、食事をし、電話で親と話し、テレビで好きな芸能人を見て、なんとなくどこかへ行きたくなって、最寄りのコンビニへ足を運ぶ。こうした日々の行為は、当人だけが知り、記憶していることで、その当人がいなくなってしまえば、だれもがそれを知る機会を失うだろう。
・『なしくずしの死』を読んでいると、ぼくは少年のころに感じた寂しさを思い出した。なにかを伝えたいし、表現したいのだけれど、「クソ」とか「馬鹿」とか「アホ」とかしかいえない。泣きたいわけではないし、死にたいほどになにかに絶望しているわけでもない。好きなものもたくさんあるし、両親はぼくを愛してくれているし、友だちと遊ぶこともたのしい。けれど、一方で、やるせない気持ちもあって、そういう得も言われぬものといったい、どう付き合えばいいのかわからない。わからないまま、その気持ちに蓋をする。あるいは、忘れてしまう。でも、その気持は消え去ったわけではなく、ぼくのこころの奥底にずっとある。
・人はこれから先に時間があると思うから、本を買うのであって、今後の人生において時間がないのであれば、人は本を買わない、ということだ。
・ぼくはこの「昇揚」に覚えがある。それはぼくが顔の見えない誰かを言い負かそうとするときに決まってあらわれる、抑えられないこころの働きのようなものであり、眼の前の具体的なだれかではなく、大多数の人たちに向けてなにかを発信しようと企んでいるときにあらわれる、こころの震えのようなものである。
・ぼくもまた、こころが沈み込むような暗い時期に、本屋さんに、図書館に救われた。そこで、自分の人生を変えるようなすばらしい物語に、運命的な言葉に出会ったというのではない。世の中にはたくさんの本があるのだ、という事実が、ぼくの暗いこころを慰めたのだ。それはつまり、世の中にはたくさんの人間がいて、たくさんの考えがあり、生き方があり、言葉があるということだ。
・かつては、目に見え、手で触られることができるものに名前を与えることだけが、言葉であり、意味だった。けれど、年齢を重ねていくにつれ、眼の前にあるそのものよりも、「意味(概念)」のほうが優先される。信号はたしかに緑であるはずなのに、「青」であるという「意味(概念)」のほうが重んじられる。つまり、視覚より、聴覚より、触覚より、知覚のほうが先にくる。それが平均的な成長ということだ。
・個性的あるというのはとてもつらいことだ。でも、だからこそ、その人にしか書けないものを書き、それが読者を感動させるのだ。