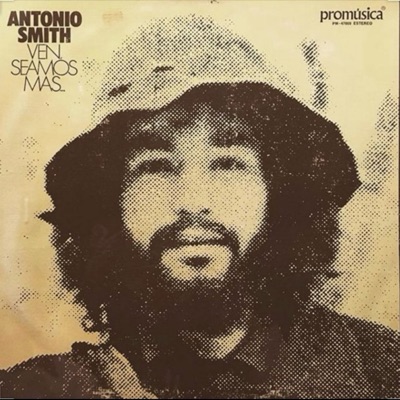
J.B.
@hermit_psyche
2025年12月31日

読み終わった
しばしば若者文化や退廃的風俗の記録として読まれるが、その理解は作品の表層にとどまっている。
このテキストの核心は、描写される出来事の過激さではなく、透明性という逆説的概念を通じて、存在・言語・主体の成立条件そのものを問い返す点にある。
透明であるとは何もないことではない。
むしろ過剰に存在するがゆえに輪郭を失い、意味として把握できなくなった状態を指す。
本作はそのような意味飽和状態に置かれた世界をほとんど冷酷なまでの平熱で記述する。
文体は感情や倫理的判断を極力排し、断片的で即物的な描写を積み重ねていく。
この語りの態度は、作者の価値観の欠如を示すものではなく、価値判断がもはや有効に機能しない世界の構造を、そのまま文体として引き受けた結果である。
ここでは言語は意味を深める道具ではなく、意味が剥落していく過程を可視化する装置として働く。
読者は物語に導かれるのではなく、言語が世界を捉えきれなくなっていく現場に立ち会わされる。
身体の描かれ方も同様に、主体性の崩壊を前提としている。
ドラッグやセックスは快楽や逸脱の象徴ではなく、自己同一性が解体されていくプロセスの触媒として配置される。
身体は私のものであることをやめ、刺激と反応が通過する場へと変質する。
その結果として現れるのは解放ではなく、自己を自己として把握できないという根源的な不安である。
ここで描かれる快楽は常に空洞化しており、充足ではなく消失へと向かっている。
この小説が書かれた時代の日本社会は、高度経済成長の余熱の中で豊かさと引き換えに意味の重力を失いつつあった。
本作はその社会的状況を批評的に説明することはしないが、登場人物たちの生の在り方そのものが、すでに社会批評として機能している。
国家や共同体、将来といった概念は、彼らにとって現実を支える軸にはなり得ず、ただ背景ノイズとして存在するにすぎない。
ここに描かれる日本は、理念としての国家ではなく、欲望と情報が漂流する空間としての日本である。
題名にある「透明に近いブルー」という表現は、視覚的イメージであると同時に認識論的な比喩でもある。
ブルーは感情や記憶と結びつきやすい色でありながら、透明に近づくことで色としての意味を失っていく。
この曖昧な状態は、存在が完全に消える直前、あるいは意味が発生する直前の不安定な領域を示している。
作品全体が、この臨界点にとどまり続けることで読者に安定した理解や解釈を与えない。
読了後に残るのはカタルシスではなく、理解しようとする意志そのものが宙吊りにされる感覚である。
この小説は答えを提示しないし、問題を整理することもしない。
むしろ問題を問題として把握するための前提条件が崩れていることを示す。
『限りなく透明に近いブルー』とは、何かを語る小説ではなく、語ることが困難になった世界そのものを、ほとんど無加工のまま差し出す文学的装置なのである。
ここにこそ本作が今なお読み継がれる理由があり、その過激さよりもはるかに深い射程が存在している。
