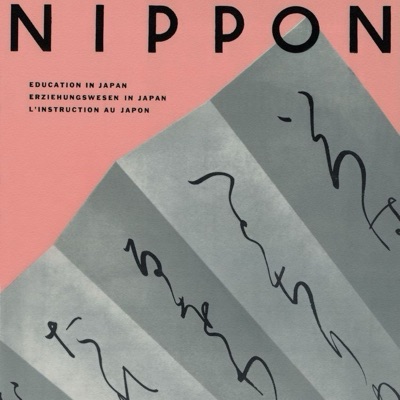
葉山堂
@hayamado
2026年1月5日

母なる夜
カート・ヴォネガット・ジュニア
新年早々家族がインフルに感染、私ももらってしまい咳が止まらず、眠れないままに読んだのだが、内容に引きずられて朝になっても心が落ち着かない。
凄惨な描写があるわけではない、むしろユーモアがあって、シニカルで、しかしそういった筆致で綴られる物語はよけいに心に重くのしかかる。
物語は、主人公であるハワード・W・キャンベル・ジュニアによる告白録というかたちで綴られる。
キャンベルはアメリカ人だがドイツで育ち、第二次世界大戦中もドイツに留まった。
ナチス宣伝ラジオの放送員として、忠実なナチ党員を装いながら、実際は放送に暗号をのせて自国へ情報を送るスパイ。
戦後、ニューヨークに隠れ孤独に生きている彼が出会う隣人のジョージ・クラフト、医師のエプスタインとその母、白人至上主義団体のジョーンズとその"親友たち"、そしてキャンベルを愛する女性。
息をつかせぬ展開で一気に読ませながら、人間のもつ善悪というものがいかに曖昧で、人によって認識の違うものかということが描かれる。
ユダヤ人の大量虐殺は悪。戦争は悪。悪に逆らい人を救うことは善。人を愛し尽くすことは善。ではその中間は?
【以下、物語の内容に触れています】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
物語(告白録)は、キャンベルの、かなり一方的な主観に基づいた内省が展開される。読み進めるうちに読者は、キャンベルの内省をそのまま受け取ってよいものか、疑わしくなってくる。
冒頭、「編集者の立場から」という"告白録のまえがき"で、キャンベルが劇作家であること、作家というものは創作の名のもとにいともかんたんに嘘をつけるということ、そして彼がアメリカ人でありながら文筆においてはドイツ語に一番堪能であり、そこにアイデンティティを持っていたことなどが記される。
ユダヤ人をガス室に送りながら、本当は"そちら側ではない"自分…
しかしアメリカ人でありながらドイツ人の妻を愛し、ドイツのアイデンティティを持つ自分…
キャンベルは大量虐殺に加担したという悪そのものを背負いながら、悪を悪と認識できない認知の歪み、精神分裂は自分にはない、そして自分のほんとうの内面にあるのは悪ではなく善である、と頑なに繰り返す。
戦争という大きな波に溺れ、思考機械の歯車の歯(真実)を自ら壊し、歯抜けの歯車を回してこそ矛盾した世界を生き続けられる多くの者たちと自分は違う…
自分は歯(真実)を自ら折ったことはないと。
しかしその真実とは一体なんなのか?
暗い影のなかに片足を浸し立っている自分を呼ぶ声を、キャンベルはずっと求めている。
『わたしはしばしば、その小エデンから聞こえてくる大声に耳を傾けた。子供の叫び声だが、なにはさておいても聞き耳を立てずにはいられなかった。それは、かくれんぼは終わったから、みんな隠れ場所から出ておいで、うちへ帰る時間だよ、ということを意味する甘くてもの悲しい呼びかけだった。
その文句はこうだ──「オリーオリー・オックス・イン・フリー」
そして、わたしを傷つけたい、殺したいと思っているであろう多くの人から身を隠していたわたしは、だれかがわたしにそう呼びかけてくれることをしょっちゅう請い願った。際限のないわたしのかくれんぼをやめさせるために、だれか甘くもの悲しい声で叫んでくれないものかと──
「オリーオリー・オックス・イン・フリー」』
………

