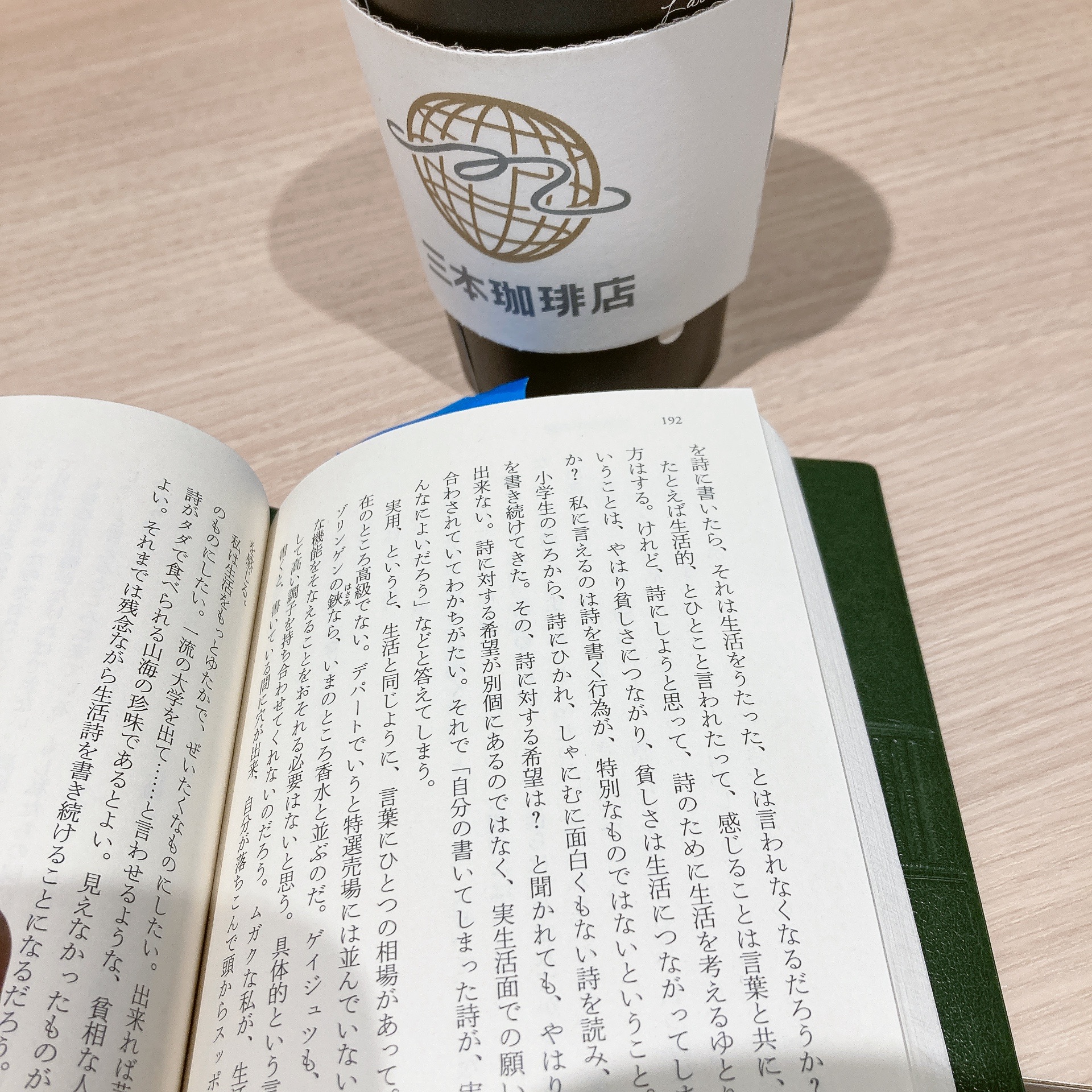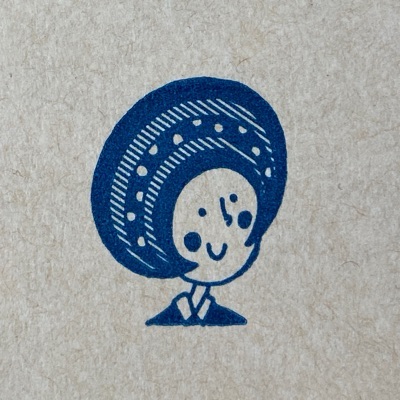deepend
@deepend
2026年1月14日

朝のあかり
石垣りん
読み終わった
かつて読んだ
14歳から定年まで働き通し、病気の父や弟、継母の生活を背負いながら試作にも励んだ石垣りん。
昭和の生活の明るさや遣る瀬なさの描写の合間に、彼女の自省に関する記載が繰り返し出てくるところも好きだった。
出征する彼女の弟に叔母が「おまえ、決死隊は前へ出ろ、と言われて、はい、なんて、まっ先に出るのではないど」と言ったことの驚きを後年振り返った際の記述。
“私が聞き捨てたはずのことばを耳が大切にしまっていて、今日でも、何かの暗示のようにとり出して見せるのは、それが、ほんとのひびきをもっていたからだと思われます”
“私は、権力とか常識のとりこになり、そういう真実の言葉を、いつも勝ち得ないで生きているのではないのか?と時々心配いたします”
(p.222)
“終戦を境にして、すっかり目をさましたように思ったのも、アテにはならないようです。現在、違った状況のもとで、私はやはり、同じように愚かだろう、と思うからです。”
(p.223)
残念ながら私は詩を理解する感性がないのだけど、この本に収録された詩のなかでは原爆被災写真によせて書かれた「挨拶」が響くものがあった。