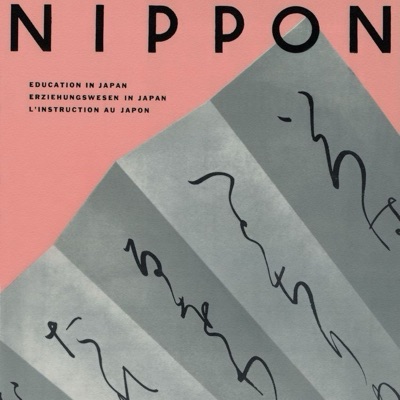たじ
@tazi
2026年1月24日

母なる夜
カート・ヴォネガット・ジュニア
読み終わった
奇妙な読後感。何を読んでいたんだろう、読まされていたんだろうという感覚。
キャンベルとはなんだったのか。
この話は、何を装い、何を装わないか(確固たる自分)、そのある意味での演劇をさせられる人たちの話。
キャンベル自身を含め、彼の周りにはスパイが出てくる。
何かを装いながら、必死に自分の足場が崩れないように守ろうとする。
彼らは芸術や愛に生きる目的を持とうとし、そこに本当の自分のアイデンティティを保とうとする。
キャンベルは、あの屋根裏部屋での亡くなった妻を思い出しながら過ごしたささやかな日常に足場を見出していたが、彼の過去がその安住を許さない。
こう書いていると、
キャンベルは何を装っていたのかわからなくなる。
一見すると、
ナチスドイツの扇動家を装いながら、
その正体はアメリカのスパイである。
ただ、キャンベルはナチスドイツに数々の残虐な提案をしたり、権力者に擦り寄ったりしている。
終戦後にアメリカ軍大佐のワータネンから「ドイツが勝利した場合、君はどういう行動をしていた?」と訝しまれるような行動を取っている。
アメリカのスパイであることも装っていたのか?どちらに転んでもいいように行動していたように見えてしまう。
そして、終戦後アメリカ国内では追われる身となり、自分の存在を消すようにひっそりと屋根裏部屋で暮らすことになる。
そうすると、装わない自分としては、亡きベルガを愛し続ける自分しかないとも言える。
が、これはレシ・ノトを愛してしまうことで崩れてしまう。
もはや何も残らない。装えるものも、確固たる自分も何もかも無くなった時、キャンベルの過去の罪だけが残る。
もはや罪しか残らない体と精神を、自ら罰することで救われる話だとすると、
この小説自体が、何もかもを取り上げられて途方に暮れる可哀想なキャンベルを描いていることになり、あまりにも悲劇的だ。
そして、ここに小説冒頭の"編集者から"が活きてくる。
「彼は劇作家であり、うそつきになれる素養があるということ」
アイヒマンのように、本当はどこかで拉致されてイスラエルに連れてこられた末に、独房で書いたものかもしれない。
エイブラハム・エプスタイン医師とその母に、通報されていたかもしれない。
私は、この小説を読み終えた読後感が非常に奇妙なものであると感じたものの正体は、
この小説こそがキャンベルが装ったものであるという感覚からかもしれない。
虚実入り乱れたこの小説こそが彼の闇であり、彼の悲劇を正しく誤解してくれる読者とその同情が光だとしたら恐ろしい小説である。
という、間違った深読みも多分にありながら、
まだまだ欠けている歯車だらけでそれを自覚していながらも、(いのち!)
色々な読み方ができる非常に面白い小説だということを言っておきたいわけであります。
(これ読んだ人と喋りてえええ!!)