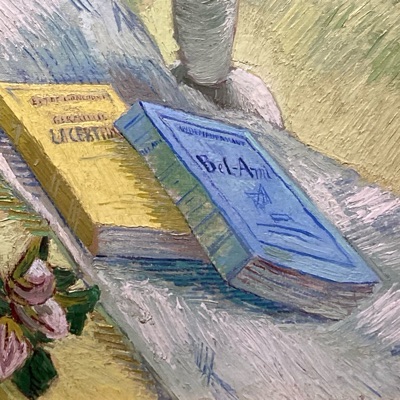DN/HP
@DN_HP
2026年2月5日

祝山
加門七海
読み終わった
リアルホラー
作家自身の「実体験を下敷き」にして一人称で書かれた怪異小説、「リアルホラー」。作家と体験者、事実と真実、理性と狂気あるいは倫理と衝動、偶然と因果、幾つもの相反する視点、立場の間を揺れ彷徨いながら、巻き込まれて、不安定に、しかし確実に進んでいく、いってしまう物語、小説。
現れない怪異。明らかに変貌していく友人たち、変調をきたしはじめる自らの心身。その理由がわからない、断定することが出来ない、そこにあるどうしようもない不安の恐ろしさ。不安と恐怖に纏わりつかれながら、振り払う様に、作家の書く小説は最後のページに向かっていくし、体験者は「解決」に向けて「解釈」を確かめる行動を起こす。ある人は死に、ある人の行方は杳として知れず……
「できることのすべては終わ」り、事態は終息し、小説も終わりを迎える。わたしはその顛末を読んでいる。読み終わり「現実」に戻る。それでも、やはり、「真実はわからない」。不安と恐怖はまだ振り払うことが出来ていない。
怖かった!まだ怖い。とても良い怖い本だった。
-
「体験者にとってリアルなら、怪異もまた、現実の記憶として残るのだから。」
「だが、私はもう、現実の合理性を求める気はない。」
「人ひとりが死んだのだ。(…)その死を祟りと決めつけて、そら見たことか、というような、弁舌を振るうのは気が退ける。」
「結局、祟りのなんのといっても、当事者達に自覚がなければ、それらは存在しないに等しい。日々、つつがなく暮らしている人に、不吉な文言を押しつけるのは、霊感商法と変わらない。」
「私達の身の上に起こったすべてが偶然でも、気のせいでも、私はもう、構わない。」
「真実はわからない。」