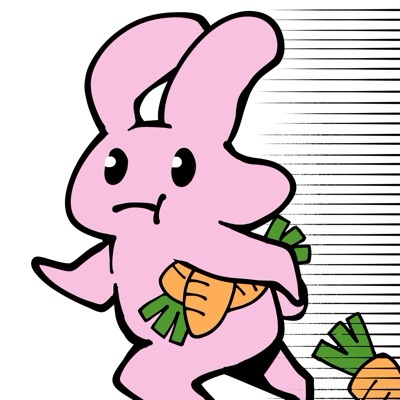法律婚って変じゃない?

9件の記録
 中根龍一郎@ryo_nakane2025年5月27日読み終わった大きくなったらだれだれくん/だれだれちゃんと結婚する、というのは、私が小さかったころまだ身近な言い方だった。今の子供たちも言うのかはわからない。 もちろん子供たちは〈結婚〉がなにを意味するのかよくわかっていなかった。それがどのようなものであり、どのように進み、どのように終わり、あるいは終わらないのかを知らなかった。 しかし大人になった今も、私たちが〈結婚〉とはなんであるのかをわかっているかというと、それなりに疑わしい。社会にはひとつの類型的な目的地としての〈結婚〉があって、私たちはしばしばそこへ類型的に吸い込まれていく。そして結婚が国家にとって何であり、社会にとって何であり、法的に何であり、哲学的に何であるのかを、筋道立てて考えなくても、結婚することはでき、婚姻状態を継続することもできる。 そうした結婚について、できる限り明晰な言葉で語ろうとするとき、その試みにもかかわらず、その明晰になりきらない部分や合理的に切り分けることのできない部分、すっきり処理できない部分がどうしても残る。法と哲学の話はそういうところが面白い。 近年の法律婚をめぐるイシューは、同性婚と選択的夫婦別姓に偏った関心が寄せられる。でも同性婚にせよ選択的夫婦別姓にせよ、それは既存の法律婚を「より望ましい法律婚」に変えていこうとする試みであって、法律婚という制度自体は温存しようとする。しかしこの本の論考は全体的に、そもそも法律婚の存立自体を疑問に付すものだ。 法律婚は変ではないのか。では変だとしたら、変であるにもかかわらず、なぜ社会は法律婚を維持するのか。なぜ法律婚はいまだ解体されていないのか。法律を問題にするだけに、議論はしばしば現実の法制度の運用や、法を実際に変更することの実務的な難しさといったところでしばしばつまずき、すっきりしない形になる。でもその、現実の法の対象であるカップルたちの問題の前で戸惑い、うまく処理できないところに、むしろ好感が持てた。 大島梨沙の論考「民法から婚姻を削除するとどうなるか」は、サイエンティフィックな思考実験としてとりわけ面白い。民法における婚姻に関する条文を削除してみることで、民法上の婚姻の諸規定が具体的にどのような社会的機能を果たしているのかを分析していき、そのプロセスで婚姻制度のさまざまな問題や改善点が見えてくる。婚姻を削除するとどうなるか、という手法はきわめてドラスティックだが、導かれる結論はかなり穏当なものだ。というより、現に存在する社会のなかの諸個人を考えるなら、穏当なものにならざるを得ないのだろう。 結婚にはさまざまな問題があり、結婚を選択しない人や結婚を忌避する人ももちろんいる。でも一方で、結婚を求め、結婚による保護を受ける人、その保護を必要とする人もまたたくさんいる。法制度に関する議論は、現に存在する結婚というものの扱いにくさの前で戸惑ってしまう。 論者はおそらくみんな法律婚というものに一定の距離を持とうとしているにもかかわらず、実際の制度の前で誠実に学術的見識を働かせようとすると、歯切れの良いことが言えなくなる、その言い切れなさ、あいまいさの手触りを、私は好ましく思う。そういう知性の姿が好きなのだろう。
中根龍一郎@ryo_nakane2025年5月27日読み終わった大きくなったらだれだれくん/だれだれちゃんと結婚する、というのは、私が小さかったころまだ身近な言い方だった。今の子供たちも言うのかはわからない。 もちろん子供たちは〈結婚〉がなにを意味するのかよくわかっていなかった。それがどのようなものであり、どのように進み、どのように終わり、あるいは終わらないのかを知らなかった。 しかし大人になった今も、私たちが〈結婚〉とはなんであるのかをわかっているかというと、それなりに疑わしい。社会にはひとつの類型的な目的地としての〈結婚〉があって、私たちはしばしばそこへ類型的に吸い込まれていく。そして結婚が国家にとって何であり、社会にとって何であり、法的に何であり、哲学的に何であるのかを、筋道立てて考えなくても、結婚することはでき、婚姻状態を継続することもできる。 そうした結婚について、できる限り明晰な言葉で語ろうとするとき、その試みにもかかわらず、その明晰になりきらない部分や合理的に切り分けることのできない部分、すっきり処理できない部分がどうしても残る。法と哲学の話はそういうところが面白い。 近年の法律婚をめぐるイシューは、同性婚と選択的夫婦別姓に偏った関心が寄せられる。でも同性婚にせよ選択的夫婦別姓にせよ、それは既存の法律婚を「より望ましい法律婚」に変えていこうとする試みであって、法律婚という制度自体は温存しようとする。しかしこの本の論考は全体的に、そもそも法律婚の存立自体を疑問に付すものだ。 法律婚は変ではないのか。では変だとしたら、変であるにもかかわらず、なぜ社会は法律婚を維持するのか。なぜ法律婚はいまだ解体されていないのか。法律を問題にするだけに、議論はしばしば現実の法制度の運用や、法を実際に変更することの実務的な難しさといったところでしばしばつまずき、すっきりしない形になる。でもその、現実の法の対象であるカップルたちの問題の前で戸惑い、うまく処理できないところに、むしろ好感が持てた。 大島梨沙の論考「民法から婚姻を削除するとどうなるか」は、サイエンティフィックな思考実験としてとりわけ面白い。民法における婚姻に関する条文を削除してみることで、民法上の婚姻の諸規定が具体的にどのような社会的機能を果たしているのかを分析していき、そのプロセスで婚姻制度のさまざまな問題や改善点が見えてくる。婚姻を削除するとどうなるか、という手法はきわめてドラスティックだが、導かれる結論はかなり穏当なものだ。というより、現に存在する社会のなかの諸個人を考えるなら、穏当なものにならざるを得ないのだろう。 結婚にはさまざまな問題があり、結婚を選択しない人や結婚を忌避する人ももちろんいる。でも一方で、結婚を求め、結婚による保護を受ける人、その保護を必要とする人もまたたくさんいる。法制度に関する議論は、現に存在する結婚というものの扱いにくさの前で戸惑ってしまう。 論者はおそらくみんな法律婚というものに一定の距離を持とうとしているにもかかわらず、実際の制度の前で誠実に学術的見識を働かせようとすると、歯切れの良いことが言えなくなる、その言い切れなさ、あいまいさの手触りを、私は好ましく思う。そういう知性の姿が好きなのだろう。