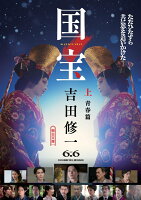noko
@nokonoko
- 2026年1月31日
 遺骨と祈り安田菜津紀読み終わった買った心に残る一節ジャーナリストの魂… 福島、沖縄、パレスチナ…知らないということ自体が悪なのだと思わずにはいられない。 ↓↓書き抜き (娘の遺骨の)捜索はまだ続けたい、見つかった場所は慰霊のための場所にしたい、けれども、自分の娘のためにそうした思いを抱くのは、"わがまま"なことなのだろうか。 「これは人間の尊厳の問題で、人数が一人だから、二人だからという問題じゃないですよ。たとえたった一人であったとしても、あなたには声をあげる権利があるんです。"一人の利益のために全体の利益を損なうな“という人がいますけれど、そんなの関係ない。一人の人間を大切にできないのに、社会を大切にできるはずがないんですよ」 日本で掲げられる「平和が良い」という言葉を思う。一般論として、その理念自体は重要なものかもしれない。ただ、「憎しみでは、何も生まれない、無力に走ってはならない」という呼びかけは、加害者がある程度、公正に裁かれる社会があってこそ機能するものではないだろうか。 安全圏から突然やってきた私が、弟を殺され、青ざめる少年に、「憎しみでは、何も生まれない」などと講釈を垂れるのは、あまりにグロテスクな構図ではないか。 「武力に走るな」という言葉は、力を振りかざしている側にこそ言うべきなのだ。
遺骨と祈り安田菜津紀読み終わった買った心に残る一節ジャーナリストの魂… 福島、沖縄、パレスチナ…知らないということ自体が悪なのだと思わずにはいられない。 ↓↓書き抜き (娘の遺骨の)捜索はまだ続けたい、見つかった場所は慰霊のための場所にしたい、けれども、自分の娘のためにそうした思いを抱くのは、"わがまま"なことなのだろうか。 「これは人間の尊厳の問題で、人数が一人だから、二人だからという問題じゃないですよ。たとえたった一人であったとしても、あなたには声をあげる権利があるんです。"一人の利益のために全体の利益を損なうな“という人がいますけれど、そんなの関係ない。一人の人間を大切にできないのに、社会を大切にできるはずがないんですよ」 日本で掲げられる「平和が良い」という言葉を思う。一般論として、その理念自体は重要なものかもしれない。ただ、「憎しみでは、何も生まれない、無力に走ってはならない」という呼びかけは、加害者がある程度、公正に裁かれる社会があってこそ機能するものではないだろうか。 安全圏から突然やってきた私が、弟を殺され、青ざめる少年に、「憎しみでは、何も生まれない」などと講釈を垂れるのは、あまりにグロテスクな構図ではないか。 「武力に走るな」という言葉は、力を振りかざしている側にこそ言うべきなのだ。 - 2026年1月31日
 家族村井理子借りてきた読み終わった映画「兄の終い」が気になってたけど観なかったので、読んでみた。 家族の犠牲から身を守ろうとする筆者の賢さと、でもどうしても家族を見捨てきれない優しさに切なくなる。 不条理がいとおしい…
家族村井理子借りてきた読み終わった映画「兄の終い」が気になってたけど観なかったので、読んでみた。 家族の犠牲から身を守ろうとする筆者の賢さと、でもどうしても家族を見捨てきれない優しさに切なくなる。 不条理がいとおしい… - 2026年1月27日
 笹の舟で海をわたる角田光代借りてきた読み終わった左織目線の語りだから、風美子にぞっとするんだけど、真実はわからない… 私は角田光代の描く主人公の不如意に共感するタイプなんだけど、それは少数派だと思ってたけど、実は多くの人がそうなのか…? うっすらそれに気づいた時はもう誰もいない。 八日目の蝉とかとは違った怖さ…
笹の舟で海をわたる角田光代借りてきた読み終わった左織目線の語りだから、風美子にぞっとするんだけど、真実はわからない… 私は角田光代の描く主人公の不如意に共感するタイプなんだけど、それは少数派だと思ってたけど、実は多くの人がそうなのか…? うっすらそれに気づいた時はもう誰もいない。 八日目の蝉とかとは違った怖さ… - 2026年1月18日
 自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった買った心に残る一節自炊は確かにセルフケア。春から一人暮らしの予定の息子にあげようと思った。 ↓↓ 子どもは文字の書き方、時計の読み方、泳ぎ方、体験すること全てが初めてであり、「何かができないこと」に慣れてますよね。絵が上手くなりたい私のように、すぐに上手になろうとしません。小学生の子どもたちに料理を教えていて感じるのは、少しずつ料理が上手くなることに対する胆力の有り様です。牛歩の成長を飛び跳ねるように喜ぶ様子はとても眩しくて、同時にちょっとうらやましいと感じてしまいます。 ↑これね。だいじ。
自分のために料理を作る山口祐加,星野概念読み終わった買った心に残る一節自炊は確かにセルフケア。春から一人暮らしの予定の息子にあげようと思った。 ↓↓ 子どもは文字の書き方、時計の読み方、泳ぎ方、体験すること全てが初めてであり、「何かができないこと」に慣れてますよね。絵が上手くなりたい私のように、すぐに上手になろうとしません。小学生の子どもたちに料理を教えていて感じるのは、少しずつ料理が上手くなることに対する胆力の有り様です。牛歩の成長を飛び跳ねるように喜ぶ様子はとても眩しくて、同時にちょっとうらやましいと感じてしまいます。 ↑これね。だいじ。 - 2026年1月16日
- 2026年1月15日
 隆明だものハルノ宵子読み終わった買った心に残る一節「何か善いことをしているときは、ちょっと悪いことをしている、と思うくらいがちょうどいいんだぜ」と言うのは、父の言葉だったと思う また、これは絶対社会正義だからと、同調圧力を振りかざす世間の空気からも"ひとり"であらねばならない 父は、自分たちこそが"絶対善"、それ以外の考えは、絶対に"悪"と言う理念から徒党を組み、活動することを最も嫌った
隆明だものハルノ宵子読み終わった買った心に残る一節「何か善いことをしているときは、ちょっと悪いことをしている、と思うくらいがちょうどいいんだぜ」と言うのは、父の言葉だったと思う また、これは絶対社会正義だからと、同調圧力を振りかざす世間の空気からも"ひとり"であらねばならない 父は、自分たちこそが"絶対善"、それ以外の考えは、絶対に"悪"と言う理念から徒党を組み、活動することを最も嫌った - 2026年1月15日
 感じるオープンダイアローグ森川すいめい借りてきた読み終わった心に残る一節7つの原則の意味は、固定されたものではない。時代やその場にいる人たちによって、柔軟に変化する。不確実な状況の中にとどまるとは、どういう意味なのか、どうしたらそうなるのか、責務とは何か、対話主義とは何か、そうした話し合いをスタッフ全員で対話的に行うのだという。 子供が生まれた時、私はヤーコ・セイックラ氏に、 「子どもが生まれたんだ。どんなふうにしていったらいいか、何かアドバイスをくれないか?」 と聞いてみた。セイックラ氏は驚いた表情で答えた。 「何を言ってるんだ。君の大切なプロセスを、僕が奪うことなんてできないよ」 それは、私にとって最高の言葉だった。 「同じ意見のスタッフだったら、そこにいなくてもいいのです」 と話すのを聞いてわかった気になっていたが、この時初めて腑に落ちた。 それまでの、医師の私が中心になって行う対話は、対話なのか、単に輪になっただけなのかわからないものだったが、スタッフと対等の立場で話すようになったら、明瞭に対話が広がった。今では、他のスタッフが入ることで、対話がこれまでと全然違う、豊かなものになることを実感している。私一人の考えではどうにもならないことがしばしばあるし、他のスタッフが話しているのを聞くことで刺激も受けられる。また、話さない時間があることで、考える間が生まれ、私自身の中にも新しい考えが浮かびやすくなる。台湾の場にいるそれぞれの思いが重なって、新しい考えやこれまで話されていなかったことが話されるようになっていく。
感じるオープンダイアローグ森川すいめい借りてきた読み終わった心に残る一節7つの原則の意味は、固定されたものではない。時代やその場にいる人たちによって、柔軟に変化する。不確実な状況の中にとどまるとは、どういう意味なのか、どうしたらそうなるのか、責務とは何か、対話主義とは何か、そうした話し合いをスタッフ全員で対話的に行うのだという。 子供が生まれた時、私はヤーコ・セイックラ氏に、 「子どもが生まれたんだ。どんなふうにしていったらいいか、何かアドバイスをくれないか?」 と聞いてみた。セイックラ氏は驚いた表情で答えた。 「何を言ってるんだ。君の大切なプロセスを、僕が奪うことなんてできないよ」 それは、私にとって最高の言葉だった。 「同じ意見のスタッフだったら、そこにいなくてもいいのです」 と話すのを聞いてわかった気になっていたが、この時初めて腑に落ちた。 それまでの、医師の私が中心になって行う対話は、対話なのか、単に輪になっただけなのかわからないものだったが、スタッフと対等の立場で話すようになったら、明瞭に対話が広がった。今では、他のスタッフが入ることで、対話がこれまでと全然違う、豊かなものになることを実感している。私一人の考えではどうにもならないことがしばしばあるし、他のスタッフが話しているのを聞くことで刺激も受けられる。また、話さない時間があることで、考える間が生まれ、私自身の中にも新しい考えが浮かびやすくなる。台湾の場にいるそれぞれの思いが重なって、新しい考えやこれまで話されていなかったことが話されるようになっていく。 - 2026年1月9日
- 2026年1月6日
 満月が欠けている穂村弘読み終わった買った緑内障になって、死生観のことなど何書いてある。 緑内障になって、人生振り返っちゃうのを笑う人もいると思うけど、なんとなくわかるなー。 目にアツをかけないようにしよう。
満月が欠けている穂村弘読み終わった買った緑内障になって、死生観のことなど何書いてある。 緑内障になって、人生振り返っちゃうのを笑う人もいると思うけど、なんとなくわかるなー。 目にアツをかけないようにしよう。 - 2026年1月4日
- 2026年1月3日
- 2025年12月29日
 火花: 北条民雄の生涯高山文彦読み終わった心に残る一節読み応えのある本だった。 川端康成の人としての誠実さが際立った。 「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです。僕の言うこと、解ってくれますか、尾田さん。あの人たちの『人間』は、もう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけが、びくびくと生きているのです」
火花: 北条民雄の生涯高山文彦読み終わった心に残る一節読み応えのある本だった。 川端康成の人としての誠実さが際立った。 「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです。僕の言うこと、解ってくれますか、尾田さん。あの人たちの『人間』は、もう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけが、びくびくと生きているのです」 - 2025年12月28日
 ハチドリ舎のつくりかた安彦恵里香読み終わった心に残る一節「お店はやりたいようにやったらいいんよ。いろんな人がいろんなことを言うけど、大事なのは自分の直感。それを信じて楽しくやるのが一番よ!」 わたしが場づくりに関して思うのは、「その人がその人らしくそこにいられる状況をいかにしてつくるか?」。何でもかんでもわたしがやってしまうのは、むしろその人が自分で行動し、得られるはずだった手ごたえや達成感、失敗や経験値というものを奪ってしまう感じがする。 大事なのは「立ちなさい」と強引にうながすのではなく、「あなたが立てること知ってるよ」という空気を創り出すことなんじゃないだろうか。
ハチドリ舎のつくりかた安彦恵里香読み終わった心に残る一節「お店はやりたいようにやったらいいんよ。いろんな人がいろんなことを言うけど、大事なのは自分の直感。それを信じて楽しくやるのが一番よ!」 わたしが場づくりに関して思うのは、「その人がその人らしくそこにいられる状況をいかにしてつくるか?」。何でもかんでもわたしがやってしまうのは、むしろその人が自分で行動し、得られるはずだった手ごたえや達成感、失敗や経験値というものを奪ってしまう感じがする。 大事なのは「立ちなさい」と強引にうながすのではなく、「あなたが立てること知ってるよ」という空気を創り出すことなんじゃないだろうか。 - 2025年12月26日
- 2025年12月26日
 10代のための読書地図本の雑誌編集部気になる
10代のための読書地図本の雑誌編集部気になる - 2025年12月23日
 ヒロのちつじょ佐藤美紗代気になる読みたい
ヒロのちつじょ佐藤美紗代気になる読みたい - 2025年12月23日
 村上春樹語辞典ナカムラクニオ,道前宏子気になる
村上春樹語辞典ナカムラクニオ,道前宏子気になる - 2025年12月23日
 村上春樹作品研究事典村上春樹研究会気になる
村上春樹作品研究事典村上春樹研究会気になる - 2025年12月23日
 村上春樹と仏教平野純気になる読みたい
村上春樹と仏教平野純気になる読みたい - 2025年12月23日
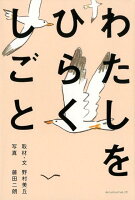 わたしをひらくしごと藤田二朗,野村美丘読みたい
わたしをひらくしごと藤田二朗,野村美丘読みたい
読み込み中...