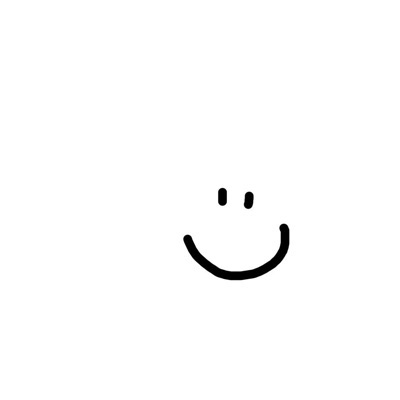人間関係を半分降りる

18件の記録
 はな@hana-hitsuji052026年1月21日読んでる図書館本図書館で借りた人間関係って「しんどい」の対岸に「少しマシかもいけるかも」があって、私はその間に流れる川を延々と往復してる気がする。 今は「しんどい」のターンが来てて、特に好きなものの共通点さえない職場の人間関係で無自覚の女性蔑視発言にどんな態度取れば正解なのかな?と思ったり、何となく仲良しグループでつるんでる人たちの群れに入れなさを感じてそういう人達の方が正しいみたいな空気にぐったりしている。 子どもの頃は自分も仲良しグループがあってそれに属していたんだけどな。 相手と自分の、それぞれ違うポイントでの身勝手さに疲れる。もう少しこうだったら、と思うことをやめたい。 (詳しく知らないくせに)私は性悪説派だと思う。人間はすぐに悪いものに染まりやすいので、より良くなろうと努力しないといけないと思って生きてきた。でも、自分のことを以前よりもより良くなったね!と他者から認めて欲しかったんだろうか? そんなことを考えながら第1章「友人から一歩離れる」を読んでる。今の感じだと一歩の加減が分からずにだいぶ離れてしまいそうだから、一旦落ち着こう。
はな@hana-hitsuji052026年1月21日読んでる図書館本図書館で借りた人間関係って「しんどい」の対岸に「少しマシかもいけるかも」があって、私はその間に流れる川を延々と往復してる気がする。 今は「しんどい」のターンが来てて、特に好きなものの共通点さえない職場の人間関係で無自覚の女性蔑視発言にどんな態度取れば正解なのかな?と思ったり、何となく仲良しグループでつるんでる人たちの群れに入れなさを感じてそういう人達の方が正しいみたいな空気にぐったりしている。 子どもの頃は自分も仲良しグループがあってそれに属していたんだけどな。 相手と自分の、それぞれ違うポイントでの身勝手さに疲れる。もう少しこうだったら、と思うことをやめたい。 (詳しく知らないくせに)私は性悪説派だと思う。人間はすぐに悪いものに染まりやすいので、より良くなろうと努力しないといけないと思って生きてきた。でも、自分のことを以前よりもより良くなったね!と他者から認めて欲しかったんだろうか? そんなことを考えながら第1章「友人から一歩離れる」を読んでる。今の感じだと一歩の加減が分からずにだいぶ離れてしまいそうだから、一旦落ち着こう。






 はな@hana-hitsuji052025年9月4日気になる読みたい少し前にReadsのタイムラインで見かけていて、タイトルを見た時に「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の中に出てきた「半身で生きる」という著者の言葉を思い出して気になっていた。 でも気になっていた本を片っ端からマークすることにその日は少し謎のためらいがあって流れていくままにした気がする。 完全自殺マニュアルの著者じゃんこの人!と再びタイムラインにこの本が現れた時気づき、人も本も謎に年月を超えて巡り会うの流星群みたいだなと思っている。 この本がまた私に近づいてきたような気がして、やっぱり読んでみたいという気持ちが再燃してきた。気になる。
はな@hana-hitsuji052025年9月4日気になる読みたい少し前にReadsのタイムラインで見かけていて、タイトルを見た時に「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の中に出てきた「半身で生きる」という著者の言葉を思い出して気になっていた。 でも気になっていた本を片っ端からマークすることにその日は少し謎のためらいがあって流れていくままにした気がする。 完全自殺マニュアルの著者じゃんこの人!と再びタイムラインにこの本が現れた時気づき、人も本も謎に年月を超えて巡り会うの流星群みたいだなと思っている。 この本がまた私に近づいてきたような気がして、やっぱり読んでみたいという気持ちが再燃してきた。気になる。









 えつこま@e2coma2025年8月22日読み終わった近所の男女共同参画センター図書コーナーにて拾い読み。最近文庫版が出たらしく気になってたが、なかなか読みやすい。まあ感受性が強い人はこういう生きづらさを感じる方が普通なんよな〜。
えつこま@e2coma2025年8月22日読み終わった近所の男女共同参画センター図書コーナーにて拾い読み。最近文庫版が出たらしく気になってたが、なかなか読みやすい。まあ感受性が強い人はこういう生きづらさを感じる方が普通なんよな〜。


 福藻@fuku-fuku2024年10月1日読み終わった社交不安障害、いわゆる対人恐怖症だった著者が、どうしてこの社会は息苦しいのか、どうすれば気楽に生きられるのかを自身の経験から綴る。 対人恐怖症「だった」ということは、現在はその心の病は彼のものではない。フリーライターになり、オフィスや教室のような“人の詰まった場所”に通うのをやめたことが転機だったようだ。その環境の変化で話の合う友だちが格段に見つかりやすくなり、病はいつの間にか消えていたという。 “人の詰まった場所”には、否定的な視線が満ちやすい。「みんな同じ」が強いられるから、人からどう思われるかがまるで最重要事項かのように扱われてしまう。 私も集団にはことごとく馴染めない。他者の言動や容姿をジャッジするモワッとした空気が生まれ始めた小学4年生あたりから、教室の笑い声は全部自分を嘲笑する声に聞こえるようになった。中学は教室にいることもできなくなったし、高校でもなお「ウケる〜!!!」とか「キモッッ!!!」とか聞こえるたびに胃のあたりを握りつぶされるような感覚は治らなかった。 高校時代、教室の喧騒が届かない場所を求めて、図書室に逃げ込んだ。そこで初めて、私の声を、私の声として受け取ってくれる人と出会った。俳優のもたいまさこにそっくりな、口数少ない図書の先生。私の声ってちゃんと聞こえるんだ、と思った。初めての居場所だった。 「ある集団を自分の居場所だと思えるためには、 条件がある。単に人とのつながりがあればいいわけではない。それが、ありのままの自分を受け入れてくれるつながりでなければ、そこは居場所とは呼べない」 (本文より) 著者は、「不適応者の居場所」という集まりをひらいている。何をするかというと、飲食をしながら座って話をする。それだけだ。でも、それだけじゃない。会社や学校や家庭でうまくやれない時の逃げ道になる。ただそこにいてもいい、いるだけでいい、そんな居場所があったなら、どれほど楽になれるだろう。 そんな場所がずっとほしいと思っていた。どこかに、同じような思いでいる人がきっといるんじゃないかとも思っていた。だから読書会をひらいている。高校の図書室のような、普段はかき消されてしまう声の届く場所を目指して「ちいさな声の読書会」と呼んでいる。 ずっと黙って、じっとして、うまくつながれないまま生きてきた不適応者でも、つながりを諦めなくていいはずだ。
福藻@fuku-fuku2024年10月1日読み終わった社交不安障害、いわゆる対人恐怖症だった著者が、どうしてこの社会は息苦しいのか、どうすれば気楽に生きられるのかを自身の経験から綴る。 対人恐怖症「だった」ということは、現在はその心の病は彼のものではない。フリーライターになり、オフィスや教室のような“人の詰まった場所”に通うのをやめたことが転機だったようだ。その環境の変化で話の合う友だちが格段に見つかりやすくなり、病はいつの間にか消えていたという。 “人の詰まった場所”には、否定的な視線が満ちやすい。「みんな同じ」が強いられるから、人からどう思われるかがまるで最重要事項かのように扱われてしまう。 私も集団にはことごとく馴染めない。他者の言動や容姿をジャッジするモワッとした空気が生まれ始めた小学4年生あたりから、教室の笑い声は全部自分を嘲笑する声に聞こえるようになった。中学は教室にいることもできなくなったし、高校でもなお「ウケる〜!!!」とか「キモッッ!!!」とか聞こえるたびに胃のあたりを握りつぶされるような感覚は治らなかった。 高校時代、教室の喧騒が届かない場所を求めて、図書室に逃げ込んだ。そこで初めて、私の声を、私の声として受け取ってくれる人と出会った。俳優のもたいまさこにそっくりな、口数少ない図書の先生。私の声ってちゃんと聞こえるんだ、と思った。初めての居場所だった。 「ある集団を自分の居場所だと思えるためには、 条件がある。単に人とのつながりがあればいいわけではない。それが、ありのままの自分を受け入れてくれるつながりでなければ、そこは居場所とは呼べない」 (本文より) 著者は、「不適応者の居場所」という集まりをひらいている。何をするかというと、飲食をしながら座って話をする。それだけだ。でも、それだけじゃない。会社や学校や家庭でうまくやれない時の逃げ道になる。ただそこにいてもいい、いるだけでいい、そんな居場所があったなら、どれほど楽になれるだろう。 そんな場所がずっとほしいと思っていた。どこかに、同じような思いでいる人がきっといるんじゃないかとも思っていた。だから読書会をひらいている。高校の図書室のような、普段はかき消されてしまう声の届く場所を目指して「ちいさな声の読書会」と呼んでいる。 ずっと黙って、じっとして、うまくつながれないまま生きてきた不適応者でも、つながりを諦めなくていいはずだ。



 さや@saya_shoten2023年7月1日かつて読んだ以前から気になっていて「そうだ!今こそ読もう!」と思って読み始めたら、スルスルと言葉が入ってきた。素麺の様なさっぱりツルツル感。 私は割と0か100かしかないなーと改めて思ったり。 「しないことリスト/pha」にも通じる50%位のスタンスでええんやで~って感じがタイムリーで良かった。 あと、リアルも大事に。グサッ。
さや@saya_shoten2023年7月1日かつて読んだ以前から気になっていて「そうだ!今こそ読もう!」と思って読み始めたら、スルスルと言葉が入ってきた。素麺の様なさっぱりツルツル感。 私は割と0か100かしかないなーと改めて思ったり。 「しないことリスト/pha」にも通じる50%位のスタンスでええんやで~って感じがタイムリーで良かった。 あと、リアルも大事に。グサッ。