「社会」を扱う新たなモード

20件の記録
 socotsu@shelf_soya2025年10月5日読み終わった心に残る一節社会に所属して、その構造に関わっている責任に自覚的になり、何をできるか考え実行すること。 "社会構造とは、他者との関係によって位置づけられた個人の行為の集積である。個人が許容された規則と規範の範囲内で自らの目的や関心を追求しようと行為したとしても、その結果、広範な行為の選択肢が与えられる人もいれば、行為の選択肢を狭められる人もいる。このような構造的プロセスに注意を向けるならば、私たちの行為は、限られた選択肢しか持たない立場の人々を窮地に陥れながら、構造的不正義の生産・再生産に絶えず加担していることになる。したがって、たとえ間接的であれ、不正義をもたらすプロセスに関与している以上、私たちは個人の行為の集積としての構造的不正義に対する責任を分有している。構造的不正義への責任があるということは、不正義をもたらす現在の構造的プロセスを変化させる責任を負うことを意味している。これがヤングの言う「社会的つながりモデル」である。" p.223
socotsu@shelf_soya2025年10月5日読み終わった心に残る一節社会に所属して、その構造に関わっている責任に自覚的になり、何をできるか考え実行すること。 "社会構造とは、他者との関係によって位置づけられた個人の行為の集積である。個人が許容された規則と規範の範囲内で自らの目的や関心を追求しようと行為したとしても、その結果、広範な行為の選択肢が与えられる人もいれば、行為の選択肢を狭められる人もいる。このような構造的プロセスに注意を向けるならば、私たちの行為は、限られた選択肢しか持たない立場の人々を窮地に陥れながら、構造的不正義の生産・再生産に絶えず加担していることになる。したがって、たとえ間接的であれ、不正義をもたらすプロセスに関与している以上、私たちは個人の行為の集積としての構造的不正義に対する責任を分有している。構造的不正義への責任があるということは、不正義をもたらす現在の構造的プロセスを変化させる責任を負うことを意味している。これがヤングの言う「社会的つながりモデル」である。" p.223

 socotsu@shelf_soya2025年10月5日読書メモ「社会の側に障害がある」という考え方、「社会モデル」は知ったときから本当にその通りだと思っていたし、自分の身の回りやニュース等で体験・見聞きする具体的な出来事についても浮かぶものがあるが、実際にはここでいう「社会」を「障害が発生するメカニズムが社会にあること 」「障害の解消に向けてこの社会にはどのような手段があるか」そして「発生した障害を解消する責任は社会に帰属するということ」という3つに分けて考える必要があることを知った。 当事者研究、「心のバリアフリー」の推進、性の権利、合理的配慮等、各章それぞれ扱うトピックに細かく深く切り込んでいくため、非常に読み応えがある、というときれいな表現だけれど、自分が見ないようにしていた特権性を突きつけられて苦しくなる瞬間も多々あった。「心のバリアフリー」の章でも取り上げられているように、やさしさ、思いやりでの解決は推奨されないが、それよりもこの社会に帰属するがゆえの応答責任を重たく感じている。
socotsu@shelf_soya2025年10月5日読書メモ「社会の側に障害がある」という考え方、「社会モデル」は知ったときから本当にその通りだと思っていたし、自分の身の回りやニュース等で体験・見聞きする具体的な出来事についても浮かぶものがあるが、実際にはここでいう「社会」を「障害が発生するメカニズムが社会にあること 」「障害の解消に向けてこの社会にはどのような手段があるか」そして「発生した障害を解消する責任は社会に帰属するということ」という3つに分けて考える必要があることを知った。 当事者研究、「心のバリアフリー」の推進、性の権利、合理的配慮等、各章それぞれ扱うトピックに細かく深く切り込んでいくため、非常に読み応えがある、というときれいな表現だけれど、自分が見ないようにしていた特権性を突きつけられて苦しくなる瞬間も多々あった。「心のバリアフリー」の章でも取り上げられているように、やさしさ、思いやりでの解決は推奨されないが、それよりもこの社会に帰属するがゆえの応答責任を重たく感じている。





 socotsu@shelf_soya2025年10月1日読んでる社会モデルは障害の「発生メカニズムの社会性」を発見することにあるという主張に貫かれている本。 当事者研究に関する論考を取り上げ、個人の特性としての障害、社会と接する際に発生する障害、と2段階で障害を切り分ける考え方について、個人と社会はそんなに素朴に切り分けられるのか?と切り込む第一章から鷲掴みにされている。
socotsu@shelf_soya2025年10月1日読んでる社会モデルは障害の「発生メカニズムの社会性」を発見することにあるという主張に貫かれている本。 当事者研究に関する論考を取り上げ、個人の特性としての障害、社会と接する際に発生する障害、と2段階で障害を切り分ける考え方について、個人と社会はそんなに素朴に切り分けられるのか?と切り込む第一章から鷲掴みにされている。

 socotsu@shelf_soya2025年9月30日心に残る一節"インペアメントの状態が変動しやすい障害者は、たとえ一日の間でさえ自分の身体がどうなるのか予測がつかず、それと連動して意思決定も困難となる。また、精神障害や発達障害の当事者など、困りごとを言葉にできず、自分のニーズを主張しようにもその手立てがないという人々も存在する。このように、「意思決定することこそが自立である」という考え方はそもそも意思決定の基盤となるものが不確かな人々や困りごとを表現する言葉自体を持たない人々、すなわち「自分の障害の特徴やニーズを記述(可視化)」(熊谷 2020:20)することのできない当事者を置き去りにしてしまっている。" p.34
socotsu@shelf_soya2025年9月30日心に残る一節"インペアメントの状態が変動しやすい障害者は、たとえ一日の間でさえ自分の身体がどうなるのか予測がつかず、それと連動して意思決定も困難となる。また、精神障害や発達障害の当事者など、困りごとを言葉にできず、自分のニーズを主張しようにもその手立てがないという人々も存在する。このように、「意思決定することこそが自立である」という考え方はそもそも意思決定の基盤となるものが不確かな人々や困りごとを表現する言葉自体を持たない人々、すなわち「自分の障害の特徴やニーズを記述(可視化)」(熊谷 2020:20)することのできない当事者を置き去りにしてしまっている。" p.34
 ゆう@suisuiu2025年1月26日やっと読み通せた。半分くらいまではメモしながらじゃないとよく意味がわからなかった。「障害」は社会がつくり出しているものだという視座を徹底的に深掘りされる。熊谷晋一郎の当事者研究運動を批判的に論じるところからはじまるので驚いた。この驚き自体に内省しないといけないと気付かされる。 「心のバリアフリー」の普及活動も各種NPOや大学等での支援活動も、「社会側が変わらないといけない」と謳いつつ、結局、障害のある「個人」に責任を持たせようとしてない?「個人」が変われば「社会」と交わることができるってなってない?とがしがしつっこまれる。ううううと胸が痛い。でも、とはいえどうしたらいいんだろうというのは残る。残るが、でもその戸惑いこそがこの本で与えたかった刺激なのかもしれない。いろんな障害やマジョリティとの壁に挑むいろんな実践者たちを立ち止まらせる効能みたいなものがある。
ゆう@suisuiu2025年1月26日やっと読み通せた。半分くらいまではメモしながらじゃないとよく意味がわからなかった。「障害」は社会がつくり出しているものだという視座を徹底的に深掘りされる。熊谷晋一郎の当事者研究運動を批判的に論じるところからはじまるので驚いた。この驚き自体に内省しないといけないと気付かされる。 「心のバリアフリー」の普及活動も各種NPOや大学等での支援活動も、「社会側が変わらないといけない」と謳いつつ、結局、障害のある「個人」に責任を持たせようとしてない?「個人」が変われば「社会」と交わることができるってなってない?とがしがしつっこまれる。ううううと胸が痛い。でも、とはいえどうしたらいいんだろうというのは残る。残るが、でもその戸惑いこそがこの本で与えたかった刺激なのかもしれない。いろんな障害やマジョリティとの壁に挑むいろんな実践者たちを立ち止まらせる効能みたいなものがある。









 ゆう@suisuiu2025年1月23日まだ読んでる@ 電車週二回出勤することになり、よし電車で読書の時間つくれると少し楽しみにしていたのに平日朝の京王線はそんなこと許してくれなくて、「またまた〜」と思っていたがほんと肋骨圧迫されるくらいやばい。本なんて開こうものなら。でもたま〜にほんとたま〜に開けて、昨日はちょっと読めた。最前か最後尾の号車に入ることがポイントかも。
ゆう@suisuiu2025年1月23日まだ読んでる@ 電車週二回出勤することになり、よし電車で読書の時間つくれると少し楽しみにしていたのに平日朝の京王線はそんなこと許してくれなくて、「またまた〜」と思っていたがほんと肋骨圧迫されるくらいやばい。本なんて開こうものなら。でもたま〜にほんとたま〜に開けて、昨日はちょっと読めた。最前か最後尾の号車に入ることがポイントかも。





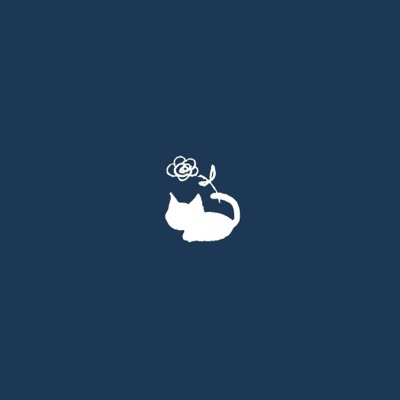

 ゆう@suisuiu2024年12月30日読んでる@ 自宅共生社会などに関するメッセージやステートメントでよく見かける・書いてもしまう「すべての人」や「あらゆる人」が「ひとりひとりの力を発揮して」的な内容への違和感や気持ち悪さがよく解明されていく、が、ではどうしたらいいのだろうという疑問は残る。まだまだ半分。
ゆう@suisuiu2024年12月30日読んでる@ 自宅共生社会などに関するメッセージやステートメントでよく見かける・書いてもしまう「すべての人」や「あらゆる人」が「ひとりひとりの力を発揮して」的な内容への違和感や気持ち悪さがよく解明されていく、が、ではどうしたらいいのだろうという疑問は残る。まだまだ半分。













