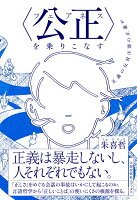ゆう
@suisuiu
- 2026年1月24日
 統合失調症の一族ロバート・コルカー,柴田裕之読みたい
統合失調症の一族ロバート・コルカー,柴田裕之読みたい - 2026年1月5日
 人といることの、すさまじさとすばらしさきくちゆみこ読み終わった組織づくりやマネジメントなるものでむんむん悩んだ昨年、いろいろあったけれど、年末年始にたっぷり休んだリフレッシュした頭で捉え直すと、つらいことばかりではなく、いろんなすばらしさもあった。この経験がなければ知らなかったさまざまな人間活動。そんなすばらしさに気付かせてくれるのも人との対話がきっかけだった。人といることは本当にすさまじい!(この言葉選びがちょうどいい)けれど、すばらしさだってちゃんとある。
人といることの、すさまじさとすばらしさきくちゆみこ読み終わった組織づくりやマネジメントなるものでむんむん悩んだ昨年、いろいろあったけれど、年末年始にたっぷり休んだリフレッシュした頭で捉え直すと、つらいことばかりではなく、いろんなすばらしさもあった。この経験がなければ知らなかったさまざまな人間活動。そんなすばらしさに気付かせてくれるのも人との対話がきっかけだった。人といることは本当にすさまじい!(この言葉選びがちょうどいい)けれど、すばらしさだってちゃんとある。 - 2026年1月4日
- 2026年1月4日
- 2026年1月2日
- 2025年12月31日
 違和感のゆくえ垣花つや子,椋本湧也,認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ読み終わった18人の違和感のゆくえが綴られる。 ところでさっき、お正月飾りや仏花の束でいっぱいの地元の花屋さんの前を通りがかった。店頭に「正月生花 希望」という紅白の立派なポップがあり、唯一の品切れ商品だったこともあり目を引いた。あかるくて良い名前、お正月っぽいね〜希望はいいよねと足を止めて写真を撮り、再び歩き出すと店内からオーナーと思しき方が出てきてしっかりと注意された。「ひとこと言ってからにしてください」と伝えていただに、ほんとうにその通りだと思った。「地元の」お花屋さん=ゆるそうと勝手に無意識に判断していた愚かさ、甘えと油断、お花そのものではなく商品名を消費的に消費した浅はかな行動に反省した。焦ってしまい、ちゃんと謝れたかどうかもわからない。 こういうことは日常的に起こしてしまっているんだと思う、という改めての自覚。今回のことに限らず、内面化された軽視、蔑視、弱さ、保身、ひねくれ、劣等感、照れ、そういうものから生じるあれやこれやをないものにしないこと。そういう意味で、もっと私は私に出会いたい。これはそういうこと(?)が書かれた本でもあると思う。年が明けたらそのお花屋さんで花を買って、その時にまたちゃんと謝ろう。
違和感のゆくえ垣花つや子,椋本湧也,認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ読み終わった18人の違和感のゆくえが綴られる。 ところでさっき、お正月飾りや仏花の束でいっぱいの地元の花屋さんの前を通りがかった。店頭に「正月生花 希望」という紅白の立派なポップがあり、唯一の品切れ商品だったこともあり目を引いた。あかるくて良い名前、お正月っぽいね〜希望はいいよねと足を止めて写真を撮り、再び歩き出すと店内からオーナーと思しき方が出てきてしっかりと注意された。「ひとこと言ってからにしてください」と伝えていただに、ほんとうにその通りだと思った。「地元の」お花屋さん=ゆるそうと勝手に無意識に判断していた愚かさ、甘えと油断、お花そのものではなく商品名を消費的に消費した浅はかな行動に反省した。焦ってしまい、ちゃんと謝れたかどうかもわからない。 こういうことは日常的に起こしてしまっているんだと思う、という改めての自覚。今回のことに限らず、内面化された軽視、蔑視、弱さ、保身、ひねくれ、劣等感、照れ、そういうものから生じるあれやこれやをないものにしないこと。そういう意味で、もっと私は私に出会いたい。これはそういうこと(?)が書かれた本でもあると思う。年が明けたらそのお花屋さんで花を買って、その時にまたちゃんと謝ろう。 - 2025年12月21日
 踊るのは新しい体太田充胤読み始めたメタバースの居場所をアバターで駆け回り、チャットやスタンプなどテキストや記号によるコミュニケーションを駆使し、ゲーム実況などで人とつながり自分を表現するこどもたちは、新しい居方を次々と見せてくれる。その様子はこの本に書かれているように、アバターではあるが「魂」が宿っているとすらほんとうは感じている、けどそう思うことにどこか躊躇もあった。でも、オンラインやゲームのカルチャーに馴染みのないわたしには見えない解像度でお互いの個性を感じ取っているのは確かなように見える。この現象の面白さをもっと知りたい。という自由研究読書。
踊るのは新しい体太田充胤読み始めたメタバースの居場所をアバターで駆け回り、チャットやスタンプなどテキストや記号によるコミュニケーションを駆使し、ゲーム実況などで人とつながり自分を表現するこどもたちは、新しい居方を次々と見せてくれる。その様子はこの本に書かれているように、アバターではあるが「魂」が宿っているとすらほんとうは感じている、けどそう思うことにどこか躊躇もあった。でも、オンラインやゲームのカルチャーに馴染みのないわたしには見えない解像度でお互いの個性を感じ取っているのは確かなように見える。この現象の面白さをもっと知りたい。という自由研究読書。 - 2025年12月20日
 日本で一番美しい県は岩手県である三浦英之読みたいこれはこれは岩手育ちの民として気になる。目次だけでも興奮する。それにしても一番とはまた思い切った表現で、最上級とかとびきりとか、いろんな表現の候補はきっと他にも出たはずで、にも関わらずそんな順位の概念持ち出しちゃっていいんですかと、誇り、照れ、不安、遠慮、期待への責任みたいなものが混在した気持ちが謎に湧く。こういう岩手県民の自信のなさみたいなもののカウンターというか、まあまあ、わかるけど、言い切っちゃいなYO!この波に乗っちゃいなYO!というメッセージなのかもしれない。気になる。
日本で一番美しい県は岩手県である三浦英之読みたいこれはこれは岩手育ちの民として気になる。目次だけでも興奮する。それにしても一番とはまた思い切った表現で、最上級とかとびきりとか、いろんな表現の候補はきっと他にも出たはずで、にも関わらずそんな順位の概念持ち出しちゃっていいんですかと、誇り、照れ、不安、遠慮、期待への責任みたいなものが混在した気持ちが謎に湧く。こういう岩手県民の自信のなさみたいなもののカウンターというか、まあまあ、わかるけど、言い切っちゃいなYO!この波に乗っちゃいなYO!というメッセージなのかもしれない。気になる。 - 2025年12月4日
 帰れない探偵柴崎友香読み終わっちゃう先月夫が「小説が必要だ」みたいなことをつぶやいて、そうだその通りだと思って、その日のうちにくまざわで買ったのだった。寝る前にのろのろのろりと読んでいるがそろそろ読み終わっちゃう。帰れなくなるのもいいかもしれない。
帰れない探偵柴崎友香読み終わっちゃう先月夫が「小説が必要だ」みたいなことをつぶやいて、そうだその通りだと思って、その日のうちにくまざわで買ったのだった。寝る前にのろのろのろりと読んでいるがそろそろ読み終わっちゃう。帰れなくなるのもいいかもしれない。 - 2025年12月4日
 恋とか夢とかてんてんてん 3.世良田波波読み終わった好きな人がいること、好きなことがあること。それでもまたカイちゃんは絵を描いた。捨てずに閉まったことにじんとする。河川敷で食べるたこ焼きとどこのメーカーかわからないソーダはキラキラしていた。大阪の土地勘はないけれど、この年頃のこの時期のこの感じだったら、東京なら、岩手なら、と重ねて読んでいる。
恋とか夢とかてんてんてん 3.世良田波波読み終わった好きな人がいること、好きなことがあること。それでもまたカイちゃんは絵を描いた。捨てずに閉まったことにじんとする。河川敷で食べるたこ焼きとどこのメーカーかわからないソーダはキラキラしていた。大阪の土地勘はないけれど、この年頃のこの時期のこの感じだったら、東京なら、岩手なら、と重ねて読んでいる。 - 2025年11月2日
 近代美学入門井奥陽子読みたい
近代美学入門井奥陽子読みたい - 2025年10月5日
 ウズベキスタン日記高山なおみふと思い出した再読中北欧暮らしの道具店のYouTubeで高山なおみが動いて喋っている様子を見て、ふと思い出した。むかしむかし22歳くらいの時に読んだ『帰ったら、お腹がすいてもいいようにと思ったのだ』がわたしの中で神がかりすぎ、逆に日々ごはんはまったく読めなかった。周りで読む人がちらほらいた、ああいいよねえ高山なおみはとてきとうに合わせていた。読むものか!とすら思っていた。若かったし恥ずかしい、けどその時はその時で大事な距離だったんだろうなあと思う。この本はその若さをまだ引きずっていた頃、発売と同時に買ったんだった気がする。 この歳になって、みたいなことが夏から増えた。皮剥け、脱皮。今の年齢自体にどうこうではなく、何かしらの段階を踏んでる、はーいそろそろアップデートですよ〜と運営から言われてるような気分なのかも。今むしろ読んでみたくなってる日々ごはん。
ウズベキスタン日記高山なおみふと思い出した再読中北欧暮らしの道具店のYouTubeで高山なおみが動いて喋っている様子を見て、ふと思い出した。むかしむかし22歳くらいの時に読んだ『帰ったら、お腹がすいてもいいようにと思ったのだ』がわたしの中で神がかりすぎ、逆に日々ごはんはまったく読めなかった。周りで読む人がちらほらいた、ああいいよねえ高山なおみはとてきとうに合わせていた。読むものか!とすら思っていた。若かったし恥ずかしい、けどその時はその時で大事な距離だったんだろうなあと思う。この本はその若さをまだ引きずっていた頃、発売と同時に買ったんだった気がする。 この歳になって、みたいなことが夏から増えた。皮剥け、脱皮。今の年齢自体にどうこうではなく、何かしらの段階を踏んでる、はーいそろそろアップデートですよ〜と運営から言われてるような気分なのかも。今むしろ読んでみたくなってる日々ごはん。 - 2025年9月27日
 エイヴォン記庄野潤三まだ読んでる寝る前にちょっと読むふがふがアドレナリンが出て眠りにくかったけど孫娘フーちゃんのおかげですやすや。おばあちゃんからもらった新しいサンダル履いて、鏡のある部屋に走ってって、フーちゃんごきげん。
エイヴォン記庄野潤三まだ読んでる寝る前にちょっと読むふがふがアドレナリンが出て眠りにくかったけど孫娘フーちゃんのおかげですやすや。おばあちゃんからもらった新しいサンダル履いて、鏡のある部屋に走ってって、フーちゃんごきげん。 - 2025年9月27日
- 2025年9月22日
 ボローニャ紀行井上ひさし読んでる通勤読書東京、いきなり秋。アメリカからボローニャ。大学やまちづくりや法律や市民協働、パルチザン、ホームレス支援など、町の根底に流れる自治の文化について。井上ひさしがボローニャに到着した当日に100万円入った鞄をすられててかわいそう。
ボローニャ紀行井上ひさし読んでる通勤読書東京、いきなり秋。アメリカからボローニャ。大学やまちづくりや法律や市民協働、パルチザン、ホームレス支援など、町の根底に流れる自治の文化について。井上ひさしがボローニャに到着した当日に100万円入った鞄をすられててかわいそう。 - 2025年9月21日
 Shrink〜精神科医ヨワイ〜 16七海仁,月子読み終わった統合失調症。訪問看護。精神科作業療法。父親の受容。母子分離。世界中、ここに出てくる先生たちばっかりになったらいいのに。次の17巻の発売は2026年1月で、それっていつなんだろう。漫画の次巻発売予定日ってその時見ると途方に暮れるけど、いざ発売されると忘れてる
Shrink〜精神科医ヨワイ〜 16七海仁,月子読み終わった統合失調症。訪問看護。精神科作業療法。父親の受容。母子分離。世界中、ここに出てくる先生たちばっかりになったらいいのに。次の17巻の発売は2026年1月で、それっていつなんだろう。漫画の次巻発売予定日ってその時見ると途方に暮れるけど、いざ発売されると忘れてる - 2025年9月21日
 アメリカ紀行千葉雅也読み終わった生活のセットアップ。ダンキンドーナツなど近所のカフェの領土化。薄くて酸味のあるコーヒー。シンプルでパワフルなアメリカ。日本食レストランで飲むビール。あらゆるものが包装された日本。Iもyouもないのに、個々の振る舞いが結果的に重視される日本。 今読むと、千葉雅也が障害や自閉症の視点をつなげながら哲学の考察を進めている様子が気になる。「社会の障害」の中で、それを前提としてより良く生きるとはどういうことなんだろう。
アメリカ紀行千葉雅也読み終わった生活のセットアップ。ダンキンドーナツなど近所のカフェの領土化。薄くて酸味のあるコーヒー。シンプルでパワフルなアメリカ。日本食レストランで飲むビール。あらゆるものが包装された日本。Iもyouもないのに、個々の振る舞いが結果的に重視される日本。 今読むと、千葉雅也が障害や自閉症の視点をつなげながら哲学の考察を進めている様子が気になる。「社会の障害」の中で、それを前提としてより良く生きるとはどういうことなんだろう。 - 2025年9月18日
 アメリカ紀行千葉雅也また読んでる通勤読書最近の通勤はずっとポッドキャストだったけどイヤホンがどっかいったので本。いつもより二本遅い電車になって人が満杯になったけど、どうにか言葉にしがみつく。千葉雅也が異国での生活を再構築している。実在の人間による紀行文はやっぱりなまなましくて、小説より小説みたいだ。VR小説。
アメリカ紀行千葉雅也また読んでる通勤読書最近の通勤はずっとポッドキャストだったけどイヤホンがどっかいったので本。いつもより二本遅い電車になって人が満杯になったけど、どうにか言葉にしがみつく。千葉雅也が異国での生活を再構築している。実在の人間による紀行文はやっぱりなまなましくて、小説より小説みたいだ。VR小説。 - 2025年9月14日
 アメリカ紀行千葉雅也ちょっと開いたまた読んでるエイヴォン記を読んでいたら、それを初めて読んでいた当時に読んでいたアメリカ紀行を思い出したので本棚から引っ張り出した。固有の喜びと享楽。生活の再セットアップ。今日はやたら拾い読みと再読の日。
アメリカ紀行千葉雅也ちょっと開いたまた読んでるエイヴォン記を読んでいたら、それを初めて読んでいた当時に読んでいたアメリカ紀行を思い出したので本棚から引っ張り出した。固有の喜びと享楽。生活の再セットアップ。今日はやたら拾い読みと再読の日。 - 2025年9月14日
読み込み中...