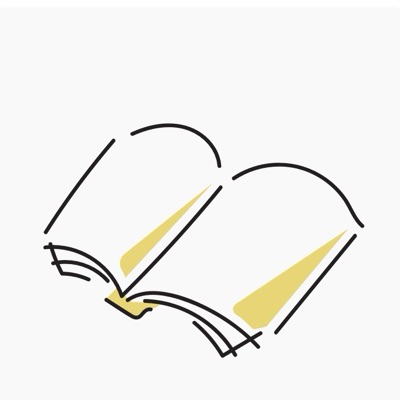
徒然
@La_Souffrance
1900年1月1日

侍女の物語
マーガレット・アトウッド
読み終わった
めっっちゃ面白かった……あまりにも真に迫っていて「面白い」と言って良いのか迷うほど。
心のうちの多彩な比喩と、外の閉塞感の対比が鮮烈で、一文一文を味わいたいのに結局駆け抜けてしまった。
内面を守ろうとする心と、外部の見えない力に縛られる構図が強烈に響く。
"彼らに捕まえられないほど深く自分の内部に入り込むことは可能なのだ。"
という文章がもういっそ痛々しかった。
ジャニーンの出産シーンで主人公含め周りの女性たちが一心同体になるところは、映画『ミッドサマー』でみんなで一緒に笑ったり悲しんだりするところを思い出した。
以下、『侍女の物語』『1984年』のネタバレあります。
作中にはこちらに語りかけるような文もあり、過去の手記を拾い上げたような読書体験。そしてラスト、この手記をギレアデ共和国の証言記録として歴史家たちが紹介する場面で締めるのも鮮やかだった。
ディストピアものだとジョージ・オーウェルの『1984年』も名作。
両作品の共通点は、国家や体制が個人を徹底的に管理し、もはや駒のようになるところだと思う。
しかし、『1984年』が、行動の監視や言葉の制御で思考をも支配しているとしたら、
『侍女の物語』は、制度化された日常や宗教的正当化で人を絡め取っていく。
ウィンストンが最後には心まで支配されるのに対し、オブフレッドは語りや記憶を手放さず、手記として未来に残していく。その違いがとても印象的だった。



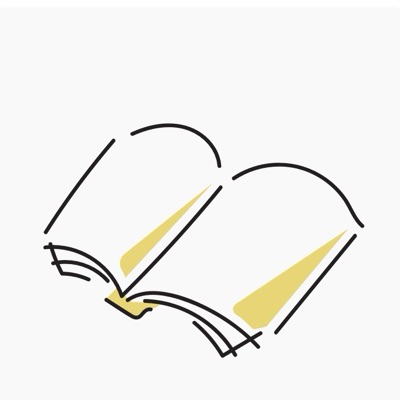


nornacum
@nornacum
フォローバックありがとうです!
わたしもアトウッドの本でいちばんショックを受けたのはやっぱり『侍女の物語』で、とくに最近のアメリカの動向を見ていると、作家の想像力はほとんど予言のようで怖くなります。なおかつ、オルタナ右翼のなかには、『侍女の物語』の世界観とギレアデ共和国の体制をそのまま真に受けて、この作品をこれから実現すべき世界を表現した書、「聖典」としているグループもあるようです。怖い世の中になってきたと思います。文学はつねにアクチュアルであるということを痛感させられますね。
これからもどうぞよろしくです!
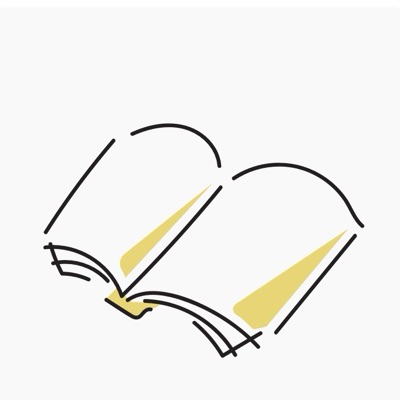
徒然
@La_Souffrance
こちらこそフォローありがとうございます!
『侍女の物語』は、ただのディストピア小説というより現実の隣にある可能性を描いているからこそ、なおさら怖さを感じますね……。一部の人たちが理想の社会像のように受け止めてしまうというのも、作品の強烈さを物語っている気がします。文学の力を実感すると同時に、背筋が寒くなる思いです。改めて、私たちに現実を見つめ直すきっかけを与えてくれる作品だと感じました。
これからもよろしくです!

