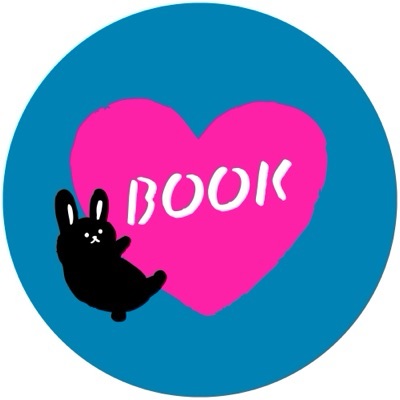咒(まじない)の脳科学

8件の記録
 しまりす@alice_soror2025年5月14日読み終わった美の基準、時代による変遷 アメリカで最も美しい女性 →19世紀後半から20世紀初頭 歌手で女優のリリアン・ラッセル →2014年 ルピタ・ニョンゴ 英、米、カナダにおける刑務所整形プログラム 外見の変化とその後の行動変化のあいだには明らかな相関が認められた 虚像の姿が現実を変える オンライン上、仮想空間のアバター→実際の能力の変化 リーダー選びも外見的魅力度が基準 男性の顔の魅力度と男性ホルモンとの関連 男性ホルモンによって支配的資質があると評価されるタイプの顔→実際支配的 容姿のよい人は得だと言い切れる検証結果の数々 失敗は許され、成功はより賞賛される 悪意が露出すれば美人は不美人よりさらに恨まれる→関心の強さ故? 教師、アーティストなども同じ 脳は人間の価値を判断できない 平時と有事、敵味方での生命の価値が変わってしまうことを見れば、我々が生命の価値を認知できないことは明らか 人間は他人と比べないと自分の価値を決められない→ダニング=クルーガー効果 見た目に現れない価値を評価する能力こそが知性である 女性の成功について 18世紀、ドイツ、哲学者、イマヌエル・カント 学問の研究や思索で女性が成功したとしても、性に相応しい美点を破壊する 冷ややかな尊敬を受けるが異性に対しての絶大な魅力を失う 人類学者、フィッシャー 女性の経済的自立と離婚率には相関がある 17世紀フランスの宮廷人の姿を書き綴った作家 「13歳から22歳までは女、それも美しい娘になり、その後は男になりたい」 見た目で本当に得をするのは男か女か 文化圏の9割以上が男が女を容姿で選ぶ(同性愛者でも同じ) 美人は「わきまえて」いることが華 男性の成功は容姿の良さと相関関係だが、女性の成功は事務職なら相関あり、管理職なら逆効果となる→ガラスの天井 女性は女性を無意識のうちに引き下ろす 容姿の良い男性は悪い男性より幸福度は「わずかに」高く 容姿の良い女性は悪い女性よりも幸福に感じることもあるが、より不幸も強く感じる ーーーー 社会がかける咒 「公正世界仮説」「公正世界誤謬」の認知バイアス 因果応報と類似の概念、人間の行いは必ず将来の報いの原因となる 1960年代、社会心理学者、ラーナー提唱 →真実がどうかは問題でなく、どれだけ多くの人が信じているかという点が重要 →ビッグファイブで協調性と外交性が高いタイプがより信じやすい カルフーンのユートピア実験 過密化がもたらした「社会的崩壊」 社会的ストレスや競争の増加が、繁殖力の低下や攻撃的行動の増加に寄与する可能性 →現代問題の少子化に関連づけられよう ーーーー 咒がかなうということ 人間以外にも咒の行動が判明 「生まれ直し」を求めて→円環運動ということ? 人にとって鏡とは、客体化して自らを認識するツール 自他の命のつながりと咒 自他の境界は曖昧、影響しあうもの、個でありながら個ではない にもかかわらず社会的報酬や社会関係資本は自他の境界をはっきりとつけるもの 世界が「生まれ直し」(擬似円環運動?)を続けることを感じられるのは限られた人間に許される能力だろうが、より自分自身の価値を感じられる助けになるようにという咒を著者はこの本にこめる
しまりす@alice_soror2025年5月14日読み終わった美の基準、時代による変遷 アメリカで最も美しい女性 →19世紀後半から20世紀初頭 歌手で女優のリリアン・ラッセル →2014年 ルピタ・ニョンゴ 英、米、カナダにおける刑務所整形プログラム 外見の変化とその後の行動変化のあいだには明らかな相関が認められた 虚像の姿が現実を変える オンライン上、仮想空間のアバター→実際の能力の変化 リーダー選びも外見的魅力度が基準 男性の顔の魅力度と男性ホルモンとの関連 男性ホルモンによって支配的資質があると評価されるタイプの顔→実際支配的 容姿のよい人は得だと言い切れる検証結果の数々 失敗は許され、成功はより賞賛される 悪意が露出すれば美人は不美人よりさらに恨まれる→関心の強さ故? 教師、アーティストなども同じ 脳は人間の価値を判断できない 平時と有事、敵味方での生命の価値が変わってしまうことを見れば、我々が生命の価値を認知できないことは明らか 人間は他人と比べないと自分の価値を決められない→ダニング=クルーガー効果 見た目に現れない価値を評価する能力こそが知性である 女性の成功について 18世紀、ドイツ、哲学者、イマヌエル・カント 学問の研究や思索で女性が成功したとしても、性に相応しい美点を破壊する 冷ややかな尊敬を受けるが異性に対しての絶大な魅力を失う 人類学者、フィッシャー 女性の経済的自立と離婚率には相関がある 17世紀フランスの宮廷人の姿を書き綴った作家 「13歳から22歳までは女、それも美しい娘になり、その後は男になりたい」 見た目で本当に得をするのは男か女か 文化圏の9割以上が男が女を容姿で選ぶ(同性愛者でも同じ) 美人は「わきまえて」いることが華 男性の成功は容姿の良さと相関関係だが、女性の成功は事務職なら相関あり、管理職なら逆効果となる→ガラスの天井 女性は女性を無意識のうちに引き下ろす 容姿の良い男性は悪い男性より幸福度は「わずかに」高く 容姿の良い女性は悪い女性よりも幸福に感じることもあるが、より不幸も強く感じる ーーーー 社会がかける咒 「公正世界仮説」「公正世界誤謬」の認知バイアス 因果応報と類似の概念、人間の行いは必ず将来の報いの原因となる 1960年代、社会心理学者、ラーナー提唱 →真実がどうかは問題でなく、どれだけ多くの人が信じているかという点が重要 →ビッグファイブで協調性と外交性が高いタイプがより信じやすい カルフーンのユートピア実験 過密化がもたらした「社会的崩壊」 社会的ストレスや競争の増加が、繁殖力の低下や攻撃的行動の増加に寄与する可能性 →現代問題の少子化に関連づけられよう ーーーー 咒がかなうということ 人間以外にも咒の行動が判明 「生まれ直し」を求めて→円環運動ということ? 人にとって鏡とは、客体化して自らを認識するツール 自他の命のつながりと咒 自他の境界は曖昧、影響しあうもの、個でありながら個ではない にもかかわらず社会的報酬や社会関係資本は自他の境界をはっきりとつけるもの 世界が「生まれ直し」(擬似円環運動?)を続けることを感じられるのは限られた人間に許される能力だろうが、より自分自身の価値を感じられる助けになるようにという咒を著者はこの本にこめる
 しまりす@alice_soror2025年5月13日読んでる外見の魅力で「能力」まで判断する社会 ただし魅力の基準は時代や地域によって異なる 虚構の姿が現実を変える →プロテウス効果……仮想的な姿を適用することで現実にも影響が現れる心理学的な現象 人は容姿の美醜に判断を左右されるという事実 脳は人間の価値を判断できない 他人と比べないと自分の価値を決められない →見た目に現れない価値を評価できる能力が知性 脳の性差による相手選びの違い 男性は相手を選ぶ時、脳の島皮質の視覚関連領域が活性化しており、ほとんど見た目以外の要素は処理されていない 女性は相手を選ぶ時、視覚関連領域はあまり使われておらず、前帯状皮質が活性化しており、相手の言動を記憶と照合して違和感がないかどうかを精査するプロセスが行われている(容姿より言動を重視)
しまりす@alice_soror2025年5月13日読んでる外見の魅力で「能力」まで判断する社会 ただし魅力の基準は時代や地域によって異なる 虚構の姿が現実を変える →プロテウス効果……仮想的な姿を適用することで現実にも影響が現れる心理学的な現象 人は容姿の美醜に判断を左右されるという事実 脳は人間の価値を判断できない 他人と比べないと自分の価値を決められない →見た目に現れない価値を評価できる能力が知性 脳の性差による相手選びの違い 男性は相手を選ぶ時、脳の島皮質の視覚関連領域が活性化しており、ほとんど見た目以外の要素は処理されていない 女性は相手を選ぶ時、視覚関連領域はあまり使われておらず、前帯状皮質が活性化しており、相手の言動を記憶と照合して違和感がないかどうかを精査するプロセスが行われている(容姿より言動を重視)
 しまりす@alice_soror2025年4月3日読んでる自分で自分の発した言葉に驚かされることがある →意味理解に使われる脳機能部位と、音声言語を発するための脳機能部位が異なっていて。おたがいに連絡をとるには遠い距離にあるため 発した言葉が無意識のレイヤーに影響する 真言、陀羅尼、アル=クルアーン「読誦されるもの」などは読まれる音を大事にし、美しい響きを持つ 認知科学的には美しい音の連なりやくり返しには、人間の思考を止める力がある 人間の一生は不完全情報ゲーム 戦略立案能力や論理的な最善手を迅速に探す能力よりも、「相手がどう考えるか」を読む心理戦 近年、脳科学ブームが続いているのは、脳科学がこうした技術の源泉になり得る科学的な根拠を与えるものだと一般に考えられているから 呪詛による突然死、Voodoo Death(ヴードゥー・デス) 「誰かからネガティブで攻撃的な感情を向けられているに違いない」という信念がアドレナリンの動態を変化させることによって心血管系が深刻なダメージを受け、それが死につながるという生理学者による考え方 プラシーボ効果、ノーシーボ効果 偽薬でODに至るケースも、医療の現場での言葉の選び方や伝え方にもある程度の配慮が必要 「競争に負けたオス」の負けグセが子に伝わる実験 虐待された側がする側になるという説 私たち人間の脳は苦痛よりも、快楽に弱くできている 正義中毒より根深い依存の実態 空気がルールの「コンプライアンス中毒」 依存症というのは本人の意志の力や心の弱さなどといった個人の資質に拠るものではなく、そもそも人間には快楽に抗える仕組みがないために、極めてベーシックな人間の(あるいは生物の)脳の機構を由来として起こるということを知っておく必要がある サイコパスは反社会性パーソナリティに分類される しかし、大衆の声が認知構造を支配せんとする時代となったいま、場合によっては、向社会性を維持しようとする大多数の人々のほうが、少数の反社会性パーソナリティの個体よりもずっと恐ろしいという現象が周期的に起こるようになった 「ウソをつく脳」が恋愛強者か恋愛弱者かの分かれ目 男性では恋愛経験の乏しい人ほど正直者 報酬が期待されるときに側坐核の活動がより高くなる人ほど、ウソをつく割合が高い 側坐核というのは、脳におけるいわゆる“快楽中枢”である 自分たちはそれと気づくことができないほど、私たちは自分たちのつくった虚構の中に搦めとられて生きており、この虚構を制する力を持つ者が世界を制すると言っても過言ではない なぜ人は「わかりやすいもの」を見下すのか 現代アートはただ心地よく美しいだけでは価値を持たない、わかりにくく「難解」であることこそがその作品の質の高さを担保するのだという、ある種のスノビズムがこの中に内包されている バーラインの理論、覚醒レベルを上昇させる刺激特性を「覚醒ポテンシャル」と呼び、複雑さや新奇さがその刺激に相当する 感性評価と覚醒レベルの関係は逆U字型の関数になると考えられる つまり、理解しやすく、よく見知った刺激に対しては、単純であるとして物足りなさを感じ、時には批判するが、覚醒水準を最適にする刺激の値ーーどの程度の単純さと複雑さを持った刺激ならば最も快を高められるのかーーは、感情の種類、そして受け手によっても異なる わかりやすさを理由に最初から敬遠して見ることすらしない人、というのは、この覚醒ポテンシャルのレベルが一定以上でないともう満足できなくなってしまった、閾値の上がりすぎた人 より難解で、複雑で、わかりにくいものに新奇性を感じるため、好もしく思う 現代アートの面白さは作品ないしは展示というひとつの「虚構」を通じて、現実を客体化して見る目を鑑賞者にもたらしてくれる点
しまりす@alice_soror2025年4月3日読んでる自分で自分の発した言葉に驚かされることがある →意味理解に使われる脳機能部位と、音声言語を発するための脳機能部位が異なっていて。おたがいに連絡をとるには遠い距離にあるため 発した言葉が無意識のレイヤーに影響する 真言、陀羅尼、アル=クルアーン「読誦されるもの」などは読まれる音を大事にし、美しい響きを持つ 認知科学的には美しい音の連なりやくり返しには、人間の思考を止める力がある 人間の一生は不完全情報ゲーム 戦略立案能力や論理的な最善手を迅速に探す能力よりも、「相手がどう考えるか」を読む心理戦 近年、脳科学ブームが続いているのは、脳科学がこうした技術の源泉になり得る科学的な根拠を与えるものだと一般に考えられているから 呪詛による突然死、Voodoo Death(ヴードゥー・デス) 「誰かからネガティブで攻撃的な感情を向けられているに違いない」という信念がアドレナリンの動態を変化させることによって心血管系が深刻なダメージを受け、それが死につながるという生理学者による考え方 プラシーボ効果、ノーシーボ効果 偽薬でODに至るケースも、医療の現場での言葉の選び方や伝え方にもある程度の配慮が必要 「競争に負けたオス」の負けグセが子に伝わる実験 虐待された側がする側になるという説 私たち人間の脳は苦痛よりも、快楽に弱くできている 正義中毒より根深い依存の実態 空気がルールの「コンプライアンス中毒」 依存症というのは本人の意志の力や心の弱さなどといった個人の資質に拠るものではなく、そもそも人間には快楽に抗える仕組みがないために、極めてベーシックな人間の(あるいは生物の)脳の機構を由来として起こるということを知っておく必要がある サイコパスは反社会性パーソナリティに分類される しかし、大衆の声が認知構造を支配せんとする時代となったいま、場合によっては、向社会性を維持しようとする大多数の人々のほうが、少数の反社会性パーソナリティの個体よりもずっと恐ろしいという現象が周期的に起こるようになった 「ウソをつく脳」が恋愛強者か恋愛弱者かの分かれ目 男性では恋愛経験の乏しい人ほど正直者 報酬が期待されるときに側坐核の活動がより高くなる人ほど、ウソをつく割合が高い 側坐核というのは、脳におけるいわゆる“快楽中枢”である 自分たちはそれと気づくことができないほど、私たちは自分たちのつくった虚構の中に搦めとられて生きており、この虚構を制する力を持つ者が世界を制すると言っても過言ではない なぜ人は「わかりやすいもの」を見下すのか 現代アートはただ心地よく美しいだけでは価値を持たない、わかりにくく「難解」であることこそがその作品の質の高さを担保するのだという、ある種のスノビズムがこの中に内包されている バーラインの理論、覚醒レベルを上昇させる刺激特性を「覚醒ポテンシャル」と呼び、複雑さや新奇さがその刺激に相当する 感性評価と覚醒レベルの関係は逆U字型の関数になると考えられる つまり、理解しやすく、よく見知った刺激に対しては、単純であるとして物足りなさを感じ、時には批判するが、覚醒水準を最適にする刺激の値ーーどの程度の単純さと複雑さを持った刺激ならば最も快を高められるのかーーは、感情の種類、そして受け手によっても異なる わかりやすさを理由に最初から敬遠して見ることすらしない人、というのは、この覚醒ポテンシャルのレベルが一定以上でないともう満足できなくなってしまった、閾値の上がりすぎた人 より難解で、複雑で、わかりにくいものに新奇性を感じるため、好もしく思う 現代アートの面白さは作品ないしは展示というひとつの「虚構」を通じて、現実を客体化して見る目を鑑賞者にもたらしてくれる点