調香師日記
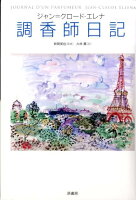
6件の記録
 木埜真尋@stilllifeppap2025年3月20日読み終わった図書館で借りた調香師日記 ジャンクロードエレナ 250320読了 モレスキンの手帳 就寝前の読書タイム エドモンド・ルドニツカ「問われる美学」 ゴーゴリ「鼻」 ジャンクロードエレナの誕生日は4/7 メビウスに広告を頼んだ話 尾形光琳 燕子花図屏風 五月革命 侘び寂びを理解する日本にはドビュッシーかラベルが似合う p25 製造所内にたちこめている匂いには、機械のけたたましい音をかき消してしまいかねない威力があり、思わず私はのけぞった。そしてなすがまま、全身が匂い浸るにまかせた。仕事では、匂いとの距離を測りながら、匂いをつかみ、理解し、その裏側)を嗅ぎとろうとしているのに、ここでは匂いが私のなかに侵入し、逃れるすべもなく、ただただ匂いに覆いつくされ、包みこまれるにまかせた。一面一色の匂いを前にしたイメージである。加工されていない、ありのままの匂いから、まさに全身で喜びを受けたような経験だった。思考がすっかり飛んでしまった瞬間だった。 P29. 調香師であれば、だれもが自分の仕事を芸術ととらえているはずである。その仕事の原動力となるのが欲望。なぜなら、欲望が真っ先に心的エネルギーを取りこんで、それが香水づくりに活かされるからー私はそう信じている。 p45. 不安とのつき合いはもう長い。むろん、好きこのんで不安を招いたことは一度もない。最初は二〇歳かそこらだったと思う。不安は突然現れた。嫌な感情だったが、甘んじて受け入れた。それからだいぶ経ってからのこと。不安によって、ある言葉の言わんとする意味がとてもよく理解できた。 「この世の本当の不思議は、目に見えるものであって、見えないものではない」 という、オスカー・ワイルドの小説『ドリアン・グレイの肖像』の一節。 単純なようで奥の深い言葉である。この言葉を本で読んだとき、私はひどく不安を覚え、しばしうろたえてしまった。自分がとてつもない危機に瀕して、なんの術もなく立ちつくしているような気がした。だが、それは東の間の感覚だった。次の瞬間、私は感動していた。そんな感覚に陥ったのは、自分が明らかに覚醒しているからにほかならない。不安は生きていることの証しである。そう気づかされた。 p55 香水は流行の移ろいやすさとは縁がない。 P61. 東京 梅花が散り、桜の蕾がふくらむ頃 並べること 日本では、四季折々の季節感に文化的な意味をもたせている。日本人は手紙をしたためるとき時候の挨拶からはじめるのが常である。また、季節の色を取りいれた和服を着たり、四季折々の旬の食材を大事にする。今夜、私たちは「ソバ」料理の店でご馳走になった。「ソバ」は蕎麦粉をベースにしたヌードルである。店内は私たちだけだった。店はホテルのホールのように広々として、紛れもない蕎麦粉の匂いがする。それは焼き栗の匂いを思わせた。杉板のカウンター席につくと、白衣にブルーの鉢巻き姿の料理人が三人、私たちに挨拶をした。彼らはまず、調理に入る前にこちらの好みや意向を聞いてくれた。一人が生地をこねだす。そして、それをしばらく寝かせてから、儀式に準じているかのようにきちんと生地をのして広げていき、最後に四角いかたちにたたむ。次に、それを計ったように正確に切り分けると、細いひも状のヌードルができあがる。そのあいだ、もう一人は石臼で蕎麦の実を挽いて粉にし、次の料理に備えている。切り分けたヌードルは手でつかんで、湯がぐらぐらと煮たっているところに入れる。すぐにヌードルは引き揚げられ、それぞれ椀に分けられて、私たちの前に供された。食事がはじまった。料理人は、私に「すすって」食べるようにと勧めた。日本ではヌードルは音をたてながら食べるものという。 最初の椀が終わると、次々とたくさんの料理が供された。それぞれが違った器に盛られている。日本では季節に応じて器も変える。たとえば、冬なら焼き物を、夏ならガラスや竹を、といった案配である。その都度、目でも舌でも驚きが味わえるようにするためである。どのひと品も素材別に並べるようにして盛りつけられ、色、食感、味わいの違いが堪能できるようになっている。素材の新鮮味が命であり、味つけは繊細である。ここの料理には、積み重ねたり、たっぷりと盛ったりということがなく、ソースの存在もない。西洋料理本来の材料を混ぜるというやり方ならば、失敗しても修正のしようがあるだろう。しかしここでは、ごまかしは利かない。目前で繰り広げられたこの光覧は、私たちにとって至福以外のなにものでもなかった。快楽主義者になって至福を味わえたひとときだった。言い換えれば、料理人たちにとっては卓越した技術が要求されるひとときだったということではないだろうか。 p87. 数カ月前から、イタリア語の勉強を再開している。仕事に使うためではなく、楽しいから勉強している。初心者として学ぶ身にあることが楽しい。外国語あるいはそれ以外でも、なにかを学ぶことは、新しい世界への扉が開かれることであり、謙虚な気持ちを思いだす。 P91. フェミナンH カブリ 4月30日金 2010 洋梨をテーマにした香水の試作品をテーブルに置きっぱなしにして二ヵ月が経つ。そのなかで最後につくった匂いを嗅いでみた。私が気に入っていたあの匂いがした。 私はアシスタントに光を当てないように戸棚に保管しておくように頼んだ、試作の原液をもってこさせた。そのサンプルをとって希釈してみると、まだ丸みにける粗野な匂いがする。 洋梨のノートの丸みを得るには、このアルコールで希釈した溶液を長時間熟成させる必要がある。この「フェミナン H」を表現する言葉は、小悪魔的、惚れ惚れする、魅惑的、けれども、少しだけ冷たい。そこで、さらに洋梨のアコードを修正し、もっと果汁をたっぷり含んでいる感じをもたせ、ささやかな調べを奏でているシプレを強調するようにして、官能性を際立たせてみた。 私は試作を一つ選び、熟成させるために同じものを半リットル用意するようアシスタントに指示した。 画家のセザンヌは、「リンゴ一つでパリを驚かせたい」と言ったらしいが、同じような野心なら私ももっている。日常にある匂い一つで、はっとさせたり、えっと思わせたりしたい。 P101 ご馳走 パリとジャンブルーを往復して 5月17日月 2010 ベルギー・リエージュ近郊のジャンブルーで、三つ星シェフのピエール・ガニエールが友人同士の食事会を企画した。作家や多岐にわたる分野の博士、大学の学長らが集うらしいと聞き、心躍らせながらも、どうしてまた突然にと不思議に思いつつ、すぐに招待を受ける返事を出した。そして、今日の午後、パリ北駅からリエージュ行きの列車に乗ったというわけである。車内で偶然、招待客の一人に会った。乗っているあいだ、私たちはいろいろと話をした。そしてわかったことは、いったいなにが待ち受けているのか、互いにさっぱりわからないということだった。それでも、シェフへの友情から、それに好奇心も手伝って、二人とも喜んでこの招待に応じたことは事実である。リエージュ駅では運転手が待っていて、私たちをジャンブルーの農業大学へ連れて行ってくれた。 キャンパスに着くと、熱帯植動園に案内され、ガニエール夫妻が出迎えに現れた。まるで異国の地に誘われるような心地がした。これまた変わった場所を舞台に選んだものである。シェフは、この舞台の片側に、火口が四つあるガスレンジと、作業台としてテーブルを一台設えていた。正面には、会食者用のテーブルがある。舞台の奥には、流し、冷蔵庫、白い木製の戸棚がいくつか据えられている。戸棚には、皿類、グラスなどの食器一式、調理器具が並んでいた。 招待客は単なる観客ではなく、シェフとともに夜の部を演じる役者という筋立てである。味わう幸福に身をゆだね)というタイトルの芝居である。各自に、小さなメモ帳と鉛筆一本が手渡され、そこに感じたことを書きとめるように言われた。そう言われたものの、今夜は無理そうに思われた。 刺数的な体験を味わいながら、感じたことすべてを書きとめることなど、とてもできまい。 ディナーはヘラングスティーヌとマテ貝のタルタル・ザクロ添え>からはじまった。甘みと酸味の絶妙なコンビネーションである。続いて、へ真館の心臓・ネトルのヴルーテソース)を堪能する。ネトルのグリーンに、魚のやわらかな身が隠れている遊び心のある一品。お次は、フレッシュモリーユ茸・リコリスの香り)。森林を想起させる味わいと、リコリスの根茎の苦みのバランスは非の打ちどころがない。それにヘズッキーニの花・ホワイトアスパラガスの穂先とともに)が続く。こうして招待客は、細やかな愛情とほのかに苦みのある味わいを楽しんだ。料理はさらに続き、(グリーンピースとソラマメの温かいスープ>と<自家製ビーツのラビオリ・オリーブ風味・海香の香り>をワインとともにいただく。このワインもまたアニマリックで、フランボワーズが香る。 ここまでで、コースのまだ三分の一である。ピエール・ガニェールはずっと厨房にいて、鍋の前にはりつき、集を近づけて匂いを嗅ぎ、耳を澄ませて音を聴き、しばらくそのままにし、中身を指で混ぜて温度を確かめている。五感すべてを働かせている。私たちは客同士で語りあったり、シェフに声をかけたりした。拍手喝采とブラボーのかけ声、歓声が上がるたび、おしゃべりもその都度中断する。ただシェフのほうにはやや疲れも見えてきた。髪がだんだん乱れ、その健闘ぶりがうかがえる。いったいどれだけの喜びをもたらしていることか、と彼には感心するばかりである。そのあとも、彼は何度も前掛けを取り換えていた。 食事がはじまったのは午後九時だったが、もう午前二時を回っていた。想像の世界を際限なく広げてくれるメニューに、美しいものを堪能したがる私たちの気持ちはすっかり満たされていた。実際、胃袋のほうもはちきれんばかりだった。デザートはあっさりしていた。もちろん、これほどのご馳走のあとだから、甘ったるいものは避けたのだろう。五時間に及ぶ大盤振る舞いだった。彼の料理は、空腹を満たすだけの料理とは違う。そうではなく、愛のある言葉で語られた一つの表現形式なのである。これはもうまちがいなく、芸術である。 P132. ところで、一人でいるということは、孤独を克服できるということでもある。孤独とうつは関係があるようだが、うつ状態にもならずにすんでいる。私は粘り強いたちで、どんなささやかなアイデイアでも積極的に取り組み、つねに、進行中のアイディアと処方箋を何本か抱えている。自分に課していることもある。仕事はル帳面に行い、規則的にスケジュールをこなし、結果を出すということ。 これらはどれも、自分のなかに閉じこもらないようにするための予防策である。一人きりの状態を、私は極上の自由だと考えている。その埋め合わせとして、定期的にパリに顔を出すことにしている。
木埜真尋@stilllifeppap2025年3月20日読み終わった図書館で借りた調香師日記 ジャンクロードエレナ 250320読了 モレスキンの手帳 就寝前の読書タイム エドモンド・ルドニツカ「問われる美学」 ゴーゴリ「鼻」 ジャンクロードエレナの誕生日は4/7 メビウスに広告を頼んだ話 尾形光琳 燕子花図屏風 五月革命 侘び寂びを理解する日本にはドビュッシーかラベルが似合う p25 製造所内にたちこめている匂いには、機械のけたたましい音をかき消してしまいかねない威力があり、思わず私はのけぞった。そしてなすがまま、全身が匂い浸るにまかせた。仕事では、匂いとの距離を測りながら、匂いをつかみ、理解し、その裏側)を嗅ぎとろうとしているのに、ここでは匂いが私のなかに侵入し、逃れるすべもなく、ただただ匂いに覆いつくされ、包みこまれるにまかせた。一面一色の匂いを前にしたイメージである。加工されていない、ありのままの匂いから、まさに全身で喜びを受けたような経験だった。思考がすっかり飛んでしまった瞬間だった。 P29. 調香師であれば、だれもが自分の仕事を芸術ととらえているはずである。その仕事の原動力となるのが欲望。なぜなら、欲望が真っ先に心的エネルギーを取りこんで、それが香水づくりに活かされるからー私はそう信じている。 p45. 不安とのつき合いはもう長い。むろん、好きこのんで不安を招いたことは一度もない。最初は二〇歳かそこらだったと思う。不安は突然現れた。嫌な感情だったが、甘んじて受け入れた。それからだいぶ経ってからのこと。不安によって、ある言葉の言わんとする意味がとてもよく理解できた。 「この世の本当の不思議は、目に見えるものであって、見えないものではない」 という、オスカー・ワイルドの小説『ドリアン・グレイの肖像』の一節。 単純なようで奥の深い言葉である。この言葉を本で読んだとき、私はひどく不安を覚え、しばしうろたえてしまった。自分がとてつもない危機に瀕して、なんの術もなく立ちつくしているような気がした。だが、それは東の間の感覚だった。次の瞬間、私は感動していた。そんな感覚に陥ったのは、自分が明らかに覚醒しているからにほかならない。不安は生きていることの証しである。そう気づかされた。 p55 香水は流行の移ろいやすさとは縁がない。 P61. 東京 梅花が散り、桜の蕾がふくらむ頃 並べること 日本では、四季折々の季節感に文化的な意味をもたせている。日本人は手紙をしたためるとき時候の挨拶からはじめるのが常である。また、季節の色を取りいれた和服を着たり、四季折々の旬の食材を大事にする。今夜、私たちは「ソバ」料理の店でご馳走になった。「ソバ」は蕎麦粉をベースにしたヌードルである。店内は私たちだけだった。店はホテルのホールのように広々として、紛れもない蕎麦粉の匂いがする。それは焼き栗の匂いを思わせた。杉板のカウンター席につくと、白衣にブルーの鉢巻き姿の料理人が三人、私たちに挨拶をした。彼らはまず、調理に入る前にこちらの好みや意向を聞いてくれた。一人が生地をこねだす。そして、それをしばらく寝かせてから、儀式に準じているかのようにきちんと生地をのして広げていき、最後に四角いかたちにたたむ。次に、それを計ったように正確に切り分けると、細いひも状のヌードルができあがる。そのあいだ、もう一人は石臼で蕎麦の実を挽いて粉にし、次の料理に備えている。切り分けたヌードルは手でつかんで、湯がぐらぐらと煮たっているところに入れる。すぐにヌードルは引き揚げられ、それぞれ椀に分けられて、私たちの前に供された。食事がはじまった。料理人は、私に「すすって」食べるようにと勧めた。日本ではヌードルは音をたてながら食べるものという。 最初の椀が終わると、次々とたくさんの料理が供された。それぞれが違った器に盛られている。日本では季節に応じて器も変える。たとえば、冬なら焼き物を、夏ならガラスや竹を、といった案配である。その都度、目でも舌でも驚きが味わえるようにするためである。どのひと品も素材別に並べるようにして盛りつけられ、色、食感、味わいの違いが堪能できるようになっている。素材の新鮮味が命であり、味つけは繊細である。ここの料理には、積み重ねたり、たっぷりと盛ったりということがなく、ソースの存在もない。西洋料理本来の材料を混ぜるというやり方ならば、失敗しても修正のしようがあるだろう。しかしここでは、ごまかしは利かない。目前で繰り広げられたこの光覧は、私たちにとって至福以外のなにものでもなかった。快楽主義者になって至福を味わえたひとときだった。言い換えれば、料理人たちにとっては卓越した技術が要求されるひとときだったということではないだろうか。 p87. 数カ月前から、イタリア語の勉強を再開している。仕事に使うためではなく、楽しいから勉強している。初心者として学ぶ身にあることが楽しい。外国語あるいはそれ以外でも、なにかを学ぶことは、新しい世界への扉が開かれることであり、謙虚な気持ちを思いだす。 P91. フェミナンH カブリ 4月30日金 2010 洋梨をテーマにした香水の試作品をテーブルに置きっぱなしにして二ヵ月が経つ。そのなかで最後につくった匂いを嗅いでみた。私が気に入っていたあの匂いがした。 私はアシスタントに光を当てないように戸棚に保管しておくように頼んだ、試作の原液をもってこさせた。そのサンプルをとって希釈してみると、まだ丸みにける粗野な匂いがする。 洋梨のノートの丸みを得るには、このアルコールで希釈した溶液を長時間熟成させる必要がある。この「フェミナン H」を表現する言葉は、小悪魔的、惚れ惚れする、魅惑的、けれども、少しだけ冷たい。そこで、さらに洋梨のアコードを修正し、もっと果汁をたっぷり含んでいる感じをもたせ、ささやかな調べを奏でているシプレを強調するようにして、官能性を際立たせてみた。 私は試作を一つ選び、熟成させるために同じものを半リットル用意するようアシスタントに指示した。 画家のセザンヌは、「リンゴ一つでパリを驚かせたい」と言ったらしいが、同じような野心なら私ももっている。日常にある匂い一つで、はっとさせたり、えっと思わせたりしたい。 P101 ご馳走 パリとジャンブルーを往復して 5月17日月 2010 ベルギー・リエージュ近郊のジャンブルーで、三つ星シェフのピエール・ガニエールが友人同士の食事会を企画した。作家や多岐にわたる分野の博士、大学の学長らが集うらしいと聞き、心躍らせながらも、どうしてまた突然にと不思議に思いつつ、すぐに招待を受ける返事を出した。そして、今日の午後、パリ北駅からリエージュ行きの列車に乗ったというわけである。車内で偶然、招待客の一人に会った。乗っているあいだ、私たちはいろいろと話をした。そしてわかったことは、いったいなにが待ち受けているのか、互いにさっぱりわからないということだった。それでも、シェフへの友情から、それに好奇心も手伝って、二人とも喜んでこの招待に応じたことは事実である。リエージュ駅では運転手が待っていて、私たちをジャンブルーの農業大学へ連れて行ってくれた。 キャンパスに着くと、熱帯植動園に案内され、ガニエール夫妻が出迎えに現れた。まるで異国の地に誘われるような心地がした。これまた変わった場所を舞台に選んだものである。シェフは、この舞台の片側に、火口が四つあるガスレンジと、作業台としてテーブルを一台設えていた。正面には、会食者用のテーブルがある。舞台の奥には、流し、冷蔵庫、白い木製の戸棚がいくつか据えられている。戸棚には、皿類、グラスなどの食器一式、調理器具が並んでいた。 招待客は単なる観客ではなく、シェフとともに夜の部を演じる役者という筋立てである。味わう幸福に身をゆだね)というタイトルの芝居である。各自に、小さなメモ帳と鉛筆一本が手渡され、そこに感じたことを書きとめるように言われた。そう言われたものの、今夜は無理そうに思われた。 刺数的な体験を味わいながら、感じたことすべてを書きとめることなど、とてもできまい。 ディナーはヘラングスティーヌとマテ貝のタルタル・ザクロ添え>からはじまった。甘みと酸味の絶妙なコンビネーションである。続いて、へ真館の心臓・ネトルのヴルーテソース)を堪能する。ネトルのグリーンに、魚のやわらかな身が隠れている遊び心のある一品。お次は、フレッシュモリーユ茸・リコリスの香り)。森林を想起させる味わいと、リコリスの根茎の苦みのバランスは非の打ちどころがない。それにヘズッキーニの花・ホワイトアスパラガスの穂先とともに)が続く。こうして招待客は、細やかな愛情とほのかに苦みのある味わいを楽しんだ。料理はさらに続き、(グリーンピースとソラマメの温かいスープ>と<自家製ビーツのラビオリ・オリーブ風味・海香の香り>をワインとともにいただく。このワインもまたアニマリックで、フランボワーズが香る。 ここまでで、コースのまだ三分の一である。ピエール・ガニェールはずっと厨房にいて、鍋の前にはりつき、集を近づけて匂いを嗅ぎ、耳を澄ませて音を聴き、しばらくそのままにし、中身を指で混ぜて温度を確かめている。五感すべてを働かせている。私たちは客同士で語りあったり、シェフに声をかけたりした。拍手喝采とブラボーのかけ声、歓声が上がるたび、おしゃべりもその都度中断する。ただシェフのほうにはやや疲れも見えてきた。髪がだんだん乱れ、その健闘ぶりがうかがえる。いったいどれだけの喜びをもたらしていることか、と彼には感心するばかりである。そのあとも、彼は何度も前掛けを取り換えていた。 食事がはじまったのは午後九時だったが、もう午前二時を回っていた。想像の世界を際限なく広げてくれるメニューに、美しいものを堪能したがる私たちの気持ちはすっかり満たされていた。実際、胃袋のほうもはちきれんばかりだった。デザートはあっさりしていた。もちろん、これほどのご馳走のあとだから、甘ったるいものは避けたのだろう。五時間に及ぶ大盤振る舞いだった。彼の料理は、空腹を満たすだけの料理とは違う。そうではなく、愛のある言葉で語られた一つの表現形式なのである。これはもうまちがいなく、芸術である。 P132. ところで、一人でいるということは、孤独を克服できるということでもある。孤独とうつは関係があるようだが、うつ状態にもならずにすんでいる。私は粘り強いたちで、どんなささやかなアイデイアでも積極的に取り組み、つねに、進行中のアイディアと処方箋を何本か抱えている。自分に課していることもある。仕事はル帳面に行い、規則的にスケジュールをこなし、結果を出すということ。 これらはどれも、自分のなかに閉じこもらないようにするための予防策である。一人きりの状態を、私は極上の自由だと考えている。その埋め合わせとして、定期的にパリに顔を出すことにしている。 木埜真尋@stilllifeppap2025年3月12日読んでる小津夜景の本にタイトルが載っていたので図書館で借りてきて読み始めた。借りた本の写真を撮ってそのまま特に分類せずにあとで参照もしない悪癖があるので、気になるところをreadsに貼り付けてみようと思う。火打石の匂いがする香水、試してみたい。 P7. 「テールドウエルメス」は火打石の匂いがするが、実際にそれを使っているわけではない。だが、それらのフレグランスを嗅いだ人は、そういう匂いがする<錯覚>を起こしている。ジャン・ジオノの言葉を借りるなら、「表現という作業は、読者側の知性においてなされる。読者はそれを楽しみ、また楽しんでいるから、満たされ、歓びを覚えるのだ」。かねてより、調香師は作曲家にたとえられてきた。けれども、私はつねづね自分は香りの文筆家だと思っている。 P14. ところで、何年も前から日課にしていることがある。一人で静かに実験を重ね、そこで得られた香調を記録しているのである。二種類から五種類の構成要素を使い、匂いの輪郭をスケッチしていく。原料を並べて匂いの錯覚をつくりだすのである。必要に応じてその錯覚を創作にも利用している。 そうやって私は周囲の日常的な匂いをできるだけ簡潔なかたちで表してきた。自然とは複雑でたとえば、ローズの匂いは五〇〇もの芳香分子から成り立っている。チョコレートの香りにいたってはそれ以上で、ニンニクの場合はもっと少ない。私はこの天然の匂いを複製するつもりはない。だから、ゲーム感覚でこのような実験をはじめた。つまり、匂いの意味論を追求しているというわけである。そうやって複雑な構造をもつ自然の匂いというものを香水というかたちで表現する。この作業が<匂いが語る言葉>の基礎ともなっている。もちろんそれが万人に通用するとは限らない。そのことはつねに意識するようにしている。
木埜真尋@stilllifeppap2025年3月12日読んでる小津夜景の本にタイトルが載っていたので図書館で借りてきて読み始めた。借りた本の写真を撮ってそのまま特に分類せずにあとで参照もしない悪癖があるので、気になるところをreadsに貼り付けてみようと思う。火打石の匂いがする香水、試してみたい。 P7. 「テールドウエルメス」は火打石の匂いがするが、実際にそれを使っているわけではない。だが、それらのフレグランスを嗅いだ人は、そういう匂いがする<錯覚>を起こしている。ジャン・ジオノの言葉を借りるなら、「表現という作業は、読者側の知性においてなされる。読者はそれを楽しみ、また楽しんでいるから、満たされ、歓びを覚えるのだ」。かねてより、調香師は作曲家にたとえられてきた。けれども、私はつねづね自分は香りの文筆家だと思っている。 P14. ところで、何年も前から日課にしていることがある。一人で静かに実験を重ね、そこで得られた香調を記録しているのである。二種類から五種類の構成要素を使い、匂いの輪郭をスケッチしていく。原料を並べて匂いの錯覚をつくりだすのである。必要に応じてその錯覚を創作にも利用している。 そうやって私は周囲の日常的な匂いをできるだけ簡潔なかたちで表してきた。自然とは複雑でたとえば、ローズの匂いは五〇〇もの芳香分子から成り立っている。チョコレートの香りにいたってはそれ以上で、ニンニクの場合はもっと少ない。私はこの天然の匂いを複製するつもりはない。だから、ゲーム感覚でこのような実験をはじめた。つまり、匂いの意味論を追求しているというわけである。そうやって複雑な構造をもつ自然の匂いというものを香水というかたちで表現する。この作業が<匂いが語る言葉>の基礎ともなっている。もちろんそれが万人に通用するとは限らない。そのことはつねに意識するようにしている。








