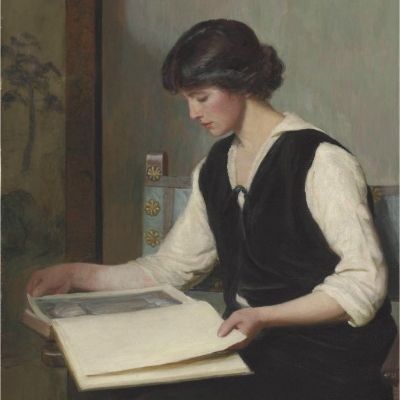悲しみが言葉をつむぐとき

6件の記録
 noko@nokonoko2025年8月13日読み終わった借りてきた心に残る一節容易に言葉になろうとしない想いで胸が満たされたとき人は、どうにかしてそれを語ろうとしてもがく。伝えたいことがある時よりも、伝えきれないことがあるとき私たちは、言葉との関係を深めている。奇妙に聞こえるかもしれないが、言葉とは、言葉たり得ないものの顕れなのである。 人の言葉が食物を必要とするように、私たちの心は言葉を必要とする。言葉は文字通りの意味において心の糧である。言葉から離れた心は飢え、渇く。 内なる言葉は、最初、いわゆる言葉の姿をしていない。想いにとどまっていることもあれば、想いとして自覚されないこともある。無形の言葉、これをここでは「コトバ」とカタカナで書くことにする。 コトバを言葉にすること、それが想う、あるいは書くということだ。 想うだけでも心に言葉が宿ることがある。それは私たちは祈りと呼んできた。だが、どうしても書き記して、コトバを文字の姿に移し替えなければならないことが私たちの人生には何度かある。 人は、しばしば、自分が泣いていることを知らないことがある、そう思うようになりました。見えない涙が心の中に流れる時人は、そのことに気が付かない。しかし、その魂は、頬を濡らす時と同じように、また、それよりも深く悲しみを感じているのかもしれません。 昔の人は、「かなし」を、悲し、哀し、とだけではなく、愛し、あるいは、美しとすら書いて、「かなし」と読みました。悲しみは、いつも、深い情愛と結びつき、美としか呼ぶことのできない何ものかを伴って顕れることを、古の人々は、はっきりと感じていたのだと思われます。 昨年、石巻に講演に行った時のことでした。主題は、悲しみと死者でした。悲しみとは、死者と離れてしまったことを示す感情ではなく、むしろ、私たちは死者が寄り添うのを感じるとき、悲しむのではないか。悲しみとは、世に言われるような悲惨な出来事ではなく、愛しみを全身で感じる出来事なのではないかという話をしました。 多くの人にとって死者は、それが何であるかは語り得ないがしかし、実在する何ものかなのではないでしょうか。当然ながら、語り得ないことと存在しないことは、まったく関係がないのです。
noko@nokonoko2025年8月13日読み終わった借りてきた心に残る一節容易に言葉になろうとしない想いで胸が満たされたとき人は、どうにかしてそれを語ろうとしてもがく。伝えたいことがある時よりも、伝えきれないことがあるとき私たちは、言葉との関係を深めている。奇妙に聞こえるかもしれないが、言葉とは、言葉たり得ないものの顕れなのである。 人の言葉が食物を必要とするように、私たちの心は言葉を必要とする。言葉は文字通りの意味において心の糧である。言葉から離れた心は飢え、渇く。 内なる言葉は、最初、いわゆる言葉の姿をしていない。想いにとどまっていることもあれば、想いとして自覚されないこともある。無形の言葉、これをここでは「コトバ」とカタカナで書くことにする。 コトバを言葉にすること、それが想う、あるいは書くということだ。 想うだけでも心に言葉が宿ることがある。それは私たちは祈りと呼んできた。だが、どうしても書き記して、コトバを文字の姿に移し替えなければならないことが私たちの人生には何度かある。 人は、しばしば、自分が泣いていることを知らないことがある、そう思うようになりました。見えない涙が心の中に流れる時人は、そのことに気が付かない。しかし、その魂は、頬を濡らす時と同じように、また、それよりも深く悲しみを感じているのかもしれません。 昔の人は、「かなし」を、悲し、哀し、とだけではなく、愛し、あるいは、美しとすら書いて、「かなし」と読みました。悲しみは、いつも、深い情愛と結びつき、美としか呼ぶことのできない何ものかを伴って顕れることを、古の人々は、はっきりと感じていたのだと思われます。 昨年、石巻に講演に行った時のことでした。主題は、悲しみと死者でした。悲しみとは、死者と離れてしまったことを示す感情ではなく、むしろ、私たちは死者が寄り添うのを感じるとき、悲しむのではないか。悲しみとは、世に言われるような悲惨な出来事ではなく、愛しみを全身で感じる出来事なのではないかという話をしました。 多くの人にとって死者は、それが何であるかは語り得ないがしかし、実在する何ものかなのではないでしょうか。当然ながら、語り得ないことと存在しないことは、まったく関係がないのです。