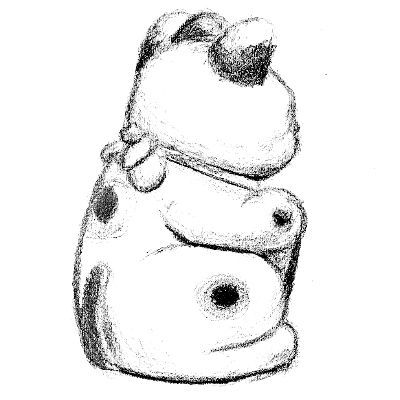
いつもすこやか
@itsmo_skoyaka
- 1900年1月1日
 石川啄木詩歌集伊藤信吉,石川啄木かつて読んだ『不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心』 という、高校の国語の教科書に載ってた歌に感銘を受けたのを覚えてて読んだ。 詩集とはあるけどかなりエッセイみたいな読み味。というか、感じたあらゆることを書き連ねてて現代でいうTwitterのようにも思える。 昔も今も思うことは似ているんだなぁと感じる短歌が多々あって親近感が湧く。ただ、読むだけで情景が鮮明に浮かび上がる表現力も遺憾無く発揮されてる。 特に好きだった短歌 『とかくして家を出づれば日光のあたたかさあり息深く吸う』 『さりげなく言ひし言葉は さりげなく君も聴きつらむ それだけのこと』
石川啄木詩歌集伊藤信吉,石川啄木かつて読んだ『不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心』 という、高校の国語の教科書に載ってた歌に感銘を受けたのを覚えてて読んだ。 詩集とはあるけどかなりエッセイみたいな読み味。というか、感じたあらゆることを書き連ねてて現代でいうTwitterのようにも思える。 昔も今も思うことは似ているんだなぁと感じる短歌が多々あって親近感が湧く。ただ、読むだけで情景が鮮明に浮かび上がる表現力も遺憾無く発揮されてる。 特に好きだった短歌 『とかくして家を出づれば日光のあたたかさあり息深く吸う』 『さりげなく言ひし言葉は さりげなく君も聴きつらむ それだけのこと』 - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか黒川伊保子かつて読んだ社会人で読書再開して最初の一冊 大学の感覚学の講義中に教授がチラッとオススメしててメモってそれをずっと覚えてて選んだ。 印象やイメージとは切り離した、発声するときの身体的感覚(口内の動きや湿り方、息を吐く速度など)から音を考える話。 かなり斬新だけど説得力があって面白い。 あと初めて物語以外の本を読んだので、研究で裏付けがあること以外にもそんなに主観やこじつけを本に書いちゃっていいんだという驚きもあった。
怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか黒川伊保子かつて読んだ社会人で読書再開して最初の一冊 大学の感覚学の講義中に教授がチラッとオススメしててメモってそれをずっと覚えてて選んだ。 印象やイメージとは切り離した、発声するときの身体的感覚(口内の動きや湿り方、息を吐く速度など)から音を考える話。 かなり斬新だけど説得力があって面白い。 あと初めて物語以外の本を読んだので、研究で裏付けがあること以外にもそんなに主観やこじつけを本に書いちゃっていいんだという驚きもあった。
読み込み中...


