もふもふ毛布
@mofu-mofu
- 2026年2月3日
- 2026年1月27日
 組織の違和感勅使川原真衣読み終わった買ったソーシャルスタイルの4類型。私はアナリティカルよりのエミアブルかなぁ。血液型占いに代表される枠にはめるような分類は好きではないが、自分の型がわかることで安心する気もした。 「ズレの交通整理こそがリーダーの職務」というのは、すごく納得。 「誰にでもできる仕事」について触れてくれているのもうれしかった。低賃金の仕事と誰にでもできる仕事がイコールで語られることに違和感がある。
組織の違和感勅使川原真衣読み終わった買ったソーシャルスタイルの4類型。私はアナリティカルよりのエミアブルかなぁ。血液型占いに代表される枠にはめるような分類は好きではないが、自分の型がわかることで安心する気もした。 「ズレの交通整理こそがリーダーの職務」というのは、すごく納得。 「誰にでもできる仕事」について触れてくれているのもうれしかった。低賃金の仕事と誰にでもできる仕事がイコールで語られることに違和感がある。 - 2026年1月19日
- 2026年1月5日
 「頭がいい」とは何か (祥伝社新書 727)勅使川原真衣気になる
「頭がいい」とは何か (祥伝社新書 727)勅使川原真衣気になる - 2026年1月5日
- 2025年12月29日
 沖縄社会論上原健太郎,上間陽子,岸政彦,打越正行,石岡丈昇買った
沖縄社会論上原健太郎,上間陽子,岸政彦,打越正行,石岡丈昇買った - 2025年12月24日
 裸足で逃げる上間陽子読み終わった買った「さがさないよ さようなら」の春菜さんを探さないと決めた上間さんの優しさ、過去を断ち切ると決めたと思われる春菜さんの覚悟、そのどちらも強い意志を尊敬する。 少子化が叫ばれる中、未成年の妊娠も問題となっていることに、社会ができることはもっとあるのではないかと思わざるを得ない。
裸足で逃げる上間陽子読み終わった買った「さがさないよ さようなら」の春菜さんを探さないと決めた上間さんの優しさ、過去を断ち切ると決めたと思われる春菜さんの覚悟、そのどちらも強い意志を尊敬する。 少子化が叫ばれる中、未成年の妊娠も問題となっていることに、社会ができることはもっとあるのではないかと思わざるを得ない。 - 2025年12月11日
 読み終わった買った答え合わせしたい欲求や正解を教えてほしいという欲求について。私は20代の頃、少し年上の人達に、歳を重ねれば、世の中は白黒つけられることばかりじゃなくて、白と黒の間には多くのグラデーションがあることがわかってくるよと教えてもらった。白黒つけたい年上の人もいたかもしれないけど、グラデーションがあるという考え方の人のほうが、こういう大人になりたいと思わせてくれる人だった。 誰にでもできる仕事について。小売業の販売スタッフが長かったので、そう言われたり、思われたりしていることへの悔しさがあった。低賃金の仕事、アルバイト雇用が多い仕事は、誰にでもできると言われがちだが、それは違うという実感がある。 p216に書かれている「今しあわせを感じるのなら、それを多くの人に還元する取り組みこそが『成功』なのだ」ということを皆が共有できる社会だったら、生きやすいのに…。 自分が序列の上位にいたいという欲求を持つ人の気持ちを変えるには、どうすればいいのだろう。 大学生だった頃、ハービー・山口さんに初めてお会いし、写真集にサインをしてもらったときに「君、おもしろいね。」と言ってもらったことを思い出した。20年以上前のことで、ハービーさんは覚えていらっしゃらないと思うが、褒めてもらってうれしかったという記憶として、自分の中に残っている。
読み終わった買った答え合わせしたい欲求や正解を教えてほしいという欲求について。私は20代の頃、少し年上の人達に、歳を重ねれば、世の中は白黒つけられることばかりじゃなくて、白と黒の間には多くのグラデーションがあることがわかってくるよと教えてもらった。白黒つけたい年上の人もいたかもしれないけど、グラデーションがあるという考え方の人のほうが、こういう大人になりたいと思わせてくれる人だった。 誰にでもできる仕事について。小売業の販売スタッフが長かったので、そう言われたり、思われたりしていることへの悔しさがあった。低賃金の仕事、アルバイト雇用が多い仕事は、誰にでもできると言われがちだが、それは違うという実感がある。 p216に書かれている「今しあわせを感じるのなら、それを多くの人に還元する取り組みこそが『成功』なのだ」ということを皆が共有できる社会だったら、生きやすいのに…。 自分が序列の上位にいたいという欲求を持つ人の気持ちを変えるには、どうすればいいのだろう。 大学生だった頃、ハービー・山口さんに初めてお会いし、写真集にサインをしてもらったときに「君、おもしろいね。」と言ってもらったことを思い出した。20年以上前のことで、ハービーさんは覚えていらっしゃらないと思うが、褒めてもらってうれしかったという記憶として、自分の中に残っている。 - 2025年11月26日
 43歳頂点論角幡唯介読み終わった買った20代30代を自分の思い通りに過ごせて、やりたいことをやりきった人は、40代をこういうふうに受け止めるのだなぁと、うらやましい気持ちで読んだ。角幡さんは、今も何者かにならなくてはならないという考えのままなのかと思って読んでいたが、最後のほうにそうではないと思える文章があり、安心した。「この年になって気付くのは、若い頃に恐れていた類型的人生などじつはこの世界にただのひとつも存在しないということだ。人は誰しもそれぞれ異なる道を歩むなかで、少しずつ他人とズレながらその人自身になってゆくのである。」(p176〜177)
43歳頂点論角幡唯介読み終わった買った20代30代を自分の思い通りに過ごせて、やりたいことをやりきった人は、40代をこういうふうに受け止めるのだなぁと、うらやましい気持ちで読んだ。角幡さんは、今も何者かにならなくてはならないという考えのままなのかと思って読んでいたが、最後のほうにそうではないと思える文章があり、安心した。「この年になって気付くのは、若い頃に恐れていた類型的人生などじつはこの世界にただのひとつも存在しないということだ。人は誰しもそれぞれ異なる道を歩むなかで、少しずつ他人とズレながらその人自身になってゆくのである。」(p176〜177) - 2025年11月21日
 見えないものが教えてくれたこと大宮エリー買った
見えないものが教えてくれたこと大宮エリー買った - 2025年11月21日
 思いを伝えるということ (文春文庫)大宮エリー買った
思いを伝えるということ (文春文庫)大宮エリー買った - 2025年11月18日
 生活史の方法岸政彦読み終わった買ったタイトルから、教科書のような内容だと思っていたのだけど、そうではなかった。温度感のある文章で、いろいろなことを考えさせられた。 「私はできれば、この世界で、声を残す力を持たない人びとの声を残したいと思います。」という岸先生のメッセージがうれしかった。何者かにならなくても、ひとりの人が生きていること、生きていたことを残していく意味があるのだと思えると、何者にもなれないことへの不安や焦りを軽減できると思う。
生活史の方法岸政彦読み終わった買ったタイトルから、教科書のような内容だと思っていたのだけど、そうではなかった。温度感のある文章で、いろいろなことを考えさせられた。 「私はできれば、この世界で、声を残す力を持たない人びとの声を残したいと思います。」という岸先生のメッセージがうれしかった。何者かにならなくても、ひとりの人が生きていること、生きていたことを残していく意味があるのだと思えると、何者にもなれないことへの不安や焦りを軽減できると思う。 - 2025年11月4日
 ルポ 低賃金東海林智読み終わった買った帯に書かれている「なぜ、この国では、普通に働いても、普通に暮らせないのか」というメッセージ。長く非正規雇用で働いてきた私が、ずっとずっと思っていたことだ。正規雇用で働けている現在も、この疑問は持ち続けている。 第5章に書かれていた「500円のランチが高いので、100円のパンを食べる」というのは、私も経験してきた。でも、ペットボトルの水のみという経験していないので、見えていなかったことも多くあると感じる。 高度成長の時代にも日雇い労働者はいたと思うのだが、その当時は今のような問題がなかったのだろうかという疑問は残る。
ルポ 低賃金東海林智読み終わった買った帯に書かれている「なぜ、この国では、普通に働いても、普通に暮らせないのか」というメッセージ。長く非正規雇用で働いてきた私が、ずっとずっと思っていたことだ。正規雇用で働けている現在も、この疑問は持ち続けている。 第5章に書かれていた「500円のランチが高いので、100円のパンを食べる」というのは、私も経験してきた。でも、ペットボトルの水のみという経験していないので、見えていなかったことも多くあると感じる。 高度成長の時代にも日雇い労働者はいたと思うのだが、その当時は今のような問題がなかったのだろうかという疑問は残る。 - 2025年10月21日
- 2025年10月4日
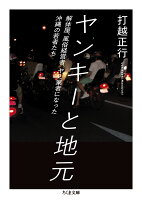 ヤンキーと地元打越正行読み終わった買った以前、「地元を生きる」を読んだときに、打越さんのことを知った。いつか、お会いしてみたいと思っていた人だった。 沖縄は、家族や親戚、ご近所などの人間関係は良好だという勝手なイメージを持っていたことを申し訳なく思う。打越さんの調査がなければ、知らないままだったことを教えてもらえたことに感謝している。
ヤンキーと地元打越正行読み終わった買った以前、「地元を生きる」を読んだときに、打越さんのことを知った。いつか、お会いしてみたいと思っていた人だった。 沖縄は、家族や親戚、ご近所などの人間関係は良好だという勝手なイメージを持っていたことを申し訳なく思う。打越さんの調査がなければ、知らないままだったことを教えてもらえたことに感謝している。 - 2025年10月4日
 「いきり」の構造武田砂鉄読み終わった買った23章「自分で考える」に、私が発信力のある人に言ってほしいことが書かれていて、うれしかった。なぜ、自分がいつも優位でいられると思う人がいるのか、本当に不思議だ。「誰だって、明日から、彼らの設定するファーストではなく、セカンドに転げ落ちるかもしれない。」「物議をかもす発言で人を操ろうとする人は、そちら側にはいかない確信があるようだが、そんなはずがない。」
「いきり」の構造武田砂鉄読み終わった買った23章「自分で考える」に、私が発信力のある人に言ってほしいことが書かれていて、うれしかった。なぜ、自分がいつも優位でいられると思う人がいるのか、本当に不思議だ。「誰だって、明日から、彼らの設定するファーストではなく、セカンドに転げ落ちるかもしれない。」「物議をかもす発言で人を操ろうとする人は、そちら側にはいかない確信があるようだが、そんなはずがない。」 - 2025年9月12日
 エッセイストのように生きる松浦弥太郎読み終わった買った第二章に書かれている「自分を見つめ続けてきたから、どんなときに体や心の調子がよく、どんなときにバランスを崩してしまうのかを把握できるようになった。」ということ。私も、もっとできるようになりたい。 第三章、“「知る」と「わかる」はまったく違うものです。”は、何となく気付いていたけど、気にしないふりをしていたかも。“なんでもかんでも浅く知るより、自分の中にいくつかの「わかった」があるほうが自分の軸が太くなります。”も心に留めておきたい。 第5章に書かれている「自分の心にあるほんとうのことをありのままに告白している文章が、人の心にいちばん届くし、いつまでも残りつづけるのです。」ということは、実感として理解できるし、松浦さんもそう考えていらっしゃることがうれしかった。
エッセイストのように生きる松浦弥太郎読み終わった買った第二章に書かれている「自分を見つめ続けてきたから、どんなときに体や心の調子がよく、どんなときにバランスを崩してしまうのかを把握できるようになった。」ということ。私も、もっとできるようになりたい。 第三章、“「知る」と「わかる」はまったく違うものです。”は、何となく気付いていたけど、気にしないふりをしていたかも。“なんでもかんでも浅く知るより、自分の中にいくつかの「わかった」があるほうが自分の軸が太くなります。”も心に留めておきたい。 第5章に書かれている「自分の心にあるほんとうのことをありのままに告白している文章が、人の心にいちばん届くし、いつまでも残りつづけるのです。」ということは、実感として理解できるし、松浦さんもそう考えていらっしゃることがうれしかった。
読み込み中...




