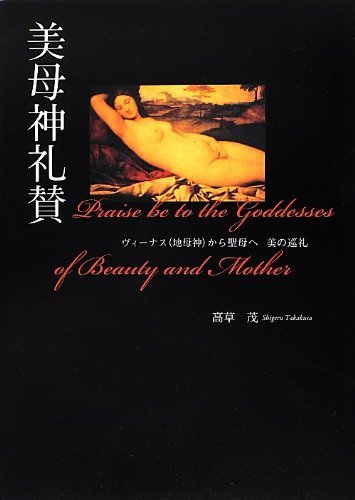ayame
@tsukinofune
すべて自己満足の感想および独り言
- 2026年1月25日
 怪物たちの食卓:物語を食べる赤坂憲雄読み終わった
怪物たちの食卓:物語を食べる赤坂憲雄読み終わった - 2026年1月3日
 サンダカン八番娼館新装版山崎朋子気になる読みたい
サンダカン八番娼館新装版山崎朋子気になる読みたい - 2026年1月3日
 影を買う店皆川博子気になる読みたい
影を買う店皆川博子気になる読みたい - 2026年1月3日
 サロメの断頭台夕木春央気になる読みたい
サロメの断頭台夕木春央気になる読みたい - 2026年1月3日
 べにはこべ (河出文庫)バロネス・オルツィ気になる読みたい
べにはこべ (河出文庫)バロネス・オルツィ気になる読みたい - 2026年1月3日
 夜ふけに読みたい数奇なアイルランドのおとぎ話 夜ふけに読みたいおとぎ話加藤洋子,吉澤康子,和爾桃子,長島真以於気になる読みたい
夜ふけに読みたい数奇なアイルランドのおとぎ話 夜ふけに読みたいおとぎ話加藤洋子,吉澤康子,和爾桃子,長島真以於気になる読みたい - 2026年1月3日
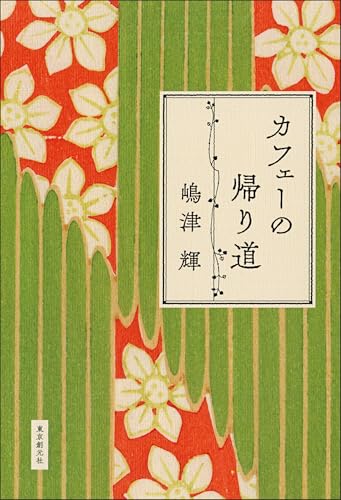 カフェーの帰り道嶋津輝気になる読みたい
カフェーの帰り道嶋津輝気になる読みたい - 2025年11月26日
- 2025年11月18日
 ペネロピアド 女たちのオデュッセイア (角川文庫)マーガレット・アトウッド,鴻巣友季子読み終わった「オデュッセイア」の英雄・オデュッセウスが20数年もの冒険を続けた間、彼の留守を守ったとしてその良妻と貞節ぶりが讃えられるペネロペイアはその実どんな女であったのか? 彼女の結婚生活の実態とは? という方面から「オデュッセイア」を女たちの視点から翻案し、古典を語り直したいわゆるリトールドものの作品。 そのなかでもこの作品は語る女の声がペネロペイア1人のものだけでなく、いろんな女の声が多様な形式(遊び歌や舟歌、牧歌、芝居、講義、裁判風など)で再現されていて、それが本筋のペネロペイアの語りとは異なる事実を語るものだから、真実を紐解こうとすると一筋縄ではいかない。 いろんな女の声が響くから、主人公のペネロペイアの語りでさえどこまで本当のものか実は最後まではっきりとは分からないところが個人的に強い引きを持って絶妙な読後感を与えて好き。 なかでも強い存在感を放っていたのはペネロペイアに従っていた12人の女中たちで、古典「オデュッセイア」では彼女たちはオデュッセウスやその息子テレマコスに首吊り処刑を命じられる。 その理由が「主人(オデュッセウス)の留守中に主人の許可なく客人に凌辱されたから」という限りなく理不尽で信じられないもので、こいつ20何年も留守にしていたくせにマジかよと正直ドン引いた。 (しかも客人からの誘いを女中の彼女たちが断る術もないので、なぜ女たちばかりが知恵を働かせて男たちから逃げなければならないんだ神話ってほんとそういうとこ〜〜とちょっとした怒りが湧くなどした) 鴻巣氏もあとがきで言及しているが、女性の被害者ほど語ろうとする口を押さえつけられ処罰されるのは古代から変わらないらしい。 その乙女たちの運命は今作「ペネロピアド」でも変わらないが、なぜ彼女たちは処刑されたのか? ということを後世の人間(私たち)による神話の解釈としてではなく、生身の彼女本人たちの「どうして」という悲鳴と疑念で語らせたのがこの翻案作品の真骨頂のひとつだと思う。 (私たちはついこの12人の少女たちの首吊り処刑を物語の出来事として捉えてしまうけど、それが良しとされ語られてきた背景には実際にそうやって排除されてきた人たちの存在があったはずなので) 主人公のペネロペイアについては、おそらく私がこの12人の処刑をめぐる一連がすごくショックで若干見方が偏っているからなんだけど、あとがきと解説ほどペネロペイアを賞賛することはできなかった。 時代が時代だから今の価値観で神話時代の女性である彼女を語ることはフェアじゃないけど、ペネロペイアだってなんかずるくない!? と思う部分があったので、そんな言うほど乙女たちの気持ちを汲んだ女主人じゃなくない? という感じが今のところ拭えない。(ここはまだあまり自分のなかで腑に落ちていないのと考えが固まっていないので、今後感じ方が変わっていくかも) ただ、それがこの作品の悪い読後感を与えているということはまったくなく、この作品の女たちは連帯できていないと解説でも述べられていたように、男性優位社会に抗い閉ざしていた口を開いた女が清廉潔白な女でなければならないということはまったくないので、ペネロペイアもまた生々しい1人の女として描かれていたんだなという感想に落ち着いている。 彼女が生前オデュッセウスの資質に惑わされていたと語るように、きっと冥界に落ちた現在のペネロペイアも未だオデュッセウスを自らの夫として完全に切り離して見ることができず、その価値観の支配から逃れられていないんだろうなと、今のところそう読んでいる。 この主人公の生々しさも含めて、語る口を持たなかった女たちが死後語る口を持ち、しかしその語りも風のように音にならないという物語(しかも主人公のペネロペイアと違って女中たちの語りはもっとはるかに現実味に欠けている)が個人的に好きで面白かったので、本編、あとがき、解説すべて込みで読めて本当によかった。 ❄️ここからは鏡花も絡めた話⤵︎ 被害女性が語る口を持たず、理不尽に罰せられ、沈黙させられる話、また古典の語り直し作品という意味では鏡花もリトールドものを書いていたと言えるなぁと思ったけど、アトウッドはそこから死後の女に語らせたのが面白かった。 ここは古代ギリシャと日本の死後世界観の違いが出ているんだろうと思う。 ただ、だからといってアトウッドのほうが秀作と言いたいわけではなく、今作の「ペネロピアド」がもう覆らない運命を死後から語り直す話とするなら、鏡花作品は生前も死後も語り得ない女が語る"口"や"言葉"を持たない代わりに自らの形容や周囲の自然環境を変化させて雄弁にものを語る話と言えて、同じ「語れない女」というテーマは生まれるのに作者や文化圏の違いでまったく違う作風が生まれるんだなと、読んでいてその違いが楽しかった。
ペネロピアド 女たちのオデュッセイア (角川文庫)マーガレット・アトウッド,鴻巣友季子読み終わった「オデュッセイア」の英雄・オデュッセウスが20数年もの冒険を続けた間、彼の留守を守ったとしてその良妻と貞節ぶりが讃えられるペネロペイアはその実どんな女であったのか? 彼女の結婚生活の実態とは? という方面から「オデュッセイア」を女たちの視点から翻案し、古典を語り直したいわゆるリトールドものの作品。 そのなかでもこの作品は語る女の声がペネロペイア1人のものだけでなく、いろんな女の声が多様な形式(遊び歌や舟歌、牧歌、芝居、講義、裁判風など)で再現されていて、それが本筋のペネロペイアの語りとは異なる事実を語るものだから、真実を紐解こうとすると一筋縄ではいかない。 いろんな女の声が響くから、主人公のペネロペイアの語りでさえどこまで本当のものか実は最後まではっきりとは分からないところが個人的に強い引きを持って絶妙な読後感を与えて好き。 なかでも強い存在感を放っていたのはペネロペイアに従っていた12人の女中たちで、古典「オデュッセイア」では彼女たちはオデュッセウスやその息子テレマコスに首吊り処刑を命じられる。 その理由が「主人(オデュッセウス)の留守中に主人の許可なく客人に凌辱されたから」という限りなく理不尽で信じられないもので、こいつ20何年も留守にしていたくせにマジかよと正直ドン引いた。 (しかも客人からの誘いを女中の彼女たちが断る術もないので、なぜ女たちばかりが知恵を働かせて男たちから逃げなければならないんだ神話ってほんとそういうとこ〜〜とちょっとした怒りが湧くなどした) 鴻巣氏もあとがきで言及しているが、女性の被害者ほど語ろうとする口を押さえつけられ処罰されるのは古代から変わらないらしい。 その乙女たちの運命は今作「ペネロピアド」でも変わらないが、なぜ彼女たちは処刑されたのか? ということを後世の人間(私たち)による神話の解釈としてではなく、生身の彼女本人たちの「どうして」という悲鳴と疑念で語らせたのがこの翻案作品の真骨頂のひとつだと思う。 (私たちはついこの12人の少女たちの首吊り処刑を物語の出来事として捉えてしまうけど、それが良しとされ語られてきた背景には実際にそうやって排除されてきた人たちの存在があったはずなので) 主人公のペネロペイアについては、おそらく私がこの12人の処刑をめぐる一連がすごくショックで若干見方が偏っているからなんだけど、あとがきと解説ほどペネロペイアを賞賛することはできなかった。 時代が時代だから今の価値観で神話時代の女性である彼女を語ることはフェアじゃないけど、ペネロペイアだってなんかずるくない!? と思う部分があったので、そんな言うほど乙女たちの気持ちを汲んだ女主人じゃなくない? という感じが今のところ拭えない。(ここはまだあまり自分のなかで腑に落ちていないのと考えが固まっていないので、今後感じ方が変わっていくかも) ただ、それがこの作品の悪い読後感を与えているということはまったくなく、この作品の女たちは連帯できていないと解説でも述べられていたように、男性優位社会に抗い閉ざしていた口を開いた女が清廉潔白な女でなければならないということはまったくないので、ペネロペイアもまた生々しい1人の女として描かれていたんだなという感想に落ち着いている。 彼女が生前オデュッセウスの資質に惑わされていたと語るように、きっと冥界に落ちた現在のペネロペイアも未だオデュッセウスを自らの夫として完全に切り離して見ることができず、その価値観の支配から逃れられていないんだろうなと、今のところそう読んでいる。 この主人公の生々しさも含めて、語る口を持たなかった女たちが死後語る口を持ち、しかしその語りも風のように音にならないという物語(しかも主人公のペネロペイアと違って女中たちの語りはもっとはるかに現実味に欠けている)が個人的に好きで面白かったので、本編、あとがき、解説すべて込みで読めて本当によかった。 ❄️ここからは鏡花も絡めた話⤵︎ 被害女性が語る口を持たず、理不尽に罰せられ、沈黙させられる話、また古典の語り直し作品という意味では鏡花もリトールドものを書いていたと言えるなぁと思ったけど、アトウッドはそこから死後の女に語らせたのが面白かった。 ここは古代ギリシャと日本の死後世界観の違いが出ているんだろうと思う。 ただ、だからといってアトウッドのほうが秀作と言いたいわけではなく、今作の「ペネロピアド」がもう覆らない運命を死後から語り直す話とするなら、鏡花作品は生前も死後も語り得ない女が語る"口"や"言葉"を持たない代わりに自らの形容や周囲の自然環境を変化させて雄弁にものを語る話と言えて、同じ「語れない女」というテーマは生まれるのに作者や文化圏の違いでまったく違う作風が生まれるんだなと、読んでいてその違いが楽しかった。 - 2025年10月30日
 呪文の言語学角悠介読み終わった
呪文の言語学角悠介読み終わった - 2025年9月5日
 蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか野村育世読み終わった
蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか野村育世読み終わった - 2025年8月19日
 人魚が逃げた青山美智子気になる
人魚が逃げた青山美智子気になる - 2025年8月8日
- 2025年7月28日
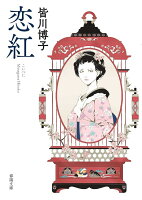 恋紅皆川博子読み終わった
恋紅皆川博子読み終わった - 2025年7月3日
 きもの幸田文読み終わったこれが幸田文最後の長編とか自伝的小説というのは読み終わってから知ったけど、最初にしていちばんの大当たりを引いたかもしれない。 すじとしては着物をめぐって主人公・西垣るつ子の人生が語られていくという話。 自分や人の着るもの、その素材や形、肌触りや用途、扱いを通して人間の観察眼やら道徳やモラルやら処世術みたいなものを身につけていくという大筋だけど、るつ子の感性の鋭さとかそれゆえの生きづらさや息苦しさが地の文の語りからひしひしと伝わってきてすごくるつ子に感情移入?というか共感みたいなものが起きた。 物語後半、関東大震災に遭って着るものの難にあたったとき 「肌をかくせればそれでいい、寒さをしのげればそれでいい、なおその上に洗い替えの予備がひと揃いあればこの上ないのである。ここが着るものの一番はじめの出発点ともいうべきところ、これ以下では苦になり、これ以上なら楽と考えなければちがう。(中略)しかしまた逆に考えると、それほどのひどい目に逢わなければ、着物の出発点は摑むことが出来ないくらい、女は着るものへ妄執をもっている、ということでもある」 とあるけど、幸田文の没後から30年以上経った今でもいろいろ思わされる文章だった。 るつ子のほかにるつ子の良き理解者であり人生の導き手であるおばあさん、田舎の雪国育ちであり東京に嫁してきたことになにか思うところのあるお母さん、性質がまったく違ううえにお互いまったく理解し合えない上の姉と中の姉、3人で仲良しの友達のゆう子と和子、ひょんなことで縁ができた清村その、といろんな女性が出てくるのも特徴だけど、この女性陣たちの間にある関係性やるつ子の目を通した人物像の描写も面白い。 すごく心を引っ掻いてきて残るという意味ではるつ子とお母さんの関係が印象深い。 でもやっぱりおばあさんとるつ子の連帯が今作いちばん好きだな。 書評によると幸田文がこの作品を「未完」と評していたらしくマッジでそこで終わる!?!?(中途半端なところで終わるという意味ではなくて、引きが強すぎる終わりという意味で)てところで終わっていたので物語への大きい満足感と同時にかなり悲しさを感じた。 令和の作品のるつ子だったら報われたかもしれないがそうもいかないのが厳しいよ幸田文。もうちょっと生きて書き切ってほしかったよ幸田文。 教養本という枠に当てはめたくないが確かに人生の手解きが書かれてあるなーと感じたしそれが好きだったので、そこが幸田文文学の旨味なのかもしれない。 久々に作家買い作家読みしたくなった素敵な作品だったので、次本を買うとき幸田文のなにかしらをリストに入れるかも。
きもの幸田文読み終わったこれが幸田文最後の長編とか自伝的小説というのは読み終わってから知ったけど、最初にしていちばんの大当たりを引いたかもしれない。 すじとしては着物をめぐって主人公・西垣るつ子の人生が語られていくという話。 自分や人の着るもの、その素材や形、肌触りや用途、扱いを通して人間の観察眼やら道徳やモラルやら処世術みたいなものを身につけていくという大筋だけど、るつ子の感性の鋭さとかそれゆえの生きづらさや息苦しさが地の文の語りからひしひしと伝わってきてすごくるつ子に感情移入?というか共感みたいなものが起きた。 物語後半、関東大震災に遭って着るものの難にあたったとき 「肌をかくせればそれでいい、寒さをしのげればそれでいい、なおその上に洗い替えの予備がひと揃いあればこの上ないのである。ここが着るものの一番はじめの出発点ともいうべきところ、これ以下では苦になり、これ以上なら楽と考えなければちがう。(中略)しかしまた逆に考えると、それほどのひどい目に逢わなければ、着物の出発点は摑むことが出来ないくらい、女は着るものへ妄執をもっている、ということでもある」 とあるけど、幸田文の没後から30年以上経った今でもいろいろ思わされる文章だった。 るつ子のほかにるつ子の良き理解者であり人生の導き手であるおばあさん、田舎の雪国育ちであり東京に嫁してきたことになにか思うところのあるお母さん、性質がまったく違ううえにお互いまったく理解し合えない上の姉と中の姉、3人で仲良しの友達のゆう子と和子、ひょんなことで縁ができた清村その、といろんな女性が出てくるのも特徴だけど、この女性陣たちの間にある関係性やるつ子の目を通した人物像の描写も面白い。 すごく心を引っ掻いてきて残るという意味ではるつ子とお母さんの関係が印象深い。 でもやっぱりおばあさんとるつ子の連帯が今作いちばん好きだな。 書評によると幸田文がこの作品を「未完」と評していたらしくマッジでそこで終わる!?!?(中途半端なところで終わるという意味ではなくて、引きが強すぎる終わりという意味で)てところで終わっていたので物語への大きい満足感と同時にかなり悲しさを感じた。 令和の作品のるつ子だったら報われたかもしれないがそうもいかないのが厳しいよ幸田文。もうちょっと生きて書き切ってほしかったよ幸田文。 教養本という枠に当てはめたくないが確かに人生の手解きが書かれてあるなーと感じたしそれが好きだったので、そこが幸田文文学の旨味なのかもしれない。 久々に作家買い作家読みしたくなった素敵な作品だったので、次本を買うとき幸田文のなにかしらをリストに入れるかも。 - 2025年6月18日
 誇りと偏見ジェーン・オースティン読み終わった・個人的によいな〜と感じた文章 「自分の洞察力を誇っていたこの私が! ──能力があると自負していたこの私が! 心が広く公平無私な姉を見下し、姉に無益で非難されるべき不信を向けて私自身の虚栄心を満たそうとしていた。──そう発見するとは、何と屈辱的なことか! ──それでいて、その屈辱は何と正当であることか! もし私が恋をしていたとしても、これほど盲目になれた筈がない。でも恋ではなく、虚栄が私の愚行をもたらしたのだ。(中略)この瞬間まで、私は自分自身を知らなかった」 映画は尺があるからいろいろ省かれるのは仕方ないとして(それでも2005年のキーラ・ナイトレイ主演「プライドと偏見」は観るに値する映画だと思う)、単に恋愛小説と読むには表題の"pride"の扱いがさまざまで面白くて、その味わいは小説でしか味わえないものだなーと思った。 内容としては古くさくないし現代にも通じる面白さがある。 特にエリザベスとダーシーが互いを通して自分のなかの高慢を見つけて葛藤し、それに苦心しながら克服しようとして互いを1人の人間として見つめる過程が彼らの恋愛の過程として描かれているのが好き。これを19世紀にして描けたオースティンが凄い。 電子版ゆえの弊害なのかなにか分からないけど、不自然な改行や空白があったり校正ルールが一貫していないのが少し気になった。 翻訳に関してはおそらく原文に忠実に訳しているので文章はやや複雑化しているけど、意味が汲み取れないほどではないし当時の文化を知るための註は適度にあって理解しやすい。 ただある程度の意訳で読みやすさを優先したいなら別の翻訳版でもいいかなという気はする。
誇りと偏見ジェーン・オースティン読み終わった・個人的によいな〜と感じた文章 「自分の洞察力を誇っていたこの私が! ──能力があると自負していたこの私が! 心が広く公平無私な姉を見下し、姉に無益で非難されるべき不信を向けて私自身の虚栄心を満たそうとしていた。──そう発見するとは、何と屈辱的なことか! ──それでいて、その屈辱は何と正当であることか! もし私が恋をしていたとしても、これほど盲目になれた筈がない。でも恋ではなく、虚栄が私の愚行をもたらしたのだ。(中略)この瞬間まで、私は自分自身を知らなかった」 映画は尺があるからいろいろ省かれるのは仕方ないとして(それでも2005年のキーラ・ナイトレイ主演「プライドと偏見」は観るに値する映画だと思う)、単に恋愛小説と読むには表題の"pride"の扱いがさまざまで面白くて、その味わいは小説でしか味わえないものだなーと思った。 内容としては古くさくないし現代にも通じる面白さがある。 特にエリザベスとダーシーが互いを通して自分のなかの高慢を見つけて葛藤し、それに苦心しながら克服しようとして互いを1人の人間として見つめる過程が彼らの恋愛の過程として描かれているのが好き。これを19世紀にして描けたオースティンが凄い。 電子版ゆえの弊害なのかなにか分からないけど、不自然な改行や空白があったり校正ルールが一貫していないのが少し気になった。 翻訳に関してはおそらく原文に忠実に訳しているので文章はやや複雑化しているけど、意味が汲み取れないほどではないし当時の文化を知るための註は適度にあって理解しやすい。 ただある程度の意訳で読みやすさを優先したいなら別の翻訳版でもいいかなという気はする。 - 2025年5月7日
 ウィステリアと三人の女たち川上未映子読み終わった
ウィステリアと三人の女たち川上未映子読み終わった
読み込み中...