
はじめ
@vishaz8014
- 2025年11月3日
- 2025年11月3日
- 2025年11月3日
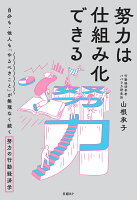 読み終わった仕組み化。習慣化。 すごく、したい。 流行りと言われればそれまでだが、今、習慣にしたいことがあるので流行りにでも乗る。 というわけで、「努力は仕組み化できる」努力の行動経済学。行動経済学というのも陳腐になったものだとも思う。 読み始めはまあまあの好感触(この手の本は、文体なのか書き方なのか、合わないものもあるため)で読み進められそう。 (11/01読み始め) 内容メモ) 異時点間の選択問題(今もらえる1000円と一年後もらえる1500円)では、「待つという心的コスト」が高い人(待つのが苦手)より待てる人の方が優れているように思える。しかし心的コストは人により異なるためどちらを選べば生涯効用が高くなるかは人により違っていておかしくない。各個人が生涯効用を最大化できていれば回答自体は全く問題ではない。問題なのは生涯効用を最大化できないケース(自分にとって最良の選択を行えていない)。 フィードバックは努力に効果的だが、フィードバックがあるだけでは効果がない時もある。鍵はフィードバックで得られた情報を目標設定に生かすことができたか。 フィードフォワードも効果的。フィードフォワードの方が自分で意思決定した感じが強いため、満足度が高い。 実行意図(どこで、いつ、どのように行うか)を作る(漠然としているより具体的に決める)と効果がある。ただし実行意図はやめる努力には適さない。 自動化されるには、行動により日数が異なる。中央値は66日。 内発的動機付け>外発的動機付け ナッジ=強制するのではなく、よりよい選択肢を気づかせる デフォルト・ナッジ=初期設定に従ってしまう 努力には、努力が得意な人と不得意な人という個人差があり、苦手な人はデフォルト・ナッジの効果を受けやすい EASTフレームワーク=効果的なナッジのポイント Easy 簡単にすること Attractive 興味を引くようにすること Social 社会的にすること Timely タイムリーにすること 努力できない理由 ソフィスティケイテッド=目先の利益に目が眩みがちで最終的に後悔する可能性があると自覚がある人 ナイーフ=その自覚がない人 ソフィスティケイテッドが使う手立て→コミットメント=将来の自分が誘惑に負けないように事前に行っておく工夫(行動を縛っておく) 性格は変えられないが、ナイーフがソフィスティケイテッドになることはできる(行動は変えられる)→コミットメントなど、努力するための工夫を行う 内的統制=自分の力が結果に関係する 外的統制=全ては運で決まる 内的統制が強い方が低所得でも不幸を感じない、リハビリ後の予後が良い、など 外的統制タイプなら周囲の力を適切に借りる 運の捉え方や幸運の自覚は努力に大きく影響する 自分は幸運だ、どうにかなるというポジティブさは美徳だが努力を妨げる悪癖となる可能性もある 楽観的であるほど死亡率が低く手術からの復活率が高い 「楽観主義は赤ワインのようなもの」ほどほどの楽観はいい影響を招くが行き過ぎると危険 行き過ぎた楽観主義の人は長期的な計画で資産運用を行っていなかった→将来をきちんと考えられていない 過度のどうにかなるだろう、は危険 (過度の楽観主義=楽観バイアス) どんな努力であれ、続けたいなら環境を変えてはいけない こうなりたい、という習慣を持つ人たちの中に身を置いた方が努力が継続しやすい 「今は我慢という努力をした方がいい」「今目の前にある利益をとった方がいい」という二つの自分が存在し、この間で意見が揺れることが後悔を引き起こす 今の自分に直接関係ないことについては我慢しろと言い、今の自分が関係することについては我慢できないと思う一貫性のなさが問題 努力の弊害→サンクコスト=既にかけたコストのうち、どう頑張っても回収できない費用 努力したという事実がよくない選択に導いてしまう可能性(後に引けなくなる) 例)コンコルドの誤謬 大事なのは、サンクコストが発生する前に時が戻ったら自分はどうするか、を考える 感想) 個人的には面白かった。四つほど自分の尺度を測れるテストがあり、それを実際にしてみて自分は中庸な人間なのだと分かった。 気になる点として、実験例(研究例)が多数出てくるのだが、それらの結果の棒グラフに標準偏差が示されていないこと。 時々統計的に優位、という言葉が出てくること(時々なので、書かれていない時は本当に優位なのか?と思ってしまう)。 知らなかった!素晴らしい本だ!という感覚はない。行動経済学がこれだけ世に広がっているので、これはどこかで読んだな、という例が多い。 しかし、努力という観点でまとめなおし、一つにしたということで面白いと思う。 (11/3読了)
読み終わった仕組み化。習慣化。 すごく、したい。 流行りと言われればそれまでだが、今、習慣にしたいことがあるので流行りにでも乗る。 というわけで、「努力は仕組み化できる」努力の行動経済学。行動経済学というのも陳腐になったものだとも思う。 読み始めはまあまあの好感触(この手の本は、文体なのか書き方なのか、合わないものもあるため)で読み進められそう。 (11/01読み始め) 内容メモ) 異時点間の選択問題(今もらえる1000円と一年後もらえる1500円)では、「待つという心的コスト」が高い人(待つのが苦手)より待てる人の方が優れているように思える。しかし心的コストは人により異なるためどちらを選べば生涯効用が高くなるかは人により違っていておかしくない。各個人が生涯効用を最大化できていれば回答自体は全く問題ではない。問題なのは生涯効用を最大化できないケース(自分にとって最良の選択を行えていない)。 フィードバックは努力に効果的だが、フィードバックがあるだけでは効果がない時もある。鍵はフィードバックで得られた情報を目標設定に生かすことができたか。 フィードフォワードも効果的。フィードフォワードの方が自分で意思決定した感じが強いため、満足度が高い。 実行意図(どこで、いつ、どのように行うか)を作る(漠然としているより具体的に決める)と効果がある。ただし実行意図はやめる努力には適さない。 自動化されるには、行動により日数が異なる。中央値は66日。 内発的動機付け>外発的動機付け ナッジ=強制するのではなく、よりよい選択肢を気づかせる デフォルト・ナッジ=初期設定に従ってしまう 努力には、努力が得意な人と不得意な人という個人差があり、苦手な人はデフォルト・ナッジの効果を受けやすい EASTフレームワーク=効果的なナッジのポイント Easy 簡単にすること Attractive 興味を引くようにすること Social 社会的にすること Timely タイムリーにすること 努力できない理由 ソフィスティケイテッド=目先の利益に目が眩みがちで最終的に後悔する可能性があると自覚がある人 ナイーフ=その自覚がない人 ソフィスティケイテッドが使う手立て→コミットメント=将来の自分が誘惑に負けないように事前に行っておく工夫(行動を縛っておく) 性格は変えられないが、ナイーフがソフィスティケイテッドになることはできる(行動は変えられる)→コミットメントなど、努力するための工夫を行う 内的統制=自分の力が結果に関係する 外的統制=全ては運で決まる 内的統制が強い方が低所得でも不幸を感じない、リハビリ後の予後が良い、など 外的統制タイプなら周囲の力を適切に借りる 運の捉え方や幸運の自覚は努力に大きく影響する 自分は幸運だ、どうにかなるというポジティブさは美徳だが努力を妨げる悪癖となる可能性もある 楽観的であるほど死亡率が低く手術からの復活率が高い 「楽観主義は赤ワインのようなもの」ほどほどの楽観はいい影響を招くが行き過ぎると危険 行き過ぎた楽観主義の人は長期的な計画で資産運用を行っていなかった→将来をきちんと考えられていない 過度のどうにかなるだろう、は危険 (過度の楽観主義=楽観バイアス) どんな努力であれ、続けたいなら環境を変えてはいけない こうなりたい、という習慣を持つ人たちの中に身を置いた方が努力が継続しやすい 「今は我慢という努力をした方がいい」「今目の前にある利益をとった方がいい」という二つの自分が存在し、この間で意見が揺れることが後悔を引き起こす 今の自分に直接関係ないことについては我慢しろと言い、今の自分が関係することについては我慢できないと思う一貫性のなさが問題 努力の弊害→サンクコスト=既にかけたコストのうち、どう頑張っても回収できない費用 努力したという事実がよくない選択に導いてしまう可能性(後に引けなくなる) 例)コンコルドの誤謬 大事なのは、サンクコストが発生する前に時が戻ったら自分はどうするか、を考える 感想) 個人的には面白かった。四つほど自分の尺度を測れるテストがあり、それを実際にしてみて自分は中庸な人間なのだと分かった。 気になる点として、実験例(研究例)が多数出てくるのだが、それらの結果の棒グラフに標準偏差が示されていないこと。 時々統計的に優位、という言葉が出てくること(時々なので、書かれていない時は本当に優位なのか?と思ってしまう)。 知らなかった!素晴らしい本だ!という感覚はない。行動経済学がこれだけ世に広がっているので、これはどこかで読んだな、という例が多い。 しかし、努力という観点でまとめなおし、一つにしたということで面白いと思う。 (11/3読了) - 2025年10月31日
- 2025年10月26日
- 2025年10月24日
 「遅読」のすすめ齋藤孝読み終わった最近本を読んでない、と焦った気持ちで読んでしまうので、それにストップをかけてくれそうで読み始める。 一番気になるのは第3章遅読の具体的な方法、次に第5章。 (第1章は、遅読とは何か、第2章は、遅読をすると何が変わるのか、第4章は、遅読に向いている本とは、第5章は、遅読力を鍛え、読書の質を高める) 気になるところを重点的に読書中(10/19)。 第3章 遅読で使える七つの技術 1.場を作る 読む時間、場所の設定 2.読む仲間を作る 3.SNSを記録に使う 4.読んだことを即アウトプットする 引用の引き出しを増やし活用する 5.多色ボールペンで線を引く(これは個人的には感心しない、本は綺麗なままがいい) 6.ドッグイヤーをつくる(これも感心しない) 7.日付を入れる 本には読むための最適時間がセットされている(読むためのスピードは本の方が決めている) 実用書や新書は速読と遅読を組み合わせて読む(気になるところを何度も読む) 第5章 読書の時間を確保する→時間枠を設定する(通勤時間中は読書時間にしてしまう、など) スマホを目の前から消す スマホは必要な時に確認にいく(30分に一回くらい) 少なくとも読書するときは視界から消す(そうでなくても、自分の時間を大切にしたいならスマホとの距離感について考えてみてもいいかも→これは納得、考えなおしたい) ちょっとずつ無理なく続ける(散歩と同じ) 習慣にしてしまえばこっちのもの 年齢によって最適な読み方を考える 読書でメンタルをととのえる(槙島的にいうチューニングか、紙の本を読みなよ) 知性の足腰を鍛える タイパやコスパではなく、過程を楽しむ 読書は急ぐ必要のない旅 感想) タイトルから想像される通り。 この本を読んだからといって遅読できたり、読書習慣が身につくものではない(当たり前か) 実用書との向き合い方も、その通り。 遅読と速読の併用。 第4章は面白いかも。 読了(10/24)
「遅読」のすすめ齋藤孝読み終わった最近本を読んでない、と焦った気持ちで読んでしまうので、それにストップをかけてくれそうで読み始める。 一番気になるのは第3章遅読の具体的な方法、次に第5章。 (第1章は、遅読とは何か、第2章は、遅読をすると何が変わるのか、第4章は、遅読に向いている本とは、第5章は、遅読力を鍛え、読書の質を高める) 気になるところを重点的に読書中(10/19)。 第3章 遅読で使える七つの技術 1.場を作る 読む時間、場所の設定 2.読む仲間を作る 3.SNSを記録に使う 4.読んだことを即アウトプットする 引用の引き出しを増やし活用する 5.多色ボールペンで線を引く(これは個人的には感心しない、本は綺麗なままがいい) 6.ドッグイヤーをつくる(これも感心しない) 7.日付を入れる 本には読むための最適時間がセットされている(読むためのスピードは本の方が決めている) 実用書や新書は速読と遅読を組み合わせて読む(気になるところを何度も読む) 第5章 読書の時間を確保する→時間枠を設定する(通勤時間中は読書時間にしてしまう、など) スマホを目の前から消す スマホは必要な時に確認にいく(30分に一回くらい) 少なくとも読書するときは視界から消す(そうでなくても、自分の時間を大切にしたいならスマホとの距離感について考えてみてもいいかも→これは納得、考えなおしたい) ちょっとずつ無理なく続ける(散歩と同じ) 習慣にしてしまえばこっちのもの 年齢によって最適な読み方を考える 読書でメンタルをととのえる(槙島的にいうチューニングか、紙の本を読みなよ) 知性の足腰を鍛える タイパやコスパではなく、過程を楽しむ 読書は急ぐ必要のない旅 感想) タイトルから想像される通り。 この本を読んだからといって遅読できたり、読書習慣が身につくものではない(当たり前か) 実用書との向き合い方も、その通り。 遅読と速読の併用。 第4章は面白いかも。 読了(10/24) - 2025年10月19日
読み込み中...





