民族とネイション

13件の記録
- チャモピーピーチャマ@chu_berry2026年2月2日ちょっと開いた第1章でエスニシティ、民族、国家、ネイションについての定義と相互関係の類型を確認したのち近代国家以降の個別具体事例をざっとみるという構成。総論が見たかったので2-4章は流し読みしてしまった すみません ネイションと国家の相互関係(ディアスポラのように国家に少数民族としてネイションが入っている場合とか、アラブ国家のようにアラブ民族というクソデカネイションの中に国家がある場合とか)について、頭が整理された感じがある。歴史なり政治なりで民族とネイションが合致する場合は少ない、むしろ近代国家が作為によって境界を引いていることを考慮すれば一致しないことが自然と書いてあってなるほど〜と思っている あとがきの、ナショナリズム研究において個別具体の事例なしに考えることはできないという節が印象的だった。ベネディクトアンダーソンの場合、インドネシアでは「マレー語という公用語を共有するネイションとしてのインドネシア」というふうにネイションと国家が接近しているためエスニックの説明が手薄になっているという指摘、これから『想像の共同体』読もうとしてた身からすると大変ありがたい、、 個別具体の事例に取り組む必要があるといわれちゃったので、一旦は日本ないし東アジアのナショナリズムについて考えるかね 次は小熊英二『単一民族神話の起源』かなあ


 益田@msd2025年7月10日読み終わったネイション・エスニシティといった用語の定義から始めそこから各国の事例を参照して最終的には現代の問題に繋げている本。 4章以降の国際化によるナショナリズムやエスニシティが抱える問題・利点(難題)はこの2025年にまで繋がっている(というよりここ最近で顕著になっている)ので読み応えがあった。 紛争や戦争の問題にかなり慎重な姿勢で書いており、それだけことの複雑怪奇さがあるのだなと実感した。 「同時に「強者」でも「弱者」でもある集団が「自分たちは弱者だ」という自己意識に基づいて集団行動をとるとき、それは往々にして「過剰防衛」ー他者の眼からみれば「過剰な攻撃」ーになってしまう。このことは民族問題に限らず、より一般的に、「強者」と「弱者」、「加害者」と「犠牲者」の線引きの難しさという問題と重なり、アイデンティティ・ポリティクスの一般的な難間をなしている。」(p186)
益田@msd2025年7月10日読み終わったネイション・エスニシティといった用語の定義から始めそこから各国の事例を参照して最終的には現代の問題に繋げている本。 4章以降の国際化によるナショナリズムやエスニシティが抱える問題・利点(難題)はこの2025年にまで繋がっている(というよりここ最近で顕著になっている)ので読み応えがあった。 紛争や戦争の問題にかなり慎重な姿勢で書いており、それだけことの複雑怪奇さがあるのだなと実感した。 「同時に「強者」でも「弱者」でもある集団が「自分たちは弱者だ」という自己意識に基づいて集団行動をとるとき、それは往々にして「過剰防衛」ー他者の眼からみれば「過剰な攻撃」ーになってしまう。このことは民族問題に限らず、より一般的に、「強者」と「弱者」、「加害者」と「犠牲者」の線引きの難しさという問題と重なり、アイデンティティ・ポリティクスの一般的な難間をなしている。」(p186)




 益田@msd2025年7月7日読んでる「ヨーロッパ諸国でエスニック・マイノリティ問題が深刻化する中で、「新右翼」「極右」「右翼ポピュリズム」等々と呼ばれる動きが各国で活性化している(中略) 新右翼は雑多な潮流を含み、全体としての特徴づけは難しいが、経済グローバル化やEU統合進展の中で自己の地位が掘り崩されていると感じる社会層=客観的状況は多様だが、少なくとも主観的には「被害者」「弱者」意識をいだく人たちーの不満を集約している面のあることが注目される。そこには、自由主義政党と社会民主党を中軸とする既存政党システムの機能不全への苛立ちが看取される。EU統合の進展の中で、政策決定が国民の手から遠ざかっていることへの反撥もこれに重なる。こうした新右翼運動の中で大きな位置を占めているのが、外国人労働者・移民の増大への反撥であることはいうまでもない。」(p153-154)
益田@msd2025年7月7日読んでる「ヨーロッパ諸国でエスニック・マイノリティ問題が深刻化する中で、「新右翼」「極右」「右翼ポピュリズム」等々と呼ばれる動きが各国で活性化している(中略) 新右翼は雑多な潮流を含み、全体としての特徴づけは難しいが、経済グローバル化やEU統合進展の中で自己の地位が掘り崩されていると感じる社会層=客観的状況は多様だが、少なくとも主観的には「被害者」「弱者」意識をいだく人たちーの不満を集約している面のあることが注目される。そこには、自由主義政党と社会民主党を中軸とする既存政党システムの機能不全への苛立ちが看取される。EU統合の進展の中で、政策決定が国民の手から遠ざかっていることへの反撥もこれに重なる。こうした新右翼運動の中で大きな位置を占めているのが、外国人労働者・移民の増大への反撥であることはいうまでもない。」(p153-154)
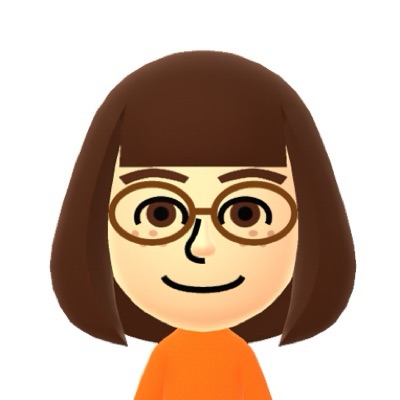


 益田@msd2025年6月30日読んでる「「国民の一体性」という観念は、現実にはそれほど広く分かちもたれたわけではない。しかし、それでも、いったん「国民国家」という自己意識をもった国家が登場すると、その国家が共通語(国家語)形成、公教育の整備、国民皆兵制度などを推進し、「国民」意識を育成するようになる。そのような政策がとられ出した後も、「国民の一体性」という観念は文字通り全国民に共有されるわけではなく、しばしば国民の中での裂が問題となるが、そうした亀裂をできるだけ覆い隠し、あたかも一体性が存在するかの如き外観が整備されていく。このようにして成立するのが「国民国家」である。」(p41)
益田@msd2025年6月30日読んでる「「国民の一体性」という観念は、現実にはそれほど広く分かちもたれたわけではない。しかし、それでも、いったん「国民国家」という自己意識をもった国家が登場すると、その国家が共通語(国家語)形成、公教育の整備、国民皆兵制度などを推進し、「国民」意識を育成するようになる。そのような政策がとられ出した後も、「国民の一体性」という観念は文字通り全国民に共有されるわけではなく、しばしば国民の中での裂が問題となるが、そうした亀裂をできるだけ覆い隠し、あたかも一体性が存在するかの如き外観が整備されていく。このようにして成立するのが「国民国家」である。」(p41)



 益田@msd2025年5月30日読んでる「「民族」は第三者的・学者的には人為的構築物と捉えられる一方、当事者にはむしろ原初的・本質的なものとして受けとめられがちだが、それはいま述べたような事情に基づくものと考えられる。実際、民族感情は外から見ると「つくられたもの」と捉えられるにしても、内からは「自然なもの」と受けとめられてこそ意味をもつ。そのことと関係して、あれこれの国のナショナリズムが対抗しているとき、相手方のナショナリズムは「政府やマスメディアによって人為的にあおられたものだ」と見えるが、自分の方のナショナリズムは「自然」に見えるということがよくある。最近の日本と中国・韓国のあいだでの歴史論争において、相手側の論調については「政治的に利用されたものだ」「上から動員されたものだ」と批判する一方、自国側については「自然な感情」とみなすといった傾向が見受けられるのも、こうした事情によって説明されるだろう。」(p35)
益田@msd2025年5月30日読んでる「「民族」は第三者的・学者的には人為的構築物と捉えられる一方、当事者にはむしろ原初的・本質的なものとして受けとめられがちだが、それはいま述べたような事情に基づくものと考えられる。実際、民族感情は外から見ると「つくられたもの」と捉えられるにしても、内からは「自然なもの」と受けとめられてこそ意味をもつ。そのことと関係して、あれこれの国のナショナリズムが対抗しているとき、相手方のナショナリズムは「政府やマスメディアによって人為的にあおられたものだ」と見えるが、自分の方のナショナリズムは「自然」に見えるということがよくある。最近の日本と中国・韓国のあいだでの歴史論争において、相手側の論調については「政治的に利用されたものだ」「上から動員されたものだ」と批判する一方、自国側については「自然な感情」とみなすといった傾向が見受けられるのも、こうした事情によって説明されるだろう。」(p35)









