あんちゃん
@an_choco
- 2025年11月29日
 善のはかなさツヴェタン・トドロフ,小野潮ブルガリアの国際関係 ・ブルガリアは「第一に、第二次バルカン戦争の結果、そして第一次大戦の結果としてらブルガリア人が部分的に移住していたいくつかの地方を失った。」 ・「南ドブルジャはルーマニア領となり、西トラキアはギリシア領となり、マケドニアはセルビア領となっており、その後セルビアはユーゴスラビアに合併される。」 =「ブルガリアの世論はこれらの地方をブルガリアの管理下へ戻したいという期待を強く示していた。」 (p14 7行目〜) ブルガリアの国内の様子 ・「1934年5月に起きた軍事クーデターは伝統的な議会の役割を弱め、さらには無に帰してしまった。」 →「執政権は国王ボリス3世によって任命され支配された政府の手に集中させられていた。」 But, その体制に反対する勢力も国会内では存在しており、権威主義的なものであったが、ファシズム体制と形容できるものではない。」 ・1941年3月、ブルガリアは枢軸国側に加わる。 枢軸国側に加わったことで、失われていたブルガリア領を取り戻すことができた。(にすぎない) (p17-18)
善のはかなさツヴェタン・トドロフ,小野潮ブルガリアの国際関係 ・ブルガリアは「第一に、第二次バルカン戦争の結果、そして第一次大戦の結果としてらブルガリア人が部分的に移住していたいくつかの地方を失った。」 ・「南ドブルジャはルーマニア領となり、西トラキアはギリシア領となり、マケドニアはセルビア領となっており、その後セルビアはユーゴスラビアに合併される。」 =「ブルガリアの世論はこれらの地方をブルガリアの管理下へ戻したいという期待を強く示していた。」 (p14 7行目〜) ブルガリアの国内の様子 ・「1934年5月に起きた軍事クーデターは伝統的な議会の役割を弱め、さらには無に帰してしまった。」 →「執政権は国王ボリス3世によって任命され支配された政府の手に集中させられていた。」 But, その体制に反対する勢力も国会内では存在しており、権威主義的なものであったが、ファシズム体制と形容できるものではない。」 ・1941年3月、ブルガリアは枢軸国側に加わる。 枢軸国側に加わったことで、失われていたブルガリア領を取り戻すことができた。(にすぎない) (p17-18) - 2025年11月20日
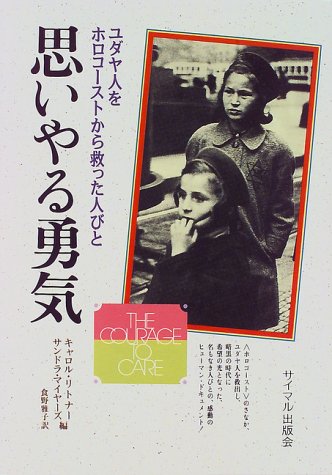 思いやる勇気: ユダヤ人をホロコーストから救った人びとキャロル・リトナー,サンドラ・マイヤーズ,食野雅子・ポーランドに住んでいた大部分のユダヤ人は、別個の民族集団を形成し、顔つきも服装もポーランド人とは違い、ポーランド語を話さず、教育のあるごく少数を除いては、すぐにユダヤ人とわかるような生活をしていた。(p.95 3行目)
思いやる勇気: ユダヤ人をホロコーストから救った人びとキャロル・リトナー,サンドラ・マイヤーズ,食野雅子・ポーランドに住んでいた大部分のユダヤ人は、別個の民族集団を形成し、顔つきも服装もポーランド人とは違い、ポーランド語を話さず、教育のあるごく少数を除いては、すぐにユダヤ人とわかるような生活をしていた。(p.95 3行目) - 2025年11月13日
 図表と地図で知るヒトラー政権下のドイツクリス・マクナブ,松尾恭子・ヒトラーは反キリスト教だった。(p.284) →キリスト教がユダヤ教から生まれたものだから。 戦争、暴力、冷酷さ、異民族への憎しみも必要だ と考えていたから。(キリスト教の教えに反する) ・ユダヤ人の犠牲者数の割合 ギリシア=87%、オランダ=71%、 スロヴァキア=80%、ドイツ=93% ポーランド=91%
図表と地図で知るヒトラー政権下のドイツクリス・マクナブ,松尾恭子・ヒトラーは反キリスト教だった。(p.284) →キリスト教がユダヤ教から生まれたものだから。 戦争、暴力、冷酷さ、異民族への憎しみも必要だ と考えていたから。(キリスト教の教えに反する) ・ユダヤ人の犠牲者数の割合 ギリシア=87%、オランダ=71%、 スロヴァキア=80%、ドイツ=93% ポーランド=91% - 2025年11月7日
 人種主義の歴史平野千果子ナチス・ドイツは「ドイツ人」であることを重要視し、ドイツ人以外、アーリア人以外の人々を迫害する人種差別の権化であった。 しかし、実際はノルウェーや人種的には劣るとみなしていたフランス、ポーランドの女性とドイツ人兵士を結婚、出産させ、その子供をドイツに送ることを推奨、活発に行われてきた。 →「ドイツ人」とは。
人種主義の歴史平野千果子ナチス・ドイツは「ドイツ人」であることを重要視し、ドイツ人以外、アーリア人以外の人々を迫害する人種差別の権化であった。 しかし、実際はノルウェーや人種的には劣るとみなしていたフランス、ポーランドの女性とドイツ人兵士を結婚、出産させ、その子供をドイツに送ることを推奨、活発に行われてきた。 →「ドイツ人」とは。 - 2025年10月5日
 ユダヤ人を救え!: デンマークからスウェーデンへエミー・E.ワーナー,Emmy E.Werner,池田年穂
ユダヤ人を救え!: デンマークからスウェーデンへエミー・E.ワーナー,Emmy E.Werner,池田年穂 - 2025年10月4日
 沈黙の勇者たち岡典子・「ドイツ国内において、ナチス期の救援者たちの存在が重要な研究対象とみなされるようになってのは、終戦から四〇年以上も経過した一九九〇年代になってからであった。」(p.270 13行目) →「それ以降の研究と検証が可能となったのは、当のドイツの人びとが関心をもつはるか以前から救援活動の実態を掘り起こし、地道に記録し続けてきたユダヤ人たちがいたから」(p.270 17行目) ・『称えられれない勇者たち-暗黒期のドイツにおける人びと-』(1956年)出版されて以来、「ドイツ国内でユダヤ人救援者の存在に光があたるまでの長い間、その存在と行動は、彼らに救われたユダヤ人たちによって語られ、記録が蓄積されてきた」 →色々な事業がなされたが、ほとんどの人が関心を持たなかった。 ・「ドイツ国内外に広く「沈黙の勇者」の存在を伝えた最大の功労者は、・・・インゲ・ドイチュクロンであった。」(p.271 16行目) →「全体主義の時代にあっても国家に迎合せず、自らの信念にしたがった人びとがいた事実を次代に伝えていくことこそ、救われた自分の責務だと彼女は考えた。」(p.272 6行目) =映画「潜伏者たち」 ・ユダヤ人夫妻を村全体で匿った(p.175 1行目) ・80人以上のユダヤ人に手を貸したアベックについて(p.181 10行目) ・200人以上の人々に助けられたクラカウアー夫妻(p183 1行目) ・滞在先の多くは牧師館(p.194 11行目) ・ドイツ人の処罰(p.253 1行目)
沈黙の勇者たち岡典子・「ドイツ国内において、ナチス期の救援者たちの存在が重要な研究対象とみなされるようになってのは、終戦から四〇年以上も経過した一九九〇年代になってからであった。」(p.270 13行目) →「それ以降の研究と検証が可能となったのは、当のドイツの人びとが関心をもつはるか以前から救援活動の実態を掘り起こし、地道に記録し続けてきたユダヤ人たちがいたから」(p.270 17行目) ・『称えられれない勇者たち-暗黒期のドイツにおける人びと-』(1956年)出版されて以来、「ドイツ国内でユダヤ人救援者の存在に光があたるまでの長い間、その存在と行動は、彼らに救われたユダヤ人たちによって語られ、記録が蓄積されてきた」 →色々な事業がなされたが、ほとんどの人が関心を持たなかった。 ・「ドイツ国内外に広く「沈黙の勇者」の存在を伝えた最大の功労者は、・・・インゲ・ドイチュクロンであった。」(p.271 16行目) →「全体主義の時代にあっても国家に迎合せず、自らの信念にしたがった人びとがいた事実を次代に伝えていくことこそ、救われた自分の責務だと彼女は考えた。」(p.272 6行目) =映画「潜伏者たち」 ・ユダヤ人夫妻を村全体で匿った(p.175 1行目) ・80人以上のユダヤ人に手を貸したアベックについて(p.181 10行目) ・200人以上の人々に助けられたクラカウアー夫妻(p183 1行目) ・滞在先の多くは牧師館(p.194 11行目) ・ドイツ人の処罰(p.253 1行目) - 2025年10月3日
 ナチスに抗った障害者岡典子精肉店主や農家の人々について(間接的) 「彼らは、自分が売った食料が誰の口に入るのかを薄々は知っていながら、救援者たちの求めに応じて食糧を提供し続けた。」(p.246 6行目)
ナチスに抗った障害者岡典子精肉店主や農家の人々について(間接的) 「彼らは、自分が売った食料が誰の口に入るのかを薄々は知っていながら、救援者たちの求めに応じて食糧を提供し続けた。」(p.246 6行目) - 2025年8月16日
 アンパンマン あいうえお かくれんぼわだことみ,やなせたかし,トムス・エンタテインメント「キリスト教とホロコースト」 ・「ヒトラーの思想の中で最も情熱を帯びるのは、〜この世の万人の生命を支配しようとするアーリア人の優位性を舞台裏でこそこそと抹殺しようとしている世界のユダヤ人勢力への憎悪であった。」 (p.56 12行目) ・「この目的を達成するために平等主義、民主主義、平和主義、国際主義といった思想、さらにキリスト教を含めたイデオロギーという兵器庫をもっぱら利用する、と彼は主張した。」 ・「さらに、『我が闘争』の中でふんだんにユダヤ人を梅毒、売春を含むありとあらゆる病弊を撒き散らすものと非難した。ユダヤ人の生命力自体が敵以外の何ものでもなかった。」 =ヒトラーにとって反ユダヤ主義は「最も長く保ちこたえた対象であり、最も強力な信仰の一つであった。」(p.57 5行目)
アンパンマン あいうえお かくれんぼわだことみ,やなせたかし,トムス・エンタテインメント「キリスト教とホロコースト」 ・「ヒトラーの思想の中で最も情熱を帯びるのは、〜この世の万人の生命を支配しようとするアーリア人の優位性を舞台裏でこそこそと抹殺しようとしている世界のユダヤ人勢力への憎悪であった。」 (p.56 12行目) ・「この目的を達成するために平等主義、民主主義、平和主義、国際主義といった思想、さらにキリスト教を含めたイデオロギーという兵器庫をもっぱら利用する、と彼は主張した。」 ・「さらに、『我が闘争』の中でふんだんにユダヤ人を梅毒、売春を含むありとあらゆる病弊を撒き散らすものと非難した。ユダヤ人の生命力自体が敵以外の何ものでもなかった。」 =ヒトラーにとって反ユダヤ主義は「最も長く保ちこたえた対象であり、最も強力な信仰の一つであった。」(p.57 5行目) - 2025年8月12日
 戦時下のベルリン: 空襲と窮乏の生活1939-45ロジャー・ムーアハウス・「アーリア人が匿っている逃亡ユダヤ人が亡くなると、事態を始末するのが極めて困難だった。」 (p.395 4行目) 30.78.ナチスがドイツ市民にもたらした娯楽 37.大きな戦争が起きるとは思っていないドイツ市民 48.52.86.ドイツの人々は戦争を歓迎していない 64.灯火管制 ・「当時ベルリンで亡くなったユダヤ人の四人に一人が自殺者だった。そして、強制移送通知を受け取った者の10%が自殺を選んだ。」(p.241 1行目) 243.競売 311.密告によって逮捕された人びと 343.ヒトラーユーゲント
戦時下のベルリン: 空襲と窮乏の生活1939-45ロジャー・ムーアハウス・「アーリア人が匿っている逃亡ユダヤ人が亡くなると、事態を始末するのが極めて困難だった。」 (p.395 4行目) 30.78.ナチスがドイツ市民にもたらした娯楽 37.大きな戦争が起きるとは思っていないドイツ市民 48.52.86.ドイツの人々は戦争を歓迎していない 64.灯火管制 ・「当時ベルリンで亡くなったユダヤ人の四人に一人が自殺者だった。そして、強制移送通知を受け取った者の10%が自殺を選んだ。」(p.241 1行目) 243.競売 311.密告によって逮捕された人びと 343.ヒトラーユーゲント - 2025年8月5日
 ホロコースト全史M・ベーレンバウム1933年以降のユダヤ人迫害に対するユダヤ人の対応 ・「大半のユダヤ人は、依然としてドイツにおける自らの未来を信じていた。彼らは伝統的に反シオニストであり、ユダヤ人としてではなく、ドイツ人としてドイツ人としてドイツの愛国心を表明していた。ドイツ文化を愛する彼らは、ワイマール共和国時代の、ドイツ人との見せかけの共棲関係に欺かれていた。」(p.81 9行目) =「ユダヤ人はドイツの政治・経済・文化の面で活躍し、ドイツ人と対等のパートナーであると自負していた」 →しかし、ナチの支配に耐えることができず、自殺する者が急増した。 「1933年から1938年のあいだに、ドイツに住むユダヤ人60万人のうち、15万人がドイツから出国している」(p.82 8行目) ・「ドイツに残ったユダヤ人の多くは、自分たちのルーツを大切にするようになった。」(p.82 11行目) →「シナゴーグ「足を運ぶ者の数が激増した。祈りには新しい意味がこめられ、ヘブライ語の聖書に出てくる暴君ファラオとハマンは、ヒトラーを示す隠語になった。」 →「また、ユダヤ人の学問と教育も、かつて中盛んになった。」 =「状況がさらに悲惨なものになっていくにつれ、逆にユダヤ人たちは結束し、ユダヤ人しゃかいは、これまでにない活気を帯びていった。」 ・「さまざまなユダヤ人が、職業訓練や農業移民のためなの準備資金を提供した。」(p.83 2行目) ・「ドイツ文化協会は、芸術家や音楽家に仕事を世話し、ユダヤ教の神学校は、ドイツの大学を除名された学生たちに正規の大学教育の場を提供した。ユダヤ人の子供がドイツ人の学校に行くのは危険な状況になっていたため、ユダヤ人学校が開かれるようになった。」 ・マルティーン・ブーハーが説いた内容 (p.83 7行目) ・「総統の権力には制限がなかった。1934年、ゲーリングは『総統の意思が法である』と述べている。そこにはチェック・アンド・バランス(権力の分立)が入り込む余地はなく、ヒトラーは法に勝る存在であり、行政面だけではなく、立法と司法の権力までも握っていた。ヒトラーの命令一つで、あらゆる法規範や政令が覆され、すべてはヒトラーの意思一つで決定された。」(p.85 7行目) ・「レストランのウェイターは客についての情報を流し、労働者は雇い主の体制批判に耳をそばだてた。子供たちは、学校の先生や牧師・神父、さらには両親まで監視するように教えられた。」(p.87 最後) ・ゲシュタポには、国民を令状なしに逮捕して強制収容所に収容できるという権限を持っていた。 ・避難場所を求めて(p.120) 「ユダヤ人に行き場所はなかった。パレスチナへの移民はイギリスによって厳しく制限され、中立国のスイスはユダヤ人の流入を恐れていた。そしてアメリカもまた複雑な手続きを課すことで、移民の締め出しをはかっていた。」 アメリカの場合 ・「アメリカへ移住するためのビザを取るには、膨大な数の書類をヨーロッパ各地のアメリカ領事館に送らなければならなかった。〜さらに移民にふさわしいかどうかを証明する善行証明書も必要だったが、この証明書を発行するのは、ドイツではゲシュタポだった。」(p.120 4行目) ・また、「ヨーロッパでww2が勃発した1939年以降、ドイツ国籍のユダヤ人は、スパイ予備軍とみなされて入国を禁じられた。」(10行目) ・「長引く不況で失業者が増えており、アメリカ人たちは、ユダヤ人移民に自分たちの仕事を奪われるのではないかと怖れていた。」 ・「当時の世論調査では、ナチに批判的な人たちのあいだでさえ、移民の割り当てを増やすことに反対の意見が多かった。」(p.122 1行目) ・「1938年と1939年に行われた世論調査では、アメリカ人の95%がドイツの政治体制を批判しながら、アメリカの制度を変えてまで移民枠を増やすべきだと考える者は5%にもら満たなかった。」 ・「アメリカのユダヤ人もまた、社会的に少数なうえ、結束が弱く、無力だった。彼らは、アメリカ国内の反ユダヤ主義を誘発することを恐れていた。」 ・ヒトラーの『我が闘争』にて「最終的目標は、ユダヤ人の完全なる排除である。」と述べている。 (p.222 9行目) ・「ホロコーストには、政治的あるいは領土的目的はなかった。〜ユダヤ人はナチに対し領土面での脅威になる恐れはなかった。ユダヤ人を殺したところで、地政学的なメリットは何もなく、領土の拡張につながるわけでもなかった。ユダヤ人の殺害は何かのための手段ではなく、殺害それ自体が目的だった。」(p.227 8行目) =「ホロコーストは、すべてのユダヤ人の絶滅を目的としていた。」 ・「ホロコーストは、それまでの反ユダヤ主義な暴力行為とも、完全に異なっていたものだった。」 =「過去のユダヤ人に対する攻撃は偶発的なものであり、ある一定の地域に限られたものだった。しかも〜行為は違法とされ、時として法的取り締まり対象にもなった。」(p.228 1行目) =「過去における反ユダヤ主義的な暴力行為は違法とされ、時として法的取り締まりの対象にもなった。〜それまでユダヤ人は、自らの信仰にやって殺害の対象になってきたが、そこには改宗と出国という逃げ道が残されていた。だがナチズムは、そんな容赦はしなかった。」 ・p.108.120ユダヤ人受け入れの各国の反応
ホロコースト全史M・ベーレンバウム1933年以降のユダヤ人迫害に対するユダヤ人の対応 ・「大半のユダヤ人は、依然としてドイツにおける自らの未来を信じていた。彼らは伝統的に反シオニストであり、ユダヤ人としてではなく、ドイツ人としてドイツ人としてドイツの愛国心を表明していた。ドイツ文化を愛する彼らは、ワイマール共和国時代の、ドイツ人との見せかけの共棲関係に欺かれていた。」(p.81 9行目) =「ユダヤ人はドイツの政治・経済・文化の面で活躍し、ドイツ人と対等のパートナーであると自負していた」 →しかし、ナチの支配に耐えることができず、自殺する者が急増した。 「1933年から1938年のあいだに、ドイツに住むユダヤ人60万人のうち、15万人がドイツから出国している」(p.82 8行目) ・「ドイツに残ったユダヤ人の多くは、自分たちのルーツを大切にするようになった。」(p.82 11行目) →「シナゴーグ「足を運ぶ者の数が激増した。祈りには新しい意味がこめられ、ヘブライ語の聖書に出てくる暴君ファラオとハマンは、ヒトラーを示す隠語になった。」 →「また、ユダヤ人の学問と教育も、かつて中盛んになった。」 =「状況がさらに悲惨なものになっていくにつれ、逆にユダヤ人たちは結束し、ユダヤ人しゃかいは、これまでにない活気を帯びていった。」 ・「さまざまなユダヤ人が、職業訓練や農業移民のためなの準備資金を提供した。」(p.83 2行目) ・「ドイツ文化協会は、芸術家や音楽家に仕事を世話し、ユダヤ教の神学校は、ドイツの大学を除名された学生たちに正規の大学教育の場を提供した。ユダヤ人の子供がドイツ人の学校に行くのは危険な状況になっていたため、ユダヤ人学校が開かれるようになった。」 ・マルティーン・ブーハーが説いた内容 (p.83 7行目) ・「総統の権力には制限がなかった。1934年、ゲーリングは『総統の意思が法である』と述べている。そこにはチェック・アンド・バランス(権力の分立)が入り込む余地はなく、ヒトラーは法に勝る存在であり、行政面だけではなく、立法と司法の権力までも握っていた。ヒトラーの命令一つで、あらゆる法規範や政令が覆され、すべてはヒトラーの意思一つで決定された。」(p.85 7行目) ・「レストランのウェイターは客についての情報を流し、労働者は雇い主の体制批判に耳をそばだてた。子供たちは、学校の先生や牧師・神父、さらには両親まで監視するように教えられた。」(p.87 最後) ・ゲシュタポには、国民を令状なしに逮捕して強制収容所に収容できるという権限を持っていた。 ・避難場所を求めて(p.120) 「ユダヤ人に行き場所はなかった。パレスチナへの移民はイギリスによって厳しく制限され、中立国のスイスはユダヤ人の流入を恐れていた。そしてアメリカもまた複雑な手続きを課すことで、移民の締め出しをはかっていた。」 アメリカの場合 ・「アメリカへ移住するためのビザを取るには、膨大な数の書類をヨーロッパ各地のアメリカ領事館に送らなければならなかった。〜さらに移民にふさわしいかどうかを証明する善行証明書も必要だったが、この証明書を発行するのは、ドイツではゲシュタポだった。」(p.120 4行目) ・また、「ヨーロッパでww2が勃発した1939年以降、ドイツ国籍のユダヤ人は、スパイ予備軍とみなされて入国を禁じられた。」(10行目) ・「長引く不況で失業者が増えており、アメリカ人たちは、ユダヤ人移民に自分たちの仕事を奪われるのではないかと怖れていた。」 ・「当時の世論調査では、ナチに批判的な人たちのあいだでさえ、移民の割り当てを増やすことに反対の意見が多かった。」(p.122 1行目) ・「1938年と1939年に行われた世論調査では、アメリカ人の95%がドイツの政治体制を批判しながら、アメリカの制度を変えてまで移民枠を増やすべきだと考える者は5%にもら満たなかった。」 ・「アメリカのユダヤ人もまた、社会的に少数なうえ、結束が弱く、無力だった。彼らは、アメリカ国内の反ユダヤ主義を誘発することを恐れていた。」 ・ヒトラーの『我が闘争』にて「最終的目標は、ユダヤ人の完全なる排除である。」と述べている。 (p.222 9行目) ・「ホロコーストには、政治的あるいは領土的目的はなかった。〜ユダヤ人はナチに対し領土面での脅威になる恐れはなかった。ユダヤ人を殺したところで、地政学的なメリットは何もなく、領土の拡張につながるわけでもなかった。ユダヤ人の殺害は何かのための手段ではなく、殺害それ自体が目的だった。」(p.227 8行目) =「ホロコーストは、すべてのユダヤ人の絶滅を目的としていた。」 ・「ホロコーストは、それまでの反ユダヤ主義な暴力行為とも、完全に異なっていたものだった。」 =「過去のユダヤ人に対する攻撃は偶発的なものであり、ある一定の地域に限られたものだった。しかも〜行為は違法とされ、時として法的取り締まり対象にもなった。」(p.228 1行目) =「過去における反ユダヤ主義的な暴力行為は違法とされ、時として法的取り締まりの対象にもなった。〜それまでユダヤ人は、自らの信仰にやって殺害の対象になってきたが、そこには改宗と出国という逃げ道が残されていた。だがナチズムは、そんな容赦はしなかった。」 ・p.108.120ユダヤ人受け入れの各国の反応 - 2025年7月22日
 ヒトラーとナチ・ドイツ石田勇治読んでる「解放法」についてp.94 ・「例えば、カトリックの強い地域では、神を恐れないマルクス主義が貶められ、労働者地区では、資本家の横暴と金権政治がやり玉にあげられた。農村では、都市に頽廃をもたらした物資文明、食糧生産を軽視する都市の政治家が批判された。」 (p.101 13行目 ) ・「共通にしていたのは、どんな場所でもユダヤ人が引き合いにだされ、不満をユダヤ人に向ける扇動が行われといたことだ。そしてどの地域でも、現下の苦境の原因はヴァイマル共和国の議会政治家にあるという批判を展開し、議会制民主主義の打破を訴えた。」(p.102 2行目) 議会政治家=社民党、中央党、民主党、ドイツ人民党? =「ナチ党はおよそすべての社会階層に支持された。」 ・「あらゆる層で支持を得たもう一つの理由の例は、選抜兵士の追悼式での挙行である」 (p.102 11 行目) ・「第一次世界大戦のドイツ戦没兵士を追悼し、傷痍軍人の栄誉を称えることの意義を強調した。」 →ヴァイマル共和国はその点消極的だった。 ・また、「ミュンヘン一揆のような反ヴァイマル闘争に身を投じて亡くなったナチ党の若者たちを、ww1で斃れたドイツ兵と同様の『民族の大義』に殉じた英雄だと称えた。」(p.103 6行目) →・「第一次世界大戦で重傷を負い、そのために社会復帰が困難となった多くの傷痍軍人は、戦後の社会は自分たちの敬意を示さず、報われないのと感じていた。」 ・「ヒトラーは、戦場で戦い、傷ついた者は、それ相応の補償を与えられるべきだと政府に要求した。」 =「傷痍軍人の心を掴み、彼らのナチ党の支持勢力とすることに成功した。」 ・「ヴァイマル期の農民は、共和国政府が進める二つの政策によって苦境に立たされた。」 (p.104 12行目) 「①ドイツの経済再建に向けた貿易振興政策だ。これによって農産物の関税が引き下げられ、国内農業市場が外国産農作物に開放された結果、農民は厳しい国際競争にさらされた。②安価で良質な外国産農作物に対抗するため、生産の集約化・標準化をはかる合理化政策だ。」 →「困窮にあえぐ一部の農民は、共和国が安定期にあった28年、北ドイツを中心に衝撃的な事件を次々と引き起こしした。」 =「ヒトラーはこうした過激な破壊運動の出現に、ナチ党の農村進出の好機を見てとった。」 また、「工業利益を優先しがちな共和国だけではなく、既成の政党と農業利益団体に対する農民の幻滅の表れでもあった。」 ・1932年ナチ党の支持率が低下した理由 「①投票率が前回の84%から4%下がり、浮動票が掴めなかったこと。②これまでの選挙で票を与えてきた都市部の中間層・保守層が、選挙の直前にナチ党がベルリン交通局のストライキ加わり、共産党とともに首都の公共交通を麻痺させたことに幻滅してナチ党から離れたこと。③ナチ党の急伸に危機感を覚えた保守層がパーペン政府を支持する意味で国家人民党に投票したこと。④経済状況が好転し始めたこと。など」(p.115 8行目) 「だが一番の原因は、ヒトラーのカリスマ性の限界であった。ヒトラーは、新しい国民的な大衆運動の指導者として、多くの有権者に希望を与えたが、まだ何一つ成果を示すことができないでいた。」(p.116) ・ヒトラーは1933年2月1日のラジオで「農民、労働者、手工業者など国民各階層の苦況を引き合いにだし、その原因が共和国を率いた『十一月諸政党』にあるとしたうえで、『四年の時間を我らに与えて欲しい。我らに審判を下し、我らを裁くのはそのときにしてほしい』と訴えた。」(p.137 最後の行) ・「『四年のうちに農民は困窮から脱し、四年のうちに失業は克服されるだろう』」(p.138 2行目) ・1933年3月の選挙はこれまでの選挙戦といくつかの点で異なっていた。 「①ラジオ放送と飛行機が宣伝の手段としてフルに利用したこと。②公権力の介入によって、ナチ党に圧倒的に有利に選挙戦が行われていたこと。」 (p.143 7行目) ・②の具体的な内容 「『ドイツ国民を防衛するための大統領緊急令』は集会と言論の自由に制限を加え、政府批判を行う政治組織の集会、デモ、出帆活動等を禁止した。」 →「共産党をはじめ、野党勢力はナチ党の攻撃に応戦しようにも自由な意見表明ができなくなった。」 (p.143 12行目) ・国会議事堂炎上事件によって、共和国の政治と社会のあり方を一変させた。(p.146) ・ヒトラー政権樹立から半年の流れ(p165) ・なぜ人々はナチの政策に反発しなかったのか 「国民の大半がヒトラーの息をのむ政治弾圧に当惑しながらも、『非常時に多少の自由が制限されるのはやむを得ない』とあきらめ、事態を容認するか、それこら目をそらしたから。とりあえず様子を決め込んだ者も、大勢いた。実際、当局に拘束されていた者は多いとはいえ、国民全体から見ればごく少数に過ぎなかったのだ。」(p.168 4行目) 「『議事堂炎上令は一時のもので、過激な共産主義者が一掃されればすぐに廃止されるだろう』」 「『基本権が停止されたといっても、共産主義や社会民主主義のような危険思想に染まらなければ弾圧されることはない』」 「『いっそヒトラーを支持して体制側につけば楽だし安泰だ』」 ヒトラーの支持が熱狂的になった理由 ・「ヒトラーが新生ドイツにふさわしい『正当な指導者』だ、と世代・性別・党派・地域を超えて認識されるようになった。」(p.170 3行目) ・「プロテスタントとカトリックの両キリスト教会が、それぞれの宗教指導者の態度表明を通して、ヒトラーへの支持を訴えたことである。」→when ・「高名な大学教授や作家・文化人など知的エリートというべき人びとがヒトラーを礼賛する声明文や論説記事を次々と発表した。」【ex)マルティン・ハイデガー】(p.172 1行目) ・「宣伝省の戦術が国民に親しみやすいヒトラーのイメージ作りに効果をあげた」 ・「ヒトラーを偉大な指導者とすふゲッベルスの宣伝は、ヒトラーを神がかった存在にする『ヒトラー神話』を生み出していた。」(p.175 6行目) →「夏になると休暇中のヒトラーを一目見ようと山荘に多くの人びとが押し寄せ、巡礼者の聖地となった。そこで人びとと気さくに歓談する『民衆宰相』の様子はフィルムに収められ、宣伝映画となって国民の共感を得た。」 ・「ラジオ・新聞・出版・映画から文学・音楽・美術・舞台芸術にあたるまで、すべてのメディア・文化活動を監視統制しながら、活発なプロパガンダを展開した。」(p.194 4行目) ・「非合法化された共産党、社会民主党、左翼系労組がこれまで刊行していたおびただしい数の新聞・雑誌は全て廃刊となり、編集者も職を追われた。」 (p.194 8行目) ・「プロパガンダは〜大衆の行動をある方向へ取る誘導することができた。」(同ページ 14行目) ・「自らにふりなじょうほうはいっさい伝えず、有利な情報だけを誇張、潤色、捏造もお構いなしに発信し続け、大衆の共感を得る。敵を仕立て上げることも情報操作ひたつでたやすきことだ。」(p.195) ☆「ドイツの経済はヒトラー政権の誕生前にすでに景気の低を脱し、いまや政府の強力な後押しがあれば一気に回復局面へ移行できる段階にあった。」 (p.208 14行目) →パーペン、シュライヒャー両政府によって ex)・「世界恐慌を生き延びた企業はどこも社員を大量に解雇し、コスト削減をはかった。そのため、生産性が向上し、経営に改善の兆しが見られた。」 but ・一方で、ヒトラーは公約に掲げたものの「そのために練り上げられて計画を持ち合わせていなかった。」(p.209 2行目) ・フォルクスゲマインドシャフト(p.214) =民族共同体 →ドイツ市民を再び戦争のできる国民に作り変えることを目標に掲げた。 ・ナチ党大会(p.218) ・「『力による喜び』(歓喜力行団)は、演劇、音楽会、スポーツ、旅行など昔の労組が全く実現できなかったさまざまな余暇と娯楽の機会をメンバー全員(労働戦線)に提供した。毎月の積立金で外国旅行をしたり、乗用車が手に入ったりする。そんな触れ込みで人気を博した。」(p.226 12行目) ・「『世界に冠たるドイツ』と言えないまでにも、せめて英仏と同等の地位を取り戻したいという思いは、同時代のドイツ人なら誰もが共有していたと言えるだろう。」(p.228 9行目) ・「ユダヤ人が職を追われ、地位を失う方で逆に利益を得る者もかなりの数にのぼった。既成組織の人事がどご一時的に流動化し、昇進したりする者が多数現れた。」(p.176 3行目) =「ユダヤ人の上司や同僚を快く思わない人にとって、職業官吏再建方は好都合だった。」 ・ヒトラーは『我が闘争』からも分かる通り「ヒトラーはww1のドイツの敗因を、国内ユダヤ人の『裏切り』と、ユダヤ人の本性を見抜かなかった旧ドイツ帝国の『無能さ』に求めていた。」(p.278 6行目) →「首相として戦争への意志を固めたヒトラーにとって、同じ過ちを繰り返すことは許されない。ユダヤ人は混交によってアーリア人種を墜落させる有害な異人種で〜、戦争になれば敵国に通じ、人心を乱し、〜。」 =「『ユダヤ人なきドイツ』な実現は、ヒトラーが戦争をするために必要不可欠」(p.278 最後の行 ) ・『水晶の夜』事件の経緯「ポーランドからドイツに出稼ぎに来ていた約1万7千人のユダヤ人に国外退去命令が下された。これに反発した出稼ぎポーランド・ユダヤ人の17歳の少年が、パリのドイツ人外交官エルンスト・フォム・ラートに発砲して重傷を負わせた。」(p.286 14行目) ・ドイツ市民による反ユダヤ政策に対する反応 「人口の1%にも満たない少数派であるユダヤ人な運命は、当時の大多数のドイツ人にとってさほど大きな問題ではなかった。」(p.290 最後の行) ・「ヒトラー政権下の国民は、あからさまな反ユダヤ主義者ではなくても、あるいはユダヤ人に特別な感情を抱いていなくても、ほとんどの場合、日常生活でユダヤ人迫害、とくにユダヤ人財産の『アーリア化』から何らかの実利を得ていた。」 (p.291 3行目) ex)「同僚のユダヤ人がいなくなって出世した役人」「近所のユダヤ人が残した立派な家屋に住むことになった家族」「ユダヤ人の家財道具や装飾品、楽器などを競売で安く手に入れた主婦」「ユダヤ人が経営するライバル企業を安値で買い取って自分の会社を大きくした事業主」「ユダヤ教ゲマアンデの動産・不動産『アーリア化』と称して強奪した自治体の住民たち」 =無数の庶民が大小の利益を得た。 ・「ドイツ社会では、優生思想の普及がはかられた」 →「学校、〜などの公共の場で、『人の価値には生来の差があること』が事実として教えられ、『劣等種との交配は高等種の価値を低下をもたらすこと』『劣等種は増殖能力が高等種の何倍も大きいため、隔離しなければならないこと』など周知徹底された。」 (p.304 1行目) ・ヒトラーの「預言者演説」(p.324 6行目)
ヒトラーとナチ・ドイツ石田勇治読んでる「解放法」についてp.94 ・「例えば、カトリックの強い地域では、神を恐れないマルクス主義が貶められ、労働者地区では、資本家の横暴と金権政治がやり玉にあげられた。農村では、都市に頽廃をもたらした物資文明、食糧生産を軽視する都市の政治家が批判された。」 (p.101 13行目 ) ・「共通にしていたのは、どんな場所でもユダヤ人が引き合いにだされ、不満をユダヤ人に向ける扇動が行われといたことだ。そしてどの地域でも、現下の苦境の原因はヴァイマル共和国の議会政治家にあるという批判を展開し、議会制民主主義の打破を訴えた。」(p.102 2行目) 議会政治家=社民党、中央党、民主党、ドイツ人民党? =「ナチ党はおよそすべての社会階層に支持された。」 ・「あらゆる層で支持を得たもう一つの理由の例は、選抜兵士の追悼式での挙行である」 (p.102 11 行目) ・「第一次世界大戦のドイツ戦没兵士を追悼し、傷痍軍人の栄誉を称えることの意義を強調した。」 →ヴァイマル共和国はその点消極的だった。 ・また、「ミュンヘン一揆のような反ヴァイマル闘争に身を投じて亡くなったナチ党の若者たちを、ww1で斃れたドイツ兵と同様の『民族の大義』に殉じた英雄だと称えた。」(p.103 6行目) →・「第一次世界大戦で重傷を負い、そのために社会復帰が困難となった多くの傷痍軍人は、戦後の社会は自分たちの敬意を示さず、報われないのと感じていた。」 ・「ヒトラーは、戦場で戦い、傷ついた者は、それ相応の補償を与えられるべきだと政府に要求した。」 =「傷痍軍人の心を掴み、彼らのナチ党の支持勢力とすることに成功した。」 ・「ヴァイマル期の農民は、共和国政府が進める二つの政策によって苦境に立たされた。」 (p.104 12行目) 「①ドイツの経済再建に向けた貿易振興政策だ。これによって農産物の関税が引き下げられ、国内農業市場が外国産農作物に開放された結果、農民は厳しい国際競争にさらされた。②安価で良質な外国産農作物に対抗するため、生産の集約化・標準化をはかる合理化政策だ。」 →「困窮にあえぐ一部の農民は、共和国が安定期にあった28年、北ドイツを中心に衝撃的な事件を次々と引き起こしした。」 =「ヒトラーはこうした過激な破壊運動の出現に、ナチ党の農村進出の好機を見てとった。」 また、「工業利益を優先しがちな共和国だけではなく、既成の政党と農業利益団体に対する農民の幻滅の表れでもあった。」 ・1932年ナチ党の支持率が低下した理由 「①投票率が前回の84%から4%下がり、浮動票が掴めなかったこと。②これまでの選挙で票を与えてきた都市部の中間層・保守層が、選挙の直前にナチ党がベルリン交通局のストライキ加わり、共産党とともに首都の公共交通を麻痺させたことに幻滅してナチ党から離れたこと。③ナチ党の急伸に危機感を覚えた保守層がパーペン政府を支持する意味で国家人民党に投票したこと。④経済状況が好転し始めたこと。など」(p.115 8行目) 「だが一番の原因は、ヒトラーのカリスマ性の限界であった。ヒトラーは、新しい国民的な大衆運動の指導者として、多くの有権者に希望を与えたが、まだ何一つ成果を示すことができないでいた。」(p.116) ・ヒトラーは1933年2月1日のラジオで「農民、労働者、手工業者など国民各階層の苦況を引き合いにだし、その原因が共和国を率いた『十一月諸政党』にあるとしたうえで、『四年の時間を我らに与えて欲しい。我らに審判を下し、我らを裁くのはそのときにしてほしい』と訴えた。」(p.137 最後の行) ・「『四年のうちに農民は困窮から脱し、四年のうちに失業は克服されるだろう』」(p.138 2行目) ・1933年3月の選挙はこれまでの選挙戦といくつかの点で異なっていた。 「①ラジオ放送と飛行機が宣伝の手段としてフルに利用したこと。②公権力の介入によって、ナチ党に圧倒的に有利に選挙戦が行われていたこと。」 (p.143 7行目) ・②の具体的な内容 「『ドイツ国民を防衛するための大統領緊急令』は集会と言論の自由に制限を加え、政府批判を行う政治組織の集会、デモ、出帆活動等を禁止した。」 →「共産党をはじめ、野党勢力はナチ党の攻撃に応戦しようにも自由な意見表明ができなくなった。」 (p.143 12行目) ・国会議事堂炎上事件によって、共和国の政治と社会のあり方を一変させた。(p.146) ・ヒトラー政権樹立から半年の流れ(p165) ・なぜ人々はナチの政策に反発しなかったのか 「国民の大半がヒトラーの息をのむ政治弾圧に当惑しながらも、『非常時に多少の自由が制限されるのはやむを得ない』とあきらめ、事態を容認するか、それこら目をそらしたから。とりあえず様子を決め込んだ者も、大勢いた。実際、当局に拘束されていた者は多いとはいえ、国民全体から見ればごく少数に過ぎなかったのだ。」(p.168 4行目) 「『議事堂炎上令は一時のもので、過激な共産主義者が一掃されればすぐに廃止されるだろう』」 「『基本権が停止されたといっても、共産主義や社会民主主義のような危険思想に染まらなければ弾圧されることはない』」 「『いっそヒトラーを支持して体制側につけば楽だし安泰だ』」 ヒトラーの支持が熱狂的になった理由 ・「ヒトラーが新生ドイツにふさわしい『正当な指導者』だ、と世代・性別・党派・地域を超えて認識されるようになった。」(p.170 3行目) ・「プロテスタントとカトリックの両キリスト教会が、それぞれの宗教指導者の態度表明を通して、ヒトラーへの支持を訴えたことである。」→when ・「高名な大学教授や作家・文化人など知的エリートというべき人びとがヒトラーを礼賛する声明文や論説記事を次々と発表した。」【ex)マルティン・ハイデガー】(p.172 1行目) ・「宣伝省の戦術が国民に親しみやすいヒトラーのイメージ作りに効果をあげた」 ・「ヒトラーを偉大な指導者とすふゲッベルスの宣伝は、ヒトラーを神がかった存在にする『ヒトラー神話』を生み出していた。」(p.175 6行目) →「夏になると休暇中のヒトラーを一目見ようと山荘に多くの人びとが押し寄せ、巡礼者の聖地となった。そこで人びとと気さくに歓談する『民衆宰相』の様子はフィルムに収められ、宣伝映画となって国民の共感を得た。」 ・「ラジオ・新聞・出版・映画から文学・音楽・美術・舞台芸術にあたるまで、すべてのメディア・文化活動を監視統制しながら、活発なプロパガンダを展開した。」(p.194 4行目) ・「非合法化された共産党、社会民主党、左翼系労組がこれまで刊行していたおびただしい数の新聞・雑誌は全て廃刊となり、編集者も職を追われた。」 (p.194 8行目) ・「プロパガンダは〜大衆の行動をある方向へ取る誘導することができた。」(同ページ 14行目) ・「自らにふりなじょうほうはいっさい伝えず、有利な情報だけを誇張、潤色、捏造もお構いなしに発信し続け、大衆の共感を得る。敵を仕立て上げることも情報操作ひたつでたやすきことだ。」(p.195) ☆「ドイツの経済はヒトラー政権の誕生前にすでに景気の低を脱し、いまや政府の強力な後押しがあれば一気に回復局面へ移行できる段階にあった。」 (p.208 14行目) →パーペン、シュライヒャー両政府によって ex)・「世界恐慌を生き延びた企業はどこも社員を大量に解雇し、コスト削減をはかった。そのため、生産性が向上し、経営に改善の兆しが見られた。」 but ・一方で、ヒトラーは公約に掲げたものの「そのために練り上げられて計画を持ち合わせていなかった。」(p.209 2行目) ・フォルクスゲマインドシャフト(p.214) =民族共同体 →ドイツ市民を再び戦争のできる国民に作り変えることを目標に掲げた。 ・ナチ党大会(p.218) ・「『力による喜び』(歓喜力行団)は、演劇、音楽会、スポーツ、旅行など昔の労組が全く実現できなかったさまざまな余暇と娯楽の機会をメンバー全員(労働戦線)に提供した。毎月の積立金で外国旅行をしたり、乗用車が手に入ったりする。そんな触れ込みで人気を博した。」(p.226 12行目) ・「『世界に冠たるドイツ』と言えないまでにも、せめて英仏と同等の地位を取り戻したいという思いは、同時代のドイツ人なら誰もが共有していたと言えるだろう。」(p.228 9行目) ・「ユダヤ人が職を追われ、地位を失う方で逆に利益を得る者もかなりの数にのぼった。既成組織の人事がどご一時的に流動化し、昇進したりする者が多数現れた。」(p.176 3行目) =「ユダヤ人の上司や同僚を快く思わない人にとって、職業官吏再建方は好都合だった。」 ・ヒトラーは『我が闘争』からも分かる通り「ヒトラーはww1のドイツの敗因を、国内ユダヤ人の『裏切り』と、ユダヤ人の本性を見抜かなかった旧ドイツ帝国の『無能さ』に求めていた。」(p.278 6行目) →「首相として戦争への意志を固めたヒトラーにとって、同じ過ちを繰り返すことは許されない。ユダヤ人は混交によってアーリア人種を墜落させる有害な異人種で〜、戦争になれば敵国に通じ、人心を乱し、〜。」 =「『ユダヤ人なきドイツ』な実現は、ヒトラーが戦争をするために必要不可欠」(p.278 最後の行 ) ・『水晶の夜』事件の経緯「ポーランドからドイツに出稼ぎに来ていた約1万7千人のユダヤ人に国外退去命令が下された。これに反発した出稼ぎポーランド・ユダヤ人の17歳の少年が、パリのドイツ人外交官エルンスト・フォム・ラートに発砲して重傷を負わせた。」(p.286 14行目) ・ドイツ市民による反ユダヤ政策に対する反応 「人口の1%にも満たない少数派であるユダヤ人な運命は、当時の大多数のドイツ人にとってさほど大きな問題ではなかった。」(p.290 最後の行) ・「ヒトラー政権下の国民は、あからさまな反ユダヤ主義者ではなくても、あるいはユダヤ人に特別な感情を抱いていなくても、ほとんどの場合、日常生活でユダヤ人迫害、とくにユダヤ人財産の『アーリア化』から何らかの実利を得ていた。」 (p.291 3行目) ex)「同僚のユダヤ人がいなくなって出世した役人」「近所のユダヤ人が残した立派な家屋に住むことになった家族」「ユダヤ人の家財道具や装飾品、楽器などを競売で安く手に入れた主婦」「ユダヤ人が経営するライバル企業を安値で買い取って自分の会社を大きくした事業主」「ユダヤ教ゲマアンデの動産・不動産『アーリア化』と称して強奪した自治体の住民たち」 =無数の庶民が大小の利益を得た。 ・「ドイツ社会では、優生思想の普及がはかられた」 →「学校、〜などの公共の場で、『人の価値には生来の差があること』が事実として教えられ、『劣等種との交配は高等種の価値を低下をもたらすこと』『劣等種は増殖能力が高等種の何倍も大きいため、隔離しなければならないこと』など周知徹底された。」 (p.304 1行目) ・ヒトラーの「預言者演説」(p.324 6行目) - 2025年7月16日
 ヒトラーを支持したドイツ国民ロバート・ジェラテリー,根岸隆夫・ダニエル・ゴールドハーゲン「ユダヤ人憎悪が宿す殺害可能性が1933年以前にすでにあった」 (p.4 16行目) →ヒトラーが台頭して初めてユダヤ人迫害が始まったわけではない。 =ドイツのユダヤ人迫害は主として「ドイツ人のあいだに人種差別と抹殺指向の悪魔的反ユダヤ主義がすでに存在していて、ヒトラーがそれを解き放った」 ・「ユダヤ人迫害はかならずしも人種差別によるとは限らなかった。」(p.6 1行目) ・「時として強い憎悪感と利益追求に結びつく利己的な理由を動機とした。」(同ページ 4行目) ・ユダヤ人迫害が勢いを増した(p.145〜) ・加速する差別(p.148〜) ・ユダヤ人の金品がドイツ国家とナチ党員、ドイツ市民に行き届いた(p.156 15行目) ・ユダヤ人の労働先と労働人数(p.157 9行目) ・黄色い星に対するカトリックの反応 →「カトリック中産階級の居住地では憐憫(あわれみ)の声が聞かれ、『中世のやり方』だという人もいた」(p.157 17行目) ↔︎「ドイツの地方によっては、プロテスタント教会信者は多くの(改宗の)ユダヤ人が教会に行くのを見て不快感を隠さず、牧師にむかってユダヤ人のそばで自分たちに聖餐式をしないでほしいし、ユダヤ人を礼拝にこさせないように求めた。」 =ここでは、カトリックとプロテスタントどちらの方が反ユダヤ的であったかは判断できない。 ・「カトリック・ユダヤ人は分けて礼拝式をやるよう提案をした」カトリック教徒もいた。 ・ユダヤ人の定義(p.147 6行目) ・ニュルンベルク法に対するドイツ人の反応 (p.147 19行目) ・ドイツ人大学生によるユダヤ人迫害(p.35 6行目) →「4月25日に政府は「人数制限条項」を、大学に入学できるユダヤ人学生の割合を制限すべく導入した。」 =「ドイツ人の大学生・教授の入学率・就職率の上昇につながり、学者の失業が高かった折から好評を博した。」 ・「1933年3月と4月に、すでに差別の対象となっていなかったユダヤ人で専門職についていた人々に更なる圧力が加えられた」(p.35 19行目) ・「4月の上旬にヒトラーは「ドイツから外国人知識層の影響と異人種による神道を排除する」と確約した。」(p.35 1行目)
ヒトラーを支持したドイツ国民ロバート・ジェラテリー,根岸隆夫・ダニエル・ゴールドハーゲン「ユダヤ人憎悪が宿す殺害可能性が1933年以前にすでにあった」 (p.4 16行目) →ヒトラーが台頭して初めてユダヤ人迫害が始まったわけではない。 =ドイツのユダヤ人迫害は主として「ドイツ人のあいだに人種差別と抹殺指向の悪魔的反ユダヤ主義がすでに存在していて、ヒトラーがそれを解き放った」 ・「ユダヤ人迫害はかならずしも人種差別によるとは限らなかった。」(p.6 1行目) ・「時として強い憎悪感と利益追求に結びつく利己的な理由を動機とした。」(同ページ 4行目) ・ユダヤ人迫害が勢いを増した(p.145〜) ・加速する差別(p.148〜) ・ユダヤ人の金品がドイツ国家とナチ党員、ドイツ市民に行き届いた(p.156 15行目) ・ユダヤ人の労働先と労働人数(p.157 9行目) ・黄色い星に対するカトリックの反応 →「カトリック中産階級の居住地では憐憫(あわれみ)の声が聞かれ、『中世のやり方』だという人もいた」(p.157 17行目) ↔︎「ドイツの地方によっては、プロテスタント教会信者は多くの(改宗の)ユダヤ人が教会に行くのを見て不快感を隠さず、牧師にむかってユダヤ人のそばで自分たちに聖餐式をしないでほしいし、ユダヤ人を礼拝にこさせないように求めた。」 =ここでは、カトリックとプロテスタントどちらの方が反ユダヤ的であったかは判断できない。 ・「カトリック・ユダヤ人は分けて礼拝式をやるよう提案をした」カトリック教徒もいた。 ・ユダヤ人の定義(p.147 6行目) ・ニュルンベルク法に対するドイツ人の反応 (p.147 19行目) ・ドイツ人大学生によるユダヤ人迫害(p.35 6行目) →「4月25日に政府は「人数制限条項」を、大学に入学できるユダヤ人学生の割合を制限すべく導入した。」 =「ドイツ人の大学生・教授の入学率・就職率の上昇につながり、学者の失業が高かった折から好評を博した。」 ・「1933年3月と4月に、すでに差別の対象となっていなかったユダヤ人で専門職についていた人々に更なる圧力が加えられた」(p.35 19行目) ・「4月の上旬にヒトラーは「ドイツから外国人知識層の影響と異人種による神道を排除する」と確約した。」(p.35 1行目) - 2025年7月13日
 20世紀ドイツ史石田勇治・「ヴァイマル共和国はヴェルサイユ条約の経済的、物理的負担を直接の原因として崩壊したわけではない。」(p.125 3行目) →「ドイツの工業生産指数は1927年に戦前の水準を回復している」 「巨額の賠償金も31年には支払い義務自体が事実上解消している」 ・「また、ドイツは依然として大国の地位を維持することができた」 →「ヴァイマル期のドイツ外交と比べて行動の余地を広げたと言える」(p.126 1行目) ⭐︎「ヴェルサイユ条約は過酷であったがドイツの存在を脅かすカルタゴの和ではなかった」(p.126 2行目) ・「ヴァイマル共和国期、戦争責任をめぐる問題は世論を激昂させた」(p.127 10行目)
20世紀ドイツ史石田勇治・「ヴァイマル共和国はヴェルサイユ条約の経済的、物理的負担を直接の原因として崩壊したわけではない。」(p.125 3行目) →「ドイツの工業生産指数は1927年に戦前の水準を回復している」 「巨額の賠償金も31年には支払い義務自体が事実上解消している」 ・「また、ドイツは依然として大国の地位を維持することができた」 →「ヴァイマル期のドイツ外交と比べて行動の余地を広げたと言える」(p.126 1行目) ⭐︎「ヴェルサイユ条約は過酷であったがドイツの存在を脅かすカルタゴの和ではなかった」(p.126 2行目) ・「ヴァイマル共和国期、戦争責任をめぐる問題は世論を激昂させた」(p.127 10行目)
読み込み中...
