

七瀬由惟/Yui Nanase/あーしぇ
@ashe_dalmasca
本のメモです。
青空⬇️は近況とか。
- 2026年2月14日
 書店員の怒りと悲しみと少しの愛大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太,大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太読み終わった
書店員の怒りと悲しみと少しの愛大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太,大塚真祐子/水越麻由子/篠田宏昭/前田隆紀/笈入建志/モーグ女史/小国貴司/嶋田詔太読み終わった - 2026年2月12日
 ジャック・ラカン松本卓也読み終わった
ジャック・ラカン松本卓也読み終わった - 2026年1月29日
 無常商店街酉島伝法読み終わったあれ、おかしいな。ふつーだなー。あれ? あれれ? あーれーー! いつの間にか酉島節に絡め取られていましたー。おもしろかった! とくにお姉さんのキャラは好きかも。 傾いてしまった自分のなぶら天秤を元の位置に戻すためにエペペってもよいかな。 あ、なぶらって微分の▽だよね。
無常商店街酉島伝法読み終わったあれ、おかしいな。ふつーだなー。あれ? あれれ? あーれーー! いつの間にか酉島節に絡め取られていましたー。おもしろかった! とくにお姉さんのキャラは好きかも。 傾いてしまった自分のなぶら天秤を元の位置に戻すためにエペペってもよいかな。 あ、なぶらって微分の▽だよね。 - 2026年1月23日
 無常商店街酉島伝法読み始めた
無常商店街酉島伝法読み始めた - 2026年1月22日
 秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わった
秘儀(下)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わった - 2026年1月21日
- 2026年1月12日
 資本主義に出口はあるか荒谷大輔読み終わった
資本主義に出口はあるか荒谷大輔読み終わった - 2025年12月21日
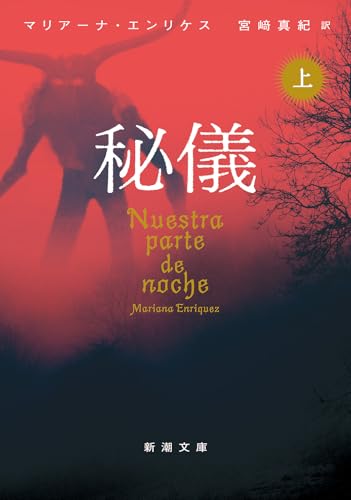 秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わった
秘儀(上) (新潮文庫 エ 9-1)マリアーナ・エンリケス,宮崎真紀,宮﨑真紀読み終わった - 2025年12月15日
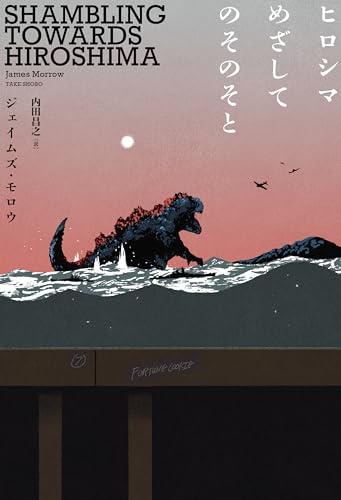 ヒロシマめざしてのそのそとジェイムズ・モロウ読み終わった
ヒロシマめざしてのそのそとジェイムズ・モロウ読み終わった - 2025年12月13日
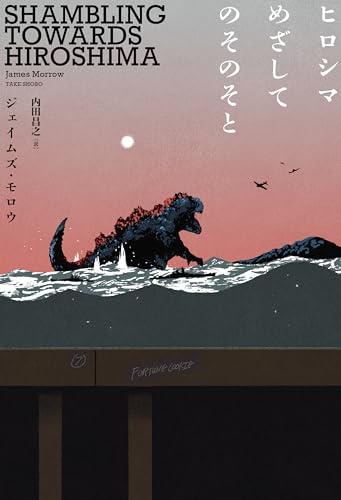 ヒロシマめざしてのそのそとジェイムズ・モロウ読み始めた
ヒロシマめざしてのそのそとジェイムズ・モロウ読み始めた - 2025年12月13日
 天空龍機 鋼鉄紅女2 下シーラン・ジェイ・ジャオ,中原尚哉読み終わった2下巻読了。後半の凄まじい展開に驚いた。なるほどそうか。そういうことか。上巻での、妙に現代世界っぽい舞台に違和感を覚えたのは正しかったようだ。あちこちで覗かせる思想が強すぎてちょっとシンドいですが、怒濤のアクションパートはよかった。
天空龍機 鋼鉄紅女2 下シーラン・ジェイ・ジャオ,中原尚哉読み終わった2下巻読了。後半の凄まじい展開に驚いた。なるほどそうか。そういうことか。上巻での、妙に現代世界っぽい舞台に違和感を覚えたのは正しかったようだ。あちこちで覗かせる思想が強すぎてちょっとシンドいですが、怒濤のアクションパートはよかった。 - 2025年12月11日
 天空龍機 鋼鉄紅女2 上シーラン・ジェイ・ジャオ,中原尚哉読み終わった2上巻読了。1巻読了からだいぶ経っているので記憶は曖昧ですが、作中に無菌室やタブレット端末、プロレタリア革命などが出てきて、ぽかんとしてしまった。もっとファンタジーっぽい印象でしたが、こんなに近現代的だったとは。下巻突入に際してはそのバイアスは捨て去ったほうがよさそう。ただ読ませるストーリー展開はさすが。
天空龍機 鋼鉄紅女2 上シーラン・ジェイ・ジャオ,中原尚哉読み終わった2上巻読了。1巻読了からだいぶ経っているので記憶は曖昧ですが、作中に無菌室やタブレット端末、プロレタリア革命などが出てきて、ぽかんとしてしまった。もっとファンタジーっぽい印象でしたが、こんなに近現代的だったとは。下巻突入に際してはそのバイアスは捨て去ったほうがよさそう。ただ読ませるストーリー展開はさすが。 - 2025年11月30日
 絶滅の牙レイ・ネイラー,金子浩読み終わった
絶滅の牙レイ・ネイラー,金子浩読み終わった - 2025年11月27日
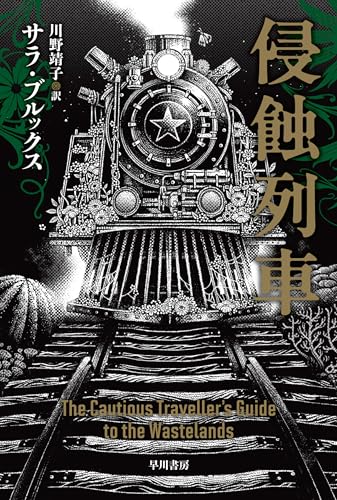 侵蝕列車サラ・ブルックス,川野靖子読み終わった
侵蝕列車サラ・ブルックス,川野靖子読み終わった - 2025年11月21日
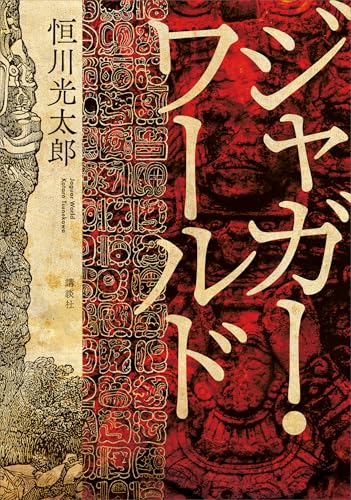 ジャガー・ワールド恒川光太郎読み終わった
ジャガー・ワールド恒川光太郎読み終わった - 2025年11月14日
 反転領域アレステア・レナルズ,中原尚哉読み終わった
反転領域アレステア・レナルズ,中原尚哉読み終わった - 2025年11月8日
 シナバー 辰砂都市エドワード・ブライアント,市田泉読み終わった
シナバー 辰砂都市エドワード・ブライアント,市田泉読み終わった - 2025年11月3日
 火星の女王小川哲読み終わった
火星の女王小川哲読み終わった - 2025年10月31日
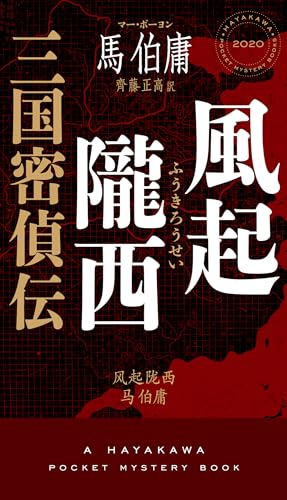 風起隴西 三国密偵伝馬伯庸,齊藤正高読み終わった二週間ほど昼休みの時間を使って読了。中国三国時代、魏と蜀の間諜たちの物語。読み終わるのがもったいないくらい面白かった。 前に読んだ西遊記ならはじめから全部が嘘だとわかるのに、三國志が舞台だと、とたんに作者による虚実の虚の部分が効(利)いてくる。またそのバランスも絶妙。 頭の回転が早い行動派な諜報員ってボンドとかフェルプス君をすぐに思い浮かべるが、これからは荀詡もそこに加えよう。 この主人公、あるいは彼の仲間を主役に据えた、この時代の間諜たちの暗躍話をもっと読んでみたいけど、続篇は無理そうだなあ。
風起隴西 三国密偵伝馬伯庸,齊藤正高読み終わった二週間ほど昼休みの時間を使って読了。中国三国時代、魏と蜀の間諜たちの物語。読み終わるのがもったいないくらい面白かった。 前に読んだ西遊記ならはじめから全部が嘘だとわかるのに、三國志が舞台だと、とたんに作者による虚実の虚の部分が効(利)いてくる。またそのバランスも絶妙。 頭の回転が早い行動派な諜報員ってボンドとかフェルプス君をすぐに思い浮かべるが、これからは荀詡もそこに加えよう。 この主人公、あるいは彼の仲間を主役に据えた、この時代の間諜たちの暗躍話をもっと読んでみたいけど、続篇は無理そうだなあ。 - 2025年10月26日
 人はみな妄想する松本卓也買った
人はみな妄想する松本卓也買った
読み込み中...
