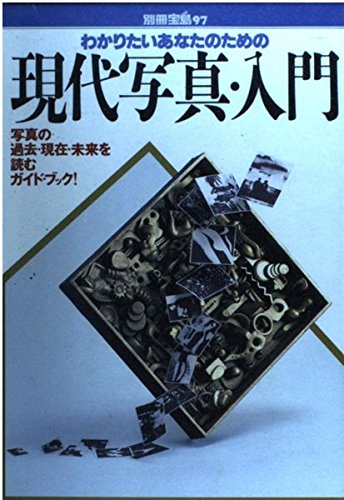素潜り旬
@smog_lee_shun
詩人。『パスタで巻いた靴』(港の人)
- 2026年2月24日
 晩年様式集 イン・レイト・スタイル大江健三郎読み終わった
晩年様式集 イン・レイト・スタイル大江健三郎読み終わった - 2026年2月24日
 ゴダール、ジャン゠リュック四方田犬彦読み終わった
ゴダール、ジャン゠リュック四方田犬彦読み終わった - 2025年12月29日
 マニフェスト 政治の詩学エドゥアール・グリッサン,パトリック・シャモワゾー読み終わった
マニフェスト 政治の詩学エドゥアール・グリッサン,パトリック・シャモワゾー読み終わった - 2025年11月8日
- 2025年11月5日
 背丈ほどあるワレモコウコマガネ・トモオ読み終わった
背丈ほどあるワレモコウコマガネ・トモオ読み終わった - 2025年11月5日
 火曜日になったら戦争に行(い)く渡辺玄英読み終わった
火曜日になったら戦争に行(い)く渡辺玄英読み終わった - 2025年11月5日
 遙かなる光郷へノ黙示菊井崇史読み終わった
遙かなる光郷へノ黙示菊井崇史読み終わった - 2025年11月5日
 モ-将軍田口犬男読み終わった
モ-将軍田口犬男読み終わった - 2025年10月22日
 晴れる空よりもうつくしいもの白鳥央堂読み終わった俺の詩集に近いものを感じた。 《私はだから お前もお前もお前も お前も 待っていたんだ》 「破水の陸」 《そういう歌がありさえすれば あなたもすぐに歌い終えるさ》 「つぐみに訊いた、いくつかの讃歌」 など俺個人の高揚timeが続き、めっちゃ好きだった。
晴れる空よりもうつくしいもの白鳥央堂読み終わった俺の詩集に近いものを感じた。 《私はだから お前もお前もお前も お前も 待っていたんだ》 「破水の陸」 《そういう歌がありさえすれば あなたもすぐに歌い終えるさ》 「つぐみに訊いた、いくつかの讃歌」 など俺個人の高揚timeが続き、めっちゃ好きだった。 - 2025年10月22日
- 2025年10月22日
 生成する非在: 松下千里評論集松下千里読み終わった
生成する非在: 松下千里評論集松下千里読み終わった - 2025年10月22日
- 2025年10月17日
 御世の戦示の木の下で中尾太一読み終わった
御世の戦示の木の下で中尾太一読み終わった - 2025年10月17日
 フィールド映像術分藤大翼読み終わった《しかしこのラリベロッチの路上のパフォーマンスの映像記録を行うなかで、私は壁にぶち当たる。 撮影をはじめた当初は、路上に繰り広げられる人びとのやりとりをただ淡々と客観的に”記録し、映像として抽出できる、とナイーブに考えていた。しかしながら、私の意図とは裏腹に、撮影中の私 に対して、被写体の人びとが盛んに話しかけたり、ジョークを言うようになった。それどころか、こ ちらがあらかじめ撮影対象の歌い手たちに、私やカメラの存在を無視して振る舞うことをお願いした にもかかわらず、撮影中の私の存在をおもしろおかしく歌詞に取り入れる始末である。このラリベロッ チの撮影の経験を経てはじめて、フィールドワークのなかで撮影者である私の存在や主観を排除した 映像記録が不可能であることに気づかされた。》川瀬慈「音楽・芸能を対象とした民族誌映画制作と公開をめぐって エチオピアの音楽職能集団の事例より」 《川瀬:私は撮影者である自らの存在を前景化する映画的な話法を探求してきました。映像をはじめ るまえはずっと音楽をやっていました。そのためなのでしょうか、民族誌や映画よりも、音 楽から映画的なインスピレーションを受けます。とくに、複数の奏者によって奏でられる improvisation(完全な free improvisation ではなく、ある程度の予定調和をもった、たとえば jazz などの)を参考にします。自らが奏者である、と同時に他の奏者の音を注意深く引き出す 行為は、映像が対象とする文化の脈絡のなかで、自らの立ち居振る舞いを展開させていく、私 の撮影手法と呼応します。》「映像が切り拓くフィールドワークの未来」
フィールド映像術分藤大翼読み終わった《しかしこのラリベロッチの路上のパフォーマンスの映像記録を行うなかで、私は壁にぶち当たる。 撮影をはじめた当初は、路上に繰り広げられる人びとのやりとりをただ淡々と客観的に”記録し、映像として抽出できる、とナイーブに考えていた。しかしながら、私の意図とは裏腹に、撮影中の私 に対して、被写体の人びとが盛んに話しかけたり、ジョークを言うようになった。それどころか、こ ちらがあらかじめ撮影対象の歌い手たちに、私やカメラの存在を無視して振る舞うことをお願いした にもかかわらず、撮影中の私の存在をおもしろおかしく歌詞に取り入れる始末である。このラリベロッ チの撮影の経験を経てはじめて、フィールドワークのなかで撮影者である私の存在や主観を排除した 映像記録が不可能であることに気づかされた。》川瀬慈「音楽・芸能を対象とした民族誌映画制作と公開をめぐって エチオピアの音楽職能集団の事例より」 《川瀬:私は撮影者である自らの存在を前景化する映画的な話法を探求してきました。映像をはじめ るまえはずっと音楽をやっていました。そのためなのでしょうか、民族誌や映画よりも、音 楽から映画的なインスピレーションを受けます。とくに、複数の奏者によって奏でられる improvisation(完全な free improvisation ではなく、ある程度の予定調和をもった、たとえば jazz などの)を参考にします。自らが奏者である、と同時に他の奏者の音を注意深く引き出す 行為は、映像が対象とする文化の脈絡のなかで、自らの立ち居振る舞いを展開させていく、私 の撮影手法と呼応します。》「映像が切り拓くフィールドワークの未来」 - 2025年10月13日
 ゴダール/映画誌山田宏一読み終わった『勝手にしやがれ』についての記述、メモ 《ラストシーン、ジャン=ポール・ベルモンドが腰骨を撃たれてよろよろと逃げていき、そして倒れて息絶えるところは、これもゴダールが批評家時代に、「最も映画的なジャンル」である西部劇を「発明し直 しているのだ」とまで絶識した(「カイエ・デュ・シネマ」誌一九五九年二月第32号)、アンソニー・マン 監督の『西部の人』(一九五八)で強盗団の首領、リー・J・コップが背中に一撃をうけながらゴースト タウンの果てしなく長い坂道をよろよろと下り、最後の息切れの瞬間にひと声叫ぶ断末魔のシーンの引用的再現であったが、同時にラオール・ウォルシュ監督のギャング映画『彼奴は顔役だ!」(一九三九)の ジェームズ・キャグニーが銃弾をうけながらよろよろと走りつづけ、教会の石段のところで息絶える感動的なラストシーンをも合わせた引用だった。ジェームズ・キャグニーを抱きかかえる情婦のグラディス・ ジョージに警官がたずねる。「何者かね?」「顔役だった男よ」とグラディス・ジョージはつぶやく。「マイ ・メランコリー・ベイビー」のせつなく美しいメロディーが流れる。》
ゴダール/映画誌山田宏一読み終わった『勝手にしやがれ』についての記述、メモ 《ラストシーン、ジャン=ポール・ベルモンドが腰骨を撃たれてよろよろと逃げていき、そして倒れて息絶えるところは、これもゴダールが批評家時代に、「最も映画的なジャンル」である西部劇を「発明し直 しているのだ」とまで絶識した(「カイエ・デュ・シネマ」誌一九五九年二月第32号)、アンソニー・マン 監督の『西部の人』(一九五八)で強盗団の首領、リー・J・コップが背中に一撃をうけながらゴースト タウンの果てしなく長い坂道をよろよろと下り、最後の息切れの瞬間にひと声叫ぶ断末魔のシーンの引用的再現であったが、同時にラオール・ウォルシュ監督のギャング映画『彼奴は顔役だ!」(一九三九)の ジェームズ・キャグニーが銃弾をうけながらよろよろと走りつづけ、教会の石段のところで息絶える感動的なラストシーンをも合わせた引用だった。ジェームズ・キャグニーを抱きかかえる情婦のグラディス・ ジョージに警官がたずねる。「何者かね?」「顔役だった男よ」とグラディス・ジョージはつぶやく。「マイ ・メランコリー・ベイビー」のせつなく美しいメロディーが流れる。》 - 2025年10月7日
 <私>の映画史稲川方人,荒井晴彦読み終わった
<私>の映画史稲川方人,荒井晴彦読み終わった - 2025年10月7日
 高貝弘也(Hiroya)詩集高貝弘也読み終わった
高貝弘也(Hiroya)詩集高貝弘也読み終わった - 2025年10月7日
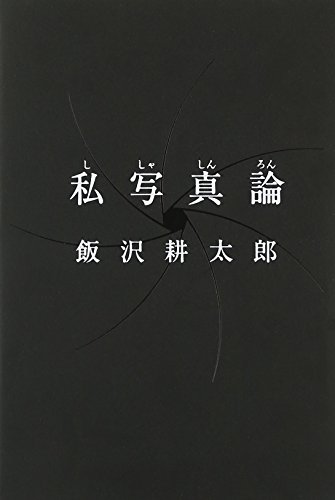 私写真論飯沢耕太郎読み終わった
私写真論飯沢耕太郎読み終わった - 2025年10月7日
 A TASTE OF TANIKAWA 谷川俊太郎の詩を味わうウィリアム・I・エリオット,川村和夫,西原克政読み終わった
A TASTE OF TANIKAWA 谷川俊太郎の詩を味わうウィリアム・I・エリオット,川村和夫,西原克政読み終わった - 2025年10月7日
読み込み中...