

都麦
@tsumugiterao
ライスワークは事業企画部のデータアナリスト、ライフワークは映画制作。24年秋からアイヌについての勉強会“ふむふむアイヌ”を月に1-2回開催しています。自宅本棚のお気に入りゾーンは[恵文社][誠光舎][出町座][エルカミノ][小豆書房]から。故郷は北海道。25歳、犬好き。
- 2025年10月30日
 アイヌがまなざす 痛みの声を聴くとき村上靖彦,石原真衣読み終わった@ 自宅「ふむふむアイヌ」にて、4月から半年間をかけて、みなさんと共に完走。読み終えたのは先々週だけれど、今日開催された「『アイヌがまなざす』総集編」を経てまたこの本が自分の体の一部となってくれた感覚があるので、今日を読み終えた日としよう。 まずこの本を読み終えて最も大きかった変化は、自身の揺らぎの芽生え。それは石原さんの厳しさ(これは毅然とした態度というべきかな)と、村上さんの慎重な言葉選びを浴びて、ある種これまでの自分の矜持の喪失とも言える、目線の破壊でもある、とにかく何らかの変化/揺らぎを引き出してもらった感覚。そのとき、ずっと当たり前のように誰か/何かをまなざしてきた自分の存在が浮かび上がる。これを遠くから眺めたときに、これこそが“まなざし”の変化か!と腑に落ちた。 しかしそれと同時に、やはりこの本に綴られた5名+1名の“遺書”を、いつでも忘れられる環境から、やっぱり“まなざして”いる自分の存在の色濃さも拭えない。これこそがまさに自分の特権性だし、まなざす側としての乱暴な態度であり、思想的消費を意味するのだろうなと反省する。 では思想的消費をしないために、どうしたら良いのだろうか?というのは、考えれば考えるほど非常に難しい。「回復に向けたコミットメント」と「知識的遊戯」は全く異なるもののように思えて、しかし和人の自分の立場ではその線引きが意外とシビアな気がする。 さらには、「思想的消費をしないぞ」という意志と、「100%責任を持てる人しか学んではならない”ということについては否定したい」という個人的な願望を、どのようにして両立して自分と他人に向き合っていくかという視点は、知ることを増やすたびに立ち返るべき課題として記憶したい。 そうして、ずっとこの本から教えてもらったこと/この本を経て疑問に思ったこと/この本から課せられた課題と共に生きていきたい。そう思うほどに、本当に読んでよかった。
アイヌがまなざす 痛みの声を聴くとき村上靖彦,石原真衣読み終わった@ 自宅「ふむふむアイヌ」にて、4月から半年間をかけて、みなさんと共に完走。読み終えたのは先々週だけれど、今日開催された「『アイヌがまなざす』総集編」を経てまたこの本が自分の体の一部となってくれた感覚があるので、今日を読み終えた日としよう。 まずこの本を読み終えて最も大きかった変化は、自身の揺らぎの芽生え。それは石原さんの厳しさ(これは毅然とした態度というべきかな)と、村上さんの慎重な言葉選びを浴びて、ある種これまでの自分の矜持の喪失とも言える、目線の破壊でもある、とにかく何らかの変化/揺らぎを引き出してもらった感覚。そのとき、ずっと当たり前のように誰か/何かをまなざしてきた自分の存在が浮かび上がる。これを遠くから眺めたときに、これこそが“まなざし”の変化か!と腑に落ちた。 しかしそれと同時に、やはりこの本に綴られた5名+1名の“遺書”を、いつでも忘れられる環境から、やっぱり“まなざして”いる自分の存在の色濃さも拭えない。これこそがまさに自分の特権性だし、まなざす側としての乱暴な態度であり、思想的消費を意味するのだろうなと反省する。 では思想的消費をしないために、どうしたら良いのだろうか?というのは、考えれば考えるほど非常に難しい。「回復に向けたコミットメント」と「知識的遊戯」は全く異なるもののように思えて、しかし和人の自分の立場ではその線引きが意外とシビアな気がする。 さらには、「思想的消費をしないぞ」という意志と、「100%責任を持てる人しか学んではならない”ということについては否定したい」という個人的な願望を、どのようにして両立して自分と他人に向き合っていくかという視点は、知ることを増やすたびに立ち返るべき課題として記憶したい。 そうして、ずっとこの本から教えてもらったこと/この本を経て疑問に思ったこと/この本から課せられた課題と共に生きていきたい。そう思うほどに、本当に読んでよかった。 - 2025年10月25日
 腸脳力長沼敬憲読み終わった@ 自宅腸活のTipsが詰まった本だと思って読み始めたのに、腸活のさらにその先の話というか、まさにそれが“腸脳力”なのだけど、強引に言い換えれば「腸を中心に生きる」という啓発本だった。バッキバキに腸至上主義者だし、この本の思想は全ての身体的/精神的/社会的敗因は腸を労らないことにあるくらいの勢い。後半にかけてさらにその違和感は増していくので(最終的に霊感の話が出てきて、流石に声が出た)、自分としては、話半分で読むことが比較的重要だった。 そして、だいたいこの本で出ている「XXという話がでている」とか「XXといわれている」とかのほとんどは、この本のどこにも出典元が明記されていない。先日まで『アイヌがまなざす』を読んでいたので、出典がない「XXといわれている」への不信感が半端ない。 この著者はあくまでもサイエンスライターであり、専門的な知識を研究機関で学んだ医者/学者ではない。自分の選んだ専門家から聞いた話を、自分の解釈を挟みながら本にする、ある種の危うさを感じる。 この本は常に「どのように腸活するか」ではなく「なぜ腸活が重要なのか(腸活しないからダメなんだぞ)」ということを延々と語っていた。
腸脳力長沼敬憲読み終わった@ 自宅腸活のTipsが詰まった本だと思って読み始めたのに、腸活のさらにその先の話というか、まさにそれが“腸脳力”なのだけど、強引に言い換えれば「腸を中心に生きる」という啓発本だった。バッキバキに腸至上主義者だし、この本の思想は全ての身体的/精神的/社会的敗因は腸を労らないことにあるくらいの勢い。後半にかけてさらにその違和感は増していくので(最終的に霊感の話が出てきて、流石に声が出た)、自分としては、話半分で読むことが比較的重要だった。 そして、だいたいこの本で出ている「XXという話がでている」とか「XXといわれている」とかのほとんどは、この本のどこにも出典元が明記されていない。先日まで『アイヌがまなざす』を読んでいたので、出典がない「XXといわれている」への不信感が半端ない。 この著者はあくまでもサイエンスライターであり、専門的な知識を研究機関で学んだ医者/学者ではない。自分の選んだ専門家から聞いた話を、自分の解釈を挟みながら本にする、ある種の危うさを感じる。 この本は常に「どのように腸活するか」ではなく「なぜ腸活が重要なのか(腸活しないからダメなんだぞ)」ということを延々と語っていた。 - 2025年8月29日
 私は男でフェミニストですチェ・スンボム,金みんじょん読み終わった@ 電車弟や父親、友人に手渡したい。女性の友人にも贈りたい。地獄みたいな世の中で、こんな良書が生まれてくれるのなら、まだ生きる道筋はあるのかもしれない。 小学校5年生でも読めるように書いたとのことだったが、通勤電車の1往復半と、帰宅してからの1時間ちょっと。合計3時間46分で読めてしまった。それにしては良書すぎる。 「男性は生き、女性は生きのびる。」 金みんじょんさんの翻訳も素晴らしかった。 この本を読んだ人が増えることに比例して、 明日誰かを傷つける言葉が一文減るかもな、 なんて、本気で思ってしまう。 本気で思ってしまう。
私は男でフェミニストですチェ・スンボム,金みんじょん読み終わった@ 電車弟や父親、友人に手渡したい。女性の友人にも贈りたい。地獄みたいな世の中で、こんな良書が生まれてくれるのなら、まだ生きる道筋はあるのかもしれない。 小学校5年生でも読めるように書いたとのことだったが、通勤電車の1往復半と、帰宅してからの1時間ちょっと。合計3時間46分で読めてしまった。それにしては良書すぎる。 「男性は生き、女性は生きのびる。」 金みんじょんさんの翻訳も素晴らしかった。 この本を読んだ人が増えることに比例して、 明日誰かを傷つける言葉が一文減るかもな、 なんて、本気で思ってしまう。 本気で思ってしまう。 - 2025年4月17日
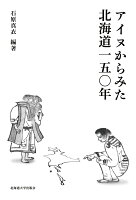 アイヌからみた北海道150年石原真衣読み終わった@ 胡弓 原宿店ふむふむアイヌ1冊目の課題図書。 いまを生きるアイヌの人々の語りが、人の数だけの角度から紡がれたのち、最後に迎える新井かおりさんと鵜澤加那子さんの文章。個から論へ発展させ、その論から最後はまた個のリスペクトへ。この本の構造がとても真摯で、その姿勢からも感じることがとてつもなく多い良書。自分の当たり前がいかに自分だけの当たり前かという事実に打ちのめされる。 法は、政策は、育てゆく苗である。 自分の生まれ育った愛する故郷、北海道/アイヌモシリを、愛し続けるために、自分に何ができるのか考え続けたい。 [「人間である」とは、物語を継承し、紡ぎ続けるということです。痛みに向き合い、受け入れ、それを希望にすることができるのは、人間である証です。]
アイヌからみた北海道150年石原真衣読み終わった@ 胡弓 原宿店ふむふむアイヌ1冊目の課題図書。 いまを生きるアイヌの人々の語りが、人の数だけの角度から紡がれたのち、最後に迎える新井かおりさんと鵜澤加那子さんの文章。個から論へ発展させ、その論から最後はまた個のリスペクトへ。この本の構造がとても真摯で、その姿勢からも感じることがとてつもなく多い良書。自分の当たり前がいかに自分だけの当たり前かという事実に打ちのめされる。 法は、政策は、育てゆく苗である。 自分の生まれ育った愛する故郷、北海道/アイヌモシリを、愛し続けるために、自分に何ができるのか考え続けたい。 [「人間である」とは、物語を継承し、紡ぎ続けるということです。痛みに向き合い、受け入れ、それを希望にすることができるのは、人間である証です。] - 2025年4月9日
 シーズ・レイン平中悠一読み終わった@ デニーズ 亀有駅前店ハタチの夏から憧れ続けていた一冊。書店もネットもどこにも売っていなくて、2023年の4月に目黒川沿いの本屋で見つけて、まだ初任給も出ていないのにプレミア価格で即購入した。読むなら絶対に雨の日に休憩を入れることなく読み切りたくて、ずっと本棚のいちばん真ん中に待機させ続けて2年弱。今日は1人、我が家のふわもこ犬はトリミング。そして久しぶりの雨。ファミレス快適認定研究所設立の原点とも言える駅前のデニーズにおひとり様入店。時は来たり。ハムの盛り合わせと味噌汁で挑んだその内容は、まさかの、微妙……! 何が微妙と感じたのだろうか。おそらくそれは、時代とともに気づけるようになった価値観の問題なのだと思う。“僕”の文章からあまりに自己陶酔を感じすぎて、冷めてしまった。 憧れてから4年だもんな、きっと4年前に読んでいたらバイブルになっていただろうな。けどこの4年間でいろんな本や映画と出会って、僕はフェミニストになった。だからこの本のあらゆる場面に、モヤっとしてしまうことがあった。だからナルシズムを受け入れられなかった。今の価値観でひと昔前を測るのはナンセンスだというのもあるけれど、だからと言って今を生きている僕はこの本を絶賛できない。タイミングってあるよね。でも偶然なのかこの本は「タイミングってあったんだね」ということを話していた本な気もする。人は時間の流れとともに変わっていくし、少年はいつかPOPEYEを卒業する。けれど今も昔も、すべての瞬間で人は弱くて脆くて面白いし、今も昔も、神戸はずっと良い街だ。そういう本だった。
シーズ・レイン平中悠一読み終わった@ デニーズ 亀有駅前店ハタチの夏から憧れ続けていた一冊。書店もネットもどこにも売っていなくて、2023年の4月に目黒川沿いの本屋で見つけて、まだ初任給も出ていないのにプレミア価格で即購入した。読むなら絶対に雨の日に休憩を入れることなく読み切りたくて、ずっと本棚のいちばん真ん中に待機させ続けて2年弱。今日は1人、我が家のふわもこ犬はトリミング。そして久しぶりの雨。ファミレス快適認定研究所設立の原点とも言える駅前のデニーズにおひとり様入店。時は来たり。ハムの盛り合わせと味噌汁で挑んだその内容は、まさかの、微妙……! 何が微妙と感じたのだろうか。おそらくそれは、時代とともに気づけるようになった価値観の問題なのだと思う。“僕”の文章からあまりに自己陶酔を感じすぎて、冷めてしまった。 憧れてから4年だもんな、きっと4年前に読んでいたらバイブルになっていただろうな。けどこの4年間でいろんな本や映画と出会って、僕はフェミニストになった。だからこの本のあらゆる場面に、モヤっとしてしまうことがあった。だからナルシズムを受け入れられなかった。今の価値観でひと昔前を測るのはナンセンスだというのもあるけれど、だからと言って今を生きている僕はこの本を絶賛できない。タイミングってあるよね。でも偶然なのかこの本は「タイミングってあったんだね」ということを話していた本な気もする。人は時間の流れとともに変わっていくし、少年はいつかPOPEYEを卒業する。けれど今も昔も、すべての瞬間で人は弱くて脆くて面白いし、今も昔も、神戸はずっと良い街だ。そういう本だった。
読み込み中...
