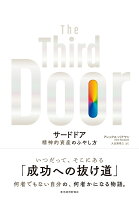積読本を減らしたい
@tsundoku-herasu
毎日本のことばかり考えてる。
「いつか読もう」と溜め込んだ数百冊の積読本を
少しでも減らしたい。
減らしたいのに読みたい本はどんどん増えてる。
2026年の目標:積読本を減らして本棚を捨てる
- 2026年2月25日
 自分を変える方法ケイティ・ミルクマン,アンジェラ・ダックワース,櫻井祐子かつて読んだいやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学 「私たちの意思決定は、仲間集団の規範に大きな影響を受ける。だから高い目標をめざすときはよい仲間に囲まれることが大切であり、またよくない仲間に囲まれると害を受けることがある」
自分を変える方法ケイティ・ミルクマン,アンジェラ・ダックワース,櫻井祐子かつて読んだいやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学 「私たちの意思決定は、仲間集団の規範に大きな影響を受ける。だから高い目標をめざすときはよい仲間に囲まれることが大切であり、またよくない仲間に囲まれると害を受けることがある」 - 2026年2月25日
- 2026年2月25日
 囚われし者たちの国──世界の刑務所に正義を訪ねてバズ・ドライシンガー,梶山あゆみかつて読んだ「確率論と心理学に関する研究からは、刑務所がもつ抑止効果など幻想にすぎないことが浮き彫りにされている。刑務所行きを恐れて犯罪を思いとどまる者などほとんどいない。犯罪行為がなされようとしているまさにそのときに、刑務所が存在するという現実が犯罪者の思考回路をよぎることなどまずないのだ」 ブックデザイン:鈴木成一デザイン室 2021年3月6日日本経済新聞書評欄掲載
囚われし者たちの国──世界の刑務所に正義を訪ねてバズ・ドライシンガー,梶山あゆみかつて読んだ「確率論と心理学に関する研究からは、刑務所がもつ抑止効果など幻想にすぎないことが浮き彫りにされている。刑務所行きを恐れて犯罪を思いとどまる者などほとんどいない。犯罪行為がなされようとしているまさにそのときに、刑務所が存在するという現実が犯罪者の思考回路をよぎることなどまずないのだ」 ブックデザイン:鈴木成一デザイン室 2021年3月6日日本経済新聞書評欄掲載 - 2026年2月25日
 山火事と地球の進化アンドルー・C・スコット,矢部淳,矢野真千子かつて読んだ『私たちが現在の世界でも未来の世界でも火事と共存していくつもりなら、火のことをもっと知らなければならないということだ。4億年の火の歴史について、「地球システム」を動かしている火の役割について、ヒトは火とどんな関係を築いていけばいいのかについて、学ぶべきことはたくさんある』
山火事と地球の進化アンドルー・C・スコット,矢部淳,矢野真千子かつて読んだ『私たちが現在の世界でも未来の世界でも火事と共存していくつもりなら、火のことをもっと知らなければならないということだ。4億年の火の歴史について、「地球システム」を動かしている火の役割について、ヒトは火とどんな関係を築いていけばいいのかについて、学ぶべきことはたくさんある』 - 2026年2月25日
 男も女もみんなフェミニストでなきゃくぼたのぞみ,チママンダ・ンゴズィ・アディーチェかつて読んだフェミニストについてのエッセイ。 ブックデザイン:水戸部功 2017年8月20日朝日新聞 2017年12月24日読売新聞 書評欄掲載
男も女もみんなフェミニストでなきゃくぼたのぞみ,チママンダ・ンゴズィ・アディーチェかつて読んだフェミニストについてのエッセイ。 ブックデザイン:水戸部功 2017年8月20日朝日新聞 2017年12月24日読売新聞 書評欄掲載 - 2026年2月24日
 新版 地図で見る中国ハンドブックティエリ・サンジュアンかつて読んだ「新疆ウイグル自治区のとくに北部は、地政学的要衝であるため、国家投資によって優遇を受けていた。中国政府が特権的政策をとったのは、東部地域や外国からの投資を西部にひきつけ、それによって経済協力や技術協力を確立し、教育を推進するためであった」
新版 地図で見る中国ハンドブックティエリ・サンジュアンかつて読んだ「新疆ウイグル自治区のとくに北部は、地政学的要衝であるため、国家投資によって優遇を受けていた。中国政府が特権的政策をとったのは、東部地域や外国からの投資を西部にひきつけ、それによって経済協力や技術協力を確立し、教育を推進するためであった」 - 2026年2月24日
 地図で見るヨーロッパハンドブックフランク・テタール,ピエール=アレクサンドル・ムニエ,蔵持不三也かつて読んだ「ヨーロッパとアジアにまたがる世界最大の領土を擁し、きわめて豊富な鉱物資源を誇り、世界第2位の核保有国、さらに旧ソ連を引き継いで国連安全保障常任理事国にもなっているロシアは、プーチン大統領の就任以来、国際的にもヨーロッパ的にもグローバルパワーをもって任じ、EUとその加盟国とのあいだで緊張を高めている」
地図で見るヨーロッパハンドブックフランク・テタール,ピエール=アレクサンドル・ムニエ,蔵持不三也かつて読んだ「ヨーロッパとアジアにまたがる世界最大の領土を擁し、きわめて豊富な鉱物資源を誇り、世界第2位の核保有国、さらに旧ソ連を引き継いで国連安全保障常任理事国にもなっているロシアは、プーチン大統領の就任以来、国際的にもヨーロッパ的にもグローバルパワーをもって任じ、EUとその加盟国とのあいだで緊張を高めている」 - 2026年2月24日
 はてなの国際法岩本誠吾,戸田五郎かつて読んだ「領土問題は、法解釈を含めて、国際法に基づいた議論が最優先させるべきです。中国の領有権主張も力を背景とした現状変更よりも、日本が韓国に申し出たように、国際司法裁判所への付託が、相手国の国民感情を逆なですることなく、最も国際社会に説得的な解決方法であると思われます」
はてなの国際法岩本誠吾,戸田五郎かつて読んだ「領土問題は、法解釈を含めて、国際法に基づいた議論が最優先させるべきです。中国の領有権主張も力を背景とした現状変更よりも、日本が韓国に申し出たように、国際司法裁判所への付託が、相手国の国民感情を逆なですることなく、最も国際社会に説得的な解決方法であると思われます」 - 2026年2月24日
- 2026年2月24日
- 2026年2月24日
- 2026年2月24日
- 2026年2月24日
 がろあむし舘野鴻かつて読んだ私たち人間は常に住みやすい環境を作り出してる。 ところが虫たちにとってはそれは必ずしもいい環境ではなかったりする。 共生とは何かを考えさせられる。 「いま私たちが見ているこの世界も、ずっと同じではなく、長い時間のうちに変わっていきます。変わらないものはあるのでしょうか。循環しつづける命の境目は、どこにあるのでしょうか」
がろあむし舘野鴻かつて読んだ私たち人間は常に住みやすい環境を作り出してる。 ところが虫たちにとってはそれは必ずしもいい環境ではなかったりする。 共生とは何かを考えさせられる。 「いま私たちが見ているこの世界も、ずっと同じではなく、長い時間のうちに変わっていきます。変わらないものはあるのでしょうか。循環しつづける命の境目は、どこにあるのでしょうか」 - 2026年2月24日
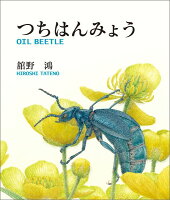 つちはんみょう舘野鴻かつて読んだ知らないことばかりで自分の「人間目線」を反省した。 絵本とは思えないようなあとがきにしびれる。 「どんな姿でも、奇跡の末に生まれた命です。それはつちはんみょうだけではなく、私たちを含めたどの生き物も同じ。そして、死んでいったたくさんの命の上にいま私たちがいる」
つちはんみょう舘野鴻かつて読んだ知らないことばかりで自分の「人間目線」を反省した。 絵本とは思えないようなあとがきにしびれる。 「どんな姿でも、奇跡の末に生まれた命です。それはつちはんみょうだけではなく、私たちを含めたどの生き物も同じ。そして、死んでいったたくさんの命の上にいま私たちがいる」 - 2026年2月24日
 メンタルと体調のリセット術中谷彰宏かつて読んだ『本の役割は、いろいろな考え方を提示して、みんなが考えるキッカケをつくることです。 本の通りにする必要はありません。 本を読むことで、「そんな考え方、そんなやり方もあるのか」と、考えてもらえればいいのです』
メンタルと体調のリセット術中谷彰宏かつて読んだ『本の役割は、いろいろな考え方を提示して、みんなが考えるキッカケをつくることです。 本の通りにする必要はありません。 本を読むことで、「そんな考え方、そんなやり方もあるのか」と、考えてもらえればいいのです』 - 2026年2月23日
- 2026年2月23日
 「専門家」とは誰か佐藤卓己,村上陽一郎,瀬川至朗,神里達博,藤垣裕子,隠岐さや香かつて読んだ「教養とは、本を読んで知識を蓄えればよいのではない。また、異分野のひととの意見の対立をこわがっていてはいけない。本を批判的に読んで鍛えられた思考力と議論の実践で、他者との対立を生む自らの暗黙の前提に立ち返り、多角的に物事を考えることを通して、答えのでない問いや直面する課題に応用すること」
「専門家」とは誰か佐藤卓己,村上陽一郎,瀬川至朗,神里達博,藤垣裕子,隠岐さや香かつて読んだ「教養とは、本を読んで知識を蓄えればよいのではない。また、異分野のひととの意見の対立をこわがっていてはいけない。本を批判的に読んで鍛えられた思考力と議論の実践で、他者との対立を生む自らの暗黙の前提に立ち返り、多角的に物事を考えることを通して、答えのでない問いや直面する課題に応用すること」 - 2026年2月23日
 イネという不思議な植物稲垣栄洋かつて読んだ面白い。 「玄米に対して、私たちが食べる白いお米は胚芽の部分が取り除かれている。つまり、私たちは、種子の発芽の栄養分の部分だけを取り出して食べているのである。たとえるなら、赤ちゃんのミルクを横取りしているようなものなのだ」
イネという不思議な植物稲垣栄洋かつて読んだ面白い。 「玄米に対して、私たちが食べる白いお米は胚芽の部分が取り除かれている。つまり、私たちは、種子の発芽の栄養分の部分だけを取り出して食べているのである。たとえるなら、赤ちゃんのミルクを横取りしているようなものなのだ」 - 2026年2月23日
 自然のとびらさいとうみわ,ケイ・マグワイア,ダニエル・クロルかつて読んだダニエル・クロルさんの絵が好き。 2015年の本なので SDGs というキーワードは出てこないけど、それでも生き物や環境のことも学ことができる。
自然のとびらさいとうみわ,ケイ・マグワイア,ダニエル・クロルかつて読んだダニエル・クロルさんの絵が好き。 2015年の本なので SDGs というキーワードは出てこないけど、それでも生き物や環境のことも学ことができる。 - 2026年2月23日
 ケチャップマン鈴木のりたけかつて読んだ面白い。 終盤、ホラーな展開になったのはかなり意外だった。 ハッピーエンドなのかアンハッピーエンドなのかどっちにも解釈できる終わり方。 ケチャップマンは自分のケチャップを褒めてもらってるのにそれほどうれしそうじゃない。 彼は何を求めていたのか気になる。
ケチャップマン鈴木のりたけかつて読んだ面白い。 終盤、ホラーな展開になったのはかなり意外だった。 ハッピーエンドなのかアンハッピーエンドなのかどっちにも解釈できる終わり方。 ケチャップマンは自分のケチャップを褒めてもらってるのにそれほどうれしそうじゃない。 彼は何を求めていたのか気になる。
読み込み中...