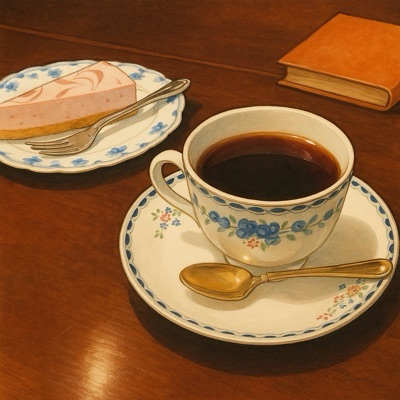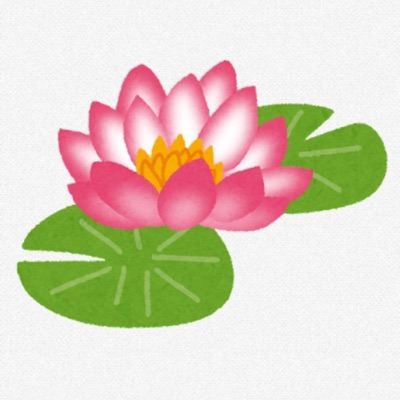父ではありませんが 第三者として考える

23件の記録
 おいしいごはん@Palfa0462025年8月20日読み終わった後半はしんどくてだいぶ駆け足で読んだけど、とりあえず読んで良かったと思う。自分にはない視点がたくさんだったし、それをきっかけにして共感だけではなく反発も含めて考えることができた。 途中にも書いたけど、問いかけやその対象に対しては納得する部分も多いものの、その中での議論の持っていき方はうーんと思うところが多かった(からこそ、考える契機になったので個人的には良かったのかも)。
おいしいごはん@Palfa0462025年8月20日読み終わった後半はしんどくてだいぶ駆け足で読んだけど、とりあえず読んで良かったと思う。自分にはない視点がたくさんだったし、それをきっかけにして共感だけではなく反発も含めて考えることができた。 途中にも書いたけど、問いかけやその対象に対しては納得する部分も多いものの、その中での議論の持っていき方はうーんと思うところが多かった(からこそ、考える契機になったので個人的には良かったのかも)。



 おいしいごはん@Palfa0462025年8月19日読んでる半分を過ぎたところまで読んでいる。 大半は賛成に思える考えだし、視点も自分にはないものが多くて面白い。一方、論理に疑問を覚えることも少なくない。 憶測を断定したり、一つのケースをもって全体を語ろうとしたりしていると感じてしまった。
おいしいごはん@Palfa0462025年8月19日読んでる半分を過ぎたところまで読んでいる。 大半は賛成に思える考えだし、視点も自分にはないものが多くて面白い。一方、論理に疑問を覚えることも少なくない。 憶測を断定したり、一つのケースをもって全体を語ろうとしたりしていると感じてしまった。
 おいしいごはん@Palfa0462025年8月16日読んでる借りてきたこれも図書館で借りてきた本。 自分にない視点が多くて面白い。 --- p.19で引用されている長島有里枝さんの発言 "長島さんが「当事者の切実な言葉を傾聴することが重要事項であることにちがいないのだけれど、『第三者には言われたくない』と思ってしまうような意見が存在することと、第三者が語る行為そのものを切り離さないと、何も言えなくなってしまうのでは、という疑問も湧きます」(『すばる』2018年9月号)と言っていた。第三者にも当事者性がある。" たしかにそうだなと思いつつ、今読んでいるページでは子育てをしながら働いている人が、子育てを経験している人から「決めつけられる」経験について書かれており、当事者性という言葉の難しさを感じている。当事者の事の部分を抽象化すればするほど、その語りは多様になるだろう。そうなった時に当事者は一体どういう意味を持つんだろうかって思ったりした。
おいしいごはん@Palfa0462025年8月16日読んでる借りてきたこれも図書館で借りてきた本。 自分にない視点が多くて面白い。 --- p.19で引用されている長島有里枝さんの発言 "長島さんが「当事者の切実な言葉を傾聴することが重要事項であることにちがいないのだけれど、『第三者には言われたくない』と思ってしまうような意見が存在することと、第三者が語る行為そのものを切り離さないと、何も言えなくなってしまうのでは、という疑問も湧きます」(『すばる』2018年9月号)と言っていた。第三者にも当事者性がある。" たしかにそうだなと思いつつ、今読んでいるページでは子育てをしながら働いている人が、子育てを経験している人から「決めつけられる」経験について書かれており、当事者性という言葉の難しさを感じている。当事者の事の部分を抽象化すればするほど、その語りは多様になるだろう。そうなった時に当事者は一体どういう意味を持つんだろうかって思ったりした。




 もみぃ@momie_6662025年7月25日読み終わった私は「じゃないほう」だ。 母ではない。今後、妻になることはあるかもしれないが、おそらく母にはなれない。ならないのではなく、なれないという罪悪感は消えることはないけど、それでいいと思う。 自分語りをしてしまったが、ぐるぐるする思考を淡々と解いてくれるような本だった。 本文にも「連載時に、毎回読んでくれている人から『あの連載は、同じところをぐるぐるまわっているような感じがあって、それがいい』と言われた。」とあり、同意する。 いない人は、いる人を優勢とすると常に劣勢で被害者みたいな位置に置きたがる。というかその位置だと無限に愚痴を言えるから。 とても偏見で個人的な言葉だ。 いい加減その位置から脱皮したい。
もみぃ@momie_6662025年7月25日読み終わった私は「じゃないほう」だ。 母ではない。今後、妻になることはあるかもしれないが、おそらく母にはなれない。ならないのではなく、なれないという罪悪感は消えることはないけど、それでいいと思う。 自分語りをしてしまったが、ぐるぐるする思考を淡々と解いてくれるような本だった。 本文にも「連載時に、毎回読んでくれている人から『あの連載は、同じところをぐるぐるまわっているような感じがあって、それがいい』と言われた。」とあり、同意する。 いない人は、いる人を優勢とすると常に劣勢で被害者みたいな位置に置きたがる。というかその位置だと無限に愚痴を言えるから。 とても偏見で個人的な言葉だ。 いい加減その位置から脱皮したい。