カウンターエリート

20件の記録
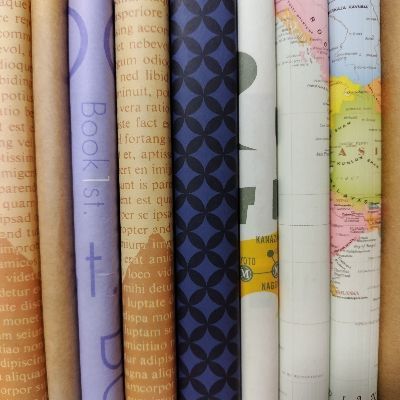 六輪花@rokurinka2025年12月20日読み終わった図書館本コンパクトに今までの流れが分かって良かった。 民主党支持したり共和党に行ったりと彼らの行動って矛盾していないか?と思っていたけど、ちゃんと彼らの中では筋が通っているらしい。
六輪花@rokurinka2025年12月20日読み終わった図書館本コンパクトに今までの流れが分かって良かった。 民主党支持したり共和党に行ったりと彼らの行動って矛盾していないか?と思っていたけど、ちゃんと彼らの中では筋が通っているらしい。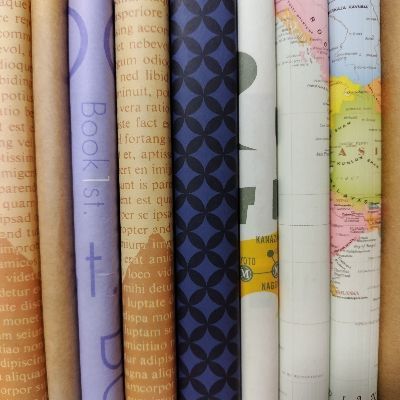 六輪花@rokurinka2025年12月17日図書館本読んでいるちょっと前に流行った新書を読みシリーズ テクノリバタリアンと登場人物が多少被っている。まぁ、そうだよね⋯。こっちの方が物語っぽい語り口かな。
六輪花@rokurinka2025年12月17日図書館本読んでいるちょっと前に流行った新書を読みシリーズ テクノリバタリアンと登場人物が多少被っている。まぁ、そうだよね⋯。こっちの方が物語っぽい語り口かな。
 夏の季語@natsunokigo2025年10月5日読み終わった・「いま最も大衆を惹きつける物語は何なのか?」という嗅覚が大きな意味を持つようになってきている時代。 ・昨日読んだ朝井リョウの小説『イン・ザ・メガチャーチ』と重なる部分も多く、面白く読んだ。
夏の季語@natsunokigo2025年10月5日読み終わった・「いま最も大衆を惹きつける物語は何なのか?」という嗅覚が大きな意味を持つようになってきている時代。 ・昨日読んだ朝井リョウの小説『イン・ザ・メガチャーチ』と重なる部分も多く、面白く読んだ。

 いなだ易@penpenbros2025年10月3日読み終わったピーター・ティールの話。投資家ってやぱバチクソエリートなんや〜て思って読んでたらなんか急にクソわかる話はじまってびっくりした。ローファーム、この世の最果ての労働。 「ティールは大学で教わったジラールの思想、すなわち模倣の欲望を身に染みて理解した。自分がどうしても学歴や地位を欲しいと思っていた理由は、実はそれが魅力的なのではなく、他人が欲しがっているからだという事実に気が付いたのだ。そして、模倣の欲望によって競争を続けても、ほとんどの人は敗者になると悟った。」 ↑がちでがちでがちでわかる 模倣と競争を無限回繰り返してこれが出来上がるなら、人類は模倣をやめろ!!!!とめちゃくちゃ思っている。俺ってカウンターエリートだったの?模倣の欲望に対する批判、、、 やぱ、【ブルシット】ビッグローファームについて語るスレ【激務】が必要かも。現代を生きててビッグローファーム以上に潜入したい場所なくない?! ごめんこのテンションで読むものではないか? しかし、モチベーションや課題感には共鳴してしまったものの、現状の破壊によって作りたかったのはどんな空間、どんな風景だったの?と思う。国家が移民を有形無形の暴力で排斥する風景ですか。 分極化するアメリカ政治を理解するうえで重要なのはイデオロギー的な左右ではなく、破壊主義者か、現状維持主義者か。という評価軸(理解の補助線)にはかなり納得した。 私自身、上に書いたとおり官僚主義的なシステムに退屈し、内面化に挫折した人間である。けれどもそうした場所で働き続ける人々の、ある種職人的な献身によって、社会秩序ーー現代を生きる私たちが当たり前だと思っている社会システムのことーーが保たれている事実を今こそ強調すべきだと感じてもいる。韓国の戒厳令が適正な手続によって、きわめて迅速に解除された時に強く実感したのでした。 「まず官僚制の解体によって、市民の暮らしを支える行政サービスなどが、公務員や官僚の恣意性に左右される可能性がある。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが指摘したように、官僚制は恣意性を排除した事務処理を特徴としている。すなわち、人によって業務処理のやり方に差が出ないように、規則によって対応方法が規定されている。 」 めっちゃ面白かったし今読めて良かった本ですね。
いなだ易@penpenbros2025年10月3日読み終わったピーター・ティールの話。投資家ってやぱバチクソエリートなんや〜て思って読んでたらなんか急にクソわかる話はじまってびっくりした。ローファーム、この世の最果ての労働。 「ティールは大学で教わったジラールの思想、すなわち模倣の欲望を身に染みて理解した。自分がどうしても学歴や地位を欲しいと思っていた理由は、実はそれが魅力的なのではなく、他人が欲しがっているからだという事実に気が付いたのだ。そして、模倣の欲望によって競争を続けても、ほとんどの人は敗者になると悟った。」 ↑がちでがちでがちでわかる 模倣と競争を無限回繰り返してこれが出来上がるなら、人類は模倣をやめろ!!!!とめちゃくちゃ思っている。俺ってカウンターエリートだったの?模倣の欲望に対する批判、、、 やぱ、【ブルシット】ビッグローファームについて語るスレ【激務】が必要かも。現代を生きててビッグローファーム以上に潜入したい場所なくない?! ごめんこのテンションで読むものではないか? しかし、モチベーションや課題感には共鳴してしまったものの、現状の破壊によって作りたかったのはどんな空間、どんな風景だったの?と思う。国家が移民を有形無形の暴力で排斥する風景ですか。 分極化するアメリカ政治を理解するうえで重要なのはイデオロギー的な左右ではなく、破壊主義者か、現状維持主義者か。という評価軸(理解の補助線)にはかなり納得した。 私自身、上に書いたとおり官僚主義的なシステムに退屈し、内面化に挫折した人間である。けれどもそうした場所で働き続ける人々の、ある種職人的な献身によって、社会秩序ーー現代を生きる私たちが当たり前だと思っている社会システムのことーーが保たれている事実を今こそ強調すべきだと感じてもいる。韓国の戒厳令が適正な手続によって、きわめて迅速に解除された時に強く実感したのでした。 「まず官僚制の解体によって、市民の暮らしを支える行政サービスなどが、公務員や官僚の恣意性に左右される可能性がある。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが指摘したように、官僚制は恣意性を排除した事務処理を特徴としている。すなわち、人によって業務処理のやり方に差が出ないように、規則によって対応方法が規定されている。 」 めっちゃ面白かったし今読めて良かった本ですね。

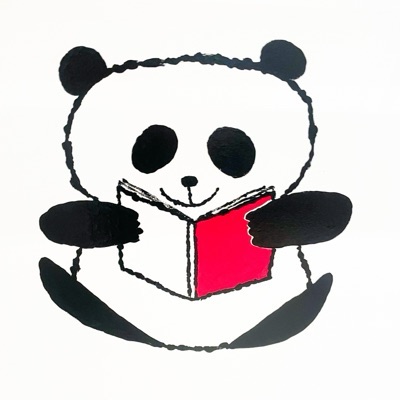 ぱんだちゃん@pandamental2025年9月24日読み終わった主にトランプとその周囲のカウンターエリートが、なるべくしてなったんだと理解できた。 本にも書かれているが、アメリカ以外でも再現性が高く、欧州各国や日本でも例外なく同じような流れがあると感じた。
ぱんだちゃん@pandamental2025年9月24日読み終わった主にトランプとその周囲のカウンターエリートが、なるべくしてなったんだと理解できた。 本にも書かれているが、アメリカ以外でも再現性が高く、欧州各国や日本でも例外なく同じような流れがあると感じた。
 semi@hirakegoma2025年4月17日読み終わったラジオで著者が紹介しているのを聞いて購入。トランプに対しての報道は、差別や強引なディールに関する話が多いが、なぜイーロン・マスクをはじめとしたシリコンバレーを代表するに人たちが支持しているのか、興味があった。 エリート主義に対するカウンターとして生じた現象なのだというストーリーで、何となくしっくりと理解することができた。差別主義、権威主義、右翼、反知性主義のイメージがあったが、トランプ支持者はそれらが親和性を持ちながらも全て当てはまるわけではなく、現状に対して「何かがおかしい」と感じ、その破壊を求めることを共有しているのだと理解した。日本で起きていることも含めて気持ちはよくわかる。世界で起きている現象を知るひとつの大きな手がかりを得た感じ。 ただ、「おわりに」で述べられている筆者の考え(?)は正直なところよくわからなかった。私の頭が悪いだけかも。
semi@hirakegoma2025年4月17日読み終わったラジオで著者が紹介しているのを聞いて購入。トランプに対しての報道は、差別や強引なディールに関する話が多いが、なぜイーロン・マスクをはじめとしたシリコンバレーを代表するに人たちが支持しているのか、興味があった。 エリート主義に対するカウンターとして生じた現象なのだというストーリーで、何となくしっくりと理解することができた。差別主義、権威主義、右翼、反知性主義のイメージがあったが、トランプ支持者はそれらが親和性を持ちながらも全て当てはまるわけではなく、現状に対して「何かがおかしい」と感じ、その破壊を求めることを共有しているのだと理解した。日本で起きていることも含めて気持ちはよくわかる。世界で起きている現象を知るひとつの大きな手がかりを得た感じ。 ただ、「おわりに」で述べられている筆者の考え(?)は正直なところよくわからなかった。私の頭が悪いだけかも。













