

semi
@hirakegoma
読みたい本のメモをしています。読むのは遅いです。
- 2026年2月24日
 本当の登山の話をしよう服部文祥気になる
本当の登山の話をしよう服部文祥気になる - 2026年2月19日
 言語化するための小説思考小川哲気になる
言語化するための小説思考小川哲気になる - 2026年2月19日
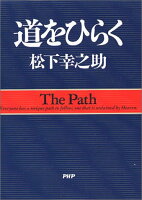 道をひらく松下幸之助気になる
道をひらく松下幸之助気になる - 2026年2月15日
 フランス人記者、日本の学校に驚く西村カリン気になる
フランス人記者、日本の学校に驚く西村カリン気になる - 2026年2月6日
- 2026年2月5日
 意味の深みへ井筒俊彦気になる
意味の深みへ井筒俊彦気になる - 2026年2月2日
 その島のひとたちは、ひとの話をきかない森川すいめい気になる
その島のひとたちは、ひとの話をきかない森川すいめい気になる - 2026年2月1日
 体育会系小野雄大気になる
体育会系小野雄大気になる - 2026年1月30日
 忘れられた日本人宮本常一読み終わった
忘れられた日本人宮本常一読み終わった - 2026年1月26日
 単一民族神話の起源小熊英二気になる
単一民族神話の起源小熊英二気になる - 2026年1月24日
 僕たちにはキラキラ生きる義務などない山田ルイ53世気になる
僕たちにはキラキラ生きる義務などない山田ルイ53世気になる - 2026年1月20日
 社会学史大澤真幸気になる
社会学史大澤真幸気になる - 2026年1月17日
- 2026年1月17日
 幻の麺料理魚柄仁之助気になる
幻の麺料理魚柄仁之助気になる - 2026年1月17日
 古本屋台Q.B.B.,久住卓也,久住昌之気になる
古本屋台Q.B.B.,久住卓也,久住昌之気になる - 2026年1月17日
 哲学者たちの<ほんとう>の仕事ナシム・エル・カブリ,野村真依子気になる
哲学者たちの<ほんとう>の仕事ナシム・エル・カブリ,野村真依子気になる - 2026年1月17日
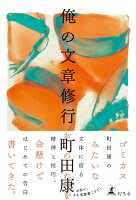 俺の文章修行町田康気になる
俺の文章修行町田康気になる - 2026年1月17日
 日本人柳田國男気になる
日本人柳田國男気になる - 2026年1月15日
 存在論的、郵便的東浩紀読み終わった筆者の本は、『動物化するポストモダン』に始まり、『訂正可能性の哲学』まで、思想地図やゲンロンも含めて何冊も読んでいる気がするが、この本はハードルが高い気がしてずっと及び腰だった。積読状態だったが、昨年末に思い立って読み始めた。 私は哲学を体系的に学んだことのないサラリーマンだが、通勤時間にちまちま読み進め、なんとか読了。ハイデガーとフロイトだけは関連本を読んだことあったので助かったが、正直なところかなり読み進めるのは苦しかった。でも最後まで読み進められたのは、筆者の明解な文体と、何度も振り返りながら議論を進めてくれたためだろう。 内容の理解度としては不十分な気もするが、刺激的な読書だった。これからも別の本を読みつつ、この立ち戻りながら理解を深めていきたい。
存在論的、郵便的東浩紀読み終わった筆者の本は、『動物化するポストモダン』に始まり、『訂正可能性の哲学』まで、思想地図やゲンロンも含めて何冊も読んでいる気がするが、この本はハードルが高い気がしてずっと及び腰だった。積読状態だったが、昨年末に思い立って読み始めた。 私は哲学を体系的に学んだことのないサラリーマンだが、通勤時間にちまちま読み進め、なんとか読了。ハイデガーとフロイトだけは関連本を読んだことあったので助かったが、正直なところかなり読み進めるのは苦しかった。でも最後まで読み進められたのは、筆者の明解な文体と、何度も振り返りながら議論を進めてくれたためだろう。 内容の理解度としては不十分な気もするが、刺激的な読書だった。これからも別の本を読みつつ、この立ち戻りながら理解を深めていきたい。 - 2026年1月1日
 親鸞五木寛之気になる
親鸞五木寛之気になる
読み込み中...

