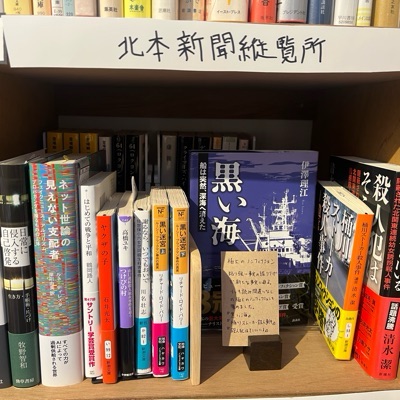日本経済の死角

32件の記録
 Ritsuki@Ritsu_second2026年2月23日読み終わったこういう本なかなか読んだことなかったけど、データから読み取れることと意見の棲み分けがちゃんとしていたし、論理構造も丁寧に述べられていてとてもわかりやすかった
Ritsuki@Ritsu_second2026年2月23日読み終わったこういう本なかなか読んだことなかったけど、データから読み取れることと意見の棲み分けがちゃんとしていたし、論理構造も丁寧に述べられていてとてもわかりやすかった- 酒泉@reads_mandara2026年1月31日買った読み終わった近代化の観点で歴史と現代をつなげて考えるときに、多くの学びを与えてくれる本であった。一般的な歴史書だけだと、イノベーションと格差の問題を扱うにしても、それを語る言葉が不足していたが、経済の用語で語ることで問題を整理しやすくなった。著者も言うように社会科学の再統合が必要であると、深く首肯した。

 でんてぃすこ@axelasayaka2026年1月4日読んでる結構わかりやすそうだなーって思って読み始めたけど、微妙に躓くところもあり…。経済音痴を実感。 自分の業界、生産性とは全く関係ないんだけど、教養として読んでみた。 日本経済が元気になって、たくさん皆さんに納税してもらわないとお国は医療にお金回してくれないからなぁ…(笑)
でんてぃすこ@axelasayaka2026年1月4日読んでる結構わかりやすそうだなーって思って読み始めたけど、微妙に躓くところもあり…。経済音痴を実感。 自分の業界、生産性とは全く関係ないんだけど、教養として読んでみた。 日本経済が元気になって、たくさん皆さんに納税してもらわないとお国は医療にお金回してくれないからなぁ…(笑)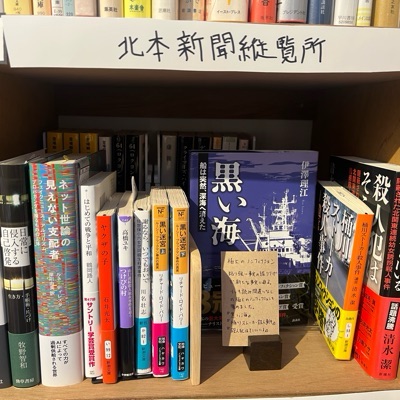 北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年11月5日読み終わった日本では労働生産性が30%も向上しているにもかかわらず、なぜ賃金が上がらないのかを解き明かす一冊。 極力専門用語を少なくしようと腐心されているのも伝わり、経済オンチの私でも理解しながら読み進めることができた。各章の冒頭には前章までの内容が要約されており、話題の転換に伴って論旨迷子になることもないような工夫も。読者に親切でだいぶ嬉しかった。 イノベーションには収奪的なものと包摂的なものがあるというのは新たな視点だった。 加えて、働き方改革が正社員労働者の労働力供給の柔軟性を失わせたことも問題視しており、直近の労働時間増を目論む政府の検討との一致を見た。いち労働者としては労働強化に繋がるような施策はやって欲しくないのが本音ですが…。 繰り返し述べられているのは、大企業が賃金上昇を行ってこなかったことが、いかに日本経済の成長を妨げたかの罪。 本筋では全くないが、「資本から得られる所得を優遇することで、労働から得られる所得を不利にしているのではないか(p258)」という一文。労働への忌避感、強く言うと嫌悪感のようなものを社会全体が持つようになっているのでは、という仮説を持っており、その考察を進めるヒントになりそう。
北本新聞縦覧所@kitamoto_juran2025年11月5日読み終わった日本では労働生産性が30%も向上しているにもかかわらず、なぜ賃金が上がらないのかを解き明かす一冊。 極力専門用語を少なくしようと腐心されているのも伝わり、経済オンチの私でも理解しながら読み進めることができた。各章の冒頭には前章までの内容が要約されており、話題の転換に伴って論旨迷子になることもないような工夫も。読者に親切でだいぶ嬉しかった。 イノベーションには収奪的なものと包摂的なものがあるというのは新たな視点だった。 加えて、働き方改革が正社員労働者の労働力供給の柔軟性を失わせたことも問題視しており、直近の労働時間増を目論む政府の検討との一致を見た。いち労働者としては労働強化に繋がるような施策はやって欲しくないのが本音ですが…。 繰り返し述べられているのは、大企業が賃金上昇を行ってこなかったことが、いかに日本経済の成長を妨げたかの罪。 本筋では全くないが、「資本から得られる所得を優遇することで、労働から得られる所得を不利にしているのではないか(p258)」という一文。労働への忌避感、強く言うと嫌悪感のようなものを社会全体が持つようになっているのでは、という仮説を持っており、その考察を進めるヒントになりそう。


- mac_355@mac_3352025年8月2日読み終わった・大企業の正社員を中心とした長期、雇用性におけるゼロベアが長く継続したことが、日本の長期停滞の原因 ・過去四半世紀で時間あたりの生産性は3割も上がっており、人口減が引き起こし、所得減少を十分に相殺できている。 ・メインバンク性が崩壊したことで、企業は、雇用リストラを避けるために、自己資本を厚くして、潤沢な流動性を保有する傾向になった ・イノベーションには包摂的なイノベーションと収奪的なイノベーションの二種類がある。
 たなぱんだ@tanapanda2025年2月7日読み終わった感想巷でよく言われる「日本の実質賃金を上げるために、労働生産性を向上させなければならない」という議論。しかし、本書が指摘する通り、実際に起きているのは「失われた30年の間、日本の労働生産性は着実に上がっていたのに、それが実質賃金に反映されてこなかった」という問題だ。こうした事実確認をした上で、著者は、金融緩和ではなく、雇用制度や税制、企業統治などの構造的な改革こそが必要だと論じている。 エコノミストや経済評論家の中には、極端な主張で注目を集めようとする人も多いが、著者の河野氏は比較的冷静な分析を行うタイプ。細かな点をみれば、経済学の知見を十分に踏まえていない部分や論拠不足な箇所もあるが、全体としての議論の方向性は妥当だと感じた。最終的に本書の主張に賛同しなかったとしても、少なくとも耳を傾ける価値はある議論だと思う。 「賃上げ」問題や日本経済の構造問題に関心がある人にはオススメできる一冊。
たなぱんだ@tanapanda2025年2月7日読み終わった感想巷でよく言われる「日本の実質賃金を上げるために、労働生産性を向上させなければならない」という議論。しかし、本書が指摘する通り、実際に起きているのは「失われた30年の間、日本の労働生産性は着実に上がっていたのに、それが実質賃金に反映されてこなかった」という問題だ。こうした事実確認をした上で、著者は、金融緩和ではなく、雇用制度や税制、企業統治などの構造的な改革こそが必要だと論じている。 エコノミストや経済評論家の中には、極端な主張で注目を集めようとする人も多いが、著者の河野氏は比較的冷静な分析を行うタイプ。細かな点をみれば、経済学の知見を十分に踏まえていない部分や論拠不足な箇所もあるが、全体としての議論の方向性は妥当だと感じた。最終的に本書の主張に賛同しなかったとしても、少なくとも耳を傾ける価値はある議論だと思う。 「賃上げ」問題や日本経済の構造問題に関心がある人にはオススメできる一冊。