

たなぱんだ
@tanapanda
とくに何者でもありません。ただ、博士課程にいるので、ちょっとだけ経済学のことを知っています。ほかの人より、写真を撮ることに少しばかり慣れています。いくらか本を読む時間も長いです。 そんなふうに暮らしています。
YouTube番組の「積読チャンネル」や「ゆる言語学ラジオ」が好きです。それぞれのサポーターコミュニティでも書籍レビューしてます。
- 2025年3月7日
 ネタバレなし読み終わった感想2025年のマイベスト小説がもう決まってしまった。 それくらい圧倒的な作品だった。 864ページ、一度も手を止められずに没入した。気づいたら朝。 物理的には読み終わっているのに、しばらく心は物語の中に残り続けていた。 長い長い旅をして、ようやく現実に帰って来られた。こんな読書体験、久しぶりだ。 主人公・空子は、自分自身を持たない。 他者の言動を〈トレース〉し、その場にふさわしい人格を作りながら生きていく。 そんな空子の生きる世界には、ピョコルンという可愛らしいペットがいる。 このピョコルンにある能力が備わったことで、世界は予想もつかない方向に向かっていく──。 SF感が出てくる中盤以降は、この物語がどこに向かっているのか全くわからず、ただただページを捲る手が止まらなかった。いつもの村田作品どおり「当たり前」がぶっ壊される。そして、読んでる間、頭を掴まれて揺さぶられるような感覚を覚える。 本作で、村田作品はひとつの到達点に辿り着いていたように思う。アイデンティティ、社会への適応、女性の生き方——これまでのテーマがすべて集結している。さらには、社会の分断や差別、テクノロジーと人間の関係性など、現代社会が抱える様々な問題までもが折り重なり、圧倒的な密度で迫ってくる。1回読んだだけでは消化しきれない。間違いなく、何度も読み返すと思う。 ただ、村田作品なので、いつもどおり好き嫌いは分かれるとは思う。 性的な表現やグロテスクな表現も多いし、人によっては倫理的に嫌悪感を抱くような描写もある。 正直、気軽に勧められる本ではない。それでも、いろんな人に読んでもらいたい。そんなジレンマに囚われている。
ネタバレなし読み終わった感想2025年のマイベスト小説がもう決まってしまった。 それくらい圧倒的な作品だった。 864ページ、一度も手を止められずに没入した。気づいたら朝。 物理的には読み終わっているのに、しばらく心は物語の中に残り続けていた。 長い長い旅をして、ようやく現実に帰って来られた。こんな読書体験、久しぶりだ。 主人公・空子は、自分自身を持たない。 他者の言動を〈トレース〉し、その場にふさわしい人格を作りながら生きていく。 そんな空子の生きる世界には、ピョコルンという可愛らしいペットがいる。 このピョコルンにある能力が備わったことで、世界は予想もつかない方向に向かっていく──。 SF感が出てくる中盤以降は、この物語がどこに向かっているのか全くわからず、ただただページを捲る手が止まらなかった。いつもの村田作品どおり「当たり前」がぶっ壊される。そして、読んでる間、頭を掴まれて揺さぶられるような感覚を覚える。 本作で、村田作品はひとつの到達点に辿り着いていたように思う。アイデンティティ、社会への適応、女性の生き方——これまでのテーマがすべて集結している。さらには、社会の分断や差別、テクノロジーと人間の関係性など、現代社会が抱える様々な問題までもが折り重なり、圧倒的な密度で迫ってくる。1回読んだだけでは消化しきれない。間違いなく、何度も読み返すと思う。 ただ、村田作品なので、いつもどおり好き嫌いは分かれるとは思う。 性的な表現やグロテスクな表現も多いし、人によっては倫理的に嫌悪感を抱くような描写もある。 正直、気軽に勧められる本ではない。それでも、いろんな人に読んでもらいたい。そんなジレンマに囚われている。 - 2025年3月5日
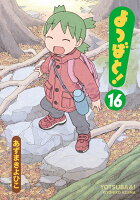 よつばと!(16)あずまきよひこネタバレあり読み終わった感想冒頭、よつばが自転車に乗る。 それだけのシーンなのに、胸がいっぱいになった。 1巻では、とーちゃんに「乗っちゃダメ」って言われていたのに。補助輪なしで風を切って走るよつばを見て、「成長したなぁ……」としみじみしてしまった。そういう視点で改めて見ると、1巻と比べてよつばの身長も伸びている。少しずつではあるけど、時間は確かに流れているんだな、と思う。 そして、最後の話。 まさかの大阪さんの登場に思わず声が出た。 あの独特の雰囲気……まさか「よつばと!」の世界に降臨するとは。 この巻が出るまでに4年待った。次の巻は何年後になるんだろう? きっとその頃には、よつばよりもうちの娘の方が大きくなってるはず。 現実の時間はあっという間に過ぎていく。 だからこそ、この物語の中のゆったりとした時間の流れが、たまらなく愛おしいのかもしれない。
よつばと!(16)あずまきよひこネタバレあり読み終わった感想冒頭、よつばが自転車に乗る。 それだけのシーンなのに、胸がいっぱいになった。 1巻では、とーちゃんに「乗っちゃダメ」って言われていたのに。補助輪なしで風を切って走るよつばを見て、「成長したなぁ……」としみじみしてしまった。そういう視点で改めて見ると、1巻と比べてよつばの身長も伸びている。少しずつではあるけど、時間は確かに流れているんだな、と思う。 そして、最後の話。 まさかの大阪さんの登場に思わず声が出た。 あの独特の雰囲気……まさか「よつばと!」の世界に降臨するとは。 この巻が出るまでに4年待った。次の巻は何年後になるんだろう? きっとその頃には、よつばよりもうちの娘の方が大きくなってるはず。 現実の時間はあっという間に過ぎていく。 だからこそ、この物語の中のゆったりとした時間の流れが、たまらなく愛おしいのかもしれない。 - 2025年3月5日
 ルポ 秀和幡ヶ谷レジデンス栗田シメイ読み終わった感想書籍化すると聞いた時点で「これは間違いなく面白い」と期待していたが、その期待を裏切らない一冊だった。 「なんだこの総会は。北朝鮮かよ!!」 マンションの総会で、こんな衝撃的な一言が飛び出す。引っ越し時の荷物はすべて「検閲」され、理事会が認めていない不動産業者は管理人が木槌で威嚇して追い返す。そんな独裁的な管理体制が敷かれたマンションで、住民たちが自治を取り戻すべく戦った1,200日の記録。 最終的に住民たちは理事会のポジションを奪還するのだけど、そこに至るまでの準備が緻密で驚かされる。決戦の場となる総会では、薄氷の上を進むかのような攻防のなかで、彼らが用意周到さが上手く機能していく。結末を知っていても手に汗握る展開で、ノンフィクションとは思えないほどのスリルがある。 ただ、この本が面白いのは、「悪の理事会 vs 正義の住民」といった単純な対立構造ではないこと。住民たちは一枚岩ではなく、急進派もいれば穏健派もいる。住民運動に不信感を抱いてる人もいる。運動の中で何度も対立し、「有志の会」は何度も解散の危機に遭う。 象徴的だったのが、総会当日の様子。1時間の予行演習をした後、会場へ向かう住民たち。だけど、みんな一緒に会場に行くのかと思いきや、直接向かう人もいれば一旦自宅に戻る人もいて、まったくまとまりがない。その光景が、そこまでの戦いの難しさを象徴しているようだった。けれど、そんなバラバラの人たちが、一致団結して目標を成し遂げた。そこに、この物語の本当の感動ポイントがあるのだと思う。 「独裁的な理事会と戦うマンション住民の闘争」という枠を超えて、異なる考えの人々をどう巻き込み、どう説得していくかという普遍的なテーマが描かれている。そういう意味では、以前「積読チャンネル」というYouTubeで紹介された『政治学者、PTA会長になる』と似た雰囲気もあるなと思っていたら、実は担当編集者が同じだったらしい。 ノンフィクション好きや不動産の闇エピソードが好きな人はもちろん、説得術についてヒントを得たい人にもおすすめしたい。
ルポ 秀和幡ヶ谷レジデンス栗田シメイ読み終わった感想書籍化すると聞いた時点で「これは間違いなく面白い」と期待していたが、その期待を裏切らない一冊だった。 「なんだこの総会は。北朝鮮かよ!!」 マンションの総会で、こんな衝撃的な一言が飛び出す。引っ越し時の荷物はすべて「検閲」され、理事会が認めていない不動産業者は管理人が木槌で威嚇して追い返す。そんな独裁的な管理体制が敷かれたマンションで、住民たちが自治を取り戻すべく戦った1,200日の記録。 最終的に住民たちは理事会のポジションを奪還するのだけど、そこに至るまでの準備が緻密で驚かされる。決戦の場となる総会では、薄氷の上を進むかのような攻防のなかで、彼らが用意周到さが上手く機能していく。結末を知っていても手に汗握る展開で、ノンフィクションとは思えないほどのスリルがある。 ただ、この本が面白いのは、「悪の理事会 vs 正義の住民」といった単純な対立構造ではないこと。住民たちは一枚岩ではなく、急進派もいれば穏健派もいる。住民運動に不信感を抱いてる人もいる。運動の中で何度も対立し、「有志の会」は何度も解散の危機に遭う。 象徴的だったのが、総会当日の様子。1時間の予行演習をした後、会場へ向かう住民たち。だけど、みんな一緒に会場に行くのかと思いきや、直接向かう人もいれば一旦自宅に戻る人もいて、まったくまとまりがない。その光景が、そこまでの戦いの難しさを象徴しているようだった。けれど、そんなバラバラの人たちが、一致団結して目標を成し遂げた。そこに、この物語の本当の感動ポイントがあるのだと思う。 「独裁的な理事会と戦うマンション住民の闘争」という枠を超えて、異なる考えの人々をどう巻き込み、どう説得していくかという普遍的なテーマが描かれている。そういう意味では、以前「積読チャンネル」というYouTubeで紹介された『政治学者、PTA会長になる』と似た雰囲気もあるなと思っていたら、実は担当編集者が同じだったらしい。 ノンフィクション好きや不動産の闇エピソードが好きな人はもちろん、説得術についてヒントを得たい人にもおすすめしたい。 - 2025年3月4日
 科学的思考入門植原亮読み終わった感想「科学的とは何か?」という大きな問いから、「相関と因果の違い」「認知バイアス」など、議論の際に気をつけるべきポイントまで、幅広く解説された一冊。説明は丁寧だし、「次の文を検証可能な形に言い換えてみよう」といった実践的な問題も用意されていて、能動的に学べる構成になっている。 本の中で説明されている内容は適切だと思う。やや自然科学寄りの価値観ではあるけれど、アカデミックに研究している人は多かれ少なかれ、この本に書かれているようなことは常識として理解してるはず。 唯一ひっかかったのは、まえがきで語られる執筆動機。「科学的思考が広まれば、陰謀論はなくなる」といった筆者の目標が書かれているけど、「そもそも陰謀論にハマる人の中には、科学的思考ができるかどうかとは別の次元で『反科学』に傾倒している人もいるのでは?」という疑問が残った。「科学的思考が広まれば〜」の部分は論点先取な気がする。 とはいえ、メインとなる内容は非常に参考になる。「入門」という割には文章が硬い気もするが、科学などの専門知識は一切不要。大学生が読むと、学問的な考え方の基礎を築くのに役立つはず。もちろん、科学的な主張と科学風の感想を見分る力が欲しい社会人にもおすすめ。
科学的思考入門植原亮読み終わった感想「科学的とは何か?」という大きな問いから、「相関と因果の違い」「認知バイアス」など、議論の際に気をつけるべきポイントまで、幅広く解説された一冊。説明は丁寧だし、「次の文を検証可能な形に言い換えてみよう」といった実践的な問題も用意されていて、能動的に学べる構成になっている。 本の中で説明されている内容は適切だと思う。やや自然科学寄りの価値観ではあるけれど、アカデミックに研究している人は多かれ少なかれ、この本に書かれているようなことは常識として理解してるはず。 唯一ひっかかったのは、まえがきで語られる執筆動機。「科学的思考が広まれば、陰謀論はなくなる」といった筆者の目標が書かれているけど、「そもそも陰謀論にハマる人の中には、科学的思考ができるかどうかとは別の次元で『反科学』に傾倒している人もいるのでは?」という疑問が残った。「科学的思考が広まれば〜」の部分は論点先取な気がする。 とはいえ、メインとなる内容は非常に参考になる。「入門」という割には文章が硬い気もするが、科学などの専門知識は一切不要。大学生が読むと、学問的な考え方の基礎を築くのに役立つはず。もちろん、科学的な主張と科学風の感想を見分る力が欲しい社会人にもおすすめ。 - 2025年3月2日
 異形のヒグマ OSO18を創り出したもの山森英輔,有元優喜読み終わった感想ヒグマ「OSO18」の騒動を追ったNHK記者によるノンフィクション。 類書の『OSO18を追え』に比べると現場の臨場感は控えめだけど、被害酪農家や研究者など、多方面への取材が充実していて、事件をより客観的に捉えられるのが特徴。 「OSO18って結局、何だったの?」という全体像を知りたいなら、この本か『OSO18を追え』のどちらか一冊を読めば十分。どちらの本を選ぶかは「主観的な臨場感 vs 報道的な多面性」の間の好み。ちなみに両方読むと、著者同士がお互いの本に登場するので、ちょっとエモい。
異形のヒグマ OSO18を創り出したもの山森英輔,有元優喜読み終わった感想ヒグマ「OSO18」の騒動を追ったNHK記者によるノンフィクション。 類書の『OSO18を追え』に比べると現場の臨場感は控えめだけど、被害酪農家や研究者など、多方面への取材が充実していて、事件をより客観的に捉えられるのが特徴。 「OSO18って結局、何だったの?」という全体像を知りたいなら、この本か『OSO18を追え』のどちらか一冊を読めば十分。どちらの本を選ぶかは「主観的な臨場感 vs 報道的な多面性」の間の好み。ちなみに両方読むと、著者同士がお互いの本に登場するので、ちょっとエモい。 - 2025年3月2日
 禁忌の子山口未桜ネタバレなし読み終わった感想これはもう、歴代の鮎川哲也賞(ミステリーの新人賞)受賞作の中でもトップレベルの作品だと思う。 もちろん、純粋な「謎解き」としての完成度なら、過去の受賞作(『ジェリーフィッシュは凍らない』とか)の方が上かもしれない。だけど、小説としての深み、ストーリーテリングの力強さが群を抜いている。 物語の導入から、最高に惹きつけられる。 ある夜、救急医の主人公のもとに、心肺停止状態の男が搬送される。 驚くべきことに、その男は主人公と瓜二つだった。 顔立ち、体格、体毛の生え方までそっくりなこの男は、一体何者なのか? そんなゾクッとする謎から始まり、一気に物語の深みに引き込まれる。 著者が現役の医師ということもあって、医療現場の描写はめちゃくちゃリアル。現場の緊迫感などが鮮明に描かれていて、ミステリーであることを忘れ、医療ドラマとして没入してしまう場面もあった。 そして、中盤。 とある理由で主人公が岐阜へ向かうあたりから、物語の雰囲気がガラッと変わる。 単なるミステリーではなく、過去と向き合う重みなど、さまざまなテーマが容赦なくのしかかってくる。 ラストで明かされる真実には、納得感があると同時に、胸を締めつけられるような切なさもあった。 「本屋大賞」にノミネートされているけど、ミステリーというジャンルやテーマの重さを考えると受賞は厳しいと思う。 でも、ここまで読んだ候補作6作の中では、間違いなくマイベスト。 ミステリー好きはもちろん、医療倫理や「家族とは何か」などといったテーマに切り込む物語を求めている人にもオススメしたい。 一部の展開は、倫理的に物議を醸しそうな内容。だからこそ、(著者には悪いけど)あまり世間の注目を集めずに、静かに「傑作」として語り継がれていってほしい。そんなふうに思わされる作品だった。
禁忌の子山口未桜ネタバレなし読み終わった感想これはもう、歴代の鮎川哲也賞(ミステリーの新人賞)受賞作の中でもトップレベルの作品だと思う。 もちろん、純粋な「謎解き」としての完成度なら、過去の受賞作(『ジェリーフィッシュは凍らない』とか)の方が上かもしれない。だけど、小説としての深み、ストーリーテリングの力強さが群を抜いている。 物語の導入から、最高に惹きつけられる。 ある夜、救急医の主人公のもとに、心肺停止状態の男が搬送される。 驚くべきことに、その男は主人公と瓜二つだった。 顔立ち、体格、体毛の生え方までそっくりなこの男は、一体何者なのか? そんなゾクッとする謎から始まり、一気に物語の深みに引き込まれる。 著者が現役の医師ということもあって、医療現場の描写はめちゃくちゃリアル。現場の緊迫感などが鮮明に描かれていて、ミステリーであることを忘れ、医療ドラマとして没入してしまう場面もあった。 そして、中盤。 とある理由で主人公が岐阜へ向かうあたりから、物語の雰囲気がガラッと変わる。 単なるミステリーではなく、過去と向き合う重みなど、さまざまなテーマが容赦なくのしかかってくる。 ラストで明かされる真実には、納得感があると同時に、胸を締めつけられるような切なさもあった。 「本屋大賞」にノミネートされているけど、ミステリーというジャンルやテーマの重さを考えると受賞は厳しいと思う。 でも、ここまで読んだ候補作6作の中では、間違いなくマイベスト。 ミステリー好きはもちろん、医療倫理や「家族とは何か」などといったテーマに切り込む物語を求めている人にもオススメしたい。 一部の展開は、倫理的に物議を醸しそうな内容。だからこそ、(著者には悪いけど)あまり世間の注目を集めずに、静かに「傑作」として語り継がれていってほしい。そんなふうに思わされる作品だった。 - 2025年3月1日
 「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わった感想「積読チャンネル」で紹介されていた本。 『「好き」を言語化する技術』というタイトルの本だけど、個人的に秀逸だと思ったのは「ネガティブな感情の言語化」について語った章。意図せず発言が炎上することもある今の時代だからこそ、「一般を代弁しようとしない」とか、この章に書かれているアドバイスを多くの人に読んでもらいたい。 文章術の面では、「書いた後に修正する癖をつける」という部分が実践的。丁寧に before / after を示しながら解説されているので、具体的にどのように見直せば良いかが分かりやすい。また、全体を通じて、文章を書くことをポジティブに後押ししてくれる語り口も魅力で、「よし、書いてみよう」とやる気を引き出してくれる。 「推しの素晴らしさを語りたいのに〜」というサブタイトルがついてるけど、書く文章のジャンルに関わらず参考になるアドバイスが多い。ビジネス文書でもなんでも、文章を書くことに少しでも興味がある人には、一読をおすすめしたい。
「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わった感想「積読チャンネル」で紹介されていた本。 『「好き」を言語化する技術』というタイトルの本だけど、個人的に秀逸だと思ったのは「ネガティブな感情の言語化」について語った章。意図せず発言が炎上することもある今の時代だからこそ、「一般を代弁しようとしない」とか、この章に書かれているアドバイスを多くの人に読んでもらいたい。 文章術の面では、「書いた後に修正する癖をつける」という部分が実践的。丁寧に before / after を示しながら解説されているので、具体的にどのように見直せば良いかが分かりやすい。また、全体を通じて、文章を書くことをポジティブに後押ししてくれる語り口も魅力で、「よし、書いてみよう」とやる気を引き出してくれる。 「推しの素晴らしさを語りたいのに〜」というサブタイトルがついてるけど、書く文章のジャンルに関わらず参考になるアドバイスが多い。ビジネス文書でもなんでも、文章を書くことに少しでも興味がある人には、一読をおすすめしたい。 - 2025年2月28日
 読み終わった感想2019年から2023年にかけて、北海道東部で牛を次々と襲ったヒグマ「OSO18」。この本は、その捕獲・駆除作戦の中心にいた NPO 法人「南知床・ヒグマ情報センター」のトップが、自らの体験をもとに記したノンフィクション。 実際に OSO18 を追った中心人物の視点で書かれているため、手に汗握る迫力があった。「なぜ OSO18 の目撃情報がほとんどないのか?」「なぜ OSO18 は襲った牛を食べないのか?」といった謎が次々に提示され、まるでミステリー小説のような読み応えもある。ページをめくる手が止まらなくなる一冊だった。 当時の報道では、「OSO18 =恐怖の巨大ヒグマ」というイメージが強調されていた記憶があるけど、本書を読むとその印象が大きく覆される。OSO18 が牛を襲うようになった背景には、間違いなく人間の影響があったし、そして、「巨大で恐ろしいクマ」というイメージ自体も、人間が勝手に作り上げた幻想であったことが見えてくる。 『死の貝』のようなノンフィクションが好きな人にはもちろん、「北海道でヒグマの被害があったらしい」くらいの認識だった人にも、ぜひ手に取ってほしいと思う。
読み終わった感想2019年から2023年にかけて、北海道東部で牛を次々と襲ったヒグマ「OSO18」。この本は、その捕獲・駆除作戦の中心にいた NPO 法人「南知床・ヒグマ情報センター」のトップが、自らの体験をもとに記したノンフィクション。 実際に OSO18 を追った中心人物の視点で書かれているため、手に汗握る迫力があった。「なぜ OSO18 の目撃情報がほとんどないのか?」「なぜ OSO18 は襲った牛を食べないのか?」といった謎が次々に提示され、まるでミステリー小説のような読み応えもある。ページをめくる手が止まらなくなる一冊だった。 当時の報道では、「OSO18 =恐怖の巨大ヒグマ」というイメージが強調されていた記憶があるけど、本書を読むとその印象が大きく覆される。OSO18 が牛を襲うようになった背景には、間違いなく人間の影響があったし、そして、「巨大で恐ろしいクマ」というイメージ自体も、人間が勝手に作り上げた幻想であったことが見えてくる。 『死の貝』のようなノンフィクションが好きな人にはもちろん、「北海道でヒグマの被害があったらしい」くらいの認識だった人にも、ぜひ手に取ってほしいと思う。 - 2025年2月28日
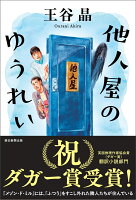 他人屋のゆうれい王谷晶ネタバレなし読み終わった感想表紙のポップな雰囲気から気軽なエンタメ小説かと思い手に取ったら、思いがけず深い純文学的な一冊だった。いい意味で裏切られた作品。 物語の主人公は、急死した伯父の部屋に住むことになる。ところが、その部屋には幽霊がいた。……とはいえ、いわゆるホラー的な存在とは違う。玄関から出入りし、ラーメンを食べる。まるで生きた人間のように振る舞うこの幽霊は、一体何者なのか? 前半は、幽霊の存在がじわりと不気味な雰囲気を醸し出すホラー寄りの展開。だが後半になると、幽霊の正体を探るミステリーへと移行し、さらに物語が進むにつれて、これは「心の成長」を描いた作品なのだと気付かされる。 この小説で幽霊とは、ただの怪異ではなく、「何かに囚われてしまった人」のメタファーだ。主人公自身も、自分の殻に籠り、皮肉や冷笑で周囲を遠ざけて生きてきた存在だった。だが、幽霊の謎を追ううちに、彼の世界は少しずつ変わり始める。 物語の結末も絶妙。作中で出てくる「落としどころ」というキーワードに合った終わり方だ。すべてをきっちり整理するようなものではない。謎の一部は明かされるが、そこには余白が残る。それでも、登場人物たちが前より少し軽やかに生きていけそうな気配があることが、この作品の温かさにつながっているのだと思う。そんなやさしい気持ちのまま、本を閉じられた一冊だった。
他人屋のゆうれい王谷晶ネタバレなし読み終わった感想表紙のポップな雰囲気から気軽なエンタメ小説かと思い手に取ったら、思いがけず深い純文学的な一冊だった。いい意味で裏切られた作品。 物語の主人公は、急死した伯父の部屋に住むことになる。ところが、その部屋には幽霊がいた。……とはいえ、いわゆるホラー的な存在とは違う。玄関から出入りし、ラーメンを食べる。まるで生きた人間のように振る舞うこの幽霊は、一体何者なのか? 前半は、幽霊の存在がじわりと不気味な雰囲気を醸し出すホラー寄りの展開。だが後半になると、幽霊の正体を探るミステリーへと移行し、さらに物語が進むにつれて、これは「心の成長」を描いた作品なのだと気付かされる。 この小説で幽霊とは、ただの怪異ではなく、「何かに囚われてしまった人」のメタファーだ。主人公自身も、自分の殻に籠り、皮肉や冷笑で周囲を遠ざけて生きてきた存在だった。だが、幽霊の謎を追ううちに、彼の世界は少しずつ変わり始める。 物語の結末も絶妙。作中で出てくる「落としどころ」というキーワードに合った終わり方だ。すべてをきっちり整理するようなものではない。謎の一部は明かされるが、そこには余白が残る。それでも、登場人物たちが前より少し軽やかに生きていけそうな気配があることが、この作品の温かさにつながっているのだと思う。そんなやさしい気持ちのまま、本を閉じられた一冊だった。 - 2025年2月25日
 読み終わった感想タイトルだけ見ると俗っぽく感じるけど、中身は至ってマジメな文章術の本。 新聞記者出身で、「47NEWS」の責任者だった著者が、「PVを稼ぐネット記事と新聞記事は何が違うのか?」という問いに真正面から向き合い、地道な比較と分析を積み重ねた一冊。 著者が考えているのは、釣りや煽りのような小手先のテクニックではなく、読まれる記事の本質。ネット記事が成功する共通項を「読者に共感してもらうこと」と「読者を迷子にさせないこと」に見出した上で、読者に長文を読んでもらうための具体的なテクニックを解説している。 実際、その理論がしっかりしているからこそ、この本自体もスッと頭に入ってくるほど読みやすかった。 あと、PVを指標の1つにしつつも、それを至上命題とせず、あくまで読者とのコミュニケーションを重視している姿勢にも好感を持てた。 note やブログで文章を書く人、読みやすい文章を書きたい人にはかなり参考になる一冊だと思う。
読み終わった感想タイトルだけ見ると俗っぽく感じるけど、中身は至ってマジメな文章術の本。 新聞記者出身で、「47NEWS」の責任者だった著者が、「PVを稼ぐネット記事と新聞記事は何が違うのか?」という問いに真正面から向き合い、地道な比較と分析を積み重ねた一冊。 著者が考えているのは、釣りや煽りのような小手先のテクニックではなく、読まれる記事の本質。ネット記事が成功する共通項を「読者に共感してもらうこと」と「読者を迷子にさせないこと」に見出した上で、読者に長文を読んでもらうための具体的なテクニックを解説している。 実際、その理論がしっかりしているからこそ、この本自体もスッと頭に入ってくるほど読みやすかった。 あと、PVを指標の1つにしつつも、それを至上命題とせず、あくまで読者とのコミュニケーションを重視している姿勢にも好感を持てた。 note やブログで文章を書く人、読みやすい文章を書きたい人にはかなり参考になる一冊だと思う。 - 2025年2月25日
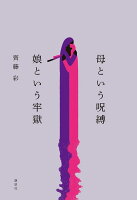 読み終わった感想まったくもって、予想外の読後感だった。 母親からの虐待の末、娘が母を殺してしまう——そんな事件を扱ったノンフィクションだから、読む前はひたすら重い展開を覚悟していた。だからこそ、気持ちに余裕があるタイミングで手に取ったのだけど、中盤までは想像以上に痛ましい母と娘の関係が描かれ、胸が締めつけられるようだった。 殺人を犯したあかりさん(仮名)は、母の期待に応えるために9浪もしていた。僕がセンター試験を受けた年、彼女もどこかで同じ試験を受けていたのだろう。そう考えると、この物語が遠い世界の話には思えなかった。だからこそ、途中まではリアルなツラさがひしひしと伝わってきた。 だけど、終盤の展開は意外だった。 弁護士団、父親、裁判官——彼女を理解し、受け入れてくれる人々との出会いの中で、あかりさんの心が少しずつほどけていく。そして、裁判官が彼女にかけた言葉がとても印象に残った。 「お母さんに敷かれたレールを歩み続けていましたが、これからは自分の人生を歩んでください」 この一言が、どれだけ彼女を救っただろうか。 重いテーマの本なのに、最後のページをめくったとき、なぜか優しい気持ちになっていた。それは、筆者の温かな文章によるものかもしれないし、あかりさんがようやく見つけた光のせいかもしれない。 そして、詳しく書くのはためらわれるけど、最後の一文には著者の粋な計らいを感じた。あれは、あかりさんのためにそっと添えられたエールだったのかもしれない。深読みかもしれないけれど、そんなふうに思えてしまう優しい終わり方だった。
読み終わった感想まったくもって、予想外の読後感だった。 母親からの虐待の末、娘が母を殺してしまう——そんな事件を扱ったノンフィクションだから、読む前はひたすら重い展開を覚悟していた。だからこそ、気持ちに余裕があるタイミングで手に取ったのだけど、中盤までは想像以上に痛ましい母と娘の関係が描かれ、胸が締めつけられるようだった。 殺人を犯したあかりさん(仮名)は、母の期待に応えるために9浪もしていた。僕がセンター試験を受けた年、彼女もどこかで同じ試験を受けていたのだろう。そう考えると、この物語が遠い世界の話には思えなかった。だからこそ、途中まではリアルなツラさがひしひしと伝わってきた。 だけど、終盤の展開は意外だった。 弁護士団、父親、裁判官——彼女を理解し、受け入れてくれる人々との出会いの中で、あかりさんの心が少しずつほどけていく。そして、裁判官が彼女にかけた言葉がとても印象に残った。 「お母さんに敷かれたレールを歩み続けていましたが、これからは自分の人生を歩んでください」 この一言が、どれだけ彼女を救っただろうか。 重いテーマの本なのに、最後のページをめくったとき、なぜか優しい気持ちになっていた。それは、筆者の温かな文章によるものかもしれないし、あかりさんがようやく見つけた光のせいかもしれない。 そして、詳しく書くのはためらわれるけど、最後の一文には著者の粋な計らいを感じた。あれは、あかりさんのためにそっと添えられたエールだったのかもしれない。深読みかもしれないけれど、そんなふうに思えてしまう優しい終わり方だった。 - 2025年2月21日
 小説野崎まどネタバレなし読み終わった感想スペースマウンテンに乗ったみたいな読書体験だった。 どこに向かっているのかもわからないまま、気づいたら全力疾走で物語の終着点にいた。 小説好きの小学生ふたりが、大人になるまでの軌跡を描きながら、「小説とは何か」「人はなぜ小説を読むのか」「小説を書かなくてもいいのか」という問いを投げかける物語。 一目で分かる区切りをつけずに、視点や時間がガンガン飛ぶ。なので、気を抜くと「今何の話をしているんだ?」と足元がぐらつく感覚に襲われる。そんな構成のクセに戸惑いながらも、不思議と流れに乗ってしまう作品。終盤にはファンタジー要素まで加わり、「この話、どこへ向かうんだ?」と戸惑っているうちに、ふっと物語の出口に辿り着いていた。 好き嫌いがありそうな構成だけど(なので「本屋大賞」候補作としては大穴感がある)、小説を読むのが好きな人なら、必ず引っかかる問いが詰まった作品。
小説野崎まどネタバレなし読み終わった感想スペースマウンテンに乗ったみたいな読書体験だった。 どこに向かっているのかもわからないまま、気づいたら全力疾走で物語の終着点にいた。 小説好きの小学生ふたりが、大人になるまでの軌跡を描きながら、「小説とは何か」「人はなぜ小説を読むのか」「小説を書かなくてもいいのか」という問いを投げかける物語。 一目で分かる区切りをつけずに、視点や時間がガンガン飛ぶ。なので、気を抜くと「今何の話をしているんだ?」と足元がぐらつく感覚に襲われる。そんな構成のクセに戸惑いながらも、不思議と流れに乗ってしまう作品。終盤にはファンタジー要素まで加わり、「この話、どこへ向かうんだ?」と戸惑っているうちに、ふっと物語の出口に辿り着いていた。 好き嫌いがありそうな構成だけど(なので「本屋大賞」候補作としては大穴感がある)、小説を読むのが好きな人なら、必ず引っかかる問いが詰まった作品。 - 2025年2月20日
 翻訳者の全技術山形浩生読み終わった感想口が悪いけど、めちゃくちゃ面白かった。バッサバッサと斬っていく感じが心地よい。例えば森博嗣の仕事論系のエッセイとかが好きな人には刺さると思う。 第1章は、山形さんの翻訳に対する考え方がコンパクトにまとまっている。技術がものすごく具体的に書かれているわけじゃないけど、「こんな考え方で訳語を決めている」といった翻訳哲学がよくわかる。実名ありで、他の翻訳者を褒めていたり、とある大物編集者をボロカスに言っていたりもする。 第2章の読書論も面白かった。表面的には辛口でも、言っていることは「もっと気軽に本を読めばいい」「積読してる本も細かいことは気にせずどんどん読もう」と、読者を励ますような温かさがある。読みたい本が溜まりがちな人にとっては、ヒントをもらえる内容だと思う。 それぞれの章は独立してるので、読みたい部分だけつまみ食いする感じで十分楽しめる。
翻訳者の全技術山形浩生読み終わった感想口が悪いけど、めちゃくちゃ面白かった。バッサバッサと斬っていく感じが心地よい。例えば森博嗣の仕事論系のエッセイとかが好きな人には刺さると思う。 第1章は、山形さんの翻訳に対する考え方がコンパクトにまとまっている。技術がものすごく具体的に書かれているわけじゃないけど、「こんな考え方で訳語を決めている」といった翻訳哲学がよくわかる。実名ありで、他の翻訳者を褒めていたり、とある大物編集者をボロカスに言っていたりもする。 第2章の読書論も面白かった。表面的には辛口でも、言っていることは「もっと気軽に本を読めばいい」「積読してる本も細かいことは気にせずどんどん読もう」と、読者を励ますような温かさがある。読みたい本が溜まりがちな人にとっては、ヒントをもらえる内容だと思う。 それぞれの章は独立してるので、読みたい部分だけつまみ食いする感じで十分楽しめる。 - 2025年2月20日
 人魚が逃げた青山美智子ネタバレなし読み終わった感想温かみのあるストーリーと、鮮やかな伏線回収が光る一冊だった。 「本屋大賞」に5年連続ノミネートされている著者だけど、今年こそ受賞してもおかしくない仕上がりだと思う。 物語の舞台は銀座。 「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」 そんな謎めいた言葉を残し、「王子」と名乗る青年が銀座の街をさまよい歩く。 まるでアンデルセンの『人魚姫』から抜け出してきたかのような彼の存在が、いつの間にか人々の心に変化をもたらしていくーー。 本書は、そんな「王子騒動」を軸にした5人の人物に関する連作短編。共通しているのは、彼らが人生のどこかで迷子になっていること。仕事や人間関係に疲れ、前に進むのが怖くなってしまった彼らが、「王子」との出会いをきっかけに少しずつ前を向いていく。 落ち込んだ時、フィクションに触れることで気持ちを切り替えられる。「王子」は、まさにそんな小説が持つ力のメタファーのようだった。そして、「この作品そのものが読者の背中をそっと押してくれるような存在だ」というメタ的な構造になっているのが面白い。 そして、読後はぜひもう一度、表紙をじっくり眺めてほしい。ミニチュア写真家・田中達也さんが手がけたカバーアートには、物語を読んだ後だからこそ気づく、細やかな仕掛けが散りばめられている。 伊坂幸太郎の『アイネクライネナハトムジーク』のような、心にじんわりと染みる爽やかな読後感。 優しい気持ちになりたいとき、そっと手に取りたくなる物語。
人魚が逃げた青山美智子ネタバレなし読み終わった感想温かみのあるストーリーと、鮮やかな伏線回収が光る一冊だった。 「本屋大賞」に5年連続ノミネートされている著者だけど、今年こそ受賞してもおかしくない仕上がりだと思う。 物語の舞台は銀座。 「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」 そんな謎めいた言葉を残し、「王子」と名乗る青年が銀座の街をさまよい歩く。 まるでアンデルセンの『人魚姫』から抜け出してきたかのような彼の存在が、いつの間にか人々の心に変化をもたらしていくーー。 本書は、そんな「王子騒動」を軸にした5人の人物に関する連作短編。共通しているのは、彼らが人生のどこかで迷子になっていること。仕事や人間関係に疲れ、前に進むのが怖くなってしまった彼らが、「王子」との出会いをきっかけに少しずつ前を向いていく。 落ち込んだ時、フィクションに触れることで気持ちを切り替えられる。「王子」は、まさにそんな小説が持つ力のメタファーのようだった。そして、「この作品そのものが読者の背中をそっと押してくれるような存在だ」というメタ的な構造になっているのが面白い。 そして、読後はぜひもう一度、表紙をじっくり眺めてほしい。ミニチュア写真家・田中達也さんが手がけたカバーアートには、物語を読んだ後だからこそ気づく、細やかな仕掛けが散りばめられている。 伊坂幸太郎の『アイネクライネナハトムジーク』のような、心にじんわりと染みる爽やかな読後感。 優しい気持ちになりたいとき、そっと手に取りたくなる物語。 - 2025年2月19日
 エビデンスを嫌う人たちリー・マッキンタイア,西尾義人読み終わった感想表紙のインパクトに反して、著者自身が地球平面説支持者の集会に潜入するなど想像以上に人間臭くて泥臭いエピソードが描かれている。書き味もエモくて、サイエンス本というより上質なノンフィクション。いい意味で裏切られた。 著者が掲げるのは「対立ではなく対話」。単に科学的・論理的な正論をぶつけるのではなく、相手が何を信じ、なぜその考えに至ったのかを理解しようとする。そして、そこから信頼関係を築き、対話を重ねていくことの重要性を説いている。 象徴的なのは、原著のタイトルが 『How to Talk to a Science Denier』(科学否定論者と話す方法) であり、『How to Talk to Science Deniers』(科学否定論者たちと話す方法) ではないこと。著者が意識しているのは、「集団」としての科学否定論者ではなく、目の前にいる「一人ひとり」と向き合うこと。レッテルを貼るのではなく、一個人として対話することが何よりも大事だと教えてくれる。 特に第7章で描かれる、遺伝子組み換え作物(GMO)をめぐる論争が圧巻だった。相手は著者の長年の友人であり、科学者でありながらGMOに否定的な立場をとる人物だ。信頼関係があるからこそ、真正面からぶつかり合い、互いの立場を理解しようとする姿が描かれている。これこそが、科学否定論に対処するための本質なのかもしれない。 また、この本自体は「科学的思考の大切さ」を説く本だが、その裏側で「文学の重要性」が浮き彫りになっているとも感じた。著者も指摘するように、人は動揺をもたらすような大事件に直面し、心理的に不安定になると、何かすがる「物語」を求めてしまう。その「物語」が陰謀論やカルト宗教の教義になってしまうことが、科学否定論の根底にある問題だ。もし、そうした「乾き切ったスポンジ」のような心に、より良い物語を提供することができたなら、それは科学否定論に対する予防策になり得る。それこそが、文学が社会にとって必要な理由なのだろう。そんなことに考えを巡らせる余白の大きさも持ち合わせた一冊だった。 単なる理屈やデータだけで陰謀論に対抗するのではなく、信頼と対話を通じて相手の心を動かす。読後、暖かな余韻が残った。
エビデンスを嫌う人たちリー・マッキンタイア,西尾義人読み終わった感想表紙のインパクトに反して、著者自身が地球平面説支持者の集会に潜入するなど想像以上に人間臭くて泥臭いエピソードが描かれている。書き味もエモくて、サイエンス本というより上質なノンフィクション。いい意味で裏切られた。 著者が掲げるのは「対立ではなく対話」。単に科学的・論理的な正論をぶつけるのではなく、相手が何を信じ、なぜその考えに至ったのかを理解しようとする。そして、そこから信頼関係を築き、対話を重ねていくことの重要性を説いている。 象徴的なのは、原著のタイトルが 『How to Talk to a Science Denier』(科学否定論者と話す方法) であり、『How to Talk to Science Deniers』(科学否定論者たちと話す方法) ではないこと。著者が意識しているのは、「集団」としての科学否定論者ではなく、目の前にいる「一人ひとり」と向き合うこと。レッテルを貼るのではなく、一個人として対話することが何よりも大事だと教えてくれる。 特に第7章で描かれる、遺伝子組み換え作物(GMO)をめぐる論争が圧巻だった。相手は著者の長年の友人であり、科学者でありながらGMOに否定的な立場をとる人物だ。信頼関係があるからこそ、真正面からぶつかり合い、互いの立場を理解しようとする姿が描かれている。これこそが、科学否定論に対処するための本質なのかもしれない。 また、この本自体は「科学的思考の大切さ」を説く本だが、その裏側で「文学の重要性」が浮き彫りになっているとも感じた。著者も指摘するように、人は動揺をもたらすような大事件に直面し、心理的に不安定になると、何かすがる「物語」を求めてしまう。その「物語」が陰謀論やカルト宗教の教義になってしまうことが、科学否定論の根底にある問題だ。もし、そうした「乾き切ったスポンジ」のような心に、より良い物語を提供することができたなら、それは科学否定論に対する予防策になり得る。それこそが、文学が社会にとって必要な理由なのだろう。そんなことに考えを巡らせる余白の大きさも持ち合わせた一冊だった。 単なる理屈やデータだけで陰謀論に対抗するのではなく、信頼と対話を通じて相手の心を動かす。読後、暖かな余韻が残った。 - 2025年2月18日
 金融詐欺の世界史ダン・デイヴィス,大間知知子読み終わった感想詐欺の歴史や手口を、豊富な実例とともに解説した一冊。「取り込み詐欺」や「ネズミ講」など、さまざまな種類の詐欺の歴史が丁寧に描かれている。 単に詐欺の手口を読むだけでも十分面白いけど、本書の魅力は、より構造的な視点から詐欺を捉えている点だと思う。特に興味深かったのは、「万引きなどの犯罪と違い、金融詐欺師は資金繰りのために嘘を積み重ねないといけないため、精神的に追い込まれていく」 という指摘。実際、本書にはこんな一節がある。 「逮捕前は華やかなライフスタイルを楽しんでいた人もいる。しかし、ついに悪事がバレたとき、多くの詐欺師は苦しくストレスの多い仕事がやっと終わって、うれし涙を流した。」 この一文を読んで、ふと『リーマンの牢獄』で斎藤栄功氏が語っていた言葉を思い出した。「これで詐欺は終わった」「もう苦しいカネ集めに奔走する必要がない。気持ちがずっと楽になりました」。 森功『地面師』のような犯罪系ノンフィクションが好きな人には刺さる内容だと思う。とはいえ、『クロサギ』や『地面師たち』のようなエンタメ作品ではないので、あくまで真面目な視点から「詐欺」を読み解いた本として手に取るのがいいと思う。
金融詐欺の世界史ダン・デイヴィス,大間知知子読み終わった感想詐欺の歴史や手口を、豊富な実例とともに解説した一冊。「取り込み詐欺」や「ネズミ講」など、さまざまな種類の詐欺の歴史が丁寧に描かれている。 単に詐欺の手口を読むだけでも十分面白いけど、本書の魅力は、より構造的な視点から詐欺を捉えている点だと思う。特に興味深かったのは、「万引きなどの犯罪と違い、金融詐欺師は資金繰りのために嘘を積み重ねないといけないため、精神的に追い込まれていく」 という指摘。実際、本書にはこんな一節がある。 「逮捕前は華やかなライフスタイルを楽しんでいた人もいる。しかし、ついに悪事がバレたとき、多くの詐欺師は苦しくストレスの多い仕事がやっと終わって、うれし涙を流した。」 この一文を読んで、ふと『リーマンの牢獄』で斎藤栄功氏が語っていた言葉を思い出した。「これで詐欺は終わった」「もう苦しいカネ集めに奔走する必要がない。気持ちがずっと楽になりました」。 森功『地面師』のような犯罪系ノンフィクションが好きな人には刺さる内容だと思う。とはいえ、『クロサギ』や『地面師たち』のようなエンタメ作品ではないので、あくまで真面目な視点から「詐欺」を読み解いた本として手に取るのがいいと思う。 - 2025年2月16日
 読み終わった感想「誤解を招いたとしたら申し訳ない」のような政治家の無理筋な弁明が、なぜ機能するのかを議論した一冊。 そういう無理筋な弁明があることは、言語表現の豊かさの裏返しなのだと気付かされた。もちろん「言葉の豊かさは守りつつ、それを悪用した弁明を減らすにはどうすべきか」という点は考えるべきだけど、「誤解を招いたとしたら申し訳ない」が機能してしまうこと自体は、あながち悪いことじゃないんだなと少し前向きになれた。 なんとなく、全体の2/3くらいを使って展開される「否認可能性」の議論は、期待効用と主観確率のベイズ更新の枠組みでモデル化できそうな気がした。数理モデルで一般化しつつ、この本で取り上げられている様々な否認可能性の基準を具体例として扱えば、より全体像が見えやすい気がする。 引きのある話題から入って、語用論や意味論を援用して掘り下げていくスタイルなので、YouTubeの「ゆる言語学ラジオ」が好きであればハマる本だと思った。新書よりは骨太だけど、専門書みたいに事前知識を要求されるわけではないので、選書らしいレベル感。途中で議論が込み入る部分もあったけど、「これから何を主張するのか」「この章の要点は何か」が逐一整理されていて、論旨は追いやすかった。
読み終わった感想「誤解を招いたとしたら申し訳ない」のような政治家の無理筋な弁明が、なぜ機能するのかを議論した一冊。 そういう無理筋な弁明があることは、言語表現の豊かさの裏返しなのだと気付かされた。もちろん「言葉の豊かさは守りつつ、それを悪用した弁明を減らすにはどうすべきか」という点は考えるべきだけど、「誤解を招いたとしたら申し訳ない」が機能してしまうこと自体は、あながち悪いことじゃないんだなと少し前向きになれた。 なんとなく、全体の2/3くらいを使って展開される「否認可能性」の議論は、期待効用と主観確率のベイズ更新の枠組みでモデル化できそうな気がした。数理モデルで一般化しつつ、この本で取り上げられている様々な否認可能性の基準を具体例として扱えば、より全体像が見えやすい気がする。 引きのある話題から入って、語用論や意味論を援用して掘り下げていくスタイルなので、YouTubeの「ゆる言語学ラジオ」が好きであればハマる本だと思った。新書よりは骨太だけど、専門書みたいに事前知識を要求されるわけではないので、選書らしいレベル感。途中で議論が込み入る部分もあったけど、「これから何を主張するのか」「この章の要点は何か」が逐一整理されていて、論旨は追いやすかった。 - 2025年2月15日
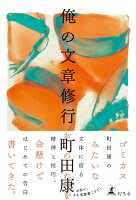 俺の文章修行町田康読み終わった感想「文章の書き方」を指南するハウツー本っぽい雰囲気を醸し出してるけど、そんな甘いもんじゃなかった。これは「町田康がどうやって町田康になったか」を探る本だと思う。文章術というより、町田康の思考回路をのぞき見する一冊。 そもそも、町田康の文章は技術でどうにかなる代物じゃないと思う。町田康の本を読んだからといって真似できるもんでもないし、書き方を知ったところで再現できるわけでもない。結局、「町田康だから書ける文章」でしかなくて、読めば読むほど「これはもう天才の仕事だな」と実感させられる。 でも、そのプロセスを知れるのは面白い。なぜこんなリズム感になるのか、どうしてこういう言葉選びになるのか、その秘密が垣間見える。町田作品を一冊でも読んで「この文体、クセになるな」と思ったことがある人なら、間違いなく楽しめる本だと思う。
俺の文章修行町田康読み終わった感想「文章の書き方」を指南するハウツー本っぽい雰囲気を醸し出してるけど、そんな甘いもんじゃなかった。これは「町田康がどうやって町田康になったか」を探る本だと思う。文章術というより、町田康の思考回路をのぞき見する一冊。 そもそも、町田康の文章は技術でどうにかなる代物じゃないと思う。町田康の本を読んだからといって真似できるもんでもないし、書き方を知ったところで再現できるわけでもない。結局、「町田康だから書ける文章」でしかなくて、読めば読むほど「これはもう天才の仕事だな」と実感させられる。 でも、そのプロセスを知れるのは面白い。なぜこんなリズム感になるのか、どうしてこういう言葉選びになるのか、その秘密が垣間見える。町田作品を一冊でも読んで「この文体、クセになるな」と思ったことがある人なら、間違いなく楽しめる本だと思う。 - 2025年2月14日
 涼宮ハルヒの劇場いとうのいぢ,谷川流ネタバレあり読み終わった感想奇抜な設定だけど、まさに「ハルヒ」らしい一冊だった。 第2章までは初期に雑誌掲載されたエピソードなので、ハルヒの言動が初期のトゲトゲした感じそのままで、どこか懐かしさを覚える。時系列的には『溜息』(2巻)〜『消失』(4巻)の間に位置づけられていて、まだ尖っているハルヒのキャラクター像を考えると、この落とし所はしっくりくる。 「フィクションの世界に入り込む」という大胆な設定ながら、根底にあるのは「非日常ではなく、元の日常を選択する」というシリーズを通して描かれてきたテーマ。これは『憂鬱』から繰り返し提示されてきたものだし、今作もまさに「The <ハルヒ> シリーズ」という仕上がりになっている。「エンドレス・エイト」のように長門に負荷がかかる展開も、『消失』前のエピソードとしての説得力がある。 さらに、「分裂」や「天蓋」といったワードをさりげなく入れてくる演出もニクい。 このあたりの細かい仕掛けも含めて、新刊として待った甲斐のある一冊だった。
涼宮ハルヒの劇場いとうのいぢ,谷川流ネタバレあり読み終わった感想奇抜な設定だけど、まさに「ハルヒ」らしい一冊だった。 第2章までは初期に雑誌掲載されたエピソードなので、ハルヒの言動が初期のトゲトゲした感じそのままで、どこか懐かしさを覚える。時系列的には『溜息』(2巻)〜『消失』(4巻)の間に位置づけられていて、まだ尖っているハルヒのキャラクター像を考えると、この落とし所はしっくりくる。 「フィクションの世界に入り込む」という大胆な設定ながら、根底にあるのは「非日常ではなく、元の日常を選択する」というシリーズを通して描かれてきたテーマ。これは『憂鬱』から繰り返し提示されてきたものだし、今作もまさに「The <ハルヒ> シリーズ」という仕上がりになっている。「エンドレス・エイト」のように長門に負荷がかかる展開も、『消失』前のエピソードとしての説得力がある。 さらに、「分裂」や「天蓋」といったワードをさりげなく入れてくる演出もニクい。 このあたりの細かい仕掛けも含めて、新刊として待った甲斐のある一冊だった。 - 2025年2月14日
 課税と脱税の経済史マイケル・キーン,ジョエル・スレムロッド,中島由華読み終わった感想「税金の話ってこんなに面白かったっけ?」と思わされる一冊だった。 税制の専門家が、税の歴史を豊富な具体例とともに読み解いていく本。「為政者はどうやって効果的な課税を試みてきたのか?」「人々はどうやってその課税から逃れようとしてきたのか?」という問いを軸に、税金にまつわる奇想天外なエピソードが次々と登場する。 面白いエピソードはあげればキリがないけど、たとえば、こんな話が出てくる。 ・17世紀のイギリスで、窓の数に応じて税金を取る「窓税」が導入された。結果、節税のために人々は窓を埋めてしまい、換気が悪くなって伝染病が流行。おまけに日光不足で子どもの発育にも悪影響 ・ドイツのある男性は「犬税」を払いたくないため、飼い犬を「これは羊だ」と言い張って税金を払わずに済まそうとした ・オランダでは、モルモットの餌は21%の税率、うさぎの餌は9% ・19世紀のアメリカでは、関税法の文書に余分なカンマがたった1つが入ったせいで、果物すべてが免税になってしまった こういうエピソードが山盛りで、読んでて「いや、税金の話ってこんなにぶっ飛んでるんだ?」ってなること間違いなし。日本人に馴染み深いエピソードだと、酒税を安くするため「ビール → 発泡酒 → 第三のビール」のイタチごっこが起きた話も紹介されている。 この本がすごいのは、単に「税金のトンデモ話」だけじゃなくて、ちゃんと税制の理論や未来についても深掘りしているところ。ラッファーカーブとかラムゼールールとか経済学の教科書で頻出の概念もきちんと説明されているし、「どんな税制なら人々が納得するのか?」とか「未来の税制ってどうあるべき?」といった大きなテーマもしっかり議論されている。こうした「真面目な税の議論」と「珍妙な税の歴史」が絶妙なバランスで絡み合っていて、税制の本質を楽しみながら理解できる仕掛けになっている。 「税金って、こんなにカオスで、人間臭い話だったのか」と思えること間違いなし。600頁超の鈍器本(注釈と参考文献だけで100頁以上ある骨太本)だし翻訳も硬めなので、それなりに読書筋力は必要だと思うけど、税金やお金の話に興味がある人には刺さる一冊。
課税と脱税の経済史マイケル・キーン,ジョエル・スレムロッド,中島由華読み終わった感想「税金の話ってこんなに面白かったっけ?」と思わされる一冊だった。 税制の専門家が、税の歴史を豊富な具体例とともに読み解いていく本。「為政者はどうやって効果的な課税を試みてきたのか?」「人々はどうやってその課税から逃れようとしてきたのか?」という問いを軸に、税金にまつわる奇想天外なエピソードが次々と登場する。 面白いエピソードはあげればキリがないけど、たとえば、こんな話が出てくる。 ・17世紀のイギリスで、窓の数に応じて税金を取る「窓税」が導入された。結果、節税のために人々は窓を埋めてしまい、換気が悪くなって伝染病が流行。おまけに日光不足で子どもの発育にも悪影響 ・ドイツのある男性は「犬税」を払いたくないため、飼い犬を「これは羊だ」と言い張って税金を払わずに済まそうとした ・オランダでは、モルモットの餌は21%の税率、うさぎの餌は9% ・19世紀のアメリカでは、関税法の文書に余分なカンマがたった1つが入ったせいで、果物すべてが免税になってしまった こういうエピソードが山盛りで、読んでて「いや、税金の話ってこんなにぶっ飛んでるんだ?」ってなること間違いなし。日本人に馴染み深いエピソードだと、酒税を安くするため「ビール → 発泡酒 → 第三のビール」のイタチごっこが起きた話も紹介されている。 この本がすごいのは、単に「税金のトンデモ話」だけじゃなくて、ちゃんと税制の理論や未来についても深掘りしているところ。ラッファーカーブとかラムゼールールとか経済学の教科書で頻出の概念もきちんと説明されているし、「どんな税制なら人々が納得するのか?」とか「未来の税制ってどうあるべき?」といった大きなテーマもしっかり議論されている。こうした「真面目な税の議論」と「珍妙な税の歴史」が絶妙なバランスで絡み合っていて、税制の本質を楽しみながら理解できる仕掛けになっている。 「税金って、こんなにカオスで、人間臭い話だったのか」と思えること間違いなし。600頁超の鈍器本(注釈と参考文献だけで100頁以上ある骨太本)だし翻訳も硬めなので、それなりに読書筋力は必要だと思うけど、税金やお金の話に興味がある人には刺さる一冊。
読み込み中...